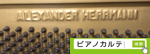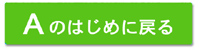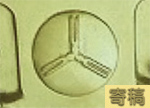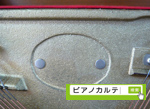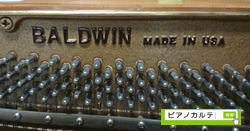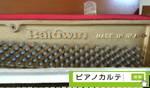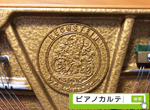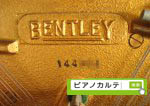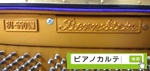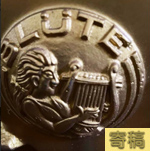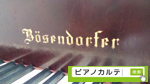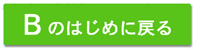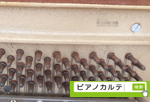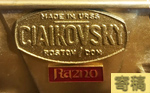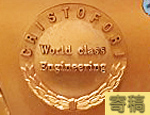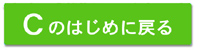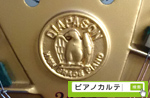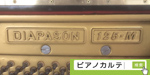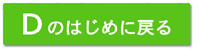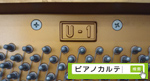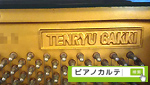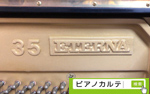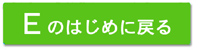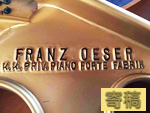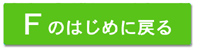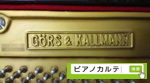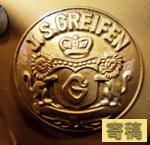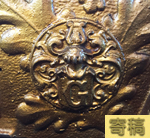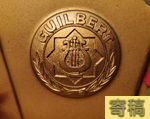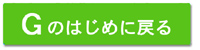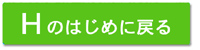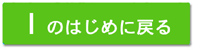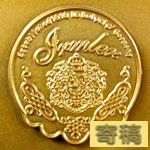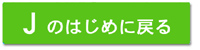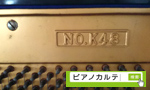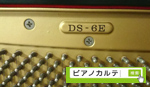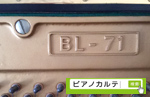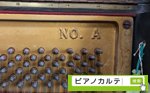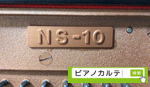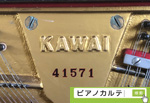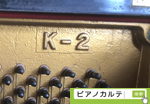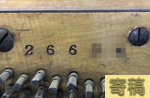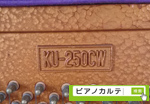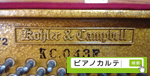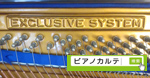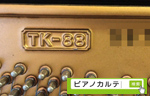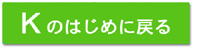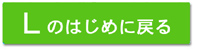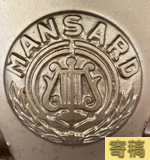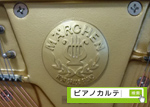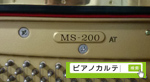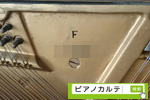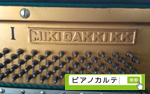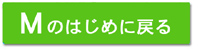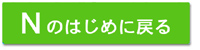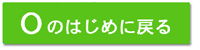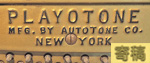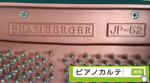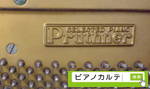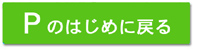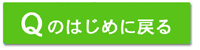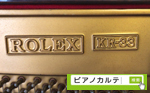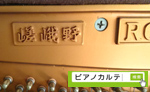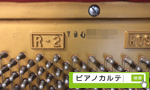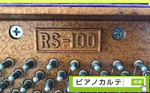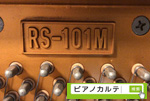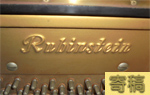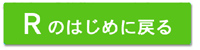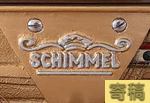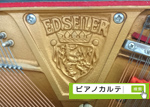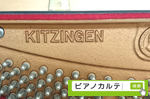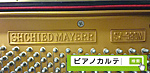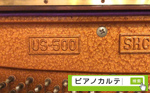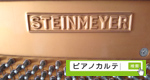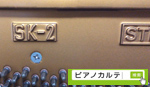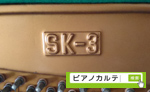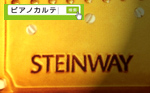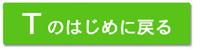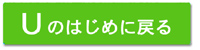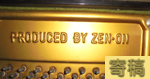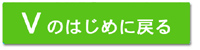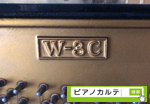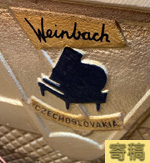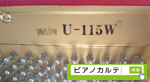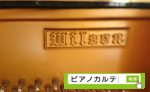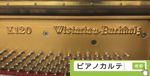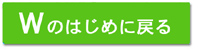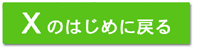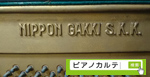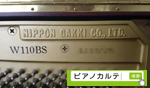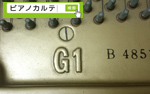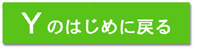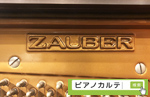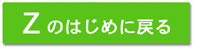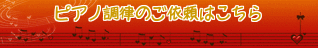★☆ 現役ピアノ調律師が作ったページです ☆★
日本国内と世界各国のピアノメーカー図鑑(A~Z)約1930種類一覧
ピアノメーカー・ブランドランキング全覧 ピアノメーカー詳細解説 ロゴ・エンブレム・トレードマーク 日本と世界のピアノメーカーの集大成

★五十音順ページもありますが、アルファベット順ページ(当ページ)の方が情報量が多いです★

五十音順(アイウエオ順)のページでの検索はこちら
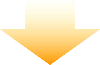 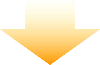 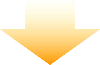

※但し、情報量や画像の多さでは当アルファベット順ページ(現在表示中のページ)の方が豊富です
 


はじめまして、ピアノ調律師の杉本豊と申します(現在職歴30年になります、被雇用20年+フリー歴10年)
日本国内をはじめ世界各国のピアノメーカー/ブランド数は優に2000種類を超える数があったと言われています。
太平洋戦争以前の国内メーカーとしてはヤマハ・カワイをはじめ、ニシカワ・マツモト・トレフリッヒ・シュー・リー
ルビンシュタイン・モートリー・シュベスター・ブッフホルツ・フクシマ・ホルーゲル・オオツカ・ヒロタ等がありました。
しかし、戦前に作られたピアノは、戦時混乱と金属類回収令等により、残念ながら現在ほとんど残っておりません。
高度経済成長期に全盛期を迎えた国内に於けるピアノ製造業も、時代の流れとともに廃業を余儀なくされてゆきますが、
販売されたピアノ自体は世の中に末長く残り続けるためにこのピアノメーカー/ブランド名のページを作りました。
聞き慣れないピアノや、初めて見るピアノを調べたい時など、当ページが広く皆様のお役に立てたら大変光栄です。
当ページ内には現在約1930種類(但し、同ブランドの重複掲載もあります)のピアノブランド名を掲載しており、
新しい情報を発見した場合や、修正及び加筆事項があった際には、出来る限りすみやかな更新を心がけております。
特に注目して頂くと面白いのが、ピアノの内部にある各ブランドそれぞれのトレードマーク画像(エンブレムマーク)です。
ピアノの鉄骨部分には大抵そのブランドを象徴するトレードマークが付いており、どれも個性豊かで興味深いです。
内部にあるので一般の方は通常あまり目にすることがないマークですが、皆様にご紹介出来たらと思っております。
良いピアノを作ろうと日々情熱を傾け、長きにわたり尽力してこられた
先人の偉大なるピアノ製作者の方々に対し、心より敬意を表します。
最終更新日:2023/11/25
Last Updated : November 25, 2023
|
当ページの内容には万全を期しておりますが、もし間違った内容を発見した場合や、
誤字・脱字、もしくは新しい情報などがございましたら 修正受付フォーム より遠慮なくお知らせ下さい。
頂いた情報はすべて当方に於きましても慎重に検証・精査した上で、ホームページに反映させて頂きます。
日頃から多くの方々からの新情報のご提供、及びトレードマークのご寄稿いつも本当に有り難うございます。
昭和40~50年頃が全盛期だった国内ピアノ製造業ですが、その当時はまだインターネットが一般的でない時代です。
当ページの公開を初めてから本当にたくさんの方々から情報を頂き、改めてインターネットの凄さを痛感しております。
これからも皆様のお力をお借りして当ページを少しでも良いものに作り上げていきたいと思っております。
ピアノ製造史を後世に出来るだけ多く残すため、ぜひご協力の程宜しくお願い申し上げます。 ピアノ調律師 杉本豊
トレードマーク(ピアノ内部のエンブレム丸マーク)の画像も皆様から広く募集中です
同業者様(調律師、買取り業者、ピアノ運送業者様)からのご寄稿もお待ちしております
ピアノ内部にあるトレードマークのご寄稿フォームは→こちら
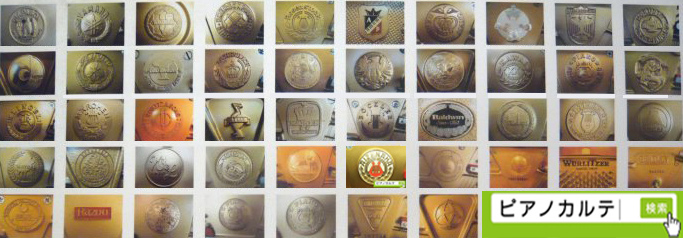


情報量がかなり多いので 「ページ内キーワード検索」 をお勧めします →パソコンでの検索方法
スマートフォンでのキーワード検索の操作方法はこちら →iPhoneの方 →Androidの方
 日本国内ピアノ知名度ランキング
日本国内ピアノ知名度ランキング  1個 (マイナー) ~ 1個 (マイナー) ~ 4個 (メジャー) 4個 (メジャー)
★星の数は当方独自の見解です。もっと有名でしょ?又はもっとマイナーでは?とお感じの方は →修正受付フォーム からお知らせ下さい

五十音検索は下記各ボタンから別ページへ直接ジャンプ出来ます




ピアノ銘柄ブランド
トレードマーク 紹介
& 知名度ランキング

|

メーカー/ブランド説明・会社沿革・歴史・製作者・特徴・音色・他
|
A.B. CHASE
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
アレン・B・チェイス アメリカ
ALLEN. B. CHASE 創業1875年
アレン・B・チェイスは、1875年にA.B.チェイス・ピアノ・カンパニーを設立。
オハイオ州ノーウォークにあった同社は、最初の10年間はオルガンを製造。
その後、主にピアノの製造に移行していった。
1922年、ユナイテッド・ピアノ・コーポレーションがA.B.チェイス社を買収し、
その後、所有者が入れ替わるという長い道のりを歩むことになった。 |
A. FOSTER

このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
A.FOSTER エー・フォスター
ベルリンピアノ製造株式会社 ※当時の住所:浜松市(現:浜松市東区)原島町195番地
似た名称で”フォルスター/FORSTER”←Rが入ります(同じベルリンピアノ製造株式会社)や、
”フォスター/FOSTER”(大和楽器製造株式会社)というブランドもあるので要参照 |
| A. GRAND |
ドイツ 創業1869年 詳細不明 |
A.M. MCPHAIL
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
A.M. McPhail Piano Co. 1837年創業 アメリカ
A.M.マクファイル・ピアノ・カンパニーは、1837年にアンドリュー・マクファイルによって設立された。
1891年に法人化されたマクファイル・ピアノ社は、1860年にはボストンでピアノを生産していた。
1920年代に入ると、生産拠点はボストンの別の場所に移転した。
世界大恐慌の猛威にもかかわらず、マクファイルピアノは1900年代初頭まで個人所有を維持し、
1950年代まで生産を続けた。1930年代にマクフェイルの名前はコーラー・ブランバックに引き継がれ、
30年代のマクフェイルのグランドピアノにブランバックのシリアルNo.が付いているものがあるのは
そのためである。
A.M.マクファイルは、高度な職人技とそれに見合った価格で知られていましたが、
当時の他のメーカーに比べて比較的生産台数は少なかったようです。
A.M. McPhail Piano Co.は、アップライトとグランドの両方を製作し、
いくつかの主要なピアノのバリエーションとスタイルを製造しました。
1900年代初頭、マクフェイルピアノは憧れの高級ピアノブランドとなった。 |
| A. STROBACH |
詳細不明 |
| AARHUS |
詳細不明 |
| ACACIA |
アカシア アカシアピアノ製作所
詳細不明 |
ACACIAN

下記は参考画像

画像クリックでHPへ戻る |
ACACIAN アカシアン (兵庫県伊丹市)
戎(エビス)ピアノ製作所(飯国一郎氏)、アカシアピアノ製作所(→後のマイシュナーピアノ製作所)
※漢字は「戒」×ではなく「戎」〇です
※ピアノブランド名はアカシアン(ACACIAN)だが、会社名はアカシア(ACASIA)製作所です。
発売元:アカシア楽器店
昭和18年頃の戦時中、アカシア木工は東洋航空機工業、東洋金属と社名を変え軍需工場として稼働。
そこでは鋳造航空機部品、砲弾類、落下タンク等を作っていたとの情報があります。
終戦後は(株)アカシアピアノ製作所を再興するも、軍需品頼りの体質からなかなか脱却できず、
当概工場で作られた「アカシアン(ACACIAN)」のブランドで製造されたのは昭和26年迄のようです。
後に、敷地の一部を使って太田一郎氏がマイシュナーピアノ製作所としてピアノ事業を継承しました。
MEISCHNERの項目も参照して下さい。
※左記トレードマークはアカシアンではなく、マイシュナー(MEISCHNER)のものです。
~別資料~
1965年頃まで、兵庫県伊丹市の北の外れに広大な敷地のピアノ工場がありました。
ACACIAN時代は出雲出身の飯国一族の経営。
会社が解散した後MEISCHNERと名前を変えて故・町田幸重氏が引き継ぎました。
しかし、2度も続けて重加算税を支払う羽目に陥り、存続できなくなったと伝えられています。
創業時期は太平洋戦争前だが詳しい時期は不明。
町田氏は、高知出身で、高等小学校卒業後、アカシアピアノ製作所に木工見習で入り
ピアノの設計や調律を習得。
独学で英語やドイツ語の専門書を読む大変な努力家だったようです。
その後、海軍に入り傷痍軍人として退役。
会社を辞めてからは、個人的に調律師として活躍。
全国ピアノ技術者協会会長。
後に社団法人日本ピアノ調律師協会設立に尽力し、その初代会長。
|
ACCORD

画像クリックでHPへ戻る |
ACCORD アコード ロシア製(旧ソ連製)
※スペルは「ACORD」でななく、「ACCORD」というように”C”が2個重なる表記が正しいです。
ベリョースカ、チャイコフスキー、エチュード、ウラジミール等のソ連RAZNO製ピアノに似たピアノです。
このピアノも上記ピアノ同様に突き板(表面に貼った化粧板)がよく剥がれてきます。
元々しっかり接着されていないことも原因ですが、日本の高音多湿環境に合わないためとも考えられます。
その他詳細不明。
トレードマーク内には”MADE IN USSR KALUGA”と入っています。
ちなみにこのカルーガとは、ロシア連邦南西部カルーガ州の州都です。モスクワの南西にある都市。
トレードマーク画像は、「匿名希望様」からご寄稿頂きました。ありがとうございます! |
| ACKERMAN & LOWE |
詳細不明 |
| ACKERMAN, F.J. |
詳細不明 |
| ACOUSTGRAND |
詳細不明 |
| ACROSONIC |
アクロソニック アメリカ ボールドウィン社
ピアノ鉄骨部分には「BUILT BY BALDWIN」と書いてあります
→詳しくはBALDWINの項目へ |
| ADAM, F. |
詳細不明 |
| ADAM, G. |
→ GERHARD ADAMの項目へ |
| ADAM GERHARD |
→ GERHARD ADAMの項目へ |
| ADAM, M. |
詳細不明 |
ADAM SCHAAF
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
アダム・シャーフ 創業1873年 アメリカ(シカゴ)
創業者のアダム・シャーフは、1873年にシカゴの工場でピアノの製造を開始した。シャーフの工場は、6階建ての美しい建物で、同様に美しい楽器を製造していた。
1920年代初頭、アダムは3人の息子に会社を譲った。
ハリー(Harry Schaaf)、フレッド(Fred Schaaf)、ウォルター(Walter Schaaf)の3人である。
1920年代の終わり頃には、シャーフピアノの需要が高まり、兄弟は注文を受けるために新たな工場を建設。
シャーフの工場では、クラリトーン(Claritone)、オルフェウス(Orpheus)、シュターブ(Staab)などの
ピアノも生産していたが、これも事業拡大の理由の一つであった。 |
| ADAMS |
詳細不明 |
ADELSTEIN

※トレードマークはなし

画像クリックでHPへ戻る |
ADELSTEIN アデルスタイン
※読みは「アーデルスタイン」ではなく「アデルスタイン」が正しいようです
(有)日米楽器工業所(アトラスピアノ社の前身) 当時:浜松市神田町
日米楽器工業所は1955年頃に設立、その後1960年頃にアトラスピアノ製造株式会社に改組
頼金忠氏が当時大きく関わったとされています。
※平成の初め頃に倒産との情報有り
機種バリエーション:AD250、AD300等 |
ADLER
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
アドラー ADLER
アメリカ(ケンタッキー州)ルイビル 創業1908年
アドラー・マニュファクチャリング・カンパニーは、1908年にピーター・アドラーによってルイビルに設立。
事業は家族経営で、アドラー氏の引退後は息子たちが会社を引き継いだ。
リードオルガンなども製造し、優れた楽器を作り続けた。
1928年、後の世界大恐慌を予見してか、アドラー・マニュファクチャリング・カンパニーは廃業した。
廃業前までの15年ほどの間に、年間約500台の楽器を生産したとされる。 |
| ADOLF ERNST VOIGT |
ドイツ(ベルリン)
ピアノの蓋部分には「Konigi. Span Hoflieferant」と書いてあります。
※Hoflieferantはドイツ語で御用達という意味
その他、「DARTER & SONS Sole Agents CAPE TOWN」とも書いてありますが、詳細不明 |
| ADOLPHGEYER |
ドイツ製 アドルフガイヤー 詳細不明
|
AEOLIAN


画像クリックでHPへ戻る |
エオリアン Aeolian Organ & Music Co. アメリカ(ニューヨーク州マンハッタン)
ウィリアム・B・トレメインによって1883年に創業 ※1887年という説もあり
初期はオルガンのみを製造していましたが1895年からはピアノ製作を開始し、
「プレーヤーピアノ」と呼ばれている自動演奏できるピアノ製品でも有名になりました。
エオリアン社の社名は、風によって鳴る楽器「エオリアン・ハープ」から由来して名付けられた。
ウィリアム・B・トレメインによって設立されたこの会社は、長い間自動演奏ピアノの市場を独占していた。
1895年にこの会社の名称は1897年にエドウィン・ヴォーティーが開発した空気式の
自動演奏ピアノ「ピアノラ」で知られるようになった。
しかし、エオリアン社を一気に大企業へ成長させたのは、その後に発売された
リプロデューシング・ピアノ「デュオ・アート/DUO ART」でした。これは1913年に同社が開発。
「デュオ・アート」は精巧な機構をもった楽器で、ロール紙に記録された演奏者による細かいニュアンスや
強弱をとても正確に読み取ることができたという。
この楽器の成功によって会社は高い地位を得て、ニューヨークにエオリアン・ホールを建設し、また、
チッカリングやメイソン・アンド・ハムリン、クナーベなど、数多くの有名なブランドを買収するに至った。
ところが、エオリアン社は極めて評価の高いブランドの楽器を生産していたにもかかわらず、その後に
陥った会社存続の危機には勝てなかった。エオリアン社は、不況に加えて非常に品質の劣る楽器を
生産し続けてしまったために財政危機に陥り、1983年にスタインウェイ社の元社長のピーターペレスによって
買収された。ペレスはこの会社の主要な財産であるチッカリングやメイソン・アンド・ハムリン、クナーベなどの
ブランドを売り込むために尽力を注ぐが、なんとか会社のイメージを回復させるまでところまでいったが、
その後も品質の劣る楽器の生産が続いたために、ついにこの有名なメーカーは消滅する時を迎えた。
そして1985年、エオリアン社は生産を中止しました。
<附録>
エオリアン 製造番号/製造年代 対照表(1903年~1930年) →★
<別解説>
エオリアン・アメリカン・ピアノの歴史
1900年代のピアノ業界で最も有名なブランドであるエオリアンの歴史は、
1860年代にコネチカット州で始まったと言われています。
ウィリアム・B・トレメインは1868年に兄弟でピアノ事業を始め、"トレメイン兄弟 "と呼ばれていました。
トレメイン兄弟は、1883年に発売された「オルギネット」と呼ばれる家庭用卓上オルガンを開発し、
市場に送り出した。
彼はボストンのオルガン会社を買収し、1888年にエオリアン・オルガン&ミュージック社を設立した。
その後、エオリアン社の成功の原動力となった自動演奏ピアノの前身である
ハイブリッドピアノオルガン「Aeriola」を発表。
1898年には、ウィリアムの息子であるハリー・B・トレメインが事業を引き継ぎ、
社名をエオリアン・カンパニーに変更し、マサチューセッツ州ウースターに移り、
会社を次のレベルに引き上げるための資本投資を募っていた。
楽器の自動演奏装置の特許を取得していたトレメイン社は、
雑誌に4ページのカラー広告を掲載して「ピアノラ」を発表。
1903年までに、ジョージ・ステック社、ウェーバー・ピアノ社など、
いくつかのオルガン・ピアノ会社を買収していた。
これを機に、ニューヨーク、ガーウッド、メリデンにピアノプレーヤー工場を、
ドイツのゴータとイギリスのヘイズにステック社とウェーバー社のピアノ工場を設立し、
業界の支配力を高めていった。
1932年には、エオリアンに投資された資本金が1,500万ドルを超え、
すべてのピアノ会社の頂点に立っていた。
同年、エオリアンはアメリカン・ピアノ・カンパニーと合併し、
エオリアン・アメリカン・コーポレーションとなった。
エオリアン・アメリカン・ピアノ・カンパニーは、アメリカで最大のピアノおよび
プレーヤー・ピアノのメーカーとしての
地位をさらに高め、現在でも多くのピアノの名前を管理している。
1940年代にアメリカで第4位のピアノメーカーだったエオリアン・コーポレーションは、
1990年代を通じて多くのピアノブランドをコントロールしていました。
この時期にエオリアンが生産していた名前のリストは膨大で、以下のようなものがあります。
Duo Art / Gabler / Stuyvesant / Acoustigrande / Ellsworth / Haines Bros.
/ Pianola
Ampicao / Emerson / Holmes & Sons / George Steck Co. / Knabe / Armstrong
J.C. Fischer / Entertainer / Stratford / Brewste / Foster Armstrong /
Laffargue / Stroud
Chickering / Marshall-Wendell / Normandie / Vose / A.B. Chase / Mason
& Hamlin
Lindeman / Weber / Franklin / Primatone / Washburn / Wheelock |
| AERTS |
詳細不明 |
| AEUTZER |
AEUTZER アウツァー 竜生楽器研究所(龍生楽器研究所) |
|
AIZENAHA



下は中国製造になってから
トレードマークがありません

画像クリックでHPへ戻る
|
アイゼナハ AIZENAHA
昭和53年に創立した大阪の日本ピアノ株式会社で発売していたブランドです。読み:にっぽん
NIPPON PIANO CO.,LTD
製造元:東洋ピアノ製造株式会社
日本ピアノという名称で紛らわしいですが、あの日本楽器(ヤマハ)とは関係ないです。
(※AIZENAHAの商標は東洋ピアノ製造所有ブランドとなっております)下記参照
創業当初の高級品ピアノにはエゾ松製の響板や、ドイツのレンナーハンマーを使用していました。
全盛期当時、アップライト10機種と、グランド2機種を製造。
機種バリエーション:U-301、U-901等
<附録>
アイゼナハピアノ 製造番号/製造年代 対照表(1990年~1999年) →★
ちなみにアイゼナハとは、ドイツ連邦共和国のテューリンゲン州にある都市名です。
この地はあの有名な音楽家「ヨハン・ゼバスティアン・バッハ」の出生地としても知られております。
(ドイツ語: Eisenach、読みはアイゼナッハとも解されます)
※上のトレードマークは創業時からのもので、真ん中のトレードマークは東洋ピアノになってからのもの。
下は中国製造になってからのピアノで、トレードマークは消失しています。
現在、ネット上でよく見かけるAIZENAHA(アイゼナハ)は東洋ピアノ管理下の中国製造です。
NS-230Cなどがこれになります。まだ私自身、調律したことがないので音色や品質・性能は不明です。
今後調律する機会がありましたらここに中国アイゼナハの解説をアップ致します。
アイゼナハのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい →★ |
| AJELLO |
詳細不明 |
ALBART
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
アルバート トニカ楽器(昭和39年創業) 浜松 詳細不明
株式会社トニカ楽器の当時の住所:浜松市浅田町1666番地
※トニカ楽器の社内資料によると、ALBART(アルバート)は「トニカ楽器製」の台湾向けピアノと、
トニカ楽器が販売を扱った「台湾製ピアノ」の両方の可能性があります。
下記アルバートと同じブランドかは不明。 ※こちらのアルバートのスペルは「ALBART」です |
ALBERT
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
アルバート 東海楽器工業有限公司 台湾(中国)
工場は台中市北屯路。ピアノメーカーとしては極めて新しい社歴で、その製作技法は
西ドイツ最大のメーカーであるシンメル社から引き継いだと言われている。
※トニカ楽器の社内資料によると、ALBART(アルバート)は「トニカ楽器製」の台湾向けピアノと、
トニカ楽器が販売を扱った「台湾製ピアノ」の両方の可能性があります。
上記アルバートと同じブランドかは不明。 ※こちらのアルバートのスペルは「ALBERT」です |
| ALBERT FAHR |
詳細不明 |
| ALBERT HALM |
アルベルト・ハルム オランダ 詳細不明
|
| ALBERT & CO. |
詳細不明 |
| ALBION |
詳細不明 |
| ALBRECHT & Co. |
ALBRECHT & Co.
1876年 フィラデルフィア(アメリカ) 詳細不明 |
| ALDEN |
詳細不明 |
| ALDRICH |
詳細不明 |
| ALEX STEINBACH |
詳細不明 |
ALEXANDER

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
アレクサンダー ※読みは「アレキサンダー」ではないようです
株式会社 福山ピアノ社(東京)
大成ピアノ製造株式会社(浜松)
村瀬克己氏
アトラスピアノ製造株式会社
東洋ピアノ製造株式会社
この下の「ALEXANDER HERRMANN」と同じブランドかもしれません。 |
| ALEXANDER |
アレクサンダー ロシア(ソ連) 詳細不明
|
| ALEXANDER CUSTOM |
アレクサンダー・カスタム 株式会社 福山ピアノ社 |
ALEXANDER HERRMANN


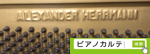
画像クリックでHPへ戻る |
ALEXANDER HERRMANN アレククンダー・ヘルマン
福山ピアノ社(フクヤマピアノ)
太平洋戦争後まだ間もない昭和20年代に新品の生産が間に合わなかったころ、
主として中古ピアノ(国産)を改装して売り出したのがはじまり。
鍵盤押さえ部分などに「MATERIAL MADE IN GERMANY」と書き添えがしてあるものが多い。
アクション部分には「Using all Materials from Germany」というプレートが貼ってあります →★
アクション部品の一部にドイツ製のものもあるという意味であろう。
ハンマーはレンナー(ドイツ製)で、まくり(ピアノの蓋部分)はビックリするほど重かったです。
ピアノまくり(蓋部分)にある銘柄ブランド名部分の写真はこちら →★
ドイツにはアレクサンダー・ヘルマンという本家本元のピアノがあります。
下記のドイツの 「ALEXANDER HERRMANN」を参照して下さい。 |
ALEXANDER HERRMANN


画像クリックでHPへ戻る |
ALEXANDER HERRMANN アレクサンダー・ハーマン (アレクサンダー・ヘルマン)
ドイツ(旧東ドイツ製)
読みづらいですが、左の写真のトレードマーク内に入っている文字は、
ROSENSTADT SANGERHAUSEN(ローゼンシュタット・ザンガーハウゼン)と入っています
ピアノまくり部分(ピアノ蓋)のブランド銘柄マークの写真 →★
こちらはピアノ全体写真です →★ ※カタログによりますと”MODEL110 DELUXE”という型番のようです
トレードマーク画像とその他すべての写真は、「匿名希望様」からご寄稿頂きました。
ご寄稿者様によりますと、このピアノは玉川高島屋取り扱いで、浜松ピアノセンターより1978年頃に
購入されたとの情報を頂きました。画像のご寄稿誠にありがとうございます!
<参考>
(株)浜松ピアノセンター(略称:HPC)/日本ベーゼンドルファーは世界3大ピアノメーカーの一つと言われる
ベーゼンドルファー(オーストリア)の日本総代理店でした。
HPCはピアノ輸入商社として1962年(?)、故・吉沢孝二氏が創業し、ベーゼンドルファー社以外にも、
ドイツなど数社のピアノ輸入総代理店になっていました。
2007年11月27日、ユーロ高などで販売不振となり負債額約3億円を抱え自己破産を申請しました。
吉沢氏が集めた名器も、債務整理で売却対象になったそうです。 |
ALEXANDER STANDARD
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
アレクサンダー・スタンダード
株式会社 福山ピアノ社、東日本ピアノ製造株式会社
<参考資料>
東日本ピアノ製造株式会社を含む会社遍歴は下記の通り
昭和28年 大岡楽器製作所が発足
昭和31年 白鳥楽器製作所
昭和33年 スワン楽器製造株式会社
昭和38年 ガーシュインピアノ株式会社
昭和42年 東日本ピアノ製造株式会社
昭和62年 株式会社バロック |
| ALFRED KNIGHT |
ALFRED KNIGHT LTD. アルフレッド・ナイト イギリス
→詳細な内容はKnightへ |
| ALFRED ROHR, LEIPZIG |
詳細不明 |
| ALLGÄUER |
詳細不明 |
ALLISON
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
Allison アリソン イギリス(ロンドン) 創業1837年
1837年にイギリスで創業したアリソン・ピアノ・カンパニーは、当時、最も評判が高く、
有名なピアノ会社のひとつでした。
イギリスのブランドであるにもかかわらず、アリソンのピアノはそのユニークな音色とスタイルで
イングランドを越えて認知されていた。
アリソンのピアノ工場は、ロンドンのニューボンドストリート50番地にあった。
スクエアグランドピアノ、アップライトピアノ、グランドピアノなど、当時最も需要の多かったピアノを製造。
特に、スクエアピアノがまだ主流であった当時、アリソンピアノブランドは
市場でもトップクラスの品質を誇っていた。
アリソン社は、イギリスのチャペル社に買収されるまで、1世紀以上にわたって大成功を収めた。
チャペル社は、1959年頃までアリソンのブランド名を作り続けた。 |
| ALLMENDIGER |
詳細不明 |
| ALOIS KERN |
詳細不明 |
|
ALTENBURG



画像クリックでHPへ戻る
|
オルテンバーグ/(アルテンバーグ) ALTENBURG ※元来はドイツ
韓国サミック社
現在は中国パールリバー社?
このピアノは珍しくトレードマーク付いていません(他にもトレードマークのないピアノもあります)
ピアノ表面(鍵盤近くの鍵盤押さえ部分)にDesigned by STEINBERG, Germanyという
シールが貼ってあってあり、外装は艶消しでモールディングが付いているなど、
一見ドイツ製のように感じますが、韓国のサミック社製造です。現在は中国製造。
写真下のように、中音部ピアノ線の後ろ側の鉄骨部分にはMade in Germanyと入っています。
音色はとても広がりのある音量豊富で豊な音ですが、やや分厚い感じの印象。
シーズニングがあまりなされておらず、音の狂いが落ち着くまで何年もかかった感じです。
<追記情報を頂きました>
アメリカのニュージャージー州にあるエリザベスという町にAltenburgというピアノ屋さん
(ALTENBURG PIANO HOUSE)という店があり、元はドイツで、その後は移民先のニューヨーク、
引っ越し先のニュージャージーでピアノを作っていたそうです。
ネットの情報によると、既に自社での製作は止めており、Otto Altenburgの名前とロゴは
韓国のサミック社が引き継ぎ、現在は中国の会社が作っているようです。
エリザベスでの販売業は今は六代目の子孫が引き継いでいます。
今回この新情報を頂いたニュージャージー州にお住まいの方によりますと、
「オルテンバーグ」に近い発音とのことです。この度は情報を頂きまして誠にありがとうございます!
※当初このピアノを「アルテンブルグ」と発音表記しておりましたがご指摘により訂正させて頂きました。
オルテンバーグのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい →★ |
| ALTENBURG, FREDERICK |
詳細不明 |
| ALTENBURG, OTTO |
詳細不明 |
|
AMABILE


画像クリックでHPへ戻る
|
アマービレ 東洋ピアノ製造(浜松) 詳細不明
トレードマークは普通の東洋ピアノとは違い、DESIGNED BY TOYO PIANOとなっています。中国製造?
一般的な東洋ピアノのトレードマークはこちら →★(似ていますが少し違います)
※アマービレとは音楽用語で「やさしく、愛らしく」という意味
アマービレのまくり(蓋部分)の銘柄マーク →★
アマービレのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい →★
|
| AMADEUS? |
AMADEUS? アマデウス 中国広州 詳細不明
|
| AMERICAN PIANOS |
詳細不明 |
| AMERICAN MUSIC |
詳細不明 |
| AMHERST |
詳細不明 |
| AMMER |
詳細不明 |
| AMPHION |
詳細不明 |
| AMPICO |
詳細不明 |
| AMYL |
詳細不明 |
| ANDERSON |
詳細不明 |
| ANDERSON BROS. |
Estey Piano Corporation
→詳しくは「Estey」の項目へ |
| ANDERSON SONS |
詳細不明 |
| ANDRÉ |
詳細不明 |
| ANDREAS |
詳細不明 |
| ANDREYS |
詳細不明 |
ANDRUS & CO.
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
Andrus & Co.
1959年にウインター(WINTER & CO.)は、エオリアン・アメリカン社と合併し、
社名をエオリアン・コーポレーションに変更していた間、
ウィンター&カンパニーが製造していたブランド名の一つです
→詳しくはWINTERの項目へ |
| ANELLI |
詳細不明 |
ANGEL
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
エンジェル
製造元:浜松楽器製造有限会社(住所:静岡県浜松市中野町670番地)
設立:1970年(昭和45年)→廃業:1989年(平成元年)
創業者の新井正男氏は、1970年に資本金200万円で浜松楽器製造有限会社を設立。
翌年の1971年(昭和46年)には従業員が13名の規模になりました。
最初はWILSON(ウィルソン)というピアノを製造→詳しくはWILSONの項目参照
トレードマークはチューニングチップの星形内部に、縦にした音叉1本を入れたデザインです。
※余談ですが、チューニングチップの星形をモチーフにしたトレードマークは他メーカーのピアノにもあり、
例えば、CARL SEILER、CASTLE、GUILBERT、LESTER、WAGNERなどもそうです。
機種バリエーション:A-1、A-3など
※尚、ANGELは 「東京ピアノ工業株式会社」と解説した資料もありますが、詳細不明です |
ANGELUS
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
アンジェラス
アンジェラスとは、ピアノブランドではないようですが、グランドピアノ・スクエアピアノ・アップライトピアノ
キャビネットピアノなど、いくつかの形のピアノに採用されていた再生式プレーヤー機構の名称である。
再現機構を搭載することで、ピアノが自動演奏できるようになり、女性がピアノを弾くことが求められていた
この時代には人気のある機能だった。
アンジェラスは、1800年代後半のプレミア・グランド・ピアノ社を皮切りに、
世界大恐慌までの間、いくつかの製造会社によって作られた。
アンジェラスは、Hallet and Davis社でも製造され、後にWilcox and White社が普及させた
どんなピアノにも簡単に適用できるユニークなハンドメイドのプレーヤー・アクションを備えた複製ピアノ。
ウィルコックス&ホワイト社は、コネチカット州メリデンにあった工場で、
年間約500台のアンジェラスピアノを生産していた。
アンジェラスという名前は、パリのオークションで高値で落札されてアメリカで話題になった
フランス絵画からヒントを得た、巧妙なマーケティングだった。
アンジェラスの商標がプレーヤーピアノに初めて登場したのは1897年のことである。 |
| ANGERHÖFER |
詳細不明 |
ANNELL
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
アネール イタリア 詳細不明
|
| ANTON PAPPENBERGER |
→PAPPENBERGERの項目へ |
ANTON WALTER
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
アントン・ワルター オーストリア(ウィーン)
製作者:ANTON WALTER アントン・ワルター/(アントン・ウォルター)
1780年頃? 5オクターブのスパンを持つチェンバロの形のピアノフォルテ
先日発見されたピアノでは、本体と脚がチェリー材を使用、響板は現在でも一般的なスプルース材とのこと。
<以下、WIKIPEDIAからの引用>
父は大工でオルガン奏者でもある。母方はイタリア系の出身。
ウィーンに移住する前の経歴はよく知られていない。
1770年代半ばにはウィーンに移住し、鍵盤楽器製作者として活動し始めたと思われる。
最初にワルターが実績を認められたのは、楽器修復者としてであった。
1781年にエステルハージ宮殿の鍵盤楽器修復を依頼され、12日間滞在し、
24グルデンの報酬を得た記録が残っている。
ウィーンにおける最初期の活動でワルターは正式に同業組合(ギルド)の会員として
認められなかったため、初期の鍵盤楽器にはワルター名義の銘板がついていない。
ギルド入りを許可されなかった理由は、この時期、ワルターは急進的な反体制運動
(ジャコバイト運動)の賛同者とみられたためウィーンでの自由な活動を制限されたからである。
1790年代初めにマリア・テレジアや息子のヨーゼフ2世の計らいにより、ギルド加入が認められ、
1790年末に「宮廷付きオルガンその他楽器製造業者」の称号を得た。
この後、製作された楽器には"ANTON WALTER in WIEN"の銘板が入ることになる。
1796年発行の『ウィーン・プラハ音楽芸術年鑑』に当時のウィーンにおけるピアノ製作者の
記事が記載されている。それによると、当時随一の製作者はアントン・ワルターで
二番手と目されるのがシャンツ、それに続くのがナネッテ・シュトライヒャーと評価されている。
1800年には義理の息子ヨーゼフ・シェフストス(JOSEF SCHÖFSTOSS)が経営に参画し、
"ANTON WALTER & SOHN"の商標を使用するようになる。
ワルターのピアノ(フォルテピアノ)はモーツァルトやベートーヴェンなどの一流の音楽家に
高く評価され、ワルター自身も19世紀初頭には時代の趨勢を担う先進的な製造業者としての名声を得る。
にもかかわらず、ワルターのピアノ事業は19世紀後半におけるピアノ製造技術の革新や
より大型の音量の大きな楽器を求める時代の流行の変化に取り残され、次第に衰退をたどることとなる。
ワルターの楽器
ワルターが皇帝ヨーゼフ2世に宛てた依頼書(正規の楽器製造者としての許可を得るための嘆願書)
によると、1770年代から1790年にかけて、グランド型のピアノ、スクエア・ピアノ、オルガン等の鍵盤楽器を
ワルターは300以上も製作している。
今世紀まで現存しているのはほとんどがフォルテピアノかスクエア・ピアノである。
楽器博物館蔵、ウィーン
ワルターの現存しているピアノのなかで、特に有名なものがモーツァルトが購入した1台であるが、
このピアノには製造業者としてのワルターの銘板がなく、ワルターがウィーンに拠点を置いてまもなく、
まだ正式な楽器製造業者としての資格がないまま製造されたワルターの初期のピアノと推察されている。
この楽器はモーツァルトの死後、未亡人のコンスタンツェから息子のカール・トーマスに相続されたが、
現在はザルツブルクのモーツァルテウム財団の所有となっており、モーツァルトの生家
(記念博物館になっている)に展示されている。
また、フランツ・シューベルトが友人の画家リーダー(Rieder)に下宿していた頃、
友人の所有するスクエア・ピアノを借用していた。
この楽器はワルターの1800年以降に作られたもので、リーダーはシューベルトの死後、
このピアノを売りに出した。一時期、ベーゼンドルファー(Rudwig Bösen-dorfer)が所有していたが、
現在はウィーンの芸術歴史博物館に所在がある。
ワルターのフォルテピアノは、フィリップ・ベルト、ロドニー・レジエ、ポール・マクナルティ、
クリストファー・クラーク他の、現代のフォルテピアノ製作者の楽器のモデルに頻繁に用いられている。 |
AOI STEIN
(AOI)

画像クリックでHPへ戻る |
アオイ スタイン/(アオイ) 島田楽器株式会社(静岡県島田市)
製造元:島田楽器株式会社(静岡県島田市)
販売元:三和精機株式会社(静岡県島田市)
非常に珍しいピアノです。製造台数もかなり少ないと想像されます。
トレードマークの下部分には「SHIZUOKA」と入っていますね。
AOI STEINのまくり(鍵盤蓋)にあるブランド銘柄部分の写真 →★
これらの写真はすべて「PIANO YOSHIKAWA様」からご寄稿頂きました。ありがとうございます!
ご寄稿頂いた「PIANO YOSHIKAWA様」によりますと、ピアノはしっかり作られており、ペダルは2本、
巻線下のフレーム部分には「Designd by SANWA」という文字が入っているそうです。
機種バリエーション:DU-25等
このピアノに関する詳細な情報は残念ながら不明ですが、
AOI STEINピアノの調整・検査票によりますと、「謹製 三和精機株式会社」と入っております →★
こちらの検査票の画像も「PIANO YOSHIKAWA様」からご寄稿頂きました。ありがとうございます! |
|
APOLLO








画像クリックでHPへ戻る
|
APOLLO アポロ
(アポロピアノ)
正式会社名称:東洋ピアノ製造株式会社(旧会社名称:有限会社 東洋楽器製作所)
(TOYO PIANO MFG.Co.,LTD.)
〒430-0913 静岡県浜松市中区船越町34番25号
〒438-0202 静岡県磐田市高木1818番地
音色は明るくきらびやかな印象のピアノです。
アポロピアノの紹介で特筆すべき事項は、弱音ペダルに採用されている、
M.O.T.方式(Muffler One Touchの略)のペダルです。
これはワンタッチで弱音に出来るペダルシステムでアポロが1978年に特許を取得。
通常、真ん中のペダルは弱音にするとペダルが左下へ下がった状態になりますが、
M.O.T.ペダルシステムのピアノはペダルが下がったままになりません。
個人的にこれのどこがすごいの?とは思います笑。(ごめんなさいww)
私の調律養成校在学時の今は亡き恩師(アポロの調律師)が、このM.O.T.をしきりに自慢していました(笑)
ただ、このM.O.T.のメカ(我々はこれをガチャガチャと呼びます)がまたよく壊れるんです。。→★
トレードマークは2本の音叉に囲まれた3個のハンマーヘッドを使ったデザインです。
尚、直近のピアノでは「TOYO」と入ったエンブレムに変更になっております。
<概要沿革>
石川隆己(いしかわ たかみ)前社長自らの設計、指導、製作により、
昭和40年ごろまでは1台1台に毛筆のサインをして世に送り出していたようです。→★
350号などの初期のものは技術者が賞賛した逸品でもある。
石川隆己氏(明治44年生)は山葉直吉氏(山葉寅楠の姪と結婚した養子)、河合小市氏らに
教えをうけ、日本楽器から河合を経て昭和9年独立、三葉楽器製作所を作りました。
アポロピアノを製造している浜松の東洋ピアノ製造株式会社の発祥の源は、
1934年にさかのぼり、初代社長であった石川隆己氏が日本楽器および河合楽器で
約十年間ピアノの技術を修行した末に、天竜川の東岸の竜洋町で三葉楽器という
小さい工場を作ったことに始まります。
<歴史>
初代社長の石川隆己氏が、日本楽器および河合楽器で約10年間ピアノの製造技術を修行した末、
天竜川の東岸の竜洋町で三葉楽器という小さな工場を作ったことにはじまります。
別の記録だと、「1933年(昭和8年)に浜松市で、技術者の石川隆巳と、
財務担当の大谷藤四郎が「三葉楽器製作所」としてピアノ作りを始めた」ともある。
このピアノ工場は終戦間際まで稼動していたと伝えられるが、何しろ戦時中であったため
どのような楽器が作られていたかはさだかではない。
東洋ピアノの設立は1948年6月10日と記録されていますが、それ以前の1947年1月に
石川社長は中島飛行機の教官であった大谷藤四郎氏を副社長として有限会社の
東洋楽器製作所を作っている。
終戦直後の混沌とした世相の中で、楽器を作って殺伐とした人の心を和らげ、
少しでも社会に貢献したいというのが2人の目的であったといいます。
最初の従業員は30人くらいで、焼けあとを走り回って材料を掻き集め、
足らないところは戦時中の経験を活かし、いわゆる代用品で補い、低音部の弦は
電線の銅線を巻き付けて、とにかくピアノらしいものを作り上げました。
いづれにしても、戦後最初のピアノを他社に先駆けて作り上げる功績を果たしました。
東洋ピアノ製造株式会社を発足させてからの石川社長の活躍はすさまじく、
その後の30年を懸命に働き続け、この会社をヤマハ、カワイに次ぐ生産台数を誇る
ピアノ製造会社に成長させました。
石川社長は非常に厳格で恐ろしい親方であったといいます。気に入らないアクションが
出来たときは乾燥炉に放り込み燃やしてしまったといいます。
鍵盤内部(KeyNo.1)に書かれた石川隆己氏の直筆サイン(一九七九年十月検と書いてあるようです) →★
次の社長に就任した長坂晁弘氏は、石川社長時代ながらく経理部長、営業本部長などを
歴任して会社に貢献してきた人で、初代社長とはうってかわって温厚な方であったようです。
「私が引き継いだときにはこの会社は出来上がっていました。私は音楽も好きではないし
ピアノにも精通していません」という謙虚な言葉の裏には、堅実で誠実な人格があります。
この社長のもとで引き続きアポロピアノは着実な発展を遂げたのは言うまでもありません。
アポロのまくり(蓋部分)の銘柄マーク →★ アポロピアノの保証書
→★
アポロの文部省教育用品審査合格シール →★ アポロアクションレールのシール
→★
アポロ純正キーカバー →★ アポロのグランドピアノ響板デカール →★
アポロピアノもワグナーピアノも東洋ピアノ製造なのでTPKと入っています(2つを並べた写真)
→★
<機種バリエーション/モデル>
■グランドピアノ
旧式
A-30(長さ152cm)、A-35(長さ206cm)、A-38(長さ231cm)
現行
AX-1(長さ151cm)、AX-2(長さ151cm)、AX-1w(長さ151cm)、AX-2w(長さ151cm)
■アップライトピアノ
旧式
SRシリーズ (黒塗 SR-5、SR-6、SR-7、SR-8)、(生地塗 SR-250、SR-260、SR-552、SR-580)
SSSシリーズ SR-65、SR-85、SR-565 (それぞれに黒塗、生地塗、アンチック塗あり)、A.350など
現行
A120PIERRE、A120LE、A126、A122、A122DX、A126B Imperial、A126CS Imperial、
A133W Imperial、A133M Imperial、A120 Imperial
<附録>
アポロピアノ 製造番号/製造年代 対照表(1948年~1988年) →★
アポロピアノ 製造番号/製造年代 対照表(1966年~1999年) →★
アポロピアノ 製造番号/製造年代 対照表(1999年~2012年) →★
アポロのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい →★ |
APOLLO
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
アポロ 創業1901年 アメリカ(ミシガン州のグランドヘイブン・イリノイ州デカルブ)
アポロピアノは、メルビル・クラーク・ピアノ・カンパニーというピアノメーカーの製品として知られている。
メルビル・クラーク・ピアノ・カンパニーは、1901年にミシガン州のグランドヘイブンとイリノイ州の
デカルブにある工場でアポロ・プレーヤー・ピアノの製造を開始した。
会社名の由来となったメルビル・クラークは、オルガンメーカーとして成功した後、
ピアノの世界に転身した人物である。クラークは発明家、クリエイターであり、
その発明品は数多くの特許を持ち、その多くがアポロピアノに採用されている。
1920年代初頭、会社はThe Rudolph Wurlitzer Companyに売却され、
1930年代まで様々なApolloモデルの生産を続けた。
世界大恐慌の影響でピアノの売り上げは減少し、第二次世界大戦の頃には
Wurlitzer社はApolloシリーズの製造を中止していた。
アポロは、Apollo、Art-Apollo、Apollo-Phone、The Apollo Reproducing Pianoという名前で
ピアノを製造しており、先駆的なプレーヤーピアノやレコーディングピアノでよく知られている。
これらのピアノは、極めて精巧に作られた高級プレーヤーピアノとされている。
88鍵すべてを弾くことができ、アップライトピアノとグランドピアノの両方が製造され、
カスタムメイドのピアノロールを演奏することができる。
また、アポロフォンには、音楽を録音・再生できる蓄音機も搭載されていた。 |
APOLLO & YAKO
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
アポロ&ヤコ (雅歌)
雅歌楽器企業股份有限公司 台湾(中国)
販売:雅歌楽器企業(台湾)
日本の東洋ピアノ製造株式会社との技術提携会社である。
工場は高雄市自強二路にあって従業員は最盛期で330人ほど。
機種:A360など |
APOLLO HELLO KITTY
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
アポロ・ハロー・キティ 東洋ピアノ製造株式会社
サンリオキャラクターであるキティちゃんとコラボした女の子向けのかわいいデザインピアノ。
ピアノ前パネル、又は拍子木、更には専用イスに、ハローキティのメダルプレートが施されている。 |
| APORO |
アトラスピアノ株式会社
詳細不明 |
| ARCADE |
詳細不明 |
| ARCHER |
詳細不明 |
ARION PIANOFABRIK
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ARION アリオン 創業1866年頃
Arion Pianoforte Company
1866年頃、ジョージ・マナーがニューヨークでアリオンピアノフォルテ社を設立した。
アリオンという言葉は、ジョージが特許を取得したピアノフォルテの革新的な技術を意味している。
アリオンはジョージ・マナーが特許を取得したピアノフォルテの革新的な技術の名称で、
ジョージ・マナーはこの技術を会社名に採用した。
1869年、シンプソン・アンド・モデル・ピアノ社のジョン・シンプソンがアリオンピアノフォルテ社を引き継ぎ、
1885年にエスティ・ピアノ社が買収するまで、この名前でピアノを製造していた。
エスティ社は1920年までアリオンピアノを製造した。
その後、J.P.ヘイルをはじめとする多くのメーカーが「アリオン」をブランド名として使用した。
世界大恐慌の前のある時期に、アリオンの名前は廃止された。
グランドピアノやアップライトピアノはよく知られているが、ピアノフォルテはあまり知られていない楽器である。
ピアノフォルテとは、文字通り「弱音と強音のあるチェンバロ」あるいは「柔らかいピアノ」を意味し、
チェンバロから現在のピアノへの飛躍のきっかけとなった初期のピアノである。
アリオンのピアノフォルテは、誰が見ても優れた業務用ピアノだった。
富裕層向けに販売されており、音だけでなく見た目も美しい。
螺鈿(らでん)などの貴重な素材を使ったものも多い。 |
ARIRANG

画像クリックでHPへ戻る |
ARIRANG 読み:アリラン? 韓国(ソウル)
SAUJINの上位機種? ピアノのまくり(蓋部分)にはSAUJINの文字
その他、詳細不明
トレードマークの文字には「ARIRANG SEOUL KOREA」と入っています。
このトレードマーク画像は「匿名希望様」からご寄稿頂きました。ありがとうございます! |
ARMBACH
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
アームバッハ ソ連(ロシア) 詳細不明
|
ARMSTRONG
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
アームストロング 創業1884年
アメリカ(ニューヨーク州 イースト・ロチェスター/East Rochester)
1884年、W.B.アームストロングによってニューヨーク州イースト・ロチェスターに設立。
アームストロング・ピアノ・カンパニーは、グランドピアノ、アップライト、さらにはコイン式ピアノを製造。
1900年代初頭、アームストロング社はフォスター・ピアノ・カンパニーと合併し、
フォスター・アームストロング社となった。
1926年、アームストロング社はオフィスを南のロチェスターからニューヨークに移した。
アームストロング社は大恐慌を乗り越え、1959年にはエオリアン・アメリカン・コーポレーションに買収。
アームストロング社の名を冠したピアノは、1982年にブランドを廃止するまで、ほぼ1世紀にわたって生産された。
"Sound in body and musical in soul "は、アームストロング・ピアノ・カンパニーのモットーであり、
まさにそれにふさわしいものでした。
アームストロングピアノは、アメリカの音楽界において、高品質で洗練された楽器として知られていました。
美しい音色を持つアームストロングピアノは、ニューヨーク州ロチェスター市の公立学校で唯一使用されていた。
信頼性が高く、見た目にも美しいアームストロングピアノは、1900年代に最も耐久性のあるピアノのひとつとして
その地位を確立していました。 |
| ARMY & NAVY |
詳細不明 |
| ARNOLD |
詳細不明 |
| ARTFIELD |
詳細不明 |
| ARTMANN |
詳細不明 |
ASAGA


画像クリックでHPへ戻る |
ASAGA アサガ
アサガピアノ調律所、浅賀ピアノ商会 創業1941年
製造元:アサガピアノ調律所(当時の住所:東京都文京区駒込動坂町221)
発売元:浅賀ピアノ商会(当時の住所:同上)/アサガピアノ調律所
※駒込動坂町は現在の千駄木四・五丁目、本駒込三・四丁目付近です
トレードマークにはASAGA(浅賀)という文字が入っています。
※ZAUBER(ツァーベル)とまったく同じトレードマークです。
創業者である浅賀伝次郎氏は1925年4月に16歳でピオバ楽器に入社、ピオバ楽器の野口喜象氏から
ピアノ製造技術を学び、1941年に32歳で独立しアサガピアノ調律所を開業。
ここで自社ブランドであるアサガピアノを完成させ、1955年には「アサガ音楽教室」を開設もしました。
同社が発売したZAUBER(ツァーベル)はスワン楽器株式会社に製造を依頼して作らせたものです。
木梨ピアノ調律所を開設した木梨信雄氏はアサガピアノ調律所出身。 |
ASAHI


画像クリックでHPへ戻る |
株式会社アサヒピアノ(朝日ピアノ)が海外向けに出しているブランドとのこと
中国製造 |
| ASHENBACK |
詳細不明 |
| ASKOLIN |
詳細不明 |
| ASTER ? |
ASTER? 韓国(英昌) 詳細不明
|
ASTIN WEIGHT

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ASTIN-WEIGHT アスティン・ウェイト
創業1959年 アメリカ(ソルトレイクシティー)
住所:120 West 3300 South, Salt Lake City, Utah ♯84115 UNITED STATES OF AMERICA
このピアノ会社は標準化されたピアノの設計を取り入れず、ユニークな手法を取り入れて製造しているのが特徴。
独特な外装がそれを物語っています。
1959年にエドウィン・アスティンとドン・ウェイトがソルトレークシティーに
アスティン・ウェイト社を設立し、1978年にレイ・アスティンが社長に就任。
アスティン・ウェイト社はグランド、アップライトともに限られた台数を製造し、ユニークな点としては
ストラングバックの設計が挙げられる(ストラングバッとは、鍵盤とアクション以外のピアノ本体のこと)
一般的なピアノの場合、響板はピン板の高さまでしかないが、このメーカーは音量と豊かな音色を得るために、
響板をケース全体へ広くしたアップライトピアノを製作。
その結果、普通のアップライトよりも高さが約25cm低いにもかかわらず、大きな面積の響板を確保に成功。
ただ、この斬新な設計は独特な音色をもたらしたと言われているが、設計上の都合で駒を高くしたことにより、
ミュージックワイヤーのエネルギーが余計に吸収され、音がひずむと指摘する批評家もいる。
これはピアノの音質に大きく関わるのは響板の大きさではなく、弦のスピーキングレングス(有効弦長)の方が、
重要ということが広く知られているからだろう。
さらにこのピアノは適切な奥行きを得るためなんと背面の支柱を省いている。
その代わり、弦の張力に耐えられるように鉄の全周一体型フレームを採用している。
このタイプの構造はすでにヨーロッパで50年以上前から採用されてきたものの、技術者の中には
背面の支柱をなくすことは、調律の安定性に欠けるという者もいる。
アスティン・ウェイト社は176cmのグランドピアノも限定的に製造しており、
こちらはアップライトよりもさらに急進的な設計で、一般的なグランドピアノとは違いって、
長辺を持たず、なんとほぼ左右対称の形をしている。
そのため低音部の駒を響板の奥に配置でき、弦長が格段に延びて230cmクラスのピアノに近づき、
また響板の面積も広くなっている。そのためピアノは非常に奇妙な形を呈しており、
蓋のヒンジは低音部ではなく、高音部側で留められている。
アスティン・ウェイト(Astin-Weight)ピアノの製造番号/製造年代 対照表(1965年~2000年) →★ |
| ASTOR |
詳細不明 |
ASTORIA

下記は参考画像

画像クリックでHPへ戻る |
ASTORIA アストリア
タイガー楽器設立の前に、山葉良雄氏の(有)山葉商会という販売店が、
浜松の小さな工場の共立楽器工芸社(浜松)に発注して作ったピアノと言われています。
※「共立楽器製作所」となっている別資料もあり(要確認)
トレードマーク画像は”KUHLMANN”とまったく同じなので参考画像として掲載しています。
なぜ同じトレードマークなのかの理由は不明です。
ちなみにワインバーガーという韓国製のピアノのトレードマークにもよく似ています。
※トレードマークを並べて比べた画像 →★ 尚、ドイツの国章にもそっくりです →★ |
ATLANTIC

画像クリックでHPへ戻る |
アトランティック 株式会社西川楽器製作所
株式会社 西川楽器製作所(横浜市神奈川青木町)
※(西川楽器は日本楽器に合併吸収されまでの1884年~1921年まで稼働)
※(西川ピアノ時代のピアノ製造期間は1916年~1921年までとの記録がある)
ATLANTICピアノの外観写真 →★
左記トレードマークと外観のお写真は、「匿名希望様」からご寄稿頂きました。
ご寄稿者様によりますとこのピアノは80歳を超えるお祖母様が子どもの頃からあったピアノだそうです。
この度は大変貴重なお写真をご寄稿頂きまして誠にありがとうございました! |
|
ATLAS




画像クリックでHPへ戻る
|
アトラス ピアノ ATLAS PIANO
1954年創業。正式会社名:アトラスピアノ製造会社
当時の会社住所:浜松市神田町1400番地
”アトラス” とは、”(画像)ギリシャ神話で地の果てで天球を支える巨大な神” が由来とされています。
アトラスはピアノメーカーとしては新しい方ですが、その後の発展は著しく、
近代的な生産設備、生産数においてはヤマハやカワイに次ぐものでした。
ただ、そう言われるほど私はこのピアノ自体には出会いませんが。。
性能、音色については総合的にバランスのとれた感じの印象です。
当初アトラスのピアノ工場は、十数畳ほどの小さな場所でした。
頼金忠氏が無一文から出発して、その後わずか20年で
資本金が3億5千万円(最盛期)にも及ぶ会社に築き上げました。
ですが、1980年代に入るとピアノの需要が落ち込み、1986年に事実上の倒産に至ります。
これも時代の流れですね。
<歴史>
アトラスピアノ製造会社は、1955年発足というピアノ製造会社にしては
かなり新しい会社になります。ですが、発足後の発展はめざましく、
近代的な設備の導入をはじめ、ヤマハ・カワイに次ぐメーカーに発展しました。
最盛期3億5千万にもおよぶこの会社の最初は、とても小さな工場からスタートしました。
その人物とは社長の頼金忠氏でした。
頼金正と解説したHPや資料もありますが、正しい頼金氏のお名前は「忠」です。
彼は無一文から出発し、なんとわずか20年で築き上げたものです。
一代で成功した人々はスタインウェイなどのように通例として仕事に全身全霊を捧げ、
人生の欲望を捨て、さらには肉親の生命を犠牲にしてまでその目的に邁進する者が多い中、
頼金忠氏はその例外であると言ってよいかもしれません。
言い伝えでは穏健な紳士でピアノで演歌を弾きこなし、七段の腕前で空手を楽しみ、
この常に明るく陽気な性格を持っている幸運な社長の半生は次のようなものです。
頼金氏は1926年広島県竹原市の酒造りの頭梁をつとめていた父の10人兄弟の6男として
生まれ、広島師範学校(現在の広島大学教育学部)に進みました。
そこでピアノの演奏に興味を持ち始め、連日練習に励んだのがピアノとのなれ初めでした。
終戦の混乱期は、頼金氏の教師になるという本来の目的性を失わせ、彼を実業界という
正反対の方向に走らせてしまいました。
彼は、明治大学の商学部に進むかたわらアルバイトでピアノの販売に没頭・熱中し、
なんと月間30台も売ったという逸話も。さらに空手の練習にも傾注されたとのことのようです。
このアルバイトはほとんど本職に転化していったと伝えられています。
彼は大学を卒業する直前、1953年に兄との共同で東京の青山に「日響ピアノ」という
店を開業発足させました。しかし彼は販売だけにはあきたらずピアノの製造技術を学ぶため、
兄に日響ピアノの経営をまかせ、浜松にあった遠州ピアノ製造株式会社などで武者修行をし、
自らはピアノ製造メーカーの世界に身を乗り入れました。
アトラスピアノの源となった「日米楽器工業所」は、1955年6月10日に発足。
場所は浜松市の浅田町。発足当初はピアノ職人を数人かき集め、外注依存の組み立て専門の
工場として出発したことに始まります。
どんなピアノにでも付けられるという便利な鉄のフレームを作り、設計書もなしに意外に
品質の良いピアノを次々と生み出していったようです。
当時はこのような組み立てピアノの全盛期で、小さい工場が国内に35~40社ほどもあり、
さまざまなブランドのピアノを作っていました。
当時の日米楽器では「スタンダード」、「ノーベル」、「アトラス」、「アーデルスタイン」などの
ブランドのピアノを作ったと記録されています。
創業2年目である1956年に日本のピアノの創始者である山葉寅楠氏の直弟子の中の一人である
匹田幸吉氏が参加し、この頃から独自の設計のピアノが作られ始め、品質は劇的に向上しました。
この頃、国立音楽大学楽器研究所の主任であった西村武氏に認められ、国立音大の
指定工場となり、販売、技術ならびに資金の援助を仰ぐようになった。
尚、当時国立音大の研究室で作られていた同じ仕様のピアノには、「コンセルバトワール」
というブランド名が付けられていたそうです。
※西村武氏はわが国でも古いピアノメーカーの一つである松本ピアノ出身の技術者で、
ピアノの製造技術を学問的に解明した学者肌の人で、惜しくも49歳で亡くなってしまいます。
西村武氏は、わが国のピアノ調律界の元老だった中谷孝男氏と共に、日本のピアノの
品質向上に多大なる貢献を果たした人物です。
「アトラス」というブランドは国立音大の指定工場になった1956年から使われており、
このアトラスという商標はこの西村武氏から譲られたものでした。
ちなみにこの”アトラス”とは、遥か西の地の果てで天球を支えているギリシャの
途方もない巨大な神で、西村武氏ご自身の身体は小さかったが、希望は大きい方が良い、
世界を目指そうという主旨で決められたと言い伝えられています。アトラス参考画像 →★
1990年代に国内メーカーとしてのアトラスは事実上の廃業に至ります。
現在は中国のメーカーが商標を買取り、販売しているとされているが、詳細は不明である。
(少々判明したので下記★★★へどうぞ)
<アトラスピアノ画像集>
アトラスの蓋部分のメーカーロゴ →★ アトラスの外装に貼ってある物品税証紙
→★
アトラスピアノの純正キーカバーです →★
アトラスピアノの響板に描かれたアトラス(ギリシャ神話で地の果てで天球を支える巨大な神)
→★
<レア画像>
昭和50年代に納品されたアトラスピアノに付いていたカセットテープ式自動演奏機システム
→★
<附録>
アトラスピアノ 製造番号/製造年代 対照表(1971年~1990年) →★
※アトラスで珍しいものとして「津軽」という機種があり、外装がまさに津軽塗で作られています。
<機種バリエーション>A30、A35、AL30、NA150、NA505等
<以下、ウィキペディアより引用抜粋>
アトラスピアノ製造株式会社(アトラスピアノせいぞう)は、かつて静岡県浜松市にあった
日本のピアノメーカーである。当時の会社住所:浜松市神田町1400番地。
広島県出身の頼金忠は、学生時代に学業の傍らピアノ販売のアルバイトをしていたが、
卒業後は遠州ピアノ製造株式会社などでピアノ製造技術を学び、1958年、有限会社日米楽器工業所を設立、
1960年に商号および組織を改変しアトラスピアノ製造株式会社となる。
1961年、日本で最初のピアノJIS工場の認可を受け、翌年には広島支店を開設、
その後日本ピアノ製作所を買収、日本ピアノアクション製造株式会社を吸収合併するなど、
1960年代から1970年代にかけては、日本のピアノメーカーとして、生産設備、生産台数において
ヤマハ、カワイに次ぐ勢いであった。1980年代に入るとピアノの需要が落ち込み、
1984年には業務提携していたブラザー工業株式会社が撤退し、1986年に事実上の倒産に至る。
再建にむけて本社を移転し再出発するも、1990年代には国内での生産は廃業し、
その後は中国のメーカーが商標を買取り、販売しているとされているが、詳細は不明である。
(少々判明したので下記★★★へどうぞ)
いずれにしても、日本国内で生産されたアトラスピアノは姿を消した形になる。
アトラスはギリシャ神話で地の果てで天球を支える巨大な神であるが、ピアノの響板にもこの姿が描かれている。
命名者は日米楽器の頃よりピアノ製造の中心的な存在であった、国立音楽大学楽器研究所主任でピアノ調律師の
西村武であり、以後アトラスピアノ工場は国立音楽大学の指定工場となり、品質向上に大きく携わる。
以下は日米楽器工業所及びアトラスピアノ製造株式会社で製造されたピアノのブランド名の一部です。
★★★
~中国のアトラスピアノについて~
老舗だった日本のアトラスは1990年代に完全に廃業しており、今現在アトラスはピアノを製造していません。
廃業後、商標権を取得した中国にある企業(※調べによると、阿托拉斯乐器制造(大连)有限公司という会社)が
現在この「アトラス」のブランド名を使ってピアノを製造しています。
アップライトをはじめ、なんとグランドピアノも製造し、ピアノ蓋にある「Atlas」の書体ロゴもまったく同じです。
まだ私自身実際にこの中国版アトラスを見たことがないので、品質や音色については何とも言えませんが、
過去に日本で製造していたあのアトラスピアノとはまったくの別物のピアノですのでご注意下さい。
商標権を取得したからといって、輝かしい日本のアトラスの歴史を丸々パクっているところが中国らしいです。
<正真正銘日本のアトラスが製造を手がけたことがあるブランドを下記に列挙しておきます>
■ ATLAS (アトラス) - アトラス
■ ADELSTEIIN (アーデルスタイン) - 日米楽器
■ BROTHER (ブラザー) - アトラス
■ KREUIZBACH (クロイツバッハ) - アトラス
■ MEISTER (マイスター) - アトラス; 阪急百貨店のブランド
■ MORGENSTEIN (モルゲンスタイン) - アトラス
■ NOBEL (ノーベル) - アトラス、日米楽器
■ ROYAL (ローヤル) - アトラス
■ STANDARD (スタンダード)- 日米楽器
■ STEINMEYER(スタインマイヤー)- アトラス; 高島屋のブランド
■ VICTOR (ビクター) - アトラス
<注意>L. MEISTER は中国製造のようです。
アトラスのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい →★ |
ATLAS
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ATLAS 中国 阿托拉斯乐器制造(大连)有限公司
中国にある企業が、過去に日本あった「アトラス」の商標権を買い取って製造。
現在日本のアトラスは倒産しているので、日本のアトラスとはまったく別のピアノです。
詳しくは上記、日本の「アトラス」内の説明欄の下の方、
★★★「中国のアトラスピアノについて」部分をご参照下さい。 |
| ATLAS JUNIOR |
ATLAS Jr. アトラス・ジュニア
アトラスピアノ製造株式会社 |
| ATOMOS |
アトモス フローラピアノ製造株式会社 |
| AUBURN |
詳細不明 |
| AUCHER |
詳細不明 |
AUGUST FORSTER
AUGUST FÖRSTER


画像クリックでHPへ戻る |
アウグスト・フェルスター AUGUST FORSTER/AUGUST FÖRSTER
(アウグスト・フォルスター)/(オーガスト・フォルスター)/(オーガスト・フェルスター)
/(アウグスト・フォルエステル)/(アウグスト・フォルステル)
ドイツ(旧東ドイツ)ザクセン地方のレーバウ AUGUST FÖRSTER
チェコにも工場があったが太平洋戦争後に消滅。
1859年に設立されアウグスト・フェルスター社は第二次世界大戦より前に、
クオーター卜ーン・グランドピアノやエレクトロコードのような革命的な棉造の楽器を生み出した。
今日のアウグスト・フェルスターのピアノは、妥協のない細部へのこだわりで知られている。
アウグスト・フェルスター社のピアノは温もりのあるまろやかな音色が特徴で、
低音は力強くよく鳴るのが特徴。高さが116cm~125cmの6つのモデルのアップライトピアノと、
長さが170cm~275cmの5つのモデルのグランドピアノを製造している。
ジャコモ・プッチー二は、ほとんどのオペラをこのアウグスト・フェルスターのピアノで作曲した。
基本的な構造は従来のグランドピアノと変わらないが、エレクトロコードは最低音部の8音を除き、
1音に2本の弦が張られていた。ハンマーは1本の弦だけを打ち、もう1本の弦は短く、かなり弱い
テンションで張られていて、共鳴して振動する。この弦のいろいろな位置に静電ピックアップが
垂直と水平方向に設置され、幅広い音色とアタック特性を拾うことができた。エレクトロコードには
オプションでラジオや蓄音機を取り付けることも可能だったという。
<歴史>
フリードリヒ・アウグスト・フェルスターは、1829年にドイツのオーバーザイファースドルフに生まれた。
家具職人の見習いとして働きだし、空いた時間に楽器の修理を行っていた。
その後、楽器作りへの情熱が高まり、フェルスターはレーバウへ移って、ヒーケと力ール・オイレのもとで
ピアノ製作の修行を始める。
そして、小さな工房を開いて最初のピアノを作り上げ、その5年後の1854年にピアノ職人の試験に合格する。
1862年、フェルスターはレーバウ郊外に工場を設立した。その後、何度となく改修や改築が行われたが、
工場は現在もこの場所にある。
1897年、アウグスト.フェルスターは、 息子ツェーザーに会社を遺して亡くなるが、ツェーザーは
1915年までしか生きられなかった。
さらに今度はツェーザーが、息子のゲルハルトとマンフレートに会社を遺して亡くなる。
ピアノ業界ではよくあることだが、ふたりの息子は異なる特性を生かし、
それぞれのやり方で会社の成長に貢献していく。
この兄弟の場合、マンフレートはビジネスマンであり、
ゲルハルトは革命的な構造の楽器を生み出す器用な製作者だった。
1924年から1931年の間に、ゲルハルトは、チェコの作曲家アロイス・ハーバの作品を演奏するための
クオータートーン・ピアノ (4分音ピアノ。半音の半分の音を出せるピアノ) を数台製作する。
その後、ゲルハルトは、オスカー・フィアリングが1933年に特許を取得した設計に基づき、
「エレクトロコード」と称する電気ピアノを製作した。
現在の工場は、創業者一家4代目のヴォルフガング・フェルスターが所有、経営している。
■機種/モデル バリエーション
アップライトピアノ モデル:Super C
グランドピアノ モデル:170、190、170Rococo
※アウグストフェルスターピアノはBVK認証を受けています(詳しくはこちら →★)
AUGUST FORSTERのトレードマークは匿名希望様からご寄稿頂きました。ありがとうございます!
<附録>
アウグスト・フェルスターピアノ 製造番号/製造年代 対照表(1873年~2000年)→★
<以下、ウィキペディアより引用抜粋>
アウグスト・フェルスター(August Förster)はドイツのピアノ製造会社である。
正式名称は「August Förster GmbH Kunsthandwerklicher Flügel-und-Pianobau」
「Foerster」や時折「Forster」とも翻訳される。
現在は40名の従業員を雇用し、年間およそ120台のグランドピアノと150台のアップライトピアノを生産している。
1859年4月1日、アウグスト・フェルスターはドイツ・レーバウに小さなピアノ工房を開いた。
1862年にはレーバウのJahn通りに工場を拡大した。
今日まで使用されているこの施設はフェルスター家によって拡大・近代化されてきており、
オリジナルのアウグスト・フェルスターピアノの製造のための唯一の場所であり続けている。
1897年、ツェーザル・フェルスターは父アウグストの後を継いで会社の経営者となり、
1900年にボヘミア(後のチェコスロバキアとチェコ共和国)のゲオルクスヴァルデ
(チェコ名はイジーコフ Jiříkov)に2つ目の工場を開いた。
フランツ・ツェザール・フェルスターはオーストリア=ハンガリー帝国帝室・王室御用達を与えられた。
1937年、フェルスター社は最初の電気ピアノの一つである「Vierling-Förster」ピアノを製造した。
このピアノはベルリン工科大学ハインリヒ振動研究所のOskar Vierlingによって開発され、
電磁ピックアップを使用している。
第二次世界大戦後、ゲオルクスヴァルデのドイツ系住民は排斥され、
1945年にゲオルクスヴァルテ工場は国営化された。
新しい国家管理の下で質の高い多くのピアノが生産されたが、1945年以降のチェコ製ピアノは
ドイツのアウグスト・フェルスターピアノとは無関係である。
この「もう一方の」アウグスト・フェルスターは2000年までペトロフ社によってチェコ共和国で生産され、
カナダや一部の欧州の国々で販売された。
1972年、東ドイツの国営化の最終段階で会社は国有「VEB Fluegel-und-Pianobau Loebau」に変わった。
まだウォルフガング・フェルスターの管理下にあったものの、
フェルスター社はVEBドイツピアノ組合ライプツィッヒの一部として併合された。
家名は1976年に公式の会社名に戻り、楽器ブランドは「VEB Förster Pianos Loebau」となった。
また1976年に、フェルスター社はアメリカ合衆国への輸出を始めた。
多くの高名な音楽家がドイツ製フェルスターピアノを好んできた。
その中にはリヒャルト・シュトラウスやセルゲイ・プロコフィエフがおり、
どちらもフェルスターピアノを所有していた。
また、ジャコモ・プッチーニはフェルスターピアノを使って数多くのオペラを書いた。
Robert Fischer、Alex Duke、アントン・クエルティもまたフェルスターピアノを好んでいたことが記されている。
フェルスター・ピアノは品質と音色によって、1987年の「Verleihung der Goldmedaille für den Rokokoflügel
(ロココグランドピアノ・金メダル)」を含む多くの賞を受賞してきた。
ラリー・ファインの『The Piano Book』において、ドイツ製アウグスト・フェルスター・ピアノは
性能、品質管理、信頼性(一般的な耐久性を意味するファインの用語)の部門で最も高い評価を受けた。
「高品質性能ピアノ」のカテゴリーで、ファインは現代のアウグスト・フェルスター・ピアノを
C・ベヒシュタインやグロトリアン・シュタインヴェーク、ベーゼンドルファーといった
国際的に評判の高い楽器のすぐ下に順位付けした。
加えて、ファインは現代フェルスター・ピアノをその「卓越した低音」について称賛し、
またレンナー社製アクションの際だった反応の速さについても言及した。
公式HP:https://www.august-foerster.de/ |
AUGUST HOFFMAN



画像クリックでHPへ戻る |
オーガスト・ホフマン/アウグスト・ホフマン 中国
August Hoffmanは、もともとはスウェーデン生まれのピアノブランドだが、
現在は中国遼寧省のピアノメーカー営口東北鋼琴(ドンペイピアノ)で生産。
トレードマーク画像は「高永ピアノ調律事務所様」からご寄稿頂きました。
この度は画像のご寄稿を頂きまして誠にありがとうございます!
<以下、ウィキペディアより引用抜粋>
アウグスト・ホフマンス・ピアノファブリック
(典: August Hoffmanns pianofabrik、August Hoffmannのピアノ工場)は、
1838年から1988年まで存在したスウェーデン・ストックホルムのピアノ製造会社である。
会社の起源はSöderberg父子の工房にある。この工房は1859年にピアノ製造技師アウグスト・ホフマン
(August Hoffmann、1827年ザクセン州生まれ)によって買収された。
ホフマンはドイツ、オーストリア、ハンガリーで修行していた。
ライプツィヒ時代にホフマンは伝説的なハインリヒ・シュタインヴェーク
(後のヘンリー・スタインウェイ)と友人だった。
アウグスト・ホフマンは1840年代に短期間カルルスハムン(英語版)でピアニストの
A. F. Sätherbergのために働き、ドイツに戻った後、最終的にはストックホルムに定住した。
スクエア・ピアノは1870年代初頭に最も人気があり、1873-74年には200台のスクエア・ピアノが製造された。
その後アップライトピアノが次第に人気となり、1884-88年には年間わずか40台のスクエア・ピアノが生産された。
アウグスト・ホフマンは1884年に死去したが、未亡人のナンナ・ホフマン(Nanna Hoffman)が工場を経営した。
ピアノ産業では初めての王室御用達となり、25人の従業員を雇用した(6人が楽器職人・調整師、他は家具職人)
ホフマンは1890年代の初めにストックホルムを訪れたスタインウェイの助けを受けた。
その他の多くの工房と異なり、ホフマンの工程は相当量の手作業によることが特徴だった。
工場はBanérgatanにあり、整備と販売はマルムフィルナツガータン通り(英語版)33の店で行われた。
1930年代、オペラ歌手のマルティン・オーマン(フランス語版)はこの店の販売員として働いていた。
スウェーデンでの製造が終わって以降、August Hoffman(ホフマンの綴りに注意)のブランド名を
冠したアップライトピアノ、およびグランドピアノが中国遼寧省のピアノメーカー
営口東北鋼琴(ドンペイピアノ)によって製造され、香港やカナダを含む世界中で販売されている。
このブランドと元々のスウェーデンの会社との関係は不明である。
ドンペイピアノは2007年にアメリカのギターメーカー「ギブソン」(Gibson)のグループに入り、
社名を「Baldwin Dongbei Piano」に変更。
アメリカの老舗ブランド「Baldwin」や、スウェーデンブランドの「Nordiska」などを製造している。
August Hoffmanピアノは、アメリカ、カナダ、ヨーロッパで販売されているが、
日本では「August Hoffman 112G」、「August Hoffman 114WH」、
「August Hoffman 115GC」の3機種が販売されている。
いずれも木目調のコンパクト型ピアノで狭い住宅事情に適している。 |
AUTO
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
オート AUTO PIANO CO. 1903年創業 アメリカ(ニューヨーク)
1903年にニューヨークで設立されたオートピアノ社は、プレーヤーピアノを製造していた。
プレーヤーピアノとは、ピアノに空気装置を取り付け、回転する穴のあいたロールが
ピアノに音符を知らせることで、自動的に演奏できるようにしたものである。
ロールは別々に販売され、それぞれに異なる音楽が収録されていた。
例えるなら今でいうCDやレコードのようなものです。
自社ブランドのプレーヤーピアノに加え、「ピアニスタ」「シンフォトーン」というピアノラインも製造。
オートピアノ社は、当時大きな成功を収めた。
30万平方フィートの広大な工場に常時1万台のプレーヤーピアノを収容し世界中に出荷していた。
特に南米や北極圏では、湿気、暑さ、乾燥、寒さに強いオートピアノが人気を博した。
世界的な人気に加えて、オートピアノ社は、国内外で数え切れないほどの賞や栄誉、称賛を受けた。
また日本の皇室内でもオートピアノが採用され、その他多くの国の宮殿に設置されていた。
1920年代初頭にはコーラー&キャンベル社に買収され、1930年代初頭まで「オートピアノ」の生産を続けた。
しかし、残念ながら世界恐慌を乗り越えることができず、買い手がつかずに生産中止となってしまった。
オートピアノ社はプレーヤーピアノの製造に特化していたため、その道の専門家であり、
優れた製品を作ることに専念していました。
オートピアノは、卓越した表現力と美しい外観を備えています。
熟練した職人による豊かなケースデザインは、世界の厳しい気候だけでなく、
過酷な使用にも耐えることができた。
また、モデルによって価格が大き抑えられたものもあり、多くの家庭で購入することができました。
その中でも特に人気があったのが、88音の楽譜を演奏する「ウェルテ・ミニョン」と呼ばれるモデルでした。
この楽器は、アーティストの音色を模倣したものとして珍重された。
一音一音が完璧なタイミングで演奏され、テンポの変化もすべて考慮されている。
世界的に有名なピアニストや作曲家が、このウェルテ・ミニョンのために曲を録音している。 |
AYAKA

画像クリックでHPへ戻る |
AYAKA アヤカ
アトラスピアノ製造株式会社 |
AZUMA
※こちらは参考画像です

画像クリックでHPへ戻る |
AZUMA アズマ
東洋ピアノ製造株式会社
<ご注意>
左記トレードマーク画像は近年のアポロピアノのもので、AZUMAのトレードマークではありません。
実際のアズマのトレードマークは、上部にある文字の「TOYO」の箇所が、「AZUMA」になっています。
これは参考のために載せています。実際に画像をお持ちの方のご寄稿をお待ちしております。 |
上記Aから始まるブランドの中で、追記出来そうな事項や新情報を発見した場合、修正受付フォーム よりお気軽にお知らせ下さい。
どんな些細な情報でも構いませんので、広く皆様からのフィードバックをお待ちしております。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
 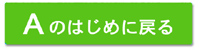 



ピアノ銘柄ブランド
トレードマーク 紹介
& 知名度ランキング

|

メーカー/ブランド説明・会社沿革・歴史・製作者・特徴・音色・他
|
B. SQUIRE & SONS
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
スクワイアー イギリス 詳細不明
|
| B. SHONINGER |
→SHONINGERの項目へ |
| B. STEINER |
詳細不明 |
| BABCOCK, ALPHEUS |
詳細不明 |
| BABCOCK, LEWIS & ALPHEUS |
詳細不明 |
| BABCOCK, APPLETON & BABCOCK |
詳細不明 |
| BACH |
詳細不明 |
BACHENDORFF
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
シンハイ(星海)のブランド 中国 詳細不明 |
| BACHMAN |
詳細不明 |
| BACHSTEIN |
ご注意→→ ドイツのあの有名なピアノ、「ベヒシュタイン」の正しいスペルはBECHSTEINです |
BACHSTEIN


画像クリックでHPへ戻る
|
BACHSTEIN バッハシュタイン/バハシュタイン
発売元:ワタナベ楽器店/ワタナベピアノ
製造元:渡辺ピアノ
新橋の楽器商だった渡辺寅雄氏が製作させたピアノで、念入りに作られた数少ないものとのこと。
初め”ワタナベピアノ”と称したそうです。
トレードマークの下部分には「WATANABE PIANOSTORE」と入っているのが分かります →★
トレードマークご寄稿者様によりますと、ご祖母様が戦後、当時の銀座渡邊ピアノで製作してもらったピアノで、
同じ時期に3台製作したうちの1台だったとのことです。
外装はマホガニーで、白鍵は象牙、黒鍵はエボナイトらしいとのことです。
渡辺氏は三田の竹内楽器店の支配人でスタインウェイなどのピアノを輸入したこともある。
<参考:エボナイトとは>
エボナイト(英語:ebonite)とは、ゴムの一形態です。
特徴としては硬く光沢をもち、外観が黒檀(ebony)に似ていることからエボナイトと呼ばれます。
エボナイトは、大変歴史の古い樹脂で、一般に広まった最初の「合成樹脂」と言われています。
1839年、米国チャールズ・グッドイヤー氏によって発明されました。
ちなみにあの有名なタイヤメーカーのグッドイヤー社は彼にちなんで命名されていますが、
グッドイヤー本人や一族と、法的・資本的な関係はないとされております。
ピアノの外観写真もご寄稿頂きました →★(家具調でとても素敵なデザインですね)
※BACHSTEINと同じスペルで青木楽器店からのピアノもありますが別のピアノのようです。
渡辺ピアノのBACHSTEINと青木ピアノのBACHSTEINを混同して解説する資料もちらほら散見され、
現在までの調査の所、真偽の程は定かではありません。
いづれにしましてもこのどちらのピアノも昭和20年代頃、日本国内でも素晴らしいと認知され始めた
あのドイツ製の名高きベヒシュタインの名称をわざと1文字変えて名乗ったピアノであることは確かです。
ちなみにドイツのあの有名なピアノ「ベヒシュタイン」の正しいスペルは”BECHSTEIN”です。
※こちらのピアノは”BACH”の部分のスペルが”E”ではなく”A”になっています。
<トレードマーク画像とピアノ外観の写真について>
このたび「匿名希望様」からワタナベ楽器店のバッハシュタインのトレードマーク画像と外観写真の
計3枚の写真をご寄稿頂きました。この度は画像のご寄稿誠にありがとうございます! |
BACHSTEIN
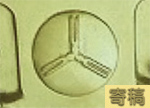
画像クリックでHPへ戻る |
BACHSTEIN バッハスタイン
発売元:青木楽器店(神戸市)
記録によるとこちらのBACHSTEINは、昭和12年に大阪市にあった清水谷女学校内で開かれた
「国産ピアノ展覧会」に青木楽器店から出品。当時の価格は380円という破格値だった。
※BACHSTEINと同じスペルで渡辺楽器店からのピアノもありますが別のピアノのようです。
渡辺ピアノのBACHSTEINと青木ピアノのBACHSTEINを混同して解説する資料もちらほら散見され、
現在までの調査の所、真偽の程は定かではありません。
いづれにしましてもこのどちらのピアノも昭和20年代頃、日本国内でも素晴らしいと認知され始めた
あのドイツ製の名高きベヒシュタインの名称をわざと1文字変えて名乗ったピアノであることは確かです。
ちなみにドイツのあの有名なピアノ「ベヒシュタイン」の正しいスペルは”BECHSTEIN”です。
※こちらのピアノは”BACH”の部分のスペルが”E”ではなく”A”になっています。
<トレードマーク画像について>
こちらのトレードマークが、青木楽器店のBACHSTEINの可能性が高いです。
「匿名希望様」よりBACHSTEINのトレードマーク画像のご寄稿を頂きました。ありがとうございます!
音叉が3本デザインされたトレードマークです。 |
BACKHAUSE
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
バックハウス 昭和32年頃に(有)小野ピアノ製作所で作られていたという記録がある。
|
BACON, FRANCIS
(FRANCIS BACON)

画像クリックでHPへ戻る |
FRANCIS BACON PIANO CO. 創業1789年 アメリカ(ニューヨーク)
フランシス・ベーコン・ピアノ・カンパニーの歴史は、1789年にさかのぼります。
ジョン・ジェイコブ・アスターが会社を設立し、その30年後にはロバート・ストダートと
ウィリアム・デュボアを迎え入れました。
1841年から1871年まで「Raven & Bacon」という社名を冠していた
フランシス・ベーコンやトーマス・レイヴンなど、最初の40年ほどはさまざまな人物が
入社・退社を繰り返していた。
その後、ベーコン家の数世代にわたる存続を経て、1904年にベーコン・ピアノ・カンパニーとして法人化された。
ベーコン・ピアノ・カンパニーは、1900年代初頭からコーラー社やキャンベル社との取引を開始し、
1933年にはコーラー社やキャンベル社の大企業に完全に統合されたため、ベーコン・ピアノの中には
コーラー社やキャンベル社のシリアルナンバーが付いているものもある。
フランシス・ベーコン・ピアノは、ニューヨークに本社を置くピアノメーカーで、アップライトピアノ、
グランドピアノ、プレーヤーピアノ、電気式表現ピアノ、リプロダクションピアノなど、
さまざまなタイプのピアノを製造・販売していた。
ベーコンピアノは何十年にもわたって製造されてきた実績があり、創業当初からその優秀さが望まれていました。
1876年のフィラデルフィア万国博覧会をはじめ、1800年代後半から1900年代前半にかけて、
このブランドのピアノはいくつものメダルや賞を受賞しました。
ベーコン・ピアノは、中程度の価格で知られていた。 |
| BAER, C. |
詳細不明 |
| BAILEY |
詳細不明 |
| BALDORR & SONS |
詳細不明 |
| BALDUR |
バルドール ドイツ 詳細不明
|
|
BALDWIN



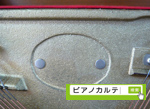


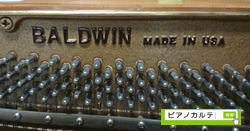
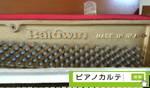
画像クリックでHPへ戻る
|
ボールドウィン
BALDWIN PIANO & ORGAN CO.
Since1862、アメリカ製ピアノでそのほとんどがスピネットタイプ。
木目を生かした外装が特徴的ですね。
あがき(→鍵盤の沈み込む深さ)がとても浅いのでご注意。
通常のピアノのあがきは10mmですが、このピアノは8~9mm程度しかありません。
日本製ピアノを使い慣れた方はタッチにかなり違和感を感じると思います。
総合的なピアノの作りは、THEアメリカ!という感じです。
その他の特徴としましては、3本ペダルのうち、真ん中のペダルが低音域のみ利きます。
アメリカのピアノにこの方式が多く、ウーリッツァーなどの3本ペダル機種もこの方式を採用しています。
(一般的な3本ペダルの真ん中は弱音ペダル、マフラーペダルです)
その他の特徴としては、チューニングピンへ巻かれるミュージックワイヤーが、
わざと最初に飛び出ささせてから巻き始めており、ボールドウィン独特な特徴です
→★
ボールドウィンのグランドピアノには、特許を取得したAcu-Justヒッチピンが取り付けられている。
これにより弦圧調整を1本づつ個別に行うことが出来る。
また、ボールドウィンのコンサートグランドピアノには、トレブル・ターミネーションという部品の特許を取得し、
この部品によりピアノの高音部の音が明瞭で力強くなり長く持続するという特徴がある。
<歴史>
1873年、アメリカ中東部の著名な音楽教師ドワイト・ハミルトン・ボールドウィンは、
ピアノとオルガンを扱う小売店ボールドウィン・ピアノ・カンパニーを設立。
19世紀の終わり頃に会社が発展してくると、ボールドウィンはオハイオ・ヴァレー・ピアノ・カンパニーと
契約を交わし、D.H.ボールドウィン・アンド・カンパニーのアップライトと、スクエアピアノの製造を委託。
1891年、ボールドウィン・ピアノは低価格のアップライトピアノの製造を開始し、
2年後には中価格のアップライトをエリントン・ピアノ・カンパニーの名で製造するようになる。
19世紀末にはボールドウィンの名で高品質の楽器を製造するようになり、
1900年のパリ万博でグランプリを獲得する。
D.H.ボールドウィンは1899年没。会社を長老教会に遺すが、ボールドウィンの元社員の
ルシエン・ワルシンと、ジョージ・アームストロングは1903年に会社の経営権を買い戻した。
1926年にルシエン・ワルシンJr.が最高経営責任者となり、1964年に亡くなるまで会社に留まった。
1920年代、ボールドウィン社は自動演奏ピアノ、マニュアロ(Manualo)プレーヤー機構の開発で有名になり、
また、シンシナティ大学物理学部の協力の下、電子楽器の実験も行った。
ボールドウィン社が財政的に安定したのは、90cmのアクロソニック・スピネットや、
100cmのアクロソニック・コンソールを生産するようになった1936年からでした。
これらの楽器は1938年から販売された112cmのハミルトン・スタジオ・アップライトの設計、
製作へと繋がった。これは最も人気の高いアップライトピアノのひとつで、
現在目にするボールドウィンピアノの原型とも言えるでしょう。
第二次世界大戦中、ボールドウィン社は飛行機の木製部品を製作などをしていたが、
戦後はエレクトリック・オルガンで成功し、飛躍的な成長を遂げた。
1960年代から1970年代にかけてボールドウィン・ピアノ・カンパニーは金融や電子分野を含む
42社を買収し、ボールドウィン・ユナイテッドとなる。
1963年にはドイツのメーカーであるベヒシュタインを買収。
1987年まで続いたこのベヒシュタインとの関係から、ボールドウィン社は国際的な
コンサート・アーティストへのピアノ提供サービスの仕事を得たという。
1965年、ボールドウィン社は初のコンサートグランドピアノSD-10を製造。
ボールドウィン社の好調さは1983年まで続いたが、この年に金利の上昇に伴い破産を申し立て。
利益性の高いピアノ部門は役員によって買われ、1984年にボールドウィン社はふたたび私有会社に。
1980年代から1990年代初めにかけて、ボールドウィン社はサミック社と提携し、
コリアン・アメリカン・ミュージック・カンパニーを設立し、ハワード・グランドピアノを生産した。
1980年代後半になると、ふたたびボールドウィン社は規模を拡大し、
アメリカのピアノ・オルガン製造会社であるワーリッツァーなど、ピアノ関連会社を買収していった。
その後、また経営に行き詰まり、ふたたび破産を申し立てると、およそ1ヶ月後の2001年11月1日に
ボールドウィン・ピアノ・アンド・オルガン・カンパニーは、ギブソン・ギター・コーポレーションに買収される。
機種バリエーション 140、4024、4026、5040、5045など ボールドウィンのシリアルナンバープレート →★
ボールドウィン天板裏側に貼ってあるシール →★ ボールドウィンならではの美しい家具調外装
→★
ボールドウィンの保証書 →★ ボールドウィンピアノのドロップアクション
→★
ボールドウィン(Baldwin)ピアノの製造番号/製造年代 対照表(1890年~2000年) →★
<以下、ウィキペディアより引用抜粋>
ボールドウィン・ピアノ・カンパニー(Baldwin Piano Company)は、
アメリカ合衆国のピアノブランドである。
かつては米国を拠点とする最大の鍵盤楽器製造業者であり、
「America's Favorite Piano(アメリカのお気に入りのピアノ)」というスローガンで知られていた。
2008年12月にほとんどの国内生産を停止し、中国へ生産を移した。
ボールドウィンは現在アメリカ最大の楽器製造業者ギブソン・ギター・コーポレーションの子会社である。
ボールドウィン社の歴史は、ドワイト・ハミルトン・ボールドウィンがオハイオ州シンシナティで
ピアノやオルガン、バイオリンを教え始めた1857年に遡る。
1862年、ボールドウィンはデッカー・ブラザーズピアノの販売特約店を始め、
1866年に販売員としてLucien Wulsinを雇った。
Wulsinは販売特約店の共同経営者となり、会社は1873年にD.H. Baldwin & Companyと
呼ばれるようになり、彼の指導の下でボールドウィン・カンパニーは1890年代までに
アメリカ合衆国中西部で最大のピアノ販売業者となった。
1889年から1890年に、ボールドウィンは「製造し得る限り最良のピアノ」を製造すると宣言し、
続いてリード・オルガンを製造するHamilton Organとピアノを製造する
ボールドウィン・ピアノ・カンパニーの2つの会社を設立した。
会社の初のピアノ(アップライトピアノ)は1891年に販売が始まった。
1895年には初のグランドピアノを発表した。
ボールドウィンは1899年に死去し、彼の資産の大部分は伝道目的に資金を供給するために残された。
Wulsinは最終的にボールドウィンの資産は購入し、会社の体制の小売から製造への転換を続けた。
会社は1900年にパリ万国博覧会に出品したモデル112でグランプリを受賞し、
こういった賞を受賞した初のアメリカ製ピアノとなった。
ボールドウィン製ピアノはセントルイス万国博覧会と1914年英米博覧会でも最高賞を受賞した。
1913年までに、事業は活発となり、ボールドウィンは米国全土の小売店を持っていたのに加えて、
32カ国へと輸出した。
ボールドウィンは、その他多くの製造業者と同様に、1920年代に自動ピアノの製造を始めた。
ピアノ工場はオハイオ州シンシナティに建設された。このモデルは1920年代末までに不人気となり、
世界大恐慌の始まりと相まって、これはボールドウィンへ災いを及ぼした。
しかしながら、社長Lucien Wulsin IIはこういった状況のために大きな積立金を作っており、
ボールドウィンは市況の低迷を乗り切ることができた。
第二次世界大戦中、米国戦時生産委員会は戦争遂行努力のために工場を使うことができるように
米国の全ての製造業の停止を命令した。ボールドウィンの工場はエアロンカPT-23初等練習機や
カーチス・ライトC-76キャラバン輸送機といった様々な航空機のための合板製部品の製造のために使われた。
軍用機における木製部品の使用は大成功とは決して考えることはできなかったが、
合板製の航空機の翼を建造するうえで学んだ教訓は結局のところは戦後のピアノモデルで使われた
21層カエデ材ピン板の設計の開発に役立った。
戦争が終わった後、ボールドウィンはピアノの販売を再開し、1953年までに戦前の2倍の生産数に達した。
1946年、ボールドウィンは初めての電気ピアノ(開発は1941年)を発売した。
電気ピアノは大きな成功を収めたため、ボールドウィンは
ボールドウィン・ピアノ&オルガン・カンパニーに改称した。
1961年、ルシアン・ウルシン3世が社長となった。
1963年までに、ボールドウィン社はC. ベヒシュタイン・ピアノフォルテファブリックを買収し、
1986年まで所有した。1959年、ボールドウィンはアーカンソー州コンウェイに最初は
アップライトピアノの製造のために新たなピアノ製造工場を建設した。
この工場では1973年までに100万台のアップライトピアノが作られた。
1961ににボールドウィンはミシシッピ州グリーンウッドに新しいピアノ工場を建設した。
それ以降にアップライトピアノの生産はオハイオ州シンシナティからグリーンウッドへ移された。
ボールドウィン社は次にポップ・ミュージックの成長から利益を得ようと試みた。
フェンダー・ミュージカル・インストゥルメンツ・コーポレーションの買収が失敗に終わった後、
ボールドウィンは1965年に38万米ドルでロンドンのバーンズを買収し、
社のピアノ小売店を通じてギターの販売を始めた。
この時期、ボールドウィンのエンジニアRobert C. Schererがナイロン弦ギターのための
Prismatoneピックアップを開発した。ギターの販売に不慣れであったボールドウィンの小売店は
多くのギター購買者の興味を引くことに失敗し、売り上げは期待外れに終わった。
1967年、ボールドウィンはグレッチギターも買収した。
グレッチは自社の経験豊かなギター販売員と公認小売店の流通網を有していた。
しかしながら、フェンダーとギブソンがギター市場の支配し続け、
売り上げは期待された水準には届かなかった。
グレッチギターの経営は1989年にグレッチ家に売り戻された。
1970年代を通して、ボールドウィン社は金融サービスへ活動分野を広げるために大きな努力を始めた。
Morley P. Thompsonの指揮の下で、ボールドウィンは数十の会社を買収し、1980年代初頭までに
MGIC投資コーポレーションを含む200社を超える貯蓄貸付機関、保険会社、投資会社を所有した。
ボールドウィン社はUnited Corp. との合併後の1977年に社名をボールドウィン-ユナイテッドに変更した。
1980年、ボールドウィン社はアーカンソー州トルーマンに新たなピアノ製造工場を開業した。
しかし、1982年までに、ピアノ事業はボールドウィンの36億米ドルの収益のわずか3パーセントになった。
その一方で、ボールドウィン社は買収と新たな施設の資金を調達するために大きな債務を負っており、
次第に貸付債務の支払が困難になっていた。
1983年、持株会社といくつかの子会社が総額90億米ドルを超える負債を抱えて破産へと追い込まれた。
これは当時市場最大の倒産だった。しかし、ピアノ事業は倒産を免れた。
1984年の倒産手続き中、ボールドウィンのピアノ事業はその経営管理者に売却された。
新会社は1986年にボールドウィン・ピアノ・アンド・オルガン・カンパニーとして公開され、
本社はオハイオ州ラブランドに移された。
しかし、人口構造の変化と外国との競争により鍵盤楽器の販売は停滞した。
ボールドウィン社は市場占有率を増やすためにウーリッツァーを買収したり、
生産コストを下げるために製造を海外に移つことで対応した。
1998年、ボールドウィン社は本社をラブランドから近隣のディアフィールド・タウンシップへ移した。
1990年代の間中ずっと、ボールドウィン社の運勢は好転し、1998年までに、
コンウェイ工場の270人の従業員は毎年2,200台のグランドピアノを作っていた。
しかしながら、2001年、ボールドウィンは再び困難に直面し、再度破産申請をした。
ボールドウィン社はギブソン・ギター・コーポレーションによって買われた。
2005年にリストラを行う際に、ボールドウィン社はトルーマン工場の一部の従業員を解雇した。
現在ギブソン・ギター・コーポレーションの子会社であるボールドウィン社はボールドウィン(Baldwin)、
チッカリング(Chickering)、ウーリッツァー(Wurlitzer)、ハミルトン(Hamilton)、ハワード(Howard)
ブランドの楽器を製造している。ボールドウィンは中国で2つのピアノ工場を購入し、
ここでグランドピアノとアップライトピアノを製造している。
過去のB米国製アップライトを再現したモデルは中国の中山市にある工場で作られている。
これらの復刻モデルにはBaldwin HamiltonスタジオモデルB243およびB247が含まれる。
これらはこれまで作られた中で最も人気のある学校ピアノである。
Donbei(東北)のより大規模な工場では現時点ではピアノは作られていない。
ボールドウィンのグランドピアノは中国の柏斯琴行(Parsons Music Group)によって作られている。
全ての新品ピアノはウーリッツァーやハミルトン、チッカリングではなく
ボールドウィンブランドの下で販売されている。
ボールドウィンは2008年12月にアーカンソー州トルーマン工場での新たなピアノの製造を止めた。
特注グランドピアノの製造と注文された多数の芸術的なグランドピアノの仕上げのために
少人数のスタッフが残っている。
ボールドウィンのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい →★ |
|
BALLINDAMM




画像クリックでHPへ戻る
|
バリンダム BALLINDAMM
末尾はMが2つです。
製造元:東洋ピアノ製造(浜松) ※アポロピアノ
現在の販売元:株式会社 ピアノ百貨
機種バリエーション:BU-10、BU-20、BU-30、BU-50、B-123、B-126、B-133等
東洋ピアノ製ということで、東洋ピアノ製造時のピアノはもちろんM.O.Tペダルを採用しています。
MOTペダルのガチャガチャ →★
バリンダムのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい →★ |
BALTHUR
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
BALTHÜR ポーランド 詳細不明 |
| BALTICA |
詳細不明 |
BALTIMORE
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ボルチモア アメリカ Baltimore Piano Factory
ボルチモア・ピアノ・ファクトリーのピアノは、メリーランド州ボルチモアの工場で生産されていたが、
会社の成長に合わせて何度かボルチモア市内に移転した。
残念ながら1800年代半ばに生産が終了したため、これらのピアノについてはほとんど知られていない。 |
| BANNERMAN |
詳細不明 |
BARBEL
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
バーベル
有限会社 野田ピアノ製作所、浜名楽器製造株式会社
その他詳細不明 |
| BARBER LONDON |
詳細不明 |
BARENBOIM
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
バレンボイム
ピアニスト兼指揮者のバレンボイムによりデザインされたピアノとのこと。
Steinway&Sonsの支援を受けて、ベルギーの楽器メーカーChris Maeneと共に製作。
最大の特徴は平行弦を採用している(※現代の一般的なピアノはほとんどが交差弦)
※参考:ダニエル・バレンボイム(Daniel Barenboim, 1942年11月15日 ブエノスアイレス - )は、
アルゼンチン出身の、ユダヤ人ピアニスト・指揮者。現在の国籍はイスラエル。 |
| BARKER |
Barker & Co 詳細不明 |
| BARNES |
詳細不明 |
BAROCK



画像クリックでHPへ戻る |
バロック BAROCK
浜松の東日本ピアノ製造KKで作っていたブランドの一つ。 →後に(株)バロックとなります
同社で製造の「クリーベル」などと同じ雰囲気のピアノです。
他に、KEMP(ケンプ)、WESTMINISTER(ウェストミンスター)がある。その他詳細不明
<付録>
バロックピアノの製造番号/製造年代 対照表(1972年~1990年) →★
バロックのまくり(蓋部分)の銘柄マーク →★ バロックのキーカバー →★ バロックの保証書 →★
<参考>
JACKSON & SONSという同じ東日本ピアノ製造のピアノもあります。同じトレードマークです。
→詳しくはJACKSON & SONS(ジャクソンアンドサンズ)の項目へ
<参考資料>
東日本ピアノ製造株式会社を含む会社遍歴は下記の通り
昭和28年 大岡楽器製作所が発足
昭和31年 白鳥楽器製作所
昭和33年 スワン楽器製造株式会社
昭和38年 ガーシュインピアノ株式会社
昭和42年 東日本ピアノ製造株式会社
昭和62年 株式会社バロック
バロックのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい →★
|
BARRAT & ROBINSON
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
バラット・アンド・ロビンソン BARRAT & ROBINSON LTD. イギリス その他詳細不明 |
BARTHOL
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
バートール ドイツ 詳細不明
|
| BARTLETT |
詳細不明 |
BARUSTEIN

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
バルシュタイン(バルスタイン)
松本ピアノ工場、東京鎌田楽器製作所(蒲田ピアノ修理所)
ピアノ調律師の宇都宮信一氏が東京月島にあった松本ピアノに依頼して製造。
琥珀のような深い味わいのある音を求めて命名したという。数は少ない。
|
| BAUER |
詳細不明 |
| BAUER, J. |
詳細不明 |
BAUMBACH
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
バウムバッハ オーストリア 詳細不明
|
BAUM DORF
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
バウムドルフ 韓国? 詳細不明
機種バリエーション:U500等 |
| BAUMEISTER |
アメリカ(ニューヨーク)
その他詳細不明 |
| BAUMGARDEN & HEINS |
詳細不明 |
BAUMGARDT
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
バウムガルト スウェーデン(都市:リンシェーピング)
<以下、ウィキペディアより引用抜粋>
バウムガルト(Baumgardt)は、スウェーデン・リンシェーピングにかつて存在したピアノ製造会社である。
1871年にJohan Otto BaumgardtとAdolf Tenggrenによって創業された。
総計約1万1千台のピアノが生産された。リンシェーピングでのピアノ生産は1968年に終了し、
その後はまずアルヴィーカのエストリンド&アルムクィストで、次にフィンランドのファッツェルで
ピアノが生産された。ファッツェルでのBaumgardtピアノの生産は1974年に終わった。 |
| BAUS |
詳細不明 |
| BAXHARD |
スペルは”BUXHARD”が正しい可能性が高いです
詳しくは→BUXHARDの項目へ |
| BAXHORD |
スペルは”BUXHARD”が正しい可能性が高いです
詳しくは→BUXHARDの項目へ |
| BAY |
詳細不明 |
BAYERN
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
バイエルン アトラスピアノ製造株式会社
機種バリエーション:U-107等 |
| BEALE |
ビール アトラスピアノ製造株式会社 |
| BEALE PATENT |
オーストラリア 詳細不明 |
| BECHNER |
詳細不明 |
BECHSTEIN
BECHSTEIN, C.

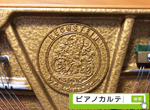






画像クリックでHPへ戻る
|
ベヒシュタイン(カール・ベヒシュタイン) C. BECHSTEIN ドイツ(ベルリン)
繊細な作りと音色で、とても素晴らしいピアノです。
1853年の創業。故カール・ベヒシュタインが1855年にベルリンでピアノ工場を開設したのが始まり。
過去に1929年の世界経済恐慌と第二次世界大戦で工場が破壊、さらに材料が損なわれ、
会社の伝統に終止符が打たれる歴史を持っています。
戦後、アメリカの大手メーカーに買収されますが、ベヒシュタインの真の復活を願うドイツ人により
1986年ベルリンに戻って復活しました。
製造工程の85%以上手作業で行っており、伝統を守りつつ進歩することを求めていきました。
ベヒシュタインはピアノのストラディバリウスと呼ばれる名器で、
ヨーロッパでも屈指の優れたピアノと言うことができます。
1826年生まれの創始者カール・ベヒシュタインは、古代ドイツ民族の一つで、
チューリンジア人の血統を引いているためか、生まれつきの詩的で音楽的才能を持っていました。
そのためか、いつのまにかピアノのメーカーとしての職を選び、22才の若さで当時ベルリンで
最も有名だったペローというピアノ工場の支配人を勤めてました。
彼はペローの工場の現場で4ヵ年間忠実に働いた後に、イギリスとフランスに放浪の旅に出かけ、
有名なパペから経験主義的なピアノ製造の秘法を学び、クリーゲルシュタインという当時の
小型ピアノのメーカーから商売上の駆け引きをおぼえてその見識を広めたといいいます。
その後、1853年にベルリンで創業し1856年に最初のグランドピアノを作り上げました。
カール・ベヒシュタインの作ったこのピアノは、その同年に当時の有名なピアニスト兼指揮者の
ハンス・フォン・ビューローの演奏会に使われ、リストのソナタを弾いたコンサートでは
一躍名声を博したと言われています。
三大ピアノメーカー(ピアノメーカー御三家)の中の1つに数えられるメーカーです。
ピアノメーカー御三家とは一般的にスタインウェイ、ベーゼンドルファー、ベヒシュタインを指します。
ベヒシュタインについてはWikipediaに詳しく書かれています
→★
ベヒシュタインの音色は澄みきった細い高音と、よく鳴る低音が特徴です。
新しいベヒシュタインのアクションはすべてレンナー社製で、響板にはバイエン地方の堅いスプルース材が
用いられ、ピン板はデリグニット社製で、最近まで総アグラフが採用されていた。
ベヒシュタインのコンサートグランドは、ベーゼンドルファー同様、総一本張り張弦のため、調律の安定性が良く、
また弦が切れた際には対処がしやすいという利点がある。
20世紀になるころに生産されたアップライトピアノには、より速いレペティション(連打)を実現するために、
ジャックに追加のスプリングが取り付けられ、ハンマーバットに接続されていた。
ベヒシュタインアップライト鍵盤押さえ部分の銘柄マーク
→★ アクションレールに貼られたシール
→★
ベヒシュタインのオリジナルキーカバー →★
製造から100年以上経つベヒシュタイングランドのデカール →★ そのグランドピアノの優美な外観 →★
ベヒシュタインアップライトのマフラー機構は、シンプルかつ理にかなった構造で本当に良く出来ており、
日本メーカーのようにビスを外す手間もなく、バネの勢いで引っかかることもなく大変優れたものです →★
上から4枚目のエンブレム画像は「PIANO YOSHIKAWA様」よりご寄稿頂きました。ありがとうございます!
上から5枚目のエンブレム画像は「I様」よりご寄稿頂きました。ありがとうございます!
上から6枚目と7枚目の写真は約100年以上前に製造のベヒシュタインです。
トレードマークは100年前からまったく変わっていませんね!ドイツの物作りの凄さを感じたピアノでした。
<100年以上前のベヒシュタインピアノ画像集>
まくり(ピアノ鍵盤蓋)にあるブランド銘柄マーク →★ ベヒシュタイントレードマークの拡大画像 →★
特徴的な白鍵(角が丸いめずらしい形状です)→★ 低音の1本弦に付けられた補助ダンパー →★
ピアノ内部に折り畳み式で収納が出来る譜面台 →★ ベヒシュタインピアノの内部全体写真 →★
■機種/モデル バリエーション (後に記載したモデルほど高級機) ※1989年当時の機種バリエーションです
アップライト
S-115(高さ115cm)、S-12n(高さ212cm)、S-12a(高さ212cm)、
S-11a(高さ230cm)、S-8a(高さ250cm)
グランドピアノ
K(奥行158cm/アクリル鍵盤)、K(奥行158cm/象牙鍵盤)、M(奥行180cm/象牙鍵盤)
B(奥行203cm/象牙鍵盤)、C(奥行221cm/象牙鍵盤)、EN(奥行280cm/象牙鍵盤)
<付録>
ベヒシュタイン(C, Bachstein)ピアノの製造番号/製造年代 対照表(1860年~2001年) →★
<以下、ウィキペディアより引用抜粋>
C. ベヒシュタイン・ピアノフォルテファブリック(C. Bechstein Pianofortefabrik)AG、
通称ベヒシュタイン(Bechstein)は、カール・ベヒシュタインによって
1853年に創業されたドイツのピアノ製造会社である。
1853年、カール・ベヒシュタインによってベルリンで創業。
「ピアノのストラディバリウス」と呼ばれるほどの名器で、最高のピアノの代名詞である。
ベヒシュタインについてフランツ・リストは「28年間貴社のピアノを弾き続けてきたが、
ベヒシュタインはいつでも最高の楽器だった」、クロード・ドビュッシーは
「ピアノ音楽はベヒシュタインのためだけに書かれるべきだ」と言う言葉を残している。
また、セシル・テイラー、チック・コリアなどジャズピアニストにも度々使用され、
クラシック界に留まらず、その演奏性は高く評価されている。
しかし、創業からの長い年月の中で、度重なる苦難の歴史もあった。
1929年、世界恐慌で打撃を受け、さらに第二次世界大戦で工場が破壊されるなどしたため、
設計図やその他の重要な資料はもとより、熟練した職人などそのほとんどを喪失した。
また、第二次大戦中ナチス・ドイツに協力したとして(ヒトラーはベヒシュタインを
「第三帝国のピアノ」としていた)、戦後はドイツ人のナチズムからの脱却とともに
その栄光の座から退いていくこととなった。
1962年、アメリカのボールドウィン社の傘下に入ったものの、
1986年にドイツのピアノ製造マイスターであるカール・シュルツェが経営権を買い取り、
念願であったドイツ人の手に経営権が戻された。
その後は資本増強を積極的に行い、1997年には株式会社(C. Bechstein AG)となり、
資本増強と東西ドイツ統一と共に、ツィンマーマン(またはツィンメルマン、Zimmermann、
1884年ライプツィヒで創業)とホフマン(W. Hoffmann、1904年ベルリンで創業)の
ブランドを傘下に収め、ベヒシュタイングループを設立。現在に至っている。
公式HP:https://www.bechstein.com/
公式HP(日本法人):https://www.bechstein.co.jp/
ベヒシュタインのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい →★ |
| BECHTEL |
詳細不明 |
BECKER
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ベッカー ロシア(ソ連) 1841年創業 ソ連で最も歴史のあるメーカー その他詳細不明
|
| BECKER, J. |
詳細不明 |
BECKER BROS.
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
Becker Brothers Pianos
ベッカー・ブラザーズ 創業1892年 アメリカ(ニューヨーク)
1892年、ジェイコブ・ベッカーは、ニューヨークに工場を持つベッカー・ブラザーズを設立した。
ベッカー・ブラザーズは、自社ブランドのピアノのほか、ベニントン(Bennington)、メロトーン(Mellotone)、
プレイアノーラ(Playernola)などのブランドを保有していた。
1928年、ジェイコブの一人息子であるルドルフが父の後を継いで会社を経営した。
ルドルフ・ベッカーは、第二次世界大戦が始まる頃にベッカー・ブラザーズが閉鎖されるまで経営を続けた。
ベッカー・ブラザーズのピアノは、生産のピーク時には高い需要がありましたが、
大量生産されることはありませんでした。ベッカー・ブラザーズのピアノは需要が高いにもかかわらず、
大量生産されることはなく、同社の厳しい基準に合わせて1台1台丁寧に作られていた。
ベッカーの名を冠したピアノには、アップライトピアノ、グランドピアノ、そしてプレーヤーピアノがあり、
耐久性と優れた音色が特徴である。ベッカーのピアノは、シンプルな構造で操作しやすく、
外観は精巧にデザインされた美しいものが多い。 |
| BECKNER |
ベックナー 東洋ピアノ株式会社
機種バリエーション:A500等 |
| BECKER |
キンボール社(KIMBALL)が取り扱ったブランド
→詳しくはKimballの項目へ |
| BECKSTEIN |
ベクシュタイン ドイツでベヒシュタインの名が有名になってきた際、いかがわしい商売も生まれ、
ベヒシュタイン(Bechstein)のスペル一文字をわざと変えたインチキ商品といわれている。 |
BECKWITH

画像クリックでHPへ戻る |
ベックウィズ/ベックウィズ・シカゴ BECKWITH CHICAGO
ベックウィズ・ピアノ&オルガン社は、19世紀末にシカゴのシアーズ・ローバック社によって設立。
ベックウィズ社の楽器は、全米の通信販売カタログや大型店舗で広く販売された。
シアーズ・ローバック社の製品が今日のように有名になったのは、高い品質と優れたマーケティング、
そして販売カタログの普及があったからである。
シアーズ・ローバック社は長年にわたり、ベックウィズ、シアーズ・ローバック社、アメリカン・ホーム、
メイウッド・ピアノ・カンパニー、ビバリー・ピアノ・カンパニー、
コールドウェル・ピアノ・カンパニーなどの名称でピアノやオルガンを製造・販売していた。
ベックウィズのピアノは、シアーズブランドの中でも最も人気があり、何千台も販売された。
シアーズは通販カタログでピアノを販売していたので、通常は列車や馬車で国の最果ての地にピアノを送っていた。
暑い、寒い、湿っている、乾いているなどの過酷な気候の中で、メーカーはピアノの耐久性を保証。
ベックウィズ社は25年間の保証をしていたので、非常に丈夫でよくできたピアノでなければなりませんでした。
画像は「ローウェル様」からご寄稿頂きました。ありがとうございます!
BECKWITHの鉄骨部分には、「ALL WORKMANSHIP GUARANTEED」や、
「WORKMANSHIP GUARANTEED BECKWITH CHICAGO」と入っているピアノなどがあります。
手作りピアノを前面にアピールしています。 |
BEHNING & SONS
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
Behning & Sons ベーニング・アンド・サン
アメリカ(ニューヨーク) 創業1861年
1861年、ヘンリー・ベーニングが設立した「ベーニング・アンド・サン・ピアノ・カンパニー」は、
「ベーニング・ピアノ・カンパニー」と呼ばれていた。
1861年、ヘンリー・ベーニングがニューヨークに事務所と工場を設立したことにより、会社は繁栄し、
ヘンリー・ベーニングの楽器は非常に高い需要があった。
1864年から1878年にかけて、ヘンリー・ベーニングはAlbrecht Klinxと、Justus Diehlという
2人のビジネスパートナーを得た。その後、ヘンリーは息子のヘンリーを会社に加え、
社名を「Behning and Son」とした。会社が発展するに伴い、会社は移転し、
ヘンリー・ベーニングSr. はもう一人の息子、Gustaveを迎え入れた。
こちらが本家のベーニングです。
下記、朝日ピアノが販売するベーニングは中国が商標権を得て作り始めた別のピアノです。 |
|
BEHNING


画像クリックでHPへ戻る
|
ベーニング 株式会社アサヒピアノ/(朝日ピアノ)
静岡県浜松市豊町3513-2にあるアサヒピアノのブランド。
中国製造、中国人社長
<朝日ピアノHPより>
Henry Behning(ヘンリー・ベーニング)
ドイツのハノーバーで1832年に生まれヨーロッパ各地でピアノ製作技術を学び1856年に渡米。
1861年からHenry Behningピアノの製作を開始。
1880年に2代目のHenry Behning Jrをパートナーにして、社名をHenry Behning & Son社と改称。
1894年Henry Behning Piano Companyに社名変更。
日本ではWeber社との提携によりアサヒピアノが製造元となってお届けしています。
こちらのベーニングは朝日ピアノが販売する中国が商標権を得て作り始めた別のピアノです。
ベーニングのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい →★ |
| BEHNING & KLIX |
詳細不明 |
| BEHNING & SONS |
詳細不明 |
BEHR BROTHERS
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
Behr Brothers ベーア・ブラザーズ/ベア・ブラザーズ
アメリカ(ニューヨーク) 1881年創業
<歴史>
ベーア・ブラザーズ・ピアノ・カンパニーは、1881年にドイツ出身のヘンリーとエドワードの
ベーア兄弟によって設立。
ニューヨークにあった彼らの工場は非常に大きく、30年近くに渡って大量のピアノを生産していました。
その工場では、ウォルドーフ(Waldorf)のピアノも製造していた。
ベーア兄弟は、1910年にピアノメーカー大手のコーラー社とキャンベル社に買収されるまで、
この名前でピアノを生産し続けた。
ベーア・ブラザーズのピアノは、エドタール・レメニ、モーリッツ・モスコフスキ、
グザビエ・シャルヴェンカなどの業界の著名人から絶賛され、
当時の最高水準の楽器としての地位を確立しました。
ベーア社のピアノには、グランドピアノ、アップライトピアノ、そしてプレーヤーピアノがあります。
これらの楽器は、美しい音色に加えて、凝ったデザインと優れたクラフトマンシップが評価されています。 |
| BEKKER |
詳細不明 |
BELARUS


画像クリックでHPへ戻る |
BELARUS ベラルーシ ロシア(旧ソ連)製
ソ連製でよくある「RAZNO」製です。
他のあらゆるRAZNO製(チャイコフスキーやウラジミール、ベリョースカ等)のピアノを
これまで多数調律してきたことがありますが、作りは正直言ってイマイチな感じです。
あと何と言ってもこのソ連製のRAZNOピアノは、突き板(外装)の剥がれがかなり酷いです。
日本の高温多湿の気候に合わないのでしょう。
その他詳細不明
<参考>
ピアノブランドの名称がロシア(ソ連)とは別国家の名称「ベラルーシ/BELARUS」ですが、
かつてのベラルーシはソビエト連邦の構成国家の一つとして機能していました。
その後、ベラルーシ共和国はソビエト連邦の崩壊によって同連邦から独立を果たしました。
トレードマーク(下)の画像は「匿名希望様」からご寄稿頂きました。ありがとうございます! |
| BELEHREDEK |
詳細不明 |
| BELL |
ベル イギリス 詳細不明 |
BELL PIANO & ORGAN CO.

画像クリックでHPへ戻る |
カナダ(グルエフ) ※グルエフはカナダのオンタリオ州にある都市
ピアノの鉄骨部には、「BELL PIANO & ORGAN CO LIMITED GUELPH CANADA」
と書いてあります。その他詳細不明
トレードマーク画像は「匿名希望様」からご寄稿頂きました。ありがとうございます! |
| BELLAK & SONS |
詳細不明 |
| BELLMAN |
Estey Piano Corporation
→詳しくは「Estey」の項目へ |
| BELLMONT |
詳細不明 |
|
BELTON




画像クリックでHPへ戻る
|
BELTON ベルトーン
※スペルはBELTONEではない
製造元:冨士楽器製造株式会社(浜松)、ベルトーンピアノ研究所/ベルトーンピアノ製造株式会社(浜松)
発売元:内外ピアノ社(当時の住所:千代田区神田神保町1-1)
※現在の三省堂書店本社(明治14年創業)と同じ住所なので、同じビル内に内外ピアノ社があったのか?
昭和7年から浜松の天竜川筋の富士楽器製造で作られていたピアノです。
戦時中に軍需工場に転換したが昭和22年にピアノ製造を再開して、
沢山清次郎氏の指導を受け飛躍的に製品が良くなったとのこと。社長は野田満氏。
ベルトーンには愛好者が多く、アップライトの上パネルの一部に
開閉できる装置を付け(特許No481852)、また沢山清次郎氏の発明による
ペダルスプリングの強弱調整装置(特許No453845)を取り付け等の
さまざまな工夫が凝らされていました。
ペダルスプリングの強弱調整装置の写真 →★ (この写真はクリーベルピアノに付いているものです)
ペダルスプリング強弱調整装置(拡大写真) →★ (この写真はウィスタリアピアノに付いているものです)
沢山清次郎(さわやま・せいじろう)氏のイニシャルを取ってネジ部分にS.Sと入っていますね。
※ちなみにこの強弱調整装置ですが、私の実感としてさほど強弱を変えられない印象です。
ベルトーンピアノは珍しくフレームの下部にもこのようなマークが入っております →★
E.S.T.D. →established 創立・創業
1932 →1932年(昭和7年)
F.G.S. →富士楽器製造
K.K. →株式会社
ちなみに芸大教授でもあったピアニスト、レオニード・クロイツァー氏によって
ベルトーンと命名されたと言われています。
→フレーム内の 「”BELTON” NAMED BY PROF. LEONID KREUTZER」 と命名由来が書かれた部分 →★
ベルトーンの調律検査記録カード →★ ※「富士」ではなく、上に点がない「冨士」なんですね(詳細不明)
ベルトーンアクションに貼られたシール →★ ベルトーンの響板にあるデカール →★ ※
※こちらにはEstablished1937年となっています。1932年と書いてあるピアノもあれば1937年もあり。詳細不明。
このベルトーンピアノは平成24年に日本力行会りっこう幼稚園様(練馬区)へ寄贈させて頂きました →★
ベルトーンのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい →★ |
| BENEDICT BROTHERS |
詳細不明 |
| BENJAMIN |
詳細不明 |
| BENKERT |
詳細不明 |
| BENNINGTON |
詳細不明 |
| BENSTED AND SONS, H.G. |
詳細不明 |
|
BENTLEY

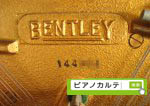

画像クリックでHPへ戻る
|
ベントレー/(ベントリー)
イギリス製(ロンドン)
1906年創業したメーカーで、1991年には生産台数16万台を超えました。
1台しか調律したことがありませんが、音量・ダイナミックにやや頼りなさを感じます。
音色は古いボールドウィンピアノ(アメリカ製)に近い感じですね。
ちなみに車メーカーで有名なあのベントレーとは関係ありません。
<歴史>
ベントレーのブランド名のピアノが初めてショールームに展示されたのは1930年だが、この人気のある
イギリスのメーカーの経営者ダグラス・グローヴァーは、ピアノメーカーの3代目だった。
そのグローヴァー・アンド・グローヴァー社は1830年頃に設立され、多いときには年間500台ほどの
楽器を生産していた。
1906年、ダグラス・グローヴァーが家業を継いだのがベントレーの始まりである。
1911年、ダグラスは思い切って店をロンドンからコッツウォルド丘陵にある使われなくなった紡績工場へ移転。
それからそこはストラウド・ピアノ・カンパニーとして知られるようになった。
ウッドチェスター・ミルの町は移転先としては完璧な立地で、絵のように美しいその場所に1605年からある
5階建ての工場には、1788年に国王ジョージ3世も訪れたことがあったという。
1920年代に生産量は増大し、1930年にダグラス・グローヴァーと息子のリチャードは、
ステューディオという新しいアップライトピアノをベントレーという新たなブランド名で売り出した。
そのピアノはすぐに人気となり、4年後には116cmのグランドピアノも生産するようになる。
ベントレー社は年間3000台のピアノを生産するまでになったが、1938年に工場が火事に遭い、
工場の大部分と機械類が焼けてしまう。それから1週間のうちにベントレー社は道を挟んだ向かい側の
小さな工場へ移った。ベントレー社はイギリスのほかのピアノメーカーなどの助けを借りて、なんとか
9ヶ月後には元々の生産レベルを取り戻した。
第二次世界大戦後、ベントレー社はアクションや鍵盤、響板、ピン板、低音部分に使われる巻線弦などを
自社で作るようになり、事実上すべての部品が自給自足可能になった。
そしてピアノを外国へ輸出して国益を支えるようになり、リチャード・グローヴァーはその貢献を称えられ、
1969年に大英帝国勲章を授与された。
ダグラスのひ孫のデイヴィッド・グローヴァーがドイツでの修行を終えて1962年に経営に加わり、
人気のあったステューディオに代わるコンパクトというピアノを1963年に新たに設計した。
このピアノも人気を博し、1980年代にベントレー社は、その多様な製品によってヨーロッパの代表的
ピアノメーカーとしての地位を確固たるものにした。
ところが、1989年にベントレー社の工場はふたたび火事に見舞われ、生産エリアの40%を失う。
その後、工場はその歴史ある場所に再建された。
1993年、ベントレー・ピアノ・カンパニーはウェルプデール・マックスウェル・アンド・コッド社に買収され、
サウスロンドンの工場へ移された。
2000年にブリティッシュ・ピアノ・マニファクチャリング社が形成され、現在、ベントレー・ピアノは、
コッツウォルド丘陵の元の工場で、オリジナルの仕様で生産されている。
ベントレーの蓋部分の銘柄マーク →★ ベントレーアクション →★
ベントレーのジャックフレンジは樹脂製です(※ジャック自体が樹脂製は良くありますがフレンジは珍しい) →★
ベントレー下パネを開けた部分のフレームに刻印されたブリティッシュメイドのマーク →★
<附録>
ベントレー・ピアノ 製造番号/製造年代 対照表(1920年~2000年) →★
ベントレーのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい →★ |
| BERDEN |
詳細不明 |
| BERDUX |
V. BERDUX ベルデュックス ドイツ(ミュンヘン)
HOF-PIANOFORTE-FABRIK
詳細不明 |
| BEREGSZASZY |
詳細不明 |
| BERGER |
詳細不明 |
| BERGMANN |
詳細不明 |
| BERNHARD STEINER |
詳細不明 |
BERLIN
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ベルリン
阿部ピアノ製作所(浜松)、ベルリンピアノ製造株式会社
その他詳細不明 |
| BERNE |
ベルネ スイス 詳細不明
|
|
BERNSTEIN



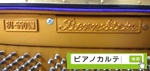
画像クリックでHPへ戻る
|
BERNSTEIN バーンスタイン
浜松ピアノ製造株式会社で製造されていたブランド(当時の住所:浜松市和田町552-3)
のちに協立楽器が販売元になりました。
有名な指揮者である「レナード・バーンスタイン」を連想させる名称を使っているものと思われます。
■機種/モデル バリエーション
TB-220、TB-660、B-127、B-131
BU230、BU350、BU380、BU550、BU850、嵯峨野など(協立楽器販売器種)
バーンスタインピアノの保証書 →★ バーンスタインのまくり(ふた部分)の銘柄マーク
→★
バーンスタイン親板内側に貼られた、ドイツ製ハンマーであるABEL(アベル)の使用を示す表示 →★
バーンスタインのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい →★ |
| BERNSTEIN WOLF |
詳細不明 |
| BEROLINA |
ベロリーナ ドイツ(ベルリン) 詳細不明 |
| BERRY |
詳細不明 |
BERYOZKA




画像クリックでHPへ戻る |
ベリョースカ BERYOZKA
ロシア(ソ連) 詳細不明
他のソ連製ピアノにもよくあるRAZNO製です(チャイコフスキーやウラジミールなど)
このメーカーの外装(突き板)はひどく剥がれてきます。
突き板が剥がれてきたピアノはこんな感じになります(ソ連製はみんなこんな感じです) →★
ベリョースカピアノのまくり部分(フタ部分)のブランド銘柄マーク →★
|
BETTING


画像クリックでHPへ戻る |
TH.BETTING ベティング/ベッティング
1887年創業 ポーランド(レグニツァ) その他詳細不明
トレードマーク画像は「匿名希望様」からご寄稿頂きました。ありがとうございます! |
| BEULHOFF |
詳細不明 |
BEYER
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
バイエル 日本 阿部ピアノ製作所 その他詳細不明
|
| BEYER-RAHNEFELD |
詳細不明 |
| BIBER |
詳細不明 |
| BIDDLE |
詳細不明 |
| BIEGER |
詳細不明 |
| BIESE, W. |
詳細不明 |
| BILLBERG |
詳細不明 |
| BIRKE, WILLY |
詳細不明 |
| BIRNBAUM |
詳細不明 |
| BISHOP |
詳細不明 |
| BJUR BROS. |
詳細不明 |
BLASIUS
BLASIUS & SONS

画像クリックでHPへ戻る |
アメリカ(フィラデルフィア) 1888年創業
フィラデルフィア・ブラシウス・アンド・サンズ・カンパニー
彫刻が施された芸術的なピアノもあり |
| BLENHEIM |
詳細不明 |
| BLONDEL, A. |
詳細不明 |
| BLONDEL, G. |
詳細不明 |
| BLUCHNER |
ブルックナー 大洋楽器工業株式会社 |
BLUEBELL

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ブルーベル
光輪楽器研究所(浜松) 昭和31年に設立された工場で、丁寧に作られたピアノであった。
昭和38年以降は記録なし。その他詳細不明。
|
| BLUEBIRD |
ブルーバード 天龍楽器製造株式会社
スペルが「BULEBIRD」としている資料もありますが詳細不明 |
| BLUEGHEL |
BRUEGHELが正しい →BRUEGHELの項目へ
|
BLUESTAR
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ブルースター 日本 詳細不明
|
BLUTHNER
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ブルツナー 広田ピアノ株式会社
1文字違いで「BRUTHNER」という大洋楽器工業株式会社のピアノもありますが別のピアノです。
※ちなみに名称が似ていますがこれも別ピアノで「PRUTHNER/プルツナー」という
そこそこ有名で広く出回っているピアノもあります。詳しくは→PRUTHNERの項目へ |
BLUE STEIN
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ブルー・スタイン BlueSteinpiano Manufacture & Co.
詳細不明 |
BLUTE/BLÜTE
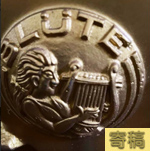
画像クリックでHPへ戻る |
BLÜTE ブリューテ 大成ピアノ製造株式会社
詳細不明
トレードマーク画像は「ハン コウキョウ様」からご寄稿頂きました。ありがとうございます! |
|
BLÜTHNER
BLUTHNER



画像クリックでHPへ戻る
|
BLUTHNER(BLÜTHNER) ブリュートナー/(ブルッツナー、ブリュットナー)
ドイツ(旧東ドイツ)旧東ドイツ国家公団(ライプツィヒ) 創業1853年。
高音部に4本目の打弦されないピアノ線を張ったアリコート弦(アリコート・スケーリング)を採用。
1872年に特許を取得。この打弦されない弦は自由に共振し、ピアノの高音域に豊かな倍音を与える。
このアリコート弦は実際に鳴らされる音の1オクターブ上に調律される。
作曲家のドビュッシーは、これを誇らしげにピアニストのモリス・デュメニルに見せていたそうだ。
初期の頃のアップライトピアノはオーバーダンパー方式(鳥かご式アクション)を採用しているものがあります。
参考:鳥かご式アクション写真 →★
品質の良い、手仕事生産のピアノで温もりのあるバランスのとれた音色のピアノで、均質な音色にするため、
ハンマーシャンクは取り付ける前に打撃音の音程を揃えるなど、多くの手間がかけられている。
木材は厳選されており、パイン材はメクレンブルク産、ビーチ材はドイツ低山地のもの、スプルース材と
メープル材、ならびにアルダー材は東アルプス産が用いられている。
総一本張りで調律の安定性が向上しており、弦が切れた際の処置がしやすいという利点がある。
ブリュートナーが特許を持つアクションは、1920年代までグランドピアノに採用されていた。
<歴史>
ドイツ・ファルケンハイン(現在のモイゼルヴィッツ)の家具職人だったユリウス・ブリュートナー
(JULIUS BLÜTHNER)は1853年にピアノ製作工場を設立した。
ブリュートナーは限られた資金で開業したものの、そのピアノは1854年にミュンヘンで開催された
産業博覧会で好評を博し、それをきっかけにライプツィヒ音楽院内のピアノを製作するように依頼される。
まもなくして、ブリュートナーピアノの品質の高さは世界中に知られるようになった。
1864年にはアップライトの生産が始まり、従業員137人の会社はライプツィヒ郊外の大きな工場へ移転。
19世紀の終わり頃には、ブリュートナー社はヨーロッパで2番目に大きなピアノ製造会社に成長し、
約5万台を生産するようになる。すべてのピアノは工場から出荷される前にブリュートナー自身によって、
チェックされていたと言われている。
1910年にユリウス・ブリュートナーが亡くなると、会社は息子のマックス・ロベルト・ブルーノが受け継ぎ、
第二次世界大戦までは着実に規模を拡大していったが、戦争中の空襲で工場は破壊されてしまった。
戦後、会社はルドルフ・ブリュートナー=ヘスラーによって再建が開始されたものの、復興には何年もかかった。
東ドイツ政府の管理の下、ブリュートナー社は一時期、ベヒシュタイン社と共同の施設を使用していた。
こうした組織上の問題はあったものの、ブリュートナーのピアノは昔と変わらず手仕事で製作されたため、
かつて賞賛された品質を損なわれることはなかった。
1935年、ドイツ海軍本部はブリュートナー社に対して、飛行船ヒンデンブルク号の中で演奏するための
軽量化されたグランドピアノの製造を依頼し、この飛行船内の演奏はラジオで放送され、ブリュートナーへの
人々の関心が一気に高まったというエピソードも残っている。
ブリュートナー社は1989年に再び民営化され、世界中の音楽愛好家に大切にされてきた
ブリュートナーは、今もライプツィヒで製造されている。
現在会社を率いるのは、ユリウス・ブリュートナーの玄孫(やしゃご/ひ孫の子)イングベルトと、
来孫(らいそん/玄孫の子)のクリスティアンとクヌートである。
※ブリュートナーピアノはBVK認証を受けています(詳しくはこちら
→★)
ブリュートナーピアノの製造番号/製造年代 対照表(1853年~2000年) →★
<以下、ウィキペディアより引用抜粋>
ユリウス・ブリュートナー・ピアノフォルテファブリック (Julius Blüthner Pianofortefabrik)GmbHは、
ドイツ・ライプツィヒにあるピアノメーカーである。
C・ベヒシュタイン、ベーゼンドルファー、スタインウェイ・アンド・サンズと共に、
たびたび世界四大ピアノメーカーの一つと言われる。
「ブリュートナーのピアノは本当に歌う事が出来、そしてそれはピアノにとって最高の褒め言葉である」と
書き残したのは、20世紀最高の指揮者ともいわれるフルトヴェングラーである。
ブリュートナーの特長の一つにアリコートシステムという独特の弦構造がある。
通常の他社製ピアノは、1音に対して、弦が3本張られているが、ブリュートナーのピアノは、
高音部にアリコート(共鳴弦)と呼ばれる4本目の弦が張られている。
この4本目の弦はハンマーで打たれることはなく、共鳴させるためだけに張られており、
この共鳴によって倍音が増幅される構造である。
この4本目の弦は、3本の弦の上部に貼られ、独立した駒を経て響板を振動させていたが、
最近のモデルでは、4本が同じ高さに一列に配置されており、豊かで純度の高い高音を実現している。
1853年、ユリウス・ブリュートナーによってドイツのライプツィヒで創業された。
そして、1872年にアリコートの特許を取っている。1867年から1905年にかけ、
パリ、ウィーン、シドニー、メルボルン、アムステルダム、ケープタウンにおいて各博覧会の
ファースト・プライズを受け、1900年のパリ、1904年のセントルイス、1910年のブラッセル、
1927年のジュネーブでグランプリを獲得するなど世界的に名声を獲得してきている。
1938年に飛行船に乗せるために、アルミ製のきわめて軽いグランドピアノが作られ話題になる。
第二次世界大戦中の1943年には、他の多くのドイツのメーカーがそうである様に、
工場が空襲で焼かれ屋根は焼け落ち楽器はもちろん材料となる木材もすべて焼き尽くされたといわれる。
その後市場にピアノを送り出すまでに回復するには1948年まで待たなければならなかった。
また東ドイツ時代には一時国営化されたが、1990年の東西ドイツ統一を期に経営権はブリュートナー家に返還。
その後順調に業績を伸ばし、2005年にはヨーロッパにおけるコンサートグランドピアノの販売台数が、
2番目に多いという記録を作るまでになっている。
イギリスのヴィクトリア女王を始め、ドイツ国内はもちろんオーストリア、デンマーク、ギリシャなどの
多くの皇室にも納品される。ブラームス、リスト、チャイコフスキー、ドビュッシー、ショスタコーヴィチ、
プロコフィエフなどの多くの有名な作曲家、ブゾーニ、アラウ、ルービンシュタイン、プレトニョフなどの
ピアニスト、そのほかヨハン・シュトラウス2世、フルトヴェングラー、メニューイン、マルケヴィッチなどの
音楽家からも高く評価されている。
なお、クロード・ドビュッシーが唯一自ら購入して愛用していたのがブリュートナーであり、
ブリュートナーを使って作曲していた。
そのほか、ビートルズの「レット・イット・ビー」でポール・マッカートニーが弾いているのは
ブリュートナーである(セッション風景を撮影した映画「レット・イット・ビー」の映像などで確認できる。
ちなみに、これはアビー・ロード・スタジオの所有である)。
フジ子・ヘミングはブリュートナーを所有しており、彼女を取り上げたNHK番組でも演奏シーンが撮影された。
中国のピアニスト牛牛もブリュートナーを使用している。
また、近年では、録音でブリュートナーを使用する世界的ピアニストが増えてきている。
なお、2007年11月までは株式会社浜松ピアノセンターが日本総代理店として販売していたが、
倒産により一時的に販売網が絶たれた。しかし2008年5月1日付けで、ブリュートナー社からの任命により
有限会社ピアノクリニックヨコヤマが日本総代理店を引き継ぎ、正規流通が復帰した。
2018年現在、6種類のサイズ(154–280 cm)のグランドピアノと5種類のサイズ(116–145 cm)の
アップライトピアノを製造している。ブリュートナーブランド以外にもBlüthner-Haesslerアップライト、
Haessler(ヘスラー)グランドおよびアップライト、そして2つのIrmler(イルムラー)製品ラインを
ドイツ工場で作っている。
ブリュートナー公式HP:http://www.bluethnerworld.com/ |
| BLÜTHNER-HAESSLER |
上記BLÜTHNERの項目を参照 |
| BOARDMAN, GRAY & CO. |
詳細不明 |
| BOCAGE |
詳細不明 |
| BOCK & HINRICHSEN |
詳細不明 |
|
BOCKLER


画像クリックでHPへ戻る
|
ベックラー BÖCKLER(BOCKLER)
販売:アポロ販売株式会社(東洋ピアノ製造株式会社)
ドイツ人が設計と謳っている韓国三益製です。
当時、販売は東洋ピアノ製造株式会社(アポロピアノ)が取り扱っていたようです。
機種:AH-28等
※東洋ピアノが扱っているCHARIS(チャリス)というピアノのトレードマークと同じなのが分かります。
ベックラーのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい →★ |
| BOG & VOIGT |
ドイツ 詳細不明
|
| BOGART |
詳細不明 |
| BOGS & VOIGT |
詳細不明 |
BOHEMIA
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ボヘミア 中国(チェコとの広告あり) 詳細不明
|
| BÖHME & SOHN |
詳細不明 |
| BOISSELOT & FILS |
詳細不明 |
BOLAND
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ボーランド 香港(中華人民共和国特別行政区)
販売会社名:香港博兰德钢琴有限公司 その他詳細不明
ホームページ:http://www.bolandpiano.com/
ホームページに掲載してあったブランド紹介文の翻訳
↓
19世紀半ばにドイツで設立された "Boland"ブランドのピアノは優雅なサウンドと高度な職人技、
そして優れたパフォーマンスで有名で世界のトップ10の有名ピアノブランドの一つです。
German Boland Pianoは、西ドイツで最も有名なピアノの製造会社で、 "German Piano City"として知られる
Brunswickにあり、100年以上前から、最高品質のピアノを製造してきました。
香港Boland Pianoは、北米市場以外の東南アジアで最も早いBOLANDピアノのライセンサーであり、
世界の金融センターにある香港には、会社の将来の発展に対する強力な保証とサポートを提供するのに
十分な人的資源と情報ネットワークがあります。市場は依然として伝統的なバイオリン製造技術を遵守しており、
各ピアノはドイツの技術者によって厳密にテストされ、すべての製品が優れた性能を発揮することを確認。
厳密にドイツのピアノ業界標準の生産、音、音質、感触、技術的な指標や生産プロセスのすべての種類では、
スタイルは純粋なドイツの降下、ヨーロッパのモデルです。 |
BOLERO


画像クリックでHPへ戻る |
BOLERO ボレロ 東海楽器製造(株)
東海楽器ピアノのトレードマークは左記画像のように2種類あります。
ちなみに東海楽器製造の”HUTTNER”などと同じです。
<東海楽器が製造したブランドを列挙いたします>
■ TOKAI(トーカイ)
■ BOLERO(ボレロ)
■ SILBER STEIN(シルバースタイン)
■ HUTTNER(ヒュッツナー)
■ GOLD STAR(ゴールドスター)
※東海楽器についての詳しい解説は、TOKAI(トーカイ)の項目を参照 |
BONNARD

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ボナール BONNARD
※ブランド名の綴りが「BONARE」となっている別資料もあり(要確認)
製作:大友楽器研究所(大友ピアノ研究所)
販売:アメリカヤ楽器店
大友雅雄氏が製作(協力:松永栄二氏)
別資料では、日米商会(発売元)、大友ピアノ工房(製作)という情報もあり |
| BÖRS, OTTO |
詳細不明 |
| BORD, A. |
詳細不明 |
| BORGATO, LUIGI |
詳細不明 |
|
BOSENDORFER



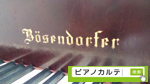
画像クリックでHPへ戻る
|
ベーゼンドルファー BÖSENDORFER (BOSENDORFER)
オーストリア 創業1828年(1827年) ジャスパーコーポレーション
※2008年にヤマハの傘下企業に。
1827年から、ベーゼンドルファーのピアノは世界中の偉大な作曲家や演奏家によって弾かれ、
賞賛され続けている。世界でもっとも製作に時間をかけるピアノメーカーとして、
ほかのメーカーとの違いを強調するべーゼンドルファー社は、グランドピアノを完成させるのに
4年もの時間をかけるが、その期間の半分は木材のシーズニングに費やされているという。
中音~高音のミュージックワイヤーがすべて1本張り(ループ弦)を採用しているのが特徴。
また、フラッグシップモデルの290インペリアルでは鍵盤の数が97鍵もあります。
通常のピアノは音域A0~C8(7オクターヴと3度)ですが、インペリアルでは
音域C0~C8で完全な8オクターヴもあります。
この黒く塗られた部分をエクステンドキー(エクストラベース)といいます。→★
これらのエクステンドベースが弾かれることは滅多にないが、
響板と駒が拡張されることで、通常の低音域の音に力強さと共鳴が加わる。
ピアニストの混乱を防ぐため、演奏中、このエクステンドキーは蓋で覆われている。
グランドのリム(側板)には堅いスプルース材が用いられており、響板の延長として機能し、
このリムとスケールデザインによって、甘く優しい高音と、基本周波数が強く鳴る低音が実現。
<歴史>
イグナーツ・ベーゼンドルファーは1794年にウィーンで生まれる。
当時ウィーンはヨーロッパ最大の文化都市であり、多くの演奏家や作曲家の本拠地だった。
ベーゼンドルファーは、名高いオルガンとピアノ製作者だったヨーゼフ・ブロッドマン(ブロートマン)
のもとで見習い修業を積んだあと、1827年に会社を設立、1828年にピアノを作り始める。
(ちなみにブロートマンはウェーバーが愛用していたピアノの製作者である)
その2年後(1830年)オーストリア皇帝から「宮廷及び会議所御用達のピアノ製造者」の称号を授けられた。
ベーゼンドルファーが作る楽器は品質が高く、造りが頑丈であったが、当時弱冠17歳だった
フランツ・リストがコンサートグランドを演奏会で弾いたことで、会社の名声は一気に高まった。
リストは単にこの楽器の音色が気に入ったのではなく、そのピアノはリストの激しい演奏スタイルにも
無傷で耐えられるほど頑丈だったのだ。こうしてベーゼンドルファ一はほぼ一夜にして、
世界のピアノメーカーのトップに上り詰めた。
1859年にイグナーツ・ベーゼンドルファーが亡くなると会社は息子のルートヴィヒに引き継がれた。
ルートヴィヒは会社をもっと大きな工場地へ移すが、成長は続いていき、1870年にはさらに広大な敷地へと
移転しなくてはならなかった。そこがウイーン第4区の現在の会社の所在地である。
ルートヴィヒには直系の子孫がおらず、1909年に引退するのを機に、会社を友人の
力ール・フッターシュトラッサ一へ売却した。
そして1931年には、その息子のヴォルフガングとアレクサンダーが受け継いだ。
1920年代の中頃まで、ベーゼンドルファー社は年間わずか数百台のピアノしか製作していなかった。
大恐慌になると生産高は急激に落ち込み、第二次世界大戦末期の数年間は、激戦で社屋が破壊されて
完全に生産が止まった。戦時中、蓄えてあった木材やピアノは薪にされてしまったという。
戦後の復興はなかなか進まず、1950年までは生産高が年間100台を超えることはなかった。
その後、1966年にキンボール・インターナショナル社の社長アーノルド・H・ハビッグが
べーゼンドルファ一社を買収する。
ベーゼンドルファー社の専門技術を活かし、キンボール社のピアノに新たな息吹を吹き込む狙いからだった。
この買収は一般的な買収と違い、両社にとって極めて有意義なものとなり、2002年1月にベーゼンドルファ一社が
キンボールとの提携を解消するまでその関係は続いた。
その後、オーストリアの銀行グループ、バーヴァック(BAWAG-P.S.K.オーストリア労働経済郵便銀行)
の支援を受け、ベーゼンドルファー社は、世界最高品質のピアノを製作する偉大なメーカーの地位を
完全に取り戻した。
ベーゼンドルファーは、ピアノメーカー御三家の中の1つに数えられるメーカーです。
ピアノ御三家とは→スタインウェイ、ベーゼンドルファー、ベヒシュタインのことを指します。
■機種/モデル バリエーション
モデル170cmグランド:鍵盤数88鍵
モデル200cmグランド:鍵盤数88鍵
セミコンサートグランド225cm:鍵盤数92鍵
フルコンサートグランド275cm:鍵盤数92鍵
フルコンサートグランド290cm:鍵盤数97鍵
1989年(平成元年4月)のプライスリストでは価格12,420,000円で当時スタインウェイよりも高価でした。
アップライトピアノ130studio:鍵盤数88鍵(高さ132cm)
ベーゼンドルファーの響板に書かれたサイン →★
<附録>
ベーゼンドルファー 製造番号/製造年代 対照表(1828年~1986年) →★
<上記データより新しい製造番号> 1990年・・・40384 2001年・・・45965
<以下、ウィキペディアより引用抜粋>
L. ベーゼンドルファー・クラヴィアファブリック(L. Bösendorfer Klavierfabrik)GmbHは、
オーストリアに所在するピアノ製造会社である。2008年からはヤマハの完全子会社。
標準的な88鍵のピアノに加えて、低音部が拡張された92鍵および97鍵のピアノを製造していることで知られる。
1828年、オーストリア・ウィーンにてイグナーツ・ベーゼンドルファーにより創業された。
以来、各国の帝室や王室の御用達として選定されたり、産業博覧会で入賞したりするなど、
名声を高めていく。第二次世界大戦後の一時期、経営難に陥って経営が
アメリカの企業体に移ったこともあったが、2002年にオーストリアの銀行グループである
オーストリア労働経済郵便銀行が経営権を取得して、名実ともにオーストリアに復帰した。
しかし2007年再び経営難に陥り、2008年にヤマハの子会社となった。
ベーゼンドルファーのピアノはフランツ・リストの激しい演奏に耐え抜いたことで
多くのピアニストや作曲家の支持を得て、数々の歴史あるピアノブランドが衰退していく中、
その人気を長らくスタインウェイと二分してきた。
ベーゼンドルファーのピアノを特に愛用したピアニストとしてはヴィルヘルム・バックハウスが有名。
ジャズ界においては、オスカー・ピーターソンが「ベーゼン弾き」としてよく知られている。
最近のピアニストではアンドラーシュ・シフ、パウル・バドゥラ=スコダ、イェルク・デームス、
フリードリヒ・グルダ、ギャリック・オールソン、ヴァレンティーナ・リシッツァも
ベーゼンドルファーのピアノを好んで用いている。
また、スヴャトスラフ・リヒテルも何枚かの録音を残している。
かつてベーゼンドルファーのピアノは1980年までショパン国際ピアノコンクールの
公式ピアノの一つであったが、のちにヤマハとカワイとファツィオリが採用されたことにより
公式ピアノから除外された。ウィーン・ベートーヴェン国際ピアノコンクールでは、
使用ピアノがベーゼンドルファーだけと決まっている。
「インペリアル」とも呼ばれる最上位機種のフルコンサートグランドピアノ「モデル290」が
ベーゼンドルファーの代表機種で、標準の88鍵の下にさらに4〜9組の弦が張られ、
最低音を通常よりも長6度低いハ音とした完全8オクターブ、
97鍵の鍵盤(エクステンドベース)を持つピアノとして有名である。
これはフェルッチョ・ブゾーニがJ.S.バッハのオルガン曲を編曲したとき、
低音部に標準のピアノでは出せない音があったため、ルードヴィッヒ・ベーゼンドルファーに
相談したことが始まりと言われている。エクステンドベースが追加されたことによって
弦の響板が広がり、共鳴する弦も増えて中低音の響きが豊かになった。
しかしそのため、しばしば一部のピアニストからは「中低音の響きは豊かだが、
高音とのバランスを考えて弾かなければならず、弾きこなすのが難しいピアノだ」と言われる。
以前は、拡張域の鍵の部分に小さな蓋を付けることで、一般の曲の演奏時に誤打を防いでいたが、
現行品では白鍵も黒くすることで区別している。音色は至福の音色と呼ばれる。
ベーゼンドルファーのピアノは1年以上の月日をかけて全工程を手作業で作られている。
代表的なモデルでは井形に組まれた強固な支柱の上にスプルース材のブロックを積み上げて
インナーリムを製作し、それに比較的薄いスプルースからなるアウターリムを張り合わせることで、
ピアノ全体がスプルース材を介して豊かな中低音を響かせる設計となっている。
現在までにベーゼンドルファーが生産したピアノは50,000台ほどで、
およそヤマハの100分の1、スタインウェイの10分の1である。
市場拡大のため、それまで経済的な理由で同社の標準モデルを導入できなかった
大学などの教育機関向けにコンサーヴァトリーシリーズ(Conservatory Series)を設計した。
生産の過程で「non-critical areas」と呼ばれる生産ラインに依存する時間を短縮することで
生産コストを削り、標準モデルより安価に提供できるシステムを構築している。
ベーゼンドルファーの創立170周年や175周年にフランツ・シューベルトや
フレデリック・ショパンなどの有名な作曲家にちなんで名付けられ、設計された特別、
限定モデルのピアノなどがある。近年の特別限定モデルとしては、
オーストリアの画家グスタフ・クリムトの代表作「KISS」を天板にあしらった
クリムトモデル、ベートーベンの月光の自筆楽譜をあしらったベートーベンモデルなどがある。
また、2013年、生産台数5万台到達を記念して1台限定生産の5万台記念モデルが造られている。
ベーゼンドルファーは100年以上前から著名な建築家やデザイナーを起用した特別モデルを制作している。
1866年にウィーン楽友協会等の設計で知られる建築家のテフォイル・ハンセン(Theophil Hansen)、
1909年にヨーゼフ・ホフマン、そのほかJosef Frank、フェルディナント・アレクサンダー・ポルシェや
アウディのデザインスタジオ等がベーゼンドルファーのピアノをデザインしている。
1990年に建築家のハンス・ホラインがデザインしたベーゼンドルファー・インペリアル・
グランドピアノは世界に2つしかない。1つはアメリカ、フロリダ州オーランドの
ウェスタン・グランド・ボヘミアン・ホテルにあり、もう1つは中国の上海にある。
1つ目のオーランドにあるピアノは1本の木の80%が使用され、それぞれの真鍮脚には
一本あたり約160万円の価値があるとされ、2つあるホライン設計のピアノには
それぞれ約3000万円の価値があるとされる。
日本国内では、過去に総代理店として日本ベーゼンドルファーが本社(静岡県磐田市)のほか
東京都中野区、大阪市淀川区の三カ所にショールームを所有していた。
本社ショールーム内に設けられているアンティークピアノのコレクションは
ベーゼンドルファーのみならずベートーヴェンの時代のジョン・ブロードウッドや
ショパンの時代のプレイエル、エラールなどの有名ブランドの他に、ピアニストの
アルフレッド・コルトーが所有していたダブルグランドピアノやジラフピアノといった
極めて珍しい形のピアノもコレクションされていた。
しかしウィーン本体側がヤマハに買収されたことにより2007年11月27日付で
日本ベーゼンドルファー(株式会社浜松ピアノセンター)は倒産し、
各地のコンサートホールの運営ならびに調律、修理などの事業は株式会社ビーテックジャパンに
引き継がれ、ベーゼンドルファーの技術メインテナンス会社として製品を維持している。
ヤマハが株式会社ベーゼンドルファー・ジャパンを発足し、東京都中野区に本社ショールーム、
静岡県浜松市にテクニカルサポートセンターを構え、東京、大阪に特約店を設置するなどした。
その後、2009年9月1日付けのベーゼンドルファー・ジャパン・グループ内のプレスリリースには、
株式会社ベーゼンドルファージャパンはヤマハ株式会社へ事業譲渡されると発表されている。
なお、2009年11月30日付のプレスリリースでは、テクニカルサポートセンターは、
静岡県掛川市に移転されたことが発表された。
2000年代初頭にオーディオ機器(スピーカー)の開発・製造をしており、日本国内では
オーディオ関連商社である株式会社ノアの手で輸入されていたが、ヤマハ傘下になり撤退した。
現在、ベーゼンドルファースピーカーの設計者が、創業者イグナーツがかつて在籍しており、
ヤマハとベーゼンドルファーの買収競争もしたオーストリアのピアノブランド、
ブロードマンに移り、Brodmann Acousticsとして販売されている。
ベーゼンドルファーのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい →★ |
|
BOSTON




画像クリックでHPへ戻る
|
ボストン BOSTON
所有:スタインウェイ・ミュージカル・プロパティーズ・インコーポレーテッド
製造:株式会社 河合楽器製作所(日本)
ボストン・ピアノ・カンパニーは1991年に、最高音質のピアノを中価格帯で生産するために、
スタインウェイ・アンド・サンズとカワイが提携して作られた会社。
当時のスタインウェイ社の中心的なオーナーたちが、日本の河合楽器製作所に作らせたピアノです。
スタインウェイ社の経験を生かし、精巧なコンピューター技術を駆使して設計と材料のテストを重ね、
このボストンピアノの開発には6年の歳月が費やされたといいます。
ハイテクを使い、量産とコストダウンを目的に作られた楽器と言えるでしょう。
ちなみにBOSTONはグランドピアノだけでなく、アップライトピアノもあります。
■機種バリエーション(グランドピアノ)
グレードの高い順に、GP-215、GP-193、GP-178、GP-163、GP-156の合計5機種
※モデル内の数字はいずれもピアノの奥行き(cm)を表します
■機種バリエーション(アップライトピアノ)
グレードの高い順に、UP-132、UP-126、UP-118の合計3機種
※モデル内の数字はいずれもピアノ高さ(cm)を表します
<特徴>
ボストンのグランドピアノは、同サイズの他社のグランドピアノよりも後部の幅が特に広く設計されている。
これを「ワイドテール設計」と呼びます。
そのため、響板の面積が広く取れるため、音がより大きく鳴るとされています。
尚、デュープレックス・スケールにより、楽器自身の音に加えて、倍音による豊かな響きが加わるとのこと。
さらに、音の減衰を抑える(音を長く保持)させるため、スケールデザインは低めの弦長力で設計されている。
2枚目のエンブレム画像は「PIANO YOSHIKAWA様」よりご寄稿頂きました。ありがとうございます!
<附録>
ボストン 製造番号/製造年代 対照表(1991年~2000年) →★
ボストンの公式ホームページはこちら →★
ボストンのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい →★ |
BOUDOIR
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ドイツ 読み方その他詳細不明
|
BOYD
BOYD LONDON |
読み方:ボイド? イギリス(ロンドン) その他詳細不明 |
| BRACKETT & ROBINSON |
詳細不明 |
| BRACKETT, J. W. |
詳細不明 |
BRADBURY

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ブラッドベリ(ブラッドベリー/ブラッドブリー) BRADBURY PIANO CO. INC. アメリカ
※当方の考察では「ブラッドブリー」より「ブラッドベリ」の方が自然な発音と考えられますので、
下記解説ではすべて「ブラッドベリ」を使って説明します。
ブラッドベリは賛美歌や歌曲を多く残した作曲家ブラッドベリによって作り出されたピアノで、
その名が付けられた。コンパクトな美しい作りと、優れた音色を持っている。
主として家庭向きのピアノでモダンな形が多く、当時シカゴに販売店があった。
ブラッドベリ社の歴史は、紆余曲折を経ている。
著名なピアニスト兼教師でもあったウィリアム・ブラッドベリは、1860年代にブラッドベリ・ピアノ・カンパニーを
設立する前は、ライト・ニュートン&ブラッドベリ・ピアノ・カンパニーに所属していた。
ブラッドベリ社は、もともと1848年にライト&ニュートン社として設立されたが、
1851年にウィリアム・ブラッドベリが同業者と組んで、ライト、ニュートン&ブラッドベリのグループを結成した。
そのわずか2年後、ニュートンがパートナーシップを離脱し、会社は解散した。
ブラッドベリのピアノは、その製造方法や材料のグレードの高さで評価されています。
彼は1950年までピアノの製造を続け、アルトリオ・アンジェラスの再生機構と
プレーヤー・アクションを自分の楽器に搭載する権利を獲得した。
1861年、ウィリアム・ブラッドベリは独立してブラッドベリ・ピアノ・カンパニーを設立した。
1865年、F.C.ライトはルイス・アーネストと提携してライト&アーネスト・ピアノ社を設立し、
1867年にブラッドベリが死去すると、F.G.スミスがこの会社を買収した。
1890年頃まで非常に優れたピアノを製造していた。
ブラッドベリのブランドは、後にマサチューセッツ州レオミンスターに工場を持つニューヨークの
W.P.ヘインズ&アンドが使用し、その後ブラッドベリのブランドは20世紀後半までウィンター&カンパニーで使用。
1959年にウインター(WINTER & CO.)は、エオリアン・アメリカン社と合併し、
社名をエオリアン・コーポレーションに変更していた間、BRADBURYは
ウィンター&カンパニーが製造していたブランド名の一つです
→詳しくはWINTERの項目へ |
| BRADBURY, WM. B. |
詳細不明 |
| BRADFORD |
詳細不明 |
BRADLEY
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ブラッドリー アメリカ(フォールリバー/Fall River, Massachusetts) 創業1900年頃
ブラッドリーピアノは、マサチューセッツ州フォールリバーで1900年頃創業した
International Piano Manufacturing Company
(インターナショナル・ピアノ・マニュファクチャリング・カンパニー)によって製造されました。
同社は1900年頃からブラッドリーピアノの製造を開始し、1926年まで製造を続けていましたが、
ブラッドレーピアノは25年ほどしか存在せず、生産量も多くなかったため、ほとんど知られていない。 |
BRAMBACH
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ブランバッハ アメリカ 創業1823年
1823年に設立されたブランバッハ・ピアノ社は、最も早くからピアノを製造していた会社の一つであり、
当時最大の規模を誇っていた。
ブランバッハの名でピアノを製造していたが、ブランバッハ・ピアノ工場では、
コーラー&キャンベル(Kohler & Campbell)やマシューシェク(Mathushek)など、
アメリカの有名なピアノメーカーのピアノを製造。
1920年代後半からはコーラー・ブランバックの名前を使い、
1933年以降はコーラー&キャンベルの製造番号が付いているものもあるが、
ブランバッハの名前は1957年に廃止された。
ブランバッハピアノの工場は非常に大きく、大量に生産することができた。
そのため、品質が落ちるのではないかと思われがちだが、実際にはそうではなく、
一般的にブランバッハピアノは安定した品質で、純粋な音色を持っていると言われている。
ブランバッハ・ピアノ社は、小さなグランドが一般家庭にマッチし、
より多くの愛好家に豊かでまろやかな音を届けることができると考え、
国内で最も小さなグランドを作ることに注力しました。
ブランバッハ・グランドピアノは、特許を取得したブランバッハ・トーン・エクスパンダーと
カスタム・サウンドボードを搭載していた。
このトーン・エキスパンダーは、フルサイズのグランドピアノと同じように、
音色の量を増やし、広げることができます。
ブランバッハ・プレーヤー・グランドは、ピアノとプレーヤー・メカニズムを組み合わせたもので、
その品質の高さを売りにしていた。
ブランバッハ・グランドに使われているアクションは、すべてブランバッハの工場で作られている。
このアクションは、現代の一般的なピアノの響板に比べて耐久性が高いことで業界内でも評価されていた。
ブランバッハ・グランドには、4フィート8インチ、5フィート5インチの3つのサイズがある。 |
| BRANDTNER, H. RUDOLF |
詳細不明 |
| BRANSTON |
詳細不明 |
| BRASIL |
詳細不明 |
| BRASTED |
詳細不明 |
| BREITKOPF & HÄRTEL |
詳細不明 |
| BREMITZ |
詳細不明 |
| BRENTWOOD |
詳細不明 |
| BRETSCHNEIDER ,ALEXANDER |
詳細不明 |
| BREWSTER |
BREWSTER PIANO Co.
ROCHESTER-NEW YORK
詳細不明 |
| BREYER |
詳細不明 |
| BRIEM |
詳細不明 |
| BRIGGS |
詳細不明 |
BRINKERHOFF
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ブリンカーホフ アメリカ(シカゴ) 創業1906年
ブリンカーホフ社のピアノは、アメリカピアノの製造・販売の全盛期に製造されました。
1906年にウィル・T・ブリンカーホフによって設立され、1911年にイリノイ州シカゴで法人化されました。
ブリンカーホフ社は、伝統的なアップライトピアノ、プレーヤーピアノ、リプロダクションピアノ、
ミニチュアグランドなど様々な種類のピアノを製造し、1950年まで全米の多くのピアノを製造。
同社は当初、シカゴ通りとモーガン通りにある工場で、ブリンカーホフとシュリバー・アンド・サンズの
ピアノを製造していた。その後、M.シュルツ・アンド・カンパニーと提携して製造されたピアノには、
シュルツのシリアルナンバーが付いています。
ブリンカーホフ社のピアノはどれも美しい音色で、ケースのデザインも装飾性の高いものや
美しいシンプルな木製のものが多く見られます。ブリンカーホフのプレーヤーピアノは、
世界最高のアーティストが演奏しているかのように、ピアノが自動的に楽曲を表現することができる
特別な特許装置を備えていました。ブリンカーホフのミニチュア・グランドは、5フィートの大きさでありながら、
大きなグランドの音色を持っていると、多くのピアノ専門家に評価されています。 |
| BRINKMANN |
詳細不明 |
| BRINSMEAD, JOHN |
詳細不明 |
| BRISTOL |
詳細不明 |
| BROADWAY |
詳細不明 |
BROADWOOD & SONS

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ブロードウッド・アンド・サンズ
イギリス(ストラウド) ブロードウッドは多くの演奏者に愛用され、ヨーロッパ各地の王室に納入された。
1780年から1867年のブロードウッドの生産台数は驚異的で、13万5千台ものピアノが作られた。
ジョン・ブロードウッドはモダンピアノの音色や外観、演奏機構に大きな衝撃を与えたという。
ブロードウッドは一流の音楽家や熟練した同業者に囲まれ、永遠の価値を持つ革新的発想を生むための
最高の環境に恵まれたのである。
1783年、ブロードウッド社は2本ペダルのピアノの製作を開始した。
片方のペダルはダンパーを弦から離すもので、もう片方は弦に柔らかい布を当てて
音を弱めるものだった。それまでの操作しづらい膝レバーは、これらのペダルに
取って代わられた。1817年にトーマス・ブロードウッドはウィーンのベートーヴェンを訪ね、
翌1818年にグランドピアノを贈った。それは6オクターヴの広い音域を待ち、3本弦だった。
このピアノは後にリス卜が所有し、現在はハンガリー国立博物館が所蔵している。
1888年、ブロードウッド社は『バーレス』と呼ばれるフレームの特許を取得した。
この圧延綱(あつえんこう)のフレームは外縁部にかかる弦張力に耐えられる強さを持ち、
ストレスバー(弦方向に伸びる数本の鉄骨)を必要としない。
ストレスバーは駒の質量を犠牲にするため、音を弱めてしまう欠点があるためだ。
グランド、アップライトともに、この「バーレス」のピアノが作られた。
ショパンもリストも、イギリスにおける最後の演奏会ではブロードウッドの
グランドピアノを弾いた。リストはこのメーカーの推薦を頼まれ、
『ブロードウッドのように長く持つピアノフォルテは他にない』と書いたという。
1875年、ネアズ隊長率いるイギリスの北極探検隊は、HMSディスカバリー号に
ブロードウッドの小型アップライトピアノを積んで出発した。
また1910年にはブロードウッドの自動演奏ピアノがスコット隊長の南極探検に持参され、
最初のベースキャンプの氷上で演奏されたという。
<歴史>
1732年にスコットランドで生まれ、家具職人の修業を積んだジョン・ブロードウッドは、
1761年にロンドンへ出て、著名なチェンバロ製作者のバーカット・シューディのもとで働く。
1770年にシューディの娘と結婚し、翌年にはロンドンのグレート・パルトニー通り33番の
義父シューディの工房を任される。その工房ではモーツァル卜が演奏したこともあり、
またシューディの親友だったヘンデルはそこで多くの曲を作曲した。
1760年代には、新たに登場した楽器ピアノフォルテがロンドンで話題を呼んでおり、
ジョン・ブロードウッドはこの楽器にますます魅了されていった。
シューディが亡くなった1773年、ブロードウッドはネームボードに「Johannes Broadwood」
(当初は「John」ではなく「Johannes」と署名)の名を入れた最初のスクェアピアノを売り出す。
そしてその8年後に最初のグランドピアノを発売する。
ピアノという新たな市場に専念するため、ブロードウッドは1793年をもってチェンバロの製造を終了。
(※1791年にチェンバロ製造をやめたという文献もあるが詳細不明)
そして1807年に息子のトーマスとジェームズが共同経営者になった際に、社名を
「ジョン・ブロードウッド・アンド・サンズ』に改めた。
1780年から1867年の間のブロードウッド社のピアノ生産高は驚異的で、135,344台ものピアノが生産され、
その中の30,481台がグランドピアノだった。
あらゆるタイプのピアノにおける主要な改良はブロードウッド社によってなされた。
ブロードウッド社はアクションとストラングパック(鍵盤とアクション以外のピアノ本体)の設計で
いくつもの特許を取得している。総木製だった従来のピアノに鋼鉄の棒と金属のヒッチプレートを
いち早く取り入れ、それまでの単一の駒を分割して低音部に独立した駒を設けた。
また、操作しにくい膝レバーを廃止し、代わりに特許を取得した「ピアノとフォルテのペダル」を導入する。
さらにブロードウッド社はイギリス式グランドアクションを改良し、ハンマーが弦を押さえつけたままにならない、
素早いレぺティション(連打)を初めて実現させた。その機構は19世紀後半まで採用され続けた。
前途洋洋に見えたブロードウッド社も、無敵というわけではなかった。19世紀には、世界最大の
ピアノメーカーというイメージを揺るがしかねない大打撃を二度受けている。
一度目は、1821年にエラール社がグランドピアノのレペティション・アクションの特許を取得したことで、
そのあとに国王ジョージ4世がエラール社の楽器を注文したのだ。
このことはジョージ2世の時代から英国王室御用達を守り続けてきたブロードウッド社にとって脅威であった。
そして1851年、ブロードウッド社を窮地に追い込んだのは、またしてもエラール社だった。
今度はロンドン大博覧会で金賞を獲得したのだ。
その後の数年間にブロードウッド社は別のいくつかの博覧会で金賞を受賞し、またジョージ4世以降の
王や女王にもピアノを納めることができて、名誉を挽回したものの、会社の運気は下降し始める。
しかし、1860年代に生産された小型アップライトピアノの人気が状況を好転させるきっかけとなり、
19世紀の終わりごろには、ストレスバーが不要となる革新的な圧延鋼(あつえんこう)フレームの設計が
導入された。1903年にグレート・パルトニー通りの歴史的な建物は取り壊され、会社は東ロンドンの
ハックニーへ移転する。このときのオーナーはシューディ=ブロードウッドの6代目だった。
その後、自動演奏ピアノの完全自社生産が始まるが、会社の財政難は解消されなかった。
皮肉なことに、ブロードウッド社を財政危機から救ったのは、1914年の第一次世界大戦勃発であった。
戦争により多くのピアノ製造業者は廃業を余儀なくされたが、ブロードウッド社の工場は飛行機の
製造を許可され、一機につき125ポンドの収入を得ることができたのだ。そのため、少なくとも経済的には
終戦まで乗り切ることができた。終戦により儲かる戦時中の仕事はなくなり、ピアノ生産が再開された。
しかし、1939年に再び戦争が勃発すると、政府の規定によりピアノ製造会社は合併を強いられることになった。
そしてブロードウッド・ピアノの生産は、サウスロンドン、クラパムの、ウェルプデール、
マックスウェル・アンド・コッド社の工場へ移った。以後20世紀の終わりまで、ブロードウッド・ピアノは
同社のライセンスのもと、ウェルプデール・マックスウェル・アンド・コッド社で生産された。
広範にわたる再編を行い、また時代の変化に合わせてグランド、アップライト、自動演奏ピアノの生産を
切リ変えながらブロードウッド・アンド・サンズは生き残り、驚くほど長い歴史を築き上げてきた。
今日、ブロードウッドのピアノは、2000年にストラウドに設立されたブリティッシュ・ピアノ・
マニュフアクチャリング・カンパニーによって生産されている。
同社はまた、ベントレー、ナイト、ウェルマー、ウッドチェスターなど、ほかのイギリスのブランドの
ピアノも製作している。
<附録>
ブロードウッド・アンド・サンズ 製造番号/製造年代 対照表(1932年~2000年) →★
|
| BROADWOOD WHITE |
詳細不明 |
| BRODMANN |
詳細不明 |
| BRODWIN |
BRODWIN ブロッドウィン ニューヨーク
詳細不明
※有名なBALDWIN(ボールドウィン)ではないので注意 |
| BROOKS |
詳細不明 |
BRASTED BROTHERS
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ブラステッド・ブラザーズ BRASTED BROTHERS LIMITED イギリス その他詳細不明
|
| BRØDRENE HALS CHRISTIANIA |
詳細不明 |
BRODMANN
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ブロッドマン オーストリア 詳細不明
|
| BRINSMEAD |
JOHN BRINSMEAD の項目へ |
|
BROTHER




画像クリックでHPへ戻る
|
ブラザーピアノ
販売元:ブラザー楽器株式会社(愛知県名古屋市)、(ブラザー工業株式会社)
製造元:アトラスピアノ製造株式会社
ブラザー工業株式会社の住所(当時):名古屋市瑞穂区堀田通9丁目35番地
ブラザーミシンが自社の販売網を活用するためにアトラスピアノに発注したピアノ。
ミシンの会社がピアノを販売していた時代もあるんですね♪
アトラスピアノが製造していただけあって、そこそこ良く出来たピアノです。
他の例として家電メーカーのナショナルや、音響機器メーカーのビクターもピアノを委託製造していました。
機種バリエーション GU-172、GU-101、GU-107、GU-113など
ブラザーピアノのアクション全体写真 →★1 →★2
ブラザーピアノのまくり(蓋)部分のブランド銘柄 →★1 →★2
ブラザーピアノの純正キーカバー →★
ブラザーピアノの検査合格証 兼 調整履歴票 →★
ブラザーのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい →★ |
BROTHER CRESCEND
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ブラザー・クレッシェンド
販売:ブラザー楽器株式会社(名古屋)、(ブラザー工業株式会社)
製造:アトラスピアノ製造株式会社 |
| BROWN & ALLEN |
詳細不明 |
| BROWNING |
詳細不明 |
| BRUCKNER |
詳細不明 |
BRUEGHEL



画像クリックでHPへ戻る
|
BRUEGHEL ブリューゲル/(ブルーゲル)
製造:株式会社 坂本ピアノ製作所(旧:坂本楽器製作所)
当時の住所(坂本楽器製作所の頃):静岡県浜名郡和田村薬師481(昭和26年創業)
当時の住所(株式会社 坂本ピアノ製作所の頃):静岡県浜松市瓜内町498(昭和42年に法人化)
昭和62年3月31日解散
浜松の株式会社 坂本ピアノ製作所(大成ピアノ製造の前身)で作っていたピアノ
※似た名称あり 注:フルーゲルとは異なる
ブリューゲルのまくり(蓋)部分の銘柄マーク →★
<株式会社 坂本ピアノ製作所の歴史>
坂本岩義(大正2年生まれ)が設立。坂本氏は河合楽器と富士楽器で勤務後、ドレスデンピアノの顧問に就任。
その後、38歳の時に独立して坂本ピアノを創業させる。当時16人の従業員と共にブリューゲルピアノを製造。
その他、ピアノ製造の下請け会社としても各社のピアノを製造した。FUKUYAMA(フクヤマ)もその一つ。
法人化した昭和42年(1967年)の際は、資本金200万円で従業員は20人だったとの記録が残っています。 |
| BRUNGER |
詳細不明 |
| BRUNNEN |
ブルンネン 東洋ピアノ製造株式会社 |
| BRUNNER |
詳細不明 |
BRUTHNER
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ブルツナー 大洋楽器工業株式会社
詳細不明
1文字違いで「BLUTHNER」という広田ピアノ株式会社のピアノもありますが別ピアノです。
※ちなみに名称が似ていますがこれも別ピアノで「PRUTHNER/プルツナー」という
そこそこ有名で広く出回っているピアノもあります。詳しくは→PRUTHNERの項目へ |
BUCHHOLZ

このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
BUCHHOLZ ブッフホルツ/ブーフホルツ/(ブッホルツ)/(ブホルツ)
東京蒲田楽器製作所(蒲田ピアノ修理所) 大田区蒲田
斉藤喜一郎氏によって、大田区蒲田で作られていた。
ブランド名は斉藤氏の夫人でドイツ人のブッフホルツの名に由来しているという。
現在のウィスタリア・ピアノ製作所。
トレードマーク画像は「匿名希望様」からご寄稿頂きました。ありがとうございます!
<ウィスタリア・ピアノ歴史抜粋>
1924年、創立者斉藤喜一郎は1920年から23年までピアノ製作技術研究のためドイツに留学、
帰国後東京蒲田楽器製作所を設立し、「ブッフホルツ」および「ホルーゲル」を製作する。
戦後、横浜に(有)クレールピアノ製作所を設立。西ドイツピアノ製作業界視察のため再渡欧、
特にグロトリアン・スタインウェッヒピアノ会社の親交を得てピアノ製作技術の指導を受ける。
1956年、製作者の紋章に象り、ウィスタリア・ピアノ製作所と改称。
ブッフホルツのまくり部分の銘柄マーク部分 →★ |
| BULOW |
詳細不明 |
| BURG VAN DEN |
詳細不明 |
| BURGASSER |
詳細不明 |
BURGER & JACOBI
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
バーガー&ジャコビ アトラスピアノ製造株式会社 |
| BURGDORFER |
詳細不明 |
| BURGER & JACOBI AG |
詳細不明 |
|
BURGMULLER
BURGMÜLLER

このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ
|
BURGMÜLLER/BURGMULLER ※スペルは”BRUGMULLER”ではないので注意
ブルグミューラー/ブルグミュラー
■ビオン楽器製作所
■日本シュバイツァピアノ株式会社
磐田市の日本シュバイツァーピアノ(株)で作っていたブランド |
| BURLING MANSFIELD |
詳細不明 |
BUSH & GERTS


画像クリックでHPへ戻る |
ブッシュ・アンド・ゲルツ アメリカ(ロックフォード) 創業1885年
1885年、ウィリアム・H・ブッシュは、息子のウィリアム・L・ブッシュとジョン・ガーツとともに、
イリノイ州ロックフォードにW・H・ブッシュ・アンド・カンパニーを設立した。
1890年には資本金が20倍の企業に成長し、Bush & Gertsと改名しました。
1920年には工場と事務所をイリノイ州シカゴに移し、1942年までブッシュ&ゲルツブランドのピアノを製造した。
ジョン・ゲルツは、ドイツのハンブルグで名門ピアノメーカーのオットー・ベルスから技術を学んだ経験から、
芸術性の高いピアノを作ることができた。
ウィリアム・L・ブッシュは、著名なピアノメーカーの名前を騙った
「ステンシル」ピアノの販売を防ぐために尽力した。
ブッシュは、ピアノメーカーの名前と住所をすべてのピアノの目立つところに記載することを提案したが、
これは現在でも受け継がれている。
ブッシュ&ゲルツピアノは、西欧の偉大な革新者の一人であるジョン・ゲルツによって作られたピアノである。
ジョン・ゲルツらが手がけたピアノは、当時としては最大級の規模と設備を持つ工場で、
最高の木材と労働力を用いて丁寧に作られていました。
彼らの高い基準は、美しい音色のピアノを作ることで評価された。
左記トレードマーク画像は「匿名希望様」からご寄稿頂きました。寄稿頂き誠にありがとうございます! |
BUSH & LANE
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ブッシュ・アンド・レーン アメリカ(シカゴ) 創業1901年
ブッシュ・アンド・レーン社は、1901年にイリノイ州シカゴでビクター・ピアノ・アンド・オルガン社として設立。
ブッシュ・アンド・レーン社は1905年にミシガン州ホランドに移転したが、そこにはより大きな設備の整った工場と
オフィスが建設されていた。ブッシュ・アンド・レーン社は、最新の設備とユニークな奏者のアクションなどの
特許を駆使して、評判の高いブランドを着実に育てていった。
セシリアン、ビクター、パウルス、ファーランドなど、いずれもブッシュ・アンド・レーン社の
製造技術に裏打ちされたピアノである。
ビクターのピアノには1901年以降、セシリアン・ピアノにはセシリアン・プレーヤー・アクション・カンパニーが
買収された1914年以降にブッシュ・アンド・レーンのシリアルナンバーが付けられている。
この会社は1931年に製造を終了したが、1940年代初頭には他社がブッシュ&レーンの名を冠した
ピアノを製造していた。例えば、ウェザー・ブラザーズはコンソールピアノにこの名前を使用していた。
ビクターはブッシュ&レーン社のオリジナル製品であり、著作権を取得して同社の独占所有物となった。
他のブッシュ・アンド・レーン社製品と同様に、Victorは耐久性と信頼性が高く、
心地よい音質を持つ楽器として作られた。
また、セシリアン・ピアノは、汎用性が高く、使いやすく、高度な演奏機構により破壊されないと評判であった。
さらに、ブッシュやレーンのピアノは、当時の他のピアノブランドに匹敵する
甘美な音色を持つことで知られていた。
ブッシュ・アンド・レーン社が販売したVictorとCecilianは、大恐慌で倒産するまで、何千台も販売された。
ブッシュ・アンド・レーン社は、大企業に会社を売却して品質を犠牲にするよりも、
ピアノの生産を完全に停止するという立派な決断をしたのである。 |
| BUTLER BROS. |
詳細不明 |
BUXHARD
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
バックスハルト ※バッハルトと発音表記する資料もあり
有限会社 アサヒ工芸社(前身:朝日楽器製作所) 大石寛一氏の創業
創業1966年(昭和41年)※創業年については要調査 →廃業1970年(昭和45年)
当時の住所:浜松市中野町798、浜松市天龍川町677
他に、SUNSHINE(サンシャイン)という鍵盤数が73鍵のピアノもあった。
WAGNER(ワグナー)も製造したとの情報あり。
※スペルは”BAXHARD”や”BAXHORD”という情報も散見されますが、正しくは”BUXHARD”です
<追記>
BUXHARDについて修正受付フォームに匿名希望様から新たな情報を頂きました。
情報ご提供者様によりますと、1957年(昭和32年)~1958年(昭和33年)頃にこのBUXHARDを
ご購入されたとの情報を頂きました。購入時は既に中古として売られていたピアノだったとのことです。
当方でも引き続き調査させていただきますが、1966年(昭和41年)創業という情報が合いません。
ひょっとしたらBUXHARDのブランドを朝日楽器製作所が引き継いで製造したのかもしれませんが、
詳細は当方でも一切不明です。もし何かお分かりになる方がいたら新たな情報お待ちしております。
ちなみに情報を頂いた方によりますと、このピアノは1972年頃まで何とかご使用されていたとのことです。
手放された際に記念で撮影した写真もご丁寧に頂きました(1973年頃とのことです) →★
この度は貴重な情報とお写真を頂きまして誠にありがとうございました! |
| BYELLORUSS |
詳細不明 |
上記Bから始まるブランドの中で、追記出来そうな事項や新情報を発見した場合、修正受付フォーム よりお気軽にお知らせ下さい。
どんな些細な情報でも構いませんので、広く皆様からのフィードバックをお待ちしております。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
 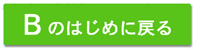 



ピアノ銘柄ブランド
トレードマーク 紹介
& 知名度ランキング

|

メーカー/ブランド説明・会社沿革・歴史・製作者・特徴・音色・他
|
| C. BAER |
詳細不明 |
| C. BECHSTEIN |
BECHSTEIN(→ベヒシュタインの項を参照) |
C. HARMAN



画像クリックでHPへ戻る |
シー・ハーマン/C・ハーマン
※シー・ヘルマンという発音表記する資料も散見されますが”ハーマン”の読み表記が正しいです
製造元:井ヅツ楽器株式会社(ヰヅツ楽器)大阪府堺市堺区
当時のショールーム:大阪市バス住吉車庫前
<井ヅツ楽器 会社住所変遷>
大阪府大阪市住吉区万代西6-10
↓
大阪府大阪市住吉区万代5-14-6
↓
大阪府堺市堺区新在家町東4-3-7
井ヅツ楽器株式会社のはじまりは静岡県袋井市にあった山下楽器の技術顧問であった
榊原清作氏の実用新案技術を多数取り入れて作り始めたと伝えられています。
創業時は大阪市住吉区にあり、最後の住所は大阪府堺市にありました。
小型でありながら3本弦を採用し、高さを抑えたモダンなデザインが売りだったようです。
Cハーマン販売当時、同社が製造する「ローリス&サンズ/LORIS & SONS」と共に売り出されていました。
当時のラインナップとして、U-110W、U-110M、U-5C、U-7Cの4機種がありました。
シーハーマンの当時の定価の記録が残っておりますので列挙します
U-110W:45万円、U-110M:46万円、U-5C:48万円、U-7C:60万円
尚、井ヅツ楽器は他社からもピアノ製造を依頼されてOEM製造をしておりました。
※参考画像→井ヅツ楽器の保証書 →★(ちなみにこれは「KUHLMANN」というピアノの保証書です)
左記トレードマーク画像は「F様」からご寄稿頂きました。
この度は写真のご寄稿を頂きまして誠にありがとうございました! |
| C. KONING |
C. Konig 詳細不明 |
C. THWAITES
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
シー・スウェイツ (シー・ツワイスという発音表記する資料もあり)
スウェイツ商会 |
CABLE


画像クリックでHPへ戻る |
ケーブル CABLE PIANO CO. The Cable Piano Company 創業1880年
エオリアン・アメリカン・コーポレーションの子会社
工場:オレゴン州 販売店:シカゴ
詳しくはAEOLIAN(エオリアン)の項を参照
オルガンの製造を始めたH.D.ケーブルは、1880年にケーブル・ピアノ・カンパニー
(通称:ケーブル・カンパニー)を設立した。
1880年創業のケーブルは、ウォルフィンガー・オルガン社でキャリアをスタートさせた後、
シカゴ・コテージ・オルガン社に移籍した。
1890年、ニューヨークのConover Brothersと合併し、ケーブルの2人の兄弟も経営に加わった。
イリノイ州のシラー・ピアノ社を買収し、1920年にはアメリカ国内にセントチャールズと
シカゴの2つの工場を持つようになった。
最盛期には500人を超える従業員が働いていた。
ケーブル社は、音楽活動やコーラス、野球チームなどの福利厚生を充実させ、
従業員を大切にする社風を築いていた。
1900年代半ばから後半にかけての一連の買収により、ケーブル・カンパニーは
エオリアン・アメリカン・コーポレーションに買収された。
2001年には、ギブソン・ギターズがケーブル社の名前の権利を購入し、中国でのピアノ生産を続けている。
ケーブル・カンパニーは、1920年代には、Conover、Cable、Kingsbury、Wellington、Schillerなどの
名前でピアノを製造していた。
また、コノバー・カローラ・インナー・プレイヤー、コノバー・ソロ・カローラ・インナー・プレイヤー、
カローラ・インナー・プレイヤー、ソロ・カローラ・インナー・プレイヤー、ユーフォナ・インナー・プレイヤー、
ソロ・ユーフォナ・インナー・プレイヤーという名称で、さまざまなプレーヤー・ピアノを発表したのである。
ケーブルピアノ社は、響板とフレームの構造に関する独自の技術を商標登録していた。
アップライトでは「トナーク」、グランドでは「クラウンステイ」と呼ばれ、ピアノの要素を構成する方法は
業界でもユニークで、高い評価を得ていた。
これは、響板を取り付けた後に理想的な音色が得られるよう、
フレームに組み込まれた曲線状のブレースである。
ケーブルピアノの美しい木目調の外観 →★ ケーブルのまくり(フタ)部分の銘柄マーク →★
ケーブルピアノに貼られた各シール類 →★ →★ |
| CABLE, HOBART M. |
→Hobart Cableの項目へ |
CABLE-NELSON
CABLE NELSON

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
CABLE-NELSON PIANO CO. ケーブル・ネルソン
1903年シカゴで創業。その後ミシガン州に移り、
1926年にボストンのエベレットピアノ(EVERET PIANO)と合併。
ケーブル・ネルソンのブランドによるピアノは、創業以来合計40万台作られたといい
エベレットピアノの廉価版として広く販売された。
尚、この会社ではKINGSBURY(キングスブリー)、WELLINGTON(ウエリントン)、
SCHILLER(シーラー)というブランドも作っていました。
<さらに詳しい解説>
ケーブル・ネルソン・ピアノの始まりは、1903年にフェイト・S・ケーブルが、
当時有名だった2つのピアノ会社を買収したことに始まります。
レイクサイド・ピアノ社とスウィートランド・ピアノ社である。
1905年に同僚のH.P.ネルソンが入社すると、社名を「ケーブル・ネルソン」に変更した。
買収した2社はシカゴにあったが、合併して新ブランドを立ち上げたことを機に、
共同経営者たちはミシガン州サウスヘイブンに会社を移転した。
彼らのビジョンは、アメリカ中西部の小さな町で会社を設立し、そこで愛用者を増やして
有名になろうというものだった。1926年にエバレット・ピアノ・カンパニーに買収されるまでの約20年間、
同社はこの考えのもとに繁栄した。
当初は同社の一部門であったが、1954年にはハモンド・オルガン社に買収された。
1954年、ハモンドオルガン社がエバレットピアノ社を買収したことで、
ケーブル・ネルソンピアノの製造方法やブランドイメージが大きく変化したのである。
1973年、EverettとCable-Nelsonの両方のピアノ会社がヤマハ・コーポレーションに買収され、
生産拠点はジョージア州に移された。
1990年代から2000年代初頭にかけて、Cable-Nelsonの名前が使用されたが、
2014年現在、ヤマハはケーブル・ネルソンピアノの新製品を生産していない。
ケーブル・ネルソンは、アメリカ中西部の良質なピアノブランドとして知られており、
アップライトピアノ、グランドピアノ、各種サイズのピアノが存在していた。
1900年代前半から半ばにかけての家庭用ピアノの隆盛の中で、ケーブル・ネルソンのピアノは、
品質を犠牲にすることなく手頃な価格であることが評価されていた。
当時、他のピアノブランドと同様に、ケーブル・ネルソンは、ビジネスのやり方がユニークであり、
信頼に値するものであることをお客様に知ってもらいたいと考えていた。
そして、高級な材料を使用しながらも、平均的なアメリカ人にとって、
コストパフォーマンスの高いピアノであることを誇りにしていたのです。
合併や買収を繰り返しながら、Cable-Nelsonは以下の名前でピアノを製造していました。
Lakeside、Radcliffe、Sweetland、Dulcitone Player、Denton、Cottier、Daniels |
| CÄCILIA |
詳細不明 |
| CAHN & CAHN |
詳細不明 |
CALACE
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
カラチ 販売元:佐藤商会(名古屋)
佐藤商会が戦前に取り扱ったもの。
その他詳細不明 |
CALISIA
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
CALISIA/カリシア
ポーランド 創業1878年
CALISIAの工場は2007年に生産を停止。ポーランドで操業していた最後のピアノ工場でした。
2010年以降、Calisiaのブランドは中国で製造されています。その他詳細不明
※ブランドスペルは「GALISIA/ガリシア」ではありません |
| CALISIA |
シンハイ(星海)のブランド 中国 詳細不明 |
CAMBRIDGE
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ケンブリッジ Cambridge Piano Company
1902年、ニューヨークに設立されたケンブリッジ・ピアノ・カンパニーは、
ニューヨークにあった数多くのピアノメーカーの一つでした。
その後8年の間に、ケンブリッジ社はリッカ&サンズ社に買収され、生産を続けました。
数年後、ケンブリッジ社はジェイコブ・ドール社に買収され、その後ウィンター社に売却されました。
1900年代初頭、ケンブリッジピアノが成功したのは、アップライトピアノのサイズが小さかったからだ。
ケンブリッジピアノには、42インチ、44インチ、45インチ、51インチのサイズがあった。
このサイズは、ニューヨーク周辺の小さな家やアパートに住むピアニストや音楽家に最適だった。
残念ながら、第二次世界大戦が始まった頃には、ケンブリッジのシリアルナンバーは止まっており、
他の多くの製品と同様に製造中止になったことを示している。
ケンブリッジのピアノは、当時、中流家庭の予算内で購入できる価格帯として人気がありました。
価格に加え、サイズが小さかったこともあり、増え続ける中産階級の社会経済的な層に選ばれていました。
その価格にしては、ケンブリッジの楽器は驚くほど美しく、心地よい音色を持っていた。 |
| CAMEO |
詳細不明 |
| CAMERON |
詳細不明 |
| CAMILLO |
詳細不明 |
| CANARIA |
カナリア 豊楽器製造株式会社(ユタカ楽器)
卓上ピアノを製造 |
| CAPEN |
ケーペン? アメリカ(ニューヨーク) NEW YORK
詳細不明 |
CAPMAN
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
キャップマン イタリア 詳細不明
|
| CAPPELEN |
詳細不明 |
CARHART & NEEDHAM
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
カーハート・ニーダム アメリカ(ニューヨーク) 創業1851年
1851年にニューヨークで設立されたカーハート&ニーダム社は、
オルガンとメロディオン(オルガンの一種)を製造していた。
メロディオンとは、1840年代に流行した小型のリードオルガンのことである。
メロディオンは、1840年代に流行したリードオルガンで、創業者の一人であるJerahmiah Carhartが、
リードオルガンを意味する "melodeon "という名前を作ったとされている。
カーハートは、この名前を作っただけでなく、メロディオンを柔らかく改良するために多くの発明を行い、
その多くが販売されたり、特許を取得したりしました。
カーハート&ニーダム社は、1868年にジョージ・プリンスと提携するまで、
オルガンとメロディオンを製造していた。
カーハート&ニーダム社は、1868年にジョージ・プリンス社と提携するまで、
オルガンやメロディオンを製造していたが、これは後にアメリカの音楽史において
非常に重要な合併であると認識されている。
カーハート&ニーダム社の楽器は、それまでの楽器に比べて、音を外側に押し出すのではなく、
内側に押し出すように設計されている点が特徴であった。
(カーハートの発明により、それまでにない方法でパイプを曲げることができた)
カーハート&ニーダム社のメロディオンは、その落ち着いた音色に加えて、
精巧な木材を使って美しく作られています。
繊細なスクロールや手彫りのディテールは、1世紀半前と変わらない美しさを誇っています。 |
| CARL DÖRR |
詳細不明 |
CARL ECKE
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
カール・エッケ 創業1843年
ポーランド(Poznań/ポズナン)
ドイツ(Berlin/ベルリン)
ドイツ(Dresden/ドレスデン)
Carl Eckeは、19世紀から20世紀まで製造していたドイツのピアノブランドです。
ピアノ製造は1843年、今のポーランド(Poznań/ポズナン)で始まり、
当初はグランドピアノのみを製造していましたが、1870年にアップライトピアノも製造を開始しました。
その後、会社は発展して1873年にベルリンに移転、さらにその後ドレスデンに移転しました。 |
CARL & SONS
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
カール・アンド・サンズ 東洋ピアノ製造株式会社
機種バリエーション:CS130等 |
CARL HARDT


画像クリックでHPへ戻る |
CARL HARDT/カール・ハルト
販売:福山ピアノ社(東京)
白鍵は2枚象牙のようです。その他詳細不明
※ちなみにアメリカの「CARHART & NEEDHAM」とは違うピアノです
CARL HARDTの全体写真 →★ CARL HARDTのまくり(蓋部分)のブランド名部分 →★
CARL HARDTの特徴的な天屋根部分 →★ 特徴的な猫脚 →★ 下パネル内部 →★
これらの画像は「ピアノ調律塾様 https://www.piano-juku.com/」からご寄稿頂きました。
この度はたくさんの貴重な画像をご寄稿頂きまして誠にありがとうございました! |
CARL HERT

画像クリックでHPへ戻る |
カール・ヘルト/カールヘルト
大成ピアノ製造株式会社
東洋ピアノ製造株式会社
※アメリカの「CARHART & NEEDHAM」とは違うピアノです |
| CARL. KIERSTON |
詳細不明 |
CARL SEILER


画像クリックでHPへ戻る |
カール・ザイラー/カールザイラー
製造:株式会社 プルツナーピアノ(浜松)
発売元:三協ピアノ株式会社(浜松)
プルツナーとともに(株)プルツナーピアノで作られていたピアノ。
鍵盤押さえの部分にPruthner PIANO MFG, CO, LTDと入っています。
発売元は三協ピアノ株式会社。
トレードマークは音叉の後ろにチューニングハンマー2本を交差させたデザインですで、
回りの星形は調律に使うチューニングハンマーのチップ(差し込み部分)の形をモチーフにしています。
カールザイラーのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★ |
CARL STEINBERG
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
宜昌金宝楽器製造(中国湖北省宜昌市)/Yichang Jinbao Musical Instrument Manufacturing Company
シンガポールに販売店があるようですが詳細不明 |
CARL STEINMANN
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
カール・スタインマン ドイツ(ドレスデン) 詳細不明 |
CARL MAND
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
<以下、ウィキペディアより引用抜粋>
カール・マント(Carl Mand、1811年10月27日 - 1892年8月28日)は、
ドイツのピアノ製作者であった。
カール・マントの経歴に関する情報はわずかである。
彼の父はコブレンツ近郊のホルヒハイムの指物師・ワイン醸造家であった。
彼の邸宅の近くにベルリンの銀行家メンデルスゾーンの別荘があり、
時折フェリックス・メンデルスゾーンが訪れていた。
メンデルスゾーン家は最初にカール・マントの兄弟ニコラウス(Nikoraus)に
ウィーンで音楽とピアノ製作の知識を深めるよう働き掛けた。
しかしながら、ニコラウスが病気になると、カールがウィーンへの旅を始めた。
カールは1827年か1835年までウィーンでピアノ製作者として働いた。
帰郷後、カールはコブレンツで自身のピアノ製造会社を設立し、
この会社はその後数十年もの間大きな成功を収めた荒るそのため、
マントは宮廷御用達称号を得て、彼の会社を自信を込めて「19年間最高賞のみ
(国際博覧会での11の賞を含む)を受賞している世界唯一の工場」と呼んだ。
1909年、マントの会社はコブレンツを拠点とするピアノ製作者ハインリッヒ・クラウス
(Heinrich Knauß)によって買収され、同年にRheinische Pianofortefabrik AG
(ライン・ピアノ工場株式会社)となった。
会社は1911年にKapplerによって買収され、1928年に生産が終わった。
カール・マントの現存する楽器の大半は個人によって所有されている。
コレクションはエーレンブライトシュタイン城塞にあるコブレンツ州立博物館で維持されている。
1900年頃に建築家・デザイナーのヨゼフ・マリア・オルブリッヒによって設計された
独特なデザインのグランドピアノは、ベルリン楽器博物館に展示されている。
この八角形のマント=オルブリッヒ・グランドピアノには他のモデルも存在し、
入り組んだ装飾を持つ黒色モデルはダルムシュタットのMathildenhöheにある。
カール・マントが特許を取得したベル・グランドピアノ(Glockenflügel)および
Eckflügelはとりわけ特殊である。
これらの特に小型のグランドピアノは場所を節約するために部屋の角に置くことができる。 |
| CARLTON |
詳細不明 |
CARLZEILER
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
カールザイラー 大洋楽器工業株式会社(浜松) 詳細不明
(プルツナーピアノのカールザイラーとは違うのか??) |
CAROD
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
キャロッド 中国(湖南省長沙市) 2014年~ 詳細不明
HP:http://www.carodpiano.net/ |
CAROL OTTO

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
C.OTTO
当時国内での販売元:ドーリング商会(デーリング商会)(横浜)※
英語名:J.G.DOERING'S PIANOS ORGANS
キャロル・オットー (CAROL OTTO/Carol Otto)
カロル・オットー (CAROL OTTO/Carol Otto)
ドイツ製(ベルリン)
キャロル・オットー社は、1866年創立
ベーゼンドルファー、スタインウェイ、ベヒシュタインと同世代のメーカー。
当時ドイツベルリンのピアノメーカーは、高い製造技術を持っており、
特徴のあるの燭台付きピアノや2本ペダル式のアップライトピアノを多く製造。
※ドーリング商会(デーリング商会)は1874年横浜で創業 |
CASTELLO
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
カステロ イタリア 詳細不明
|
|
CASTLE



画像クリックでHPへ戻る
|
キャッスル CASTLE
六郷ピアノ(大田区六郷 →後に茨城県土浦)、キャッスルピアノ製作所
田中貞三氏が田口氏の協力を得て、初め六郷で、後に茨城県土浦で製造した。
2種類あって音は良かったが、外装に厚い材料を使用していたため温度に弱かったとのこと。
私が実際に拝見したキャッスルピアノは、1枚貼りの象牙鍵盤で、とても重厚な作りでした。
当時としては大変珍しく曲線を意識した脚が特徴的です。
所有者様はオーバーホールはせずを処分するとのことで、貴重な象牙鍵盤だけ引き取らせて頂きました。
キャッスルまくり部分(フタ部分)のブランド銘柄 →★ キャッスル全体写真
→★
頂いた象牙鍵盤 →★ ※この象牙鍵盤が欲しい技術者の方へ格安でお譲りいたします(当方は利用の予定なし)
※キャッスルのトレードマークはこれ以外にもう一つ若干デザインの異なるマークもあります。
|
CASTLE


画像クリックでHPへ戻る |
キャッスル
鈴木ピアノ製作所
このキャッスルは上記の郷ピアノとは別ブランドで、
トレードマークは星形(チューニングハンマーのチップ部形状)の中に”S”の文字が入ったマークになります。
トレードマーク画像は「匿名希望様」からご寄稿頂きました。ありがとうございます! |
| CAUWENBERGHE |
詳細不明 |
| CHAIKA |
→TCHAIKAの項目へ |
CHAIKOVSKY
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
CHAIKOVSKY チャイコフスキー
チャイコフスキーというブランド名で日本国内でも製造販売していたようですが、詳細不明
ピアノのまくり(鍵盤蓋)部分の銘柄ブランドマーク →★
ソ連製のチャイコフスキーはCIAIKOVSKYの項目へ |
|
H, CHALLEN


画像クリックでHPへ戻る
|
チャーレン イギリス/ロンドン
1986年からはマレーシア西部で作れれている
チャールズ・H・チャーレンは1804年にすでに最初のピアノを製作していたと考えられているが、
イギリスのピアノメーカー、チャーレン・アンド・サンズは1830年に設立された。
チャーレンといえば信頼性と耐久性であり、そのピアノの音質は高く評価されている。
チャーレン・ピアノは英国放送協会(BBC)で頻繁に使用されている。
チャーレン社は小型のグランドピアノでよく知られているが、1935年の英国王ジョージ5世即位25周年には、
世界最大のグランドピアノを製作したというエピソードがある。
全長355センチ、弦の総張力は30トンあったそう。
19世紀の最後の四半世紀から20世紀の最初の四半世紀にかけて、チャーレン社は年問約500台の
高品質のピアノを生産していた。この会杜に好機をもたらしたのは、1926年に新社長に就任した元チャペル社の
ウィリアム・エヴァンスだった。
エヴァンスは、チャーレン社が20世紀の初めに開発した全長152cmのベビーグランドピアノを再開発する。
大量生産技術の導入により、チャーレン社はこの楽器の価格を125ポンドから65ポンドに下げることに成功し、
その結果、ベビーグランドはイギリスの家庭からアップライトを追い出すほどの人気となった。
ほとんどのピアノ製造業者に打撃を与えた1930年代の大恐慌も、チャーレン社には影響を及ぼさなかったといい、
ピアノの生産高は1925年の500台から、1935年の2,500台にまで跳ね上がった。
チャーレン社は1932年にブロ―ドウッド社のピアノの生産を引き受け、また1936年には、
スタインウェイ社、ベーゼンドルファー社とともに、BBC(英国放送協会)にピアノを供給する契約を取り付けた。
これによりチャーレンピアノの音がイギリス中の家庭で聞かれるようになった。
1959年のウィリアム・エヴァンスの引退に伴い、チャーレンのブランド名はブラステッド・ブラザー社に売却され、
その後1970年に同社が消滅した際に、バラット・アンド・ロビンソン社へ移った。
1986年からチャーレンピアノは、ヴィエナ・ミュージック・Sdn・Bhd社の工場部門であるミュージカル・
プロダクツ・Sdn・Bhd社によって、マレーシア西部で組み立てられている。
<附録>
チャーレン・アンド・サンズ 製造番号/製造年代 対照表(1850年~2000年) →★ |
| CHALLENGER |
詳細不明 |
CHALLIOT
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
シャリオ(フランス・パリ) 詳細不明 |
CHAPPELL


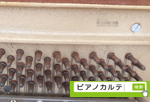
画像クリックでHPへ戻る |
THE CHAPPELL PIANO CO.,LTD.
/Chappell & Company チャペル・アンド・カンパニー
イギリス チャペル社 ※所有:ワーナー・ブラザーズ
※ちなみに教会や礼拝堂に近い言葉である”チャペル”のスペルは”CHAPEL”です(PとLが1つです)
チャペル社といえば、現在、ロンドンのヴィクトリア・アンド・アルバート博物館に所蔵されている風変わりな
スクエア・グラス・ピアノで有名。この楽器には弦の代わりにガラスの棒が取り付けられており、
ダウンストライキング方式のハンマーで叩く仕組みになっている。
チャペル製のコンサートグランドは非常に変わっていて、最高音部に3本ではなく 4本の弦が張られている。
リヒャルト・シュトラウスはチャペル・ピアノについてこう書いている。
「音色は極めて甘く、共鳴しやすい音質。タッチはとても反応が良く、軽い。
英国のメーカーのこのような完璧な楽器に出会えたことは、私にとって素晴らしく快い驚きだった」と。
すでに楽譜出版社を始めていたサミュエル・チャペルと、ヨハン・クラーマーと、フランシス・ラトゥールは、
1811年にチャペル・アンド・カンパニー社をロンドンに設立した。
その後、彼らの会社は1840年代にようやくピアノの製造を開始し、「ウェア・ルーム』と称する
特別なショールームで展示販売を始めた。
クラーマーはロンドンで人気の作曲家、音楽教師であったため、彼自身が店にあるすべてのピアノを
選んだということは、ライバル会社に差をつける良い宣伝になった。
楽譜やピアノの販売の他に、チャペル社はロンドン内のコンサートのプロデュースも行うようになり、
フィルハーモニック協会と密接な関係を築いた。
1840年にチャペル社はロンドンのソーホーでピアノを製造するようになるが、生産量が増えると、
チョークファームの工場へ移転した。
1901年にチャペル・ピアノ・カンパニーとパブリッシング・カンパニーが分離すると
ピアノの生産高は増大し、1920年代と30年代は年間1,000台も生産された。
1929年にチャペル社はアリソン・ピアノ社とカラード・アンド・カラード社を買収し、さらに1938年には
ジョン・ストローメンガー・アンド・サンズ社を買収して規模を拡大した。
1968年、フィリップス・レコード・カンパニーがチャペル・カンパニーを1750万ポンド
(2550万米ドル)で購入する。
そしてワーナー・チャペル社が所有するケンブル社がライセンスのもと、
2000年までチャペル・ピアノを製造した(ワーナー社は独占権を保有し続けている)
今もボンド通りにはチャペルの店があり、楽譜や楽器を販売している。
チャペルピアノのまくり(フタ部分)にある銘柄ブランドマーク →★ →★
チャペルのアクションレールに貼られているシール →★ MADE IN ENGLANDのプレート →★
<附録>
チャペル・アンド・カンパニー 製造番号/製造年代 対照表(1840年~1969年) →★
<以下、ウィキペディアより引用抜粋>
チャペル& Co.(Chappell & Co.)は、かつて存在したイングランドの企業である。
音楽出版とピアノ製造を行っていた。
1810年にサミュエル・チャペル(c.1782年–1834年)によって音楽教授Francis Tatton Latourと
ヨハン・バプティスト・クラーマーと協力して創業された。
クラーマーは有名なロンドンの作曲家、教師、ピアニストでもあった。
会社の店舗には複数のフロアにピアノやその他の楽器(販売または貸し出し)、楽譜のための広い展示室があり、
ボンド・ストリートの目立つ目印となった。チャペルはロイヤル・フィルハーモニック協会の創設にも取り組んだ。
チャペル社の評判は急成長し 、1819年にはルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンが出版したいと
思っている作品に関して仲間に手紙を書いている;
「ポッターは、ボンド・ストリートにあるチャペルが現在最良の出版社に一つだと言っている」。
サミュエル・チャペルは1834年に死去し、長男のウィリアム・チャペル(1809年–1888年)が会社を引き継ぎ、
母のエミリー・チャペル(旧姓Patey)の代理として会社を経営した。
1843年頃、ウィリアムはクラーマー& Co. に加わり、その後パーシー協会と音楽古物研究協会
(Musical Antiquarian Society)を設立した。
弟のトーマス・ペティー・チャペル(1819年–1902年)が次に経営を引き継いだ。
最初は音楽出版と演奏会の主催に専念していたチャペル社は1840年代にピアノ製造を始めた。
トーマスはチャペル& Co. の出版事業を拡大し、ミュージカルに関する出版に重点的に取り組んだ。
これは今日もチャペルの成功にとって重要である特異分野である。
チャペル社は楽譜販売のための市場を作ることになるかもしれないコンサートやオペラ、その他の催しを主催した。
トーマスはチャペル家が部分的に所有していたセント・ジェームズ・ホールにおける月曜から土曜までの
ポピュラーコンサートを思い付き、出資した(1859年)。
このコンサートは弟のサミュエル・アーサー・チャペルによってうまく運営され、1901年まで続いた。
トム・チャペルの成功の一つはギルバート・アンド・サリヴァンのオペラとアーサー・サリヴァンのその他の楽曲、
古いグノーのオペラ『ファウスト』、バルフのオペラ『ボヘミアの少女』の出版であった。
トーマスは王立音楽大学の最初のDirectorの一人やロイヤル・アルバート・ホールの最初の
支配人の一人でもあった。トーマスは1902年に死去した。
トーマスは音楽出版社協会の創設メンバーであり、協会の初代会長となり、
1881年から1900年まで会長職を務めた。
20世紀の間、チャペル社はイギリスで一流の音楽出版社・ピアノ製造業者となった。
1964年、建物が火災で破壊されたが、その後に再建された。
1970年代末までに、チャペル社はミュージカル作品(ロジャース&ハマースタインなど)の出版で有名な
世界的一流音楽出版社となった。1980年、チャペルは小売事業を売却し、音楽出版のみに専念した。
ロンドンのボンド・ストリートの店舗はヤマハピアノの大流通業者であったケンブル& Co.によって購入され、
ケンブル社はチャペル・オブ・ボンド・ストリートの名称でこの楽器店を経営した。
チャペル& Co. の出版事業は後にポリグラムによって、1987年にはワーナー・ミュージック・グループによって
2億米ドルで買収され、ワーナーの音楽出版部門と合併してワーナー/チャペル・ミュージックが設立された。
チャペルのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★ |
| CHAPPELL |
チャペル
国内でもCHAPPELL(チャペル)というブランド名で製造販売していたピアノもあったようですが詳細不明 |
CHARIS


画像クリックでHPへ戻る |
カリス CHARIS ※読みはチャリスではない
東洋ピアノ販売 韓国製造 その他詳細不明
※東洋ピアノが扱っていたBÖCKLER(BOCKLER)/ベックラーというピアノのトレードマークと
まったく同じマークということが分かります(文字の部分を除いて)
ちなみに、ドイツ製の「グロトリアン・チャリス」とはまったく別のピアノです |
CHARLES J. HOLDER
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
1834年、チャールズ・J・ホルダーは、自分の名前を冠した会社をニューヨークに設立した。
興味深いことに、ウェーバーピアノ社のアルバート・ウェーバーは、チャールズ・J・ホルダーのもとで
見習いをした後、会社を設立した。
残念ながら、1800年代半ばから後半にかけて消滅したと思われるこの小さなピアノ会社については、
ほとんど知られておらず、時の経過とともに多くが失われている。
数少ない資料によると、チャールズ・J・ホルダーのピアノは品質が高く、
いくつかの賞を受賞し、高い評価を得ていたという。
また、チャールズ・J・ホルダー社が製造したピアノ・フォルテ
(1800年代初頭に流行した現在のピアノの原型)は、
ニューヨークのアメリカン・インスティテュートでクラス最高の銀メダルを獲得している。 |
CHARLES STIEFF
CHARLES M. STIEFF
CHAS. M. STIEFF
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
チャールズ・M・スティーフ 創業1842年 アメリカ(ボルチモア/BOLTIMORE)
ピアノ内部のフレームには、「ESTABLISHED 1842」と書いてあります。
1831年にドイツからアメリカに渡ったチャールズ・M・スティーフ、
1841年にヨーロッパから輸入したピアノの販売を開始し。
1842年にメリーランド州ボルチモアにピアノ会社を設立した。
スティーフ氏の長男であるジョン氏が会社を引き継ぎ、彼の指揮のもとで会社は大きく成長した。
1876年、ジョンは自分の会社の株式を兄弟に売却した。
スティーフ社は、自社製品だけでなく、Bennett-Bretz社、Davies & Sons社、
Leslie Brothers社、Shaw社の製品も製造し、何十年にもわたってそれなりの成功を収めた。
残念なことに、100年以上の歴史を持つ同社は、1951年に倒産した。
チャールズ・M・スティーフは、高名な実業家として知られており、
最高水準のピアノを製造していた。
グランドピアノとアップライトピアノの両方を製造していたスティーフ社の楽器は、
信じられないほど長く使える耐久性のあるピアノとして業界で知られていました。 |
CHAS. THWAITES
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
CHAS.スウェイツ スウェイツ商会 |
| CHASE, A.B. |
→A.B. CHASEの項目へ |
CHASSAIGNE

画像クリックでHPへ戻る
|
CHASSAIGNE FRERES/Chassaigne Frères
スペイン 詳細不明
画像は「匿名希望様」からご寄稿いただきました。ありがとうございます! |
| CHAVANNE |
詳細不明 |
CHERNY
 
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
CHERNY チェルニー
製造:東洋楽器製造株式会社(広島市)
広島の東洋楽器製造のワグナー、ヒロタに次ぐ第三のブランドでした。
<参考>
あのピアノ練習曲を数多く残したことで有名なカール・チェルニーの正しいスペルは”CZERNY”ですが、
東洋楽器製造株式会社が作っていたピアノ、ツェルニーのスペルは”CHERNY”です。 |
CHEW
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
→S. CHEW(周ピアノ)の項目を参照
|
CHICAGO COTTAGE ORGAN & PIANO COMPANY
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
Chicago Cottage Organ & Piano Company
シカゴ・コテージ・オルガン・アンド・ピアノ・カンパニーは、
1879年にウォルフィンガー・オルガン・カンパニーという名前で設立された。
F.R.ウォルフィンガー、ジョン・コムストック、そして後にニューヨークでケーブル・ピアノ・カンパニーを
設立したハーマン・ケーブルの3人がシカゴの会社の元々のオーナーであったが、
1885年にコムストックがE.E.ワイズとジョージ・テュークスベリーに株式を売却した。
この時、社名を「シカゴ・コテージ・オルガン・カンパニー」と正式に変更した。
最盛期にはピアノを年間16,000台、オルガンを年間18,000台ほど生産していたが、
その需要に応えるために、シカゴにいくつかの工場や事務所を開設したのである。
1900年代初頭にシカゴ・コテージ・オルガン社の名前は消え、ケーブル・ピアノ社として知られるようになった。
残念ながら、シカゴ・コテージ・オルガンの楽器が出す音や音色については、ほとんど情報がない。
買収されて製造方法のほとんどが変更されるまでの短い期間に製造された様々なモデルやタイプについても、
会社の記録にはほとんど見られない。
また、シカゴ・コテージ・オルガンの音の特徴、音色、音響特性についての歴史的な記述は非常に少ない。
このような愛すべきオルガンの所有者の中には、その価値を証言してくれる人もいるが、
多くの古い、あまり知られていないブランドと同様に、そのような情報の多くは過去に失われてしまっている。 |
| CHICKERING, JACOB |
詳細不明 |
| CHICKERING & MACKAYS |
詳細不明 |
CHICKERING & SONS

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
チッカリング・アンド・サンズ アメリカ(ボストン)
ボストンとニューヨークにコンサートホールを所有・運営
CHICKERING & SONS
創業1823年。エオリアン・アメリカン・コーポレーション傘下の系列会社の製品。
※エオリアン(AEOLIAN)の項目も参照
チッカリングは19世紀中盤は一流のメーカーとして君臨していたのは皆様ご存知だと思います。
なんといってもチッカリングを有名にしたのは、現代のピアノを決定づけたといってもよい、
鉄のフレームの特許をとっていることです。
1867年にはパリの世界博覧会で金メダルもとっています。
この金メダルをとったピアノもリストに献呈され、リスト・アカデミーの院長室にあるようです。
リストは贈呈されたチッカリングのピアノが運ばれてきたとき、大感激して2時間も弾きつづけたという。
<歴史>
1823年、ピアノ製作者ジョン・オスボンの弟子として働いていたジョナス・チッカリングが
同僚であったスコットランド人と共同でボストンに工房を開いてスクエア・ピアノの製作を開始。
1830年、イギリスのブックケースタイプと呼ばれる楽器をモデルにして最初のアップライトを製作。
その後事業拡大のため実業家のジョン・マッケイと組み、工場の名称もチッカリング・アンド・マッケイと改め、
スポンサーを得たチッカリングはピアノの製作と研究に専念する。1840年にはグランドピアノも完成。
総鉄骨が採用されたこのグランドピアノは特許を取得しアメリカにおけるピアノ製造の基礎を築いた。
<附録>
チッカリングピアノ 製造番号/製造年代 対照表(1850年~1980年) →★
<以下、ウィキペディアより引用抜粋>
チッカリング&サンズ(Chickering & Sons)は、アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストンに所在した
ピアノ製造会社であり、優れた品質と設計の楽器の生産で知られていた。
1823年にジョナス・チッカリングとJames Stewartによって「Stewart & Chickering」が創業されたが、
4年後にこの協力関係は解消した。1830年までにジョナス・チッカリングはジョン・マッケイと共同経営者となり、
「Chickering & Company」、後には「Chickering & Mackays」としてピアノを製造した。
1841年に老Mackayが死去し、1853年に会社は「チッカリング&サンズ」として再編された。
チッカリングブランドのピアノは1983年まで作られ続けた。
ピアノ製作者ジョン・オスボンの弟子として働いていたジョナス・チッカリングが1823年、
同僚であったスコットランド人と共同でボストンに工房を開いてスクエア・ピアノの製作を開始した。
1830年、イギリスのブックケースタイプと呼ばれる楽器をモデルにして最初のアップライトピアノを完成した。
その後事業拡大のため実業家のジョン・マッケイと組み、工場の名称もチッカリング・アンド・マッケイと改め、
スポンサーを得たチッカリングはピアノの製作と研究に専念した。1840年にはグランドピアノを完成。
総鉄骨が採用されたこのグランドピアノは特許を取得しアメリカにおける
ピアノ製造の基礎を築いたといわれている。
1841年に事業を担当していたジョン・マッケイが船で遭難し行方不明となってしまい、このためチッカリングは
経営事業にも直接携わるようになった。ロンドンでピアノメーカーの最高の栄誉賞を受けるなど
ピアノ事業は順調だったが1852年、不幸にもピアノ工場が火災に遭い全焼してしまった。
新工場の再建に着手するも、創業者のジョナス・チッカリングは
1853年でこの世を去った。その頃、工場はチッカリング・アンド・サンズと名称を改めており、
チッカリング社のピアノ製造事業は、ジョナスの長男であるトーマス・E・チッカリングが引き継いだ。
トーマスは商才にたけた人物で、将来を期待されていたが若くして死去した。
トーマスの死後はジョナスの次男であるC・フランク・チッカリングが事業を引き継いだ。
1867年、パリ万博覧会にピアノを出品して最優秀賞を獲得したが、その数日後、フランク・チッカリングは
当時のフランスの皇帝であったナポレオン3世に拝謁を仰せつかるという栄誉を受け、
音楽芸術に対する貢献として十字勲章を授けられた。
この頃、ヨーロッパにはピアニストとして名をはせていたフランツ・リストがおり、
チッカリングはリストが滞在していたローマまでピアノを届けている。
チッカリングが製作したピアノが運ばれてきたときリストは感激して2時間弾き続けたという。
また「今日、私はリストの壮麗な音のチッカリングを弾いた」と手紙に記している。
1891年にフランク・チッカリングはニューヨークで死去したが、チッカリング社は1904年に
クォーターグランドピアノと呼ばれる当時世界最小のピアノを製作した。
1909年以降チッカリング社はエオリアン・アメリカン・カンパニーに吸収され、
チッカリング一族は経営から姿を消した。
<チッカリング史 時系列解説>
チッカリング&サンズ社は、1823年にジョナス・チッカリングとパートナーのジェームス・スチュワートによって
ボストンに設立された、アメリカで最も初期のピアノメーカーのひとつである。
この会社の初期の歴史は、何度もビジネスパートナーや社名が変更されたことが特徴である。
<以下、チッカリング年表>
1823年 -
ジョナス・チッカリングがパートナーのジェームス・スチュワートとともに
「スチュワート&チッカリング」を設立
1827年 -
チッカリングとスチュワートの提がを解消
1830年 -
チッカリングが船長のジョン・マッケイと提携し、ピアノの材料を南米から調達
1839年 -
ジョン・マッケイの息子ウィリアム・マッケイが提携し、
「チッカリング&マッケイ」という新しい名前でピアノを製造。
1841年 -
チッカリング社とマッケイ家の提携が解消。
この短い期間に「チッカリング&マッケイ」として製造されたピアノは、
現在では非常に珍しく、貴重なものとなっている。
1852年 -
チッカリングの息子のジョージ、フランク、トーマスが提携し、
「チッカリング&サンズ」が新しい会社名となる。
1853年 -
ジョナス・チッカリングが亡くなり、息子たちがビジネスを継続。
1908年 -
「チッカリング&サンズ」がアメリカ・ピアノ・カンパニーに売却され、
チッカリング・ピアノの製造を継続。
1932年 -
アメリカ・ピアノ・カンパニーとエオリアン・ピアノ・カンパニーが合併し、
チッカリングピアノの生産を継続。
1985年 -
エオリアン・アメリカン・ピアノ社が廃業し、チッカリングピアノブランドの生産が終了。
<チッカリング&サンズのピアノ技術>
チッカリング&サンズ社は、19世紀を代表するピアノブランドとして、その品質の高さと、
グランドピアノの技術にいくつかの重要な進歩をもたらしたことで知られています。
特にジョナス・チッカリングは、現在のすべてのピアノに標準装備されている1枚の鋳鉄製プレートを
ピアノに追加した。この鉄製フレームは、グランドピアノの高い弦の張力を支えるのに大変役立った。
さらにチッカリングは、スクエアピアノの省スペース化のために、弦を重ねるという新しい弦の張り方を
発明したことでも知られている。これらの功績により、チッカリング&サンズ社は、
1867年に音楽への貢献が認められ、皇帝ナポレオン3世から
レジオン・ドヌール勲章をはじめとする多くの賞を受賞。
1900年代初頭にスタインウェイが台頭してくるまで、チッカリングピアノは当時のコンサートピアノとして
好まれていた。チッカリング社は、自社の職人技とピアノの品質をアピールするために、
ボストンとニューヨークにコンサートホールを所有・運営していた。
実際、リンカーンはホワイトハウスにチッカリングのピアノを数台持ち込み、大統領一家が愛用していた。 |
| CHICKERING BROS. |
詳細不明 |
CHIYODA
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
チヨダ 千代田楽器製造所 戦前にあったブランド |
| CHOLLARD |
詳細不明 |
| CHOLLARD & CHOLLARD |
詳細不明 |
CHOPIN

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ショパン
製造元:三高アクション製作所(浜松市薬師町763番地)、及川ピアノ製作所(浜松市)
発売元:三浦ピアノ店(文京区東大前)
WALDSTEIN ワールドシュタイン(バルトシュタイン)の項目も参照。
戦前から東京文京区東大前の三浦ピアノ店を代理店として売り出された。
ワールドシュタイン(バルトシュタイン)も同様に売り出されていた。
|
| CHRISTENSEN |
詳細不明 |
| CHRISTOFORI |
詳細不明 CRISTOFORIとは違うのか? |
| CHRISTMAN |
詳細不明 |
| CHU-SENG |
詳細不明 |
CIAIKOVSKY

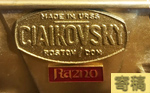

画像クリックでHPへ戻る |
CIAIKOVSKY
チャイコフスキー ロシア(ソ連製USSR) RAZNO製造
フレームのロゴにはRazno(ラズノ)と書いてあります。いろいろな楽器を作っていた会社のようです。
(ベリョースカやウラジミールなど)
このメーカーの外装(突き板)はひどく剥がれてきます。
何台か調律したことがありますが、外装、アクション、音色含めかなり酷い作りのピアノで苦労しました。。
※ちなみにあの有名な音楽家であるチャイコフスキーの正しいスペルは、TCHAIKOVSKYです。
スペルは、「CHAIKOVSKY」や「TCHAIKOVSKY」ではないので注意。
※CHAIKOVSKY(チャイコフスキー)というブランド名で日本国内でも
製造販売されていたピアノが存在するようですが、詳細不明。その銘柄ブランドマーク →★ |
CITY LIFE


画像クリックでHPへ戻る |
CITY LIFE シティー・ライフ 株式会社河合楽器製造所
カワイが作った廉価版小型ピアノ。
ピアノの各所を細かく見ますと、鍵盤が1枚板からではなく、中央部分で継いである
2枚の接ぎ合わせ板を使用していたり、フェルトブッシングの代わりに段ボールのような硬い紙を使っていたり、
アクション部品を新たに開発した新素材(プラスチック等)に変更したりしています。
「シティーライフ」という名称からも分かるように、都会の団地向けの小型軽量ピアノという位置づけで
河合楽器が開発したとも言われています。小型ということもあり、出せる音量は控えめな感じがします。
シティーライフのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★ |
CLAIR

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
クレール 有限会社クレールピアノ製作所
東京蒲田楽器製作所の創始者である斉藤喜一郎氏が戦後、
横浜に(有)クレールピアノ製作所を設立して製作したピアノ。
現在のウイスタリア・ピアノ製作所
<ウィスタリア・ピアノ歴史(抜粋)>
1924年、創立者斉藤喜一郎は1920年から23年までピアノ製作技術研究のためドイツに留学、
帰国後東京蒲田楽器製作所を設立し、「ブッフホルツ」および「ホルーゲル/ホリューゲル」を製作する。
戦後、横浜に(有)クレールピアノ製作所を設立。西ドイツピアノ製作業界視察のため再渡欧、
特にグロトリアン・スタインウェッヒピアノ会社の親交を得てピアノ製作技術の指導を受ける。
1956年、製作者の紋章に象り、ウィスタリア・ピアノ製作所と改称。 |
| CLARENDON PIANO CO |
アメリカ(イリノイ州ロックフォード/ROCKFORD ILL.)
その他詳細不明 |
| CLARK MELVILLE |
詳細不明 |
| CLASSENTI |
詳細不明 |
| CLASSIC |
詳細不明 |
CLEA
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
クリア 有限会社クリア商会 |
CLEAR
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
クリアー 株式会社 井上楽器製作所 |
CLEMENT
CLÉMENT
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
クレマン 韓国 SAUJIN 詳細不明
CLEMENT/CLÉMENTのまくり(蓋部分)の銘柄ブランドマーク →★
※SAUJINの項目も参照 |
| CLEMENTI |
詳細不明 |
| CLINE |
詳細不明 |
COBLENZ
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
Königl. Hof-Pianofabrik 詳細不明 |
| COCKUIJT |
詳細不明 |
COLLARD & COLLARD

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
コラード・アンド・コラード イギリス(ロンドン) 詳細不明
<以下、ウィキペディアより引用抜粋>
コラード&コラード(Collard & Collard)は、かつて存在したロンドンに拠点とする
有名なアップライトピアノおよびグランドピアノ製造業者である。
社名は2人の兄弟フレデリック・ウィリアム・コラードとウィリアム・フレデリック・コラードに由来する。
1767年、ロンドン・チープサイド通り26番地に音楽販売および製造業者である
Longman & Broderipが設立された。
Longman & Broderipが販売する楽器は、ピアノメーカーのGeib and Guilfordが製造した。
現在知られている最も古いLongman & Broderipの楽器は1770年製の5オクターブの
スクエア・ピアノであり、ボストンの博物館に展示されている。
Longmanの共同経営者は何度か変わり、社名は1771年にはLongman & Lukey、
1774年にはLongman, Lukey & Comp. と呼ばれていた。
1778年に作曲家でピアノ教師のムツィオ・クレメンティが会社に加わり、
会社はLongman & Clementiとなった。
クレメンティの後の共同経営者の一人が木製家具職人のフレデリック・コラードであった。
コラードは楽器製作者として、特に響板の専門家として需要があった。
クレメンティが販売を担当したのに対して、コラードはピアノ生産に責任を持つようになった。
クレメンティは非常に保守的であり、ピアノ製造における革新に反対していた。
ウィリアムとサモシン・コラードの息子フレデリック・ウィリアム・コラードは、
1772年6月21日にサマセット州ウィベリスクームで洗礼を受けた。
14歳の時にロンドンへ移り、Longman, Lukey & Broderipに雇われた。
弟で共同経営者のウィリアム・フレデリック・コラードは、1776年8月25日にウィベリスクームで
洗礼を受けた。ピアノ製造技師および発明家としての才能に加えて、彼は詩や文学にも情熱を持っていた。
1799年、Longman & Co. は経営難に陥り、John Longman、ムツィオ・クレメンティ、
Frederick Augustus Hyde、フレデリック・W・コラード、Josiah Banger、
およびDavid Davisの新会社が事業を引き継いだ。
1800年6月28日、LongmanとHydeが引退し、会社はMuzio Clementi & Co. となった。
しばらくした後、弟のウィリアム・F・コラードが共同経営者として加わった。
1817年6月24日、Bangerが共同経営を下りた。
1831年6月24日、F・W・コラード、W・F・コラード、クレメンティの間の共同経営が終了した。
コラード兄弟は弟のW・F・コラードが引退する1842年6月24日まで事業を継続し、
F・W・コラードが単独の経営者となり、彼の2人の甥フレデリック・ウィリアム・コラードJr. と
チャールズ・ルーキー・コラードが共同経営に加わった。
1832年の後、長年クレメンティの名前で販売されていたピアノのブランドが
「コラード&コラード」と命名された。
多くの特許が取られ、主に演奏機構とフレームシステムの改良が含まれた。
会社はすぐに音楽出版を中止し、ピアノ製造に集中した。
例外として、彼らは1858年までイギリス東インド会社向けのラッパ、横笛、太鼓の製造も行なった
(1858年にインドの統治権がヴィクトリア女王に譲渡され、東インド会社は解散した)
コラードは1851年のロンドン万国博覧会にグランドピアノを出品した。
会社は2度の大火にあった。1807年3月20日、トテナム・コート・ロードにあった工場が全焼した。
1851年12月10日、カムデン・タウン、オーバル・ロードに新たに建設された工場が全壊した。
弟のウィリアム・フレデリック・コラードは1842年にピアノ製造業から引退し、
1866年10月11日にフォークストーンで死去した。
兄のフレデリック・ウィリアム・コラードは1860年1月31日にチープサイド通り26の自宅で88歳で死去した。
彼は1786年にロンドンに着いてからずっと同じ住所に居住した。
より多くのドイツのピアノメーカーがイギリスの市場で成功し始めたため、コラード&コラードは
1900年からイングランドにおけるピアノ製造の落ち込みに巻き込まれた。
1929年、コラード社はチャペル& Co.に買収された。
1963年の火災でコラードとクレメンティの全ての記録が失われた。
1980年、チャペルのピアノ製造および小売事業はケンブル&カンパニー(Kemble & Company)に売却された。 |
| COLBY |
詳細不明 |
| COLONIAL |
詳細不明 |
COLONIET
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
コロニエット
WESER BROTHERSが製造していたブランド
→詳しくはWESER BROTHERSの項目へ |
COLORATURA


画像クリックでHPへ戻る |
コロラトゥーラ
製造元:HAILUN楽器(中国) 出荷最終調整:アサヒピアノ(中国人社長、浜松)
ピアノ線(ミュージックワイヤー)は、レスロー弦を使用しているとのこと。
ピアノ自体のの雰囲気や作り、製造&販売背景が私がよく調律する
「ウエンドル・アンド・ラング」というピアノによく似ています。
ピアノの音色はまだ実際に聴いたことがないので感想はまだ書けませんが、
今後、調律する機会があればここに感想をアップさせていただきます。
<参考>
コロラトゥーラとは、クラシック音楽の歌曲やオペラにおいて、速いフレーズの中に装飾を施し、
華やかにしている音節のこと。具体的にはトリルが多用される。
これが使われている曲の中で特に有名なものとしては、モーツァルトの歌劇『魔笛』における
第2幕の夜の女王によるアリア「復讐の炎は地獄のように我が心に燃え」がある。
<ハイルンピアノ詳細:Wikipediaより引用抜粋>
海倫鋼琴(かいりんこうきん、ハイルンピアノ、Hailun Piano Co., Ltd.、SZSE: 300329)
股份有限公司は、中華人民共和国のピアノメーカーである。
2001年に陳海倫(董事長兼CEO)によって寧波市において寧波海倫楽器製品有限公司として設立された。
アップライトピアノおよびグランドピアノの製造と販売を世界的に展開している。
同社が製造している主要ブランドはPETROF(ペトロフ)、ROSS、
WENDL & LUNG(ウェンドル・アンド・ラング)、ZIMMERMANN(ツィンマーマン)、
FEURICH(フォイリッヒ)である。
株式は2012年6月19日に深圳証券取引所に上場された。
買収価格は21人民元、1,677万株が発行され、募集額は3億5000万人民元であった。
ハイルンピアノ公式HP:http://www.hailunpiano.com/ |
COLTOT
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
コルトー 販売:内外ピアノ社(東京千代田区神田神保町1-1) 詳細不明 |
CONCERT
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
コンサート 羽衣楽器製造(株)浜松市 詳細不明
|
| CONN |
キンボール社(KIMBALL)が取り扱ったブランド
→詳しくはKimballの項目へ |
CONOVER
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
コノーバー/(コノバー) ケーブルピアノ社製(アメリカ・オレゴン州)
生涯をかけて音の研究に没頭したJ.フランク・コノーバーが作り出した最高級品質のピアノとのこと
この下の「CONOVER CABLE」と同一のピアノか?不明 |
CONOVER CABLE
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
1880年、ミズーリ州カンザスシティにコノバー社が設立された。
1890年には、コノバー社とケーブル社が合併し、コノバー・ケーブル社が設立された。
1890年にコノバー社とケーブル社が合併し、コノバー・ケーブル社が誕生した。
この合併は、両社の歴史の中で重要な時期であり、その後のピアノの生産に大きな影響を与えた。
合併後すぐにシラー・ピアノ社を買収。
コノーバーとシラーのピアノブランドのモデルは、同社の最高価格帯のピアノであった。
1904年になると、The Conover Cable CompanyはMason and Hamlin Piano Co.を
倒産から救う機会を得て、新しい支店を開設した。
この時点で、コノバー・ケーブル社は、メイソンとハムリンの販売店も手に入れた。
結局、コノバー・ケーブル社は、エオリアン・コーポレーションに買収される
20世紀初頭の多くのピアノメーカーと一緒になった。
この上の「CONOVER」と同一のピアノか?不明 |
CONSERVATOIRE
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
コンセルバトワール Conservatoire アトラスピアノが国立音大の楽器研究室で作っていたブランド
※詳しくはアトラスの項を参照
|
| CONSOLAT DE MAR |
詳細不明 |
| CONTINENTAL |
詳細不明 |
CONSOLE
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
コンソール 日本 村瀬克己氏 詳細不明
|
| CONWAY |
詳細不明 |
CORBERT
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
コルベール 日本 小出一三氏 詳細不明
|
| CORNISH |
詳細不明 |
COSMOPOLITAN
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
コスモポリタン 日本 詳細不明
|
COSMOS

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
コスモス
大倉楽器工業(株)東京都杉並区上高井戸
二本弦の小型ピアノが多かったが、大型のものは音色に特色があった。
その他にも違うブランドでピアノを製造していたとの記録あり。
|
| COSMOS HARVARD |
コスモス・ハーバード 大倉楽器工業株式会社 |
| COSMOS NOBEL |
コスモス・ノーベル 大倉楽器工業株式会社 |
| COSMOS PRINCETON |
コスモス・プリンストン 大倉楽器工業株式会社 |
| COSMOS ROYAL |
コスモス・ロイヤル 大倉楽器工業株式会社 |
COTTIER
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
Cable Nelso(ケーブル・ネルソン)n社が製作していたブランド
→詳しくはCable Nelsonの項目へ |
| COTTO |
詳細不明 |
COWBELL

画像クリックでHPへ戻る |
COWBELL カウベル
レスターピアノ製造が作っていたピアノのようですが、詳細不明
※レスターピアノ製造株式会社についての詳しくは→LESTERの項目へ
<参考>
カウベル(英: cowbell)とは、牛 (cow) などの放牧してるような家畜の首に付け、
見失わないようにするための金属製の鐘鈴 (bell) のことです。 |
CRAMER

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
J.B.Cramer クラーマー/(クラマー)
イギリス(ロンドン)
<以下、ウィキペディアより引用抜粋>
J・B・クラーマー& Co.(J. B. Cramer & Co.)はロンドンにかつて存在した楽器製造、楽譜出版、
音楽販売業者である。1824年にヨハン・バプティスト・クラーマーによって創業された。
ボンド・ストリートにあった建物は1964年に会社がケンブル& Co.に買収された時に閉鎖された。
1824年に音楽家のヨハン・バプティスト・クラーマーとRobert Addison、Thomas Frederick Bealeによって
共同で創業され、「Cramer, Addison & Beale」と呼ばれていた。
ヨハン・バプティスト・クラーマーは1833年末に事業への関与をやめ、
1844年にAddisonはBealeとの協力関係を解消してRobert Hodsonとの事業を始めた。
Robert Hodsonは以前ルイス・ヘンリー・ラベニューと協力関係にあった人物で、
AddisonとHodsonはコンデュイット・ストリートの反対側のリージェント・ストリート210番地にあった
Cramer & Co.の道路の向こう側に「Addison & Hodson」を設立した。
Cramer & Co. 社はその後Cramer, Beale & Co. と呼ばれた。
次にウィリアム・チャペルがBaeleの事業に加わったが、1847年に関係を解消し、
事業はThomas Bealeによって行った。
チャペルは再び事業に加わったが、最終的に1861年に引退した。
当時「Cramer, Beale & Chappell」という名称が出版物上で使用された。
1862年、George WoodがBaeleとの事業に加わり、その期間は「Cramer, Beale & Wood」という
名称が使われた。1864年までに、Baeleは会社を離れ、名称は「Cramer, Wood, & Co.」に変わった。
主な店舗はリージェント・ストリート201番地、コンデュイット・ストリート67番地、
コンデュイット・ストリートとリージェント・ストリートの角にあった。
この住所は1820年代から1890年代までこの会社との結び付きがあった。1873年に会社は
「Cramer's Great City Warehouse」または「Cramer's City Warerooms」と呼ばれた展示場を開業した。
(最初はムーアゲート・ストリート43から46番地、後に40から42番地にも拡大した)
1896年から1901年に主要な店舗はリージェント・ストリート207および209番地に移転し、
その後1902年までにオックスフォード・ストリート126番地に移った。
1912年、主要店舗はニューボンド・ストリート139番地に移され、
1964年にピアノ製造会社ケンブル& Co.に買収されるまでここで営業を続けた。
ケンブルは限られた期間「J. B. Cramer & Co.」ブランドを使い続けた。 |
| CRANE & SONS |
イギリス CRANE & SONS, LTD. 詳細不明 |
CRANES
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
鍵盤蓋にEst 1851とあるので、1851年設立?
トレードマークは2種類あるようですが、その中の1つがREID-SOHN、KAFMANN、SAMICK、
SCHNABEL、WEINBURGなどと同じマークなので商標権を獲得した韓国メーカーが現在製造?
詳細不明 |
CREABEL
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
クリーベル
販売:協立楽器 製造:大成ピアノ製造株式会社
※注:他にもクリーベルという名称のピアノあり |
CRISTOFORI
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
クリストフォーリー(クリストフォリ) 発売元:三協ピアノ株式会社(浜松市) 詳細不明
|
CRISTOFORI


画像クリックでHPへ戻る |
CRISTOFORI クリストフォリ
製造元:大成ピアノ製造株式会社
発売元:株式会社 渡辺商店
その他詳細不明 |
|
CRISTOFORI


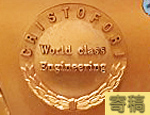
画像クリックでHPへ戻る
|
CRISTOFORI クリストフォリ
製造元、発売元:東洋ピアノ製造株式会社
製造国:インドネシア→最終調整:日本
18世紀にピアノを発明したとされるイタリアのBartolomeo Cristoforiにちなんで
命名されたクリストフォリシリーズ。
家具調のRU-118と木目調ピアノのスタンダードなデザインのRU-121など。
CR-110、CR-121、C-126などもあり。
鍵盤押さえ部分には「TOYO PIANO MFG. CO:LTD」というシールが貼られております。
トレードマーク画像は「匿名希望様」からご寄稿頂きました。ありがとうございます! |
CROWN



画像クリックでHPへ戻る |
CROWN クラウン アメリカ(シカゴ)
1870年設立 ジョージ・P・ベントピアノカンパニー
4本ペダルが特徴でチェンバロ風に音色を変えられるとのこと。
<クラウンピアノの歴史>
1870年に設立された「クラウン」ピアノは、当初あまり知られていないピアノ名であったが、
ジョージ・P・ベント・ピアノ・カンパニーによって製造されたもので、名誉あるピアノ会社に成長した。
しかし、世界大恐慌により1929年頃にジョージ・P・ベント社がピアノの製造を中止したため、
クラウンピアノは製造中止となったが、Crownのブランド名で1940年代後半まで別会社で生産されていた。
ジョージ・P・ベントは「クラウン」ブランドのオルガンも生産しており、
20世紀末にはシアーズ・ローバック・アンド・カンパニーが限定的に販売・流通していた。
ブランド名は他に「Concord」というブランドも製造していた。
The Geo. ベント社は現在、ケンタッキー州ルイビルのアドラー社が所有しており、
アドラー社は「クラウン」ピアノを製造している。
世紀末のクラウンピアノの代表的な革新技術は、「オーケストラ・アタッチメント」と
「練習用クラヴィーア」で、これらはいずれもフットペダルの操作でコントロールできる特別な機能だった。
クラウンは、他の近代的なピアノメーカーではあまり採用されなかったユニークな機能であり、
今でもリンデブラードの店頭で見かけることがありますが、斬新なものでした。
クラウン・コンビノーラピアノは88音というフルスケールを演奏し、チューブは柔軟性のある金属製で、
シルクで覆われており、当時の広告によれば、一生使えるという。
CROWN COMBINOLAの4本ペダル部分 →★ CROWNピアノの全体写真 →★
ピアノの蓋にあるブランド名の部分 →★ ※当時輸入元だった十字屋楽器店のプレートが貼ってあります
鉄骨右側にある文字部分の拡大写真 →★ 製造番号の部分 →★
これらの画像はすべて「匿名希望様」からご寄稿頂きました。たくさんの画像をありがとうございました! |
| CUIJPERS, J.F. |
詳細不明 |
CUNNINGHAM
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
CUNNINGHAM PIANO COMPANY カニンガム/(カニングハム) 創業1891年
ピアノのまくり(蓋の部分)には「CUNNINGHAM PHILADELPHIA USA」と書いてあります。
パトリック・カニンガムは、1891年にカニンガム・ピアノ・カンパニーを設立した。
ペンシルバニア州フィラデルフィアの工場では、カニンガムの名を冠したピアノのほか、
ジラード、フォレスト、ペインター&ユーイングのピアノも製造していた。
1924年には、オーバーブルック・ピアノ・カンパニーを買収し、会社は再び成長しました。
2008年に父親から会社を受け継いだローズ・カーとドリス・レーバー姉妹が会社を売却するまで、
会社は何世代にもわたって受け継がれてきました。
ティム・オリバーとリチャード・ガラッシーニという2人の男性が、カニンガム・ピアノ・カンパニーを買い取り、
100年以上ぶりに家族経営ではなくなったのです。
しかし、ティムとリチャードの下で、カニンガムピアノは繁栄した。
2人は、同社の最も人気のあるモデルであるマッチレス・カニンガムを再導入し、
第二次世界大戦前の設計図に基づいてデザインやスケールを更新して新たな命を吹き込んだ。
現在、カニンガム・ピアノ・カンパニーはフィラデルフィアにオフィスを構えているが、
マッチレス・カニンガム・ピアノ・シリーズは中国で製造されている。
世界大戦、不況、音楽産業の近代化などを乗り越えて、カニンガム・ピアノ・カンパニーが存続しているのは
非常に珍しいことで、人気と品質の高さを物語っていると言えるだろう。 |
CURRIER

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
キュリエール CURRIER アメリカ
インターナショナル・ミュージカル・インストゥルメント社
会社名はやや大げさな名前ですが、大衆的なピアノを作る会社で、
工場はノースカロライナにあり、アメリカのピアノ工場としては
10本の指に数えられるほどの大規模な工場です。
ハワイ州、アラスカ州を含むアメリカ50州すべてに代理店を持ち、
ヨーロッパ、南米、カナダ、カリブ海諸島などにも輸出されています。
この会社は歴史こそありませんが、スピネットの小型のものから
一般的なアップライト、そしてグランドにいたるまでその種類は
極めて多く、さらに会社の中に独自の配送部門も持ち。全米各地へ
工場から自社のトラックで輸送が可能だそう。
伝統的な品質を誇るというよりは、販売力で勝負しようとする会社といえよう。
ボストンで同じ名前のキュリエール(CURRIER)というピアノが
作られているが、これとは全く無関係です。
こちらのキュリエール社は100年以上の歴史を持つ有名なピアノメーカーです。
|
CURRIER

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
アメリカ ボストン
100年以上の歴史を持つ有名なピアノメーカーです。上記キュリエールとはまったく別の会社です。
|
| CURRIER & GILBERT |
詳細不明 |
| CZAPKA & SOHN |
詳細不明 |
CZERNY
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
あのピアノ練習曲を数多く残したことで有名なチェルニーの正しいスペルは”CZERNY”ですが、
東洋楽器製造株式会社が作っていたピアノ、ツェルニーのスペルは”CHERNY”です。
→この上方、CHERNYの項目へ |
CZERNY
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
チェルニー ロシア(ソ連) 詳細不明 |
上記Cから始まるブランドの中で、追記出来そうな事項や新情報を発見した場合、修正受付フォーム よりお気軽にお知らせ下さい。
どんな些細な情報でも構いませんので、広く皆様からのフィードバックをお待ちしております。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
 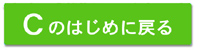 



上記Dから始まるブランドの中で、追記出来そうな事項や新情報を発見した場合、修正受付フォーム よりお気軽にお知らせ下さい。
どんな些細な情報でも構いませんので、広く皆様からのフィードバックをお待ちしております。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
 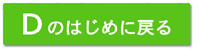 



上記Eから始まるブランドの中で、追記出来そうな事項や新情報を発見した場合、修正受付フォーム よりお気軽にお知らせ下さい。
どんな些細な情報でも構いませんので、広く皆様からのフィードバックをお待ちしております。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
 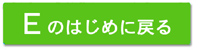 



ピアノ銘柄ブランド
トレードマーク 紹介
& 知名度ランキング

|

メーカー/ブランド説明・会社沿革・歴史・製作者・特徴・音色・他
|
| F. BACH |
詳細不明 |
F. CHOPIN
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
エフ.ショパン 日本 戦前のブランド 詳細不明
|
| F. DÖRNER & SOHN |
詳細不明 |
F. QUANTE
F. QUANTÉ
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
エフ・クウォンテ フランス(パリ) 詳細不明
スペルはQUANPÉ(QUANPE)ではなく、QUANTÉ(QUANTE)です。
まくり(蓋部分)にある銘柄文字の「T」の部分が「P」に見えます。 |
| F. ROSENER |
詳細不明 |
| FABBRINI |
詳細不明 |
FAHR ALBERT
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ドイツ 読み方不明(ファール・アルバート?、ファー・アルバート?) 詳細不明
|
FALCONE

画像クリックでHPへ戻る |
ファルコーネ 中国 詳細不明
下記、ピアノディスク社が所有していた本場ファルコーネとは違います。
中国の企業が商標を買い取ったのか?不明
このブランドに限らず、中国の企業は世界中の有名ピアノ企業の商標をたくさん買い取っています。
機種バリエーション:CF12等
画像は「匿名希望様」からご寄稿頂きました。ありがとうございます! |
FALCONE

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ファルコーネ Falcone Piano Company
現所有:ピアノディスク社
この会社はイタリア出身のピアノ技術者サンティ・ファルコーネによって1984年に設立された。
ファルコーネの目標は、世界トップレベル品質のグランドピアノを手頃な価格で提供することだった。
ファルコーネは1978年に、成功していた小売店チェーンを売却し、ピアノ製作の実験をスタートさせた。
ボストンの投資家と技術者を集め、1982年に長さ183cmの最初のグランドピアノを作り上げ、
その翌年には、274cmのコンサートグランドを完成させた。
1984年、ファルコーネ社は11人の技術者を雇い、月にわずか2台のピアノを製作した。
1987年には40人が月に5台製作するようになり、会社はマサチューセッツの古い靴工場を買って、
最上階をコンサートホールに改造した。
1989年、ファルコーネ社は、ゾーマー・アンド・カンパニーを買収。
買収されたゾーマー・アンド・カンパニーはすでにメイソン・アンド・ハムリンのブランド名を所有していたため、
ファルコーネ社はゾーマー(SOHMER)のブランド名も取得した。
サンティ・ファルコーネは1991年に会社を実業家のバーナード・グリアに売却し、
ファルコーネのブランド名はメイソン・アンド・ハムリン・カンパニーに取り込まれた。
1994年、メイソン・アンド・ハムリン社の倒産に伴い、ファルコーネ・ピアノの生産は終了。
その後、1996年にピアノディスク社がメイソン・アンド・ハムリン社を買い取り、
このファルコーネのブランドも所有している。
今のところ、このファルコーネというブランドでピアノ製造が再開される予定はない。
<特徴>
ファルコーネ社は、「サウンドボード・キャリブレーター」という響板の調整装置の特許を取得した。
これは響板の張力を調整でき、ピアノの音色を変化させられるというものである。
ファルコーネ社はグランドサイズで、9ft、7ft 4in、6ft 1inの3種類のピアノを生産。
これより小さなピアノは手作り楽器としての良さを失うと信じており、小さなピアノは生産しなかった。
ファルコーネピアノの音質は、全音域を通してどのようなダイナミクスで弾いても、豊かで均一であると、
ジャズ界やクラシック界の有名ピアニストの多くが認めている。
※その他、MASON & HAMLINや、SOHMERの項目も参照 |
FAMILY
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ファミリー 東海楽器製造株式会社 |
FAMILY
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ファミリー 東和楽器木業股份有限公司
日本の河合楽器製作所との技術提携のメーカー。社長は陳文聰氏。
工場は桃園県大渓にあって従業員数は最盛期で500人を超えたこともあり、
ピアノ工場としてはかなりの規模。
ブランドはKAWAIという名称も使っていたが、アップライトの一部には
FAMILYというブランドも開発していた。 |
| FANDRICH |
詳細不明 |
| FANDRICH & SONS |
詳細不明 |
| FANTAGIA |
ファンタジア 河合楽器が一時期出していたピアノの愛称(ブランド名ではない) |
| FARFISA |
詳細不明 |
| FARRAND |
詳細不明 |
FAUTH
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
フォース 日本 戦前のブランド ※ドイツ製アクションに同名のものがあるが詳細不明 |
| FAYETTE S. CABLE |
詳細不明 |
FAZER
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ファツェル フィンランド 詳細不明
HELLASは1989年、このFAZERも買収し、
フィンランド国営企業として2つのブランドのピアノを製造。
ピアノ背面に一般的にある支柱(バックポストと言います)がないのが特徴。
鉄骨のみで弦の張力を支えています。 |
| FAZER MUSIK |
詳細不明 |
|
FAZIOLI




画像クリックでHPへ戻る
|
ファツィオリ イタリア
住所:Via Ronche 47, 33077 サチーレ(サチレ) 設立:1981年
1981年のフランクフルト・ミュージック・フェアに於いて、それまで誰も知らなかったイタリアのメーカーが、
新しい設計の4台のピアノをお披露目した。
そのわずか20年後、ファツィオリ・ピアノは、世界最高のピアノメーカーの候補として自ら名乗りを上げた。
ファツィオリ・ピアノは豊かな音色で、音とタッチが均一であり、フルオーケストラと協演しても
耳障りな音にならずによく通る響きを持っている。
ファツィオリはグランドピアノのみ製作され、すべて手仕事生産である。
全長308cmのグランドは、現在入手可能なコンサートグランドピアノの中で最大。
そのピアノには4本目のペダルがあり、踏むとハンマ―が弦に接近して音が弱くなるが、
ウナコルダペダルのように音色を変化させることはない。
ファツィオリ・ピアノは、ふたつのアクションとペダルリラをセットで購入することも可能で、
演奏者は好きなときにボイシングの異なるアクションに取り換えることができるのが特徴。
響板に使用される木材は一般的なスプルースではなく、
イタリアのフィエンメ渓谷から伐採された赤トウヒが使用されている。
<広告より>
1981年ピアニストでありエンジニアであるPaolo Fazioli (パオロ・ファツィオリ) 氏によって設立、
グランドピアノのみを少数生産しています。
ヴェネチアの北東60kmに位置する木工産業で有名なSacile (サチーレ) に工房を構え、
素材選びに始まり細部の仕上げにまで徹底したこだわりを持ち、ハンドメイドを追求するため、
生産数は年間数100台程のみ。
また、出来上がった全てのピアノを社長パオロ自ら試弾してチェックするという
徹底したこだわりによって、"名誉あるピアノ" が生み出されているのです。
<歴史>
機械工学の知識と、ぺサロの音楽院でディプロマを取得したほどのピアノ演奏技術とを
合わせ持つパオロ・ファツィオリは、ピアノに何を求めればよいかを知るユニークな立場にある。
それまでに試したどのピアノにも満足できず、ファツィオリは35歳のときに、家族が経営する
大きな家具店で働くという保証された道を捨て、まったく新しいピアノの設計と製作に賭けた。
家族の工場の隅に店を構え、パオロはあらゆる既存メーカーのピアノの研究に取りかかった。
そして、木材のシーズニングから音響学にいたるまでの、さまざまな分野の専門家からなる
チームを結成し、多くの研究と実験を重ねたのちに、4つの試作モデルを作り出した。
それらはすべてグランドで、全長156、183、228、278センチの4タイプだった。
パオロの最大のリスクはイタリア語のブランド名を用いることだった。なぜなら、
イタリアのピアノ産業はクリストフォリの時代以来、ほぼ休眠状態にあったからである。
しかしパオロは、ピアノが十分優れたものならきっと市場を獲得できるはずと信じ、
意思を曲げなかった。この企業がまさに大成功であったことは、ほとんど疑う余地がない。
4つの試作品はすベて1981年のフェア終了後に売れ、製造を開始した1年目にさらに6台のピアノが製作された。
1986年には新たなふたつのモデルの生産が開始された。それらは全長228cmと308cmの大きなグランドである。
ファツィオリは今も手作りで、2001年の夏に移転した特設工場では生産高が年間80台から120台へと増えた。
新しい会社内には研究施設とコンサートホールも併設されている。
<附録>
ファツィオリ・ピアノ 製造番号/製造年代 対照表(1981年~2001年) →★
<以下、ウィキペディアより引用抜粋>
ファツィオリ・ピアノフォルティ(伊: Fazioli)は、1981年に創業したイタリアのピアノメーカーである。
創始者兼現社長、パオロ・ファツィオリは、家具職人の家に生まれ、ロッシーニ音楽院でピアノを、
ローマ音楽院で作曲を専攻した後、ファツィオリ社を1981年に創業した。
綿密な手作業をふんだんに盛り込み、世界で最も高額なピアノとして知られている。
また独立アリコート方式、「第4ペダル」など特殊な設計でも知られる。
現時点で世界最長サイズ(奥行き308センチメートル)のモデルも製作している。
工場はイタリア北部のサチーレにある。
この際、各分野の専門家たちに、ゼロからピアノを設計する計画への参加を要請。
ミケランジェリのピアノ調律も務めたピアノ調律師兼製作者のチェーザレ・アウグスト・タローネの
弟子らを招聘し、1980年に最初のモデルを完成させた。
製品ラインナップはグランド・ピアノに限定されている。生産台数は、2009年時点で年間120台程度とされる。
ピアノの音色を決定づける響板は、フィエンメ峡谷産のレッドスプルースが使用されている。
またファツィオリの響板は、製作が終わってから2年間、空気管理された倉庫で熟成される。
他メーカーでは機械によるハンマーのフェルト作りが一般的であるが、
ファツィオリはフェルトに硬化剤を使用せず、
手作業でフェルトを作る。これにより弾力に優れたハンマーが得られる。
現代の一般的なピアノ製造工程では、ピアノ内部の鉄製フレームを鋳造する際、真空吸引法を用いる。
これは鋳型の隅々に鉄を確実に流し込み、作業を短時間で進めることができるという利点を持つが、
ファツィオリでは、伝統的な方法で時間をかけて鋳造している。
多くのピアノの中高音部の駒からヒッチまでの弦(バックストリング)には倍音を豊かに響かせるための
アリコートブリッジが取り付けられている。
通常のアリコートブリッジは一体型で、各音程毎にアリコートブリッジの位置を独立して
調節することは不可能である。
ファツィオリでは各音のブリッジを個別に移動できる独立アリコート方式を採用している。
ただし、独立式アリコートブリッジはファツィオリのみに見られる特徴ではない。
ファツィオリでは、駒の基礎(カエデとマホガニーとの積層材)上に貼る木材に
カエデとシデとツゲの3種を用い、硬度の違いを生かして音域ごとに
(低音から中音域にカエデ、高音域にシデ、最高音域にツゲ)3種を順に使用するよう設計している。
駒の表面の加工も、熟練した職人の手作業で仕上げられる。
通常の3本のペダルのさらに左側に4番ペダルのあるものがあり、この特許を取得している。
このペダルによって、ハンマーと弦の距離が短くなり、同時に鍵盤が浅くなる。
ファツィオリはこれを「音色を変えることなく音量のみが小さくなる」としている。
これによってピアニッシモの効果が得られるだけでなく、グリッサンドや速いパッセージに利点がある。
4番ペダルは、モデルF308のみ、標準仕様である。
他機種ではオプションで4本ペダル仕様にすることが可能であるが、追加料金が必要となる。
また購入後にペダルの増設はできない。
ファツィオリでは防錆と美観を考慮し、金属部品に金メッキ処理を採用している。
<ファツィオリは、下記6種類のグランドピアノを製造>
■F156 ※ヤマハで例えるとC1とほぼ同じサイズ
■F183 ※ヤマハで例えるとC3とほぼ同じサイズ
■F212 ※ヤマハで例えるとC6とほぼ同じサイズ
■F228(通常のセミコンサート・グランドピアノ) ※ヤマハで例えるとC7とほぼ同じサイズ
■F278(通常のフルコンサート・グランドピアノ) ※ヤマハで例えるとCFXとほぼ同じサイズ
■F308(ファツィオリ独自の特大コンサート・グランドピアノ) ※ヤマハにはないサイズです
→機種番号のFに続く数字は、ピアノの奥行きを(センチメートル単位で)表しています。
※ただし、F308の現行機種の実際の奥行きは302cmになっておりますので注意。
※ちなみにベーゼンドルファーのフラッグシップモデルである「インペリアル」の奥行きは290cmです
《日本における納入先施設(一般公開施設のみ) 上から納入時期が早かった順です》
■栗東芸術文化会館さきら(滋賀県栗東市)F278 ※日本で初めてファツィオリを納入したホール(1999年?)
■北上市文化交流センター さくらホール(岩手県北上市)F278 ※2005年 アルド・チッコリーニが再来日し演奏
■石川県こまつ芸術劇場うらら(石川県小松市)F212 ※詳細は公開されていない
■美浜町生涯学習センターなびあす(福井県三方郡美浜町)F308 ※2012年納入、F308の設置としては国内初
■豊洲シビックセンター(東京都江東区)F278 ※2015年9月納入、舞台壁が総ガラス張りで夜景が見えるホール
■渋谷ホール(東京都渋谷区)F212 ※2018年11月納入
■風テラスあくね(鹿児島県阿久根市)F278 ※2019年1月納入
■フェニーチェ堺(堺市民芸術文化センター)(大阪府堺市)F308(特注モデル) ※2019年3月納入
■中札内文化創造センターハーモニーホール(北海道中札内村)F278 ※2020年1月納入
《日本における納入先施設(非公開施設で判明している場所) 上から納入時期が早かった順です》
■幕張ベイタウン・コア(千葉県千葉市美浜区)F278 ※2002年4月納入、利用は共催イベントのみ審査あり
■渋谷教育学園幕張中学校・高等学校田村記念講堂(千葉県千葉市美浜区)F278 ※2009年納入
ファツィオリの調律もお任せください(但し、ホールの調律は毎回施設側の許諾が必要です)→★ |
| FEIGL, ALOIS |
詳細不明 |
FEINTON
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
フェイントン 北朝鮮 パコやグラチアと同系ピアノ 詳細不明 |
FELIX SCHULER
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
フェリックス・シューラー 昭和楽器 詳細不明
スペルは”FELIX SHULLER”ではない |
| FENNER |
詳細不明 |
FERD. THÜRMER
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
フェルディナント・ テュルマー 1834創業 ドイツ
<以下、ウィキペディアより引用抜粋>
Ferd. テュルマー・ピアノフォルテファブリック(Ferd. Thürmer Pianofortefabrik)は、
ドイツ・ボーフムのピアノ製造会社である。
テュルマー家は100年以上ピアノの製造を続けて、現在はボーフムに工場を持つ。
1834年にフェルディナント・テュルマー(Ferdinand Thürmer)によて創業された。
第二次世界大戦で工場はソビエトに破壊されたが、戦後に再建され成功を収めた。
公式HP:https://www.ferdthuermer.de/ |
|
FEURICH



画像クリックでHPへ戻る
|
フォイリッヒ (ホイリッヒ) ドイツ(旧西ドイツ) 1851年創業
ジュリアス・フォイリッヒはドイツ・ライプツィヒでピアノ製造会社FEURICH社を創業
ユリウス・グスタフ・フォイリッヒは、パリのプレイエルの工場でピアノ製作を学び、
1851年にドイツに帰ってライプツィヒに会社を設立した。
フォイリッヒはそれまでドイツで知られていなかったアップライトピアノ製作の詳細な
知識を持ち帰った。1930年代には、フォイリッヒのグランドピアノは世界中の40以上の
コンサートホールに所蔵されるようになった。
フォイリッヒはユリウス・ブリュートナーと同じ街で開業することになったため、
当初、フォイリッヒ社はアップライ卜のみを、ブリュートナー社はグランドのみを製作するという
取り決めがなされた。しかしその平和な合意も4年しか続かず、競争心に動かされたふたつの会社は
ともに両タイプのピアノを製作するようになる。
フォイリッヒ社は着実に成長していき、20世紀の初めには良質のピアノを製作していた。
第一次世界大戦が始まった1914年、フォイリッヒ社の360人の従業員は、年間1,000台のアップライトと
600台のグランドを生産した。1920年代には生産高が落ち込むが、それでも社長のカール・ミューラーは、
経営不振に陥ったベルリンのオイテルペ社とW・ホフマン・カンパニー社を買収した。
第二次世界大戦ではライプツィヒの工場が破壊されたが、
戦後ミューラーは3つすベてのメーカーのピアノの生産をベルリンで開始する。
1949年、創業者のひ孫のユリウス・フォイリッヒはミューラーの支援を受け、ラングラウに新工場を建設する。
以後、この場所はオイテルぺ社の工場になった。
1958年に会社は国営化され、グループはオイテルペ・ピアノ・カンパニーの旗印のもと着実に成長し続け、
1979年のピーク時には276人の従業員が年間2,500台のアップライトと250台のグランドピアノを生産した。
1991年7月、ベヒシュタイン社がオイテルペ・ピアノ・カンパニー社の株の過半数を買い占める。
自治的経営を認められたフォイリッヒ社は、5キロほど離れたところに新たな工場地を見つけて、
1990年代の大半は徐々に生産高を増やした。現在フォイリッヒ社は、グンツェンハウゼンの工場で
アップライ卜とグランドピアノを安定して生産しており、1920年代と30年代の自社の美しい楽器をモデルにした
コンサートグランドの製作を計画している。
※現在のフォイリッヒは中国メーカーの傘下なのでBVK認証は受けておりません。BVK認証とは →★
トレードマークの下が中国製造のものです。
<附録>
フォイリッヒ・ピアノ 製造番号/製造年代 対照表(1860年~2000年) →★
<以下、ウィキペディアより引用抜粋>
フォイリッヒ(Feurich)は1851年にザクセン王国ライプツィヒで創業したピアノ製造会社であり、
1948年までライプツィヒで生産していた。
現在、フォイリッヒブランドのピアノは中国の海倫鋼琴(ハイルンピアノ)の工場と
ウィーンの6区の工場で製造されており、ウィーンの7区に所在する
ヴェンドル・ウント・ルングGmbHによって流通されている。
フォイリッヒはライプツィヒに歴史的ルーツを持つピアノ製作者一族およびピアノブランドである。
フォイリッヒピアノは現在中国寧波市にある海倫鋼琴(ハイルンピアノ)の工場で生産され、
ウィーンのピアノ販売・開発会社ヴェンドル・ウント・ルングの指揮の下で世界中で販売されている。
加えて、2016年からは、オーストリア・ウィーンの6区にも生産施設が存在する。
創業者の曾孫のユリウス・フォイリッヒは2012年からはもはやフォイリッヒブランドの権利と
フォイリッヒピアノの生産には関わっていない。
ライプツィヒはパリ、ロンドン、ウィーンに次いで、ヨーロッパの音楽文化の
最も重要な都市の一つであった。
ここで、1851年にユリウス・グスタフ・フォイリッヒ(1821年-1900年)が
「Pianofortefabrik Feurich」を創業した。
1860年までに、400台以上の楽器が製造販売された。
その後、より大規模で現代的な工場が建設された。世紀の代わり目には、
1万4千台近いアップライトピアノとグランドピアノが作られた。
フォイリッヒに加えて、ピアノ製造業者のブリュートナー、シンメル、Gebr. ツィンマーマン、
フップフェルト、およびその関連産業もライプツィヒを拠点としていた。
ユリウス・グスタフ・フォイリッヒとヘルマン・ハインリヒ・フォイリッヒは
ザクセン王国王室御用達の称号を与えられた。
その後、自動ピアノの時代が訪れた。フォイリッヒはこの産業における
多くの非常に成功した企業と協同した。
機械式楽器製造者であるヒューゴ・ポッパーとは親交を深めた。
M・ウェルテ&ゼーネによる自動演奏システムウェルテ=ミニョンやフップフェルトによる
Phonola、PhilipsによるDucaが導入された。
第一次世界大戦はこの地域に厳しい挫折をもたらした。
そのため、ピアノの代わりに様々な戦争物資のための包装容器が次第に製造されるようになった。
1919年までに、3万4千台以上のアップライトピアノとグランドピアノが製造された。
インフレーションの間、通貨の価値が維持されず、人々は通貨を素早く有形資産へと変換したため、
ピアノ生産は全速力で行われた。
後に、大恐慌が来ると、人々は通貨を生活必需品に使わなければならず、
ピアノ生産は大幅に低下した。フォイリッヒはこの時期、無線機器のための筺体も生産した。
第二次世界大戦中、戦争必需品(光学機器や抗対空砲火ヘッドライトのための梱包用箱)の生産を
再び余儀無くされた。1943年、工場建物は爆撃され、生産施設や会社に歴史的に関係のある
全ての展示品、その他の書類、設計のための模型が失われた。
当面はハーモニウム工房テオドール・マンボルクでの生産が続けられた。
戦後、工場の修復が行われ、1950年にようやく新らしい楽器が工場から出荷された。
ユリウス・フォイリッヒJr. は1951年に西ドイツへ逃れ、ミッテルフランケンのピアノ製造業者
オイテルペ(Euterpe)に加わり、共同経営者となった。
フォイリッヒ・ブランドのピアノも生産されていた。ドイツ民主共和国(東ドイツ)当局は
ライプツィヒで経営を行っていたユリウス・フォイリッヒSr.にラングラウでの事業の継続に難色を示した。
1958年、ユリウス・フォイリッヒSr. は事業の国営化を勧告された。
その後、東ドイツに残っていた残りのフォイリッヒ家の人々も西側へ逃れた。
1959年、「ユリウス・フォイリッヒ・ピアノフォルテファブリックGmbH」が西側で新たに設立された。
日本のピアノメーカーヤマハとカワイの出現により、ドイツのメーカーが数を保つのが次第に困難となった。
1991年、オイテルペ社(したがってその傘下のフォイリッヒ社)が
ベヒシュタイン・グループによって買収された。
楽器は当初ベヒシュタインのベルリン工場で生産された。
フォイリッヒのCEOであったユリウス・マティアス・フォイリッヒはフォイリッヒの社名が
それほど重要ではない役割しか果たさないことに不満だったため、
1993年にベヒシュタイン・グループからフォイリッヒの株式を購入した。
再び独立してから3年後の1994年、フォイリッヒはフランクフルト・ムジークメッセ
(楽器と音楽の国際専門見本市)に出品した。
ニュルンベルク近郊のグンツェンハウゼンの自社工場が完成するまでは、
楽器はライプツィヒのレーニッシュ社によって製造された。
1999年から2009年までは、全てのフォイリッヒ・アップライトピアノおよびグランドピアノは
グンツェンハウゼン工場で一流のピアノ職人によって手作りされた。
1998年までに、フォイリッヒ社は76,210台のピアノを生産した。
以後、特に118 cmと123 cmの2種類のアップライトピアノと172 cmと227 cmの
2種類のグランドピアノが少量生産された。
2010年と2011年に、ウィーンの企業ヴェンドル・ウント・ルング社とフォイリッヒ・クラヴィア・
ウント・フリューゲルファブリカツィオーンGmbHとの間で業務提携が行われた。
意図はポートフォリオの拡大であった。一方では低価格帯のピアノを中国での安価に生産し、
それと同時にグンツェンハウゼン工場で手作りされたアップライトピアノとグランドピアノが売り出された。
グンツェンハウゼンにおける生産の経済発展により、2012年1月1日からの業務提携の解消が
2011年末に決定された。
2010年、ヴェンドル・ウント・ルング社はフォイリッヒの株式の大半と世界的な商標権利を取得した。
2012年にはフォイリッヒ社の買収が完了した。
今日、フォイリッヒ・ピアノの研究開発・設計はウィーンで行われ、生産のほとんどは中国・寧波市の
海倫鋼琴(ハイルンピアノ)の工場で行われている。
フォイリッヒ社の売却後、フォイリッヒ家のユリウス・フォイリッヒは
J.F. Pianofortemanufaktur GmbHの代表取締役社長となった。
フォイリッヒの商標は売却されたため、この会社はフォイリッヒ・クラヴィア・ウント・
フリューゲルファブリカツィオーンGmbHとは関係がなく、製品は「J.F.」というブランドの元で
それ以来販売されている。
1985年、「Pédale Harmonique」と呼ばれる第四のペダルによる新たな音響効果の開発が始まった。
ペダルが完全に押し下げられると、従来のダンパーペダルと同じ挙動となる。
ペダルが中間まで押し下げられると、全てのダンパーが持ち上がるが、演奏され放された鍵の
ダンパーのみが弦に落ちる。演奏されていないその他の弦はダンパーで消音されないままになる
(ソステヌート・ペダルの逆の挙動)。
2006年、試作品がムジークメッセ・フランクフルトに出品された。
ピエール・ブーレーズはこの革新を好意的に論評した。 |
FIBICH
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
読み方不明
チェコスロバキア製 (現在:チェコ共和国) ペトロフ社のブランド |
| FIBIGER |
詳細不明 |
FIEDLER
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
フィドラー ドイツ 詳細不明
|
| FIEDLER, GUSTAV |
詳細不明 |
FINETONE
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ファイントーン 株式会社 富士楽器製作所(外国ピアノ輸入商会?) 詳細不明 |
| FINGER |
詳細不明 |
| FIONA |
詳細不明 |
FIRST

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
FIRST ファースト
東京楽器製造(株)(株式会社 森技術研究所、森技研)
当時の住所:東京都江東区深川平井町2-5
沢山清次郎氏が森健氏の後を受けて東京深川の東京楽器製造株式会社で製作したもの。
東京楽器は森健氏が東京の深川で多年の経験を生かして名器を作ろうと工場を設立した。
|
FISCHER
J. & C. FISCHER

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ジェー・アンド・シー・フィッシャー J.& C.FISCHER/J. & C. Fischer Pianos
エオリアン・アメリカン・コーポレーション傘下の系列会社の製品
工場:ニューヨーク 創業1840年
FISCHERは極めて古いメーカーで、創設者のフィッシャーはフェルディナンド一世
(18世紀から19世紀にかけてのナポリ王。マリア・テレサの娘を王妃とし、
ナポレオンと戦って敗れ、暴君であったと歴史上の記録に残っている)のお抱えの
ピアノメーカーであったということから、さぞピアノの発祥地であるイタリアの伝統を
伝えるピアノであったのであろう。
この創始者、フィッシャーの二人の息子のジョン・フィッシャーとチャーレス・フィッシャーとが
アメリカでピアノの製造を始めたので、そのブランドはジェー・アンド・シー・フィッシャー
(J. & C. FISCHER)となっています。
フィッシャーはアメリカのピアノ工業の発達のために大きく貢献したメーカーです。
<別解説>
孫のジョンとチャールズが会社をアメリカに移す前に、フィッシャーは一族のピアノ作りを始めました。
フィッシャーは18世紀末にウィーンからイタリアのナポリに移り住んだ。
ナポリでピアノ製作を始めたフィッシャーは、すぐにその名を知られるようになり、
「ナポリ王フェルディナンド1世のピアノ製作者」として宮廷に任命された。
その後、息子のカール・フィッシャー(ジョンとチャールズの父)は、ナポリで父の事業を引き継ぎ、
自分の息子たちにも教えて、1839年には海を越えてニューヨークの中心部で生産を開始した。
有名なウィーンのピアノ職人の孫にあたるジョンとチャールズ・フィッシャーは、
ウィリアム・ナンズが引退する1840年まで、ナンズ&フィッシャー社からJ.C.フィッシャー社に
社名を変更するまで、ナンズとパートナーを組んでいた。
1896年には、年間5,000台近くのピアノを生産し、すでに10万台目の生産を達成していた。
1908年にJ.C.Fischer社がAmerican Piano Companyに買収されてから一連の買収が始まり、
オフィスはニューヨークに残りました。
1985年にはウーリッツァーがJ.C.フィッシャーを買収し、1995年にはボールドウィンが
J.C.フィッシャーを買収した。
ギブソンは2001年にBaldwin Piano Companyを買収した際にこの名前を取得しました。
現在、J.C.フィッシャーピアノは中国で製造され、アジアの輸入品としてアメリカで販売されています。 |
| FISCHER, CARL |
詳細不明 |
FLEMMING
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
フレミング 株式会社 福山ピアノ社
ブランドのスペルは”FLEMING”ではなく”FLEMMING”で、Mが2個重なります |
FLICKLER

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
FLICKLER フリックラー
大洋楽器工業有限会社・(株)プルツナーピアノ・及川ピアノ製作所 いづれも浜松
昭和31年から38年まで大洋楽器工業で作られており、
その後プルツナーピアノを経て、昭和45年から及川ピアノのブランドとなった。
|
FLINGEL

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
FLINGEL フリンゲル
発売元:ピオバ楽器社(神田神保町) 製造:広田ピアノ株式会社(川崎?)
野口喜象氏が神田ピオバ楽器を経営していたときに発売したピアノ。
昭和11年頃、広田ピアノ製作所で作られた。
|
FLOBAL
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
フローバル 浜松 中部楽器製造(株) 詳細不明
※大洋楽器工業株式会社という資料もあるが不明 |
| FLOBEL |
→FROBELの項目へ
フローラピアノ製造(株)の作っていたフローベルのスペルは”FLOBEL”ではなく、”FROBEL”です |
|
FLOBERGER

画像クリックでHPへ戻る
|
フローベルガー
この機種は1台しか調律の経験ありません。詳細不明。
”キャッスル(CASTLE)” というピアノのトレードマークにやや似ていますが詳細は不明。
フローベルガーのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★ |
|
FLORA



画像クリックでHPへ戻る
|
フローラ
フローラピアノ製造株式会社、日本鍵盤製造株式会社
昭和37年に、浜松市に設立されたフローラピアノ製造(株)で作られていたブランドです。
当時8機種が作られていました。
音色はややシャリシャリした感じです。。まさにTHEフローラといった音色(分かる方は分かるはずです)
ちなみに、アールウィンザーというピアノもフローラピアノ製造です。
上から2枚目のエンブレム画像は「PIANO YOSHIKAWA様」よりご寄稿頂きました。ありがとうございます!
フローラのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★ |
FLORA
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
フローラ 台湾 詳細不明
|
FLOWER
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
フラワー 羽衣楽器製造株式会社 |
FLUGEL

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
FLUGEL(FLÜGEL) フルーゲル/フリューゲル
坂本ピアノ製作所/坂本楽器研究所(大成ピアノ製造の前身) 浜松市
昭和24年から昭和46年まで作られていた。
|
| FOCKÉ |
詳細不明 |
| FOCKÉ, GEORGES |
詳細不明 |
FORCKENBECK

画像クリックでHPへ戻る |
FORCKENBECK フォルケンベック
東洋ピアノ製造株式会社 |
| FORENEDE |
詳細不明 |
FORO
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
フォロ(FORO) 福楽鋼琴股份有限公司 台湾(中国)
工場は台中県石岡郷。従業員数200人を超えたこともあり、グランドピアノからアップライトまで。
|
FOREST


画像クリックでHPへ戻る |
FOREST フォレスト
■ 東京楽器製造株式会社
■ 森技術研究所
■ アトラスピアノ製造株式会社
■ 有限会社 ツルミ楽器
■ トニカ楽器製造株式会社
東京楽器製造(株)東京都江東区深川平井町、(トニカ楽器(三田?))
森健氏が東京の深川で多年の経験を生かして名器を作ろうと工場を設立したのが東京楽器製造。
FORESTは森氏の姓からとったもので独特の設計で音色は美しかったとの情報。
尚、多数の有能な技術者を養成して、これらの技術者は十八会と呼ぶ会合を続けていた。
その後、トニカ楽器扱いに。
FU-10、FU-20、FU-30、FU-50、FU-55、FU-70、FU-80の7機種があった。
FOREST(フォレスト)のトレードマークは当然ながらトニカピアノとほぼ同じトレードマークです。
音符が3つ交差したトニカのトレードマークはこちら →★
エンブレム画像は「PIANO YOSHIKAWA様」よりご寄稿頂きました。ありがとうございます!
フォレストのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★ |
| FORREST |
詳細不明 |
FORSTEI VON MELOS


画像クリックでHPへ戻る
※下記は参考画像

|
FORSTEI VON MELOS
フォルステイ・フォン・メロス
製造元:レスターピアノ製造株式会社
製造元:東洋ピアノ製造株式会社
<一番上のトレードマーク画像>
モルゲンスターン(MORGENSTERN)とまったく同じトレードマークで、韓国のサミック社製の5機種
REID-SOHN、KAFMANN、SAMICK、SCHNABEL、WEINBURG(現在把握しているもの)とも酷似。
比較した画像はこちら →★ これらトレードマークの類似点については現在調査中です。
<上から2番目のトレードマーク画像>
文字の部分が”F V M”になっていますね。→FORSTEI VON MELOSの頭文字から
匿名希望様からご寄稿頂きました。ありがとうございます!
<一番下のトレードマーク画像>
画像は参考で、アポロピアノのトレードマークです。
”FVM”の文字の部分だけが違うことが分かります。 |
FORSTEIN
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
フォルスタイン 東洋ピアノ製造株式会社 |
FORSTER
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
フォルスター ドイツ 詳細不明 |
FORSTER
FÖRSTER


画像クリックでHPへ戻る |
FORSTER/FÖRSTER フォルスター
福島昭彦氏
ベルリンピアノ製造株式会社 ※当時の住所:浜松市(現:浜松市東区)原島町195番地
有限会社 光輪楽器製作所
昭和34年から昭和46年まで作られていた。
トレードマークには「BERLIN PIANO・CO・HAMAMATSU JAPAN」と入っています。
マーク内にはライオン?とみられる動物が向かい合わせに描かれていてとても印象的ですね。
このトレードマークは「wakopin様」からご寄稿頂きました。ありがとうございます!
似た名称で”エー・フォスター/A.FOSTER”(同じベルリンピアノ製造株式会社)や、
このすぐ下の”フォスター/FOSTER”(大和楽器製造株式会社)というブランドもあるので要参照 |
| FÖRSTER, AUGUST |
詳細不明 |
FOSTER
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
フォスター 大和楽器製造株式会社
似た名称で”エー・フォスター/A.FOSTER”(ベルリンピアノ製造株式会社)や、
このすぐ上の”フォルスター/FORSTER”(ベルリンピアノ製造株式会社)もあるので要参照 |
| FORTH |
フォルス/フォース アカシアピアノ製作所 |
FOUDRICH
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
フードリッヒ
有限会社 野田ピアノ 詳細不明 |
| FOUGEL |
フーゲル 明音楽器製作所 |
| FR. HELMHOLZ |
→HELMHOLZの項目へ |
| FRANCESCA |
TEH AEOLIAN CO.(エオリアン社) ニューヨーク
その他詳細不明 |
FRANCIS BACON
(BACON, FRANCIS)

画像クリックでHPへ戻る |
FRANCIS BACON PIANO CO. 創業1789年 アメリカ(ニューヨーク)
フランシス・ベーコン・ピアノ・カンパニーの歴史は、1789年にさかのぼります。
ジョン・ジェイコブ・アスターが会社を設立し、その30年後にはロバート・ストダートと
ウィリアム・デュボアを迎え入れました。
1841年から1871年まで「Raven & Bacon」という社名を冠していた
フランシス・ベーコンやトーマス・レイヴンなど、最初の40年ほどはさまざまな人物が
入社・退社を繰り返していた。
その後、ベーコン家の数世代にわたる存続を経て、1904年にベーコン・ピアノ・カンパニーとして法人化された。
ベーコン・ピアノ・カンパニーは、1900年代初頭からコーラー社やキャンベル社との取引を開始し、
1933年にはコーラー社やキャンベル社の大企業に完全に統合されたため、ベーコン・ピアノの中には
コーラー社やキャンベル社のシリアルナンバーが付いているものもある。
フランシス・ベーコン・ピアノは、ニューヨークに本社を置くピアノメーカーで、アップライトピアノ、
グランドピアノ、プレーヤーピアノ、電気式表現ピアノ、リプロダクションピアノなど、
さまざまなタイプのピアノを製造・販売していた。
ベーコンピアノは何十年にもわたって製造されてきた実績があり、創業当初からその優秀さが望まれていました。
1876年のフィラデルフィア万国博覧会をはじめ、1800年代後半から1900年代前半にかけて、
このブランドのピアノはいくつものメダルや賞を受賞しました。
ベーコン・ピアノの価格帯は、中程度のものが多い。 |
FRANKE. H.
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ドイツ フランケ 詳細不明 |
FRANKLIN

画像クリックでHPへ戻る |
FRANKLIN
フランクリン アメリカ(ニューヨーク)
その他詳細不明
左記トレードマーク画像は「ミルキー杏様」からご寄稿頂きました。ありがとうございます! |
| FRANZ MEYER |
詳細不明 |
FRANZ OESER

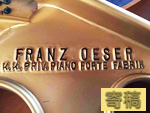
画像クリックでHPへ戻る
|
FRANZ OESER
フランツ・エーゼル/フランツ・エーザー/フランツ・ウーザー/フランツ・オーザー
オーストリア=ハンガリー帝国(ハンガリー製)
オーバーダンパーの写真 →★ 外観写真 →★ 銘柄マーク →★ 響板デカール →★
写真ご寄稿:平田康裕様よりご提供いただきました |
| FREDERIC |
フレデリック 東京楽器研究所 |
FRENCH, JESSE
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
アメリカ 読み方不明、詳細不明 |
FRIEDMAN
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
フリードマン 東洋楽器製造株式会社(広島) 詳細不明 |
FRIEDRICH



画像クリックでHPへ戻る |
フリードリッヒ FRIEDRICH
福島ピアノ研究所
東京楽器研究所
東日本ピアノ製造株式会社
株式会社バロック
静岡楽器製造株式会社
神楽坂の途中に福島ピアノ店という専門店があり、
元輸入商だった福島昭彦氏が材料を提供して作りました。
福島貿易商はもともと横浜にあり”福嶋”が本姓で、
中国の天津や上海にもフリードリッヒのブランドがあり、
それらと契約もあったと伝えられています。
当時、発売店は新宿区神楽坂通り三丁目にありました。
機種バリエーション:F104等
左記トレードマーク画像は「匿名希望様」からご寄稿頂きました。
この度は画像をご寄稿頂きまして誠にありがとうございました!
東日本ピアノ製造(株)の「バロック(BAROCK)」や「クリーベル(KRIEBEL)」の項目も参照
<参考資料>
東日本ピアノ製造株式会社を含む会社遍歴は下記の通り
昭和28年 大岡楽器製作所が発足
昭和31年 白鳥楽器製作所
昭和33年 スワン楽器製造株式会社
昭和38年 ガーシュインピアノ株式会社
昭和42年 東日本ピアノ製造株式会社
昭和62年 株式会社バロック |
| FRIEDRICH EHRBAR |
詳細不明 |
FRITZ DOBBERT



画像クリックでHPへ戻る |
フリッツ・ドッベルト/フリッツ・ドベルト ブラジル(サンパウロ)
ローズウッド材の本場なので外装が美しいものが多い。その他詳細不明
<以下、ウィキペディアより引用抜粋>
フリッツ・ドッベルト(Fritz Dobbert)は、ブラジル・サンパウロを拠点とするピアノ製造業者である。
1950年5月13日創業。
ラテンアメリカで最大のピアノメーカーであり、ブラジルのアコースティックピアノのトップ企業である。
工場はドイツ人のOtto Halben、CelioおよびThyrso Bottura兄弟によって、
Canindé地区でIndústria de Pianos Halben(ハルベン・ピアノ産業)として創業された。
1956年、会社はPirituba地区の倉庫複合施設へ移転し、
Pianofatura Paulista(サンパウロ・ピアノ製造)と解明した。
この時にはHalbenは既に会社に関与していなかった。
Pianofatura Paulistaは20種類を超えるピアノブランド名を使用した。
1958年、工場従業員で職人のFritz Wilhelm Ernst Otto Dobbertがピアノの新しい設計を開発した。
このピアノは非常に成功を収め、彼の名を冠した。
間もなく、Pianofatura PaulistaはFritz Dobbertブランドのみを使用するようになった。
長年にわたって、Fritz Dobbertはブラジル最大のピアノメーカーの一つとしての地位を確立してきた。
2015年5月、65周年を迎えた時に、工場はPirituba近郊を離れて、オザスコのより近代的な施設へと移転した。
会社は現在創業者の2世代目によって経営されている。
公式HP:https://www.fritzdobbert.com.br/pianos/fritz-dobbert/
公式FBページ:https://www.facebook.com/FritzDobbert/
フリッツドベルトのその他の写真です →★ |
|
FRITZ KUHLA




画像クリックでHPへ戻る
|
FRITZKUHLA フリッツ・クーラ/(フリッツクーラ)
製造:東洋ピアノ製造株式会社(浜松市)
鉄骨部分には”TOYO PIANO”と刻印があります。
音色はデフォルトではやや堅めのピアノですね。
東京藝術大学や武蔵野音大の指定ピアノだった時期あり?(不確定情報)
<読み方>
○ フリッツクーラ × フリッツクーラー
ピアノのトレードマークとしては珍しい三角形をしています。
他にも三角形のロゴもありますが、このページの中から探してみて下さい^^
<機種バリエーション>
特製30号、特製38号、特製50号、特製70号など
フリッツクーラのまくり(蓋内部の右上部)にある大きくて独特なブランド銘柄マーク →★
フリッツクーラのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★ |
FRITZKUHLA
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
フリッツクーラ ドイツ 1872~ その他詳細不明 |
FRITZ KHULA
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
フリッツ・クーラ フィリピン 詳細不明
|
FRIXSHURER
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
フリックスシューラー 本間ピアノ楽器工作所 |
FROBEL
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
FROBEL フローベル フローラピアノ製造株式会社(浜松)
※フローラピアノ製造株式会社が作る代表ピアノ、”フローラ”のスペルはFLORA”なのですが、
同じフローラピアノ製造が作るこの”フローベル”のスペルは”L”ではなく何故か”R”になっています。 |
FUCKS & MOHR
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
FUCHS & MÖHR フックス・アンド・メーア ドイツ(旧西ドイツ) 詳細不明
|
FUJI

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
FUJI フジ
富士楽器製造株式会社(富士ピアノ製作所)
シェーンベルグ製造当時の富士楽器が昭和11年に作ったピアノのブランド。
創立者は野田秀治氏。二代目は野田満氏である。
|
FUKUSHIMA

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
FUKUSHIMA フクシマ
福島ピアノ研究所(東京都大井町)、東京楽器研究所
福島ピアノは大井町の東京楽器研究所で作り出されたものである。
この研究所の所長であった福島琢郎氏は、ピアノの技術者としては飛び抜けた人であった。
彼は早稲田大学の商学部を卒業後、日本楽器に入社しているが、
当時の農商務省と音楽学校の推薦で渡米し、スタインウェイで2年ピアノの製造技術を学び取ったが、
帰国後、理論と技術が噛み合わず、日本楽器を飛び出している。
福島氏の父親は三井の重役で、当時のエリート中のエリートであったため、
三越の重役その他の出資を得て、さらに実際の技術者として、後にヒロタピアノを作った
日本楽器の広田米太郎氏を招いて、1918年に株式会社東京楽器研究所を設立した。
名前は研究所であったが、実際はピアノ工場で、福島氏は音楽学校の顧問もしていたので、
その製品は品質も優れていたが、販売機構を持たなくても飛ぶように売れていった。
当時のヤマハのアップライトは最低500円であったが、関東のメーカーのピアノの方が値段が高く、
ニシカワが650円、フクシマが最も高く800円だったという。
ちなみに1918年の大卒の初任給は40円だそうです。
製造台数はわずか500台程度であったが、この研究所で技術を習得した多くのピアノ技術者たちが、
後の関東地方のピアノ製造を支えたのである。
技術者として活躍した方々は次の通り極めて多い。
木下乙弥氏、藤原梅太郎氏、太田一郎氏、山崎秀雄氏、清水栄一氏、伊藤辰雄氏、橋本勝美氏、
足立三郎氏、斉藤喜一郎氏、渥美亘弘氏、竹内友三郎氏、森吾市氏、大越勇喜氏、淵田栄氏、
松崎妙氏、大岩隆平氏、大友雅一氏、飯国一郎氏、福井辰利氏、大井長一氏、の各氏。
|
FUKUYAMA

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
フクヤマ
株式会社 福山ピアノ社
大成ピアノ製造株式会社
有限会社 興和楽器製作所
坂本ピアノ
株式会社 坂本ピアノ製作所 |
FUKUYAMA DELUXE
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
フクヤマ・デラックス 株式会社 福山ピアノ社 |
|
FUKUYAMA & SONS



画像クリックでHPへ戻る
|
フクヤマ/フクヤマ・アンド・サンズ
株式会社 福山ピアノ社(本社住所:東京都千代田区神田神保町1の14番地)※当時
東京ピアノ工業株式会社
富士楽器製造株式会社
フローラピアノ製造株式会社
明治12年生れの福山松太郎氏が明治末期より神田小川町に開業した福山ピアノが、
昭和40年代になって自らの姓をつけて製作した自信作とのことである。
高級品を目指して努力したと伝えられています。
音色、出来栄えともになかなか良いピアノだと感じます(※ただしピアノの個体差は大きいです)
ピアノの蓋には、FUKUYAMA & SONSと書かれています。
上のトレードマーク画像がアップライト、下のトレードマーク画像がグランドです。
グランドピアノの方のトレードマークは、「I様」よりご寄稿頂きました。ありがとうございます!
フクヤマのグランドのフタ部分にある銘柄マーク →★ フクヤマピアノのキーカバー →★
フクヤマピアノの保証書 →★ (株) 福山ピアノ社の本社は千代田区神田神保町1丁目14番地とあります
フクヤマのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★ |
FUKUYAMA & SONS SPECIAL
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
フクヤマ&サンズ スペシャル 株式会社 福山ピアノ社 |
FURSTEIN (FARFISA)
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
フルシュタイン(ファルフィサ) イタリア 詳細不明
|
FURTADOS
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
インド 総合楽器メーカーでピアノもわずかに製造しているようです
その他、詳細不明
公式ホームページ:https://www.furtadosonline.com/
フェイスブックページ:https://www.facebook.com/FurtadosIPT/ |
上記Fから始まるブランドの中で、追記出来そうな事項や新情報を発見した場合、修正受付フォーム よりお気軽にお知らせ下さい。
どんな些細な情報でも構いませんので、広く皆様からのフィードバックをお待ちしております。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
 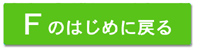 



ピアノ銘柄ブランド
トレードマーク 紹介
& 知名度ランキング

|

メーカー/ブランド説明・会社沿革・歴史・製作者・特徴・音色・他
|
G & GRAND
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ジー・アンド・グランド 東日本ピアノ製造(株)、株式会社バロック
1953年創業の東日本ピアノ製造。
<参考資料>
東日本ピアノ製造株式会社を含む会社遍歴は下記の通り
昭和28年 大岡楽器製作所が発足
昭和31年 白鳥楽器製作所
昭和33年 スワン楽器製造株式会社
昭和38年 ガーシュインピアノ株式会社
昭和42年 東日本ピアノ製造株式会社
昭和62年 株式会社バロック |
| G. RÖSLER |
→RÖSLERの項目参照 |
| G. SCHWECHTEN |
→SCHWECHTENの項目へ |
GABRIELGAD
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ガブリエルガド 竜生楽器研究所 |
GALNER
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ガルナー 遠州ピアノ製造(株)浜松 昭和31年より昭和36年まで生産されていた。
|
GARTCHEN
<注意> |
<ご注意>
■スペル:GARTCHEN
■読み:ガルトヘン
■製造:(株)シュベスターピアノ製作所
と解説している資料もありますが、これは下記の「GARTEN」とスペル表記を間違えているものと推測されます。
協信社ピアノ製作所(シュベスターピアノの前身)が過去に製造したピアノは「GARTEN」です。
「GARTEN」についての詳しくは、このすぐ下にある「GARTEN」の項目を参照
※ちなみに、よく似た名称でGERTCHEN(ゲルトヘン)というピアノもあります(松本楽器製造株式会社) |
GARTEN


画像クリックでHPへ戻る |
GARTEN/ガルテン、(ガーテン)、(ガーデン) ※読み方不明
製造元:協信社ピアノ製作所(東京蒲田 北糀谷工場)
※協信社ピアノ製作所は、シュベスターピアノ製造KKの前身になります
シュベスターピアノ製造株式会社(旧:協信社ピアノ製作所)はヤマハ、カワイに次ぐ
日本で3番目に古いピアノメーカーです(ピアノ製造をしていなくても何らかの事業継承している中において)
シュベスターピアノ製造株式会社についてのさらに詳しい解説は→「SCHWESTER」の項目へどうぞ
シュベスターピアノ第1号機(1929年/昭和4年製造)は、大田区田園調布の佐治家(病院)へ初めて納品され、
その後昭和50年代に修復されたのち、ピアノは武蔵野音楽大学(東京都練馬区羽沢1-13-1)へ寄贈されました。
現在このシュベスターピアノ1号機は武蔵野音楽大学(江古田キャンパス)内に併設されている
楽器ミュージアム(鍵盤楽器コーナー)に展示保存されております。※一般公開中(要予約)
楽器ミュージアムに展示中のGARTENピアノのキャプションボードです →★
先日、武蔵野音楽大学楽器ミュージアム様から特別な許可を頂き、当ピアノの調査に伺わせて頂きました。
シュベスターピアノの記念すべき第1号機は病院へ納入されたとのことですが、この「病院」というのは
当初私は人間の病院だと思っていたのですが、実は犬の病院(当時の病院名:田園愛犬病院)ということが
同大学内に保存されていた資料や、その他の情報により判明致しました。
その後、このGARTENピアノはシュベスターピアノ創立50周年に合わせて修復された後、
1979年(昭和54年)11月25日、佐治家から武蔵野音楽大学内の楽器博物館へ寄贈されました。
ちなみに現在の同大学の博物館名は「楽器博物館」から「楽器ミュージアム」に改称されております。
ところで「GARTEN」の名称の由来ですが、これは東京大田区にある田園愛犬病院の初代院長であった
佐治正次郎氏のご夫人のお名前に含まれる1文字、「園」から「GARTEN」という名称が付けられました。
※ここでは敢えて正確なお名前は伏せております。
ドイツ語で「GARTEN」とは「庭・庭園・菜園・果樹園」という意味ですのでその名付けの理由が分かりますね。
これらのことから、この「GARTEN」は佐治家のために特別に作られた1台だということが分かります。
<参考>
田園愛犬病院の初代院長、佐治正次郎氏は日本におけるペット医療の発展に大きく貢献された方です。
ちなみに、この動物病院は現在も3代目の方が大田区田園調布で病院を経営されており、
こちらの動物病院(現在の病院名:佐治動物病院)様の公式ホームページの病院沿革によりますと、
「1929(昭和4)年、佐治動物病院は日本初の犬の病院として、田園調布に開院しました」とあります。
昭和4年ということは、開院と同時期にシュベスターピアノ第1号機「GARTEN」が納入されたことになります。
今回、武蔵野音楽大学様から特別な許可を頂き、GARTENの撮影もさせて頂きましたので公開させて頂きます。
■ ガルテン(GARTEN)ピアノの上前パネルを開けた全体写真(右から)→★
■ ガルテン(GARTEN)ピアノの上前パネルを開けた全体写真(左から)→★
■ 下前パネルも開けた状態の全体写真 →★ ■ 下前パネルを開け、巻線部分を撮影 →★
■ アクション内、キャッチャー部分拡大画像 →★ ■ 象牙鍵盤拡大画像 →★
■ まくり(鍵盤蓋)部分にあるGARTENのブランドレッテル文字 →★ 少し引いた画像 →★
ピアノの外観は黒色でごく普通の雰囲気のピアノで、戦前の古いピアノなのでもちろんペダルは2本でした。
上前パネルや下前パネルは近年の一般的なピアノより軽量な作りでした。
鍵盤材質ですが黒鍵はエボナイトのようですが、白鍵の方は天然象牙の2枚貼りでした。
上前パネルには美しい象眼モールが施されておりましたので、上記各画像を参照してください。
<トレードマークについて>
一般的にピアノ内部(フレーム部分)にはそのピアノブランドを象徴するトレードマークがあるのですが、
このGARTEN(ガルテン)にはそのトレードマークはありませんでした。その部分の拡大画像 →★
特徴的だったのはフレーム表面で、波紋のような美しい模様が大変特徴的でした。
今回このピアノの調査と撮影は、武蔵野音楽大学楽器ミュージアム様からの特別な許可により実現致しました。
通常、ミュージアム内での写真撮影は一切禁止ですのでご注意下さい。手を触れることも禁止となっております。
この度は「GARTEN」ピアノの調査と撮影にご協力頂きました武蔵野音楽大学様へ心より感謝申し上げます。
ご協力をいただき誠にありがとうございました!訪問日:令和4年5月10日 |
GAVEAU


画像クリックでHPへ戻る |
ガヴォ― フランス(パリ) 創業1847年 プレイエル社が製造
ジョセフ・ガブリエル・ガヴォー(Joseph Gabriel GAVEAU)は、
1824年ロモランタン(Romorantin)生まれ。
ガヴォーはいくつかの工房で修業と経験を積んだ後、1847年にパリに自身の工房を作る。
当初からガボーは丈夫で良いアップライトピアノを作ることに拘り、エラールの設計を真似て
アップライトピアノアクションで、特にジャックの角度についての改良に取り組みました。
そして、「ガヴォ―アクション」と呼ばれる独自の特色を持つアクションを作り上げました。
ガヴォーは高い品質のチェンバロと、特に小型のアップライトピアノで素晴らしい名声を獲得しました。
彼のピアノに対する評判は高まり、セルヴァン通りに工場を構えます。
1890年頃には200人の職人を雇い年間1500台を生産するほどまでに大きくなりました。
1893年、70歳になった彼は会社を息子のガブリエル・ウジェーヌとエチエンに譲り、
会社名は"Société GAVEAU"となりました。
1896年からはパリ近郊のフォントネー・スー・ボワ(Fontenay sous bois)にモダンな新工場を建て、
約300人の職人を雇い生産量は年間2000台にのぼりました。
この工場では多くのパリの有能な職人たちが育てられました。
エティエンヌ・ガヴォー(Etienne Gaveau)は経営を担当し、パリ中心部に本社を構え、
1908には自社のピアノを宣伝するためにコンサートホール「サル・ガヴォ―」を建設しました。
1911年、兄弟は仲違いし、ガブリエルは独自の会社を興し、グランドピアノ製作で新しいアイデアを取り入れ、
木材にこだわって作られたおしゃれな外装の小さなグランドピアノを製作することで独自のスタイルを構築。
1930年頃、子会社のM.A.G. (Marcel と André Gaveau)が設立され、丈夫で小さくてしかも安価な
アップライトピアノの製造を担当。
1939年に戦争が始まった時、ガヴォ―社は95,000台目のピアノを製造したところでした。
エチエンは1943年に死去し、息子のマルセルとアンドレは困難の中でも経営を続けました。
1960年、エラール社と合併し、"Société Gaveau-Erard"と名付けられました。
その後プレイエルも加わり、"LES GRANDES MARQUES REUNIES"(大メーカーの集合)となりましたが、
1965年に倒産、工場は閉鎖。
しかし、不安定な財政状況は続き、この複合企業はドイツのシンメル・カンパニーに買収された。
シンメルとの契約が1994年に切れると、この人気のあるフランスのメーカーは再びフランスへ戻った。
1996年以降、ガヴォーのピアノは、フランス南部のプレイエル社の工場で生産されている。
※Rameau(ラモー)もプレイエル社が製造
<附録>
ガヴォー・ピアノ 製造番号/製造年代 対照表(1855年~1988年) →★
<以下、ウィキペディアより引用抜粋>
ガヴォー(Gaveau)はかつて存在したフランスのピアノ製造会社である。
1847年にパリでジョゼフ・ガブリエル・ガヴォーによって創業され、エラールとプレイエルに次ぐ
フランスで第三のピアノメーカーであった。大工場はフォントネー・スー・ボワにあった。
一部のガヴォー製ピアノは芸術的なキャビネットを持っていた。
多くのピアノは空圧システムを備えている(Odeola、Ampico、ミニョン)
1960年、ガヴォーはエラールと合併した。
1971年から1994年まで、ガヴォーピアノはピアノ製造会社のヴィルヘルム・シンメルによって作られた。
ガヴォーブランドは現在フランス・ピアノ製造会社(Manufacture Francaise De Pianos)によって所有されている
(プレイエルおよびエラールブランドもこの企業によって所有されている)
今日、フランス・ピアノ製造会社はガヴォーブランド名で幾つかのモデルを製造している。
ジョゼフ・ガブリエル・ガヴォーには6人の子供がおり、エティエンヌ・ガヴォーが継いだ。
ガブリエル・ガヴォーは1911年に設立された。
ガブリエル・ガヴォーはペダルまたはデュオ・アート(自動演奏)システムを持つ幾つかのピアノを作り、
1919, 55-57 Av. Malakoff, 75016(現トロカデロ)に近いAv. Raymond Poincaré)にあった。
この工場は1939年にドイツによって徴発された。
また1911年には、オーギュスタン・ガヴォーが独自のアップライトピアノを作る自身のピアノ会社を設立]
自伝『My Young Years』において、アルトゥール・ルービンシュタイン はコンサートで
ガヴォー製ピアノを演奏する契約をいかに結んだかについて詳しく述べている。
ルービンシュタインはガヴォー製ピアノの「堅く応答がないアクション」と「音色の冷たさ」について書いている。
またカミーユ・サン=サーンスやアルフレッド・コルトーのような音楽家も
自身のガヴォーピアノの演奏を楽しんだ。 |
GAVEAU
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ガヴォー 竜生楽器研究所
※フランスのGAVEAUとは関係ない |
GEBR. PERZINA

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
GEBR.PERZINA ペレツィーナ(ペルツィーナ) ドイツ製
ペレツィーナ(ペルツィーナ)Perzina/Gebr. Perzinaは、北ドイツ生まれのピアノブランドで、
現在はオランダと中国の資本による中国煙台の民営企業・煙台ペレツィーナで製造。
1871年、ヴィルヘルム1世によりドイツ帝国が生まれたその年に、
北部のシュヴェリンという都市でGebr.Perzinaも生まれました。
現在も宮廷の残るメクレンブルク=シュヴェリーン公、オランダのウィルヘルミナ女王に
こよなく愛されたGebr.Perzinaは6王家の宮廷ピアノとしてドイツで最も権威ある
ピアノのひとつとなりました。
また、1905年にはペルツィーナコンサートホールも開設され、
ドイツ帝国内で最も愛されるピアノとなりました。
しかしながら、第一次世界大戦で移転を余儀なくされ、さらに第二次世界大戦後は
東ドイツに組み込まれたGebr.Perzinaは手造りでピアノを作り続けたものの、
大戦後のピアノの歴史では表舞台にはあまり出てこなくなりました。
2002年公開の映画 「戦場のピアニスト」(※)で使われたピアノとしても有名です。→★
※ 第二次世界大戦におけるワルシャワを舞台としたフランス・ドイツ・ポーランド・イギリスの合作映画。
|
GEBRÜDER STINGL
GEBRUDER STINGL
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
Gebrüder Stingl ドイツ(ウィーン) 詳細不明
<以下、ウィキペディアより引用抜粋>
ゲブルーダー・シュティングル
(独: Gebrüder Stingl、ゲブリューダー・シュティングル、シュティングル兄弟)は、
ピアノを製造するウィーンの同族経営事業であった。
住所はウィーンの3区ラントシュトラーセ、Ungargasse 27であった。
創業者アントン・シュティングル(Anton Stingl、1808年9月11日ラーズニェ・キンジュヴァルト生、
1895年ピッテン没)は1840年におじの家具職人イグナーツ・シュティングルと共にウィーンへ移住した。
アントンは1853年からピアノ木工職人として働き、1860年に独立した。
作業場は4区のStarhemberggasse 28に位置していた。当初は、工芸ピアノ製造業者に供給した。
会社は1887年に拡張・再編された。3人の息子ヴィルヘルム(1860年-1908年)、
イグナーツ(1861年-1915年)、グスタフ(1868年9月7日–1906年11月27日)が会社に加わった。
ヴィルヘルムは商工会議所会員、イグナーツは名誉称号Kaiserlicher Rat(帝国顧問)を授与され、
グスタフは1900年から1904年までキリスト教社会同盟評議員であった。
父の死後、彼らはオーナーとなり、会社は「ゲブルーダー・シュティングル」(シュティングル兄弟)と呼ばれた。
会社は急成長し、10区のLaxenburger Strasse 32に新たな工場が建設された。
1895/1896年、古い伝統企業Johann Baptist Streicherがゲブルーダー・シュティングルに売却された。
シュティングルの生産はNeuer Streicherhofに移転した。
ゲブルーダー・シュティングルはオーストリア=ハンガリー帝国帝室・王室御用達ピアノフォルテ製造業者に
指名され、1900年4月14日から宮廷ピアノ製造業者となった。ペルシアやセルビア、ブルガリア王室の御用達の
称号もゲブルーダー・シュティングルに贈られた。
会社はウィーン式とイングランド式のレペティション機構(ダブルエスケープメント)を備えたグランドピアノを
製造したが、高品質のコンサートピアノも開発した。
特色はハーフペダルと世界最小のピアノ「Piccolo-Mignon」であった。
第一次世界大戦まで、シュティングルオーストリア=ハンガリー帝国で最大のピアノフォルテ工房へと発展し、
約400人の従業員を雇用した。ブダペストにも支店を開いた。
帝国の崩壊によって会社は大きな打撃を受け、1918年に「シュティングル・オリジナル」(Stingl-Original)
として再編され、次に有限会社、1922年に株式会社となった。住所はTroststraße 10であった。
1935年、シュティングルはLauberger & Glossによって買収され、 Lauberger & Glossは
「Stingl-Original」のブランド名で楽器の製造を続けた。
Lauberger & Glossは1960年代初頭にウィーンのその他のピアノ工房と同様に製造をやめた。
もう一つの「シュティングル」がグスタフ・シュティングルの息子グスタフ・イグナーツ(1900年-1960年)の
会社であった。1921年、彼は4区Favoritenstraße 17に会社を設立した。
1923年、Robert Rellaが会社に加わった。この会社「グスタフ・イグナーツ・シュティングル」は
1920年代以降輸出に重きを置いた。
グスタフ・イグナーツ・シュティングルは1932年からピアノおよびオルガン製造業者のギルドの会員であり、
後にはその役員であった。会社の本店は後に4区のWiedner Hauptstraße 18に移転し、
作業場は12区のWolfganggasse 38に位置した。1948年、ファミリーの合名会社が設立された。
これは後にシュティングル家の最後の人物の甥のグスタフ・イグナーツ・スィーヒ(Gustav Ignaz Sych)の
単独所有となった。第二次世界大戦後、ウィーン国立音楽大学やウィーン音楽院、ザルツブルク音楽祭への
納入が始まった。
カール・ミヒャエル・ツィーラーやフランツ・レハール、ロベルト・シュトルツ、ウド・ユルゲンス、
オペラ歌手らなど数多くの音楽家がシュティングルの製品を購入した。
シュティングルは日本のピアノ製造業者KAWAIの欧州代表部でもある。
HP:https://stingl-klavier.at/ |
GEISSLER
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
GEISSLER, F.
ガイスラー フランス 詳細不明 |
GEISTREICH
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
GEISTREICH ガイストライヒ
大倉楽器工業(株) 東京都杉並区上高井戸
二本弦の小型ピアノが多かったが、大型のものは音色に特色があった。
トレードマーク内の文字には”CERTIFIED MERCHANDISE”と入っています。
CERTIFIED=保証された、公認の
MERCHANDISE=商品、製品 |
GELTHNER

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
GELTHNER ゲルツナー/(ゲルッツナー) ※発音はゲルトナーではない
発売元:音調社楽器店、製造:広田ピアノ株式会社
広田ピアノで作っていたピアノ。
|
| GEMEN |
ゲーメン ※下記のゲーメンスタインと同じピアノ? |
GEMENSTEIN
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ゲーメンスタイン 日本 詳細不明 |
GEORG HOFFMANN
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ドイツ(ベルリン) 詳細不明 |
GEORGE P. BENT
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
George P. Bent ジョージ・P・ベント
アメリカ(シカゴ)
1959年にウインター(WINTER & CO.)は、エオリアン・アメリカン社と合併し、
社名をエオリアン・コーポレーションに変更していた間、
ウィンター&カンパニーが製造していたブランド名の一つです
ピアノの鉄骨部には「GEO. P. BENT CHICAGO, U.S.A.」と書いてあり、ピアノ背面の木部には
「WARRANTED TEN YEARS CEO. P. BENT CHICAGO. U.S.A.」と刻印があります(10年保証)
→WINTERの項目も参照 |
GEORG SCHWECHTEN
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
GEORG SCHWECHTEN ゲオルク・シュヴェヒテン(シュベヒテン)
1853年創業 ドイツ(ベルリン)
<以下、ウィキペディアより引用抜粋>
ゲオルク・シュヴェヒテン(Georg Schwechten、1827年2月4日シュトルツェナウ生、
1902年8月19日ベルリン没)は、19世紀後半のベルリンの卓越したピアノ製作者の一人である。
オリジナルの保存状態のよい、または修復されたシュヴェヒテンのアップライトピアノおよび
グランドピアノは今でも称賛に値すると見なされており、珍しい。
ゲオルク・シュヴェヒテンは1853年に兄のハインリッヒ・シュヴェヒテン(1812年-1871年)によって
1841年にベルリンKoch通り11番地で開業されたスクエア・ピアノの工房を引き継ぎ、
弟のヴィルヘルム(1833年-1900年)と共に1853年にG. シュヴェヒテン社を創業した。
1861年、ゲオルクはKoch通り60番地に工場を建設し、その後隣の不動産も取得した。
G. シュヴェヒテン社のピアノはすぐに大きな名声を得た。
ゲオルクの死後、娘のAnna Maria Clara Fiebelkornが会社を引き継いだ。
彼女はSchwechtenhausを建設した。
ヴィルヘルムの息子フリードリッヒとヴィルヘルム(1880年-1954年)は1910年に
Pianofabrik Schwechten & Boesを設立した。
(1911年からGebr, Schwechten、1912年からFriedrich Schwechten、ヴィルヘルム通り118番地)
1918年、2人とも親会社に戻った。ピアノ生産は1854年に始まり、1925年まで続いた。
シュヴェヒテンピアノは1839年にゲオルク・シュヴェヒテンの兄ハインリッヒの店で始まった。
ゲオルク・シュヴェヒテンは1853年にベルリンで店を構え、優美な手作りピアノを専門とした。
この素晴らしいピアノはゲオルクが死去した1902年に終わった。
「Schwechten」のブランド名は中国の上海鋼琴有限公司(Shanghai Piano Co. Ltd.、1895年創業)
によっても使用されていたが、ドイツのSchwechtenとの関係は不明である。 |
GEORGE ROGERS & SONS




画像クリックでHPへ戻る |
ジョージ ロジャーズ アンド サンズ GEORGE ROGERS & SONS LONDON
イギリス(ロンドン) 詳細不明
ジョージ ロジャーズ アンド サンズの内部外観写真(前パネル部分) →★
ジョージ ロジャーズ アンド サンズの内部外観写真(下パネル部分) →★
ジョージ ロジャーズ アンド サンズのまくり(蓋部分)の銘柄部分の写真 →★
左記画像(上から2枚)と外観写真はすべて「匿名希望様」からご寄稿頂きました。
ご寄稿者様によりますと、このピアノは1927年前後に製造されたもので、工房で一度修復済みとのことです。
小柄ながら100年経った今でも美しい音色を響かせているとのことです。
この度は貴重なお写真のご寄稿を頂きまして誠にありがとうございました! |
GEORGE STECK & CO.
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ジョージ・ステック エオリアン・アメリカン・コーポレーション傘下の系列会社の製品 ニューヨーク
現所有:ピアノディスク社
※MASON & HAMLINの項目も参照
1857年、ジョージ・ステックによって設立されたジョージ・ステック・ピアノ・カンパニーは、
早くから優れた楽器とピアノの品質に定評がありました。
ドイツのカッセル出身のジョージ・ステックは、ニューヨークの12番街と3番街に店を構えた。
約2年後の1859年にはウォーカーストリートに移転し、1904年にステックが亡くなり、
会社が法人化されてエオリアン社に買収されるまで、この場所で営業を続けた。
エオリアン社が生産を引き継いだ後、ジョージ・ステックのピアノブランドは、
1994年にメイソン&ハムリン社の傘下に入るまで、「ステック」ピアノとして知られていた。
1990年代初頭から2000年代にかけて、このブランドの歴史は一連の買収によって特徴づけられた。
2015年までは中国のNanjing Moutrie Piano Co.が製造し、カナダのWelkin Sound Inc.が販売していたが、
現在ではジョージ・ステックのピアノは製造されていない。
ジョージ・ステックが会社を設立したとき、彼はピアノに様々な進歩をもたらすことを思い描いていました。
1890年代に入ると、ステックはアップライトピアノとグランドピアノを製品ラインに導入し、
厳密な正方形のグランドピアノから脱却した。
ステックは音の科学にこだわり、初期のピアノのデザインに多くの変更を加え、
それは現在のアップライトピアノやグランドピアノにも反映されている。
ステックが築き上げたピアノの名声は、時の試練に耐えてきた。
ジョージ・ステックのピアノは、楽器の精密さと高品質なサウンドで知られており、
世界的に有名なピアニストたちに支持され、正確に修復された場合には価値ある楽器となる。
エオリアン社とエオリアン・アメリカン社がこのブランドの生産を開始すると、
ステックのピアノは非常に人気が高まり、今でもヨーロッパでは最も可能性の高い
プレーヤー・ピアノの一つとなっている。
Steck Pianolaは、SteckピアノフレームとPianolaアクションのユニークな両立型である。 |
| GERARD |
詳細不明 |
| GERBSTÄDT |
ドイツ
その他詳細不明 ※検索用:GERBSTADT |
GERHARD ADAM
G. ADAM




画像クリックでHPへ戻る |
G.ADAM ゲルハルト・アダム/アダム・ゲルハルト ADAM GERHARD
ドイツ(ヴェーゼル、ヴェセル/WESEL) 創業1828年
ゲルハルト・アダムのまくり部分(鍵盤蓋部分)の銘柄ブランド部分 →★
※まくり部分にあるGEGR.1828の「GEGR.」とはドイツ語で「設立」という意味です。
トレードマークは「G」と「A」の文字をモチーフにしたとても斬新なデザインで素敵ですね。
左の画像上から3番目にあるSEIT1828の「SEIT」は英語で言う「SINCE」という意味です。
左記トレードマークを含め、ゲルハルドアダムの画像はすべて「鈴木光子様」からご寄稿頂きました。
この度はたくさんの画像のご寄稿を頂きまして誠にありがとうございました!
ご寄稿者様からの情報によりますと、このゲルハルト・アダムが1828年にドイツのヴェセルの生産工場で
ピアノを作り始めた当初は年間100台程度、1900年頃には500台程度生産していたようです。 |
GERHARD HEINTZMAN
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ゲルハルド・ハインツマン カナダ(トロント)
創業1877年
HEINTZMAN & CO.とは別の会社なので混同しないように注意
1866年、ドイツからの移民であった叔父のセオドア・ハインツマンが「ハインツマン社」を設立し、
その後、セオドアの甥が「GERHARD HEINTZMAN」を立ち上げたました。
※HEINTZMAN & COの項目も参照 |
Ger. APOLLO
※下記は参考画像
 |
ゲール・アポロ 東洋ピアノ製造株式会社
※左記トレードマークは参考画像です
実際のGer. APOLLOのトレードマークは、この”TOYO”の部分が”HAND MADE”になっています。 |
GEROG JACOBI
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ドイツ シュトゥットガルト(STUTTGART) 詳細不明 |
GERSHWIN



画像クリックでHPへ戻る |
ガーシュイン/ガーシュウィン GERSHWIN
大岡楽器製作所
白鳥楽器製作所
スワン楽器製造KK(スワン楽器製造株式会社)
ガーシュインピアノ株式会社
東日本ピアノ製造(株)
株式会社 バロック
フローラピアノ製造(株)
大成ピアノ製造株式会社
昭和28年に大岡郁平氏によって大岡楽器製作所が発足し、
ガーシュインのブランドでアップライトピアノが作られました。
その後、稲葉ピアノの後援で白鳥楽器となり、さらにスワン楽器KKと改称され、
昭和42年に東日本ピアノ製造株式会社に改組。
グランドピアノの裏側には国産初のテンション・レギュレーター装置を採用。
アップライトではペダルの重さを調整できる装置も採用。昭和を感じるピアノですね♪
機種:No500、GA-50等
上から2枚目のエンブレム画像は「PIANO YOSHIKAWA様」よりご寄稿頂きました。ありがとうございます!
<参考資料>
東日本ピアノ製造株式会社を含む会社遍歴は下記の通り
昭和28年 大岡楽器製作所が発足
昭和31年 白鳥楽器製作所
昭和33年 スワン楽器製造株式会社
昭和38年 ガーシュインピアノ株式会社
昭和42年 東日本ピアノ製造株式会社
昭和62年 株式会社バロック
ガーシュインのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★ |
| GERSTENBERGER |
詳細不明 |
GERTCHEN
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ゲルトヘン 松本楽器製造株式会社
※似た名称でGARTCHEN(ガルトヘン)というピアノ(シュベスターピアノ製作所)と解説した資料がありますが、
これは「GARTEN」と間違えている可能性があります。詳しくは→「GARTEN」の項目へ |
GERTOHD
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ゲルトード 蒲田楽器製作所 |
| G.E. RUSSELL & SON |
詳細不明 |
| GEVAERT |
詳細不明 |
GEYER
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ガイヤー ドイツ(旧東ドイツ) 詳細不明
|
| GILBERT HOFFMAN |
詳細不明 |
| GILES PIANOS LTD. |
詳細不明 |
| GILLOT-STRAUBE |
詳細不明 |
GIYAN(注意)
※存在しません |
★ご注意★
このピアノブランドは存在しません
令和4年4月6日放送のNHK朝の連続テレビドラマ「カムカムエブリバディ」の放送内で、錠一郎が弾いていた
ピアノ「GIYAN(ギヤン?)」という名称のピアノが出ていたようですが、このピアノは実際には存在しません。
貼られていた「GIYAN」というシールの下はおそらく「YAMAHA」という文字だったと推測されます。
理由は皆様ご存知の通り、NHKは放送法により民間企業の営業広告が禁じられているためです。
※元ネタがGYANというモビルスーツ(機動戦士ガンダム)的な話もありますが、当方まったく分かりません。
GIYANピアノに関するお問い合わせがあったので、敢えてここに載せております。 |
GLASER
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ドイツ 読み方不明、詳細不明
|
| GLASS & CO. |
詳細不明 |
| GLENZ (JOSEF) BRESLAU |
詳細不明 |
GLORIA
※下記は参考画像です

画像クリックでHPへ戻る |
グロリア 発売元:クニユキピアノ株式会社 製造元:不明
※トレードマークは参考画像です
このトレードマークはKREUTZER(クロイツェル)のものですが、
この文字部分が”GLORIA”になっている以外はほぼ同じです。何故同じかは不明。 |
GLORIOUS

トレードマークなし |
グロリアス/(グローリアス)
第一楽器工芸株式会社(浜松)
新東海楽器製造株式会社(浜松)
アトラスピアノ製造株式会社
新東海楽器(浜松)だが、第一楽器(浜松)で作ったこともある。
|
| GLOS & PFLUG, WIEN |
詳細不明 |
| GODFREY |
詳細不明 |
| GOETZE & CO. |
詳細不明 |
| GOETZE-GROSS |
詳細不明 |
GOLD STAR
 
画像クリックでHPへ戻る |
GOLDSTAR/GOLD STAR ゴールドスター 東海楽器製造(株)
ピアノを製造していた頃の東海楽器株式会社についての詳しい解説は「TOKAI」の項目へ
機種:120-G等
<東海楽器が製造したブランドを列挙いたします>
■ TOKAI(トーカイ)
■ BOLERO(ボレロ)
■ SILBER STEIN(シルバースタイン)
■ HUTTNER(ヒュッツナー)
■ GOLD STAR(ゴールドスター)
ゴールドスターのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★ |
GOODWAY
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
グッドウェイ 詳細不明
|
| GORDON & BAILEY |
詳細不明 |
GORDON LAUGHED

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
GORDON LAUGHEAD ゴードン・ローヘッド製造(ミシガン州グランドヘブン)
三代続いた個人企業のピアノメーカーです。
ミシガン州のグランドヘブンにあり、アップライトピアノと学校用の楽器を主として製作。
このメーカーのブランドには、社名と同じゴードン・ローヘッドの他に、
カーツマン/(クールツマン)KURTZMANNと呼ばれるブランドがあります。
ピアノ業界では一般的にそのピアノの創始者の名称が用いられることが多い中、
このピアノメーカーは例外で、社内のマネージャーの名前が使われています。
|
|
GORS & KALLMANN
GÖRS & KALLMANN


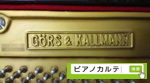
画像クリックでHPへ戻る
|
ゲルスカルマン/ゲルス・カルマン/ゲルス・アンド・カルマン/(グロスカールマン)
GÖRS & KALLMANN (GORS KALLMANN)
製造:大成ピアノ製造株式会社
販売:昭和楽器OEM
機種バリエーション GK2000、GK3000など
ドイツ(旧西ドイツ)製にも同じ名前(R.GÖRS & KALLMANN)がありますがまったく違います。
音色・作りは同じ大成ピアノで作っていたローレックスKR27等に近い感じです。その他詳細不明。
ピアノ天板をあけると裏に貼ってある昭和楽器の品質保証シール
(作ったピアノすべてに貼ってるとは思いますがね) →★
<参考1>
H. GÖRS & KALMANというアトラスピアノ製造が作っていたピアノもあり(→スペル内のLとNが1個)
<参考2>
トレードマークのデザインは、大成ピアノ製造(同社製)である「ORGAST HOLSTER」
オーガスト・ホルスターという別ブランドとほぼ同じデザインです。
ゲルスカルマンのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★ |
GORS & KALLMANN
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ゲルス ウント カールマン
R. GORS & KALLMANN (GORS KALLMANN)
ドイツ(旧西ドイツ)ベルリン 詳細不明
※大成ピアノ製造の”GÖRS & KALLMANN”とは違うピアノです |
| GÖRS & SPANGENBERG |
詳細不明 |
| GOTHA |
詳細不明 |
| GOTZMANN |
詳細不明 |
| GOURLAY |
詳細不明 |
| GRAF, CONRAD |
詳細不明 |
| GRAF, HERMANN |
詳細不明 |
| GRAND |
詳細不明 |
| GRANDE |
詳細不明 |
GRANFEEL
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
グランフィール 有限会社 藤井ピアノサービス |
|
GRATIAE


画像クリックでHPへ戻る
|
パコピアノ/グラチアピアノ
PACO/GRATIAE 製造:北朝鮮 (有)PACO
この会社は日本製ピアノの会社ではなく日本人技術者が日本製の工作機械を使い
北朝鮮でピアノを製造していたようです。最終調整は日本国内で行い出荷。
日本法人のこの会社と北朝鮮政府との合弁会社にて
日本人技術者他の技術指導・輸入販売を行っていたようです。
ブランドはGRATIAE(グラチア)という低価格のアップライトのみ。
当時本社は東京都府中市にあって販売は国内のみでなく、
アジア・ヨ-ロッパにも輸出していたという情報あり。
1台しか調律したことがないので詳細は不明ですが、
ピアノ自体は ”北朝鮮”というイメージほど悪くはなかったです。
その他詳細不明。
機種バリーエション:PU120等
グラチアピアノのまくり(フタ部分)にあるブランド銘柄マーク
→★
パコ、グラチアのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★ |
| GRAU, F. |
詳細不明 |
GREIFEN

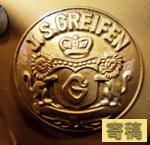

画像クリックでHPへ戻る |
GREIFEN (J.S.GREIFEN) グライフェン/グライフン
詳細不明 GREIFENとはドイツ語で「~をつかむ」、「~をつかまえる」という意味
GREIFENピアノのまくり(蓋)部分の銘柄マーク →★ GREIFENピアノ外観写真 →★
※これらの画像はすべて nosuke様からご提供頂きました |
GREIG
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
グリーグ (株)クニユキピアノ商会 神田須田町のピアノ店の国行重槌氏。
|
| GRIMM |
詳細不明 |
GRINNELL BROS.

画像クリックでHPへ戻る |
DETROIT MICH-WINDSOR ONT(Ontario)
詳細不明
画像は「匿名希望様」からご寄稿頂きました。ありがとうございます! |
GROLIA
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
グロリア (株)クニユキピアノ商会 神田須田町のピアノ店の国行重槌氏。
|
GROSS STEIN


画像クリックでHPへ戻る |
GROSS STEIN グロス・スタイン (グロススタイン)
発売元:青池楽器店(青池ピアノ店)
当時の青池ピアノ店の住所:千代田区神田一ツ橋2-3(住所遍歴その後→千代田区神田神保町救世軍横)
製造元:シュベスターピアノ製造株式会社(協信社ピアノ製作所と渡辺塗装が共同で製作開始)
グロススタインピアノは一度解散していた協信社ピアノ製作所の松崎妙氏(読み:まつざき かのお)氏と
渡辺塗装社が昭和8年に共同でピアノ製造を始めた。発売元は青池楽器店だった。
昭和11年、銀座伊東屋7階の全国ピアノ技術者協会主催の「躍進 国産ピアノ展覧会」に出品された。
この「躍進 国産ピアノ展覧会」は通称「第一回ピアノ展示会」とも言われますが、この展示会には国内の
13社、計22台のピアノが出品され、グロススタイン(20型)が青池楽器店から出品されました。
松崎氏は終戦の年である昭和20年、協信社ピアノ製作所から株式会社 協信社ピアノ製作所に改組設立。
その際、販売部門としてシュベスターピアノ販売株式会社を設立し、青池楽器店との取引を終了した。
青池楽器店との取引は約10年ほどだったとの記録が残っております。
当時のシュベスターピアノ販売株式会社の住所:港区新橋4-24
トレードマーク画像にはいろいろ文字が入っておりまして、入っている文字を紹介致しますと、
「Gross stein Piano」 「AOIKE PIANO TEN」 「KANDA TOKYO」と入っています。
トレードマークは珍しく金属製の後付けのようで、マイナスボルト2本で鉄骨に取り付けてあります。
左記画像ですと文字が小さくて見づらいので拡大画像も一応載せておきます →★
グロススタインの鍵盤蓋部分にある銘柄ブランド名部分の写真 →★ ピアノ全体写真 →★ →★
とても重厚な雰囲気のピアノですね。ご寄稿者様によりますと戦前に作られたピアノとのことです。
これらの画像はすべて「匿名希望様」からご寄稿頂きました。この度は写真のご提供ありがとうございました! |
GROTRIAN

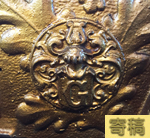
画像クリックでHPへ戻る |
GROTRIAN (GROTRIAN-STEINWEG)
グロトリアン (グロトリアン・スタインウィッヒ/グロトリアン・シュタインヴェーク)
ドイツ(旧西ドイツ) ボルフェンヴュッテル 創業1835年。
ヨーロッパの王室でも使われ、あのクララ・シューマンが、「今日からはこのピアノしか弾かない」と
言ったことでも知られており、愛用していたと伝えられている。
今も変わらずドイツ最高のピアノブランドのひとつであるグロトリアン・シュタインヴェーク社は、
ゲオルク・フリードリヒ・カール・グロトリアンと、スタインウェイ王朝の創始者ハインリヒ・
シュタインヴェークとの協力から始まった。ふたりはグロトリアンのデザインをもとに、1835年に
最初のピアノを共同で製作したと伝えられている。
グロトリアン・シュタインヴェーク社の現従業員の約半数がピアノ製造技師であり、
その特別な見習いプログラムによって、この会社の高い技術水準は将来へと受け継がれている。
独創的な『デュオ・コンサートグランド』は、二台のピアノを1枚の大屋根で結合したピアノで、
二台のグランドは取り外し可能なリム(側板)と、間の隙間を埋めるブリッジ状の響板で接続される。
二台のグランドは簡单に切り離すことができ、一台一台個別の屋根にして独奏楽器としても演奏できる。
アップライトピアノの背面構造の設計はアスタリスク形状になっており、弦張力に対抗する力がすべて
中心の一点に集まることにより、調律の安定性を高めている。
そしてその歌うような音色から、「シンギングトーン」と称されてている。
<歴史>
ビジネスに関心を持ったグロトリアンはモスクワに小売店を開いて成功した。
10年後に母国ドイツへ帰ったグロトリアンは、ハインリヒ・シュタインヴェークの息子、
カール・フリードリヒ・テオドール・シュタインヴェークとピアノ製作の共同契約を結ぶ。
ふたりはブラウンシュヴァイクへ生産拠点を置き、高品質のピアノを製作する優れた会社を設立した。
一方、ハインリヒ・シュタインヴェークはそのころアメリカへ移住して名前をスタインウェイに改め、
自身の会社を設立していた。1865年にふたりの弟が病死すると、テオドール・シュタインヴェークは
自社の株を売って、アメリカへ渡り、繁盛していたスタインウェイ社の経営に就いた。
フリードリヒ・グロトリアンはその2年後に亡くなり、会社は息子のヴィルヘルムに委ねられた。
ヴィルヘルムは株主A.ヘルフェリヒ、H.シュルツとともに、シュタインヴェークを含む
さまざまなブランド名でピアノを生産した。
会社は着実に成長していき、1920年には、1,000人の従業員が年間1,600台の楽器を生産するまでになった。
1917年にヴィルヘルム・グロ卜リアンが亡くなると、息子のヴィリとクルトが会社の経営を引き継いだ。
兄弟は、「良いピアノを作ってさえいれば、後のことは何とかなる」 という父の教えを肝に銘じ、
良質の職人技を守り抜いた。1919年に社名が正式にグロトリアン・シュタインヴェークとなり、
その社名をめぐってスタインウェイ社と法的に争ったりはしたが、1927年には生産高が3,000台にまで増大した。
それから1931年に大恐慌による打撃を受け、年間700台まで生産高は落ち込んだ。
戦時中はやむなく閉業し、戦後グロトリアン・シュタインヴェーク社がピアノの生産を再開できたのは
1948年になってからだった。
爆撃された工場を再建し、伝統のピアノ製法を復活させるにはそれなりの時間を必要とした。
1954年には良質のピアノメーカーとしての地位が回復し、会社は若いピアニストを支援するために、
グロトリアン・シュタインヴェーク・コンクールを設立した。
そして1974年、グロトリアン・シュターンヴェーク通りに最先端の設備を誇る新工場が完成した。
グロトリアン社の6代目クヌートは息子ヨプストの協力のもと、現在この場所で会社を指揮している。
※スタインウェイ・アンド・サンズとの「Steinweg」に対する商標権問題で、ドイツ以外への輸出に於いては、
GROTLIANのブランド名を使用している。
グロトリアンはスタインウェイの血縁とも言えるが、楽器の構造はかなり異なる。
グロトリアンピアノはBVK認証を受けています(詳しくはこちら
→★)
<附録>
グロトリアン・シュタインヴェークピアノ 製造番号/製造年代 対照表(1865年~2001年) →★
<以下、ウィキペディアより引用抜粋>
グロトリアン=シュタインヴェーク(Grotrian-Steinweg)は、ドイツの高級ピアノ製造会社である。
欧州外ではグロトリアンと呼ばれる。ドイツ・ブラウンシュヴァイクに本社がある。
グロトリアン=シュタインヴェークは高級グランドピアノとアップライトピアノを製造している。
同社の起源は1835年にゼーゼンのハインリッヒ・シュタインヴェーク(後のヘンリー・スタインウェイ)
が設立したピアノ工房にある。したがって、世界で最も古いピアノ製造会社の一つであり、
2015年に香港の柏斯琴行(Parsons Music Group)によって買収されるまでは
グロトリアン=シュタインヴェーク家が所有していた。
グロトリアン=シュタインヴェークの歴史は、ハインリヒ・エンゲルハルト・シュタインヴェーク
(米国への移住後にヘンリー・スタインウェイと改名し、スタインウェイ・アンド・サンズを創業した)
によって最初のシュタインヴェークのピアノ工場が建設された1835年に遡る。
1856年、フリードリヒ・グロトリアンがパートナーとなった。
1865年、フリードリヒの息子ヴィルヘルム・グロトリアンと2人の共同出資者が工場と
シュタインヴェークブランドの後継としてピアノを販売する権利を買い取った。
グロトリアン家のその後の世代が会社をドイツで最高級のピアノ製造会社にした。
グロトリアン=シュタインヴェークのピアノは一部の高名なピアニストによって好まれ、
シカゴ・コロンブス万国博覧会(1893年)にて称賛を得た。
グロトリアン=シュタインヴェークはオーケストラとコンサートホールを運営し、ドイツの6都市、
そして1920年までにロンドンに販売店を設立した。
1920年代末の最盛期には、グロトリアン=シュタインヴェークは1000人の従業員を雇用し、
年間3千台のピアノを製造した。
1930年代の不景気と1940年代の戦争によって、グロトリアン=シュタインヴェークはひどく衰退し、
その後工場を完全に失った。グロトリアン家は工場を再建し、高品質な仕事でその評判を取り戻した。
1950年代には、有望な若いピアニストを見つけるために年1回のピアノ演奏コンクールを創設した。
グロトリアン=シュタインヴェークは1960年代中頃に米国で事業を拡大しようとした。
スタインウェイ・アンド・サンズ(Steinway & Sons)はシュタインヴェーク(Steinweg)の
名称の使用を差し止める訴えを起こし、その結果合衆国第2巡回区控訴裁判所にて1975年に判決が下された。
この訴訟は、グロトリアン=シュタインヴェークというブランドはピアノ購買者がそのブランド名と
スタインウェイ・アンド・サンズのブランドを一時的に混同する原因となる、という「購買前の混同」を
説明する先例となった。裁判所はグロトリアン=シュタインヴェークに米国での「シュタインヴェーク」という
名称でのピアノの販売を差し止める命令を下した。
その後、グロトリアン=シュタインヴェーク社は北米でピアノを販売するために
グロトリアン・ピアノ・カンパニーと命名した企業を設立した。
■19世紀
1803年1月13日、ゲオルク・フリードリヒ・カール・グロトリアンはドイツ・シェーニンゲンで生まれた。
フリードリヒは1830年頃に始めたピアノの販売のためにモスクワに居を定めた。
その後、サンクトペテルブルクに拠点を置いた小さなピアノ製造会社との共同経営会社に参加し、
これらのピアノをモスクワで成功した楽器店で販売していた様々な楽器に加えた。
ドイツでは、ハインリヒ・エンゲルハルト・シュタインヴェーク(1797年-1871年)が1835年に
ハルツ山地の端のゼーセンにある自宅からピアノの製造を始めた。
ハルツ山地はピアノに使われる上質なブナノキとトウヒの産地であった。
最初の年に生産したピアノの中に、フリードリヒ・グロトリアンによって設計され、
シュタインヴェークが作ったスクエア・ピアノがあった(この楽器は現在ブラウンシュヴァイク博物館にある)
シュタインヴェークは1839年のステート・フェアに3台のピアノを出品した。
その内2台はスクエア・ピアノだったが、グランドピアノが広い注目を集めた。
1850年、シュタインヴェークは大家族のほぼ全員と共にニューヨークへ移住した。
ピアノ工場は長男のC・F・テオドール・シュタインヴェーク(1825年-1889年)に残され、
テオドールは自身の名前で経営を続けた。
その頃、ニューヨークでは、シュタインヴェーク家は米国風に姓をスタインウェイと改め、
1853年にピアノ製造会社スタインウェイ・アンド・サンズを創業した。
父の古い工場の経営権を引き継いでから間も無く、C・F・テオドール・シュタインヴェークは
ブラウンシュヴァイク近くのヴォルフェンビュッテルに移った。
ここで、テオドールは商売のために旅行していたフリードリヒ・グロトリアンと出会った。
1854年、フリードリヒ・グロトリアンは叔父からの遺産としてMüller-Mühlenbein pharmacyを受け取り、
その経営のためにドイツへ戻った。
グロトリアンは1856年にC・F・テオドール・シュタインヴェークのピアノ会社に共同経営者として加わった。
1857年、C・F・テオドール・シュタインヴェークとグロトリアンはピアノ工場をブラウンシュヴァイクへ移し、
街の中世部のBohlwe通り48にある元市長の屋敷に店を構えた。
会社は当時約25人の従業員を雇った。フリードリヒ・グロトリアンは1860年12月11日に死去し、
会社の株式は息子のヴィルヘルム(1843年)に残された。
1865年、C・F・テオドール・シュタインヴェークは兄弟のヘンリーとチャールズの死後に
スタインウェイ・アンド・サンズの経営を助けるためにニューヨークの家族に必要とされた。
ヴィルヘルム・グロトリアンはC・F・テオドールの工場の株式を買い取るために2人のピアノ職人
Adolph HelfferichとH.D.W. Schulzと手を組んだ。
新たな共同経営会社は「テオドール・シュタインヴェークの後継者」を意味する商標
「C.F. Th. Steinweg Nachf.」を使用するための権利の代金を支払った。
(Nachf. はドイツ語で後継者を意味する "Nachfolger" の省略形)
会社名は「Grotrian, Helfferich, Schulz, Th. Steinweg Nachf.」となった。
ヴィルヘルム・グロトリアンは1870年代に2人の息子ヴィルヘルム・"ヴィリ"・グロトリアンJr
(1868年-1931年)とクルト・グロトリアン(1870年-1929年)を育てた。
ニューヨークでは、C・F・テオドール・シュタインヴェークはC・F・セオドア・スタインウェイに改名し、
スタインウェイ・アンド・サンズに15年間トップおよびチーフ・テクニシャンとして働いた。
セオドアは米国での生活を好きではなく、ブラウンシュヴァイクの自宅を持ち続けており、
随時行ったり来たりしていた。1880年、セオドアは海を超えた渡航を止め、父親の古い会社
(現在のグロトリアン=シュタインヴェーク)と対抗して、欧州の顧客のためにピアノ製造する
新しいスタインウェイ・アンド・サンズのピアノ工場をハンブルクで始めた。
事業を立ち上げ後、セオドアは引退して晩年をブラウンシュヴァイクで過ごした。
セオドアは1889年に死去し、彼のピアノコレクションは市の博物館へ寄贈された。
ハンブルク工場はグロトリアン=シュタインヴェークと競い合って成功を収めた。
どちらの会社も高級ピアノを生産することで知られていた。
1880年代、ヴィリ・グロトリアンは米国メリーランド州ボルチモアのWm. クナーベ& Co.と
フランス・パリのプレイエル, ヴォルフ et Cieでピアノ製造を学んだ。
クルト・グロトリアンもまたその他の国々のピアノ製造会社で学んだ。
彼らの父ヴィルヘルム・グロトリアンSr. は1893年にヴィリをシカゴへ連れていった。
シカゴで開催されたコロンブス万国博覧会でグロトリアン=シュタインヴェーク社のピアノは
メダルを授与された。ピアニストのオイゲン・ダルベール、イグナツィ・パデレフスキ、
クララ・シューマンはグロトリアン=シュタインヴェークのピアノを好むと表明した。
グロトリアン=シュタインヴェークはベヒシュタイン、ブリュートナー、フォイリッヒ、
イバッハ、リップ、スタインウェイのハンブルク工場と共にドイツのトップピアノ製造会社に数えられた。
1895年、ヴィルヘルム・グロトリアンSr は2人の息子を共同経営者とした。
父は息子達に「いいピアノを作りなさい、残りはすべて後からついてくる」という社訓を残した。
ヴィリ・グロトリアンは、グロトリアン=シュタインヴェークがピアノ生産に使うシステムと
スタンダードの改善を系統的に始めた。
グロトリアン=シュタインヴェーク・ブランドは最高品質のものとしてよく知られた。
会社は30の帝室・王室の御用達の称号を得た。
所有者のヴィルヘルム・グロトリアン、ヴィリ・グロトリアン、クルト・グロトリアンは
オーストリア=ハンガリー帝国帝室・王室御用達を授与された。
■20世紀
ブラウンシュヴァイク(Braunschweig)において、グロトリアン=シュタインヴェークは1913年までに
500人の従業員を抱えるまで成長し、毎年約1600台のピアノを生産した。
グロトリアン=シュタインヴェークオーケストラは若い指揮者ヘルマン・シェルヘンの指揮の下
ライプツィヒで活動した。グロトリアン専門店がライプツィヒ、ハノーファー、ケーニヒスベルク、
デュッセルドルフ、ベルリンで営業していた。
第一次世界大戦中、クルト・グロトリアンはドイツ陸軍の軍務に服するため工場を離れた。
クルトは程なくして負傷し、捕虜となった。ヴィルヘルム・グロトリアンは1917年に死去した。
息子のヴィリ・グロトリアンが会社を率いたが、労働力とピアノの注文は大幅に減少した。
戦後、会社は以前のように回復し、グロトリアン=シュタインヴェークのブランド名の下で
ロンドン店を立ち上げることによって1920年に売り上げを延ばした。従業員は1000人に増えた。
1924年、グロトリアン=シュタインヴェークは微分音音楽作曲家イワン・ヴィシネグラツキーのために
特殊なピアノを製造した。このピアノは3段の手鍵盤と四分音離れて調律された弦を持っていた。
1927年まで、グロトリアン=シュタインヴェークは毎年約3000台のピアノを作っていた。
この数字は世界恐慌の間の1930年代に著しく落ち込んだ。1931年には500台未満のピアノしか作られず、
従業員は200人未満に減った。
クルト・グロトリアンは1920年代末に重病を患らい、1928年に2人の息子エルヴィン(1899年-1990年)と
ヘルムート(1900年-1977年)を株主にした。
1929年、クルト・グロトリアンは古い戦傷の合併症により死去した。
ヴィリ・グロトリアンは1931年に死去した。
第二次世界大戦中、グロトリアン=シュタインヴェークの工場は(ドイツの多くの他社と同様に)
航空機の組立部品に転向するよう命令された。工場は1944年のブラウンシュヴァイク爆撃によって破壊された。
街の中心部にあった創業者の屋敷も同様に破壊された。
その後、エルヴィンとヘルムートは工場を再建した。1948年までに生産は再開した。
作曲家でピアニストのヴィルヘルム・ケンプは戦後に製作されたピアノの「響きと精緻な出来栄え」の
称賛者として録音を続けた。
■商標争い
商標に関する2つのピアノ製造会社間の最初の摩擦は1895年に起こった。
1895年、スタインウェイ・アンド・サンズはグロトリアン=シュタインヴェークがピアノに関して
「シュタインヴェーク」という名称の使用を止めるよう提訴した。スタインウェイは裁判に破れたが、
1919年1月、ヴィリとクルト・グロトリアンはさらなる訴訟を防ぐことを期待して、家業の商標を守るために
姓をグロトリアン=シュタインヴェークに変更する決断をした。
1925年、会社はグロトリアン=シュタインヴェークカンパニーと呼ばれるデラウェア州法人として
米国での販売事業を立ち上げた。
続く3年間でグロトリアン=シュタインヴェークが米国で販売したピアノはわずか15台であった。
1928年にピアノの販売を発見すると、スタインウェイ・アンド・サンズは販売代理店と
グロトリアン=シュタインヴェークに抗議したが、1929年にグロトリアン=シュタインヴェークは47台の
ピアノを米国へ送った。スタインウェイ家の代表者はグロトリアン=シュタインヴェーク家と
この問題について直接話し合うためにドイツへ赴いた。
秘密協定が合意に達すると、両家の代表者は「友好の葉巻」を吸い、グロトリアン=シュタインヴェークは
それ以降米国での「シュタインヴェーク」および「グロトリアン=シュタインヴェーク」の名称の使用を止めた。
1930年、デラウェア州法人は 解散し、続く3年間でグロトリアン=シュタインヴェークから米国への輸出は減少、
その後完全に中止した。
1950年、グロトリアン=シュタインヴェークは(使われることのなかった)1926年の古い商標出願を放棄した。
1961年、クヌート・グロトリアン=シュタインヴェーク(1935年生)が会社に加わった。
1966年、グロトリアン=シュタインヴェーク社は米国でのピアノ販売のためにウーリッツァーと契約を結び、
スタインウェイ社はニューヨーク州で訴訟を起こした。裁判は9年続いた。
1975年、合衆国第2巡回区控訴裁判所は、
「Grotrian, Helfferich, Schulz, Th. Steinweg Nachf. 対Steinway & Sons」の陳述を聴取した。
原告のグロトリアン=シュタインヴェークは彼らのブランド名は長く確立したものであり、
ドイツにおいてスタインウェイのブランド名より前から存在する、と主張した。
被告側のスタインウェイ・アンド・サンズは、米国においてよく知られ強く確かである彼らのブランド名が
消費者の混同によって弱められた、と反訴した。
控訴審は、ピアノ購買者は2つのピアノブランドがあることで「購買前の興味」において誤って導かれることになり、
「潜在的なスタインウェイの購買者はスタインウェイよりも優れていないにしても少なくとも良い商品である
グロトリアン=シュタインヴェークのピアノで満足するかもしれない」として
被告側を支持した下級審の判決を支持。
控訴審は、米国では非常によく知られたブランドではないグロトリアン=シュタインヴェークは
スタインウェイ・アンド・サンズが築いてきた確固たる評判に基づいて一定の余分な信頼性を不当に得ている、
と考えた。高級ピアノの購買者が洗練され博識であると理解され、購買時にどの製造会社がどのピアノを
製造しているかに関して混同していなかったとしても、グロトリアン=シュタインヴェークのブランドに対する
最初の関心時に「意識下の混同」が存在するかもしれない、と控訴審は考えた。
グロトリアン=シュタインヴェーク社は1977年以後「シュタインヴェーク」の名称を使った米国での
ピアノの販売を禁止された。その結果、1976年にグロトリアン=シュタインヴェークは北米でピアノを
販売するための補助的なブランドとしてグロトリアン・ピアノ・カンパニーGmbHを作った。
裁判は現在「購買前の混同」として知られる概念を定義した初の裁判例であった。
地方裁判所判事ロイド・フランシス・マクマーンは「購買前の混同へと欺いて導かれ、
潜在的なスタインウェイの購買者はスタインウェイよりも優れていないにしても少なくとも良い商品である
グロトリアン=シュタインヴェークのピアノで満足するかもしれない」と述べた。
「購買前の」混同に関するロイド・フランシス・マクマーンの考えは控訴審判事ウィリアム・H・ティンバース
によって追認された。ティンバースは「こういった購買前の混同はスタインウェイに損害を与える」と述べた。
グロトリアンのウェブサイトの英語版は、フランス語版、ドイツ語版、ロシア語版とは異なり、
「シュタインヴェーク」という姓に一切言及していない。これはおそらく訴訟の結果であり、
法的責任を最小化したいという願望のためであろうとも考えられる。
■現在の業務
1974年、グロトリアン=シュタインヴェーク家はブラウンシュヴァイク北東部に新たな工場を建設した。
ヘルムートとエルヴィン・グロトリアン=シュタインヴェークは引退し、ヘルムートの息子クヌートが
トップとなった。この工場が現在のグロトリアン=シュタインヴェークの生産拠点である。
1999年、クヌート・グロトリアン=シュタインヴェークは社の指揮から退き、日常的な管理を
ブルクハルト・シュタイン(インダストリアルマネージャー、ピアノ職人)の手に委ねた。
2012年時点で、グロトリアン=シュタインヴェーク社はエルヴィン・グロトリアンの娘とクヌートの息子で
株主の6代目ヨブスト・グロトリアン(1969年生)によって所有されている。
毎年、グロトリアン=シュタインヴェーク社は6種類のサイズのアップライトピアノ約500台と5種類のサイズの
グランドピアノ約100台を生産している。毎年20台程のコンサートグランドピアノが作られており、
その製造にはそれぞれ8か月を要する。2010年、特別な175周年モデルとして「Composé Exclusif」と呼ばれる
118cmのサイズのアップライトピアノを発表し、50台が生産された。
2015年4月1日、柏斯琴行(Parsons Music Group、香港を拠点とする1986年創業の企業)が
グロトリアン=シュタインヴェークの株式の大半を取得した。
2017年、第2ブランドfriedrich GROTRIAN(フリードリッヒ・グロトリアン)が作られた。
このブランドのリム、鋳鉄フレーム、響板は中国(Parsons Music)で作られ、最終的な組み立て、
アクション組込み、仕上げがドイツで行われる。アクションは大部分がレンナー社製が使われている。
2018年以降、製造が完全に中国で行われる第3ブランドとして
WILHELM GROTRIAN(ヴィルヘルム・グロトリアン)と
WILHELM GROTRIAN STUDIOが存在する。
前者は高さが46インチから52インチの間のアップライトピアノ4モデルと、
長さが5フィートから6フィート11インチの間のグランドピアノ3モデルである。
WILHELM GROTRIAN STUDIOブランドは、アップライトの高さが45 1/2インチから48インチ(3モデル)と
グランドピアノの足さが5フィートまたは5フィート5インチ(2モデル)である。
グロトリアンのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★ |
GROTORIAN & SONS


画像クリックでHPへ戻る |
GROTORIAN & SONS グロトリアン・アンド・サンズ
ドイツの「GROTRIAN」(グロトリアン)とは似ても似つかぬ全く別のピアノです。
本場ドイツ製のあの有名なグロトリアンとは違い、スペルをわざと1文字変えています。
ドイツ製グロトリアンのスペルは「GROTRIAN」ですが、こちらは「GROTORIAN」になっています。
「O(オー)」が1文字多く入っているのが分かると思います。
※同様の例として挙げられるのは、あのドイツの名高き「BECHSTEIN」ベヒシュタインの文字を1文字変えた
「BACHSTEIN」(バッハシュタイン/バハシュタイン)などと同様の商売と思われます。
こちらは「E」を「A」にわざと変えているケースですね。
今となってはとても信じられない行為ですが、実は過去のピアノ業界ではよくあった話です。
ピアノ所有者ご本人もまったく悪気なく本当にドイツ製と思い込んでいることもよくあります。
販売元が当初そのように説明し販売していたのが全ての責任ではあるのですがご注意下さい。
雰囲気的には韓国製っぽいですが、詳細はまったく不明。
トレードマーク画像はローゼンクランツ(ROSENKRANZ)やシュベルマン(SCHWÄLMEN)と同じなので、
アイケー・ピアノ社販売時のピアノなのか?詳細は今のところ不明です。 |
| GROVER |
詳細不明 |
| GRUNERT |
詳細不明 |
GRUNEWALD
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
グルーネバルト ドイツ(旧西ドイツ) 詳細不明
|
GUILBERT

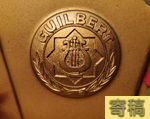

画像クリックでHPへ戻る |
ギルバート
プルツナーピアノ製造(株) 当時の住所:浜松市(南区)本郷町1366-16
→詳しくはプルツナー(PRUTHNER)の項目へ
機種バリエーション:GU133等(ピアノ内部の鉄骨部はG133Dとなっております)
<参考>
トレードマーク内の星形は調律に使うチューニングハンマーの差し込みチップの形をモチーフにしています。
この形をモチーフにしている他のピアノは多数ありまして、たとえばカールザイラー、ワグナー、レスター、
キャッスル(鈴木ピアノ)等がトレードマークにこの星形をモチーフにした形を使っております。
ギルバートピアノのまくり(蓋部分)の銘柄ブランドマーク →★
ギルバートピアノのま鍵盤抑えに貼ってあるプルツナーのシール →★
左記トレードマーク画像をはじめ、ギルバートの画像はすべて「むにと様」からご寄稿頂きました。
この度は多数の画像をご寄稿頂きまして誠にありがとうございました!
|
GULBRANSEN
Gulbransen & Dickenson Co.


画像クリックでHPへ戻る |
グルブランセン/(ガルブランセン) 1904年 アメリカ(ニューヨーク)
1904年、Axel G. Gulbransenは、パートナーと共にイリノイ州シカゴで会社を設立した。
わずか数年後にはディアフィールドに移転し、レギュラーサイズのアップライト・プレーヤーピアノを
提供する唯一のメーカーとして早くからプレーヤーピアノの生産を開始し、10年近くにわたって
プレーヤーピアノのアクションのみに注力した。
プレーヤーピアノは、1906年に設立されたガルブランセン&ディケンソン社を名乗っていた。
プレーヤーピアノに続いて、グルブランセン社は1957年に業界初の電気オルガンを発売した。
当時のキャッチコピーは「So easy, a baby could do it!」であった。
1964年、ガルブランセン社はゼーバーグ社に買収され、5年後の1969年にはアコースティックピアノの
製造を完全に中止した。ゼーバーグの傘下に入ると、同社は業界初のリズムマシンの1つである
「Seeburg/Gulbransen Select-A-Rhythm」を発売し、シンバルやドラム、その他のビートなど
様々な音を模倣できるように設計されていた。
20世紀の残りの期間は、一連の買収が同社を特徴づけた。
現在では、電子キーボードやオルガンにグルブランセンの名前が見られる。
トレードマーク画像は「匿名希望様」からご寄稿頂きました。ありがとうございます!
グルブランセン社は、プレイヤー・ピアノや電子オルガンのアンプを真空管から
トランジスタに変更した先駆者である。
1900年代半ば、ガルブランセンはこの新しい電子技術に対応した数少ない企業の一つであり、
以下のようなスタンダードとなる多くの革新的技術に貢献しました。
■世界初のトランジスタ・オルガン
■世界初の内蔵型レスリー・スピーカー・システム
■初のチャイムストップ
■初のピアノストップ
■初の自動リズム(実際には、ガルブランセン社が合併したゼーバーグ社が担当した
■初の自動ウォーキングベース
ガルブランセン社のオルガンの中で最も有名なのがリアルトKで、
61音のマニュアルが2つ、25音のペダルボードが付いている。
現在でも教会やスタジオなどで多く使用されている。 |
| GUNTHER, J. |
詳細不明 |
| GUNTHER & SOHNE |
詳細不明 |
| GUSTAFSON & LJUNGQVIST |
詳細不明 |
上記Gから始まるブランドの中で、追記出来そうな事項や新情報を発見した場合、修正受付フォーム よりお気軽にお知らせ下さい。
どんな些細な情報でも構いませんので、広く皆様からのフィードバックをお待ちしております。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
 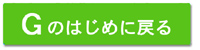 



ピアノ銘柄ブランド
トレードマーク 紹介
& 知名度ランキング

|

メーカー/ブランド説明・会社沿革・歴史・製作者・特徴・音色・他
|
| H, CHALLEN |
CHALLENの項目参照
|
H. GÖRS & KALMAN
H. GORS & KALMAN

画像クリックでHPへ戻る |
エイチ・ゲルス&カルマン アトラスピアノ製造株式会社
GÖRS & KALLMANNという大成ピアノ製造株式会社(販売:昭和楽器)もありますので注意。
こちらのアトラスピアノ製造の方は、”L”と”N”がそれぞれ1個でスペルが違います
|
H. HERZ
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
フランス(パリ) 詳細不明 |
| H. KOHL |
詳細不明 |
H. MATSUMOTO


画像クリックでHPへ戻る |
H.MATSUMOTO エチ・マツモト/エイチ・マツモト (エチ・松本)
何故かこの頃は”H”のことを、現在のように”エイチ”とは呼ばず、”エチ”と呼んでおります。
製造元:松本ピアノ工場(東京月島)
松本ピアノが故あって二つに別れたとき、長男の広氏の”H”をとって付けたピアノ。
トレードマーク内部の文字に、”H”と”M”をモチーフにしたデザインを使っている。
父、新吉氏のS・マツモトもある。
トレードマーク画像は「匿名希望様」からご寄稿頂きました、ありがとうございます!
※ 松本ピアノの詳しい歴史については、MATSUMOTO & SONSの項目もご参照下さい |
H. ORGASTHOLSTER
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
エイチ・オーガストホルスター アトラスピアノ製造株式会社 |
H. PETERS & CO.
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ペータース
ドイツ/ライプツィヒ(LEIPZIG) 詳細不明
※ペータース (Peters)というドイツ発祥の楽譜出版社もあるが楽器であるペータースピアノとの関係は不明。
ちなみにこの楽譜出版社はドイツのライプツィヒ、イギリスのロンドン、アメリカのニューヨークに拠点を持つ。
もしペータースピアノとペーターズ楽譜出版社の関係があるとの情報があれば是非お知らせ下さい。
日本でいうと、例えば「ZENONピアノ」と「全音楽譜出版社」の関係性のような感じです。 |
H. PRAIL
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
エイチ・プレイル/H・プレイル 森技術研究所(浜松) ※フランスのプレイエルとは違う |
| H. PLEYEL |
エイチ・プレイエル(森技術研究所)というピアノの情報もあるが、
これは上記のH. PRAIL(エイチ・プレイル)と混同しているものと思われます。 |
H.W. PERLMAN
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
H.W.Perlman
H.W. パールマン アメリカ(ニューヨーク) 創業1898年
H.W.パールマン社は、1898年にハリー・W・パールマンによって設立されたピアノ会社である。
同社の工場はニューヨークにあり、1900年代初頭まで少数のピアノを生産していた。
歴史は浅いが、世紀の変わり目に一気に人気を高めた。
1930年代に入ると、Shoninger、Mansfield、Newby、Evansといったピアノを製造していた
ニューヨークのNational Piano Corporationに引き継がれた。
パールマンのピアノで興味深いのは、その多くが購入者の好みに合わせた特注品であったことだ。
これは、小規模な生産を行っていたパールマン社だからこそできたサービスだったのではないだろうか。
パールマンのピアノは音色に優れ、生産台数が少なく耐久性にも優れていた。
そのためH.W.パールマンのグランドピアノやアップライトピアノは、現在も多くが使用されている。
注:正しいブランドのスペルは、「H.W. PERLMAN」です。 ×「H.W. PEARLMAN」ではありません |
| HAAKE, KARL |
詳細不明 |
HADDORFF
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ハドルフ・ピアノ・カンパニーは、1901年にチャールズ・ハドルフによって設立された。
イリノイ州ベッドフォードにあった大きなピアノ工場で、ハドルフは自ら設計して
ハドルフ・ピアノの第1号機を製作した。
ハドルフの工場は、自社ブランドの他に、スタインバック&ドレーハー、クラレドン、ブッシュ&ゲルツなどの
ピアノも生産できる規模であった。
やがて、ハドルフ・ピアノ社は、ニューヨークのクラカウアー・ブラザーズに買収され、
コン・キーボード社に事業譲渡された。
その後、Conn KeyboardsはKimball Piano Companyの一部門となった。
1960年、約60年の歴史を持つキンボール社は、ハドルフ・ピアノの製造を中止した。
ハドルフという名前を聞くと、すぐに美しい音と精巧な作りの楽器を思い浮かべることができます。
グランドピアノ、アップライトピアノ、再生ピアノ、プレーヤーピアノなど、
いずれも高い評価と品質を誇っています。
今から60年ほど前に製造中止になったものの、ハドルフピアノはその透明感と力強さで音楽業界に名を馳せた。
最高の材料を使い、熟練した職人の手によって作られたハドルフのピアノは、訓練された耳を持ってしても、
その境界線を見分けることができないほどの階調性を持っています。 |
| HADLEY |
詳細不明 |
| HAEGELE OF AALEN |
詳細不明 |
HAESSLER


画像クリックでHPへ戻る |
ヘスラー ドイツ 詳細不明
※ヘスラーピアノはBVK認証を受けています(詳しくはこちら
→★)
HAESSLERの画像は匿名希望様からご寄稿頂きました。ありがとうございます! |
| HAGSPIEL |
詳細不明 |
| HAHN, ALB. |
詳細不明 |
HAIDIEL
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
シンハイ(星海)のブランド 中国 詳細不明 |
| HAIN, STEPHAN |
詳細不明 |
HAINES BROS.
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ヘインズ社は、1851年にナポレオンとフランシス・ヘインズの2人の兄弟によってニューヨークで設立。
1908年、ニューヨーク州ロチェスターでヘインズ兄弟と他の会社が合併して
アメリカン・ピアノ・カンパニーが設立。
1920年代には、シャーロック・マニング・ピアノ・カンパニーがヘインズ兄弟の傘下に入り、
1945年に閉鎖されるまで、彼らの名前でピアノを製造していた。
創業以来、ヘインズ・ブラザーズのピアノ会社は、その優れた品質で知られており、
世紀の変わり目にはブランドの人気が大きく上昇した。
優れた品質を持つハイネス社のピアノを弾けば、他のブランドにこだわるピアニストも改心すると言われています。
ヘインズ社は、創業以来20年間はスクエアグランドピアノを製造していたが、
その後アップライトを製造するようになった。
彼らのピアノは、数十年にわたって市場の人気のトップに君臨していた。
ヘインズ兄弟の知名度が上がると、グランドピアノやベビーグランドピアノなど、
他のピアノのスタイルも人気が出始めた。
彼らのピアノが「カレッジピアノ」と呼ばれるのは、多くの音楽機関がこのブランドに忠誠を誓い、
スタジオやコンサートホール、練習室にこのブランドを置いていたからである。
また、「The Artist's Choice」という本には、Hainesを弾いたことがあるだけでなく、
Hainesだけを選んだという著名なピアニストが載っています。
(※注意)名称が似ていますが、W. P. Haines & Companyとは別会社です |
| HAINES |
→W. P. Haines & Companyの項目へ |
| HAILEER |
詳細不明 |
HAILUN
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
HAILUN ハイルン 中国(寧波市)
<以下、ウィキペディアより引用抜粋>
海倫鋼琴(かいりんこうきん、ハイルンピアノ、Hailun Piano Co., Ltd.、SZSE: 300329)
股份有限公司は、中華人民共和国のピアノメーカーである。
2001年に陳海倫(董事長兼CEO)によって寧波市において寧波海倫楽器製品有限公司として設立された。
アップライトピアノおよびグランドピアノの製造と販売を世界的に展開している。
同社が製造している主要ブランドはPETROF(ペトロフ)、ROSS、
WENDL & LUNG(ウェンドル・アンド・ラング)、
ZIMMERMANN(ツィンマーマン)、FEURICH(フォイリッヒ)である。
株式は2012年6月19日に深圳証券取引所に上場された。
買収価格は21人民元、1,677万株が発行され、募集額は3億5000万人民元であった。
公式HP:http://www.hailunpiano.com/ |
HALLET DAVIS
HALLET, DAVIS & CO.

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ハレット・デイビス/ハレットデービス
HALLET DAVIS/HALLET. DAVIS & Co./Hallet, Davis & Co. /Hallet &
Davis
アメリカ 1839年創業
アメリカ最古の歴史を持ち、優れた品質を誇る。
創業1839年であるから極めて古く、それ以来音楽学校その他の専門家用として
名声を博してきた楽器で、1867年のパリ博覧会であの有名なフランツ・リストが
このピアノを弾き、またヨハン・シュトラウスも愛用したと伝えられている。
尚、ローマ法王のバチカン宮殿にも納入されたというから、20世紀初頭の最も
優れたピアノの一つであったことは間違いないでしょう。
現在でもシカゴで販売されています。
<別解説>
ブラウン氏とハレット氏は、アメリカでのピアノ作りに早くから取り組んでいた。
彼らは1835年、マサチューセッツ州ボストンのワシントン・ストリート293番地にブラウン&ハレット社を設立。
しかし、この社名も長くは続かなかった。パートナーシップが変わったり、
オーナーが去って別の会社を設立したりしたからだ。
ブラウンは1843年に引退し、その7年後にはアレンと一緒に働くようになった。
アレンは1847年にハレット・アレン・カムストンの一員となった人物である。
ハレットは、ブラウンとのパートナーシップとアレン&カムストンとのコラボレーションを分けていた4年間、
ジョージ・H・デイビスと仕事をしていた。1879年、元の所有者が会社を率いなくなった後、
社長代理のE.N.キンボールは、ハレット・デイビス社として事業を法人化した。
その間、C.C.コンウェイが会計係、E.E.コンウェイが書記係を務めていたが、
1905年にコンウェイ家が会社を支配することになった。
コンウェイ家は、1928年に家業のコンウェイ・ピアノ社と合併して、
コンチネンタル・ピアノ社を設立したのである。
エオリアン・ピアノ・カンパニーは大恐慌の際にハレット&デイビスを買収し、
1980年代までハレット&デイビスの名前でピアノの製造を続けた。
現在、ハレット&デイビスの名前は、ニューヨークを拠点とする
ノース・アメリカン・ミュージック社が使用しており、
ピアノは生産コストを下げるために中国で製造されている。
現代のハレット&デイビスは、名称以外にオリジナルの会社と中国ピアノとの共通点はありません。
ハレット・デイビス社は、スクエア型、アップライト型、グランド型のピアノを製造していた。
1890年にはスクエアピアノを廃止し、世紀末に全米で起こったプレーヤーピアノのムーブメントに参加。
1905年から1925年にかけて製造された「ヴィルトゥオーロ/Virtuolo」は、
同社の最高級・最高価なプレーヤーピアノである。
1959年にウインター(WINTER & CO.)は、エオリアン・アメリカン社と合併し、
社名をエオリアン・コーポレーションに変更していた間、Hallet & Davisは
ウィンター&カンパニーが製造していたブランド名の一つです
→詳しくはWINTERの項目へ |
| HALLETT & CUMSTON |
詳細不明 |
| HALLETT, RUSSELL |
詳細不明 |
| HALS |
詳細不明 |
HAMAMATSU
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ハママツ 浜松ピアノ製造株式会社 |
| HAMBURGER |
詳細不明 |
HAMILTON


画像クリックでHPへ戻る |
ハミルトン アメリカ(イリノイ州シカゴハイツ) 創業1889年
ハミルトンピアノ社は、1889年に設立されたボールドウィン社傘下のピアノメーカーである。
イリノイ州シカゴハイツに工場を構えていたが、ボールドウィン社に買収され、
ボールドウィン社最大のピアノ生産工場となった。
1932年には、ハミルトンピアノの製造拠点をオハイオ州シンシナティに移した。
ギブソン・ギターがボールドウィン・ピアノ社を買収した後は、ハミルトン・ピアノの名称が引き継がれ、
2001年以降に製造された多くのピアノに使用されている。
ハミルトンピアノ社は、ボールドウィンピアノ社の中でも最大規模のハミルトンピアノの生産工場として、
アップライト、グランド、リプロダクションピアノなどで知られていた。
リプロダクション・ピアノの登場は、当時のピアノ技術の大きな進歩でした。
ハミルトンのまくり(鍵盤蓋)部分のブランド銘柄マーク →★ |
HAMMOND
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ハモンド Hammond Piano Company
アメリカ(インディアナ州ハモンド) 創業1878年
ハモンドピアノはインディアナ州ハモンドにあるストラウベ・ピアノ社の工場で製造されていた。
1878年に設立されたストラウベ・ピアノ・カンパニーは、ストラウベ、ハモンド、ギルモア、ウッドワードの
ピアノを製造し、リードオルガンも製造していた。
後にコンチネンタル・ミュージック・カンパニーの一部門となる。
ハモンドピアノは、シュトラウベが会社の過半数の所有権を得て、会社名でピアノの生産を続けるまでは、
ハモンド・ピアノ・カンパニーとしてスタートした。
ハモンドピアノは、1900年代初頭に販売されていた他の厳選されたシュトラウベピアノに代わる、
より手頃な価格の中級グレードのピアノとして販売された。
ハモンドピアノは、シュトラウベやギルモアと同じ工場で製造されたため、スタイルや音色に多くの共通点があった。
1905年、ストラウベはハモンド・アップライト・ピアノのスタイル21と23を発表した。
その後、プレーヤーピアノも発売された。ハモンドピアノ社は、シュトラウベ・ピアノ社が経営しており、
さまざまなスタイルやケースデザインを顧客に提供した。
ストラウベ・ピアノ社は、プレーヤーピアノのアクションに使われている
振り子式バルブ「アルトロノーム・プレーヤーアクション」の特許を取得し、
プレーヤーピアノにありがちな腐食や摩擦による問題を軽減した。
ハモンドピアノをはじめとするシュトラウベ社のプレーヤーピアノは、その信頼性の高さから、
業界内で高い評価を得ていた。
ストラウベ社やハモンド社の初期のプレーヤーピアノは、現在でも現役で使用されているものがある。
※下記、日本のHAMMONDとは別のピアノです |
HAMMOND
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ハモンド
アトラスピアノ製造株式会社
東洋ピアノ製造株式会社
※上記、アメリカのHAMMONDとは別のピアノです |
HAMPTON
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ハンプトン HAMPTON アメリカ ストーリー(ストリー)・アンド・クラーク社
詳細は、スートリー・アンド・クラーク(STORY & CLARK)の項目を参照
|
HANDOK

画像クリックでHPへ戻る |
ハンドク/(ハンドック?) 韓国 創業1976年
※HPが閉鎖されているので現在は廃業? 詳細不明
ハンマーはロイヤルジョージを使用、ミュージックワイヤーはレスロー弦を使用とのことです。
音色はかなりシャリシャリした硬い感じの印象を受けるピアノです。
廉価な中国製ピアノに多いのですが、無理してレスロー弦なんかを使うとこんな音になる気がします。
左記トレードマーク画像は「ハラ様」からご寄稿頂きました。この度は誠にありがとうございます!
※HANDOKのトレードマークは、日本製のクロイツェル(KREUTZER)と文字以外ほぼ同じデザインです。
クロイツェル側が韓国メーカーに作らせているのか、又はクロイツェルのトレードマークデザインを勝手に
真似しているのか、詳細は不明です。
→トレードマークの違いを参照したい場合は「KREUTZER」の項目へどうぞ |
|
HANKYU WAGNER


画像クリックでHPへ戻る
|
阪急ワグナー/ハンキュウ ワグナー (HANKYU WAGNER)
通称:ハンキューワグナー
製造元:アトラスピアノ製造株式会社
製造元:東洋ピアノ製造株式会社
販売元:阪急百貨店(現:阪急阪神百貨店)
こちらは阪急(HANKYU)と入っているワグナーピアノです。
阪急百貨店向けで売られていたブランドで、ピアノ自体はワグナーとほぼ同じです。
非常に珍しいトレードマークです。
詳細はワグナーの項目を参照してください。
ワグナーのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★ |
| HANLET |
詳細不明 |
| HANNON HALL |
詳細不明 |
HANSEN
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ハンセン ドイツ 詳細不明
|
| HANSEN, A. |
詳細不明
※上記HANSENと同じか?不明 |
| HANSEN, JULIUS |
詳細不明 |
| HANSMANN, GEBR. |
詳細不明 |
HANTHEY
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ドイツ 読み方不明、詳細不明
|
HARDMAN
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
Hardman ハードマン
1959年にウインター(WINTER & CO.)は、エオリアン・アメリカン社と合併し、
社名をエオリアン・コーポレーションに変更していた間、HARDMANは
ウィンター&カンパニーが製造していたブランド名の一つです
→詳しくはWINTERの項目へ |
HARDMAN PECK
HARDMAN & HARDMAN PECK




画像クリックでHPへ戻る |
ハードマン・ペック HARDMAN PECK & CO. アメリカ 創業1842年
Hardman & Hardman Peck Company
ハードマン・ペックはアメリカの歴史的なピアノで、メトロポリタン歌劇場の専用ピアノとして
使われ、歴史的なテナー歌手であるエンリコ・カルーソーが伴奏用に使ったと伝えられている。
グランドピアノとアップライトピアノ両方を作っており、オペラ用のピアノは繊細で優美な
音色を特徴とし、シンギングトーンと表現されています。
構造上の特徴としては、背面のポスト(支柱)が6本あることなどが知られています。
<別解説>
1842年、ヒュー・ハードマンによってニューヨークに設立されたハードマン・ピアノ社は、
そのスタイルで早くから評判になっていた。
1874年に弟のジョンとパートナーのレオポルド・ペックが加わり、
1879年にヒュー・ハードマンが引退したため、1890年に社名を「ハードマン&ペック」に変更した。
1890年に社名を「ハードマン&ペック」に変更した。
アップライト・フレームに足踏み式のプレーヤー・ピアノを搭載するなど、
いくつかの特許を取得したハードマン&ペックのピアノは、メトロポリタン歌劇場や
20世紀初頭のフランクリン・D・ルーズベルトなど、多くの人々に愛用された。
1951年、ハードマン&ペック社はウィンター社に買収され、それから10年も経たないうちに
エオリアン社が同社を買収し、1980年代までハードマンブランドのピアノの生産を続けた。
1990年、ハードマン&ペック社のピアノは、北京星海ピアノグループ製のノースアメリカンミュージック社によって
生産が再開されました。
ハードマン&ペック社のピアノは、その品質と耐久性に定評がありました。
その芸術的な外装の多くは、現在でも賞賛されています。
様々なサイズとスタイル、そしてアコースティックピアノとプレーヤーピアノの両方を生産した
ハードマン&ペックのピアノは、現在でもニューヨークのパブリックスクールやスタジオで見られる。
オートトーン、ハリントン、アンセル、ミニピアノ、プレイオトーン、スタンダード、ハードマン・オートトーン、
ハードマン・デュオ・プレーヤーなど、ハードマン&ペックのピアノには様々な名前が付けられていた。
現在、ハードマン&ペック社のピアノは、日本のカワイがブランドを所有し生産され、
高品質で手頃な価格の選択肢として残っています。
外装にあるハードマンペックのブランド銘柄マーク→★
上から3番目のトレードマークはグランドピアノです。
このグランドのトレードマーク画像はMISSA様からご寄稿頂きました。ありがとうございます!
ハードマンペックのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★ |
| HARIMATIS |
詳細不明 |
HARMONY
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ハーモニー 浜松楽器工業 (株)
浜松楽器工業 (株)は、「ディアパソン」を製造していた会社で、
「浜松楽器」が「河合楽器製作所」の子会社の時代に製作したのピアノのようです。
トレードマークは、HARMONYのブランド名に加え、丸の中に”特注”と書かれた面白いデザイン。
トレードマーク画像は「匿名希望様」からご寄稿いただきました。ありがとうございます!
※浜松楽器工業株式会社の詳細については「ディアパソン」の項目を参照 |
HARMONY
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ハーモニー 韓国
製造元:三益楽器製造株式会社(韓国)
発売元:株式会社トニカ楽器 (輸入:アトラスピアノ)
機種バリエーション:MU-2など |
| HARMSWORTH & COMPANY |
詳細不明 |
| HAROLD, F.E. |
詳細不明 |
HARRINGTON
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ハリントン アメリカ (ニューヨーク) 創業1871年
ハードマン・ペック HARDMAN PECK & CO.のブランド
1871年、ニューヨークにE.G.ハリントンピアノ社が設立された。
1871年にニューヨークで設立されたE.G.ハリントンピアノ社は、1880年には月産100台のピアノを
製造するほどの高品質な楽器で有名であった。
20世紀に入ると、ハリントン社はハードマン・ペック・ピアノ社に吸収された。
その後、大恐慌の際に工業大手のエオリアン社に買収されましたが、1960年代までハリントンピアノの製造を続け、
初期の名声を維持しました。
ハードマン・ペック社は、ハードマン、ハリントン、スタンダード、ヘンゼルという名前のピアノを製造していた。
20世紀初頭、同社はアップライトピアノ、プレーヤーピアノ、ベビーグランドピアノのフルラインを導入し、
生産を維持していた。エオリアン社に買収された後の大恐慌時代の楽器は、主に小型のコンソールピアノや
スピネットピアノ、そしてアパートサイズの小型ベビーグランドピアノであった。
彼らは多くの近代的なピアノ会社と競争し、いくつかのスタイルと種類の木材を使用して、
さまざまなデザインのケースを生産した。
ハリントンミゼットは、その中でも最も小型の普及型ピアノであるが、
大型モデルに匹敵する音色と品質を備えていることを売りにしていた。 |
HARRISON
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
キンボール社(KIMBALL)が取り扱ったブランド
→詳しくはKimballの項目へ |
| HARRISON, V. F. |
詳細不明
※上記HARRISONと同じか?不明 |
HARRODSER



画像クリックでHPへ戻る |
HARRODSER ハローザー/ハロッサー
ドイツの部品を使っているとのこと
中国製造?遠州楽器制作株式会社?詳細不明
<某HPの製品情報より>
DEHONITピンブロックは、厳選されたブナ材の19層ブロックで、
ピアノ弦のスピンドルピンの安定した位置を提供します。
黒檀の黒鍵はインドネシアのエボニーで作られており滑らかで光沢があります。
ハロッサーアクションは、すべての無垢材のアクションです。
ピアノの8800の部品が正確に一致しています。キーは1秒間に13回連打可能。
レスロー弦は、130年の歴史を持つドイツで最高のピアノ弦。耐用年数を50%増しの優れた防食処理。
ドイツABELハンマー使用、厳選されたピュアウールと洗練された手作業の研磨により、
ハロッサーピアノならではの音質を実現しています。
STRUNZサウンドボードは、トウヒ材で作られたドイツのトップレベルの響板。
可変厚の響板は、演奏中に最適なボリュームを発生させます。
<以上、某HPの製品情報より>
左記トレードマーク画像は「ピアノ調律塾様 https://www.piano-juku.com/」からご寄稿頂きました。
この度は画像の提供を頂きまして誠にありがとうございました! |
| HARTGE, HENRY |
詳細不明 |
| HARTMANN, W. |
詳細不明 |
HARVARD
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
HARVARD ハーバード
大倉楽器工業(株)東京都杉並区上高井戸
二本弦の小型ピアノが多かったが、大型のものは音色に特色があった。
|
| HARWOOD |
詳細不明 |
| HASCHE |
詳細不明 |
HASHIMOTO

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
HASHIMOTO ハシモト
製造:株式会社 協信社ピアノ製作所(シュベスターピアノ製造KK) 東京蒲田
橋本勝美氏が協信社ピアノ製作所(シュベスターピアノ)に依頼して作ったピアノ。
→詳しくはSCHWESTER(シュベスター)の項目も参照 |
| HASSELAAR |
詳細不明 |
| HASSELDIECK, DIETRICH |
詳細不明 |
| HASTI ASGHARI |
詳細不明 |
| HAUCH, J.B. |
詳細不明 |
HAUPTMANN

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
HAUPTMANN ハープトマン (ハウプトマン)
※同社カタログ内では”ハープトマン”の表記です
製造元:日本楽器製造株式会社(横浜工場)
発売元:株式会社 山野楽器店(銀座)
銀座の山野楽器店が松本ピアノから権利を譲り受けて総合楽器店として出発した時、
西川ピアノに”ヤマノピアノ”という名称で依頼、西川が日本楽器の横浜工場となってから作ったピアノ。
※HAUPTOMAN→× HAUPTMANN→○ スペル内に”O/オー”は入らず、”Nは2個”なので注意。 |
HAUPTMANN Jr.

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
HAUPTMANN JUNIOR/HAUPTMANN Jr.
ハープトマン・ジュニア
製造元:日本楽器製造株式会社(横浜工場)
発売元:株式会社 山野楽器店(銀座)
上記ハープトマンと同じように山野楽器店が日本楽器横浜工場で作らせていたブランド。
ハープトマンより一回り小型で、一般向きと言われたが堅牢で音色もきれいであった。
※HAUPTOMAN→× HAUPTMANN→○ スペル内に”O/オー”は入らず、”Nは2個”なので注意。 |
| HAUSMANN |
詳細不明 |
| HAUTRIVE |
詳細不明 |
HAWKINS
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ホーキンス 東洋ピアノ製造株式会社 |
| HAYELSON |
詳細不明 |
| HAYES, E. T. |
詳細不明 |
| HAYT, BABCOCK & APPLETON |
詳細不明 |
| HAYTS, BABCOCK & APPLETON |
詳細不明 |
HAZELTON BROTHERS
HAZELTON & BROTHER
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ヘーゼルトン・ブラザーズ アメリカ(ニューヨーク) 創業1849年
ヘンリーとフレデリックのヘーゼルトン兄弟は、1849年にヘーゼルトン・ブラザーズを設立しました。
彼らの工場は、1800年代から1900年代にかけてピアノ製造のメッカであったニューヨークにありました。
当初はF.&H.Hazelton(創業者2人の兄弟の名前)と呼ばれていましたが、
弟のJohnが入社したことで社名を変更しました。
1900年代初頭、創業者が亡くなった後、Samuel Hazeltonとその息子Halseyが会社を引き継ぎました。
ヘイゼルトン・ブラザーズは、世界大恐慌の時代を生き抜いた数少ないピアノメーカーのひとつであり、
その品質と人気の高さが証明されている。
ヘーゼルトンのブランドは、1957年にピアノ大手のKohler and Campbell(コーラー&キャンベル社)が
経営権を取得するまで生産され、ヘーゼルトンの名は消滅した。
その後、韓国のサミック社がコーラー&キャンベル(Kohler and Campbell)社を買収したことにより、
再びヘーゼルトン(HAZELTON)のブランド名を使ったピアノを作り始めました。
ヘイゼルトン・ブラザーズは、アメリカで最も古いピアノメーカーのひとつであり、
アメリカで最も有名なピアノのいくつかを製造してきました。
ヘーゼルトンのスクエアグランド、グランド、アップライト、プレイヤーピアノ(自動ピアノ)はいずれも
その信頼性と耐久性で知られています。
多くの楽器が時の試練に耐え、今日でも良好な状態で使用されています。 |
| HEALY |
詳細不明 |
| HEDKE, WILH. |
詳細不明 |
| HEGELER |
詳細不明 |
| HEIDEN, CARL VON |
詳細不明 |
HEINE
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ハイネ アメリカ(サンフランシスコ) 創業1889年
ハイネピアノ社は、1889年にサンフランシスコで設立された西海岸のピアノメーカーである。
自社製品の他にクレルピアノ社が数年間ハイネピアノを製造していた。
ハイネピアノカンパニーは、1900年代初頭にピアノの製造を中止した。 |
| HEINISCH |
詳細不明 |
HEINTZMAN & CO.
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ハインツマン・アンド・カンパニー カナダ(トロント) 創業1866年
1866年、ドイツからの移民であるセオドア・ハインツマンが「ハインツマン社」を設立した。
この会社はカナダのトロントにあった。
ただし、セオドアの甥の会社であるゲルハルト・ハインツマン・ピアノ・カンパニーと
混同しないように注意が必要である。
1899年にセオドア・ハインツマンが亡くなると、会社はオンタリオ州ハノーバーに移った。
1978年までにハインツマンピアノの製造はすべてハノーバーに集約され、
社名もハインツマン・リミテッドに正式に変更された。
1981年にはカナダの家具メーカー、スクラー・ペプラー社に買収され、
1987年にはオンタリオ州のミュージックスタンド社に売却された。
元の会社は廃業しているが、カナダと中国を拠点とするHeintzman Distributors, Limitedが
今でもハインツマンの名前を使っている。
興味深いことに、2008年の北京オリンピックの開会式で演奏されたのは、Heintzman Distributors, Limited社が
製造したハインツマンのグランドピアノでした。そのピアノはオークションで322万ドルで落札されました。
ハインツマンの名を冠したピアノは、何度も会社が変わり、名前も変わったため、
いつ頃から新しいモデルに切り替わったのかは明らかではありません。
しかし、1980年代に入って、ハインツマン社が中国に機械を売却し、在庫を整理したことで、
オリジナルのハインツマンの名前が消えたという説が有力である。
ハインツマン・アンド・カンパニーは、彼らの名前でアップライトピアノやグランドピアノを製造し、
ノルトハイマー(Nordheimer)のピアノも製造していました。
ハインツマンの名を冠した楽器は、カナダではよく知られており、
一世紀以上にわたって非常に人気がありました。
優れた音色と美しい筐体を持つハインツマンのピアノは、時の試練を経て、
今日でも音楽家たちの間で人気を博しています。 |
| HEITZMANN & SOHN |
詳細不明 |
HEINRICH


画像クリックでHPへ戻る |
ハインリッヒ 福山ピアノ社(フクヤマピアノ)
昭和40年代頃に株式会社福山ピアノ社が販売していたピアノブランド。
本社(当時):東京都千代田区神田神保町1丁目14番地
その他詳細不明
ピアノまくり(蓋部分)のブランド銘柄部分 →★ ハインリッヒの内部写真 →★
これらの画像はすべて「匿名希望様」からご寄稿頂きました。
昭和40年3月、東京お茶の水にある谷口楽器さんから購入されたとのことです。
(※ちなみにピアノの扱いはありませんが、今でも谷口楽器さんは営業しているとのことです)
その当時のピアノ購入価格は24万円だったとのことです。
この度は貴重なお写真とエピソードを頂きまして誠にありがとうございました! |
HEINRICH
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ハインリッヒ 新響工芸
※上記の福山ピアノのハインリッヒとは違うピアノなのか?不明 |
HEINTMAN

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ハインツマン HEINTMAN & COMPANY.LIMITED カナダ
トロントにあるメーカーで、創業は1850年。
あらゆるピアノを製作しており、幾多の国際的な賞を取った優れたピアノとのこと。
|
HEITER
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ハイテル 有限会社 大森ピアノ社(磐田市)
大森ピアノ社住所:静岡県磐田市西町309番地(当時) |
HELL
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ヘル 有限会社 大森ピアノ社(磐田市)
大森ピアノ社住所:静岡県磐田市西町309番地(当時) |
HELLAS


画像クリックでHPへ戻る |
ヘラス フィンランド(HELSINKI/ヘルシンキ) 創業1901年
スカンジナビア諸国(デンマーク、ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、アイスランド)の中では
最も古いピアノメーカーで、レンナーハンマーを使いドイツの伝統技術を継承して作られた
性能の優れたピアノです。機種としてはコンサートグランドから、コンソールタイプまで広範囲に生産。
最盛期の年間生産台数は約5500台で、その半数がヨーロッパや
同スカンジナビア各国へ輸出されている。その後、日本にも入ってきて好評を博す。
HELLASは1989年、FAZERも買収してフィンランド国営企業として2つのブランドのピアノを製造。
ヘラスのトレードマーク画像は「匿名希望様」からご寄稿頂きました。ありがとうございます!
ヘラスのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★ |
HELLER
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
Heller & Co. Huntington
1959年にウインター(WINTER & CO.)は、エオリアン・アメリカン社と合併し、
社名をエオリアン・コーポレーションに変更していた間、HELLERは
ウィンター&カンパニーが製造していたブランド名の一つです
→詳しくはWINTERの項目へ |
| HELLSTRÖM |
詳細不明 |
|
HELMAN



画像クリックでHPへ戻る
|
HELMAN ヘルマン
東洋ピアノ製造(アポロピアノ) 浜松 詳細不明
ピアノの鍵盤押さえ部分には「TOYO PIANO MFG. CO:LTD」というシールが貼ってあります。
ちなみに、まったく別のピアノブランドで、”HERRMANN”というピアノもあります。
ヘルマンのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★
|
HELMHOLZ

画像クリックでHPへ戻る |
FR.HELMHOLZ フリードリヒ・ヘルムホルツ
ドイツ(ハノーファー/HANNOVER)
フリードリヒ・ヘルムホルツは、1821年10月18日生まれ(グローナウ)
1890年9月22日没(ハノーバーにて)68歳
フリードリヒ・ヘルムホルツは大工として修行した後、1851年にラインシュトラーセ(Leinstraße)に
大工工房を設立。そこでピアノの製造も開始しました。
ピアノは大変品質が良く当時大きな需要があったとのことです。
ヘルムホルツはショームバーグ・リッピ王子の宮廷から御用達の称号を授与されました。
トレードマーク画像は「匿名希望様」からご寄稿頂きました。ありがとうございます! |
HENRY F. MILLER

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ヘンリー・F・ミラー/ヘンリー・ミラー Henry F. Miller 創業1863年
MILLER PIANO CO. 正式名称:ヘンリー・エフ・ミラー・ピアノカンパニー
1863年創業のアメリカ(ボストン)の老舗メーカーですが、現在は中国製造のようです
工場:テネシー州(当時)
アメリカ西部の豊富な木材資源を利用して、過去100年以上ピアノ製作を続けてきた会社です。
製造するピアノはまったく飾りのないスピネットタイプ10種類と、小型のグランドを製造。
<ヘンリー・F・ミラー社の歴史>
ヘンリー・ミラーは、1850年にブラウン&アレン社、1857年にエマーソン・ピアノ・カンパニーで働いた後、
1863年にピアノ会社を設立した。1850年にブラウン&アレン社、1857年にエマーソン社に入社し、
クラシック音楽のピアニストとして活躍したミラーは、音楽家の繊細な耳に合うピアノの作り方を知っていた。
ミラーは、マサチューセッツ州ウェイクフィールドに工場を構え、
当時、ピアノ職人として名を馳せていたJ.H.ギブソンと提携した。
ヘンリー・F・ミラーのピアノは、製造を開始して間もなく、その芸術的なフレームやデザイン、
豊かな音色、優れた職人技が評判となり、当時のプロの音楽家たちに支持されるようになった。
1884年には、ミラーの5人の息子たちが事業に参加して会社を設立し、「ミラー&サンズ」という名前で
ピアノを生産するようになった。
早くからアップライトピアノ、グランドピアノ、スクエアピアノなどのラインナップを揃えていた。
また、オルガンのようなペダルボードを備えたペダルピアノも製造していた。
ヘンリー・F・ミラーのピアノは、1800年代後半から20世紀初頭にかけて、多くのプロの音楽家に愛用され、
その品質の高さが広く知られていた。
ミラー社とギブソン社が生産開始前に綿密な設計を行ったことで、ピアノのフレームは非常によくできている。
1920年代、ヘンリー・F・ミラーはコンチネンタル・ピアノ・カンパニーの一部門であったが、
1945年にウィンター・アンド・カンパニーに買収され、1951年にオフィスをニューイングランドのボストンから
テネシー州メンフィスに移転した。
1980年代後半には、エオリアン・アメリカン・コーポレーションが
ヘンリー・F・ミラーの名前でピアノを製造していたが、その後廃業した。
2013年には、中国のメーカーがヘンリーF.ミラーのピアノを製造し、米国に輸入している。
1959年にウインター(WINTER & CO.)は、エオリアン・アメリカン社と合併し、
社名をエオリアン・コーポレーションに変更していた間、HENRY F. MILLERは
ウィンター&カンパニーが製造していたブランド名の一つです
→詳しくはWINTERの項目へ
HENRY F. MILLERピアノのまくり(蓋部分)にある銘柄ブランド部分の写真 →★ 全体写真 →★
上記2枚の画像は「匿名希望様」からご寄稿頂きました。この度は誠にありがとうございます! |
| HENRY WARD |
ヘンリーワード イギリス(ロンドン) 詳細不明 |
| HEPPEL & THEILIG |
詳細不明 |
| HERGENS, A. G. |
詳細不明 |
| HERIOS ? |
ヘリオス 詳細不明
|
| HERMANN |
詳細不明 |
| HERRBURGER |
詳細不明 |
HERRMANN
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ヘルマン
販売元:神戸堂(神戸)
ヘルマンピアノ製造
福山ピアノ(東京)
大成ピアノ製造株式会社(浜松)
龍生楽器研究所(竜生楽器研究所)
販売カタログでは”ETERNAのヤマハ姉妹品”として販売を展開
まったく別のブランドで“HELMAN”というピアノもあり |
| HERRMANN, ALEXANDER |
詳細不明 |
| HERZ, HENRI |
詳細不明 |
| HERZ NEVEU, PHILIPPE |
詳細不明 |
| HEYL, GUSTAV |
詳細不明 |
HIBIKI
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ヒビキ
製造元:有限会社 エスピー楽器製作所、東洋ピアノ製造株式会社
発売元:響楽器 |
HILGER
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ヒルガー ドイツ 詳細不明
|
| HILLGÄRTNER, HEINRICH |
詳細不明 |
| HILTON |
詳細不明 |
| HIJZ, ERNEST |
詳細不明 |
| HILLMANN |
詳細不明 |
| HINDSBERG |
詳細不明 |
HINZE
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
キンボール社(KIMBALL)が取り扱ったブランド
→詳しくはKimballの項目へ |
HIRADE
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ヒラデ 合資会社 平出楽器製作所
”モンソン”のアクションを使用 |
HIROTA

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
HIROTA
ヒロタ
広田ピアノ株式会社(現:川崎市、東京府下大森町前方3472)
東洋楽器製造株式会社(広島)
東洋ピアノ製造株式会社(浜松)
広田米太郎氏(廣田米太郎氏)は、当時最高の技術を持つ調律師で、1923年の関東大震災の翌年に
東京楽器研究所を離れて、約6~7年の間ヒロタピアノを作っていた。
(鍵盤は象牙、レンナーハンマーを使用、定価1000円にて販売の記録有り)
従業員24~25人で、年間約100台を製造していたという。
ヒロタピアノはアップライト600台、グランド70~80台が作られたと推定されており、
アクションやワイヤーはドイツ製を使い、グランドはブルッツナーをコピーしたもので、
音色は極めて美しく、ブランドとしてはY・ヒロタが用いられていた。
この米太郎氏の長男の広田武雄氏が広島で屋代千里氏と合同して
東洋楽器製造株式会社を作り、ワグナーピアノを作り出しました。
※Y.HIROTA Y・ヒロタ
製造:東洋楽器製造KK(広島)
発売元?:ヒロタピアノ(広田ピアノ)(東京都大田区大森)
広田米太郎氏によって大田区大森に創立されたヒロタピアノのブランド。
ブルッツナーをコピーしたもので、音色は極めて美しかったというが、
工場は終戦とともに消失した。広島の東洋楽器でも作られていた。
|
HITACHI

画像クリックでHPへ戻る |
HITACHI/ヒタチ
製造:日本楽器製造株式会社(現:ヤマハ株式会社)
販売:株式会社 日立製作所
ピアノのまくり(蓋部分)にあるブランド名は「HITACHI」となっていますが、ピアノ自体はヤマハです。
1960年頃、日本楽器製造の経営戦略として日立製作所(株)の社員向けに特別に販売した廉価版ピアノ。
当時、ピアノ販売にも直結するヤマハ音楽教室の拡大に力を入れていた日本楽器製造の経営戦略として、
国内の大企業である日立製作所の家族を取り込むことでピアノ販売のさらなる拡大を図ったときのもの。
ただし、製造出荷されたピアノはさほど多くはない模様。
現在残存しているピアノは当然ながら茨城県が最も多いと推測されます。
内部にあるエンブレムマークは、上のような一般的な3本音叉のヤマハマークのものと、
■機種/モデル バリエーション H-1、H-3等
<参考>
日立と同じく、電器機器メーカーの「ナショナル」や、音響機器メーカーの「ビクター」等の会社では同時期に、
自社ブランドとしてピアノ販売を展開していました。
※ただし、ナショナルやビクターの製造は東洋ピアノなど、ピアノ製造専門会社のOEM製造です。
→詳しくはこのページ内の「NATIONAL」、「VICTOR」の項目を併せてご参照ください。 |
| HLUCHÁŇ |
詳細不明 |
HOBART CABLE
HOBART M. CABLE

※中国製造になってから
画像クリックでHPへ戻る |
ホバート・M・ケーブル アメリカ 1900年(1911年創業という資料もあり)
アメリカインディアナ州ラポルテ 工場:ミシガン州
※ブランドスペルはHOBERTではなく、HOBARTです。
<ホバート・M・ケーブルの歴史>
1900年、ホバート・M・ケーブル、ホバート・M・ケーブル・ジュニア、ハワード・R・モレナスの3人によって、
インディアナ州ラポルテにホバート・M・ケーブルというピアノ会社が設立された。
ホバートは、兄弟のフェイトとH.D.ケーブルも「ケーブル・ピアノ・カンパニー」という会社を経営していたので、
ピアノの世界では知らない人はいない。
実際、ホバート・M・ケーブル社は、ケーブル・ピアノ社の関連会社であり、家族ぐるみの付き合いをしていた。
ホバート・M・ケーブルのブランドは、19世紀半ばのある時期に
ストーリー・アンド・クラーク・ピアノ・カンパニーに買収された。
ホバート・M・ケーブルの名前は優秀さの代名詞であったため、ストーリー・アンド・クラーク社はその名前を残し、
H.M.ケーブルの正確な仕様に基づいてピアノを製造し続けた。
1990年、Classic Player Piano Companyという会社がStory and ClarkとHobart M.Cableの
ブランド名称を買い取り、H.M.Cableブランドは一旦決着した。
最近では、アメリカン・セジュン・コーポレーションという会社がホバート・M・ケーブルの名前を継承し、
ピアノの生産を再開している。
このAmerican Sejung Corp.は、H.M.Cableの名を残すべく、
北米で再びピアノを販売するために多大な資金を投入しているという。
ホバート・M・ケーブルのピアノは、甘く魂のこもった、澄んだ力強さのある音が特徴で、
訓練された耳にはすぐにそれとわかる。同社は品質の科学的根拠としてスケールを用いており、
音楽好きの耳には流麗な心地よさが伝わってきます。
また、ホバート・M・ケーブル社のピアノの特徴として、グランドピアノには独自のシリアルナンバーが
付けられていること、ピアノには豊かな木材が使われ、美しい装飾が施されていることなどが挙げられる。
また、グランドピアノ以外にもプレーヤーピアノやアップライト型も製造していた。
1990年代にHOBART M. CABLEのブランドは韓国の会社であるAmerican Sejung Corpが取得し、
中国の青島市(チンタオ)にある工場で製造されるようになりました。
従いまして2000年以降のHOBART M. CABLEは確実に中国製となります。
トレードマーク画像をはじめ、外観その他の写真はすべて、「匿名希望様」からご寄稿頂きました。
内部の雰囲気から推測しますと中国製造になってからのピアノと思われます。外観などの写真はこちら →★
ご寄稿者様によりますと、ピアノの音色はとても良く、気に入っているとの情報も頂きました。
私自身早く調律をしてみたいです。この度は多数の画像のご寄稿を頂きまして誠にありがとうございました! |
| HOEK |
詳細不明 |
| HOEPFNER |
詳細不明 |
HOELLING & SPENCENGBERG
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ドイツ 読み方不明、詳細不明
|
HOEPFER
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ヘパー ドイツ 詳細不明
|
| HOERR, FRANZ |
詳細不明 |
| HOFBAUER, GUSTAV |
詳細不明 |
| HOFF & CO. |
詳細不明 |
| HOFFMANN, AUGUST |
詳細不明 |
| HOFFMANN, GEORG |
詳細不明 |
| HOFFMANN, W. |
詳細不明 |
HOFFMANN


画像クリックでHPへ戻る |
HOFFMANN(W.HOFFMANN)(& KUHNE) ホフマン&キューネ
ドイツ(旧西ドイツ)
このトレードマークにはMade by C.Bechstein Europe SINCE1964とあります
HOFFMANN(ホフマン)(ベヒシュタイングループ)はペトロフがOEM販売。
PETOROFのHPより。
エンブレム画像は「PIANO YOSHIKAWA様」よりご寄稿頂きました。ありがとうございます!
<以下、ウィキペディアより引用抜粋>
W・ホフマン(W. Hoffmann)はドイツのアップライトピアノおよびグランドピアノ製造業者である。
工房は1893年にベルリンで創業された。
1991年、「転換」の直後、ホフマンはベヒシュタイングループに買収され、
アップライトピアノとグランドピアノはザイフヘナースドルフで生産された。
2001年、生産がチェコに移転された。 |
HOFMANN

画像クリックでHPへ戻る |
HOFMANN ホフマン
株式会社 西川楽器製作所(横浜市神奈川青木町)
※(西川楽器は日本楽器に合併吸収されまでの1884年~1921年まで稼働)
※(西川ピアノ時代のピアノ製造期間は1916年~1921年までとの記録がある)
日本楽器製造株式会社(横浜工場)
有限会社 興和楽器製作所
東洋楽器製造株式会社(広島)
発売元:小野ピアノ販売店、(十字屋楽器店も?) ※SONAREの項目も参照
エンブレム画像は「匿名希望様」よりご寄稿頂きました。ありがとうございます!
※上記、本場ドイツ製のホフマンの方は”F”が2個ですがこちらは”F”が1個です |
| HOFMANN & CZERNY |
詳細不明 |
| HOFMANN, KARL |
詳細不明 |
| HOFMANN & SCHOLZ |
詳細不明 |
| HOFMANN & SCHULZE |
詳細不明 |
| HOHNER |
詳細不明 |
| HÖLLING & SPANGENBERG |
詳細不明 |
| HOLTS |
ホルツ 詳細不明 |
| HOLZL & HEITZMANN |
詳細不明 |
HOMEYER
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
HOMEYER/ERNST HOMEYER ホーマイヤー ドイツ(ライプツィヒ) 旧東ドイツ その他詳細不明 |
|
HOPKINSON



画像クリックでHPへ戻る
|
ホプキンソン 1835年創業 イギリス(ロンドン)
J.& J. HOPKINSON ホプキンソンピアノ社
ジョン・ホプキンソンによって設立
音楽出版社から出発したピアノ製造メーカーで、
1990年ベントリー社によって買収
下のトレードマーク画像は「匿名希望様」からご寄稿頂きました。ありがとうございます! |
HORACE WATERS & CO.
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
HORACE WATERS & CO. ホレイス・ウォーターズ
ニューヨーク 詳細不明 |
| HORNUNG & MOELLER |
詳細不明 |
| HÖRÜGEL |
詳細不明
※下記HORUGELと同じか?不明 |
HORUGEL
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ホルーゲル ドイツ 詳細不明
|
|
HORUGEL



画像クリックでHPへ戻る
|
ホルーゲル/(オノ・ホルーゲル)
※HORUGELの発音で”ホリューゲル”もありますが”ホルーゲル”という読み方が一般的なようです
<発売元>
小野ピアノ販売店 (住所当時:大阪市住吉区帝塚山西2-8-3*)
<製造元>
株式会社 小野ピアノ製作所
東京蒲田楽器製作所(蒲田ピアノ修理所)
斉藤楽器株式会社
有限会社 及川ピアノ製作所
西村ピアノ商会
創始者の小野好氏は仙台の富豪で、最初は最初は蓄音機の販売で成功し、
昭和8年、東京大田区の六郷にピアノ工場を持ち、
戦争中は神奈川県湯河原に疎開して大きく発展したようです。
トレードマークには、ONO PIANO,COとあります。小野ピアノ。
ホルーゲルは同社のメインブランドでした。
このピアノは私自身1台しか調律したことはありませんが、
作りはうーん。。といった印象です。ただし、かなり古いピアノでした。
<別情報>斉藤喜一郎氏がドイツ留学から帰国後、東京蒲田楽器製作所を設立し
ブッフホルツとホルーゲルピアノを製作したとの情報もあり(詳細不明)
■機種/モデル バリエーション
U5→ 特製ハンマー使用 (黒塗、マホガニー、ウォルナット)
U6→ レンナーハンマー使用 (黒塗、マホガニー、ウォルナット)
U7→ レンナーハンマー&レンナーアクション使用 (黒塗、マホガニー、ウォルナット)
|
HOTTA

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
HOTTA ホッタ
株式会社 堀田楽器製作所(名古屋)、堀田オルガン製作所、株式会社 堀田洋行
名古屋の楽器商堀田洋行は、戦後一時オルガンで大当たりし、
引き続きピアノを製作したが、こちらはそれほどではなかった。
創立者の堀田悟朗氏(明治36年生)は、上海のモートリーピアノで技術を学び、
昭和28年ごろグランド型のオルガンを発案し、ピアノの代用として一時期よく売れた。
61鍵、73鍵などがあった。
|
| HOUGEL |
HOUGEL,HUGEL,(FOOGEL?),(FOUGEL?) ヒューゲル (フーゲル)
明音楽器製作所(浜松) FOOGELの説もある
|
HOWARD/R.S.HOWARD
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ハワード R.S.HOWARD CO アメリカ(ニューヨーク) 創業1902年
R.S.ハワードは1902年に設立され、ニューヨークにありました。
R.S.ハワードとC.R.ハワードが創業したが、1920年代にヤンセン・ピアノ社に売却した。
R.S.ハワード社のピアノは、大恐慌の時代に他の多くのピアノと同様の不幸な運命を辿り、
1932年にはラインの製造を停止した。
R.S.ハワードピアノについて
残念ながらR.S.ハワードについての情報はあまりなく、
このすぐ下の、ボールドウィン社の「HOWARD」と混同しないように注意が必要です。 |
HOWARD
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ハワード Howard Pianos Company アメリカ(オハイオ州シンシナティ) 創業1895年
ハワードピアノ社は、1895年にオハイオ州シンシナティのピアノメーカーとして設立されました。
このすぐ上の「R.S.ハワード」のピアノと混同されることが多いが、ハワード・ピアノ社は
ボールドウィン・ピアノ社の子会社です。ご注意下さい。
1959年、ボールドウィン社は「ハワード」のブランド名称を使った家庭用オルガンの製造を開始した。
1960年には、グランドピアノの多くがカワイ製になり、後にサミック製になった。
ギブソン・ギターがボールドウィン・ピアノ社を買収した際、ハワードの名称も買収され、
2001年以降に製造された一部のピアノに使用されている。
ハワードピアノの名前は、ボールドウィンピアノ社やギブソンギター社で製造された
様々なスタイルのピアノに使用されていました。
1959年以前の初期のハワードピアノの多くは、「アクロソニック」ピアノという名前が付けられていました。
1959年から1968年に製造されたハワードピアノのシリアルナンバーは、アーカンソー州コンウェイの
ボールドウィンピアノの工場で製造された縦型ピアノのものだった。
ハワードピアノは、高価で高級なボールドウィンピアノの一部に対して、より手頃な選択肢として提供された。
ハワードピアノは信頼性と耐久性の高いピアノとして知られており、現在でも多くのハワードピアノが
比較的良好な状態で残っている。 |
HSINGHAI
(XINGHAI)


画像クリックでHPへ戻る
|
HSINGHAI/XINGHAI シンハイ(星海) 中国北京
同じメーカーでXINGHAIとHSINGHAIの2種類の表記が混在しますが、理由は不明。
漢字で書くと星海と書く中国北京製のピアノです。
中国の首都である北京には楽器を取り扱っている軽工業公司の総元締である
総公司があるので北京製のピアノは中国で最も優れたピアノだと言えよう(当時)
グランドはフルコンサートを含む4種類、アップライトの種類も大変多い。
北京のピアノ工場は音楽大学と密接な関係があり、音楽大学にはピアノ科の学生
一人一人に1台のピアノが備え付けられている。
ニエアル(聶耳)と同じで星海も中国の有名な作曲家で、フルネームは洗星海
(シェン・シンハイ)である。彼は1905年に広東省の漁師の家に生まれ、
努力して広東の嶺南大学を卒業後、フランスに行き、パリ音楽院で作曲を学ぶ。
そして1935に上海に帰国したとき、抗日救国運動が激しく燃え上がっている
のを見て、多くの救国歌曲を作ったと伝えられている。
後に武漢から延安に入り、すぐに芸術学院音楽家主任となり、民族音楽の採集、
整理、研究をした人で、有名な中国の歌劇である東方紅(トンファンホン)も
この時代に生まれたといわれている。
彼は多くの民族色豊かな作曲を残すと共に、1940年に社会主義リアリズムの
新しい音楽をいかにして民族音楽の形式と結合させるかという野望を抱いて
ソ連に渡り、第一交響曲(民族解放)と、第二交響曲(神聖なる戦い)を作曲したが
惜しくも胸部疾患のため1946年に他界。
彼は中国にとっては最も社会主義に尽くした文化人であるから、北京製のピアノに
彼の名前が残されたのであろう。
中国の輸出用ピアノにはエーデルスタイン(EDELSTEIN)と名付けられている。
シンハイのトレードマーク画像は「匿名希望様」からご寄稿頂きました。ありがとうございます!
会社の名前通り、海と星をモチーフにしたデザインで、マーク内には星海、HSinGHAiと入っています。
トレードマーク画像は「匿名希望様」からご寄稿頂きました。ありがとうございます!
XINGHAIの公式HP →★ |
| HUAERSEN |
HUAERSEN PIANO/華爾森鋼琴 中国(浙江省) 創業2000年
詳細不明 |
| HUGEL |
HOUGEL,HUGEL,(FOOGEL?),(FOUGEL?) ヒューゲル (フーゲル)
明音楽器製作所(浜松) FOOGELの説もある
|
| HUMMEL |
詳細不明 |
| HUMPHREY, LONDON |
詳細不明 |
| HUNDT & SOHN |
詳細不明 |
HUNTINGTON
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
Huntington Piano Company
ハンティングトン スターリング・ピアノ・コーポレーション アメリカテネシー州
※STERLINGの項目も参照
ハンティントン・ピアノ・カンパニーは、1894年にコネチカット州シェルトンで設立された。
製造はコネチカット州で行われていたが、オフィスとショールームはニューヨークのブルックリンにあった。
スターリング・ピアノ・カンパニーに支配されていたが、後にウィンター・ピアノ・カンパニーに吸収され、
1960年代まで生産と販売を続けた。
ハンティントン社は、電動式と手動式のピアノやプレーヤーピアノを製造していた。
1930年代に入ると、ハンティントンは小型のコンソールピアノやスピネットピアノ、
さらには小型のベビーグランドピアノのラインを発表した。
これらの楽器は、毎日の演奏に耐えうる耐久性があることで知られていた。
これにより、ハンティントンはアメリカの一般家庭向けのピアノメーカーとして市場に位置づけられ、
多くのピアノ教室や家庭での練習がこれらのピアノで行われた。
また、ハンティントンのピアノは、当時の多くのピアノと同じようなスタイルで、美しい外観を持っていた。
優雅なケースデザインと堅固な構造で知られています。 |
HUPFELD

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
フプフェルト
フプフェルトは1800年代後半に創立されたドイツ・ライプツィヒのメーカーです。
→詳しくはRONISCH(レーニッシュ)の項目を参照 |
HUPFER

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
HUPFER フッペル ドイツ(ツァィツ市/Zeitz) HUPFER PIANOS
1874年創業? 第二次世界大戦中、ヒトラーによって工場が壊されて閉業
ドイツにあるツァイツ市は、ドイツのライプツィヒの南南西、約30~40kmほどの所にある町です。
フッペルピアノは手づくりを貫いていたピアノ工房で、1台1台コツコツと丁寧に製作されていたとのことです。
ベーゼンドルファーなどと同様、大量生産ではない貴重なピアノで、日本国内に現存確認されているピアノは、
現在4台ほど(グランドピアノに於いて)しか確認されていません。(2020年現在私自身の調べ)
このフッペルが有名になったのは、戦時中の特攻隊員を主人公にした映画「月光の夏」(1993年公開作品)で、
この映画に登場するいわゆる「特攻ピアノ」がこのフッペルのピアノになります。
ドイツのHUPFERの鍵盤蓋に書かれている書体 →★
<参考>
映画「月光の夏」の内容はフィクションのようです。詳細は下記に記します。
実はこのフッペルのピアノを弾いたのは特攻隊員ではなく、目達原第11錬成飛行隊の3式戦未修教育を
受けていた特別操縦見習士官(特操)2期生の少尉であることがご本人への聞き取りにより確認されています。
二人が所属したことになっている特攻部隊そのものも実は実在せず、その行動経過も架空のフィクションです。
映画製作や地域おこし町おこしの観点からこの件についてはやや伏せ気味になっております。
この件に関する考察は、「244戦隊ホームページ」での解説がとても詳しいので参考にしてみて下さい →★
<映画で使われたピアノ>
現在この映画に使われたフッペルのピアノは1995年から佐賀県鳥栖市にある多目的施設「サンメッセ鳥栖」の
1階にある「情報と憩いの場(ふれあい広場)」に「平和への願いの証」として常設展示公開されております。
ちなみに、受付で手続きをすれば短時間の演奏も可能だそうです。
<現在当方が所在把握している国内に現存する4台のフッペルのグランドピアノは下記の通りです>
■佐賀県鳥栖市 「サンメッセ鳥栖」の1階「情報と憩いの場」 ※→元々は「鳥栖小学校」にあったピアノ
■鹿児島県知覧町 「知覧特攻平和会館」のロビー ※音は出せないとのこと
■鳥取県日南町 「日南町立日野上小学校」の体育館 ※日野上小学校の公式HPにフッペルの解説ページあり
■山口県岩国市 「古民家カフェ 光風堂」 ※塗装を剥がして大修復したので現在のピアノは木目調とのこと
→もし間違った情報だったり、追記情報や所在変更があった場合などがあれば是非教えて下さい。 |
HUPFER
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ
|
HUPFER フッペル
上記ドイツのHUPFER(フッペル)とは違う、国内製造のピアノのようですが、
まくり部分(ピアノ鍵盤蓋の部分)に書かれているブランド銘柄文字が上記ドイツ製の書体と同じです。
(特徴的である”U”の文字の形がまったく同じです)
これが本場ドイツのフッペルピアノのコピー商品なのか?詳細や理由は一切不明です。
参考→ドイツのHUPFERの鍵盤蓋に書かれている書体
製作が上杉 漸氏という情報もありますが詳細は不明。
ドイツ製のフッペルをただ改造しただけなのか?新情報をお待ちしております。
トレードマークは菊の御紋?の様なマークの中央に、マイナス溝のボルト?があるように見えます。 |
HUTTNER
HÜTTNER



画像クリックでHPへ戻る
|
HUTTNER/HÜTTNER
ヒュッツナー/ヒュットナー/ハッツナー(どの読み方が正式なのか不明)
トーカイ楽器/東海楽器製造(株)
当時:浜松市寺脇町36 (※東海楽器の現在のHPには寺島町とあるが詳細は不明)
現在:浜松市南区遠州浜2-26-10 (現在はギターのみの製造で、ピアノの製造はしていません)
機種:U5DM、U5DW、E1-M、E1-M(CUSTOM)等 ※Mはマホガニー、Wは木目調
TOKAI楽器には2枚目(下)のような別のトレードマークもあるようです。2人の天使?が描かれています。
こちらの画像は「Atelier sonorite」様よりご寄稿頂きました。ありがとうございます!
<東海楽器が製造したブランドを列挙いたします>
■ TOKAI(トーカイ)
■ BOLERO(ボレロ)
■ SILBER STEIN(シルバースタイン)
■ HUTTNER(ヒュッツナー)
■ GOLD STAR(ゴールドスター)
東海楽器に関するの詳しい解説は、「トーカイ」のブランド項目参照 |
| HYFTE, VAN C. |
詳細不明 |
HYUNDAI
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
Hyundai ヒュンダイ 韓国 ローゼンストックRS101などと似たピアノ
韓国の自動車メーカーのヒュンダイとは違うのか?同じなのか?詳細不明 |
上記Hから始まるブランドの中で、追記出来そうな事項や新情報を発見した場合、修正受付フォーム よりお気軽にお知らせ下さい。
どんな些細な情報でも構いませんので、広く皆様からのフィードバックをお待ちしております。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
 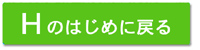 



上記Iから始まるブランドの中で、追記出来そうな事項や新情報を発見した場合、修正受付フォーム よりお気軽にお知らせ下さい。
どんな些細な情報でも構いませんので、広く皆様からのフィードバックをお待ちしております。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
 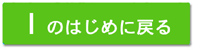 



上記Jから始まるブランドの中で、追記出来そうな事項や新情報を発見した場合、修正受付フォーム よりお気軽にお知らせ下さい。
どんな些細な情報でも構いませんので、広く皆様からのフィードバックをお待ちしております。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
 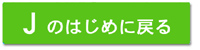 



ピアノ銘柄ブランド
トレードマーク 紹介
& 知名度ランキング

|

メーカー/ブランド説明・会社沿革・歴史・製作者・特徴・音色・他
|
| K. FENNER |
詳細不明 |
| K. KAWAI |
ケイ・カワイ 株式会社 河合楽器製作所 |
K. HERRMANN
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
K.HERRMANN K・ヘルマン 日産楽器/日産工業株式会社(浜松市) 詳細不明 |
K. TORIYAMA
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ケイ・トリヤマ
製造元:東洋ピアノ製造株式会社
製造元:株式会社 河合楽器製作所
発売元:鳥山楽器店 |
| KADETTE |
詳細不明 |
| KADENZA |
詳細不明 |
KAFMANN


画像クリックでHPへ戻る |
カフマン KAFMANN 韓国製
注:イタリア製ではありません、イギリスのKAUFMANNでもありません
発売元:東洋ピアノ製造株式会社
カフマンのまくり(フタ部分)の銘柄マーク →★
カフマンの画像はすべて匿名希望者様からご寄稿頂きました。ありがとうございます!
※参考
下記に列挙するブランドはすべて同じ雰囲気のトレードマークとなっており、どれも韓国製造と思われます。
REID-SOHN、KAFMANN、SAMICK、SCHNABEL、WEINBURG、U. WENDELL、UHLMAN SUPER |
| KAIM |
詳細不明 |
| KAIM & GUNTHER |
詳細不明 |
|
KAISER



画像クリックでHPへ戻る
|
カイザー
天龍楽器製造株式会社
日本楽器製造株式会社
ヤマハ株式会社
発売元:河合楽器株式会社
河合楽器(河合ピアノの河合滋氏の義兄の設立)が
日本楽器の天竜工場にオーダーして作ったピアノです。
製造がヤマハで、売るのがカワイということで不思議な感じがしますが、
カワイピアノ製作所とは関係がなく、エテルナと同じ背景のピアノです。
販売するお店が京橋にあったので京橋カワイとも呼ぶ人もいます。
機種バリエーション:35等
ピアノの歴史ってなかなか面白いですよね♪
カイザーのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★ |
KALLMANN
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
カルマン 井ヅツピアノ(井ヅツ楽器株式会社)大阪 井ヅツピアノで発売したブランドの一つ。
Nは1個か2個か不明 ※KALLMANN? KALLMAN?
その他詳細不明 |
| KALLMANN |
ゲルスカルマン/ゲルス・カルマン/ゲルス・アンド・カルマン/(グロスカールマン)
販売元:昭和楽器
→GÖRS & KALLMANN (GORS KALLMANN)の項目へ |
| KANN, GEORG |
詳細不明 |
| KAPPLER |
詳細不明 |
KAPS
KAPS, ERNST

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
カップス KAPS ドイツ
エルンスト・カプス・ピアノ・ファブリック
(Ernst Kaps Piano Fabrik、エルンスト・カプス・ピアノ工場)
1858年に創業されたドイツのピアノ製造会社
最初の工場はドレスデン・Seminar通り220から22番地にあった。
カプスはザクセン王国御用達称号を得た。 |
KARAJAN

画像クリックでHPへ戻る |
カラヤン KARAJAN
東日本ピアノ製造株式会社 浜松
その他詳細不明
参考:トレードマークは「KEMPF/ケンプ」と同じ天使のデザインです
<参考資料>
東日本ピアノ製造株式会社を含む会社遍歴は下記の通り
昭和28年 大岡楽器製作所が発足
昭和31年 白鳥楽器製作所
昭和33年 スワン楽器製造株式会社
昭和38年 ガーシュインピアノ株式会社
昭和42年 東日本ピアノ製造株式会社
昭和62年 株式会社バロック |
| KARLBACH |
カールバッハ アメリカ(シカゴ) 詳細不明 |
| KARL RÖNISCH |
→RÖNISCH(レーニッシュ)の項目参照 |
KARLEN
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
KARLEN カーレン 日本 杉山直次 詳細不明
|
KARN
D. W. KARN
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
カーン D.W. KARN カナダ(ウッドストック) 創業1867年
D.W.カーン社は、1867年にカナダのオンタリオ州ウッドストックに設立された。
当初は「Miller and Karn」と呼ばれていたが、1873年に正式に社名を変更した。
1900年代初頭にはモリス・ピアノ・カンパニーと提携し、
1909年から1920年にかけて社名を「カーン・モリス」に変更した。
1924年に同じカナダのシャーロック・マニング社が買収した際には、
同社のラインを吸収し、単に「Karn」と改名した。
当時のD.W.カーン社は、カナダ国内でも最大級のピアノメーカーでした。
創業者であるD.W.カーンは、ウッドストック市民に多くの仕事を提供し、市長にも選ばれ、
国会議員にも2度立候補したほど、地域の人気者だった。
1870年から1924年の間に生産されたピアノの数は約25,000台。
組立ラインが発達していなかった時代に、これだけの数を生産するのは大変なことである。
これらのピアノは、カナダ、アメリカ、そしてイギリスにまで出荷された。
残念ながら、1961年にシャーロック・マニング社が生産を中止してしまった。
大陸横断という過酷な環境に耐えうる優れた音を持つカーンピアノは、
アマチュアから上級者まで人気の高い楽器であった。
一流の工場で熟練した職人の手によって製造されたカーンピアノは、
高品質で耐久性があり、それに見合った美しいケースワークを備えていた。 |
| KASSELMAN |
詳細不明 |
| KATZMAREK & CO. |
詳細不明 |
KAUFMANN
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
カフマン イギリス 詳細不明
※韓国製のKAFMANNとは違う
|
|
KAWAI






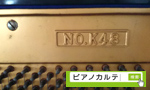

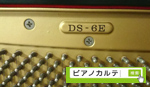
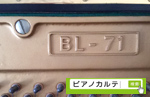
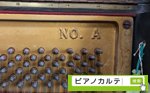

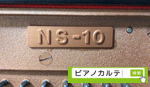




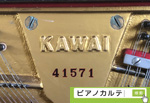
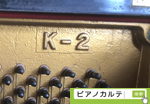
画像クリックでHPへ戻る
|
カワイ KAWAI (株)河合楽器製作所 創業1927年
※森興業株式会社
言わずと知れた日本のピアノメーカーです。ヤマハに次ぐメーカーです(生産台数として)
世界に目を向けても世界第2位の製造台数です。
トレードマークは時代によって大きく変更されたり、微妙に変わったりしています。
ちなみに製造台数(アップライトピアノ)は、ヤマハが618万台、カワイが258万台となっています。
ヤマハはカワイの倍以上の製造をしていますね。(西暦2007年時点に於いて)
製造番号はすべて1番からの通し番号で、二つとして同じ製造番号はありません。
従いまして、メーカーの製造番号から製造年も分かります。
日本楽器(現ヤマハ株式会社)に12歳から勤務していた河合小市氏が独立し、
昭和2年(西暦1927年)に河合楽器研究所として設立したのが始まりです。
カワイは日本で初めて独自のアクションを製作したピアノ会社です。
X-JAPANのYOSHIKIがカワイの透明なピアノ(クリスタルピアノ)を使っているのは有名です。
某調律師さんからこのカワイのクリスタルピアノについて下記のような情報を頂きました。
ヤマハ内部の人からの情報によりますと、YOSHIKI氏が以前浜松駅で展示されてたこのクリスタルピアノを見て、
同じような感じのピアノを作って欲しいとヤマハに一度オーダーを持ちかけたようです。
しかし、ヤマハは「プラスチック(アクリル)のボディーで作ったピアノは弊社の求める音では無い」と拒否。
それでもYOSHIKI氏は、どうしてもそのプラスチックピアノが欲かったらしく、結局カワイに頼んだそうです。
先日、1台1億円もするクリスタルピアノがカワイから売り出され、高額すぎない!?と話題になりました。
力ワイ・ピアノは、アルトゥール・ルービンシュタイン国際ピアノマスターコンクールと、
ショパン国際ピアノコンクールで、公式楽器に認定されました。
<豆知識>
カワイのアップライトピアノに一時期採用された「トーンモダレーター」と呼ばれる、
響板の一部に開けられた小窓穴により、響板内に響く籠もった音をピアノの裏側へ排出拡散させ、
音の重なりやハーモニーを豊にさせようとする目的で開けられた穴のことですが、
このトーンモダレーターの採用は一時期のみで、その後一切採用されなくなりました。
カワイのアップライトピアノのアクションレールに貼られたシール
→★
同じくカワイのアップライトピアノのアクションレールに貼られた別バージョンシール(JIS8341)
→★
古いカワイ内部にある防錆剤(ダイアナ)の小袋 →★ カワイの昔懐かしいキーカバー →★ →★
昭和38年製カワイピアノの証明書(保証書) →★ 昭和38年製カワイピアノ(K48)御愛用の栞 →★
カワイのまくり(フタ部分)にあるKAWAIブランド銘柄マーク
→★ 古いタイプはこんな感じもあり →★
カワイのフルコンサートグランド(EX)の響板デカール →★
<カワイの歴史>
河合小市氏は1897年から日本楽器(現ヤマハ)に勤めていたが、1927年に独立して自身の会社を設立した。
河合が最初に製作したピアノは64鐽のアップライトで、350円で売られた。そしてその一年後、河合は最初の
グランドピアノを製作する。河合が会社創成期に克服しなくてはならなかった困難は並大抵のものではなかった。
優秀な職人も、良質の材料も不足していただけでなく、販売網が確立されていなかったからだ。
1930年代にはすでに社名が河合楽器製作所となり、年間250台程度だった生産高が1,000台にまで増大したが、
第二次世界大戦で工場は完全に破壊され、将来の見通しが立たなくなってしまった。
河合小市氏の努力と前向きさに加え、学校のカリキュラムに音楽が組み込まれたことも追い風となり、
工場は再設立され、1949年にはアップライトとグランドの生産が開始された。
1953年にはピアノ生産高が年間1,500台にまで伸び、従業員数は500人になった。日本におけるカワイの多大な
功績を称えられ、河合小市氏は天皇陛下より栄誉ある藍綬褒章(らんじゅほうしょう)を受章した。
このような賞を受賞したのは楽器産業界初であった。
1955年に河合小市氏が亡くなると、息子の河合滋氏が会社を引き継ぎ、生産高を向上させるため、
工場に近代的な生産技術を導入する。河合は若い親たちに子どもの音楽教育の有用性を訴えるなど、
積極的なセールス手法をとり、特にピアノを推奨した。そして全国規模の音楽教室のネットワークと、
音楽講師の養成学校を設立した。その後、河合は生産ベースを工場1ヶ所から14ヶ所に拡大する。
その中には1988年に設立されたアメリカの工場も含まれる。
1960年代、力ワイは約2,000人の訪問セールス員を雇い、カワイ音楽教室には300,000人以上が受講。
アメリカ国内でピアノと電子オルガンを販売するため、1963年に力ワイアメリカコーポレーションが設立され、
力ワイヨーロッパ、力ワイカナダ、力ワイオーストラリア、力ワイアジアが続いて設立された。
1980年、面積29,879平方メートル(9,038坪)の工場が建設され、
1日に60台のグランドピアノを生産することが可能になった。
1989年に滋氏の息子の河合弘隆氏が社長に就任し、製造工程にロボット技術を導入するために
莫大な資金を投入した。近年、会社は生産拠点をアメリカやマレーシアなどの日本国外に設立した。
より丈夫で安定したアクション部品の材料を追求し、力ワイは他に先駆けて新素材を使用し始め、
現在の力ワイのアクション部品はABS樹脂などでできている。
<附録>
カワイピアノ 製造番号/製造年対照表(1951年~1988年) →★
カワイピアノ 製造番号/製造年対照表(1988年~2012年) →★
<ピアノ調律技術者向け附録>
張弦作業に役立つ当該機種ミュージックワイヤー配線仕様 →★
<以下、ウィキペディアより引用抜粋>
日本楽器製造(現・ヤマハ株式会社)に勤務していた河合小市が独立し、1927年(昭和2年)に
河合楽器研究所として設立された。1935年(昭和10年)に合名会社、1951年(昭和26年)に株式会社へと改組。
1952年(昭和27年)に河合小市が死去すると、1955年(昭和30年)、娘婿の河合滋が社長に就任。
1956年(昭和31年)にカワイ音楽教室を創設、音楽教育事業によるユーザ層の拡大に乗り出すと共に、
1989年(平成元年)に河合弘隆が社長に就任し、滋は会長に専任となった。
河合滋が社長を務めていた頃は、業界に先駆けてピアノの割賦販売を打ち出すなど、同業のヤマハと切磋琢磨し、
日本の音楽普及に貢献した。
バブル時代にはゴルフ場事業等にも進出し、非ピアノ事業の育成を企図した多角化を行ったが、
近年はピアノ事業に回帰する姿勢を鮮明にしている。
ピアノを中心とした楽器製造・販売のほか、近年はカワイ精密金属などでピアノの部品素材のノウハウを生かした
半導体素材の生産も行っている。
かつてはDTM関連製品やムーンサルト、F-I、Rockoonシリーズ等のエレキギター/エレキベース、
K5000シリーズなどのシンセサイザーを製造・販売していたが、現在では楽譜作成ソフトウェア
「スコアメーカー」や入力用の小型キーボード「HYPERCAT」を除き撤退している。
出版部門は「カワイ出版」のブランドで、多くの楽譜、音楽書を出版している。
音楽書以外にも絵本等の出版も行っている
また、ピアノの製造過程で出る端材を活用して、木製の玩具なども発売している他、
学校向けのスポーツ用具も製造している。
国内のアコースティックピアノにおけるシェアはヤマハが約6割、同社が同4割で長らくこの比率は変わっていない。
ヤマハが特約店方式で各地の楽器店と契約しているのに対し、全国に直営店を展開している。
グランドピアノは1990年代まではドイツ製ピアノの影響が強い製品を製造していたが、
現在ではスタインウェイの特徴を取り入れ、近代化されたRXシリーズを中心に、手作り工程と
入念な出荷調整を取り入れた高級機SKシリーズ、コンサート用のSK-EXシリーズを出荷している。
アップライトはKシリーズを出荷している。
いずれも炭素繊維強化プラスチックを採用してレスポンスを改善したアクションを特徴としている。
また騒音対策としてエニタイム仕様やピアノマスク仕様のピアノも出荷している。
他にも外装部が透明アクリル樹脂でできているクリスタル・ピアノ「CR-40A」を受注販売している。
連合赤軍あさま山荘事件の発生当時、連合赤軍に占拠されたあさま山荘の所有者であった。
(正確には当社の健康保険組合の所有)
1970年代以降、カワイはピアノ性能の一貫性と安定性を向上させるための代替素材の使用を開拓してきた。
1971年、カワイは木材の使用と関連する問題を克服するためにアクションの部品に
ABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)複合材料を使用し始めた。
カワイの設計エンジニアは、湿度の変化にともない顕著に収縮および膨潤する性質を持つ木材は、
安定なピアノタッチを確保するために厳密な公差を維持しなければならないピアノアクションで使用するためには
理想的とは言えない、と結論を下した。
そのため、彼らは選ばれた木製アクション部品を徐々にABS部品に置き換えた。
カワイによれば、カリフォルニア州立工科大学ポモナ校、教授Abdul Sadatによって
1998年に行われた科学的試験では、カワイのABSアクション部品が相当する木製部品よりも強く、
湿気による収縮と膨潤に対してはるかに影響されにくいことが明らかとなった。
カワイは、複合材料部品の使用によってカワイのピアノアクションは他のメーカー製のものよりも安定で
一貫性があると宣伝している。
2002年、カワイは炭素繊維入りABS樹脂を使ったウルトラ・レスポンシブ・アクションを発表した。
ABSカーボン(ABS-Carbon)と名付けられたこの新素材はカワイのアクション部品の強度を高め、重さを低減し、
これによって全体のアクション操作がより速くなった(トリルを演奏する時のコントロールのために
非常に重要である)炭素繊維の追加はABSカーボンアクション部品の剛性も高め、
これによってアクションは奏者のより少ない労力でより大きな力を生み出すことが可能となった。
カワイは、素材および設計におけるこれらの進歩が長年にわたって高い堅実性を持って
ウルトラ・レスポンシブ・アクションが奏者の意図により正確に応答するのを助ける、と強く主張している。
※一般向けグランドピアノとフルコンサートグランドの中間的ピアノである「SHIGERU KAWAI」という
特別ブランドも河合楽器製作所から出しております。詳しくは→Shigeru Kawaiの項目へ
<参考資料:河合楽器が戦後直後に製造した小型ピアノ>
ピアノ外観写真 →★ 前パネを開けた写真 →★ 下パネを開けた写真 →★
これらの写真は「匿名希望様」からご寄稿頂きました。このたびは貴重なお写真をありがとうございます!
このカワイ小型ピアノですが、戦時中は軍需工場となっていたカワイの工場が爆撃され、
製造工程リストも焼失、ピアノ部品も破壊、その後のピアノ製造が困難になってしまった頃、
終戦後のわずか2年後から河合氏が奮闘して製造を始めたピアノとのことです。
ピアノ本体サイズは、横幅109cm×高さ104cm×奥行き56.5cmで鍵盤数は64鍵。
現在の一般的なピアノの鍵盤数が88鍵なのでいかに小型なのかが分かります。
このピアノにはモデル形式が無いようで、"音響窓"の形や高音弦の数もバラバラで、
まくり部分にあるブランド表記もKAWAIだったりK.KAWAIだったりしたようです。
この情報も「匿名希望様」から頂きました。情報ありがとうございます!
カワイのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★ |
KAYSERBURG
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
中国 カイザーバーグ/カイザーブルグ?読み方不明
製造:パールリバー アップライト及びグランドも製造
その他詳細不明
HP:https://kayserburgusa.com/ |
KAZUMI
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
カズミ
アトラスピアノ製造株式会社 |
| KEILBERG |
詳細不明 |
KEIMAN
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
KEIMAN カイマン/(ケイマン)
永栄楽器(名古屋)、東洋ピアノ製造(株) 浜松市竜洋町高木
その他詳細不明
別資料によると”KWIMAN”というピアノもあるようだが、同じピアノなのか違うピアノなのかは不明です。 |
| KEISLAIR |
詳細不明 |
KEMBLE

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
KEMBLE ケンブル イギリス ミルトン・キーンズ
Kemble and Company Ltd.
ケンブルのピアノは、豊かでまろやかなヨーロッパ的な音色で知られている。
バイエルンの「持続可能森林」のスプルース材が響板に用いられており、また鍵盤も
さまざまな気候条件において安定した状態を保てるように同じくスプルース材で出来ている。
クァンタム131の外装デザインは、イギリスの有名なデザイン会社
コンラン・アンド・パートナーズ社が手掛けた。
ケンブルの従業員の70パーセント以上が同社で15年以上働いており、その豊かな経験は
世代から世代へと工場の中で受け継がれている。
1930年代に生産された『ミンクス』というアップライトピアノは高さが90cmしかなく、
アクションは鍵盤より下に位置するため、鍵盤後部が上がることによって突き上げるのではなく、
下から引き上げることでハンマーヘッドが弦へ向かう仕組みだった。
また追加で、弦が発する音量を弱くするモジュレーターを取り付けることができた。
ケンブルの輸入会社は成功し、1920年までにはロンドンのストーク・ニューイントンの工房で
自社の楽器を製作するようになった。第一次世界大戦までこの地域はピアノの町だったため、
ロバー卜・ケンブルは工房の職人を見つけるために、正面の窓にカーテン代わりにピアノフェルトを
吊るしている家を探してまわったという。そのような家を見つけると、戦前にピアノ工房で
働いていた者がいないか尋ね、もしいれば、その人を雇った。ケンブルは妻のいとこの
ヴィクター・ジェイコブスとともに働き、彼の会社は1920年代と30年代の厳しい経済情勢下でも
繁盛した。1935年にケンブル社は3つの新モデルを売り出す。ジュビリー(その年のジョージ5世
在位25周年を記念した名称)と、キュビストと、ミンクスだ。特に小型のミンクスの人気は
めざましく、これらの楽器への需要は生産が迫いつかないほど高まった。
1939年になると、ケンブル社は戦争に協力するため、爆撃機のドアを生産するようになったが、
戦後はすぐにピアノ生産を再開した。1967年、ケンブル社はクラーマー(Cramer)と
ブリンスミード(Brinsmead)のブランド名を買収し、翌年、ロンドンからミルトン・キーンズの
ブレッチリーへ移転した。ここでは今もアップライトピアノが生産されている。
その前の年に、ケンブル社はヤマハ株式会社の電子オルガンを配給する契約を結んでいた。
そしてその配給契約は株式購入へと発展する。1971年にヤマハはケンブル社の少数株主となった。
1980年代の初め、ケンブル社は廃業の一歩手前まで追い込まれるが、その寸前にディートマン・
ピアノをイギリスで生産するという大きな契約をイパッハ社から取り付ける。
1984年にケンブル社はまた苦境に陥り、ふたたびヤマハが多額の投資をして、
今回は株の過半数を取得した。1986年まで、ケンブル社はヤマハの名前でヨーロッパ市場向けの
ピアノを生産し、生産高を急激に増やすために大きな投資をした。1992年、ケンブル社は
輸出部門で英国女王賞を受賞。3年で輸出量が2倍以上になった。1999年に生産高はピークに達し、
約7,000台のピアノが生産された。そして現在も安定した生産高を保っている。
したがって、近年のものはヤマハ製アクションを使用している。
現在、ケンブル社はヨーロッパでも最も進んだピアノ製造工場を誇る。
1968年にロンドンの伝統的なピアノの町から、パッキンガムシャーのミルトン・キーンズへ
移った先見の明により、会社は見事な成長を遂げて、今やヨーロッパ最大のピアノ製作会社となった。
<附録>
ケンブルピアノ 製造番号/製造年対照表(1930年~2000年) →★
<以下、ウィキペディアより引用抜粋>
ケンブル(Kemble)は、1911年にロンドン北部のストーク・ニューイントンでマイケル・ケンブルによって
創業されたピアノ製造会社である。
2009年の生産終了までイギリスで約35万台のアップライトピアノおよびグランドピアノを製造した。
父の会社を引き継いだ後、創業者の息子はピアノ生産をミルトン・キーンズのブレッチリーへ移転した。
1964年、イギリスのピアノメーカー・J・B・クラーマー& Co.を買収した。
1968年に日本の楽器メーカーヤマハとの合弁事業Yamaha-Kemble Music (UK) Ltd. が発足し、
この会社はイギリスにおけるヤマハの輸入・楽器およびプロオーディオ機器販売業務を担当した。
1986年、創業者の孫のブライアン・ケンブルが社長となった。
1980年代はイギリスの経済が落ちこみ、1986年にヤマハがケンブル& Co. の支援に乗り出した。
以後、2009年まで約12万台のピアノが生産され、1992年には輸出に関する功績によりピアノ産業として
唯一「The Queen's Award for Export Achievement」を授与された。
2007年7月、ヤマハはケンブル家が少数保有していたYamaha-Kemble Music (UK) Ltd. の残りの株式を購入した。
売却後、Yamaha-Kemble Music (UK) Ltd. はYamaha Music U.K. Ltd. に改名されたにもかかわらず、
この売却はヤマハのイギリスにおけるピアノ販売・製造部門であるKemble & Co. Ltd. には影響を与えなかった。
2009年、ケンブルピアノの生産は全てアジアへ移され、欧州での生産が終了した。
これによってイギリスにおけるピアノ製造の幕が降ろされた。
閉鎖時にも、ケンブルはまだ年間約7千台のピアノを輸出していた。
ケンブルは2018年現在中国で生産されるヤマハの手頃な価格のブランドである。 |
KEMPF

画像クリックでHPへ戻る |
KEMPF ケンプ 東日本ピアノ製造(株) 浜松
詳細不明ですが、トレードマークはKARAJANと同じ天使のデザインのようです。
<参考資料>
東日本ピアノ製造株式会社を含む会社遍歴は下記の通り
昭和28年 大岡楽器製作所が発足
昭和31年 白鳥楽器製作所
昭和33年 スワン楽器製造株式会社
昭和38年 ガーシュインピアノ株式会社
昭和42年 東日本ピアノ製造株式会社
昭和62年 株式会社バロック
トレードマーク画像は「匿名希望様」からご寄稿頂きました。ありがとうございます! |
| KENNY & SONS |
詳細不明 |
| KENT & COOPER |
詳細不明 |
| KESSELS |
詳細不明 |
| KESTER, LUDWIG |
詳細不明 |
KEYFER
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
KEYFER キーファー 日本 詳細不明
|
| KEYLARD |
詳細不明 |
KHOHL
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
KHOHL コール ドイツ 詳細不明 |
KIDO
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
キド ミカドピアノ 詳細不明 |
| KILBOURNE |
詳細不明 |
KIMBALL


画像クリックでHPへ戻る |
KIMBALL PIANOS キンボール ジャスパーコーポレーション(アメリカ)
創業1857年 ※現在は生産されていません
キンボール社は小さな小売店から始まり、世界最大クラスのピアノ製造会社へ発展した。
それは創立者のウィリアム・ウォレス・キンボールの賢明さと努力の賜だったとも言える。
キンボールは音楽的なバックグラウンドはなかったものの、1850年代の市場変化への優れた洞察力を持ち、
アイオワの土地を売ってグロヴェスティーンとトラスローのスクエアピアノを4台購入し、
1857年にシカゴに小売店を開いた。
1864年、キンボールは名門クロスビー・オペラハウスの中に店舗を設け、低価格のリードオルガンや、
チッカリング、ヘールなどの東海岸のメーカーのピアノを販売した。
キンボールは精力的に働き、すぐにアメリカ西部で最大のピアノディーラーになり、会社は繁盛し続けたが、
1871年にシカゴ大火に見舞われ、キンボール社はすべての商品と在庫、ならびにショールームを失う。
ジョセフ・ヘールはキンボールが築き上げてきた業績への尊敬の念から、「とりあえず私の10万ドルを
使って下さい」と、火事の当日に電報を打ったと伝えられている。
キンボールは店を自宅に構えなければならないほどだったが、1880年には100万ドルを超える
収益を上げるようにまでになった。
1880年代にはリードオルガンの生産を開始し、1882年に面積960,000平方フィート(89186平米)
の工場をオープンしてからは、年間15,000台もの楽器を製造するようになった。
1887年に既存のオルガン工場を増設し、1888年からはそこでピアノの生産がスタートした。
最初の年に生産された500台のピアノは満足のいかない出来だったが、スタインウェイやベヒシュタインに
勤めていた技術者を雇ってからは、楽器の品質が一気に向上した。
キンボール・ピアノは積極的に売り込まれ、数多くのショールームに展示された。
そして展示にとどまらずキンボール社は40人の出張セールスマンによって販売もされ、北米の隅々まで
販路を広げるためにキンボールに雇われた人たちだった。
そうしたことで、キンボールは、パイプオルガンおよびピアノ製造の伝統的な長い歴史を持ち、
現在では電子オルガンのメーカーとしても世界的に知られている。
生産するピアノの種類は極めて多く、スピネットからコンサートグランドに至る各種ピアノのほかに、
プレイヤーピアノ(自動ピアノ演奏)まで作っている。
ウィリアム・ウォレス・キンボールは会社を後継者に遺して1904年に亡くなった。
キンボール社は中価格市場向けのピアノを生産し、1910年に絶頂期を迎えるが、1959年には破産状態に。
原因は1930年代の大恐慌と、当時の社長W.W.キンボール・ジュニアによる度重なる楽観的な判断だった。
1959年、オフィス家具メーカーのジェスパー・コーポレーションというインディアナ州の
アメリカ屈指の巨大なテレビおよびステレオなどのキャビネットメーカーの傘下になり、
社名はキンボール・インターナショナルに改められました。
従業員はピアノ製作の経験がなく、生産したピアノの半分が工場に戻ってくるという結果になったものの、
キンボールピアノは他のメーカーと比較した場合、はるかに有利な条件で木材が入手出来たという。
その後、生産技術は向上し、1966~67年にかけてオーストリアの偉大なピアノメーカーである
ベーゼンドルファー社を買収し、さらに1980年にはアメリカのクラカウアー社を買収したことにより、
ピアノ製作面でのサポートを得て、 その秀でたピアノ製作技術がキンボールに導入されました。
その後、1995年にグランド製造中止、翌年1996年にはアップライトも製造中止に。
<キンボール社の特徴>
キンボールはその長い製作の歴史の間に、幾多の構造上・デザイン上のパイオニア的役割を果たしています。
第一に挙げられるものとしては、”ライフクラウンド”とよばれる響板の改良である。
これは気温や湿度の変化に対して絶対に割れる危険性のない、通常の3倍の強度を持ったものとのことだ。
また、”ユニロック”とよばれるチューニングピンを確実に保持する装置の開発によってピアノの調律を
長持ちさせることに成功している。
さらにキンボールは、”スーパーフォニックスケール”とよぶアップライトピアノの音色を、
グランドピアノの音色に近づける方法や、耐水接着剤の使用を可能にしたエレクトロニック接着法の開発、
その他幾多の新技術をピアノ工業へ導入し、その製造技術を飛躍的に向上させました。
また、現在あらゆる鍵盤楽器に白と黒の鍵盤の原型を作り出したのもキンボールであると伝えられています。
ピアノやオルガンの白鍵と黒鍵の配列法は非常に微妙で、黒鍵は白鍵の真ん中にはなく弾きやすいように
各音によって少しづつ左右にずらしてあります。
<キンボールの別解説>
1857年にW.W.キンボールによって設立されたキンボール・ピアノ・カンパニーは、
当時人気のあったブランドのピアノや手頃な価格のリードオルガンを販売するピアノディーラーとしてスタート。
1877年には、W.W.キンボール自身がリードオルガンを製造するようになり、
当時の世界最大のオルガン製造を支える施設を建設した。
残念ながら、1871年のシカゴ大火で、キンボールの店が入居していたクロスビー・オペラ・ハウスは
大きな被害を受けた。最近、8万ドル以上かけて改装したばかりだったが、火事で消失しまったのだ。
火事のあわただしい中、キンボールと彼の知人たちは、残りの建物の内容物が灰燼に帰す前に、
たった7台のグランドピアノを燃える建物から運び出すことができた。
10年後の1888年、キンボール社はピアノの製造を開始し、1902年には22,000台のピアノを製造するなど、
当時としては最大級のメーカーとして名を馳せた。
その後、第二次世界大戦の影響で業績が悪化したため、キンボール社はシカゴからインディアナ州に移転。
1959年、Kimball社はJasper社に売却され、Jasper社はKimballピアノの名前とシリアルナンバーの製造を続けた。
ピアノの販売がピークを迎えた1960年代から70年代にかけて、Kimball社は家庭用・オフィス用家具や
電子機器の製造を開始し、Kimball International社として株式を公開した。
売り上げの減少に伴い、ピアノ・オルガン部門は閉鎖され、1996年に最後のキンボール・ピアノが生産された。
キンボール社は、20世紀を通じていくつかの小規模なピアノ会社を買収し、
世界恐慌の時代から1900年代半ばにかけて、最大のピアノメーカーのひとつとして名を馳せた。
ピアノのまくり(蓋部分)にあるKIMBALLのブランド銘柄マーク →★ キンボールの外観全体写真 →★
画像はすべて「gunchan様」からご寄稿頂きました。ありがとうございます!
キンボール社は、アップライトピアノ、グランドピアノ、スピネットピアノなど、
さまざまな種類のピアノをさまざまな名前で製造していた。
<過去にキンボール社が取り扱ったピアノブランド名一覧>
Kimball、Conn、Jasper-American、W.W.Kimball、Hinze、
Harrison、Schuerman、De Voe & Sons、Whittaker、Becker、
La Petite、Krakauer、Whitney、Whitmore 計14種類確認済み |
KINDERSTONE
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
キンダーストーン 発売元:(有)ツルミ楽器 |
KIMURA PIANO
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
キムラ・ピアノ 木村末雄・正雄 |
KINCAID

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
キンケイド KINCAID アメリカ(ノースカロライナ)
ノースカロライナのモルガントンで作られているピアノで、会社名はグランドピアノ会社。
この会社名から推察すると、グランドピアノを専門に作っているように想像できますが、
名称とは真逆に安価なアップライトのみを作っており、ピアノには15年の保証をつけて販売。
キンケイドピアノには種類が多く、約25種類もある。
日本のピアノといえば黒塗りが多いが、アメリカやヨーロッパのピアノといえば、
生地塗りや部屋の模様にマッチしたさまざまなデザインのものが多いのが普通です。
キンケイドにもさまざまなデザインのものがありますが、そのデザインにも伝統的な
流儀があり、あまり突飛なものがあるわけではありません。
ちなみに、キンケイドピアノのデザインは大きく分けて次の9種類に分類されます。
■モダン:近代的なデザインののっぺりしたデザイン(別名ボックストライク)
■コンテンポラリー:現代風の部屋にマッチしたケースのピアノ
■トラディショナル:伝統的なスタイルのケースで、アメリカでは最も人気
■トランシィショナル:過渡期という意味で、トラディショナルとコンテンポラリーの中間的デザイン
■アーリー・アメリカン:開拓史時代のデザインのケース
■スパニッシュ:スペイン風の優雅なスタイルのケース
■フレンチ・プロビンシアル:フランスの田舎風なという意味で、ネコ脚のついたロココ風な優美なデザイン
■イタリアン・プロビンシアル: イタリアの田舎風なという意味で、古風なデザイン
■メディタレニアン:地中海風のという意味で、重厚なデザインのもの
|
KING
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
キング アメリカ(シカゴ) 詳細不明
|
KING DAVID
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
キングデイビッド 台湾(中国)
聲茂楽器製造股份有限公司
工場は新竹県湖口工業区にある。
奥行き140cmのベビーグランド1種類のみ製造し、アメリカやイギリスなどに輸出していたとのこと。
|
| KINGSBURG |
詳細不明 |
KINGSBURY
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
キングスブリー ケーブル・ネルソン(ケーブルピアノ社) アメリカ(オレゴン州)
このブランドは、学校やピアノ教育専用に使われているとのこと。 |
KIRKMAN

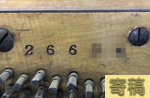
画像クリックでHPへ戻る |
KIRKMAN カークマン イギリス(ロンドン)
KIRKMANに関する画像はすべて「アンジュールの家」様よりご寄稿頂きました。ありがとうございます!
チューニングピンが特殊な形状ですね。通常のチューニングハンマーでは調律出来なさそうです。
■ 前パネ部分には見事な象眼細工が施されております。その外観写真 →★ →★
■ まくり(フタ)部分の銘柄マーク →★ →★
その他詳細不明
|
| KIRSCHNER |
詳細不明 |
| KISTING |
詳細不明 |
| KLAVINS |
詳細不明 |
| KLEIN |
詳細不明 |
| KLIMA |
詳細不明 |
| KLINGMANN |
詳細不明 |
| KLOPPE, H. |
詳細不明 |
KLEUZER
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
クリューツァー 稲葉ピアノ株式会社 |
KLIBEL

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
KLIBEL クリーベル 興和楽器製作所(浜松市天竜川西岸) S・クリーベル
クリーベルという名前は他にも多く、例えば、
■クリーベル(KRIEBEL)ドイツ製
■クリーベル(KRIEBEL)東日本ピアノ製造(株)静岡県浜松市天竜川町332番地(当時)
■クリーベル(CREABEL) 共立楽器 などがあります
クリーベルのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★ |
KLINGEL



画像クリックでHPへ戻る |
クリンゲル
昭和54年、浜松市の向宿町に設立されたトニカ楽器製造のブランドで、
戦前は東京神田神保町のピオバ楽器が広田ピアノに製作を依頼していました。
ですが、いま見かけるクリンゲルピアノは韓国製(英昌)がほとんどだと思われます。
※FOREST(フォレスト)やTONICA(トニカ)の項目も参照
トレードマーク画像は「カノン様」からご寄稿いただきました。ありがとうございます!
ご寄稿者様によりますと、昭和56年のご購入で、ペダルは3本、
左側の拍子木には着脱可能な時計が埋め込まれていたとのことです →★ →★
左記画像のピアノの販売は永栄(えいさか)楽器のようです →★ →★
クリンゲルのまくり(蓋部分)の銘柄ブランド部分 →★
機種バリエーション:KU3等 |
|
KLINGEL



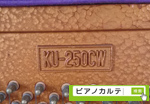
画像クリックでHPへ戻る
|
クリンゲル
※写真のトレードマークは韓国(英昌)製のものです
当時、協立楽器が販売しており、ローゼンストックなどと同じ系統のピアノです。
作りや音色もローゼンストックピアノとほぼ同じです。
■機種バリエーション
G803、G806、KU250、KU380、KU700など
クリンゲルピアノの保証書 →★ クリンゲルピアノのまくり(蓋)部分の銘柄マーク →★
※広田ピアノ株式会社、トニカ楽器製造株式会社、浜松ピアノ製造株式会社、
及び有限会社ツルミ楽器との情報もあるが、基本的に韓国の英昌楽器製造のものばかりです
クリンゲルのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★ |
KLINGMANN
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
KLINGMANN クリングマン ドイツ 詳細不明
|
KLUGE
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
クルーゲ ドイツ(レムシャイト)
詳細不明
<以下、ウィキペディアより引用抜粋>
クルーゲ・クラヴィアトゥーレン(Kluge Klaviaturen、クルーゲ鍵盤)GmbHは、
ドイツ・レムシャイトの大手ピアノ鍵盤製造業者である。
毎年グランドピアノ、アップライトピアノ、およびオルガン用の鍵盤約8千個を生産している。
現在、クルーゲは欧州における最も重要なピアノ鍵盤製造業者である。
約50人の従業員が働いている。
1876年、イバッハ社の鍵盤部門の長であったヘルマン・クルーゲ(Hermann Kluge)が、
ノルトライン=ヴェストファーレン州ヴッパータール近郊のバルメン(英語版)で
"Hermann Kluge Claviaturen-fabrik KG" を創業した。
この若い会社はすぐに市場での地位を獲得し、しばらくしてクルーゲはスタインウェイ・アンド・サンズを
顧客とした。生産数は順調に増加し、1902年には既に10万個目の鍵盤が作られた。
1943年までの生産数は50万個と推定される。
この年に全ての専用機械と供給品があった生産施設と事務所建物が破壊されたため、
正確な数をこれ以上遡ることはできない。
第二次世界大戦後、忍耐の時期に入った。賃貸の部屋で当初は家具や窓、扉などが製造された。
元の生産施設の復旧には膨大なエネルギーが必要であり、1946年に事務所建物の地下室で
鍵盤の修理を開始することができた。
ほぼ5年後、工場建物の復旧後、鍵盤の生産を再び開始することができた。
再開後の初年には既に500以上の鍵盤が完成された。
続く53年間、会社は多くの浮き沈みを経験してきた。
ハイライトは間違いなくベルリンにあった強力な競合企業Bohn Claviaturen社の買収であった。
Bohn Claviaturen社の生産はポーランドへ移転された。
また重要な出来事は、1999年にアメリカ合衆国の世界最大の楽器製造業者の一つである
スタインウェイ・ミュージカル・インスツルメンツ社によってクルーゲ・グループが買収されたことであった。
クルーゲ社はこの取引によっていかなる損害も被らなかった。
背後に名高い親会社を持つことで、会社の強固な基盤が築かれた。
ほぼ全てのヨーロッパのグランドピアノおよびアップライトピアノ製造業者と自身の鍵盤生産部門を持たない
海外の一部の業者はほぼ例外なくクルーゲから鍵盤を輸入している。
クルーゲ社の広告文句は「The key tot quality and success」である。 |
| KNABE BROS. |
詳細不明 |
| KNABE & GAEHLE |
詳細不明 |
| KNABE, GAEHLE & CO. |
詳細不明 |
|
KNABE
KNABE, WM. & CO.
|
→W. M. KNABEの項目へ |
KNABE
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
クナーベ ドイツ 詳細不明
|
KNABEL
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
クナーベル 明音楽器製作所(浜松市) 詳細不明
|
| KNAKE |
詳細不明 |
| KNAUER |
詳細不明 |
| KNAUSS |
詳細不明 |
KNIGHT

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ナイト Knight イギリス・ロンドン/イングランド Since 1935
ナイトのアップライトピアノは温もりのある歌うような音色で、高音部は均一な響きを持つ。
ナイトの鉄フレームは標準的なピアノのフレームの二倍の強度を待つ。それは桁の構造原理に基づいた
全周フレームで、ビーチ材の4本支柱の背面構造に固定されている。
極めて高い調律の安定性を得るため、ピン板はフレームのポケットに収められている。
K10モデルには高音部のストレスバーがない。ピアノの左下の角に弦張力に抵抗するためのバーが
何本かあり、響きが弱くなることを防ぐ。チューニングピンを支えて調律の安定度を強化するため、
硬質繊維板のビンブッシュが用いられている。重い純銅線が巻かれた低音部の弦は総重量が3Kgある。
<歴史>
ラジオ、映画、蓄音機の出現によってすでに苦しんでいたピアノ産業は、
1930年代の大恐慌でさらに大打撃を受ける。
そのような状況ドの1935年に、アルフレッド・ナイトは絶大な自信をもってロンドンに会社を設立した。
アルフレッド・ナイトはさまざまなピアノ会社で働いた経歴があり、また才能のあるピアノ奏者でもあったため、
自分が作った楽器を喜んで実演していた。
ナイトのピアノ作りへの情熱は報われ、創業から10年経つ頃には、
ナイト社は年間1,000台のピアノを生産していた。
第二次世界大戦中もナイト社は政府からの受注でピアノを作り続けた。
1944年のノルマンディー上陸作戦の直後、保護のため金属の緑を取り付け、ビールをこぼしても大丈夫なように
特別に作られた9台のナイト製ピアノが、ヨーロッパ大陸へ上陸したと言われている。
戦時中もピアノ生産を中断せずに済んだナイト社は、戦後、他メーカーに大きな差をつけることが出来た。
アルフレッド・ナイトは輸出先を開拓しようと休みなく働き、自社のピアノが高い水準に達していることを
センスとユーモアを交えて実演してみせた。
1955年、アルフレッドは会社をエセックス州ラフトンの大きな工場へ移し、50年代の終わりに
ブリティッシュ・ピアノ・アクション社の経営権を取得した。
アルフレッドは当時新たに開発されたプラスチックを用いて、自らピアノアクションの再設計に着手した。
彼は黒鉛を含ませたナイロンとグラスファイバーを用いて、摩擦のないジャックとフレンジを
作り出すことに成功し、さらに、染みがつかない白いプラスチックの白鍵キートップを開発した。
アルフレッドが亡くなると、会社の経営は娘の一家が引き継いだ。
1991年から、ナイト・ピアノは自社仕様の楽器の生産を、ブリティッシュ・ピアノ・マニュファクチャリング社の
一部であるウェルプデール、マックスウェル・アンド・コッドに依頼している。
<附録>
ナイトピアノ 製造番号/製造年対照表(1936年~2000年) →★ |
KNOCHEL
KNÖCHEL AD.
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
クノッヘル ドイツ 詳細不明 |
| KNUDSEN, J. |
詳細不明 |
| KNUDSEN & SONS |
詳細不明 |
| KOCH & KORSELT |
詳細不明 |
| KOCH & CO. |
詳細不明 |
KOGURO
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
コグロ
株式会社 協信社ピアノ製作所
有限会社 エスピー楽器製作所 |
|
KOHLER & CAMPBELL
KÖHLER & CAMPBELL


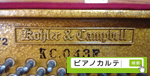
画像クリックでHPへ戻る
|
KÖHLER & CAMPBELL (アメリカニューヨーク、現在は韓国製造)
ケーラー・アンド・キャンベル/(コーラー・アンド・キャンベル)
ケーラー&キャンベルは1896年ニューヨークで創業、1983年までに毎年約1万台を生産し、
約800,000台以上のピアノを世に送り出したアメリカ最古のピアノメーカーのうちのひとつです。
1977年、韓国のサミック社にブランド譲渡され、輸出向けブランド「ケーラー&キャンベル」として 、
外装・組み立て等工賃のかかる工程をインドネシアで仕上げることによって、
コストパフォーマンスに優れた製品に改変。
日本に輸入されたピアノは、東洋ピアノの管理の中で出荷調整がなされ国内販売されています。
近年販売されたピアノはKÖHLERではなく、どこの部分を見てもKOHLERになっていますが詳細不明。
ピアノの拍子木にあるプレートの写真 →★
【歴史】
1896年にケーラーと、キャンベルの二人が組んでピアノ製作を始めたことからこのブランドが生まれました。
この会社は20年たたぬうちに、アップライトピアノ、自動ピアノと自動再生アクションの性能において
世界有数のものにのし上がったとききます。
このケーラー・アンド・キャンベル社は20世紀の初めに自動アクションの製作に専念し、
それを他のメーカーに販売する傍ら、ベルトミニヨンの再生アクションを作り出して、蓄音機が出来る以前、
はじめて一般の人にコンサート以外でピアノ演奏を聞かせるという功績を残しました。
その後、オート・ニューマチック・アクション社とスタンダード・ニューマチック・アクション社という
二つの子会社を作り、あらゆるピアノメーカーへ自動ピアノアクションを売り続け、その売上げは年間
5万台にものぼったと記録に残っています。
この会社は、その後アメリカで最も古いピアノメーカーであるフランシス・ベーコン社を吸収しているので、
その技術の源は1789年にさかのぼる最も伝統を誇れるものとなりました。
元来、ニューヨークにあった会社ではあったが、その後ノースカロライナに近代的な工場が建てられ、
全米その他に500もの代理店を持ったこともあります。
読み方
× コールアンドキャンベル、
△ コーラーアンドキャンベル
○ ケーラーアンドキャンベル
ケーラーアンドキャンベルのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★ |
KOHLER & CHASE
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
Kohler & Chase コーラー&チェイス/ケーラー&チェイス
アンドリュー・コーラーは、1850年1月にカリフォルニア州サンフランシスコに移住してきた際、
さまざまな楽器のコレクションを持ってきた。
彼は、小さな建物を借りて楽器の販売を始め、事実上、サンフランシスコで最初の楽器店を始めた。
新しいビジネスは成功し、売上も伸びてきたので、コーラーは甥のクインシー・A・チェイスと
パートナーを組むことにした。コーラーとチェイスは、カリフォルニア州の他の都市にも楽器店を展開し、
大量の楽器を集めて販売した。
1886年にアンドリュー・コーラーが亡くなった後も、クインシー・A・チェイスは繁栄していた会社を拡大し続け、
1906年にはクインシー・チェイスの息子であるジョージ・Q・チェイスが社長に就任して、
一族の楽器販売の伝統を引き継いだのである。
コーラー&チェイス社のピアノは、1895年から1957年までの製造番号が付いている。
コーラー&チェイス社は、店舗で販売する楽器の製造を外部に委託していた。
コーラー&チェイス社は、西海岸の企業でありながら、
ニューヨークでいくつかのメーカーにピアノを作らせていた。
バーチカルピアノはアーネスト・ガブラー・ピアノ・カンパニー、グランドピアノはジェイコブ・ドール&サンズ、
そして最高級のアンドリュー・コーラー・ピアノはウェルズモア・ピアノ・カンパニーが製造していた。 |
KONETZNY
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
コネツネー ドイツ 詳細不明 |
KONING (KÖNING)



画像クリックでHPへ戻る |
KONIG (KÖNIG) ケーニッヒ
有限会社 三陽楽器製作所、有限会社 ケーニッヒピアノ製作所、マライ楽器製造
当時の本社住所:浜松市伝馬町148番地(現:浜松市中区伝馬町)
当時の工場住所:浜松市中野町670番地(現:浜松市東区中野町)
神原清作氏の設計、および製造指導によって作られた。
神原清作氏は明治28年生まれ。日本楽器で山葉直吉氏、河合小市氏らに教えをうけたが、
後にアメリカに留学しボストンのフォースト調律学校を卒業した。
ケーニッヒのまくり(蓋部分)の銘柄マーク →★
ケーニッヒのエンブレム画像は「PIANO YOSHIKAWA様」よりご寄稿頂きました。ありがとうございます!
ケーニッヒのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★ |
KONKORIDIA
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
KONKORIDIA コンコリディア 日本 詳細不明
|
KONO

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
KONO コーノ
コーノピアノ研究所(浜松)
浜松の河野充喜氏が自身の工房で作り組み立てていたピアノ。
河野氏はアトラスの出身。
|
KORIN
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
コーリン 光輪ピアノ製作所/(有)光輪楽器製作所(浜松) 詳細不明 |
| KORT DE |
詳細不明 |
KRAFT




画像クリックでHPへ戻る |
KRAFT クラフト
クラフトピアノ製造株式会社
写真は、MODEL:132DW 機種:DU-9
当ページに掲載のエルスナー(ELSNER)というピアノのトレードマークに酷似しています。
トレードマークの外周の円から、ワシ(タカ)の羽根の飛び出し具合や雰囲気などを含め、
エルスナーのトレードマークにそっくりです。
ひょっとしたら、クラウス商事株式会社製のピアノなのかもしれませんが、詳細は不明です。
詳しくはエルスナーの項目へ。
クラフトピアノのまくり(蓋)部分の銘柄マーク →★
<特徴追記>
このクラフトのピアノの低音弦の巻線ですが、銅線の巻き方が一般的な向きでの巻き方とは違い、
逆巻きとなっており、極めて珍しいとのことです。断線した巻線を新たに作ってもらう際に判明しました。
ヨーロッパのピアノに逆巻きが見られますが日本製で逆巻きは見たことがないとおっしゃっていました。
左記画像の上から3枚は匿名希望様よりご寄稿頂きました。ありがとうございます! |
| KRAFT, AUG. |
詳細不明 |
KRAKAUER
KRAKAUER BROTHERS

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
クラカウアー KRAKAUER BROS アメリカ 工場:ニューヨーク 創業1869年
<読み> ○ クラカウアー × カラカウアー
この会社は創業1869年より長い間、家系を重んじ、手工業一途に作り続けてきたメーカです。
製作されているピアノの種類は多く、そのすべてが伝統的な外装を見事に引き継いだもので、
キンケイドの項目でも触れていますが、各種の典型的なクラシックピアノのケースの由来を
本格的に伝えるのがこのクラカウアピアノです。
尚、このクラカウアーピアノの特許に、アップライトピアノの背面を飾り板でふさぐ
というものがある。これは必ず壁に背を向けて置くという従来のアップライトピアノの常識を破り、
グランドピアノと同様に、部屋のどこにでも置けるようにしたもです。
大量生産のピアノではないので日本ではほとんど知られていませんが、品質は極めて優れたもので、
ニューヨークの公立学校だけでも1000台以上も使われているとのことです。
※一時期はキンボール社にて製造
<以下、ウィキペディアより引用抜粋>
クラカウアー・ブラザーズ (Krakauer Brothers) は、クラカウアー (Krakauer) としても知られていた、
アメリカ合衆国の手作り高級ピアノ製造業者で、1869年にニューヨークで、ユダヤ人の移民だった
サイモン・クラカウアー (Simon Krakauer) が、息子デイヴィッド (David) や兄弟のジュリアス (Julius)
とともに創設した。
やがて成長した同社は、ニューヨーク市ブロンクス区のサイプレス・アベニュー (Cypress Avenue) に面した
136丁目から137丁目にかけての場所に、工場を開設した。
クラカウアーは、高品質のピアノの製造とともに、19世紀末から20世紀初めのピアノの発達において
影響力の大きな革新によって知られた、卓越したピアノ製造会社であった。
1917年、クラカウアーは、マディソン・ピアノ・カンパニー (Madison Piano Company) を合併し、
「マディソン (Madison)」ブランドでも数十年間にわたってピアノを製造した。
クラカウアー・ブラザーズは、より大きなコングロマリットに吸収されることなく世界恐慌を生き延びた
数少ないアメリカ合衆国のピアノ会社のひとつであった。
1977年、ハワード・K・グリーヴス (Howard K. Graves) がクラカウアーを買収し、
事業をオハイオ州ホームズ郡バーリン(英語版)に移した。
クラカウアーは、ヴァーティコード (Vertichord)、リリコード (Lyrichord)、
そしてマディソンのブランドで製造を行った。
その後、クラカウラーは1980年にキンボール・インターナショナルの一部門になり、
製造番号86405以降はこの体制で生産された。
バーリンの工場は、1985年に閉鎖され、これによりクラカウアーの名は終わりを告げることとなった。
<別解説>
1869年、シモン・クラカウアーとその息子デビッドによって、ニューヨークに
クラカウアー・ブラザーズ・ピアノ・カンパニーが設立された。
ドイツのキッシンゲン出身のシモン・クラカウアーは、バイオリニストやオーケストラの指揮者として
活躍していたが、1854年にユダヤ人移民としてアメリカに渡り、会社を設立した。
シモンは、A.H.ゲイルやヘインズ兄弟など、当時のピアノ界の巨匠たちに師事し、
音楽家としての教養を身につけた上でピアノメーカーに転身した。
分の店を開いてからは、最高の音楽的音色を持つピアノを作ることに専念した。
1867年、ジュリアス・クラカウアーとダニエル・クラカウアーが加わり、クラウアー・ブラザーズとなった。
その数年後の1903年には、サイモンと息子のデビッドが亡くなった頃に会社が設立された。
1900年代初頭、クラウアー・ブラザーズはフェルダーやマディソンのピアノも製造していた。
フェルダー、マディソン、ベルティコード、リリコードなどのモデルがあった。
世界大恐慌の間も、クラカウアー・ブラザーズは大規模なメーカーへの売却を余儀なくされることなく、
ピアノの生産を続けた。
1977年、ハワード・グレイブスが会社を買収し、オハイオ州のベルリンに事業を移転した。
1980年にはキンボール・ピアノ・カンパニーの一部門となり、1985年にキンボール社が倒産するまで、
クラカウアー・ブラザーズのピアノは生産され続けた。
クラカウアー兄弟のピアノは、1900年代初頭の小規模なピアノブランドとは異なり、
非常に高い品質のピアノを製造していた。
クラカウアー兄弟は、スタインウェイやチッカリングと同じように、ピアノの音色の向上に力を注いでいた。
凝ったデザインのケースで知られるクラッカー兄弟のピアノは、大量生産を行う現代のピアノ会社とは異なり、
1台1台手作りで丁寧に作られていた。
クラカウアーは、アップライトピアノを壁際に置くことなくオープンに展示できる
クローズドバックケースの特許も取得している。
クラカウアー・ブラザーズのスピネットは、グランドピアノと同様に展示することができ、
音や場所の制約を受けずにアップライトの外観や感触を求める多くのピアニストにアピールすることができた。
その中でも「セレナーデ」は最も人気の高いモデルである。 |
| KRAMER |
詳細不明 |
KRANICH & BACH
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
クラニッヒ・アンド・バッハ Kranich & Bach
アメリカ 工場:ニューヨーク 創業1864年
1864年、ヘルムート・クラニッヒとジャック・バッハというピアノ技術者が共同で始めた
ピアノメーカーであるためにこの名称が生まれたという。
工場はニューヨークにあり最高級のグランドピアノを製造。
音質、デザイン共に極めて優れていると言われている。
1959年にウインター(WINTER & CO.)は、エオリアン・アメリカン社と合併し、
社名をエオリアン・コーポレーションに変更していた間、KRANICH & BACHは
ウィンター&カンパニーが製造していたブランド名の一つです
→詳しくはWINTERの項目へ |
KRASNYI OKTIABR
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
クラスヌイ・オクチャーブ ロシア、レニングラード(ソ連) ”赤い十月”という意味
その他詳細不明
スペルは「KRASNYI OKTIABR」が正しいと判断しました
独自調査によると、「KRASNY OKTYABR」や、「KRASNII OKTYABR」ではないようです。
|
|
KRAUS




画像クリックでHPへ戻る
|
KRAUS クラウス
昭和36年7月から浜松市和田町の大成ピアノ製造(株)で作られていたブランドです。
その後→株式会社 プルツナーピアノ
U-127、U-130、U-133の三機種がありました。
発売元は浜松市中野町のクラウス商事。協立楽器でも販売。
クラウスというピアノには他に、イタリア製やドイツ製にも
同じクラウス(KRAUSS)がありますが詳細不明。
※一番上のトレードマークは大成ピアノ時代の頃です。
ちなみに、ドレスデン(DRESDEN)のトレードマークも製造会社が同じなのでほぼ同じデザインです。
クラウスのまくり(フタの部分)の銘柄文字マーク部分
→★
クラウスのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★ |
| KRAUSE, MAX |
詳細不明 |
KRAUSS
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
クラウス ドイツ 詳細不明 |
KRAUSS
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
クラウス イタリア 詳細不明
|
KRELL
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
クレル アメリカ(シンシナティ) 創業1889年
クレル・ピアノ社は、1889年にアルバート・クレルがオハイオ州シンシナティで創業した。
アルバートは2人の息子、アレクサンダーとアルバート・ジュニアの協力を得て会社を設立し、
3人でピアノメーカーとしてささやかな成功を収めた。
しかし、1895年、わずか6年でアレキサンダー・クレルは亡くなってしまった。
その5年後には、父親のアルバート・シニアが亡くなった。
弟の死後、アルバート・ジュニアは一家の会社を離れ、隣のオハイオ州スプリングフィールドに
クレル・フレンチ・ピアノ・カンパニーを設立した。
しかし、ここでも悲劇が起こった。クレル・フレンチ社の工場が火事で全焼し、
再びオハイオ州のニューキャッスルに移転することになったのだ。
そんな中、アルバート・ジュニアは、自分が立ち上げた会社を辞めるという苦渋の決断をし、
「オートグランドピアノ・カンパニー・オブ・アメリカ」という新会社を立ち上げた。
この会社は、インディアナ州のコナーズビルという町にあった。
1920年代に入ると、クレルの名前はウェルナー・インダストリーズ社が所有するようになり、
彼らの工場でクレル・ラインの生産が続けられた。
1927年、スター・ピアノ社がウェルナー・インダストリーズ社を買収し、クレルのブランド名を手に入れた。
スター・ピアノ社は、大恐慌や第二次世界大戦を経て、1949年までクレルピアノの生産を続けた。
クレルのピアノには、グランドピアノ、アップライトピアノ、プレーヤーピアノなどがあり、
いずれも作りがしっかりしていて好ましい楽器として知られている。
これらのピアノは長年にわたって音楽業界で愛用され、特にワーナー・インダストリーズ社製のものは
当時とても人気があった。
一般的に、これらのピアノは内部がよくできていて、外観が美しく、すっきりとしていました。 |
| KRELL & FRENCH |
詳細不明 |
KREUIZBACH

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
クロイツバッハ KREUIZBACH (注)スペルの中には、”I”が入ります
発売元:株式会社永栄楽器(名古屋市中村区名駅5丁目)ピアノ・電子オルガン専門店
※永栄楽器の創業は1946年
製造元:アトラスピアノ製造(浜松)
※ピアノの足元にはアトラスピアノ製造のシールが貼ってあります →★
※永栄(えいさか)楽器の保証書には「クロイツバッハ」ではなく、「クロイバッハ」と記載されています。
スペルに「Z」が入るのに何故か「ツ」を表記していません。理由等は不明です。
本場ドイツのクロイツバッハからクレームが来ないようにするためなのか??
機種バリエーション:NA200、U127、特DL-117等 |
KREUTZBACH
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
クロイツバッハ KREUTZBACH ドイツ 詳細不明
(注)スペルの中には、”I”は入りません |
| KREUTZBACH, JULIUS |
詳細不明 |
|
KREUTZER



画像クリックでHPへ戻る
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ
|
KREUTZER クロイツェル (株)クロイツェル
製造元:稲葉楽器/稲葉ピアノ製作所(クロイツェルピアノの旧称)、クロイツェルピアノ製作所(製造)、
製造元:井ヅツ楽器株式会社
発売元:稲葉ピアノ株式会社
発売元:株式会社 渡辺商店
クロイツェルピアノ製作所(創業1953年)で昭和28年から製造されているピアノ。
昭和51年末に新工場設立。浜松市和田町より浜松市安新町に移転(旧称)稲葉楽器。
東京のイナバピアノと縁故が深い。
上から2枚目のエンブレム画像は「PIANO YOSHIKAWA様」よりご寄稿頂きました。ありがとうございます!
クロイツェルピアノは左記紹介の2枚の画像以外にもこれまでに何回もエンブレムを変更しています。
この2つ以外で画像をお持ちの方がいたらご連絡頂けたら幸いです。
<附録>
クロイツェルピアノ 製造番号/製造年代 対照表(1985年~2012年) →★
<以下、ウィキペディアより引用抜粋>
有限会社クロイツェルピアノ(KREUTZER)は、静岡県浜松市にあるピアノの製造業社である。1949年創業。
アップライトピアノの受注生産は2011年に終了した。
ブランド名「クロイツェル」(KREUTZER)と会社名はピアニストのレオニード・クロイツァーに由来する。
以前の名称は株式会社クロイツェルピアノ。
年間の生産台数は少ないが、手造りピアノとして、ドイツ製の基本部品を用い、
総アグラフを採用するなど高品質であり、存在を知る人の間では人気が高い。
グランドピアノは生産していないが、アップライトピアノはさまざまなバリエーションを生産している。
注文生産であり、生産台数は年間数台以下と非常に少ないため、中古ピアノの修理や再生が主な業務となっている。
機種バリエーション:KE603、特4等
<クロイツェル社の製造ブランド>
KREUTZER(クロイツェル)、LICHTENSTEIN(リヒテンシュタイン)、ROSENTHAL(ローゼンタール)
<参考>
東京ディズニーランドのアトモスフィア(開催時間、開催場所が非公開のショー)の1つに
「バイシクルピアノ」というのがある →★
アップライトピアノに椅子、ペダル付き車輪を追加装備し、
自走できるピアノを演奏する(時に走りながら演奏する)エンターテイメントである。
これに使用されている「自転車ピアノ」を製造したのがクロイツェルである。
クロイツェルのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★ |
|
KRIEBEL


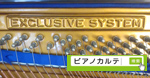

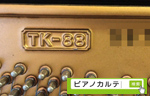
画像クリックでHPへ戻る
|
クリーベル
東日本ピアノ製造(株) 静岡県浜松市天竜川町332番地(当時)
株式会社 バロック
有限会社 興和楽器製作所
1型や3型のピアノは音色・タッチともに重厚な印象のピアノです。
機種バリエーション:TK-380、TK-88(小型)
クリーベルのまくり(フタ部分)にあるブランド銘柄 →★ クリーベルの保証書と検査カード
→★
クリーベル純正キーカバー →★
沢山清次郎氏の発明によるペダルスプリング強弱調整装置(特許No453845)も採用されています →★
ペダルスプリング強弱調整装置(拡大写真)→★(この写真はウィスタリアピアノに付いているものです)
沢山清次郎(さわやま・せいじろう)氏のイニシャルを取ってネジ部分にS.Sと入っていますね。
※ちなみにこの強弱調整装置ですが、私の実感としてさほど強弱を変えられない印象です。
クリーベルという名前は他にも多く、例えば、
■クリーベル(KRIEBEL)ドイツ製
■S・クリーベル(KLIBEL)興和楽器製作所(天竜川西岸)
■クリーベル(CREABEL) 共立楽器 などがあります
<ピアノ調律技術者向け附録>
張弦作業に役立つ当該機種ミュージックワイヤー配線仕様 →★
<参考資料>
東日本ピアノ製造株式会社を含む会社遍歴は下記の通り
昭和28年 大岡楽器製作所が発足
昭和31年 白鳥楽器製作所
昭和33年 スワン楽器製造株式会社
昭和38年 ガーシュインピアノ株式会社
昭和42年 東日本ピアノ製造株式会社
昭和62年 株式会社バロック
クリーベルのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★ |
KRIEBEL
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
クリーベル ドイツ 詳細不明
|
| KRIEGELSTEIN |
詳細不明 |
| KRIEGELSTEIN & ARNAUD |
詳細不明 |
| KRIEGELSTEIN & PLANTADE |
詳細不明 |
KROEGER
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
クローガー Kroeger Pianos アメリカ(ニューヨーク) 創業1879年
ヘンリー・クローガー&サンズ社は1879年にニューヨークで設立され、
すぐに社名を変えてクローガー・ピアノ・カンパニーとなりました。
ヘンリー・クローガーは家族と共に、アメリカ北東部で評判の良い楽器を製造する会社を作るために努力した。
この会社は、「Gildemeester-Kroeger」、「Gildemeester」、そして「Kroeger」というブランド名を持つ、
カメレオンのような会社だった。1920年代半ば、約45年間家族経営を続けてきたクローガー・ピアノ社は、
ピアノ複合企業であるコーラー&キャンベル社に売却された。
クローガーの名を冠したピアノは、1957年にコーラー&キャンベル社が生産を終了するまで生産された。
幾多の戦争や不況などの困難を乗り越えてきたこのブランドは、当時の音楽界がいかに品質と耐久性を
重視していたかを物語っている。
クローガーは、グランドピアノ、リプロダクション・グランドピアノ、プレーヤーピアノ
アップライトピアノなど、多彩なメーカーであり、そのどれもが高品質であった。
クローガーは自分の工場で生産したピアノに誇りを持っており、そのピアノはすぐに高い評価を得た。 |
| KRUMM |
詳細不明 |
| KUHLA |
詳細不明 |
KUHLMANN



画像クリックでHPへ戻る |
コールマン KUHLMANN 井ヅツ楽器株式会社
IZUTU TRADE CORPORATION(大阪市住吉区万代西6丁目10番地)
その他詳細不明
トレードマークは鳥のワシかタカ?をモチーフにしたマークですが、
共立楽器工芸社の”ASTORIA”というピアノとまったく同じトレードマークのようです。理由は不明。
ちなみにWEINBERGER(ワインバーガー)という韓国製のピアノのトレードマークにもそっくりです。
尚、ドイツの国章にもそっくりです →★ (念のためですが、「国旗」ではなく「国章」です)
参考リンク→世界各国の国章一覧 →★ (一般的に国旗よりも国章の方が複雑なデザインです)
トレードマークを並べて比べた画像 →★ (KUHLMANNとASTORIAとWEINBERGERのトレードマーク)
フレームの右上側部分には「PRODUCED BY T.YAMAHA」と入っていますが、
この”T.YAMAHA”とはあのヤマハの創始者である山葉寅楠氏のことなのでしょうか?詳細不明。
ピアノ全体像の写真 →★ ピアノまくり(蓋部分)の銘柄ブランド →★ KUHLMANN保証書 →★
トレードマーク画像を含め、これらのすべての画像は「匿名希望様」からご寄稿頂きました。
ご寄稿者様によりますと、このピアノは1979年(昭和54年)にかつて大阪にあった「心斎橋そごう」で
購入されたとの情報を頂きました。KUHLMANNの保証書画像を参照。
この度は画像のご寄稿を頂きまして本当にありがとうございました! |
| KUHSE, JOHANN |
詳細不明 |
KUNIYUKI



画像クリックでHPへ戻る |
KUNIYUKI クニユキ
発売元:クニユキピアノ社/クニユキピアノ株式会社
製造元:六郷ピアノ製作所、(東洋楽器製造株式会社でも製造していたことが判明)
戦前、神田須田町の交差点のすぐ近くにクニユキピアノ社(国行)という店があり、
六郷ピアノに作らせていたピアノをクニユキのブランドで販売、戦後もしばらく繁盛していました。
★★★
このたび興味深い事実が判明致しました。
左記トレードマーク画像とメーカー名を見てください。
東洋楽器製造(広島ワグナー)とまったく同じトレードマークになっております。
広島ワグナーでもクニユキを製造していたようです。戦後しばらく経ってからの製造だと思います。
六郷ピアノから東洋楽器に製造を依頼したのでしょうか。詳しい真相は今のところ不明です。
今後詳しく調査いたしますが、何かこの件についてご存知の方がいたら是非ご連絡下さい。
広島ワグナーについては「WAGNER」の項目に詳しく解説がございますのでそちらを参照して下さい。
<KUNIYUKI 他の写真>
KUNIYUKIの響板に描かれたデカール →★ ピアノまくり(蓋部分)のブランド名部分 →★
左記2枚の画像も含め計4枚の画像は東京都の「匿名希望様」からご寄稿頂きました。
この度は貴重な画像をご寄稿頂きまして誠にありがとうございました! |
| KUNST |
詳細不明 |
| KUNZ |
詳細不明 |
| KUPERS |
詳細不明 |
KURTZMANN
KURTZMANN & SONS
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
KURTZMANN カーツマン/クールツマン
ゴードン・ローヘッド社 アメリカ(ミシガン州グランドヘブン)
GORDON LAUGHEADの項目も参照
1848年、クリスチャン・カーツマンがニューヨーク州バッファローで創業した、
アメリカで最も古いピアノメーカーのひとつ。
1859年、カーツマンは別の紳士と提携してカーツマン&ヒンツェ・ピアノ社を設立した。
1859年、カーツマンは別の紳士と提携し、クルツマン&ヒンツェ・ピアノ社を設立したが、
1860年代後半には提携を解消し、個人でピアノ製造を開始した。
19世紀、クルツマン・ピアノ・カンパニーは、スクエア・グランド・ピアノのモデルを何種類も試し、
徐々にアップライト・ピアノやグランド・ピアノを導入していった。
カーツマンの名でピアノを製造するほか、ケイペン社やブロックポート・マニュファクチャリング社の名でも
ピアノを製造していた。1935年にウーリッツァー・ピアノ・カンパニーがカーツマンを買収し、
1938年までカーツマン・ブランドのピアノを生産した。
カーツマン社は、精巧で高価なピアノやオルガンを製造することで知られていた。
カーツマン・ピアノのブランドは、高品質な職人技と細部へのこだわりが売りであった。
また、マホガニー材とウォルナット材の張り合わせにも定評があった。
カーツマンが製造した様々なピアノの中には、有名なウェルテ・ミニョンのピアノアクションを搭載した
リプロダクション・グランドがある。
また、多くの消費者はコンサート・グランド、パーラー・グランド、そして様々なベビー・グランドを好んだ。 |
KURTZMANN AND HINZE
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
KURTZMANN(クルツマンピアノ)の項も参照。
クルツマン&ヒンツェ社は、1859年にニューヨーク州バッファローで、
クリスチャン・クルツマンがヒンツェ氏という人物とパートナーシップを結んで設立された。
ドイツのメクレンブルクに生まれたクルツマンは、アメリカに移住し、
1848年に自分の名前を冠したピアノの製造を開始した。
1850年代後半にはヒンツェ氏をパートナーに迎え、2人で新しい名前のピアノを製造した。
しかし、このパートナーシップは長続きせず、1860年代後半には二人は別れて関係が解消された。
カーツマンは1886年に亡くなるまで、自分の名前でピアノを作り続けた。
クルツマンとヒンツェの名前で製作されたピアノは、パートナーシップが短かったこともあり、
品質や音についての情報はほとんどない。
クリスチャン・クルツマンが製作したピアノは、常に高い音色と優れたクラフトマンシップを備えていた。
クルツマン&ヒンツェのピアノにも同様の配慮がなされていたと考えられます。 |
KURZWEIL
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
カーツウェル
※カーツウェルの情報は、KURZWEIL JAPAN様に当方より直接問い合わせを致しまして、
ご担当者様より下記のようなご回答を頂きました。ご協力ありがとうございました。
↓
「中国のYOUNG CHANG社が”KURZWEIL”のブランド名を使い製造していたOEMピアノと推測される」とのこと。
「日本国内に存在することは考えにくく、大変珍しい」とご回答頂きました。
尚、「KURZWEIL JAPAN」は電子楽器の輸入代理店です。
カーツウェルピアノのまくり(蓋部分)にあるブランド銘柄マーク →★
カーツウェル公式HP:http://kurzweil.com/
カーツウェル公式HP:http://www.kurzweiljapan.jp/(日本法人) |
| KWIMAN |
カイマン 東洋ピアノ製造株式会社
KEIMANとは違いうのか?不明 |
KYORITU
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
キョウリツ アトラスピアノ製造株式会社
販売元が協立楽器のピアノかと推測 |
上記Kから始まるブランドの中で、追記出来そうな事項や新情報を発見した場合、修正受付フォーム よりお気軽にお知らせ下さい。
どんな些細な情報でも構いませんので、広く皆様からのフィードバックをお待ちしております。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
 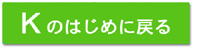 



ピアノ銘柄ブランド
トレードマーク 紹介
& 知名度ランキング

|

メーカー/ブランド説明・会社沿革・歴史・製作者・特徴・音色・他
|
L. MEISTER

画像クリックでHPへ戻る |
エル・マイスター/L.マイスター
詳細は不明ですが、「アトラス」の商標権を買い取った中国企業が製造か?
詳しくは→ATLAS(中国 阿托拉斯乐器制造(大连)有限公司)の項目参照 |
|
LA LUNA



画像クリックでHPへ戻る
|
ラ・ルーナ/(ラ・ルナ) LA LUNA
製造元:遠州ピアノ製造KK(浜松)
発売元:株式会社 日響ピアノ(渋谷)
東京の渋谷上通りにあった頼金義雄氏経営の日響ピアノ(株)が
主力商品として昭和30年頃より強力に売り出したピアノでした。
当時、渋谷上通りは1~4丁目まであり、この街区は消滅して現在この地名は存在しませんが、
現在の渋谷区道玄坂を含む東西を結ぶ通り沿いの街区でした。
詳しい旧街区を解説したページがありましたので参考にリンクを貼ります →★
鉄骨部分のロゴ(トレードマーク)は他のメーカーとは一線を画し、
五線譜とト音記号をモチーフとした印象的なマークをしています。
トレードマーク内には、E.G.Kと入っています(遠州楽器株式会社の略でしょうか)
鉄骨右側部分、LA LUNAの下には、「MANUFACTURED BY LUNAPIANO」と入っています。
※Wikipediaによると「LUNA」とはローマ神話における「月の女神」とのことです。
<ラ ルーナの画像集>
■ラ・ルーナの響板に描かれたデカール →★
→響板デカールには「ENSHU PIANO INSTRUMENT M. F. G. CO. ,LTD」と入っています
※M. F. G. = manufacturing デカールに描かれているのは月の女神でしょうか。
■ラ・ルーナの特徴的な青い鉄骨 →★
■ラ・ルーナのまくり(蓋部分)の銘柄マーク →★
■ラ・ルーナのアクション(アクションレールには「HIRADE」というシールが貼付されています) →★
→当時「合資会社 平出楽器製作所」という会社があり、「HIRADE」というピアノブランドもありましたが、
そこの会社が作ったアクションということなのでしょうか?詳細不明。
このLA LUNAの写真撮影は埼玉県のI様のご厚意により、実際にお伺いしてピアノを撮影させて頂きました。
この度はご協力頂きまして誠にありがとうございました。
ラルーナのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★ |
LA PETITE
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
キンボール社(KIMBALL)が取り扱ったブランド
→詳しくはKimballの項目へ |
| LABROUSSE |
詳細不明 |
| LAGER |
詳細不明 |
LAGONDA
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ラゴンダ アメリカ(インディアナ州ニューキャッスル) 1900年代初頭
ラゴンダ・ピアノ・カンパニーは、1900年代初頭にインディアナ州のニューキャッスルで設立されました。
最初はクレル・フレンチ社が所有していましたが、その後ジェシー・フレンチ・アンド・サンズ社の所有となる。
1940年代後半には生産が終了した。
"Lagonda Pianos, thousands in use and the demand increasing "
(直訳:ラゴンダピアノは何千台も使用されており、需要が増加している)
これはラゴンダピアノを最もよく表している宣伝文句である。
ラゴンダピアノは、その高品質な構造と人目を引く外観で、国内外に広く知られていた。
希少な木材や高級木材を含む様々な仕上げやスタイルのケースを用意し、
内部を包んでメーカーが完全に保証します。
また、アップライト、グランド、エレクトリック、フットパワーなど、さまざまなスタイルの楽器があり、
多くの音楽家に人気がありました。 |
| LAGRIMA |
詳細不明 |
LAKESIDE
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
レイクサイド
Cable Nelson(ケーブル・ネルソン)社が製作していたブランド
→詳しくはCable Nelsonの項目へ |
| LAMBERT |
詳細不明 |
L'AMOUR
(LAMOUR)
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
L’AMOUR/(LAMOUR) ラムール
※正確なスペルはLとAの間に(’)アポストロフィーが入る表記です
製造元:日本楽器製造株式会社(横浜工場)
製造元:株式会社 福山ピアノ社(フクヤマピアノ)東京
販売元:小野ピアノ販売店 |
LANCASTER
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
Estey Piano Corporation
→詳しくは「Estey」の項目へ |
LANGER
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ランゲル
戎ピアノ製作所/戎(えびす)ピアノ製作所 ※漢字は「戒」×ではなく「戎」〇です
東洋楽器製造株式会社(広島)
鈴木楽器店
ヨハネス・ウォルフ
横浜ピアノ製作所
ドイツのランゲルアクションを使用していたのでランゲルの名称が付けられた。 |
| LAUBERGER & GLOSS |
詳細不明 |
| LAUGHEAD, GORDON |
詳細不明 |
| LAURENCE & NASH |
詳細不明 |
| LAURENCE & SONS, ALEX |
詳細不明 |
LAURIE


画像クリックでHPへ戻る |
ローリー LAURIE
<販売元>
山下ピアノ社(神戸)
新宿ピアノ社(東京)
<製造元>
東日本ピアノ製造株式会社
東洋ピアノ製造株式会社(浜松)
山下楽器製造株式会社
このトレードマーク画像は匿名希望様からご寄稿頂きました。ありがとうございます!
機種バリエーション:US-3等
<参考資料>
東日本ピアノ製造株式会社を含む会社遍歴は下記の通り
昭和28年 大岡楽器製作所が発足
昭和31年 白鳥楽器製作所
昭和33年 スワン楽器製造株式会社
昭和38年 ガーシュインピアノ株式会社
昭和42年 東日本ピアノ製造株式会社
昭和62年 株式会社バロック |
LAUTER
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ラウター アメリカ(ニュージャージー州ニューアーク) 創業1862年
ラウター・ピアノ・カンパニーは、1862年にニュージャージー州ニューアークの
ブロード・ストリートに楽器店として設立されました。
S.D.ラウターは、信頼できるピアノをリーズナブルな価格で世界中のお客様に販売するという
野心的な目標を掲げて会社を設立しました。
1885年にS.D.ラウターが亡くなり、チャールズ・E.キャメロンSr.が会社を引き継ぐと、
ラウターは自社でピアノの製造を開始し、大恐慌後もその製造を続けた。
キャメロンの息子であるチャールズ・E・キャメロンJr.は、父の跡を継いだ。
父の跡を継ぎ、1936年から1966年まで会社を経営した。
後にサセックス通りにあったラウター・ピアノ・カンパニーは、1963年にピアノの製造を終了し、
1966年には販売も終了した。
ラウターピアノ社は、グランドピアノ、アップライトピアノ、プレーヤーピアノを製造し、
Lenox、Llewellyn、Lauter-Humanaなどのブランド名で販売していた。
ラウターピアノを知っている人は、彼らが外観的にも構造的にも上質な素材を使って作られていると言う。
真珠のように白い象牙の鍵盤、優れた化粧板の仕上げ、ふくよかで力強い音など、
何十年経ってもその品質の高さは目にも耳にも明らかです。
ラウター・フマナのプレーヤーピアノは、ブッシュやレーンのプレーヤーピアノと同様に、
ピアノとプレーヤーメカニズムが同じ工場で製造された希少な楽器である。
60年代のニューヨーク・タイムズ紙は、ラウター・ヒューマナのシリアルナンバー3万から5万までの
セレクションを「アメリカで最高のレギュラー・アップライト・プレーヤー・ピアノ」と評した。 |
| LAUTER-HUMANA |
→この上、LAUTERの項目へ |
LAZARE




画像クリックでHPへ戻る |
LAZARE ラザール
発売元:株式会社 福山ピアノ社(東京)
製造元:大成ピアノ製造株式会社
製造元:ドレスデンピアノ製造(浜松)
製造元:東邦楽器製造株式会社
製造元:東洋ピアノ製造株式会社
福山ピアノ社の持ちブランド。浜松のドレスデンピアノ製造で製作していました。
大型でパネルの両側の波型に特徴があります。
トレードマークには「LA CLASSE SUPÉRIEURE」とあります(上位クラス・上流階級という意味)
真ん中のトレードマークは東洋ピアノで製造したもの。
一番下の画像のようなフクヤマピアノと同じトレードマークもあります。
初期の頃のピアノ蓋部分のブランド表記はLAZAREではなく、FUKUYAMA & SONSになっています。
大型でスタイルが堂々としているのが特徴であった。
正しいスペルは「LAZARE」で、「RAZAR」ではないのでご注意。 |
LAZARO
トレードマークなし

画像クリックでHPへ戻る |
LAZARO/読み:ラザロ?ラザーロ? 日本? 詳細不明
この度、私自身、見たことも聞いたこともないピアノを偶然ネット上で発見しました。
名称が見ていますが、この上の項目にある「LAZARE/ラザール」とは別のピアノです。
最初に見たときは本当にビックリしました。極めて珍しいピアノです。
これは、宮城県にある某不動産会社様のブログからの情報で、私自身はじめてこのピアノの存在を知りました。
ご先方様に問い合わせをしたところ、写真の使用を快諾して頂いたので掲載させていただきます →★1 →★2
たくさんの貴重なお写真をご寄稿頂きまして本当にありがとうございました!
ピアノ支柱が見えない背面部やネジ部、マフラー機構、そして一昔前のベヒシュタインのように白鍵の手前部分が
丸くなっている(アール形状)等、あらゆる部分に於いてとても特徴的です(写真→★2を参照)
このピアノですが、所有者様からの情報によりますと、当時中学生だった頃、ピアノの先生から
昭和30年代初頭に譲り受けたそうです。先生が音大生だった頃に使っていたピアノだったようです。
なので、このピアノは戦前である昭和10年代頃の製造だと推測されます。
このたび新たな情報を頂きました。
中国上海で「1920-1940頃に盛業だったSam Lazaro」という情報も頂きました。製造番号表 →★ |
LEADS
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
読み:リーズ? 韓国? 詳細不明
機種:L-186等 |
LEDECZY
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
S.LEDECZY 1896年創業
Sandor Ledeczy/Sándor Lédeczy
ハンガリー(ブダペスト) その他詳細不明 |
| LEE |
→S.G.LEE 又は、T.A.LEEの項目へ |
LEGNICA


画像クリックでHPへ戻る |
レグニカ LEGNICA
ポーランド 詳細不明 |
| LEGUERINAIS |
詳細不明 |
| LEHMAN |
詳細不明 |
| LEHMANN, ADOLF |
詳細不明 |
| LEHMANN DE LEHNSFELD |
詳細不明 |
| LEICHEL |
詳細不明 |
| LEIJSER |
詳細不明 |
| LEIPZIG |
詳細不明 |
| LEIPZIGER PIANOFORTEFABRIK |
→詳しい解説は、レーニッシュ RÖNISCH (RONISCH)の項目へ |
| LELAND |
リーランド アメリカ(シカゴ) 詳細不明 |
| LENOX |
→LAUTERの項目へ |
LENYNGRAD
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
レニングラード LENYNGRAD ロシア(ソ連) 詳細不明
|
| LERPÉE, CARL |
詳細不明 |
LESAGE

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
リーセージ LESAGE PIANO LTD. カナダ
1891年に創業されたカナダ唯一の家系を重んずるメーカーです。
リーセージのモットーは「いづれにも劣らない最高品質のピアノを作る」ことにあります。
1930年台終わりに、この会社は確固とした基礎を築き上げ、他のいろいろなカナダの
ピアノメーカー(ベルピアノ、ウェーバーピアノ、クレイグピアノなど)を買収し、
その結果、カナダで第二のピアノメーカーに成長しました。
ちなみに第一はメーソン・アンド・リッシュ MASON & RISCH, LTDであろう。
リーセージはカナダ唯一の一貫工場で、極めて優れた特徴のある特殊木工機械を使い、
多くの種類の魅力的なピアノを作っている。
|
| LESCHEN, WILHELM |
詳細不明 |
|
LESTER





画像クリックでHPへ戻る
|
レスター
製造元:大和楽器製造株式会社
製造元:レスターピアノ製造株式会社
製造元:新レスターピアノ製造株式会社
大和(だいわ)楽器製造(株)で作られていたピアノで、その後レスターピアノ製造株式会社、
後の昭和46年からは新レスターピアノ製造(株)(浜松)で作られていたピアノです。
トレードマークにはSINCE1930とあります。
左記トレードマーク以外にも下部に「DAIWA GAKKI SEIZO K.K」と入っているマークもあります。
これは大和楽器製造の頃に製造されたレスターピアノです。
大和楽器製造の頃のレスターピアノのまくり(蓋部分)にあるローマ字のLの文字が
ブラックレター(Blackletter)という独特な欧文フォントで、一般の方はすぐに「L」とは分かりません。
古典的アンティークな印象の文字です。
トレードマークですが、音叉が二本交差したデザインに星形のデザインです。
この星形は調律師が使うチューニングハンマーの先端チップ部分の形からデザインしています。
ヤマハ、カワイ、アポロに次ぐ勢力を持ったこともあります。
レスターピアノのアクションレールに貼られたLESTERのシール
→★
レスターのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★ |
LESTER

※トレードマークはなし

画像クリックでHPへ戻る |
レスター LESTER アメリカ(フィラデルフィア)
LESTER PIANO COMPANY PHILADELPHIA U.S.A
現在の市場ではあまり知られていないピアノブランドであるレスターピアノは、
1900年代初頭に最も人気のあったピアノです。
1888年に設立されたレスター・ピアノ・カンパニーは、1920年代までは、Lester, Leonard & Co.、
Alden、Gounodなどの名称でピアノを製造していました。
1960年に廃業するまでの後期のピアノ名は、Lester, Betsy Ross, Bellaire, Betsy Ross Spinet,
Cable & Sons, Channing, Gramer, Lawrence, Regent, Schilling, Schubertなどであった。
ペンシルバニア州デラウェア郡に拠点を置くレスター・ピアノ・カンパニーは、1900年代初頭、
多くの人が家庭内での演奏用にピアノを購入し始めた頃のオール・アメリカン・ピアノ・ブランドであった。
レスターは、同時代の多くのブランドよりも高品質でありながら、一般のアメリカ人が手に入れやすい
価格帯であることを売りにしていた。
現在でも見られるレスターピアノの中で最も一般的なのは、「ベッツィー・ロス・スピネット」だろう。
これはサイズと音の良さから人気のモデルで、37インチと40インチがあり、様々なスタイルのものがあった。
レスターは、学校での音楽の授業や演奏時に使用する専用のピアノも販売していた。
フィラデルフィアの公立学校の多くがレスターのピアノを導入している。
1947年、レスター・ピアノ社はエルボーをプラスチック製にした新しいピアノアクションを試験的に開発した。
1940年代のプラスチックの台頭により、レスター社もその流れに乗った。
しかし、このアクションは性能が悪く、その年の暮れには会社からリコールされてしまった。
それから10年余りが過ぎ、同社はピアノの生産を完全に中止した。
内部フレームにあるLESTERブランドマーク →★ ピアノの外観写真 →★
天屋根を開けた部分にあるデカールを拡大した写真 →★
まくり(蓋部分)にあるレスター(フィラデルフィア)のブランド名部分 →★
画像でも分かるように低音域の巻線は1本張り、中~高音域のピアノ線は2本弦張りとなっているようです。
これら5枚の画像はすべて「匿名希望様」からご寄稿頂きました。ありがとうございます! |
| LESWEIN |
詳細不明 |
LEUTKE
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ロイトケ LEUTKE ドイツ 詳細不明
|
LICHTENSTEIN


画像クリックでHPに戻る |
LICHTENSTEIN リヒテンシュタイン
株式会社 クロイツェルピアノ製造
機種ブランド MK300、KS605等
<広告HPより>
LICHTENSTEIN(リヒテンスタイン)は、静岡県浜松のハンドクラフト系メーカーである
「クロイツェル」による国産ブランド。
ピアノの存在感をひときわ引き立たせる、グラデーション塗装の美しい木目調のピアノ。
譜面台には現在では珍しくなった象嵌加工、ハンドメイドならではの魅力を感じることが出来ます。
またハンマーフェルトには「レンナーフェルトハンマー(ドイツ製)」を採用しています。
<クロイツェル社の製造ブランド>
KREUTZER(クロイツェル)、LICHTENSTEIN(リヒテンシュタイン)、ROSENTHAL(ローゼンタール)
→KREUTZER(クロイツェル)の項目も参照
トレードマーク画像は「匿名希望様」からご寄稿頂きました。ありがとうございます! |
| LICHTENTAL |
詳細不明 |
LIEBERMANN

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
リーバーマン/リバーマン/(リーベルマン) LIEBERMANN 韓国(三益)
(株)協立インターナショナルの販売(協立楽器)
協立楽器が主に関西地方で多く販売したピアノで、関東ではあまり多くは販売されていません。 |
| LIEDERSTROM |
詳細不明 |
| LIEHR |
詳細不明 |
| LIESHOUT & ZONEN, M. VAN |
詳細不明 |
| LICHTENTHAL, HERMANN |
詳細不明 |
LIGE
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
リグ? 中国 詳細不明 |
LIGHT
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
LIGHT/LIGHT PIANO ライト 東海楽器製造株式会社 |
| LIGHTE, F. C. |
詳細不明 |
LIGHTE, NEWTON & BRADBURYS
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
Lighte, Newton and Bradbury Piano 創業1848年
ライト、ニュートン・ブラッドベリの歴史は非常に面白く、多くのパートナー提携の変化がありました。
ライト、ニュートン・ブラッドベリが会社になる数年前、F.C.ライトが存在していました。
ライトは1848年にF.C.ライト社を設立し、ピアノの製造を始めた。
ニューヨークのカナルストリートにあったライトは、ニュートン氏とパートナーシップを結び、
数年間一緒にピアノを生産した後、3人目のパートナーを得た。
1853年にブラッドベリ氏が入社し、1857年にニュートン氏が脱退するまで、3人でピアノ事業を行い、
そこそこの成功を収めた。数年後の1861年には、ブラッドベリ氏も脱退し、
「ブラッドベリ・ピアノ・カンパニー」を設立。
ライト、ニュートン、ブラッドベリの3社は、1853年から1857年までのわずか4年間という短い期間であった。
この3人のパートナーシップがあまりにも短命で波乱に満ちたものであったため、
これらの楽器の音や品質に関する情報はほとんどない。
しかし、1855年のコネチカット州農業協会で、彼らのピアノモデルの一つが
ベストピアノ賞を受賞していることから、良質な楽器であったと考えられる。 |
| LIGHTE & BRADBURYS |
詳細不明 |
| LIGHTE & ERNST |
詳細不明 |
| LIGHTE & NEWTON |
詳細不明 |
| LINCOLN |
詳細不明 |
| LINDBERGH |
詳細不明 |
| LINDEMAN, WM. |
詳細不明 |
| LINDEMAN & SONS |
詳細不明 |
LINDEN
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
リンデン 詳細不明 |
| LINDHOLM |
詳細不明 |
| LINDNER |
詳細不明 |
| LINDNER & SOHN, I.P. |
詳細不明 |
| LINDSAY |
詳細不明 |
LINEHORD
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ラインホルド 蒲田楽器製作所 |
| LINKE |
詳細不明 |
LIPATTI
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
リパッティ LIPATTI ルーマニア 詳細不明 |
| LIPCZINSKY, MAX |
詳細不明 |
LIPP
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
リップ LLIPP RICH (LIPP) ドイツ 詳細不明 |
| LIPPMANN |
詳細不明 |
LIRIKA
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
リリカ 旧ソ連(モスクワ) RAZNO製
まくりに書いてある文字の「R」が「K」に見えますが、「LIRIKA」ではなく「LIRIKA」です。 |
LISZT
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
リスト 袁方全、李兄弟 発売元:鈴木楽器店 |
LITMULER
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
リットミューラー LITMULER
クロイツェルピアノ製作所 |
| LITTMANN |
詳細不明 |
LIVE JANTZEN
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ライブ・ジャンセン アトラスピアノ製造株式会社 |
LIVINGSTON
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
LIVINGSTON リビングストン アメリカ
※「LIVINGSTONE」という末尾にEが入るスペルの資料もありますがこれは間違いです。
正しくは「LIVINGSTON」で、最後にEは入りません。
リビングストンピアノは、20世紀初頭にウィーバーピアノ社(Weaver Piano Company)が販売していた
3つの主要ピアノラインの1つである。
ウィーバー・ピアノ・カンパニーは、1900年頃から1930年頃まで、ペンシルバニア州ヨークの工場で、
リビングストンピアノをアップライトとプレイヤーピアノに分けて製造していた。
ウィーバーのピアノは時の試練に耐える傾向があり、それは彼らの楽器が一般のピアノよりも
高い水準で作られていたことを示している。 |
| LLEWELLYN |
→LAUTERの項目へ |
| LOHMANN PIANO CO. |
詳細不明 |
LORD
※トレードマークなし |
ロード・ピアノ・カンパニー/LORD PIANO CO.
BOSTON MASS/マサチューセッツ州 ボストン
その他詳細不明 |
| LORENZ |
詳細不明 |
LORIS
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ローリス
株式会社 プルツナーピアノ
杉山楽器製作所/杉山木工有限会社
※正しいスペルは”ROURIS”かもしれません |
LORIS & SONS

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
LORIS & SONS ローリス・アンド・サンズ
ローリスピアノ株式会社
井ヅツ楽器株式会社(大阪)
LU2B、LU2M、LU3B、LU3M、IMPB、IMPM、LUSなどの機種があり、
コールマンとともに売り出されていた。
当時の定価の記録が残っております
LU2B:53万円、LU2M:56万円、LU3B:63万円、LU3M:66万円 、LUS:83万円
→C・HARMANの項目も参照 |
LOSEN
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ローゼン LOSEN ベルリンピアノ製造(株)浜松、福山ピアノ(東京) 詳細不明
|
| LOUIS DERDEYN |
ベルギー(ROULERS ルーセラーレ) 詳細不明 |
|
LOUIS HERMANN

画像クリックでHPへ戻る
|
ルイス・ヘルマン LOUIS HERMANN ※スペルは、LOUIS HELLMANNではないので注意
発売元:株式会社 福山ピアノ社 その他詳細不明
このピアノも珍しくトレードマークがありません。
写真のピアノは弦がたくさん切れていおり、
終戦直後に作られたかなり古いピアノでした。
ルイスヘルマンピアノの外観とフタ部分にあるブランド銘柄マーク
→★ |
| LOVE, MALCOLM |
ラヴ・マルコム
※Mの項目内にある「MALCOLM LOVE」と同じピアノだと思います。
詳しい解説は「MALCOLM LOVE」の項目へ |
LOWREY
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ローリー LOWREY PIANO CO. アメリカ
ローリーは電子オルガンで名が知られているメーカーですが、ピアノ製作を開始したのは1963年です。
その後、アメリカ最大の楽器会社であるC.M.I(CHICAGO MUSICAL, INSTRUMENT CO.)の傘下に。
全盛期は34種類のピアノが作られているというが、歴史が新しいので日本ではほとんど知られていません。
|
LUBITZ
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
読み方:ルービッツ? LUBITZ,H ドイツ 詳細不明
|
LUCE
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ルーチェ LUCE 有限会社 阿部ピアノ製作所(浜松) |
LUDWIG & Co.
Ludwig & Co.
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
1888年に設立されたルートヴィヒ・ピアノ社は、ニューヨークにおけるピアノの黄金時代の幕開けとともに
ピアノ製造の世界に参入した。
20世紀初頭から半ばにかけて、ルートヴィヒ・ピアノ社はニューヨークで高品質のピアノを製造していた。
初期のピアノは「ペリー」や「ネビン」という名前で、より高価なルートヴィヒブランドの楽器の
副次的なラインとして販売されていた。
また、「クラビオラ」「ペリオラ」というブランド名は、当時流行していた「ピアニラ」のバリエーションとして、
ルートヴィヒ・ピアノ社がプレーヤーピアノのブランド名として使用していたものである。
1933年、ルートヴィヒはニューヨークのRicca & Sons Piano Companyに売却され、
第二次世界大戦までルートヴィヒの名前で製造を続けました。
1950年代半ばになると、イリノイ州シカゴのアトラス・ピアノ社が経営権を握り、
ピアノにルートヴィヒの名前を使わなくなった。
ルートヴィヒ社が製造したグランドピアノ、アップライトピアノ、プレイヤーピアノは、
そのケースデザインと、高価な大手メーカーに匹敵する音色の良さで知られていた。
最盛期から50年以上が経過した現在でも、ルートヴィヒ・ピアノ・ブランドの品質の高さには定評があります。
ルートヴィヒ社を有名にした特許のひとつに、ルートヴィヒのプレーヤー・ピアノが搭載している
「ユニット・バルブ・プレーヤー・アクション」がある。
このシステムは、値を個別に取り外すことができるため、ルートヴィヒ社はコスト削減と
継続的なメンテナンスのためのメカニックの簡素化に役立つと主張した。
そのため、プレイヤーアクションのパーツは、アクションを取り外すことなく
正面からアクセスできるようになっている。
1900年に開催されたパリ万博では、世紀の変わり目に多くの高級メーカーが競って認められたように、
ルートヴィヒ・ピアノも表彰された。
1900年のパリ万博では、スタインウェイやボールドウィンなど多くの競合メーカーの頂点に立った
ルートヴィヒ・ピアノは、パンアメリカン万博やロンドン・クリスタルパレス万博でも最高賞を受賞しています。 |
LUDWIG
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ルードウィッヒ LUDWIG 日本 詳細不明
|
| LUIS VERDUGO & HIJO |
詳細不明 |
| LUMMER, WILH. |
詳細不明 |
| LUNER |
詳細不明 |
| LURCH PIANO CO. |
ニューヨーク 詳細不明 |
LYON & HEALY
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
LYON & HEALY リヨン・アンド・ヒーリー/リオン・アンド・ヒーリィ
アメリカ(シカゴ) 創業1864年
1864年に設立されたリヨン&ヒーリー社は、もともとコンサートハープを製造しており、
世界でも有数のメーカーでした。
その後、ピアノやプレーヤーピアノ、オルガンなど、さまざまな楽器を長年にわたって製造。
リヨン・ヒーリーブランドは、楽譜や弦、ピアノの部品など、さまざまな音楽用品を販売することで知られており、
当時のアメリカでは初期の「ミュージック・ストア」のひとつとして位置づけられていた。
1876年には、工場の大火事をきっかけに、ピアノやオルガンの製造を開始。
リヨン&ヒーリー・ピアノ・カンパニー/Lyon & Healy Piano Company」に加え、
「ウォッシュボーン・ピアノ・カンパニー/Washburn Piano Company」の名でピアノを製造。
この会社はEverett pianosに買収され、Washburnの名前でピアノの生産を続けた。
1980年代後半、リヨン&ヒーリーの名前は再びアジアの輸入ピアノに使われるようになり、
現在もオランダに拠点を置くリッペンピアノのオーバーヘッドの下、シカゴで生産されている。
リヨン・アンド・ヒーリのピアノは、小売店の需要に応じて十分な数のピアノを供給するために、少量生産された。
アパートメント・グランド、コンサート・グランド、リプロダクション・グランドなどを製造していた。
1900年代半ばになっても、会社の根底にはハープの製造があったため、エバレット、
そして最終的にはスタインウェイがこの会社を買収することに価値を見出したのである。 |
| LYRA |
詳細不明 |
| LYRICA |
詳細不明 |
上記Lから始まるブランドの中で、追記出来そうな事項や新情報を発見した場合、修正受付フォーム よりお気軽にお知らせ下さい。
どんな些細な情報でも構いませんので、広く皆様からのフィードバックをお待ちしております。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
 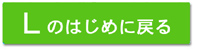 



ピアノ銘柄ブランド
トレードマーク 紹介
& 知名度ランキング

|

メーカー/ブランド説明・会社沿革・歴史・製作者・特徴・音色・他
|
| M.F. RACHALS |
→RACHALSの項目へ |
| M. FUKUSHIMA |
エム・フクシマ 三共ピアノ製作所(東京) |
M. SCHULZ & CO.
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
M. Schulz & Co.
1869年、ピアノの街シカゴでマティアス・シュルツ氏によって設立されたM.シュルツ社は、
当時、数多くのピアノを製造していました。自社ブランドだけでなく、アービング、メイナード、
ブラッドフォードなど、人気の高いラインナップを揃えていた。
1920年代初頭、マティアス・シュルツの息子であるオットー・シュルツが会社を引き継ぎ、
マティアス・オルガン・カンパニーを買収して事業を拡大した。
オルガンの種類を増やしただけでなく、「アリア・ディヴィーナ・リプロダクション・アクション」を設計し、
リプロダクション・ピアノに導入しました。
M. Schulz & Companyは大成功を収めたが、世界恐慌の影響を受け、
他の多くの会社と同様、需要の不足から閉鎖を余儀なくされたのである。
シュルツ・ビルのオリジナルの刻印は、現在もシカゴの近代的に改装されたビルに飾られている。
M. シュルツは、グランドピアノ、アップライトピアノ、リプロダクションピアノ、
プレーヤーピアノを製造しており、いずれも一流の楽器として定評があった。
M.シュルツのピアノは、完璧ともいえる正確な音階で知られており、高品質な素材を用いて作られていた。
M.シュルツのピアノは、演奏すると丸みを帯びたまろやかで純粋な音がして、
目の肥えた音楽家にもすぐにわかる。
そして、その音を奏でる楽器は、見た目にも美しいケースワークに収められており、
ピアニストにとっての楽しみでもあります。 |
M. WELTE & SOHNE
M. WELTE & SÖHNE |
ピアノには「New York」と「Freiburg」(ドイツの都市名)が書いてありますが詳細不明 |
| MAEARI-HYUNDAI |
詳細不明 |
MAESTRO
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
マエストロ
製造元:有限会社 エスピー楽器製作所
発売元:ミュージックファクトリー |
| MAETZKE |
詳細不明 |
| MAG |
詳細不明 |
| MAGE |
詳細不明 |
| MAGRINI |
詳細不明 |
| MAHLER |
詳細不明 |
| MAIER,K. |
詳細不明 |
MALCOLM LOVE
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
マルコム・ラブ MALCOLM LOVE アメリカ
すごい名前ですね
エスティピアノの代理店のブランド ※詳しくはエスティピアノの項目を参照
「Malcolm Love」のブランド名は、ニューヨーク州ウォータールー(ワーテルロー)の
ウォータールーオルガンカンパニーによって製造および販売されました。
同社はもともと1861年に設立され、元の工場はバージニアストリートにありました。
ウォータールーオルガンマニュファクチャリングカンパニーは、
パーラーオルガンとチャペルオルガンとメロディオンの工場は、小さいながらも良い製造ラインを構築。
工場が焼失した後、1881年にマルコム・ラブとアレクサンダー・C・リードに買収されました。
Love and Reedは、1888年に「The Waterloo Organ Company」として会社を設立しました。
※Lの項目内にある「LOVE, MALCOLM」と同じピアノだと思います。
<別解説>
マルコム・ラブ・ピアノ・ラインは、ウェグマン・ピアノ・カンパニーがニューヨークの工場で製造していた。
同社は1890年頃からマルコム・ラブ・ピアノの生産を開始し、1900年代初頭にウェグマン・ピアノ社は
ニュージャージー州ニューアークに工場を移し、マルコム・ラブ・ラインの生産を続けた。
マルコム・ラブのピアノは何度か手を変え品を変え、セッターグレン社、
ウォータールー・ピアノ&オルガン社、エスティ・ピアノ社でも製造された。
マルコム・ラブのピアノは、アメリカが第二次世界大戦に参戦した頃に生産を終了した。
マルコム・ラブのピアノは、一般的によくできた堅実な楽器として、音楽界から高い評価を得ていました。
マルコム・ラブのピアノは、その音色の良さと、優れた職人技で知られていました。
ケースには美しく豊かな音色の木材が使われ、繊細な彫刻が施されている。
年間約700台しか生産されないピアノは、熟練した職人の手によって一つ一つ丁寧に作られていた。
販売されたピアノには、1893年にシカゴで開催されたコロンビア万国博覧会で受賞した
賞状のコピーが添えられていた。
見た目の美しさと甘い音色で、多くのピアニストを魅了したピアノです。
Estey Piano Corporation
→詳しくは「Estey」の項目へ |
MALMSJÖ
MALMSJO |
スウェーデン?
グランドにおいて扇形のアクション(バナナグランド)を搭載したものがある
その他詳細不明 |
| MAND |
詳細不明 |
| MANN, THEODOR |
詳細不明 |
| MANNER & CO. |
詳細不明 |
| MANNER & GABLER |
詳細不明 |
| MANNHORG |
詳細不明 |
MANSARD
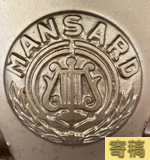
画像クリックでHPへ戻る |
マンサード 東洋ピアノ製造株式会社
左記トレードマーク画像は「匿名希望様」からご寄稿頂きました。ありがとうございます!
ご寄稿者様によりますと、このピアノはウォルナットつや消しで、納入は昭和49年5月とのことです。
機種バリエーション:D2等 |
| MANSFIELD |
詳細不明 |
MANTHEY
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
マンタイ MANTHEY ドイツ(旧西ドイツ) 詳細不明
|
MARBE
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
マルベー MARBE 株式会社 森技術研究所(浜松)、レスターピアノ製造(浜松) |
|
MARCHEN/MÄRCHEN

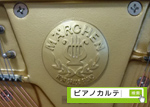
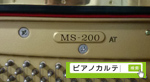
画像クリックでHPへ戻る
|
メルヘン (MARCHEN/MÄRCHEN)
株式会社 河合楽器製造所
メルヘン楽器株式会社
森興業株式会社
メルヘン楽器販売株式会社(発売元)
意外と知られていませんが、このメルヘンピアノはカワイ楽器のセカンドブランドでした。
河合楽器が製造していたK-2号という機種に付けられていた”メールヘン”という通称ネーム(愛称)で
売り出されたのが始まりで、その後独自ブランドとして個別発売に至りました。
ちなみに現在のブランド所有者(商標権者)は株式会社ディアパソンです。
メルヘンの初期消音システムは、ハンマーシャンクで打弦を止めるシステムではなく、
キャッチャー部分で止める構造だったため、打鍵直後のシャンクのしなりの影響で、
物理的にレット・オフを広く取らなければならず、消音ユニット付きは連打が非常に利きづらいのが難点です。
何故キャッチャー止めにしたのか理解に苦しみますが、その後一般的なシャンク止めに修正変更されました。
※キャッチャー部分で止める装置の実際の写真 →★
音色はカワイらしい柔らかな感じです。
メルヘンのまくり(蓋)部分の銘柄マーク →★
メルヘンのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★ |
| MARDE |
MARDE CABINET GRAND NEW YORK
アメリカ(ニューヨーク) 詳細不明 |
| MARION |
詳細不明 |
MARIST
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
メアリスト MARIST 小出一三氏が製作したもの。
|
| MARISTANY |
詳細不明 |
MARIKO

画像クリックでHPへ戻る |
MARIKO マリコ
製造元:アトラスピアノ製造株式会社 |
| MARTINS & OUVRIER |
詳細不明 |
| MARKX |
詳細不明 |
| MARSCHALL & MITTAUER |
詳細不明 |
| MARSHALL & ROSE |
詳細不明 |
MARSHALL & WENDELL
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
マーシャル&ウェンデル アメリカ(ニューヨーク州オールバニ) 創業1836年
1836年、ニューヨーク州オールバニに設立。
1836年にMarshall & Traverとしてスタートし、1855年にMarshall, James & Traverに改称した。
1870年頃、James & Traverは会社を去り、Wendell氏がパートナーとして認められる。
1900年には本社をアルバニーからニューヨーク州ロチェスターに移した。
20世紀に入ってからも、マーシャル&ウェンデル社の楽器は、
最高の品質と極めて高い耐久性を持つと考えられていた。
多くのピアノには「アンピコ」と呼ばれるプレーヤーシステムが搭載され、ケースのデザインも凝っていた。
大恐慌時代にはエオリアン・アメリカン・コーポレーションに吸収されたが、
マーシャル&ウェンデル社のピアノは1950年代半ばまで製造されていた。
マーシャル&ウェンデル社が製造したピアノは、その品質が世界的に認められ、1901年のパンアメリカン、
1909年のシアトル・ユーコン、サンフランシスコで開催されたパナマ太平洋博覧会、
ブラジル共和国独立100周年を記念してリオデジャネイロで開催された大博覧会などで受賞している。
マーシャル&ウェンデルは、アップライト、グランド、そして世紀末のプレーヤーシステム人気の
先駆けとなったアンピコ・プレーヤーシステムを製造した。
マーシャル&ウェンデル社は、スクエアピアノ、グランドピアノ、アップライトピアノの
複数のラインを製造しており、いずれも優れた品質を誇っていた。
また、19世紀後半には「パーラー・ジェム」というブランド名でスクエアグランドピアノを、
「リトル・ジェム」「ブードゥア・ジェム」というブランド名でアップライトピアノを製造していた。 |
| MARSHALLS |
マーシャルズ
JOSHUA-MARSHALL & CO, LTD.
THE ARCADE, BARNSLEY |
MARVEOLA
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
Marveola(マルヴェオラ)
WESER BROTHERSが製造していたブランド
→詳しくはWESER BROTHERSの項目へ |
MASON & HAMLIN

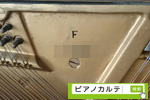

画像クリックでHPへ戻る |
メイソン・アンド・ハムリン/メーソン・アンド・ハムリン (メーソン & ハムリン)
The Mason & Hamlin Companies/旧(MASON & HAMLIN PIANO CO.)
アメリカ マサチューセッツ州(ヘーバリル/ヘイバリル/ヘーヴァリル/Haverhill)
1854年創業。 所有:ピアノディスク社のカークとゲーリー・バージェット
1882年まではオルガンのみを製造。1883年からはピアノ製造も開始。
※1881年からピアノ製造という情報もあり(要確認)
メイソン・アンド・ハムリン社は1920年代まで、スタインウェイ・アンド・サンズ社の最も手強いライバルだった。
当時、「世界で一番高価なピアノ」として売り出された楽器は、まさに最高の品質を備えていた。
かつて輝かしい業績を誇ったこの会社が低迷することになったのは、所有権が安定しなかったためだ。
メイソン・アンド・ハムリンのピアノは幅広い音色のパレットを持ち、豊かな低音域、澄んだ中音域、
そして鐘が鳴るような高音域が特徴。
1900年、メイソン・アンド・ハムリン社に雇われていたリヒャルト・ゲルツは、
テンション・レゾネーターの特許を取得。
テンション・レゾネーターは調節可能な数本の金属棒からなり、それらはグランドピアノ底面の中心から
放射状に広がってリム(側板)に接続される。
その目的は、響板クラウン(むくり)の弦に対する圧力を調整し、弦の振動が響板全体に
よく伝わるようにすることだ。
この部品はメイソン・アンド・ハムリン社のすべてのグランドピアノに取リ付けられた。
この機構は、「クラウン・リテンション・システム」と呼ばれ、現在もメイソン・アンド・ハムリン社の
グランドピアノに用いられている。
1905年まで、グランドピアノには独特の張弦設計が採用されていた。
ピン板にチュー二ングピンを差し込むのではなく、
弦の張力を調節するために金属のフランジとスクリューを用いる。
弦はフックに通され、小型のチューニングハンマーでスクリューを回して調律される。
スクリューはチューニングピンのように、ねじれたり動かなくなったりせず、回すのも容易で、
このシステムには従来の方式より有利な点がいくつもあり、調律の精度は高かった。
しかし、狙った音程にするのに通常のチューニングピンの方式より、余計に回す必要があった。
調律に長い時間がかかるのと(チューニングピンと反対に回して合わせていくスクリューの調律法に
慣れる必要があったためと言われている)、調律師の偏見のせいでこの貴重なアイディアは廃れていったという。
<歴史>
実業家でアマチュア音楽家のヘンリー・メイソンと、リードオルガンの開発を手掛けるエモンズ・ハムリンによって
1854年に設立されたこの会社は、すぐにハルモニウムとキャビネット・オルガンで有名になる。
メイソン・アンド・ハムリン社の最初のピアノが発売されたのは1881年と比較的遅かったが、
当初から品質は充実していた。(1883年からという説もあり)
その後も改良が重ねられ、1895年に雇われたドイツの著名なピアノ設計家リヒャルト・W・ゲルツによって
スケールデザインが改良され、1905年には、特許を取得したテンション・レゾネーターが導入された。
一時期、メイソン・アンド・ハムリン社のグランドピアノには独特の調律システムが採用され、
チューニングピンとピン板の代わりにスクリューが用いられていた。(これを ”スクリュー・ストリンガー” と呼ぶ)
しかし、この興味深い装置は十分な発達を待たずに、1905年に廃止になった。
メイソン・アンド・ハムリン社は、1911年にケーブル・ネルソン・カンパニーの一部になってから、
所有権が次々に移って経営が傾き、1932年にはエオリアン・アメリカン・コーポレーションの所有となった。
1985年にエオリアン社が消滅すると、メイソン・アンド・ハムリン社はゾーマー・カンパニーに買収され、
その後、ゾーマー・カンパニーが1989年にファルコーネ社に買収される。
それから1991年に行われた買収のあとにできたメイソン・アンド・ハムリン・カンパニーズ
(クナーベ、ファルコーネ、ゾーマーを含む)が1995年に破産を申請し、今度はピアノディスク社に救済された。
この救いの手は当時周りからは賭けと言われていたが結果的に大成功になった。
(※ピアノディスク社はカークと、ゲイリー・バージェットがゼロから会社を興し、
電子自動演奏ピアノの市場で2000万ドルのトップ企業に育て上げたことで有名)
この新しい熱意あるオーナーのもと、会社は完全に復活を遂げ、2002年、メイソン・アンド・ハムリンのピアノは、
20世紀初頭に作られていた最高のモデルのほぼ完璧な復元となった。
<附録>
メーソン&ハムリンピアノ 製造番号/製造年代 対照表 →★
メーソン&ハムリンのまくり(蓋部分)のブランドマーク写真 →★
<現在ピアノディスク社が取り扱うピアノブランド>
Falcone、Knabe、Mason & Hamlin、Sohmer、George Steck
<以下、ウィキペディアより引用抜粋>
メイソン・アンド・ハムリン(Mason and Hamlin)は、アメリカ合衆国
マサチューセッツ州ヘーバリルに本拠を置くピアノメーカーである。
1854年、ヘンリー・メイソンとエモンズ・アムランによりボストンに設立。
オルガン製作が元であったが、1883年にピアノ製造を開始。
ピアノのリムをテンションレゾネーターと呼ばれる金属棒で拘束することで強固な構造とし、
リムの変形や響板の沈下が長期間にわたって少ないことが特徴である。
米国ではスタインウェイに次ぐ高級ピアノと認識され有名であるが、
日本には輸入数が少なく知名度も充分ではない。
1924年のセルゲイ・ラフマニノフの演奏による彼のピアノ協奏曲第2番の録音に使われた。
公式ホームページ:http://masonhamlin.com/
<参考>
日本楽器製造(現:ヤマハ株式会社)の創始者である山葉寅楠氏が浜松尋常小学校(現:元城小学校)に
当時あったのが、このアメリカ製メーソン・アンド・ハムリン社のリードオルガンでした。
寅楠は1887年、故障したこのオルガンを初めて修理を成功させたことでヤマハの社史が始まりました。
<別資料>
現在もアメリカに存在する最古のオリジナルハンドメイドピアノメーカーのひとつである
Mason & Hamlin社は、1854年にリードオルガン製造会社としてスタートしました。
ヘンリー・メイソンとエモンズ・ハムリンは、1854年にニューヨークのブロードウェイ596番地で
共同経営を開始しました。
1883年には、アメリカで最高級のピアノを製造するようになり、オフィスもボストン、シカゴ、
ニューヨークと拡大していった。
メイソン&ハムリン社のピアノのデザインは、長い年月の間にさまざまな変化を遂げたが、
ひとつだけ変わらないものがあった。
それは、数十年にわたるピアノ製作の進化に耐えうる、ハンドメイドのピアノ製作に対するアプローチである。
テンショナーの機構は近代化され、リチャード・ガーツの専門知識を得て、すべてのピアノのために
まったく新しいスケールを開発したが、ハンドメイドのクラフトマンシップの完全性は変わらなかった。
1929年の株式市場の大暴落により、メイソン&ハムリン社を含む高級ピアノ会社の大半が経営危機に陥った。
1930年、メイソン&ハムリン社はエオリアン・アメリカン・ピアノ・カンパニーに会社を売却し、
同社のピアノはその後、ニューヨーク州のイーストロチェスターで製造されるようになった。
第二次世界大戦中、メイソン&ハムリンのピアノ工場は、終戦まで楽器ではなく
飛行機のグライダーの生産に専念していた。
1985年にシティバンクがエオリアン・アメリカン・ピアノ・カンパニーの資産を差し押さえた後、
所有権はコネチカット州アイボルトンのプラット・リードに変わった。
その後、エオリアン・アメリカン・ピアノ・カンパニーの所有権は、10年間にわたって
投資家や音楽グループの間で絶えず変化していたが、1996年に音楽家の
カーク&ゲイリー・バーゲット兄弟の手に渡るまで、その所有権は変わっていなかった。
1996年、KirkとGary Burgettの兄弟は、同社のピアノ製造を、高品質な部品を使った
手作りの職人技という原点に戻しました。
メイソン&ハムリン社は、初代オーナーの「芸術品を作る」というミッションを忠実に守り、
最高級のピアノを作り続けている。
メイソン&ハムリンのピアノは、手作りの緻密なディテールや、よくできた部品の
代表的なブランドの一つとして、20世紀初頭に最も高価なピアノの一つでした。
メイソン&ハムリン社のピアノは、スタインウェイと肩を並べることで知られ、
ピアノ業界が提供する最新の機能をすべて備えていました。
グランドピアノからアップライトピアノまでのフルラインは、絶妙な音色とダイナミックレンジを備えた
真の芸術品です。そのため、修復の対象としては非常に優れています。
メーソンアンドハムリンのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★ |
| MASON & KENDALL & SONS |
メーソン&ケンドル(ケンダル)&サンズ/メーソン・アンド・ケンド(ダ)ル・アンド・サンズ
アメリカ 詳細不明 |
MASON & RISCH


画像クリックでHPへ戻る |
メーソン・アンド・リッシュ MASON & RISCH, LTD カナダ
カナダで最も大規模なピアノメーカーで、カナダで最も代表的なピアノメーカーです。
1871年にトロントで創業され、1881年にピアノの神様であるフランツ・リストによって、
そのピアノが賞賛されるにおよび、世界的に名声を博するものとなりました。
その後、ビクトリア女王およびローマ法王も、このメイソン・アンド・リッシュのピアノを
使ったと伝えられています。
現在は、製法も近代化され、生産設備の拡張によって大衆的な価格のピアノとなっている。
トレードマーク画像は「高永ピアノ調律事務所様」からご寄稿頂きました。
この度は画像のご寄稿を頂きまして誠にありがとうございます!
マークがある場所ですが、一般的な鉄骨部分ではなく、こちらは天屋根を開けた箇所にあります。
トレードマーク以外の画像も頂きました。
ピアノ外観(WINTERとなっており、1948年にウインターに買収された後のピアノでしょうか)→★
まくり(ピアノ蓋)部分にあるWINTERの文字部分の拡大 →★ 内部アクションレール部分 →★
<参考>エオリアンに買収された後のWINTERはエオリアンのシールになっております →★
<別解説>
メイソン&リッシュは、1871年にカナダのトロントでメイソン、リッシュ、ニューコム社としてスタートした。
1878年にオクタビウス・ニューコムが独立した後、トーマス・メイソンとヴィンセント・リッシュが
メイソン&リッシュに社名を変更した。
最初は他社のピアノを販売していたが、1877年には自分たちの名前をブランドにした楽器を製造。
1886年から1890年まではLansdowne Piano Companyと密接な関係にあったが、
1948年にはWinter and Companyに買収された。
ウィンター&カンパニーはその後、ピアノ大手のエオリアン社に買収されたが、
エオリアン社は引き続きメイソン&リッシュの名前を使用した。
小さな会社からスタートし、最終的にはカナダ最大のピアノメーカーの一つに成長した
メイソン&リッシュは、カナダのピアノ業界に多くの貢献をしました。
何度か経営が変わった後、1980年代後半にメイソン&リッシュの名前は消えてしまいました。
著名な作曲家であるフランツ・リストが賞賛するなど、メイソン&リッシュのピアノは
カナダ国内外の音楽界で広く知られていた。
ローマ法王11世やヴィクトリア女王までもがメイソン&リッシュのピアノを好んで使用し、
絶賛の手紙を送っています。メイソン&リッシュのアップライトピアノやグランドピアノは、
明らかに優れたクラフツマンシップの楽器であり、よくできており、耐久性があり、
美しい外装を持ち、優れた音色を持っていました。 |
MATHSHEK
MATHUSHEK, F.
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
マシューシェク MATHSHEK/Mathushek Piano Company
アメリカ(ニューヨーク) 創業1852年
スクエアピアノ(テーブル型)のピアノ
フレデリック・マシューシェクはドイツのヴォルムスでピアノ作りを始め、見習い期間の後、
パリに移ってアンリ・パプに師事。1849年にドイツの自宅(マンハイム)からニューヨークに渡米。
Henri Papeの下で、マシューシェクはテーブルトップの八角形のピアノのような、
革新的で時に奇妙な新しいデザインを試み始めた。
マシューシェクは、音色の専門家として知られており、非常に高級な音質のピアノを作ることができた。
アメリカの多くのピアノメーカーから音階の作成やその他の改良を依頼された。
1857年までに、マシューシェクは音色の専門家として名を馳せ、
ダンハム・ピアノのためにオーバーストラング・スクエア・ピアノの音階を作成したり、
スペンサー・ドリッグスのためにまったく新しいピアノの構造プロセスを作るプロジェクトに参加したりしていた。
彼は、他のメーカーのグランドピアノの音階をたくさん描き、
他のピアノの音色の問題を解決するためによく呼ばれていました。
マシューシェクがコネチカット州ニューヘブンのマチシューシェッピアノ社の社長として独立したのは、
1866年のことである。
マシューシェク・ピアノ・カンパニーは、ピアノの設計に独創的なアプローチをしたことで知られており、
彼の「Colibri」ピアノには、リニア・ブリッジやイコライズド・スケールなどを導入した。
マシューシェクは、大量のピアノを生産することよりも、音色やピアノの構造について
実験していたと言われる発明家である。
マチューシェク・ピアノ社のピアノで最も有名なのは、小型の「コリブリ」と呼ばれるピアノだろう。小型のコリブリから発せられる音色は、当時の多くの大型スクエアピアノよりも豊かで重厚なものだと自負していた。また、オーケストラ用の角型ピアノも発売され、その音色はチェロに例えられることもあったという。
後にジェイコブ兄弟の傘下に入り、1950年代までピアノを生産していたが、完全に生産を停止した。
マチューシェックが支配していた他のピアノ名は、
Euterpe、Jacob Brothers、James & Holstrom、Nilson & Co.、Premier Spinet
Grandである。
※2005年に一旦復活したとの情報有り(未確認) |
| MATHUSHEK & KINKELDEY |
詳細不明 |
| MATHUSHEK & KÜHNER |
詳細不明 |
| MATHUSHEK & SON |
詳細不明 |
MATSUMOTO
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
マツモト
製造元:松本ピアノ製造所
販売元:松本楽器販売店(松本楽器店)東京京橋柳町
詳しくは下記、MATSUMOTO & SONSの項目を参照 |
MATSUMOTO
(MATSUMOTO GAKKI)
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
MATSUMOTO GAKKI/MATSUMOTO (GAKKI)
マツモト ガッキ
製造元:アトラスピアノ製造株式会社
発売元:松本楽器店(当時:大阪市日本橋)
1967年(昭和42年)松本楽器店の松本明氏が設立。
当時大阪市内でピアノ販売の多数の専門店を展開しており、大阪の日本橋をはじめ、
堺、豊中、吹田などの関西を中心に大きく販売していました。
ピアノの製造自体はアトラスピアノに委託した自社ブランドを作っていました。
ピアノのまくり(蓋部分)には、Matsumoto Co.,LTDと書いてあります。
1986年(昭和61年)廃業
機種バリエーション:M-1、M-2、M-3、M-5、M-7、M-8等(何故かM-4とM-6が欠番)計6機種 |
MATSUMOTO & SONS




画像クリックでHPへ戻る |
MATSUMOTO & SONS マツモト・アンド・サンズ
(有)松本ピアノ工場 千葉県君津市(当時:千葉県君津郡)
日本におけるピアノの先駆者の一人、松本新吉の六男、
松本信二氏の夫人が子息の真一氏とともに作っていたピアノで、
生産台数は少ないが極めて音の美しいピアノであったと伝えられている。
父、松本新吉氏のS・マツモトや、長男広氏のH・マツモトの項も参照。
<歴史>
松本ピアノは西川ピアノに続いて関東地方に出来たピアノメーカーです。
20世紀初頭から終戦の年までピアノを作り続けました。
その後、生産台数は少ないながらも千葉県君津市で有限会社松本ピアノ工場として
長い伝統によって培われた技術を活かし楽器を作っていました。
松本ピアノの創始者、松本新吉氏は1865年に千葉県周淮郡常代村
("すえぐんとこしろむら"と読む)現在の君津市で父 治朗吉、
母 みやの長男として生まれ、"上総の神童" といわれるほどで、
寺子屋で二十四考や論語、孟子の素読を聞いてたちまち記憶するほどの
才能があったと伝えられている。
松本新吉氏は1883年に "山田るい(るゐ)"さんという最初の奥さんと結婚。
当時新吉19歳、るいさん15歳であった。
彼は1887に西川オルガン製作所に移っているが、その理由は判然としないが、
おそらく"るい"さんが西川虎吉氏の姪だったためであろうと思う。
新吉氏と西川オルガン製作所との関係は1年とも3年とも言われているが、
いづれにせよ短期間であった。
しかし、この短期間の間に彼は驚異的な才能を発揮し、外人技師たちから
オランダ語や英語を学び取り、オルガンやピアノの調律・修理の技術を
身に付けたといわれている。
松本新吉氏が最初に作り始めた楽器はピアノではなく紙腔琴(しこうきん)でした。
紙腔琴についてはWikipediaに詳しく書かれているのでここでは割愛しますが、
日本で最初に流行した大衆楽器でした。
穴の開いたロール状の紙をハンドルを回し送り出し空気を出して音を出すふいご楽器。
日本のピアノメーカーで最初に渡米したのは山葉寅楠氏で、彼は1899年に
文部省の嘱託としてアメリカの楽器業界の視察兼、ピアノの部品購入のために渡米。
ここでピアノの鉄骨フレームにヤマハの商標を鋳込ませたものを輸入することに
成功し、このことで一挙にヤマハの市場価格が高まったと伝えられている。
一方、松本新吉氏がアメリカへ修行へ出かけたのはその翌年の1900年でした。
彼は山葉氏とは対照的で、苦節10年、紙腔琴を作るかたわらピアノやオルガンの製作、
修理などに懸命に働き、その当時としては途方もない渡米費用を調達したという。
1900年に松本新吉は日本のピアノのパイオニア、そしてまた最初の調律師としても
アメリカで絶大な歓迎を受けました。彼は日本で最初の調律師として仕事を始め、
その後数台のオルガンとピアノを作ったがこれらに満足せず、アメリカの数多くの
工場を訪問し、ブラッドベリーピアノ工場で腕を磨いたとされています。
この工場のマネージャーは、彼のことを規律正しく、熱心でしかも忍耐強い
人物であると絶賛していたようです。
このブラッドベリーはニューヨークで1837年創業のピアノメーカーで、
当時73歳になるスミス社長が松本新吉氏を熱心に指導したと伝えられています。
約半年間アメリカでの研究生活を送って帰国した新吉氏は、その年の暮れに
愛妻の急死という不遇に見舞われました。落胆した彼は、一時築地の工場を
郷里の千葉に移しましたが、材料入手に不便なため、1年後再び築地に戻っている。
1905年には長男の広氏をアメリカに送っているが、その翌年に築地工場は
火災のため全焼してしまい、苦労の連続で築地時代を終えています。
1907に月島二号地に新工場を作り、病院長の和田剣之助氏および実業家の大倉文治氏と、
松本楽器合資会社を結成、さらに銀座4丁目の伊勢善自転車店跡地に
松本楽器販売店(松本楽器店)をピアノやオルガンを販売しました。
この松本ピアノ店が、のちに現在の山野楽器に変わりました。
その後、1910年に松本楽器合資会社を解散し、月島工場を単独経営に移し、
さらに京橋の柳町に営業所を設けましたが、不幸にして1914年に月島工場も全焼。
1916年には台風の大波によって大きな被害を出し、1924年の関東大震災で再び全焼、
柳町営業所も全焼してしまいます。不運が続くとはこのことでしょうか。
※参考資料:大正9年(1920年)頃の「松本ピアノ・オルガン製造所」のピアノ →★
関東大震災後の1924年に再開されたピアノの生産は順調に伸び、月産50台にも
達し品質も向上して、一流の楽器として評価されるようになりました。
新吉氏は長男の広氏と別れて故郷の千葉に移っています。
1924年、松本ピアノ八重原工場を作り、こちらをS・松本とし、
長男の広氏の月島工場のピアノを、H・松本と呼ぶようになった。
1941年5月3日、松本新吉没(享年77歳)。
1953年松本新吉の弟子である沢山清次郎氏がMATSUMOTO & SONSにブランド名称変更。
千葉県君津におけるピアノ製造は六男の松本眞二氏が後を継ぎましたが、
彼は不幸にして事故で亡くなり、奥様の松本和子さんが長男の信一氏と共に
有限会社松本ピアノ工場として仕事を引き継いでいました。
このマツモト・アンド・サンズというピアノは月産わずか当時数台ではありましたが、
大変美しい音色で定評がありました。
一家そろって90年以上もピアノを作り続けていたのはおそらく松本ピアノだけでしょう。
2007年4月6日、君津市外箕輪の松本ピアノ工場閉鎖。
トレードマーク画像その他の写真は「匿名希望様」からご寄稿頂きました。ありがとうございます!
ピアノまくり部分(蓋部分)にあるピアノブランド銘柄部分の写真 →★
マツモト&サンズ内部の拡大写真 →★ →★
<追記>
松本ピアノの月島工場は、第二次世界大戦の米軍の爆撃により全焼し、
その55年余りにおよぶ歴史に幕を閉じましたが、この月島工場で
腕を磨いた職人達は、戦後も各地でピアノ製作に取り組みました。
例えば、シュベスター(浜松)、キャッスル(土浦)、イースタン(宇都宮)
などのブランドはいづれもその系統で育った技術者たちです。
現在はわかりませんが、日本ピアノ調律師協会(通称:ニッピ)の会員の中には
当時松本ピアノ出身者が極めて多く在籍していたようです。
松本ピアノ出身で著名な方々は下記の通りです。
宇都宮信一氏、上岸斬氏、市川祐弘氏、寺中一氏、本多匡雄氏、
宇佐美隆氏、青木栄次郎氏、森泉良平氏、田中信男氏、古賀良三氏、
松川静雄氏、市村昴氏、岩本重晴氏など。
|
| MATTHAES |
詳細不明 |
| MATZ & CO. |
詳細不明 |
| MÄTZKE, ED. |
詳細不明 |
| MAX HORN ZWICKAU |
詳細不明 |
MAXADAM
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
マックスアダム MAXADAM ドイツ 詳細不明
|
| MAY |
詳細不明 |
MAY BERLIN
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
メイ・ベルリン MAY BERLIN ドイツ(旧西ドイツ) 詳細不明
|
MAYYER
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
メイヤー MAYYER ドイツ 詳細不明
|
| MCPHAIL, A. M. |
→A.M. McPhailの項目へ |
| MECKLENBURG |
詳細不明 |
MEHLIN & SONS
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
メーリン・アンド・サンズ MEHLIN & SONS, INC. アメリカ
1853年、ポール・ジー・メーリンという有名な発明家で、一生をピアノの構造の改良に尽くしたと
伝えられる人によって創立された会社であります。
このピアノの外装・デザインは比類のない美しいもので、スピネットからグランドまでのすべてを製作。
1959年にウインター(WINTER & CO.)は、エオリアン・アメリカン社と合併し、
社名をエオリアン・コーポレーションに変更していた間、MEHLINは
ウィンター&カンパニーが製造していたブランド名の一つです
→詳しくはWINTERの項目へ |
MEILMNER
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
MEILMNER ドイツ 詳細不明
|
| MEISCHNER |
→MEISWNERの項目へ |
MEISTER
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
マイスター アメリカ(シカゴ) 創業1895年
ロスチャイルド社(デパート)シカゴ
オハイオ州モンロービル(工場)
マイスターピアノは、シカゴの大型デパート、ロスチャイルド社が製造したピアノである。
マイスターピアノの製造は1895年に開始され、オハイオ州モンロービルにある
ロスチャイルド社の工場で生産された。
ロスチャイルド社は、このピアノを店舗で販売するだけでなく、カタログでも販売した。
マイスターピアノは175ドルで購入でき、1週間に1ドル、1ヶ月に5ドルの分割払いが可能だった。
ロスチャイルド社は1923年までマイスターピアノを製造していたが、1923年に製造を中止した。
グランドピアノとアップライトピアノがありますが、マイスターピアノの音色や響き、
職人の技量についてはほとんど知られていません。
しかし、多くのピアノが販売されたのは、アメリカの中流階級の家庭にも手が届くように、
支払い方法が複数用意されていたからだと考えられる。 |
MEISTER
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
MEISTER マイスター
アトラスピアノ製造株式会社(浜松)
当時、阪急百貨店で販売していたブランドのようです。
機種バリエーション:ME28、ME38等
<参考>
L.MEISTERというピアノもありますが、Lが最初に付くピアノは中国製造だと考えられます。
詳しくは→L. MEISTERの項目へ |
MEISWNER





画像クリックでHPへ戻る |
MEISWNER Meiswner マイシュナー
※スペルは「MEISCHNER」という説も
アカシアピアノ製作所、マイシュナーピアノ製作所、
アカシア木工株式会社、(株)マイシュナーピアノ社
戦後、アカシア木工(株)が太田一郎氏を迎えてピアノ製作を再開した時のブランド。
昭和26年に町田幸重氏によって(株)マイシュナーピアノ社が興され、
昭和30年まで月産十数台の生産が維持されたとのこと。
色々と調律師さん泣かせの所もあるらしいですが、音は国産と思えないような信念のある本格派で、
これをあの時代に発売したのだから造った方の飛び抜けっぷりが目に浮かびます。
ACASIANの項目も参照してください
■ マイシュナーの画像集1
まくり(蓋)部分の銘柄マーク →★ 外装にあるエンブレム →★ マイシュナーピアノの全景写真 →★
上記2枚の写真はトレードマークに”A"が入っているため、アカシアピアノ製作所時代のものと推察されます。
これらすべての画像は「匿名希望様」からご寄稿頂きました。ありがとうございます!
■ マイシュナーの画像集2 →★ →★ →★ →★ →★
こちらは(株)マイシュナーピアノ社になってからのものか?詳細は不明です。
この画像もすべて「匿名希望様」からご寄稿頂きました。ありがとうございます! |
| MELDORF |
Estey Piano Corporation
→詳しくは「Estey」の項目へ |
MERDES
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
メルデス 中響楽器 |
MELFORD
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
メルフォード 日本製 詳細不明
機種:U131など |
MELHEN
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
メルヘン MELHEN 韓国 詳細不明
※カワイのメルヘン(MARCHEN/MÄRCHEN)とは異なります |
MELODI GRAND
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
メロディ・グランド Melodigrand
MELODIGRAND CORPORATION アメリカ 工場:テネシー州
アメリカには珍しい普及品のピアノメーカーです。
※スペルはMELODYGRANDではない
1959年にウインター(WINTER & CO.)は、エオリアン・アメリカン社と合併し、
社名をエオリアン・コーポレーションに変更していた間、MELODIGRANDは
ウィンター&カンパニーが製造していたブランド名の一つです
→詳しくはWINTERの項目へ |
| MELODIC |
詳細不明 |
MELODY
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
メロディー MELODY 三陽楽器製作所 ケーニッヒの姉妹品。
|
| MELVILLE CLARK |
詳細不明 |
MENDELSSOHN
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
メンデルスゾーン MENDELSSOHN アメリカ(テネシー州)
スターリング・ピアノ・コーポレーション ※STERLINGの項目も参照
1870年にペンシルバニア州マキースポートで設立されたメンデルスゾーン・ピアノ・カンパニーは、
アメリカ初期のピアノ製造の中心地であるニューヨークに移転した。
1900年には、当時の大手ピアノ・オルガンメーカーであるコネチカット州ダービーの
スターリング・ピアノ&オルガン社に買収された。
しかし、世界大恐慌の影響を受け、直後にスターリング・ピアノ&オルガン・カンパニーは
ウィンター・ピアノ・カンパニーと合併した。
ブランドの認知度と製造業務の資本力を高めた合併会社は、
1960年代まで再びメンデルスゾーンのブランド名で生産を開始した。
メンデルスゾーンのピアノは、現在でもアジアの輸入ピアノで生産されています。
メンデルスゾーンのピアノやプレーヤー・ピアノは、アーリーアメリカンの多くのブランドに匹敵する
美的感覚と美しい音色で定評があります。
スターリング・ピアノ・カンパニーは、メンデルスゾーン、ハンティントン、ゲッツ&カンパニー、
リチャードソン、ローマンなど、さまざまなブランドのピアノを製造していました。
メンデルスゾーンをはじめとする世紀末に作られたピアノは、ピアノの黄金時代とも呼ばれ、
高い水準で作られていた。これらのブランドの多くは、生産されていた最も有名で高価な
競合ブランドの品質に匹敵するものでした。
メンデルスゾーン社はグランドピアノを製造していましたが、主にアップライトピアノ、
つまり「キャビネット・グランド」ピアノで知られていました。
ヴィンテージの広告では、メンデルスゾーンのピアノについて、
「壮麗なローズウッドのケース、3弦、7~1オクターブ全音、特許のカンタン・アグラーフェ、
美しい彫刻が施された脚と竪琴、重厚なサーペンタインと大きなファンシー・モールディングなど」
と説明されている。 |
MENDELSSOHN MUSETTE
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
Mendelssohn Musette メンデルスゾーン・ミュゼッテ
1959年にウインター(WINTER & CO.)は、エオリアン・アメリカン社と合併し、
社名をエオリアン・コーポレーションに変更していた間、Mendelssohn Musetteは
ウィンター&カンパニーが製造していたブランド名の一つです
→詳しくはWINTERの項目へ |
| MENZEL |
詳細不明 |
MERCEDES
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
メルセデス MERCEDES フィリピン 詳細不明
|
MERCEDES DELUXE
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
メルセデス・デラックス MERCEDES DELUXE フィリピン 詳細不明
|
MERDES
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
メルデス MERDES 中響ピアノ(浜松市) 詳細不明
|
| MERKUR |
詳細不明 |
| MEROS |
メロス 日本 詳細不明 |
MERRILL

画像クリックでHPへ戻る |
MERRILL メリル Merrill Piano Co.
アメリカ(ボストン) 詳細不明 |
| MES, A. |
詳細不明 |
| METROPOLITAN |
Estey Piano Corporation
→詳しくは「Estey」の項目へ |
| MEYER, CONRAD |
詳細不明 |
| MEYER, HERMAN |
詳細不明 |
MICHAEL
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
マイケル MICHAEL 大倉楽器工業(株)東京都杉並区上高井戸 ※コスモスの項参照
|
| MICHELLE |
詳細不明 |
MIESSNER
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ミーズナー
MIESSNER アメリカ(ミルウォーキー/MILWAUKEE) 詳細不明 |
| MIGNON |
WELTE-MIGNON アメリカ(ニューヨーク)
詳細不明 |
MIKADO
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ミカド ミカドピアノ |
MIKEL
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
マイケル 大倉楽器工業株式会社 |
|
MIKI


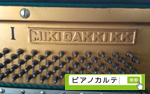

画像クリックでHPへ戻る
|
ミキ
製造元:天竜楽器製造(株)
製造元:河合楽器製作所
製造元:日本楽器(和田工場)
発売元:三木楽器株式会社
河合小市氏が日本楽器から離れてピアノを製造するにあたり、
関西の有力楽器商社三木楽器店の後援を受けましたが、
その代償として関西の販売権を譲り、ミキのブランドで販売されました。
三木楽器店は昭和36年頃より河合系列を離れたので
日本楽器系の天竜楽器がそのブランドのピアノの製作にあたり、
その後、日本楽器和田工場に引き継がれて生産されていました。
従いまして後期ミキのアクションはヤマハです →★ ミキの外装表記マーク
→★
マフラー装置/弱音装置(一般的な3本ペダルピアノの場合の真ん中ペダルに相当)が非常に特徴的で、
ペダル式ではなく棚板下のレバー式タイプがあります →★
機種:No10等
上から3番目のトレードマークはミキのグランドピアノです(ピアノの蓋にはK KAWAIと書いてあるようです)
この写真は「匿名希望様」からご寄稿いただきました。ありがとうございます!
KAWAIブランドですが、トレードマークがMIKIなのであえてこちらにしてあります。
河合小市氏が日本楽器から独立してすぐに三木楽器から後援を受けた際に作ったピアノだと推測されます。
その他下記の画像も同じく匿名希望様から頂きました、こちらもありがとうございます!
まくり(蓋部分の銘柄マーク)→★
※トレードマークはミキですが、K KAWAです(K.のドットがないのが特徴)
内部のPATENTプレート →★(プレート付きはかなり珍しいです) 響板部分のデカール →★
※ちなみにこのピアノの製造番号は4000番台なので相当古い河合小市氏製作のピアノだと思います。
三木楽器は「楽器製造会社」ではなく創業当時から「販売代理店」という形です。
<三木楽器のHPから一部抜粋>
三木楽器の前身は江戸時代の文政8年(1825年)、大阪で書籍商として勢力のあった河内屋総本家から
分家独立した「河内屋佐助」の貸本を主とする書籍業を祖としています。
1859年、農家出の友吉が8歳にして「河内屋佐助」に奉公しました。
日本が新たな時代を迎える少し前の事です。
友吉は時代のニーズを敏感に感じ取りそれを商売に転ずる商才に長けていました。
商売熱心が認められ友吉は1884年に河内屋佐助の家督を継いで、四代目佐助となり、
ヤマハの創業者 山葉寅楠は佐助の商才を見込んで自ら開発したリードオルガンを販売する
西日本の元締めを依頼しました。これが三木の楽器創業となります。
ちなみに、三木楽器本店ビルは国の登録有形文化財として平成9年9月に登録されました。
さらに詳しくはこちらの三木楽器のHPへ →★ →★
ミキのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★ |
| MIKULA, GEBR. |
詳細不明 |
| MILLER |
→HENRY F. MILLERの項目へ |
MILLET

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
MILLET ミレット/(ミレー)
新興楽器製造KK(新興楽器製作所)
長野県辰野町の新興楽器製作所のブランド。
|
MILTON
MILTON, (JOHN)
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ミルトン MILTON アメリカ(ニューヨーク) 創業1892年
ミルトンピアノカンパニーは、アメリカのピアノ生産の最盛期に、
ニューヨーク市内にあった数十社のピアノ製造会社のひとつである。
ジョン・ミルトンは1892年に542-48 W. 36th St.に会社を設立し、
ニューヨークの626-630 West 51st St.にある最新の大規模な工場でピアノを製造していた。
ミルトンピアノは高品質な楽器として作られており、1907年にコーラー&キャンベルが
会社を買収した後も、高品質な製品を作り続けていた。
しかし、1930年代後半になると品質は大きく低下します。
コーラー&キャンベル社はミルトンの名で小型グランドピアノを発売し、
半世紀以上にわたって製造された。
1950年代後半には生産が停止したが、中国に工場を設立して再びその名を広めた。
ミルトンはアップライトピアノとグランドピアノの両方のプレーヤーピアノと
ノンプレーヤーピアノを製造していた。
中国のミルトン・ピアノ・カンパニーは、元の会社とは何の関係もなく、
ミルトンの名を名乗ったダミー会社です。 |
| MINSE |
詳細不明 |
MITSUKOSHI
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
MITSUKOSHI ミツコシ
製造元:株式会社 河合楽器製作所
製造元:アトラスピアノ製造株式会社
発売元:三越(楽器部) |
| MIYATE |
ミヤテ ミカドピアノ |
MODEL
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
モデル MODEL 日本 詳細不明 |
| MODELLO |
モデロ
ボールドウィン社 アメリカ(シカゴ シンシナティ/CINCINNATI CHICAGO)
詳細不明 |
MONARCH

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
MONARCH モナーク
沢根ピアノ製作所
初期のドルファーと並ぶ沢根覚氏経営の工場で作られた。
製造期間は短かった。
|
MONARCH
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
MONARCH モナーク ボールドウィン アメリカ 詳細不明 |
MONBRAN
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
モンブラン MONBRAN
※ブランドスペルはMONBLANかもしれませんが、現時点では不明
製造元:有限会社 三陽楽器製作所
製造元:大倉楽器工業株式会社
発売元:株式会社 ピアノモンブラン |
MONDLICHT

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
MONDLICHT モンドリヒト
製造:天竜楽器製造(株)(浜松)、発売元:竹内楽器店(三田)
MOONLIGHT(ムーンライト)以前の商品名であるが、設計は異なる。
戦前(昭和11年)竹内楽器店(三田)が取次店であった。
|
MONINGTON & WESTON
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
MONINGTON & WESTON LTD. モニントン・アンド・ウェストン イギリス 詳細不明 |
|
MONSON





画像クリックでHPへ戻る
|
MONSON モンソン
ロゴには、MONSON PIANO COMPANY.LTDとあります。
製造元:有限会社 モンソンピアノ製作所
製造元:山下楽器研究所(山下楽器製造株式会社)
製造元:合資会社 平出楽器製作所
山下楽器研究所(当時の住所:静岡県袋井市高尾)は当初ピアノアクションの生産を行っていました。
その後ピアノ本体の製造にも試み、一時は関東にもかなりの台数が出荷されたようです。
アクションはもちろん”モンソン”です。
フレーム右側部分には、MATERIAL MADE IN GERMANYと書かれています。
原材料はドイツから輸入という意味でしょうか。
モンソンピアノのアクションレールに貼られたMONSONシール
→★
モンソンピアノの響板に描かれたデカール →★
モンソンのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★ |
MONTRE
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
モントル/(モントレ) 浜松ピアノ製造株式会社 |
MOONLIGHT




画像クリックでHPへ戻る |
MOONLIGHT ムーンライト
天竜工芸株式会社 昭和16年創業 (浜松市和田町)
後の天竜楽器製造(株)(製造)、[クロイツェルピアノ(株)(製造)]
天竜川のほとりにあったピアノ工場である天竜工芸のブランド。
創業当初は航空機部品を主に製造、その後ピアノも製造開始。
昭和24年ごろ天竜工芸は戦後出足早くに楽器製造を進め、静岡県勢総覧によれば、
資本金250万円で河合楽器製作所を上回り第二位、従業員数でも日本楽器、
河合に次ぐ第三位。ディアパーソン[ディアパソン](浜松楽器工業株式会社)、
シェーンベルグ(富士楽器製造)、アポロ(東洋ピアノ製造)を抜いていた。
昭和26年には平野八郎氏がヤマハ出身者を集め、ヤマハ指導のもとに新たなピアノを製造。
昭和29年、天竜楽器製造(株)に社名を改名、木工技術の優れた良品として定評があった。
日本楽器(現ヤマハ)はこれを買収してエテルナ、ミキを生産する系列工場とし、
その後合併して和田工場とした。
ちなみに「ムーンライト」はクロイツェルピアノ(株)でも作ったという記録がある。
トレードマークのデザインは土星?をモチーフにしたもの(TENRYU GAKKI SEZO K.K.)と、
ライオンとワシに天竜の「T」と工芸の「K」を使ったデザインもあります。
こちらのマーク内の文字は、TENRYŪ KŌGEI CO. Ltd と書いてあります。
ムーンライトのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★ |
MOORE & MOORE
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ムーア アンド ムーア MOORE & MOORE イギリス 詳細不明 |
| MORLEY, ROBERT |
詳細不明 |
MORGENSTEIN
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
モルゲンスタイン MORGENSTEIN 株式会社 富士楽器製作所、アトラスピアノ製造 |
MORGENSTEIN
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
韓国製 モルゲンスタイン 韓国製にもモルゲンスタインというピアノあり 詳細不明
|
MORGENSTERN
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
モルゲンスターン
有限会社 松本ピアノ工場
ベルトーンピアノ製造株式会社
松山ピアノ製作所
トニカ楽器製造株式会社
※トレードマークはライオンと一つ星のデザイン
下記のモルゲンスターン(スペル同じ)とは違うブランドなのか?不明 |
|
MORGENSTERN


画像クリックでHPへ戻る
|
モルゲンスターン MORGENSTERN
MU-2、MU-5の二機種があり、戦前は(昭和11年)竹内楽器店が取り次ぎをしていたようです。
トニカ楽器製造(?) 松本ピアノ(?) その他、詳細不明
モルゲンスターン内部の引いた画像 →★
トレードマークは韓国製のサミック(SAMICK)というピアノに酷似していますが、詳細は不明。
モルゲンスターンのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★ |
| MORI |
モリ 株式会社 森技術研究所 |
MORI & SONS
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
モリ&サンズ
製造元:フローラピアノ製造株式会社 |
MORLEY
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
モーリー イギリス(ロンドン) 詳細不明 |
| MORRISON & HARRISON |
詳細不明 |
| MÖRS |
詳細不明 |
MOUTRIE
MOUTRIE SHANGHAI

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
MOUTRIE モートリー /MOUTRIE SHANGHAI モートリー・シャンハイ
イギリスの組立ピアノ
製造元:中国上海、発売元:モートリー商会(横浜)
19世紀末、上海でイギリスの植民地政策としてこのブランドが相当数作られ、
我が国では横浜の支店で扱われていた。
※ニエアール/ニエアル NIEERの項目も参照
|
| MOZART PIANO COMPANY |
詳細不明 |
| MÜHLBACH, F. |
詳細不明 |
| MÜLLER |
詳細不明 |
| MÜLLER-SCHIEDMAYER |
詳細不明 |
MUSE
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ミューズ 倉俣楽器製作所 |
MUSENHAIM
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ミューゼンハイム?MUSENHAIM? 詳細不明
|
MUSSARD
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ムサード フランス(パリ) 詳細不明 |
| MUZELLE |
詳細不明 |
MY CONCERT
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
マイコンサート 詳細不明 |
MYSTAR
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
マイスター 詳細不明
MEISTERとは違うのか?不明 |
上記Mから始まるブランドの中で、追記出来そうな事項や新情報を発見した場合、修正受付フォーム よりお気軽にお知らせ下さい。
どんな些細な情報でも構いませんので、広く皆様からのフィードバックをお待ちしております。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
 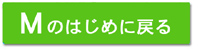 



上記Nから始まるブランドの中で、追記出来そうな事項や新情報を発見した場合、修正受付フォーム よりお気軽にお知らせ下さい。
どんな些細な情報でも構いませんので、広く皆様からのフィードバックをお待ちしております。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
 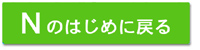 



上記Oから始まるブランドの中で、追記出来そうな事項や新情報を発見した場合、修正受付フォーム よりお気軽にお知らせ下さい。
どんな些細な情報でも構いませんので、広く皆様からのフィードバックをお待ちしております。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
 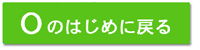 



ピアノ銘柄ブランド
トレードマーク 紹介
& 知名度ランキング

|

メーカー/ブランド説明・会社沿革・歴史・製作者・特徴・音色・他
|
| P.S. WICK |
P S WICK CO 詳細不明
※ピアノのまくり(蓋部分)には、St.Paulと書いてあります |
P. WELCE

トレードマークなし |
P.WELCE ピー・ウェルス (ピー・ヴェルチェという発音表記の別情報もあり)
フクヤマピアノ(株式会社 福山ピアノ社)
福山ピアノの命名した多数のブランドの一つで、小型で価格の安いものにつけられていた。
中音、高音域のピアノ線が通常のピアノは3本張りなのに対して2本で張られています。
鍵盤数も一般的な88鍵ではなく、鍵盤数も少ないピアノも製造で、廉価版ピアノ。
戦後間もない頃のピアノは材料を苦心して集めたピアノだったようです。 |
PACKARD
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
パッカード・ピアノ アメリカ(インディアナ州フォート・ウェイン) 創業1871年
パッカード・オルガン社→その後、「Packard Piano & Organ Company」に社名変更
ピアノのまくり(蓋部分)には、「THE PACKARD COMPANY, FORT WAYNE. IND」
と書いてあります。
パッカード・ピアノは、1871年にインディアナ州フォート・ウェインで、
パッカード・オルガン社として設立されたのが始まりである。
1893年まではオルガンのみを製造していたが、1894年にピアノ製造に参入した。
ピアノの製造に成功すると、社名を「Packard Piano & Organ Company」に変更した。
その後、世界恐慌の影響を受けながらも、1938年にStory & Clark Piano Companyに買収された。
ストーリー&クラーク社は、20世紀半ばまでパッカードのブランド名でピアノを作り続けた。
パッカード・ピアノ社は、工場での作業環境を重視していたことで知られている。
フォード・モータースの工場で組立ラインが導入されると、パッカードのピアノ製造工程も
それに倣ったものになった。
工場に調和がなければ、ピアノにも調和はない」というのが、同社の代表的な言葉である。
インディアナ州にあるこの工場は、現在も生産されている中西部最大のピアノ工場の一つである。
当初はアップライトピアノやベビーグランドピアノを製造していたが、
後にプレーヤーピアノも製造するようになった。
また、キャビネットには良質な木材を使用することでも知られていた。
パッカード・インタープリター・プレーヤー・ピアノ(グランド、アップライト、リプロダクション・スタイル)
は、パッカード・ピアノと同様の芸術的特徴を持ち、電子プレーヤー機能が追加されている。 |
|
PACO


画像クリックでHPへ戻る
|
パコピアノ/グラチアピアノ
製造元:PACO/GRATIAE 北朝鮮
販売元:有限会社パコ/(有)PACO/PACO CO.,LTD
当時の会社住所:東京都府中市寿町1-8-1 寿町KYビル5F(当時)
金正日(キム・ジョンイル)が自国でもピアノを作れとの意向で、朝鮮総連系の日本のピアノ製造会社との
合弁で『平壌ピアノ合弁会社』を1988年に設立したのが始まりとされています。
この会社は日本のピアノの製造会社ではなく、「日本人技術者」が「日本製の工作機械」を使い、
北朝鮮でピアノを製造(組立て)していたようです。最終調整は日本国内(浜松)で行い出荷。
製造が容易な部品のみを北朝鮮で作り、その他の部品は全て日本から輸入して組み立てていました。
製造開始当時は、北朝鮮製の部品の比率はわずか1%程度であったとされています。
日本法人の(有)PACO社と、北朝鮮政府との合弁会社にて
日本人技術者(大成ピアノ出身)の技術指導・輸入販売を行っていたようです。
現在は既に日本との合弁を解消しています。
日本国内での製造輸入は、『PACO社』が行なっていました。
当時の日本においては、アップライトピアノの市場が飽和していた上に、デジタルピアノが登場した事により、
アップライトピアノ製造を主とするピアノ製造業はまさに苦境を迎えていました。
こうした状況下での、北朝鮮からの技術協力要請は、好意的に受け止められていた。
日本人技術者が北朝鮮に滞在しての技術指導は約7年間ほど続いたとのことです。
一時期クロイツェルとも提携?Welt & Kreutzerというブランド名のようですが詳細不明。
ブランドはGRATIAE(グラチア)、FEINTON(フェイントン、ファイントン)など低価格のピアノ。
当時本社は東京都府中市にあって、パコピアノの販売は国内だけではなく、
東南アジア・中国・ヨ-ロッパにも輸出していたという情報もありますが、詳細は不明。
私自身、グラチア1台しか調律したことがないので何とも言えませんが、
ピアノ自体は ”北朝鮮”というイメージほど悪くはなく、そこそこの作りではありました。
機種バリエーション:PU-120等
グラチアピアノのまくり(フタ部分)にあるブランド銘柄マーク
→★
パコ、グラチアのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★ |
| PAINTER & EWING |
詳細不明 |
| PALATINO |
詳細不明 |
| PALING MINOR |
詳細不明 |
| PALLIK & SCHICKER |
詳細不明 |
| PALLIK & STIASNY |
詳細不明 |
PAPE
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
パープ 創業1817年 フランス(パリ)
詳細不明 |
| PAPE FILS (FRÉDÉRIC-EUGÈNE) |
詳細不明 |
| PAPE, JEAN-HENRI |
詳細不明 |
| PAPPENBERGER |
ANTON PAPPENBERGER/アントン・パッペンバーガー
オーストリア(ウィーン) |
| PAPPS |
詳細不明 |
| PARTTART, ALOIS |
詳細不明 |
PASTORAL
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
PASTORAL パストラル 冨田ピアノ有限会社(浜松)
詳細不明
ト音記号をモチーフにしたトレードマークが印象的です。 |
| PAUKERT |
詳細不明 |
| PAUL GERHARD |
詳細不明 |
PAUL WEISS
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
PAUL WEISS ポール・ワイス ドイツ(旧西ドイツ) 詳細不明
|
| PAUL WERNER |
PAUL WERNER (DRESDEN)
詳細不明 |
| PAWLEK, JOSEF |
詳細不明 |
PEACE
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
PEACE ピース 大和楽器製造株式会社 詳細不明 |
PEARL RIVER


画像クリックでHPへ戻る |
PEARL RIVER パール・リバー(珠江) 中国(広州)
珠江牌とよばれる広州製のピアノ。珠江とは広州の街の真ん中を流れる大河。
ピアノはすべてアップライトで、背が低く、当時スピネットタイプの小型が多かった。
中国のピアノのうちでは最も安価なものの部類。
<以下、ウィキペディアより引用抜粋>
広州珠江鋼琴集団(こうしゅうしゅこうこうきんしゅうだん、グァンヂョウジュジャンガンチィンジトゥアン、
英語: Guangzhou Pearl River Piano Group Co.,Ltd、SZSE: 002678)股份有限公司は、
中国で最大のピアノ製造業者であり、世界最大のピアノ工場を有している。
1956年に中華人民共和国広東省広州市で設立された。
通称は広州珠江鋼琴集団股份、広州珠江鋼琴集団、広州珠江鋼琴など。
中国国外ではパールリバー(Pearl River)として知られている。
パールリバーは年間10万台を越えるピアノを生産する能力があり、それらを80を越える国々へ輸出している。
今日、パールリバーピアノは幅広いブランドと水準の下で生産されている。
パールリバーは「Kaiserburg」、「珠江(Pearl River)」、「Ritmuller」、「京珠」などのブランドを中心に
様々な種類のピアノを製造・販売している。
2016年1月、パールリバーはドイツ・ブラウンシュヴァイクのピアノメーカーヴィルヘルム・シンメルの
株式90%以上を取得した。ドイツにおける経営は変わらないままであり、シンメルの工場は
今でもシンメル家によって管理されている。
1998年、パールリバーは中国のピアノメーカーとして初めて、全ての部品と構成要素を含む
グランドピアノおよびアップライトピアノの全製品について国際標準化機構ISO 9001認証
(ISO 9001)を取得した。パールリバーは最近ISO 14001も取得した。
パールリバーは米国において自社での流通を行っていたが、2000年に流通を
North American Musicに引き渡した。パールリバーは自身の社名の下で米国において
ピアノを販売した最初の中国ピアノメーカーの一つであり、ピアノ教師と調律師によく受け入れられてきた。
パールリバーは世界最大のギターおよびバイオリン製造業者の一つでもあり、
百貨店ターゲットで一般に見られる人気のあるギターブランド「ファーストアクト」の主要な供給業者である。
ドラム、金管楽器、木管楽器も国際的に販売している。
中華人民共和国では、自身のブランド名「紅棉」の下でギターを生産している。
パールリバーは新しいリットミュラー(Ritmuller)シリーズを作るために
ピアノデザイナーのLothar Thommaを雇った。
最終的に、Thommaはリットミュラーシリーズのパフォーマンスモデルとプレミアムモデルの
両方を設計するか設計を手助けするかした。
パールリバー社は、Lothar Thomma設計のリットミュラーピアノはヨーロッパのスケール設計を備え、
最高級のヨーロッパ製部品を使用し、手仕上げを行うためにより小規模でゆっくりとした製造工程である、
と述べている。パールリバーとリットミュラーの違いには、Thomma設計の低張力ドイツ式スケール、
ドイツFilzfabrik Wurzen GmbH製フェルト、ドイツ・レスラウ(Röslau)製弦、本物の黒檀鍵、
ドイツAbel製ハンマー(パフォーマンスモデル)及びドイツレンナー製ハンマー(プレミアムモデル)等がある。
米国の3つの大規模なピアノ小売企業はOEM自社ブランドの供給元としてパールリバーを使っている
(Jordan Kitts Music、Sherman Clay〔閉店〕、Schmitt Music)。
これらの小売チェーンは独自のブランド名(Henry F Miller、Christofori)を使用している。
ヤマハは1995年にパールリバーと合弁事業を作り、中国市場向けのピアノを製造するための工場を設立した。
この工場は経済技術開発区の広州の東、パールリバーの工場から約35マイル離れている。
この工場はパールリバーピアノグループのために2つのモデル、UP125M1およびリットミュラー
UP126Rを生産している。どちらの製品種目も小売ピアノ店によって米国で販売され、
鍵盤の横に「Yamaha Pearl River」という追加の刻印が押されている。
パールリバーはスタインウェイ・アンド・サンズの「エセックス」ブランドのグランドピアノと
アップライトピアノを含む全てのモデルも広州工場にて製造している。
2005年5月1日、スタインウェイ・アンド・サンズとパールリバー・ピアノグループは
合意について合同で発表した。両社はスタインウェイ・アンド・サンズが系列会社の
ボストンピアノCo., Inc. のために設計した複数の新しいエセックスモデルの開発を開始した。
エセックスピアノは2006年の初めに市場に届いた。
これはスタインウェイの中国における初の事業であり、
パールリバーが西洋のピアノメーカーと結んだ初のOEM関係であった。
Hallet, Davis & Co. Boston (HD&C) は、通常Hallet & DavisまたはH&Dと呼ばれる
ピアノ製品ラインである。元々のHallet, Davis & Companyは1841年に
George H. Davis、Russell Hallet、およびその他の共同経営者によってボストンで設立された。
この会社はDavisと創業者とは別のHallet(Benjamin Franklin Hallet)によって
1950年代にボストンで再構成された。
1900年代初めにW. W. Kimball CompanyがHallet & Davisを買収した。
1905年、持ち株会社Conway CompanyがKimballからHallet & Davisの名称を取得した。
1927年にConwayはピアノ事業を整理した。
Hallet & Davisのブランド名と100年以上続くその製造の起源に関しては混乱があった。
1904年12月版の「Piano and Organ Workers’ Official Journal」において、
編集者らは「数年前にHallet & Davisの工場がシカゴから撤去され、
Kimball Companyと合併したにもかかわらず、いわゆる業界紙がボストン製の楽器として
Hallet & Davisピアノを発表し続けていること、結果として犯罪的なごまかし・詐欺を手助けし
幇助していることについて読者は興味を持って知りたいと思っていることだろう」と述べた。
20世紀中頃、 Hallet & Davisの名称は、その他多くの 米国ピアノブランドと同じように、
エオリアン-アメリカンCorp.(1985年に破産宣告)の下に集約されていた。
Hallet & Davisブランドとその適切なボストンとのつながりを復活させようという試みが
1998年に成され、商標「HALLET, DAVIS & CO. BOSTON」がNorth American Music, Inc. によって
出願された。この出願は米国特許商標庁(USPTO)によって「拒絶/却下または無効」とされた。
その翌年の1999年、North American Musicは再びHallet & Davisの商標
(この時はBOSTONを外して単に「HALLET, DAVIS & CO.」として)を出願し、
最終的に2001年にUSPTOによって許可された。
新たなH&Dピアノがマサチューセッツ州ボストンと少しの関係もないという事実にもかかわらず、
中国のパールリバー・ピアノグループはH&Dのステンシルの下に「Boston」を
(登録商標の一部ではないにもかかわらず)入れている。
パールリバー・ピアノグループは2014年以降H&Dラインを生産してきた。
2014年以前は、このブランド名のピアノは東北鋼琴(ドンペイ・ピアノ)によって作られていた。
しばらくの間、H&Dブランドは両方のメーカーから同時に生産されていた。
今日、Hallet & DavisはNorth American Musicが卸すために製造されるピアノのOEMラインである。
ここ数年全てのH&Dピアノはパールリバーによって作られているものの、
このブランドには非常にさまざまなデザインと品質を持つ詳細が不明確な製造の歴史がある。
過去このブランドは、北京星海楽器や東北鋼琴(ドンペイ・ピアノ)、
Silberman Piano、Parsons Music、そしてパールリバー・グループを含む
複数のピアノメーカーによって製造された。
パールリバーのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★ |
PEARL RIVER
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
PEARL RIVER ユンチャン(パールリバー) 韓国 詳細不明
|
PEASE
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
Pease ピーズ
1959年にウインター(WINTER & CO.)は、エオリアン・アメリカン社と合併し、
社名をエオリアン・コーポレーションに変更していた間、PEASEは
ウィンター&カンパニーが製造していたブランド名の一つです
→詳しくはWINTERの項目へ |
| PEEK AND SON |
詳細不明 |
| PEPPER |
詳細不明 |
| PERIOD PIANO COMPANY |
詳細不明 |
PERZINA
PERZINA, GEBR.



画像クリックでHPへ戻る |
GEBR.PERZINA ペレツィーナ(ペルツィーナ) ドイツ ※現在は中国製造
(現在の製造:中国山東省東部の煙台にある、煙台ペレツィーナ(エンタイペレツィーナ)
ペレツィーナ(ペルツィーナ)Perzina/Gebr. Perzinaは、北ドイツ生まれのピアノブランドで、
現在はオランダと中国の資本による中国煙台の民営企業・煙台ペレツィーナで製造。
<歴史>
1871年、ヴィルヘルム1世によりドイツ帝国が生まれたその年に、
北部のシュヴェリンという都市でGebr.Perzinaも生まれました。
現在も宮廷の残るメクレンブルク=シュヴェリーン公、オランダのウィルヘルミナ女王に
こよなく愛されたGebr.Perzinaは6王家の宮廷ピアノとしてドイツで最も権威ある
ピアノのひとつとなりました。
また、1905年にはペルツィーナコンサートホールも開設され、
ドイツ帝国内で最も愛されるピアノとなりました。
しかしながら、第一次世界大戦で移転を余儀なくされ、さらに第二次世界大戦後は
東ドイツに組み込まれたGebr.Perzinaは手造りでピアノを作り続けたものの、
大戦後のピアノの歴史では表舞台にはあまり出てこなくなりました。
2002年公開の映画 「戦場のピアニスト」(※)で使われたピアノとしても有名です。
(※)第二次世界大戦におけるワルシャワを舞台としたフランス・ドイツ・ポーランド・イギリスの合作映画。
ペレツィーナのまくり部分(蓋部分)にある銘柄ブランドマーク →★ 他の部分にあるマーク →★
トレードマーク画像をはじめ、全ての画像は「匿名希望様」からご寄稿頂きました。ありがとうございます!
中国煙台に工場を移転した後に製造したピアノだと思われます。
欧州の部品を多く使って中国で製造・組立しているとのことです。
製造会社:合弁会社Yantai-Perzina(エンタイ・ペレツィーナ/煙台ペレツィーナ)
<参考>
「煙台」の読みで「エンタイ」と「ヤンタイ」の2種類がピアノ関係ページのネット上各所に混在しています。
当方独自の調べですと発音の雰囲気としては「イェ-ン タァ-ィ」という感じが最も日本語表記だと正確です。
なので、どちらかというと「ヤンタイ」という表記よりも「エンタイ」の方が発音的には自然かもしれません。
ちなみに、”地名”としての発音では「エンダイ」という発音表記もあります。
<以下、ウィキペディアより引用抜粋>
ペルツィーナ(Perzina、Gebr. Perzina〔ペルツィーナ兄弟〕)は、1871年から1929年頃まで
ドイツ北部のシュヴェリーンの鍵盤楽器製造業者(Gebr. Perzina GmbH、Alvari-Piano-GmbH、
Pianofortefabrik Gebr. Perzina)によって使われたブランド名である。
日本ではペレツィーナとも呼ばれる。
現在、ペルツィーナブランドのピアノはオランダと中国の資本による中国煙台の民営企業・
煙台ペレツィーナ (Yantai Perzina Piano Manufacturing Co., Ltd.) によって生産されている。
ザクセン系ピアノ職人を父に持つユリウス・ペルツィーナとアルバート・ペルツィーナの兄弟は、
20代後半になると父の仕事を引き継ぎたいと望み、ベヒシュタインの創業者である
カール・ベヒシュタインの元で修行した。
その他にもドイゼン(ドイツ語版)やシュヴェヒテン、レーニッシュの下で修行と経験をつみ、
ピアノ職人の技術を修得したペレツィーナ兄弟は、1871年7月1日にドイツ北部のシュヴェリーンという町で
「Pianoforte Fabrik Gebrüder Perzina」(ペルツィーナ兄弟ピアノ工場)を創業した。
会社を設立した初年度は20台のピアノが製造された。1883年にメクレンブルク大公家御用達の称号が
ペレツィーナに授与された。数年後、Gebr. ペルツィーナ社は「オランダ女王」、「ポルトガル王」、
「アンハルト公」の御用達称号を授与された。
ペルツィーナ社はオランダのウィルヘルミナ女王や、ハインリヒ・メクレンブルク=シュヴェリーン
(オランダ女王ユリアナ王妃の父)、オルデンブルク公爵等にピアノを納めた。
ピアノ工場を開業して数年後、兄のアルバートが引退したが、
社名のGebr. ペルツィーナ(ペルツィーナ兄弟)は残った。
1894年にペルツィーナ社はアントウェルペン国際博覧会は、1895年にアムステルダム国際博覧会へ出品した。
1900年頃から会社は急成長をし始めた。1901年のレターヘッドでは自社を
「ドイツ・バルト海諸国で間違いなく最大で最も効率的なピアノ工場」と形容していた。
1897年の始め、シュヴェリーン工場のスタッフが約10週間仕事を止めた。
従業員らは賃金の引き上げを求めてストライキを行った。
1897年4月、わずか52歳で共同創業者のユリウス・ペルツィーナが死去した。
工場の経営は、合名会社の設立後、続く20年間ハンブルクの実業家ダニエル・フス(Daniel Huss)の
手に渡った。社主の義理の息子は経営責任者としてピアノ工場を手工芸工場から産業工場へと転換した。
創業年の1872年に生産された楽器は20台だったが、1897年には既に315台、1900年までには
シュヴェリーン工場の生産数は年間768台に伸びた。
1904年7月26日の壊滅的な火災によって生産建物のほとんどが破壊された。
それからの3年間にわたって、宮廷石工のLudwig Cleweが合名会社の株主の指定にしたがって
新たな工場建物を建設した。この中にはWismarschen通り44番地の本館も含まれ、今日も現存している。
1910年頃には年間製造台数が1000台まで増加(グランドピアノの製造は1905年から開始)。
数年後、製造工場を拡大するためシュヴェリーンより約60 km南下したレンゼンという町に移転した。
第一次世界大戦まで急激に成長した。この頃がドイツ時代のペレツィーナの製造のピークであった。
第一次世界大戦の開戦以降、Gebr. ペルツィーナは「フォッカーヴェルケ・シュヴェリーン
(Fokkerwerke Schwerin)」のためにバルブとプロペラの生産を行い、
1914年8月からは弾薬袖も生産ラインに加わった。1916年、ペルツィーナ社は検察庁の標的とされた。
排出された薬莢が新たな供給品に再び混入された; 従業員1名が贈収賄で通報、逮捕された。
このスキャンダルは多忙な経営責任者ダニエル・フスを直撃し、
10カ月の禁固刑と2年間の市民権剥奪を言い渡された。
1917年8月23日、アントニー・フォッカーが工場と400名の従業員を買収した。
ヴェルサイユ条約の条項の結果として、航空機メーカーのフォッカー社は1919年に本社を
シュヴェリーンから移転した。
戦後、フォッカーはピアノ工場をオットー・ルボー(Otto Libeau)に貸した。
1920年4月から、会社はピアノに加えて家具と木箱も生産した。
グーテンベルク通りの第三工場は1923年に「Alvari-Piano-GmbH」に改称した。
Wismarschen通りにおけるピアノの生産は1929年頃まで行われた。
1930年代、「低地ドイツ・ベオハバター」(Niederdeutsche Beobachter)紙が以前の本館に移転してきた。
シュヴェリーンのピアノ製造者Wilhelm Meyerはオットー・ルボーと共に
「Gebr. ペルツィーナGmbH」という名称でピアノを製造した。
ルボーは1930年代中頃に会社を離れた。1929年まで、ペルツィーナ社はシュヴェリーンの住所録に
「Gebr. Perzina GmbH, Pianoforte-Fabrik, gegr. 1871. Inh. Wilhelm Meyer, Wismarsche Straße 153」と
掲載されていた。1984年から2013年まで、シュヴェリーン市立図書館は
「ペルツィーナハウス(Perzinahaus)」を使用した。
二度の世界大戦によって多くのピアノメーカーが姿を消す中、
ペルツィーナは東ドイツの国営企業として生き延びた。
「Perzina」ブランドのアップライトピアノとグランドピアノはレンツェンにおいて
国有企業の下で1959年から1972年まで生産された。
1930年代の始め、ベルリンのピアノ修復者Friedrich Geilがレンツェンで
「Wagner」ブランドのピアノ生産を始めた。
Geilはシュヴェリーンの議会から登録商標「Gebr. ペルツィーナ」を使用する権利を与えられた。
1972年、この会社は収用され、VEBドイツピアノ組合ライプツィヒに譲渡された。
1989年の転換後、ブランド名「Wagner」および「Perzina」はGeil家によって再び引き継がれ、
ピアノ生産の再編が目指された。経営責任者の突然死の後、1990年末に以前の生産責任者が新たに
設立された有限会社(GmbH)のトップとなった。
1990年代中頃にオランダの楽器卸売業者Ronald G. Bol(Music Brokers International B.V.)が
世界的な販売権を取得し、その後事業に参加した。
Bolは徐々に生産をドイツ国外へ移し(1998年に中国の煙台〔エンタイ〕に生産拠点を移転)、
レンツェンのピアノ工場は最終的に1996年12月に閉鎖された。
ペルツィーナブランドのピアノは、Yantai Longfeng Piano Co.での生産を経て、
現在は煙台ペレツィーナの年間15000台の生産能力(アップライト)をもつ近代的な設備のもとで製造されている。
煙台ペレツィーナは、2003年にBolと中国人実業家Sun Qiangとの共同で設立された。
Bolがこの民営企業の副社長で、海外への供給責任者である。
主任技師はドイツ人のHas Leferinkである。彼によって設計や品質管理がされている。
ドイツ・レンゼンのピアノ工場は1996年12月に閉鎖され、
現在の欧州本部はオランダ・ヴィーネンダールにある。
煙台ペルツィーナで製造されている「Gebr. Perzina」ロゴのピアノのみが、
ドイツ生まれの歴史ある「Perzina」ブランドを継承している。
それ以外では製造されていない。60%以上を日本や欧米をはじめとする海外50か国以上に、
残りは中国内100以上の都市に供給しているとしている。
日本では、1972年設立のピアノ量販店「ピアノ百貨」の全国の7店舗で販売されている。
Music Brokers Internationalは他にも欧州生まれのピアノブランドの製造権を所有しており、
煙台ペルツィーナ(ヤンタイペルツィーナ)で、これらの他ブランドのピアノも製造している。
「Gerh. Steinberg」(ドイツで1908年創業)、「Carl Ebel」(ドイツで1877年創業)、
「Eavestaff」(イギリスで1823年創業)、「Rippen」(オランダで1937年創業)などの
ブランドがそれである。
2002年に公開されカンヌ映画祭でパルムドールを受賞した映画「戦場のピアニスト」の
廃墟の中の演奏シーンで、ドイツ時代のペルツィーナのグランドピアノが使用された。
また、ペルツィーナ(Gebr. Perzina)のアップライトピアノは、アメリカのLarry Fine著
「THE PIANO BOOK (2007-2008)」のピアノランクにおいて、中国製ピアノとして初めて
グループ3のAランクに入った。当時同ランクメーカーの中では、低価格であった。
現在のペレツィーナのアップライトピアノは、現代ピアノの心臓部とも言われる響板に特徴がある。
フローティング響板(floating Soundboard)、逆クラウン響板(reverse-crown soundboard )などと
呼ばれているものである。いずれも、現代の他のピアノにはまず見られない非常に珍しい構造と言える。
一般的なピアノは、響板は響棒と接着された状態でその全周を土台である「バック」に対して接着され、
しっかりした土台を固定端とすることによって、響板振動の無駄な減衰を防止する。
しかし、現在のペレツィーナのフローティング響板は、響板の下辺が支柱等で構成されるバックから
完全に離れており、響板の左右辺は支柱にネジ止めされている。
また、通常のピアノの響板は、弦側に凸状の形状であり弦圧に対して突っぱるようになっている。
これが響板の「クラウン」であり、適切なクラウンこそが、ピアノの力強い音の源泉であると考えられている。
アップライトピアノの寿命とは、響板がひどく割れたり、響板が沈下してクラウンが失われ弦圧が
維持できなくなったときだと言われることがあるほどである。
適切なクラウンの形成とその維持には高度な技術が必要とされている。
逆クラウン響板では、最初から響板が弦圧によって弦側からみて凹状になっている。
これにより、演奏者側により多くの音響が放射され、また(逆)クラウンが長く保たれるとしている。
また、他の中国製ピアノとは異なり、多くの部品をドイツをはじめとする欧州から調達しているとしている。
このことを煙台ペレツィーナは、彼らのピアノに欧州標準品質(ESQ:European Standard Quality) という
独自のマークをつけて自己発信しています。
ペレツィーナのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★ |
| PETERBORGH |
詳細不明 |
|
PETROF





画像クリックでHPへ戻る
|
ペトロフ PETROF
旧チェコソロバキア国家公団製造
創業1864年 チェコスロバキア製(現在:チェコ共和国)
非常に音色が柔らかでまろやかなピアノで、このピアノを指弾すると一瞬で虜になる人がいるほど。
ペトロフアップライトの最高音のミュージックワイヤー(ピアノ線)は、13番よりさらに細い
12番半を使っているピアノもあります (普通のピアノは13番が一番細い弦です)
温湿度の変化に弱い印象も受けますが、総合的に良いピアノだと思います。
ただ、外装に接着してある装飾のモールディング(装飾の飾り)は本当によく剥がれます^^;
一番下のトレードマークは日本向けではないタイプ(アメリカ購入)のペトロフのアップライトです。
<概要>
ペトロフはアントニーン・ペトロフによって、チェコのボヘミア(チェコ西部・中部を指す歴史的地名)で
生み出されたとても素晴らしいピアノです。社会主義国家出身のピアノなのであまり宣伝はされませんが、
ロシア(旧ソ連)や東欧諸国、西欧諸国では名器として知られています。
このピアノ製作会社は社会主義時代に国有化される以前、三代にわたりペトロフ家が所有し、
業界の技術革新に乗り遅れることなく、博覧会で数々の賞を受賞してきた。政治変動の世紀を乗り
越え、現在もペトロフ社はチェコ共和国でもっとも有名なメーカーの地位を守り続けている。
コンサートグランドは戦前~戦後を通じて各地の博覧会や国際見本市に於いて
金賞を獲得しており、アルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリ(Michelangeli)
(ミケランジェリは、イタリア出身のピアニスト)や、スヴャトスラフ・リヒテル(ソ連出身のピアニスト)、
ヴィルヘルム・ケンプ(Wilhelm Kempff)(ドイツ出身のピアノニスト)らもこのペトロフを
愛用していたと記録が残っています。さらにはジャズ音楽のオスカー・ピーターソンや、
デューク・エリントンもペトロフを絶賛したと伝えられています。
<詳細な歴史>
家具職人の修行を積んだアントニーン・ペトロフは、1857年に19歳でウィーンへ出て、
ピアノ製作者のおじ、ヨハン・ハイツマンに弟子入りする。
アントニーン・ペトロフは、オーストリアのさまざまな製作者のもとで働いたのち、
1864年に生まれ故郷のフラデツ・クラーロヴェーに戻って会社を設立した。
初めはウィーン式アクションのピアノを少数製作していた。
旅行を多くしたペトロフは、各地の最新の技術発展を敏感に察知して自らの設計に取り入れ、
1875年には鋳鉄フレームと、イギリス式グランドアクションを改良したレぺティション・アクションを用いた。
1880年に、ペトロフはグランドに加えてアップライトピアノの生産も開始し、亡くなる1915年までに
35,500台のピアノを販売した。
アン卜ニーンの3人の息子と3人の孫たちは、ふたつの大戦と大恐慌を上手く乗リ切って会社を運営した。
会社は1948年に国有化され、産業通商団体チェスコスロヴェンスケー・フデブニー・ナーストロイェ・
ミュージックエクスポートの一部となり、その傘下で繁栄を続けた。
1970年にアップライトピアノの生産を増大するための新工場が建てられ、さらに1989年には、
グランドピアノ市場に集中するためのもうひとつの新工場が建てられた。
そして1990年までに製造番号は450,000に達した。ペトロフ社は近年、年間約12,000台のアップライトと、
年間約1,750台のグランドピアノを生産し、約1,000人の従業員を雇っている。
1997年に設立されたトヴァールナ・ナ・ピアニナ社が、2001年にペトロフ社と結合し、
1991年に始まった会社私有化へのプロセスはクライマックスを迎えた。
■機種/モデル バリエーション (並び順は後述機種ほど高級機です)
・グランドピアノ (カッコ内の数字はペダルの数)
MODELⅤ(2)、MODELⅣ(3)、MODELⅢ(3)、CHIPPENDALE(2)、ROCOCO(2)
・アップライトピアノ
CLASSIC、DEMI-CHIPPENDALE(ねこ脚)、125-I、BAROQUE、
CHIPPENDALE(ねこ脚)、ROCOCO(ねこ脚)
ペトロフ独特の鉄骨フレームの音響効果を高めるために付けられた無数の凹凸 →★
ペトロフ(日本以外向け)のまくり部分のブランド銘柄マーク →★
<ピアノ調律技術者向け附録>
張弦作業に役立つ当該機種ミュージックワイヤー配線仕様 →★
<下記はペトロフ社の扱うピアノブランド(2018年現在)>
ANT.PETROF、PETROF、Ant. Dalibor、Weinbach、Rösler、SCHOLZE、FIBICH、AKORD
<附録>
ペトロフピアノ 製造番号/製造年代 対照表(1900年~2000年) →★
<以下、ウィキペディアより引用抜粋>
ペトロフ(Petrof)はチェコ共和国、フラデツ・クラーロヴェーを本拠地とするピアノメーカーである。
1857年、アントニン・ペトロフは、ウィーンでピアノ工房を営む叔父ヨハン・ハインツマンの元で
ピアノ作りを学び始め、フリードリッヒ・エルバーやシュヴァイクホーファーといったその他の
著名なピアノ製作者の下で修行した。1864年に故郷のフラデツ・クラーロヴェーに戻り創業し、
父の工房で最初のコンサートグランドピアノを完成させた。
その後、業界で初めて鋳造フレームを採用したり、当時まだ普及していなかったアップライトピアノの
製造をいち早く始めるなど、斬新な技術と高い品質で名声を得た。
1899年にオーストリア王室御用達を取得、1958年にはブリュッセル万博金賞を受賞。
1948年に国有化され経営権は創業家の手を離れたが、1991年に4代目のヤン・ペトロフが経営者として復帰、
2004年より5代目のズザナ・ツェラロヴァー・ペトロフォバー(Zuzana Ceralová Petrofová)が
経営を引き継ぎ現在に至る。
ペトロフは1932年にエレクトロ-アコースティックピアノネオ-ベヒシュタインを生産するライセンスを取得し、
ネオ-ペトロフ(Neo-Petrof)として販売した。
ペトロフ工場は他のブランドも生産している。イジーコフ工場では、Weinbachブランドのピアノが
事前に組み上げられ、最終的に中国で組み立てられる。
この工場では第二次世界大戦までアウグスト・フェルスター社の工場があった(現在の拠点はレーバウ)
国営企業とペトロフ社は2000年までドイツのフェルスター社とは独立にこの工場で
August Försterブランドのピアノを生産した。
ペトロフ公式ホームページ(日本語)→https://jp.petrof.com/
※ペトロフはBVK認証を受けています(詳しくはこちら →★)
ペトロフのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★ |
| PETROV |
詳細不明 |
| PETZOLD |
詳細不明 |
| PEUKERT |
詳細不明 |
| PFAFFE, JULIUS |
詳細不明 |
PFEIFFER

画像クリックでHPへ戻る |
PFEIFFER プファイファー/(ファイファー)
ドイツ(バーデン=ヴュルテンベルク州) 1862創業
<以下、ウィキペディアより引用抜粋>
カール・A・プファイファー(Carl A. Pfeiffer)GmbH & Co. KGは、
ドイツ・バーデン=ヴュルテンベルク州レオンベルクのアップライトピアノおよび
グランドピアノ製造業者である。伝統的な技術を用いたピアノ製作でよく知られている。
1862年にヨーゼフ・アントン・プファイファー(1828年–1881年)によってシュツットガルトで創業された。
彼の父カール・A・プファイファーはグウォグフ(現在のポーランド。ドイツ語名グローガウ)で
既にピアノ製作者として働いていた。後者は2つの響板を持つダブルグランドピアノ(独: Doppelflügel)
を初めて製作した。今日、会社はプファイファー家の5世代目によって経営されている。
ヨーゼフの息子、カール・アントン・プファイファー(1861年–1927年、社名の由来)は
ピアノのための道具をいくつか開発した(ワイヤーを正確に曲げるためのいわゆるKröpfzange〔ペンチの一種〕等)
息子のヴァルター・プファイファーもピアノ、特にアクションを科学的に扱った。
このテーマに関する彼の著作はピアノ製作において標準となる文献として一般的に認められている。
ドイツ民主共和国(東ドイツ)の西への編入後、ライプツィヒを拠点とするピアノ工場であった
ルートヴィヒ・フップフェルトAGおよびレーニッシュを買収した。
プファイファー自身は1994年からレオンベルクを拠点としており、高品質のピアノ製造を続ける
数少ない会社の一つである。2005年時点での年間生産台数はグランドピアノが約10台、
アップライトピアノが約100台である。
レーニッシュおよびフップフェルトブランドのピアノの製造は2009年に破産するまで続けられた。
その後、レーニッシュの名称はブリュートナーが購入した。
公式HP:https://www.pfeiffer-pianos.com/en/home
※PfeifferはBVK認証を受けています(詳しくはこちら →★) |
| PFEIFFER, J. |
詳細不明 |
| PHILIPPS |
詳細不明 |
| PHILLIP |
詳細不明 |
| PHILLIPS |
詳細不明 |
PHOENIX
PHÖENIX
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
PHÖENIX (PHOENIX) フェニックス
有限会社 光輪楽器製作所
※大洋楽器工業株式会社とする資料もあり |
PIANETTE
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
Pianette ピアネッテ
1959年にウインター(WINTER & CO.)は、エオリアン・アメリカン社と合併し、
社名をエオリアン・コーポレーションに変更していた間、PIANETTEは
ウィンター&カンパニーが製造していたブランド名の一つです
→詳しくはWINTERの項目へ |
PIANETTE
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ピアネット 日本楽器製造株式会社 詳細不明 |
| PIANO DISC |
詳細不明 |
| PIANOLA |
Pianola ピアノラ
1900年代初頭にエドウィン・ヴォティーが特許を取得し、
エオリアン社が製造したプレーヤー・ピアノの名称である。
テネシー州メンフィスの工場で製造されたこのピアノは、一般のアメリカ人が家庭で使用するために
販売された最初のプレーヤー・ピアノの一つとして有名になった。
そのため、異なるメーカーのものであっても、ほぼすべてのプレーヤー・ピアノを総称して
「ピアノラ」と呼ぶことが多い。
ピアノラは1960年から1982年まで生産されていたプレーヤーピアノ。
Gibson GuitarsがAeolian Corporationを買収した際には、2001年にPianolaの名前で
プレーヤーピアノの生産を続けていた。
ピアノラは64音のプレーヤーピアノで、手動、ペダル式、自動の3種類の演奏方法がありました。
ピアノラには電動モーターが搭載されており、ロールにプログラムされた曲を
自動的に演奏することができました。[2]
今日、多くのプレーヤー・ピアノはデジタル化されているが、Pianolaプレーヤー・ピアノは
空圧システムで作られていた。穴のあいた紙や金属のロールでピアノの動きをコントロールし、
ハンマーで弦を叩き、録音された音楽を演奏する。
1959年にウインター(WINTER & CO.)は、エオリアン・アメリカン社と合併し、
社名をエオリアン・コーポレーションに変更していた間、PIANOLAは
ウィンター&カンパニーが製造していたブランド名の一つです
→詳しくはWINTERの項目へ
→Aeolian(エオリアン)の項目も参照 |
| PIANOVA |
詳細不明 |
PIANY
(トレードマークなし)

画像クリックでHPへ戻る
|
ピアニー 全音楽器製造KK(浜松) 詳細不明
PIANY(ピアニー)の登録商標(昭和46年2月登録)は現在、株式会社全音楽譜出版社にあり、
現在はピアノブランドではなく鍵盤ハーモニカの「ゼンオンピアニー」という商品名で使われているようです。
■ピアニーの外観写真 →★ 鍵盤数はかなり少なく61鍵しかありません(音域:C2~C7)
■ピアニー内部を撮影した動画(6秒動画) →★ 鍵盤1つに対して弦が1本しか張られていません
トレードマークはありませんが、「ZEN-ON」と入っているのが分かります(左記画像)
ピアニーの画像と動画はすべて「匿名希望様」からご寄稿いただきました。
この度は画像と動画のご寄稿をいただきまして誠にありがとうございました! |
| PICASSI |
詳細不明 |
PIERRE


画像クリックでHPへ戻る |
PIERRE ピエルレ 東洋ピアノ製造株式会社
“ピエルレ”は、フランス語で宝石を意味する言葉とのこと。
まくり(ピアノ蓋部分)はAPOLLOとなっております。
ピエルレのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★ |
PLAYOTONE
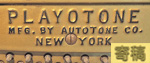
画像クリックでHPへ戻る |
PLAYOTONE アメリカ(ニューヨーク)
HARDMAN PECK & CO. NEW YORK
ピアノ内部には「MFG. BY AUTOTONE CO.」と入っていますが、ハードマンペック以前の頃でしょうか。
詳細不明。
画像は、J.Y.様からご提供頂きました。この度はご寄稿ありがとうございます! |
PLEYEL



画像クリックでHPへ戻る |
PLEYEL プレイエル フランス/パリ
工場:フランス南部アレス 創業1807年
1807年、50歳のイニャス・プレイエル/イニャス・プライエル/イグナーツ・プライエル/
イグナース・プレイエル/イグナーツ・プレイエル/(Ignace Pleyel)はピアノ会社を設立。
(→発音によって色々な読み方があり)
イニャス・プレイエルは、ハイドンの弟子であり友人でした。
プレイエルは1807年に最初のピアノをパリで製作する以前に、41曲の交響曲と、70曲の四重奏曲、
数曲の五重奏曲、そしてオペラを作曲しており、演奏家としても作曲家としても高く評価されていました。
このメーカーはのちに世界の重要な音楽遺産となりました。プレイエルの繊細な響きのピアノは、
極めて微妙なニュアンスを表現できたために人気を博し、「音楽があふれ出すのを感じ、自分自身の音を
鳴らす元気があるときなら、私はプレイエルのピアノを必要とする」と語ったのは、あのF・ショパンでした。
プレイエルの名は、200年近くもの間、ピアノ音楽の歴史と神髄を支えてきました。
類希な才能をもったイグナースは、優秀な作曲家、また発明家として多才ぶりを遺憾なく発揮し、
ヨーロッパから注目を浴びる人物でした。
「ピアノとは、演奏者の声としての楽器であり、そして芸術品であるべき」と主張したイグナースは、
厳選された素材、卓越した技術、豊かな感性が織りなす表現の可能性を信じ、楽器創りにその生涯を捧げました。
彼の思想は、熟練した職人によって堅く守られ、今なお南仏Alesの地で、その音色を響かせ続けています。
プレイエルは、洗練された響き、優雅なタッチ、多彩な表現を放つ名器の代名詞といえましょう。
<歴史>
有名な演奏家で、交響曲やオペラの作曲家でもあったイニャス・プレイエル(1757~1831)は、
楽器の製作に魅せられ、新しい作曲家たちのニーズに応えるピアノを作りたいという欲求に突き動かされ、
パリに会社を設立した。
1807年にプレイエルが最初に製作したピアノは、垂直に弦が張られた小型のアップライトで、
ロンドンでよく見られたコテージ・ピアノをもとに製作したものでした。
プレイエル自身は、ピアノ製作に関する専門家ではなかったが、幸いなことにピアノ事業を開始した初期に
アンリ・パープの助力を得ることが出来た。その時期は1811年からの5年間でパープがイギリスに渡って
ピアノ製造の技術を学ぶことができたのも、プレイエルの資金援助があったからである。
その後、パープは独立してピアノ製作を開始し、プレイエルピアノのライバルとなったが、プレイエルの側も
巧みな方法をとった。当時のヨーロッパに名高かった名ピアニストたちを見方につけたのである。
カルクブレンナーは自ら経営に参加したし、クラーマーやモシュレス、ジョン・フィールドといった
名ピアニスト達は、プレイエルのピアノを賞賛した。その中でも最も力があったのは言うまでもなく
フレデリック・ショパンだった。
19世紀のフランスにおいて、プレイエルはエラールと相競った。セバスチャン・エラールが自らピアノを作る
職人だったのに対して、イグナーツ・プレイエルは経営者であった。しかもこの2人は同じ年に没した。
ちなみに会社を引き継いだエラールとプレイエルの息子たちもなんと同年に没している。
その後、会社が著しく成長すると、イニャスは長男のカミーユを経営者に加えた。
1815年に会社を引き継いだピアニストとしての教育を受けたカミーユは、イギリスとフランスのピアノ製作者や
演奏家たちに接触して意見を求めたり、アイディアを交換したりでき、会社の重要な役割を担うようになった。
生産高は増大していったが、それは一部のプレイエル・ユーザーにとっては残念なことだったようで、
1839年にリストは、ロッシーニが語ったことを手紙の中でこう引用している。
「プレイエルはピアノを多く作りすぎている。彼にはもう、それらの面倒を見る暇がない」と。
1855年、会社はカミーユの義理の息子、オーギュスト・ヴォルフに引き継がれ、
ピアノはプレイエル、ヴォルフ・エ・コンパニー(Pleyel, Wolff & Cie)のブランド名で作られるようになった。
1865年までにプレイエル社は約36,000台のピアノを生産したが、これは27年も早く創業していた
エラール社の当時の生産高とほぼ同じだった。
1887年に会社はヴォルフの義理の息子のギュスターヴ・リヨンに受け継がれ、
プレイエル、リヨン・エ・コンパニーのブランド名で、ハープ、ティンパニー、チェンバロなど、
ピアノ以外の楽器の生産も行われるようになった。
一方、ピアノの生産も続けられ、プレイエラと称する自動演奏ピアノや、ひとつのケースに向かい合った
ふたつの鍵盤が付いているダブル・グランドピアノも作られた。1910年には年間約3,000台の
ピアノを生産するようになり、ピークを迎えたプレイエル社は、フランスの上質なピアノの市場を支配した。
1934年、プレイエル社はアントワーヌ・ボール社を買収する。しかし1961年には財政難に直面し、
エラールとガヴォー合併会社と合併した。この会社は1971年にシンメル社に買収され、
プレイエル・ピアノは毎年少数のみ生産された。それから1994年にラモー社がプレイエル(PLEYEL)と、
ガヴォー(GAVEAU)のブランド名を買い取り、その2年後に、プレイエルはふたたび経営権を取り戻す。
プレイエル社は、南フランスのアレスに最新式の生産および研究開発施設を建設して、
その後も、プレイエルの伝統を忠実に守る素晴らしいピアノを生産した。
<プレイエルのエピソード>
プレイエル社は、デュオクラーヴ(Duoclave)と称するグランドピアノを少数製作しました。
これは、J.ピアゾンが1850年にニューヨークで特許を取得したアイディアをもとにしたもので、
二つの交差弦がひとつの響板を共有し、長方形のケースに収められた楽器である。
プレイエルは気前のよい音楽界のパトロンで、才能ある音楽家を発掘する才に長けた彼は、
1832年にパリのフォブール・サントノーレ通りのサル・プレイエルで催された演奏会において、
あのフレデリック・ショパンをデビューさせました。フランス音楽文化の歴史に名を残したこの二人は
生涯友人であり続け、ショパンはプレイエルのピアノを弾き続けました。素敵な話ですね♪
2008年にアップライト、2013年にグランドの製造を停止しました。
Gaveau(ガヴォー)、Rameau(ラモー)もプレイエル社が製造
エンブレム画像は「PIANO YOSHIKAWA様」よりご寄稿頂きました。ありがとうございます!
<附録>
プレイエルピアノ 製造番号/製造年代 対照表(1810年~2000年) →★
<以下、ウィキペディアより引用抜粋>
プレイエル(Pleyel et Cie)は、フランスのピアノ製作会社である。
ピアノ製作会社「プレイエル商会(Pleyel et Cie )」は、イグナツ・プレイエルと
その息子カミーユ(1788年 - 1855年、ピアノの名手で1815年に父の仕事の共同経営者になった)
によって設立された。この会社はショパンに使用されたピアノを生産し、
また、ショパンがパリで最初に演奏会を(そして最後の演奏会も)行ったコンサートホール
「サル・プレイエル(Salle Pleyel)」も経営した。
19世紀末ころ、プレイエル社は最初の半音階ハープを製作した。
20世紀初頭には、ワンダ・ランドフスカの要請で、ハープシコードの復活に手助けをした。
イグナツ・プレイエルによって1807年にPLEYELを冠した最初のピアノが製造される。
1813年にイグナツは、正式にカミーユにその経営権を譲り、1829年にイグナツの健康状態の悪化を機に
プレイエル親子は財産の整理を始め、長年の友人であるカルクブレンナーが、プレイエルピアノの製造、
販売、貸出を行うPleyel & Co.を設立する。
1855年にカミーユよりオーギュスト・ヴォルフに経営権が引継がれ、ヴォルフは、工場をパリから
サンドニに移動させる。55000m2の広大な工場では、1866年の最盛期には年間3000台のピアノを生産した。
1887年のヴォルフの死を受け、義理の息子であるギュスターブ・リヨンが経営を引き継ぐ。
優れた音楽家でもあり、鉱山技師でもあったリヨンは、製造の近代化に成功する。
1866年には、プレイエルの経営は、パリのロシュシュアールのショールームの他に、パリ市内に2軒、
ブリュッセル、ロンドン、シドニーにそれぞれ1軒ずつ支店を持つまでに成長した。
1927年にパリにサル・プレイエルが建設される。
1930年、リヨンが経営より退く。時を同じくして、1929年のアメリカの株の大暴落を受けたプレイエルの
ピアノ部門が1933年財産管理下に陥る。翌年プレイエル破綻。
サル・プレイエルは、クレディリヨネ銀行に買収され、1998年までその管理下におかれる。
1961年、経済的苦境の中、前年に合併したばかりのガヴォー・エラールと合併し、
ガヴォー・エラール・プレイエルとなる。
この時点で、多くのピアニストの証言からプレイエルの音は消えたといわれている。
1971年に、ドイツのシンメル(Schimmel piano company)により買収され、工場をドイツの
ブラウンシュヴァイクへと移転する。このシンメルによる経営はその後25年に亘る。
この買収劇によって、プレイエルブランドのピアノはドイツ資本となったものの、
技術者たちが出資者たちの援助のもと、北フランスに工場を開き、ラモー(Rameau)の名で
フランスピアノを作り続ける。
サル・プレイエルの所有者であるクレディリヨネ銀行が、1995年に経済的なスキャンダルに見舞われ、
その財産が国の管理下におかれ、競売に掛けられる。翌年、フランス人ビジネスマンの
ユーベル・マルティニがサル・プレイエルを購入し、南仏アレスに移転していたプレイエルの
工場の再生にも着手し、名称もフランス・ピアノ製造会社(Manufacture Francaise De Pianos)に変更する。
翌1998年、サル・プレイエルの実質的な売却が行われ、70年間の分裂を経て、再びプレイエルが一つになる。
サル・プレイエルは2006年9月に再開されオーケストラの公演など多くのコンサートを開いている。
2002年マルティニの要請を受け、アルノー・マリオンがサル・プレイエルと
フランス・ピアノ製造会社の経営に関る。
2006年現在、フランス・ピアノ製造会社は、アラン・ラフォンにより運営されている。
2007年業績不振により、南フランスのアレス工場から撤退し、パリ郊外にアトリエ工房として
再出発を果たす。体制としては受注生産であり、2008年度の生産台数は20台、2009年度は16台と、
零細企業としての経営を余儀なくされていた。
2013年にはついに生産中止を発表。ただし、在庫については当面販売が続けられる。
2014年9月、パリ・ドメニル通りのヴィアデュック・デザールに本社を移転した。
現在は同社ピアノの修復が中心で、グランドピアノのみ特注で製造している。
2016年には中国に販売会社がオープンしている。
<別解説>
1807年、作曲家であり音楽出版者でもあったイグナズ・プレイエルは
フランスのパリにプレイエル社を設立しましたが、この会社が将来的にヨーロッパで最大かつ
最も長い歴史を持つピアノ製造卸売、小売の会社になるとは誰にも予測できませんでした。
1824年、カミーユ・プレイエルが父の後を継いで会社を設立し、
その後、オーギュスト・ウォルフ、ギュスターヴ・リオンと続いた。
プレイエルは、所有者の変遷に応じて、プレイエル、ウォルフ社、プレイエル、リヨン社と
何度か社名を変えた。プレイエルのピアノはパリで製造されていたが、
特に1885年に建設されたサン=ドニの製造工場で製造されていた。
1866年には、年間3,000台のピアノを生産していたという。
1927年にパリにオープンした2,500席のサル・プレイエル(プレイエル・コンサートホール)は、
現在もパリで最も格式の高いコンサートホールとして、ヨーロッパの優れたピアニストや
作曲家たちを招いている。
200年以上にわたって世界的な音楽家たちを見守ってきたピアノメーカーは、
2013年、苦しいフランス経済と中国や韓国との激しい競争についに屈した。
2003年には年間1,000台あった生産台数が、工場閉鎖の年にはわずか20台にまで激減した。
しかし、プレイエルの失敗は、高級品だけでなく低価格帯の市場にも対応できなかったことだ、
と指摘する人もいる。現在のピアノメーカーが生き残るためには、少なくともブランドの一部を
労働力の安い国で作ることがほぼ必須となっている。
プレイエルは、フランス以外の国に生産拠点を移したくなかったため、生産を完全に終了した。
プレイエルのショールームと工房は現在も営業しており、Viaduc des Artsにある。
プレイエルとあの偉大な作曲家である「フレデリック・ショパン」とは切っても切り離せない存在です。
プレイエルはショパンのために2台のピアノを製作し、1830年から1848年にかけて、
ショパンはプレイエル邸で何度も演奏したと記録に残っています。
また、リスト、ドビュッシー、ラヴェルなど、プレイエルのピアノを愛用した偉大な音楽家は数多い。
プレイエルは、ロマンティックな音色と繊細なタッチの感覚に満ちた、真のフランス流のピアノである。
あるレビューでは、プレイエルが生み出す音質を "甘くてビロードのような "と表現している。
プレイエルは1825年にはピアノの構造に金属棒を導入していた
1890年から1920年代まで製造された両端に鍵盤を持つダブル・グランド・ピアノをはじめ、
専門的な訓練を受けた技術者であり、発明家でもあったギュスターヴ・リオンは、
彼の時代にいくつかの重要な貢献をした。 |
PLEYGEL
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
PLEYGEL プレイゲル 森技術研究所(浜松市) 詳細不明
|
| PLUTHNER |
→正しいスペルはPRUTHNER |
| PLYMOUTH |
詳細不明 |
| POESTKOKE |
詳細不明 |
| POHLMANN, LEONHARD |
詳細不明 |
| POKORNY |
詳細不明 |
| POLETTI & TUINMAN |
詳細不明 |
| PONS GARY |
詳細不明 |
POOLE
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
POOLE PIANO COMPANY プーレ アメリカ
当ページの "I" の項目でも紹介した、IVERS & POND(イバース・アンド・ボンド社)の
子会社で、1893年にウィリアム・エイチ・プーレによって設立されたもの。
斬新なピアノを作っているとの情報があるが詳細は不明。
1959年にウインター(WINTER & CO.)は、エオリアン・アメリカン社と合併し、
社名をエオリアン・コーポレーションに変更していた間、POOLEは
ウィンター&カンパニーが製造していたブランド名の一つです
→詳しくはWINTERの項目へ |
PORTSNER
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
フォルツナー 大洋楽器工業株式会社 |
|
PRAMBERGER


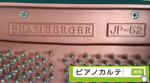


画像クリックでHPへ戻る
|
PRAMBERGER プレンバーガー
島村楽器が販売しているピアノブランド。
※読み方は「プレンバーガー」です。 ×プラムバーガー、×プランバーガーではありません。
製造:ユンチャン(Young Chang) 韓国製 →詳しくはYoung Chang(ユンチャン)の項目へ
細部にまでこだわったデザイン性や作りはなかなか良く音量も十分鳴るピアノです。
ただ、主観ではありますが音色にもっと繊細さがあると良いピアノになるかと。
三代目、ジョセフ・プレンバーガーという NYスタインウエイで設計・技術マネージャーをしていた人が設計し、
韓国のユンチャン(YOUNG CHANG)に製作してもらっているピアノとのこと。
<機種バリエーション>
アップライトピアノ:PV-118、PV-115、PV110、PV118、JP-52、JP-121、JP-125等
グランドピアノ:JP-185等 (グランドはほとんど輸入されていないとのこと)
1枚目と2枚目の写真は、プレンバーガーJP-52で、3枚目と4枚目の写真はグランドのJP-185です。
グランドの方の画像は、「Atelier Sonorite」様からご寄稿頂きました。ありがとうございます!
UP機種バリエーションとしては、スタンダードモデル・インテリアモデル・ハイクラスモデルがある。
プレンバーガーの保証書 →★ プレンバーガーのまくり(蓋部分)銘柄マーク
→★
プレンバーガーの親板内側に貼られたハングルで書かれた検査シール →★
プレンバーガーピアノ(グランド)の外観写真 →★
<島村楽器のHPに記載の紹介文から抜粋>
プレンバーガーピアノは、世界中の厳選された素材を使用して製作されています。
その歴史はさかのぼること約200年。
プレンバーガー家は、1800年代から活躍するピアノマイスターの家系でした。
1987年、ジョセフ・プレンバーガーが「PRAMBERGER」を立ち上げます。
ジョセフは、ニューヨーク・スタインウェイ社において設計・デザインを担当。
「最高のパフォーマンスは優れた設計のもとに成立する」という彼の思想に基づき、
優れた設計・デザインを有しています。
彼が長いキャリアの中で積み重ねた知識と、ピアノマイスターとしての伝統の継承、
そして技術革新がもたらしたこの高品質なピアノは、今や米国を中心に世界中で愛用されています。
芸術的な逸品に、きっとご満足頂けると思います。
プレンバーガーのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★ |
| PREIN, FRIEDRICH |
詳細不明 |
| PREMBERGER |
PREMBERGER× →正しくは、PRAMBERGERです |
| PRESIDENT |
詳細不明 |
| PRESTEL |
詳細不明 |
PRICE & TEEPLE
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
プライス&ティープル アメリカ(イリノイ州シカゴ) 創業1902年
プライス・アンド・ティープル・ピアノ社は、1902年にイリノイ州シカゴで設立された。
当初はイリノイ州カンカキーの工場でピアノを生産していたが、
その後移転してプライス・アンド・ティープル社となったのである。
プライス・アンド・ティープル社は、カールトン、コリンズ、プライス、ティープルという名前でも活動していた。
"カールトン、コリンズ、プライス・アンド・ティープル」、「シェーファー」、「シンフォノーラ」、
「レンブラント」、「ハーモノーラ」、「オートリリック」、「アートシンフォノーラ」。
興味深いことに、同社はコイン式ピアノ(コインを入れると曲が流れるという楽器)も作っていた。
現代のジュークボックスのようなものです。
1937年、Price and Teeple社はStory and Clark社に買収された。
プライス・アンド・ティープル社のピアノは、その美しいデザインと外装の美しさから、
多くのピアノ弾きに支持されました。 |
|
PRIMATONE

 





画像クリックでHPへ戻る
|
PRIMATONE プリマトン
※「プリマトーン」という伸ばす発音表記の資料も散見されますが、正式には「プリマトン」のようです。
合資会社大塚ピアノ商会(発売元)横浜元町
シュベスターピアノ製造KK(東京都蒲田)、協信社ピアノ製作所(製造)(東京都蒲田)
大正10年、沢山清次郎氏と大塚錠吉氏が共同でピアノ店を出したのが始まり。
フレーム部分には「ESTABLISHED NOV.30 1920」創業1920年(大正9年)11月20日とありますが、
どちらにしましても大正9年~大正10年頃創業のようです(下から2枚目の写真参照)
その後大塚氏のみで大塚ピアノ商会を作り、横浜元町の名店の一つになりました。
国産ピアノの最高級品を目指して斉藤ピアノ株式会社など、いくつかのピアノ工場にオーダーをしていました。
シュベスターピアノの工場で製作した時期が長く、レンナーアクションを使用した
高級品が多いのが特徴です。 レンナーアクションの写真 →★
グランドのまくりの部分にあるシュベスターピアノのプレート →★
グランドのまくり部分のプレマトンの銘柄ブランド部分 →★
側板にある当時特定の方が物品税を免除出来た「〇に免(通称:まるめん)」のマーク →★
一番下のトレードマークはPRIMATONEのグランドで、デザインがとても珍しいです。
この珍しいトレードマークは、H.Y.様からご提供頂きました。ありがとうございます!
※シュベスターの項目も参照 |
PRINCETONE

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
PRINCETONE プリンストン
製造:富士楽器製造(浜松)、発売元:東京ピアノ商会(外国ピアノ輸入商会)東京銀座
外国ピアノ輸入商会、後の銀座の東京ピアノ商会のブランド。富士楽器に製作を依頼していた。
皇太子殿下の誕生を祝って特に命名されたという。三越本店に納入されていた。
|
PRINCIPAL

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
PRINCIPAL プリンシパル
ピオバ楽器社(製造)東京都神保町
東京神保町のピオバ楽器社は、ピアノ調律師の野口喜象氏の出店であるが、
この名前でピアノを製造販売したことがある。
野口喜象氏が没した後は野口ふみ未亡人が社長になった。
|
| PROBST, GEORG |
詳細不明 |
| PRODUKTIV-G.,E. |
詳細不明 |
| PROKSCH, A. |
詳細不明 |
| PROSKOWEC |
詳細不明 |
PROTHNER
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
PROTHNER プロスナー/(プロッスナー)
プロスナー社 詳細不明 |
| PROTZE |
詳細不明 |
PRUNIER

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
PRUNIER プルニェール/プルニエール/プルニエ
大倉楽器工業(株)東京都杉並区上高井戸、広田ピアノ(ヒロタピアノ)
二本弦の小型ピアノが多かったが、大型のものは音色に特色があった。
その他のピアノあり。
|
PRUSSNER
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
PRUSSNER プロスナー ドイツ 詳細不明
|
|
PRUTHNER


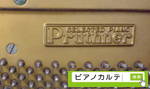
画像クリックでHPへ戻る
|
プルツナー/(プルッツナー) PRUTHNER
<注意>ブランドスペルはPLUTHNERではありません(×→PLU ○→PRU)
(ちなみに古いプルツナーはHの後に”U”が入るこのような表記だったようです→PRUTHUNER)
大洋楽器工業株式会社(岡本工業所)
株式会社 プルツナーピアノ
有限会社 及川ピアノ製作所
カールザイラーとともに(株)プルツナーピアノで作られていたブランドで、
昭和20年から浜松の岡本工業所で作られてきました。
昭和29年に有限会社 太洋楽器工業に、昭和37年6月に株式会社に改組、
その後、社名を(株)プルツナーピアノへと変更。
音色はデフォルトではかなり固めな感じですね。
プルツナーピアノのまくり部分(蓋部分)のブランド銘柄
→★
機種:P-3等
<附録>
プルツナーピアノ 製造番号/製造年代 対照表(1970年~1988年) →★
プルツナーのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★ |
PRUTHUNER
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
製造年が古いプルツナーは”U”の入るこの表記でした
岡本工業所(浜松)、大洋楽器工業株式会社 |
| PSALMIST |
詳細不明 |
| PURCELL |
Estey Piano Corporation
→詳しくは「Estey」の項目へ |
上記Pから始まるブランドの中で、追記出来そうな事項や新情報を発見した場合、修正受付フォーム よりお気軽にお知らせ下さい。
どんな些細な情報でも構いませんので、広く皆様からのフィードバックをお待ちしております。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
 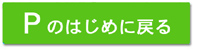 



ピアノ銘柄ブランド
トレードマーク 紹介
& 知名度ランキング

|

メーカー/ブランド説明・会社沿革・歴史・製作者・特徴・音色・他
|
Q★PIANO
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
Q PIANO キュー・ピアノ/キューピアノ
ブランド名の真ん中に星印(★)が入る珍しいブランド名です
超小型でカラフルな外装、かわいいコンパクトピアノです(鍵盤数73鍵)
発売元:音気楽(おきらく)工房株式会社(神奈川)
製造元:東洋ピアノ製造株式会社 |
QUANDT
QUANDT, J. C
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
読み方不明 QUANDT,J.C ドイツ 詳細不明 |
| QUANTE |
→F. QUANTEへ(頭文字”F”からはじまる項目へ) ※スペルはQUANPEではない |
QUEEN BELL

このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
QUEEN BELL クイーン・ベル/クイーンベル/クウィーンベル/クウィーン・ベル
※各所に間違った資料が散見されますが、スペルは「QUEENBEL」ではなく、「QUEENBELL」です。
共同工作所(横須賀市追浜) ※協同工作株式会社(楽器部)という情報もあり、未確認
クイーンベルピアノ株式会社
森健氏が参加して横須賀市で作ったピアノ。
横須賀市追浜の海軍工廠(※)の跡地でピアノを作る話となり、
森健氏や榊原清作氏が呼ばれて生産を開始したが長くは続かなかった。
(※)工廠(読み:こうしょう)とは、軍隊直属の軍需工場のことで、武器・弾薬をはじめとする
軍需品を開発・製造・修理・貯蔵・支給するための施設をいいます。
トレードマークはそのブランド名称の通り、鈴(ベル)のマークをモチーフにしたデザインです。 |
| QUISPEL |
詳細不明 |
上記Qから始まるブランドの中で、追記出来そうな事項や新情報を発見した場合、修正受付フォーム よりお気軽にお知らせ下さい。
どんな些細な情報でも構いませんので、広く皆様からのフィードバックをお待ちしております。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
 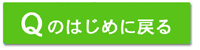 



ピアノ銘柄ブランド
トレードマーク 紹介
& 知名度ランキング

|

メーカー/ブランド説明・会社沿革・歴史・製作者・特徴・音色・他
|
| R. GÖRS & KALLMANN |
ドイツ |
| R.S.HOWARD |
R.S.HOWARD CO アメリカ(ニューヨーク)
→詳しい解説は「HOWARD R.S.」の項目へ |
| R.F. WILKS & CO. |
R.F. Wilks & Co. TORONTO
カナダ(トロント) 詳細不明 |
R.S. WILLIAMS
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
R.S. Williams カナダ(オシャワ) 創業1873年
The William Piano Company/R.S.William and Sons
1873年、カナダのオシャワにThe William Piano Companyが設立されました。
1888年、リチャード・スグデン・ウィリアムズがウィリアム・ピアノ・カンパニーの経営権を取得し、
社名を「カナダ・オルガン・アンド・ピアノ・カンパニー」に変更した。
数年後の1909年には再び社名を変更し、R.S.William and Sons Ltd.となった。
1931年、同社は閉鎖された。
1931年、楽器の需要不足と世界恐慌の影響を受け、会社の再建は不可能となった。
R.S.ウィリアムズのピアノは世界中に輸出され、オーストラリア、ニュージーランド、日本などで人気を博した。
アップライトピアノやグランドピアノに加えて、プレーヤーピアノも製造しており、人気を博していた。
なお、R.S.ウィリアムズの名で生産されたピアノについては、ほとんど知られていない。 |
RACHALS
M.F. RACHALS



画像クリックでHPへ戻る |
RACHALS/M.F.RACHALS ドイツ(ハンブルグ)
創業1832年 M.F. RACHALS & CO.
読み方は不明なのですが、例えば
ラッハルス/ラハルス/ラヘル/ラヘルス/ラッハル/ラッヘル/ラハール/ラッヘルス等だと思います。
※英語読みだと「レイチェルズ」となりますが、ドイツなので上記の読みのような感じとなります
1932年に廃業したとの情報を載せていましたが、何故か現在もRACHALSピアノの公式ページがあります。
理由は不明ですが一応URLを貼っておきます。
■RACHALSのホームページ→http://m.f.rachals.de/
■RACHALSのフェイスブックページ→https://www.facebook.com/mfrachals/
左記トレードマークの画像、並びにその他の画像はすべて「白石准様」からご寄稿頂きました。
この度は貴重な写真をご寄稿頂きまして誠にありがとうございます!
王が楽器を弾いている画像のようです。トレードマークとしてはかなり珍しいタイプのデザインに感じます。
写真を提供して頂いた白石様によりますと、このピアノは作曲家だったお父様の形見だそうです。
家に来たのが1970年頃で、その前は、あの「月の沙漠」を作曲した佐々木すぐるさんの所蔵だったようです。
1920年代の楽器で、鍵盤の数が85鍵しかありません。
そして最低音の横の拍子木の部分に、オルガン機構のようなマフラーフェルトを降ろすレバーが付いています。
一応、3本ペダルで、真ん中がそれなのですが、固定は出来ず、ここのレバーで固定します。
輸入元が銀座の十字屋ですが、蓋の裏側にプレートがあって、東京市京橋區とあるので歴史を感じます。
との情報も頂きました。下記、貴重な追加画像も頂きましたので掲載させて頂きます。ありがとうございます!
■マフラーフェルトのレバー部分の写真(SOURDINE/弱音器)と書いてありますね →★
■輸入元である銀座十字屋のプレート写真がこちらです →★ ■RACHALSの外装写真 →★ |
| RADCLIFFE |
詳細不明 |
| RAEHSE-REPIA |
詳細不明 |
| RAHMANN |
詳細不明 |
RAMEAU

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
RAMEAU ラモー
フランス(プロバンス地方)1973年~2000年頃まで
小型ピアノが、プロバンス地方で作られるようになった。グランドも少し作られたとのこと。
Gaveau(ガヴォー)、Rameau(ラモー)もプレイエル社が製造 |
| RAMSBERGER |
詳細不明 |
RANGER
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ランガー 渡辺留司氏(横浜市中区西前町) |
RAPHAEL

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
RAPHAEL ラファエル
製造元:東洋ピアノ製造株式会社
発売元:島村楽器株式会社
HPより抜粋:中古クラスの価格でお求めいただける質の高い新品ピアノを提供したい、
その思いを込めて開発したピアノです。
響板に高級材アラスカ産シトカスプルースを採用、オールウッドのアクションを採用。
|
| RATHKE, R. |
詳細不明 |
| RAUDENBUSH & SONS |
詳細不明 |
| RAUZER |
詳細不明 |
| RAVENSTEIN |
詳細不明 |
RAVENSCROFT

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
RAVENSCROFT
製造:アメリカ アリゾナ州
読み:レイヴンズクロフト/レーベンスクロフト/レイブンスクロフト/
レイヴェンスクロフト/レイベンスクロフト(発音の仕方で表記に多少の違いあり)
機種は2種類あり、モデル220とモデル275があります。
フルコンサートグランドである「Model275」の価格はなんと28万ドル(USD)、日本円で3000万円とのこと。
ちなみに「Model220」も23万ドル(USD)もします(2400万円)!
実際に音色を聞いた事がないので本当に良い音なのか不明ですが、DTM音源としても使われているようです。
※とあるホームページでの紹介では、低音域がファツィオリの音色に近く、中音域がスタインウェイで、
そして高音域がヤマハのC7に近いとの紹介あり。そのため全く新しいピアノに仕上がっているとのこと。
早く実際にこの耳で聞いてみたいです^^
実機のホームページはこちら(英語サイト)→★ |
| RAZAR |
→LAZAR ラザール の項参照
|
| RE-RENDO |
Re-Rendo(リ・レンド)
WESER BROTHERSが製造していたブランド
→詳しくはWESER BROTHERSの項目へ |
REAS. HERMAN



画像クリックでHPへ戻る
|
REAS. HERMAN リーズヘルマン
製造元:平和楽器製造株式会社
製造元:スタインリッヒピアノ製作所(浜松)
リーズヘルマンの外観写真 →★ リーズヘルマン内部に設置の調律記録カード →★
リーズヘルマンのまくり(蓋部分)の銘柄マーク →★ さらに引いた画像 →★
リーズヘルマンの純正キーカバー(STEINRICH PIANOと書いてありますね) →★
※左のトレードマークと上記画像すべて匿名希望様からご寄稿頂きました。ありがとうございます!
※ドイツに”リーズハルマン”RIESE HALLMANN”というピアノあり |
| RED OCTOBER |
詳細不明 |
| REGENT |
詳細不明 |
| REGINALD C. FOORT |
詳細不明 |
| REICHELT & BIRNBAUM |
詳細不明 |
REID-SOHN
REID SOHN

画像クリックでHPへ戻る |
REID SOHN レイドソン 韓国
韓国のサミック社がインドネシアで製造するピアノ
その他詳細不明
機種バリエーション:SU108等
※参考
下記に列挙するブランドはすべて同じ雰囲気のトレードマークとなっており、どれも韓国製造と思われます。
REID-SOHN、KAFMANN、SAMICK、SCHNABEL、WEINBURG、U. WENDELL、UHLMAN SUPER |
| REINGARDT, V. K. |
詳細不明 |
| REINHARD |
詳細不明 |
REINHOLD
※トレードマークなし |
REINHOLD ラインホルド
東京蒲田楽器製作所(蒲田ピアノ修理所) |
| REINO IKONEN |
詳細不明 |
REINVOLT
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
REINVOLT ラインボルト/レインボルト
株式会社 鈴木楽器製作所/鈴木ピアノ製作所(磐田市) 詳細不明 |
| REISBACH |
詳細不明 |
REISLAN
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
REISLAN レイスラン イギリス(ロンドン) 詳細不明 |
REKEWITZ
REKEWITZ, WILH.

画像クリックでHPへ戻る |
REKEWITZ 読み方不明(レイケヴィッツ?レイケウィッツ?レケウイッツ?) ドイツ 詳細不明
ピアノ天屋根の裏側の部分 →★ ピアノまくり(蓋部分)の銘柄ブランド部分 →★
※エンブレムやその他の画像は「匿名希望様」からご寄稿頂きました。ご寄稿ありがとうございます! |
RENN
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
RENN レン イギリス 詳細不明
|
RENNER

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
RENNER レンナー
喜多楽器店(発売元)、マイシュナーピアノ製作所(製造)
関西のピアノメーカーであるマイシュナーピアノ製作所が
喜多楽器店の依頼でレンナーハンマーを使用したものにつけられたブランド。
日本ピアノ製作所(西宮)、日本ピアノ製造株式会社、竜生楽器研究所という情報もあり |
| REPIA |
詳細不明 |
RESOTONIC
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
Resotonic レゾトニック?読み方不明
1959年にウインター(WINTER & CO.)は、エオリアン・アメリカン社と合併し、
社名をエオリアン・コーポレーションに変更していた間、RESOTONICは
ウィンター&カンパニーが製造していたブランド名の一つです
→詳しくはWINTERの項目へ |
| RHIENDORF |
詳細不明 |
RICHARD HARWOOD & SONS
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
イギリス(ロンドン)
ピアノ内部の刻印
MANUFACTURED FOR HARRODS BY THE AEOLIAN Co. LTD |
| RICHARD LIPP & SOHN |
詳細不明 ※スペルRicard Lipp? |
| RICHMANN |
詳細不明 |
RICHMOND
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
リッチモンド アメリカ(インディアナ州リッチモンド) 創業1878年
リッチモンド・ピアノ・カンパニーは、1878年にインディアナ州リッチモンドで設立されました。
今世紀に入って間もなく、リッチモンド・ピアノ・カンパニーはスター・ピアノ・カンパニーに買収されました。
リッチモンドは、高価なスター・ブランドのピアノに代わる、よりコストパフォーマンスの高いピアノとして
製造・販売されました。
スターピアノは、当時のピアノ関係者の間で評判になっていたので、
リッチモンドピアノはスターと一緒に販売カタログや店舗で売られていた。
スター・ピアノ・カンパニーは、20世紀初頭の経済的変化をうまく乗り切った。
アメリカのピアノメーカーの中では、大恐慌の際もその後も個人経営を続けた
数少ないメーカーの一つであった。1950年代までリッチモンドピアノの生産を続けていた。
リッチモンド・ピアノ・カンパニーは、非常に良質なピアノを手頃な価格で製造していた。
1913年に掲載された広告では、リッチモンドピアノの特筆すべき点として、
「プレーヤーのメカニズムが極めてシンプルであること、迅速かつ同調性の高いレスポンス、
コントロールが容易であること、標準的なトラッカーボードを備えていること」などが挙げられていた。 |
RICHTONE



画像クリックでHPへ戻る |
RICHTONE リッチトーン
製造元:有限会社 松本ピアノ工場(千葉)
製造元:斉藤ピアノ製作所
発売元:合資会社 東京ピアノ商会→東和ピアノ株式会社?(東京青山)
発売元:中島ピアノ
東和ピアノ株式会社(発売元)東京青山、中島ピアノ(発売元)、松本ピアノ(製造元)千葉
東京青山のピアノ店の東和ピアノが自社銘柄として特に吟味したピアノ。
松本ピアノ(千葉)製が多い。
東和ピアノの創設者中島順二郎氏は沢山清次郎氏の東京ピアノ商会の門下生で、
既に亡くなったが、未亡人により運営されていた。
ヤマハ、シュベスター、マツモトを取り扱い、リッチトーンは沢山氏の免許ブランド。
上から2枚目の画像に入っている文字は、「ESTABLISHED 1882」です(1882年設立という意味)
1882年に何らかの組織として発足したという意味で、ピアノを作り始めたのがこの年ということではないです。
ちなみに日本で最も古いピアノ製造会社である日本楽器(現:ヤマハ)の創業が1900年です。
リッチトーンのまくり(蓋部分)の銘柄マークと、歴史を感じるキーカバー →★
リッチトーンの前パネルを外した状態での外観写真 →★
※トレードマーク画像を含め、計4枚の画像は匿名希望様からご寄稿頂きました。ありがとうございます! |
| RIDGEWOOD |
詳細不明 |
| RIEDEL BERLIN |
ドイツ 詳細不明 |
|
RIEGER KLOSS
RIEGER-KLOSS



画像クリックでHPへ戻る
|
リガークロス/リーガークロス
RIEGER KLOSS チェコスロバキア製 (イフラヴァ:都市名)1871~
販売元:東洋ピアノ販売
年間約3000台を生産、ヨーロッパの主なピアノメーカーに位置しています。
そのうちの97%を輸出が占め、日本をはじめ、カナダ・アメリカ等へ送り出されています。
アップライトピアノは9モデル、グランドは158cm~272cmまで4モデルを揃えていますが、
日本でのニーズを考えUP・GPいずれも小型の機種に絞って輸入されています。
チューニングピン(ピン味)がやや固く、新品時から音が落ち着くまでかなり時間がかかりましたが、
総合的によく出来たピアノと感じました。しっかり作りこまれたピアノという印象です。
ちなみに、シュレーゲル(SCHLÖGL)というピアノも同じトレードマークです。
RIEGER KLOSS の純正キーカバー(国内メーカーにはないデザインですね)
→★
リガークロスのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★ |
| RIESE |
詳細不明 |
RIESE HALLMANN
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
RIESE HALLMANN リーズハルマン(リーズ・ヘルマン)
ドイツ(ベルリン) その他詳細不明
※日本のスタインリッヒ製作所製に”リーズヘルマン(REAS. HERMAN)”というピアノがありますが、
このドイツ製ピアノとはスペルが違いますのでご注意下さい。→詳しくは「REAS. HERMAN」の項目へ |
| RIGA |
詳細不明 |
| RIJKEN |
詳細不明 |
| RIJKEN & DE LANGE |
詳細不明 |
RINBEL
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
RINBEL リンベル アトラスピアノ製造株式会社 |
| RINDEN ? |
スペル不明 RINDEN? リンデン 中国(北京) 詳細不明
|
RINDNER
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
リンドナー 詳しいスペル不明→RINDNER? アイルランド
フィリピンで組み立てられていたらしい 詳細不明
|
RIPPEN


画像クリックでHPへ戻る |
リッペン RIPPEN オランダ 創業1937年
創業から3年ほど経った1940年の製造台数は年間わずか50台であったが、
1950年には10倍の500台、1960年にはそのまた10倍の5000台の
製造台数になり、戦後目まぐるしい生産数増加を果たしたのは我が国のヤマハ、カワイなどの
我が国のピアノメーカーと、このリッペンぐらいであろうと思います。
リッペンは従来の殻を破った特殊なもので、その特徴としては次に挙げる点がある。
1、重量が驚くほど軽い(※当時としては)
アップライトピアノの場合、2人で簡単に持ち運べる程度の重さといいます。
従来のピアノは重いものと相場が決まっていたが、このリッペンピアノの場合、
6フィートのグランドでも500ポンド(230Kg弱)でした。
その理由は主としてフレームが特殊なスチールで作られていることによります。
また、アップライトピアノには運搬の際に便利なように、鍵盤が折り畳めるよう
工夫されたものもあり、これは廊下などの狭い場所を通り抜けて運ぶ場合に好都合です。
2、プラスチック製のアクションを採用している(これが本当に良いかは未知数)
これは当時としては革命的なことで、耐湿性のプラスチックの採用によって
湿度の高い地方でもアクションがスティックすることがなく、またどんなに乾燥しても
ガタがくることがないと言われ、当時のリッペンの広告にはアクションを水に浸し、
その横で金魚が泳いでいるという広告写真がある。
3、特殊スチールのフレームを使っている
ピアノが重いのはフレーム(鉄骨)に鋳造鉄を使用するからで、これをリッペンでは
特殊スチール、しかも中空のパイプ式を使用しているからであります。
これはまったく斬新な考え方で、軽量にあるにも関わらず3万5千ポンド(15.8t)
にもなる弦の張力にも十分耐えるといいます。
この他、リッペンには弦が緩む危険性が少ないチューニングピン、アルミニウムのレール、
特殊な構造で絶対にひび割れしない(?)というスプルースの響板、プラスチックと
アルミニウムのキー、また、キーのバランスを取る鉛の代わりのスプリングなどの
考案が加えられています。これらの画期的な構造は1961年から採用されているようです。
音色は小型ながら極めて優れているといい、高音の抜けも良く、また低音のボリュームも
十分であるが、徹底的な構造の合理化設計により、しゃがんでピアノを見ると、
下前板(下パネ)上部の大きな隙間から弦が見えたり、底板がないため鍵盤の隙間から
ペダルが見えたりと、あまり体裁の良いものではない。
価格はヨーロッパのピアノとしては最も廉価で、アメリカをはじめ世界各国へ輸出されている。
<以下、ウィキペディアより引用抜粋>
リッペン(Rippen)は、オランダ生まれのピアノブランド (1937-2007) である。
リッペン(あるいは、リンドナー)は、運搬が容易なピアノとして、最もよく知られている。
1991年に一旦破綻した後、ブランドは新たなオーナーに買収され、中国煙台市で2007年まで製造された。
リッペンはオランダで生まれたピアノメーカーである。
1937年に設立され、1950年までハーグでピアノを
1950年頃、リッペンはアルミニウムとプラスチックを多用した「マエストロ」という名の
軽量で廉価なピアノを開発し、第二次世界大戦後の人々の経済状況と相まって、大きな成功を得た。
80%が英国、ドイツ、フランス、アメリカ合衆国に輸出された。
さらに、1964年ごろアイルランドのシャノンにも工場を設立し、
「リンドナー」ブランドの軽量で廉価なピアノを製造した。
軽量という特徴を生かし、航空機での輸送が活用された。
1970年代に入って、ピアノの市場は大きく変化した。
電子ピアノの登場によって、廉価ピアノの需要は減少し、1972年にシャノンの工場は閉鎖された。
いくつかの買収や再生の試みがなされたが、1991年2月にリッペンは解体された。
その後、オランダの楽器商、ミュージック・ブローカーズ・インターナショナル
(Music Brokers International)がリッペンブランドのピアノの製造権を取得した。
1991年から1998年まで、ロシアのサンクトペテルブルクで製造された。
部品のいくつかは、中国の煙台市から供給された。
1998年から2003年までは、煙台市のYantai Longfeng Pianoで製造された。
2004年から2007年まで、煙台市のペレツィーナ
(Yantai Perzina Piano Manufacturing.Co.,Ltd.)で製造された。
この工場では、同じオーナーのペレツィーナブランドのピアノが今日も製造されている。
また、オーナー会社のホームページには、リッペンピアノのラインナップが、
この会社が製造権をもつ他のブランド(EAVESTAFF, Gehr.Steinbergなど)とともに現在も掲載されている。
ここではエーデとシャノンで製造されたピアノの特徴について述べる。
アルミニウムとプラスチックを多用した「マエストロ」は、交差配弦ではなく、
平行配弦の構成をとっていた。このため、ハープ形状のようなデザインとすることも可能であった。
あるピアノの重量は、僅か34Kg(75ポンド)であった。
これは、通常鋳鉄を使用するフレームにアルミ材を用い、ケースなど木製の部品を可能な限り
プラスチックで置き換えた成果である。シャノンで製造されたリンドナーは、交差配弦であったが、
フレームはアルミニウムの管材を溶接した構成で、鍵盤にもプラスチックを使った設計となっていた。
ピン板はブッシング付きフレームタイプではなく、むき出しであった。
また、アップライトピアノは鍵盤部分を、グランドピアノはケース全体を折りたたみ可能という
特徴をもっていた。これにより、同じスペース中により多くのピアノを並べて輸送することができた。
軽量で折りたたみ可能という特徴は、ピアノの運搬の問題を解決する、一つの革新とも言えた。
特に航空機による輸送に適していた。
アルミニウムフレームの技術を生かして、薄型のアルミニウムグランドピアノなど、
デザイン性の高いピアノも製造した。
しかし、これらの軽量廉価ピアノは、長期耐久性に難点があった。
特に空洞三面構造の鍵盤はスナップインタイプとなっており、ロックを解除せずに取り外そうとすると
破損することがままあった。製造元が消滅した今、プラスチック製の特殊なスペアパーツは入手不可能であり、
一般的なパーツでの代替はできない。一旦破損すると修理は困難となる。
このため、中古品市場で見かけるリッペンまたはリンドナーの軽量ピアノは、
その時点で正常に動作していても決して手をだしてはならないピアノとされている。
他の珍しい特徴としては、逆クラウン響板がある。
3層合板製の響板と響棒はそれ自体平らな形状であり、弦圧がかかることによって、
逆クラウン形状になった。クラウン形状をもつ響板には、各ピアノメーカー独自の設計と
ノウハウが注ぎ込まれており、製造には手間もかかる。
平板合板の響板は、ピアノの低コスト化に大いに貢献したと考えられている。 |
RIPPEN
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
リッペン アイルランド?オランダ? 詳細不明 |
RITMULLER
RITMÜLLER
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
リットミューラー RITMÜLLER
ドイツ、ゲッティンゲン(Göttingen)
<以下、ウィキペディアより引用抜粋>
W. リットミュラー&ゾーン(W. Ritmüller & Sohn)AGは、
ドイツ・ゲッティンゲンに起源を持つかつて存在したピアノ製造業者である。
18世紀末、アンドレアス・ゲオルク・リットミュラー(Andreas Georg Ritmüller)と
息子のゴットリーブ・ヴィルヘルム・リットミュラー(Gottlieb Wilhelm Ritmüller、1770/1772-1828/1829)は
ゲッティンゲンでリュート、ギター、ハープの製作を始めた。
ゴットリーブ・ヴィルヘルム・リットミュラーは1794年11月17日に市民権を取得し、
1795年8月5日に市民宣誓を行った[3]。後者がスピネット、クラヴィコード、リュート、ギター、
ハープの工房を構えた日付と見なされている。
1800年頃に父が死去した後、工房は正式に「G. W. Ritmüller」と名付けられた。
ゴットリーブ・ヴィルヘルム・リットミュラーの2人の息子ヨハン・ヴィルヘルム(1802年生)と
ヨハン・マルティン(1803年生)が会社に加わった。
ゴットリーブ・ヴィルヘルム・リットミュラーは1829年に死去し、
会社は「W. Ritmüller & Sohn」に改名された。
会社は1890年に破産し、売却された。
所有者や共同経営者を変えながら、ピアノ生産はゲッティンゲンと後にはベルリンで続けられた。
会社は1901年に有限会社(GmbH)に、1920年に株式会社(AG)に移行した。
財政問題によって生産施設はGebr. ニーンドルフ・ピアノフォルテファブリックAGに貸された。
1933年、W. Ritmüller & Sohn社は清算された。
1990年から、中国のパールリバー・ピアノ・グループがドイツと世界中で「Ritmüller」の商標を登録し、
1997年以降「Ritmüller」ブランドのピアノを製造・販売している。
現在流通しているリットミュラーのほとんどは中国製造のパールリバー社製です。 |
| RITTER |
詳細不明 |
RIVIERE

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
RIVIERE リヴィエール/リビエール
ブランドスペルは「RIVIER」ではなく、「RIVIERE」です(最後にEが入ります)
森技術研究所(浜松)、河合楽器株式会社(京橋カワイ)
河合楽器(京橋カワイ)が東京の百貨店に売り場を持つとき当ブランドを売り出していた。
※京橋カワイについてはKAISER(カイザー)の項目を参照 |
ROADRICH

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ロードリッヒ ROADRICH
有限会社 野田ピアノ製作所
浜名楽器製造株式会社(浜松市和田町560)
ロードリッヒピアノ製作所(浜松) |
ROBIN
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ロビン
製造元:株式会社 内外ロビン楽器製作所(浜松市)
発売元:有限会社 帝国楽器貿易商会 |
| ROBINSON |
詳細不明 |
ROBSON
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ロブソン 詳細不明
※カナダのケベックにROBSONという楽器メーカーがあるが、関係は不明 |
RODESTEIN
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
RODESTEIN (S.RODESTEIN) ローデスタイン (S・ローデスタイン)
松本ピアノ 詳細不明
|
ROGERS

画像クリックでHPへ戻る
|
ロジャース フクヤマピアノ製造? 詳細不明
トレードマーク画像はなし(確認済み) |
ROGERS
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ロジャース LONDON(ロンドン) 詳細不明 |
| ROGERS, GEORGE |
詳細不明 |
| ROHLFING |
詳細不明 |
| ROHR, ALFRED |
詳細不明 |
|
ROLEX







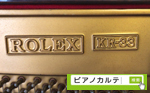
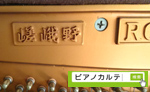
画像クリックでHPへ戻る
|
ローレックス ROLEX
製造元:大成ピアノ製造株式会社
製造元:東日本ピアノ製造株式会社
のちに、浜松ピアノ製造株式会社(浜松市和田町552番の3)(※会社の実体なし)
発売元:協立楽器(株)=全日本ピアノ卸センター株式会社(神戸市中央区元町通4丁目)
大成ピアノ製造(株)において製造されていた協立楽器のブランドでした。
お客様から、時計メーカーのロレックスと同じですか?とよく聞かれましたが、
まったく関係ありません。王冠マークは真似をしていますが(笑)
「ROLEX」の呼び方ですが、我々調律師の間では「ローレックス」と言っていました。
「ロレックス」と伸ばさない発音で説明している俄かサイトもちらほらありますが、
調律師の仲間内での言い方は伸ばす言い方「ローレックス」が一般的でした。
「ロレックス」だと時計ですもんね。
■機種バリエーション
KR22、KR27、KR30、KR31、KR33、
RX230、RX300、RX380、RX500、RX600、嵯峨野、孔雀、飛鳥、王朝など
孔雀、飛鳥、王朝はとりわけ高く、当時標準小売価格は孔雀 1,094,000円、
飛鳥と王朝の標準小売価格が1,267,000円でした。(付属品含む)
ただし、この高級グレード(孔雀、飛鳥、王朝)はほとんど売れなかったので、
私自身もほとんど見たことがありません。比較的安価な木目調の嵯峨野はよくお目にかかります。
標準小売価格(定価)は協立楽器の戦略か知りませんが、大幅値下げを売りに付けられていた
所謂ダミー価格なので、実際にはすべてのローレックスピアノは標準価格の3~4割引くらいの値段で
買えることが多かったようです。国内に於けるピアノ販売最盛期には実にたくさん売れたピアノです。
協立楽器株式会社(神戸市)がブランド販売を始めた頃は頭文字のKをとってKR~という型番になっています。
<附録>
協立楽器の販売保証書 →★ 大成ピアノ製造の保証書 →★ ローレックスのキーカバー →★
<ピアノ調律技術者向け附録>
張弦作業に役立つ当該機種ミュージックワイヤー配線仕様 →★
ローレックスのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★ |
| ROLLER & BLANCHET |
詳細不明 |
| ROLOFF, H |
詳細不明 |
ROMHILDT
RÖMHILDT
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ROMHILDT→読み方不明 ドイツ 詳細不明
|
| RONALDI |
詳細不明 |
RONISCH
KARL RÖNISCH



画像クリックでHPへ戻る |
レーニッシュ RÖNISCH (RONISCH) ドイツ(旧東ドイツ) ライプツィヒ
Leipziger Pianofortefabrik (ライプツィガー・ピアノフォルテファブリーク)
創業1845年 創業者:カール レーニッシュ(1814年生まれ~1892年没)
1845年に、貧しかったカール・レーニッシュによって設立されたこの会社は、
のちに世界の隅々までドイツのピアノを普及させる先駆的メーカーとなった。
<歴史>
力ール・レーニッシュは1814年にシレジアに生まれた。10歳のときに機械工場で5年の見習いを開始し、
その期間にピアノに興味を抱くようになった。
ピアノ製作について3年間学んだのち、レーニッシュは1845年にドレスデンで自分の名前のピアノを作り始める。
1857年にはドイツ初のベビーグランドを製作し、3台のグランドピアノをザクセン王に納めてからは、
宮廷御用達のメーカーとなった。そして1862年には、ロシア、スウェーデン、イギリス、スペイン、ポルトガルへ
ピアノを輸出するようになった。
1892年に78歳で力ールが亡くなると、息子のアルベルトとヘルマンが会社を引き継ぎ、
規模拡大を目指した。ふたりは1898年にサンクトペテルブルク支店を設立し、1902年には、
自動演奏ピアノの会社を営むルー卜ヴィヒ・フプフェル卜と協力契約を結んだ。
会社は急速に成長して輸出は記録的な量に達し、年間3,000台の楽器を生産するようになった。
しかし、レーニッシュ家に不幸があり、さらに第一次世界大戦の衝撃を受けた直後の1918年に、
ヘルマンは会社を株式会社ルートヴィヒ・フプフェルトに売り渡した。
両大戦の間もレーニッシュ社は繁盛したが、ドレスデン工場は1945年の空爆で破壊され、
生産はフプフェルト社のライプツィヒ工場へ移された。
翌年、ライプツィガー・ピアノフォルテファブリーク社が誕生し、1986年に年間生産高は8,600台に達した。
1990年のドイツ再統一のあとに生産工程が改変され、製品の再設計がなされた。
1997年、力ール・A・プファイファーがレーニッシュ社を買収し、
有限会社ライプツィガー・ピアノフォルテファブリークを設立。
新たな会社となった今も、レーニッシュ・ブランドの独創性と品質は生き続けている。
<参考>
上皇后美智子様のご結婚前、お正月に正田家において美智子様がピアノを弾かれている宮内庁映像に
出ていたピアノがこのレーニッシュになります。
ピアノを演奏する上皇后美智子様(正田美智子さん)のお写真 →★ 1958年(昭和33年)撮影
※現在この画像はパブリックドメインになっておりますので掲載しております。
パブリックドメイン(public domain=公有)とは、著作物や発明などの知的創作物について、
知的財産権が発生していない状態または消滅した状態のことをいいます。
上から2番目のエンブレム画像は「PIANO YOSHIKAWA様」よりご寄稿頂きました。ありがとうございます!
レーニッシュピアノはBVK認証を受けています(詳しくはこちら
→★)
<附録>
ライプツィガー(レーニッシュ)ピアノ 製造番号/製造年代 対照表(1855年~2000年) →★
※Leipziger Pianofortefabrikは、Hupfeld というブランド名のピアノも製作しています
<以下、ウィキペディアより引用抜粋>
カール・レーニッシュ・ピアノフォルテマヌファクトゥーアGmbH
(Carl Rönisch Pianofortemanufaktur GmbH)は、1845年創業の
ドイツのアップライトピアノおよびグランドピアノ製造会社である。
本社はドレスデン(1845年以降)、ライプツィヒのベーリッツ=エーレンベルク地区(1945年以降)、
2009年以降はライプツィヒのグロースペスナにある。
カール・レーニッシュ(Carl Rönisch、1814年-1894年)によって1845年にドレスデンで創業された。
1866年に鋳鉄製フレームを開発した。これは現代ピアノの製造のための最も重要な必須要素の一つである。
国際博覧会では金メダルを取り、工房はザクセン王室御用達となった。
高品質な製品によって、オーナーのカール・モーリッツ・レーニッシュ(Karl Moritz Rönisch)は
オーストリア=ハンガリー帝国帝室・王室御用達ピアノ製造業者の称号を授与された。
1918年、創業者の息子ヘルマン・レーニッシュ(Hermann Rönisch)は、
会社を継ぐはずであった創業者の孫が第一次世界大戦で死亡した後の1918年に
「Carl Rönisch Hof-Pianofabrik」をライプツィヒのルードヴィヒ・フップフェルトAGへ売却した。
ヘルマンは1902年以降ビジネスパートナーとしてルードヴィヒ・フップフェルトと親交があった。
1945年、レーニッシュ社の主工場がドレスデン爆撃の犠牲となった。
1948年以降、レーニッシュブランドのピアノはライプツィヒのベーリッツ=エーレンベルク地区にある
ルードヴィヒ・フップフェルト社の本社の「ライプツィヒピアノ工房」で作られた。
1967年、「ライプツィヒピアノ工房」はVEBドイツピアノ組合ライプツィヒに吸収された。
東ドイツの「転換」の後、この国営企業は解散し、レーニッシュ/フップフェルトの第一工場から
「ライプツィヒ・ピアノフォルテファブリークGmbH」が誕生した。
この会社はレオンベルクのピアノメーカー・プファイファーによって買収された。
2009年、Pianofortefabrik Leipzig GmbH & Co. KGはピアノメーカーの
ブリュートナーによって買収され、以後、「Carl Rönisch Pianofortemanufaktur GmbH」という
伝統的な名称で経営されている。
同年、ピアノ生産はライプツィヒ近郊のグロースペスナにあるブリュートナーの工場に移された。 |
| RORDORF |
詳細不明 |
| RÖSCH-LE SAGE |
詳細不明 |
ROSE
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ローズ ROSE 製造:天龍楽器製造(株)(浜松) 詳細不明 |
ROSEN



画像クリックでHPへ戻る |
ローゼン ROSEN
有限会社 阿部ピアノ製作所(浜松)
大成ピアノ製造株式会社(浜松市和田町)
株式会社 福山ピアノ社(東京)
ベルリンピアノ製造株式会社
アトラスピアノ製造株式会社
株式会社 ローゼンケーニッヒピアノ製作所
ローゼンのまくり(蓋部分)にあるブランド銘柄マーク →★
上のトレードマークの画像は、阿部ピアノ製作所の頃のトレードマークと思われます。
(下のトレードマークは、福山ピアノ販売になってからのものだと推測されます)
上の方の画像をご寄稿していただいたご寄稿者様によりますと、1940年代以前のピアノだということです。
向かい合わせに座ったライオン?のデザインがとても印象的です。
画像は「匿名希望様」からご寄稿頂きました。この度はご寄稿を頂き誠にありがとうございます! |
| ROSENBACH |
詳細不明 |
| ROSENBERG |
詳細不明 |
ROSENBERLIN
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ローゼンベルリン ROSENBERLIN (有)阿部ピアノ製作所(浜松) 詳細不明
上記の「ROSEN」とは関係あるのか?不明 |
ROSENKÖNIG
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ローゼンケーニッヒ ROSENKONING (ROSENKÖNIG)
販売:株式会社 イノセ楽器(浜松) その他詳細不明
|
ROSENKRANZ
ERNST ROSENKRANZ

トレードマークはなし |
【本家本元】
ローゼンクランツ ROSENKRANZ/ERNST ROSENKRANZ
ドイツ(ドレスデン) 詳細不明
蓋の銘柄マーク(ROSENKRANZ)の下に、DRESDENと入っているのが本場ドイツのローゼンクランツです。 |
|
ROSEN KRANZ
ROSENKRANZ





画像クリックでHPへ戻る
|
ローゼン・クランツ/ローゼンクランツ ROSENKRANZ
ウイスタリア・ピアノ製作所(製造・販売)等
その他詳細不明 真ん中の画像のような折り鶴のトレードマークや、
下のようなワシ?のマークのトレードマークもあります。→日本ローゼンクランツピアノ製造の頃?
下から2つの画像は「ピアノヨシカワ様」からご寄稿頂きました。ありがとうござます!
機種バリエーション:機種:RK.20、RU.30など
<下記情報もありますが詳細不明>
株式会社 伊藤ピアノ技研、株式会社 ツルミ楽器、日本ローゼンクランツピアノ製造、
株式会社 ウイスタリアピアノ製作所、アイケー・ピアノ社、ドレスデンピアノ株式会社
ローゼンクランツに関しては謎が多いので、下記それぞれのローゼンクランツの項目も参照。
★★★
ウイスタリアピアノで製造したローゼンクランツ(鶴のトレードマークのピアノ)はデパートからの特注品でした。
<情報求む>
Schwarmen&Sons シュベルマン&サンズというピアノの製造がIKピアノ?浜松?
ローゼンクランツ(ROSENKRANZ)と同じメーカーとの情報を見つけたが詳細不明
IKピアノはもともと鍵盤を製造していた会社?ネットからの情報(詳細不明)
そもそもローゼンクランツ(ROSENKRANZ)はウイスタリアピアノ製造ではないのか?
ローゼンクランツに関しては謎が多いので、他のそれぞれのローゼンクランツの項目も参照。
現役を引退した方や、詳しい情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら是非情報お待ちしております。 |
|
ROSEN KRANZ
ROSENKRANZ


画像クリックでHPへ戻る

画像クリックでHPへ戻る |
ローゼン・クランツ/ローゼンクランツ ROSENKRANZ
韓国 詳細不明
ドイツ製でも同じ名前がありますが、こちらは韓国製です。
<下記情報もありますが詳細不明>
株式会社 伊藤ピアノ技研、株式会社 ツルミ楽器、日本ローゼンクランツピアノ製造、
株式会社 ウイスタリアピアノ製作所、アイケー・ピアノ社、ドレスデンピアノ株式会社
ローゼンクランツに関しては謎が多いので、下記それぞれのローゼンクランツの項目も参照。
ローゼンクランツのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★
※左記画像はGROTORIAN & SONS/グロトリアン・アンド・サンズのトレードマークです。
これと同じトレードマークのローゼンクランツもあるようです。
ということは、上の画像は韓国製造、下の画像がアイケー・ピアノ社(浜松市中田町)の
ローゼンクランツだと推測(個人的考察)
尚、アイケー・ピアノ社は1970年代~80年代に事業展開していました。創業者:伊藤某氏 |
| ROSENKRAUS |
ローゼンクラウス 大成ピアノ製造株式会社 |
ROSENRICH
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ローゼンリッヒ ROSENRICH
有限会社 坂本楽器研究所(坂本ピアノ製作所)←大成ピアノ製造の前身(浜松)
浜松楽器工業株式会社 |
ROSENSTEIN
ROSEN STEIN

画像クリックでHPへ戻る |
ローゼン・スタイン/ローゼンスタイン ROSENSTEIN/ROSEN STEIN
大和楽器製造株式会社(大和ピアノ)
株式会社 イノセ楽器
浜松楽器工業株式会社
フローラピアノ製造株式会社
浜松ピアノ製造株式会社
発売元:日本ビクター株式会社
機種バリエーション:V-R2等 |
|
ROSENSTOCK

 


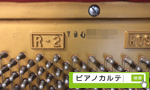
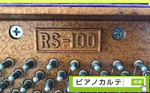
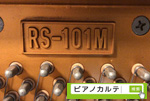


画像クリックでHPへ戻る
|
ROSENSTOCK ローゼンストック 韓国製
韓国にある英昌楽器製造のブランドです。
販売は協立楽器(全日本ピアノ卸センター)で、当時かなりの台数が売れたようです。
製品の中にはチューニングピンが斜めに入っていたり、かなりひどいピアノもありましたが、
製造年数、製造経験が増すにつれてそこそこの品質になってきました。
音色はTHE韓国製といった感じですが、中にはかなり良い音色のピアノもあります。
■機種バリエーション
<アップライトピアノ>
R-101、R-2、R-200、R-202、R-303、R-606、
RS-100、RS-101、RS-108、RS-200、RS-202、RS-205、
RS-208、RS-230、RS-250、RS-280、R-3、RS-300、RS-303、
RS-308、RS-505、RS-600、RS-608、RS-808など
※RS-1**ではじまる機種は、小型のスピネットタイプ
※RS-2**ではじまる機種は、1型のアップライトピアノ
※RS-3**ではじまる機種は、3型のアップライトピアノ
<グランドピアノ>
G-150、G-157、G-175、G-185、G-213、G-275、RG-157、RG-175など
ローゼンストック(協立楽器)の保証書 →★ ローゼンストックの蓋部分の銘柄マーク
→★
ローゼンストックグランドの響板に描かれたデカール →★
ローゼンストックチビ(RS-101)の上前側(前パネ)部に貼ってあるシール
→★
<英昌楽器>
仁川と漢域に工場があり、仁川ではグランドピアノを、漢域ではアップライトを
最盛期で月産1500台を作っていたといいます。
<ピアノ調律技術者向け附録>
張弦作業に役立つ当該機種ミュージックワイヤー配線仕様 →★
<参考>
トレードマーク画像に、文字部分がROSENSTOCKになっている「ワグナー」とまったく同じものもあります。
ローゼンストックのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★ |
ROSENTHAL


画像クリックでHPへ戻る |
ROSENTHAL ローゼンタール
製造元:クロイツェルピアノ製作所 住所:浜松市和田町924番地、浜松市和田町278番地(2つの住所情報あり)
製造元:有限会社 松本ピアノ工場
松本ピアノ工場の高級ピアノとのこと。
森泉氏がこのブランドをもらってクロイツェルピアノ製作所に作らせていました。
トレードマークですが、内部ブランド文字が違うだけでKREUTZER/クロイツェルのデザインとほぼ同じです。
ローゼンタールのトレードマーク画像は「匿名希望様」からご寄稿頂きました。ご寄稿ありがとうございます!
ローゼンタールのまくり(蓋部分)の銘柄ブランドマーク →★
<クロイツェル社の製造ブランド>
KREUTZER(クロイツェル)、LICHTENSTEIN(リヒテンシュタイン)、ROSENTHAL(ローゼンタール)
→KREUTZER(クロイツェル)の項目も参照 |
ROSLER
RÖSLER


画像クリックでHPへ戻る |
レースラー RÖSLER (ROSLER)
チェコスロバキア製 (現在:チェコ共和国) ペトロフ社のブランド
トレードマーク画像は「匿名希望様」からご寄稿頂きました。ご寄稿ありがとうございます! |
ROTH & JUNIUS
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ROTH & JUNIUS 読み方不明 ドイツ 詳細不明 |
| ROTH PIANOS |
詳細不明 |
| ROURI |
ローリー 東洋ピアノ製造株式会社 |
ROURIS
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ローリス 株式会社 プルツナーピアノ
※ブランドスペルの表記が”LORIS”という資料もあり。詳細不明。 |
ROYAL
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ロイヤル アメリカ(オハイオ州シンシナティ) 1895年頃
クレルピアノ社
ロイヤルは、1895年頃、オハイオ州シンシナティのクレルピアノ社で製造されたのが始まりである。
19世紀初頭、クレル社はオハイオ州シンシナティのワーナー・インダストリーズ社に買収された。
1927年、スター・ピアノ・カンパニーがウェルナー・インダストリーズ社を買収し、ロイヤルのブランド名を取得。
ロイヤルピアノは、世界大恐慌を乗り越えてほぼ1世紀にわたって生産されたが、1949年頃以降、
ロイヤルの製造は中止された。
ロイヤルピアノについては、現在残っている楽器が少ないため、ほとんど知られていない。
アップライトピアノ、ベビーグランドピアノ、プレーヤーピアノなどのブランドがあった。
現在残っている数少ないロイヤルピアノからもわかるように、質の高い楽器であったことが伺える。 |
ROYAL

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ロイヤル ROYAL
大倉楽器工業株式会社
アトラスピアノ製造(浜松)
大倉楽器工業(株)東京都杉並区上高井戸
二本弦の小型ピアノが多かったが、大型のものは音色に特色があった。
機種バリエーション:R503等 |
ROYALE & SONS
ROYALE


画像クリックでHPへ戻る |
ロイヤル アンド サンズ 機種:RS-114、RS-115等 詳細不明
韓国の大宇財閥がブランド所有?
Daewoo Group(大宇財閥)で作られたピアノ?
ピアノフレームには、「BY L.S. DESIGN WEST GERMANY」と入っています。 |
| ROYALE-CLASSIC |
詳細不明 |
| RUBBY |
ルビー 発売元:ルビーピアノ商会 |
| RUBENSTEIN |
詳細不明 |
RUBINSTEIN



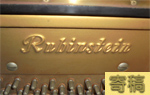
画像クリックでHPへ戻る |
RUBINSTEIN ルビンシュタイン
(読み方:ルビンシュタイン→○ ルービンシュタイン→×)
製造元:斎藤ピアノ製作所(横浜市保土ヶ谷?)
※住宅兼工場:横浜市中区堀之内町
※本社工場:横浜市南区井土ヶ谷下町と、浜名郡和田村薬師、及び和田村永田という情報もあり
斉藤ピアノ株式会社、斉藤楽器株式会社(浜名郡、現:浜松市)
→ルビンシュタインピアノ製造(株)(浜松市→その後掛川市?)
※斉藤ピアノの社史はこの項目の下の方を参照
広田ピアノ株式会社
西村ピアノ商会
横浜市の保土ヶ谷付近で昭和10年頃、斉藤栄一氏が製造を始めたピアノで、
ポーランド出身のピアニスト、アルトゥール・ルービンシュタインがその工場を訪問した時、
あわててピアノのふたを閉じたという逸話が残っている。
太平洋戦争後、ピアノが不足している時、良く流通していたようです。
斉藤楽器(斉藤ピアノ)は斉藤栄一氏の次男である武司氏の創業で、森健氏も参加したことがある。
横浜市南区弘明寺に店があったが、後に浜松に移って
ルビンシュタインを作り、それが天竜工芸の母体になった。
除響板(高音域の鳴りをより際立たせるため響板の一部を三角形に切り欠いた構造)を採用している。
この除響板はドイツのベヒシュタインを参考にしていると言われています。
1番上の画像は文字のみでトレードマークがまだない頃(おそらく斉藤ピアノ時代)に作っていたもので、
上から2番目のトレードマークはルビンシュタインピアノ製造(株)になってからのもののようです。
宮殿と交差させた2本の音叉を組み合わせた印象的なマークとなっております。
ルビンシュタインのまくり(蓋)部分のブランドマーク →★
ルビンシュタインピアノの保証書 →★ ルビンシュタインのアクションレールに貼られたシール →★
ルビンシュタインの外観写真 →★ こちらの写真は「ブティック アヤ」様からご寄稿頂きました。
機種:RM-303等
<斉藤ピアノ製作所からルビンシュタインピアノ株式会社までの歴史>
ピアノ輸入商社スウェイツ商会に勤めていた斉藤栄一氏が中心となって斉藤ピアノ製作所が設立され、
上海モートリー商会から来日したドイツ人技師のカンホール指導の下、カンホールが連れてきた中国人技師や
西川楽器出身者などのプロ集団でピアノ製造が始められた。
生産は年々増加したが、その売り上げの背景には東京ピアノ(後の大塚ピアノ商会)の大塚錠吉氏や、
協信社ピアノ製作所の松崎妙氏などが製造・流通・販売を支援したことが大きく貢献していると言われている。
1938年(昭和13年)、事業は斉藤栄一氏の次男である斉藤武司氏が引き継ぐことになる。
その後、太平洋戦争によるピアノ製造休止時には斉藤航空機製作所を設立し、主に飛行機の翼を製造。
しかし1945年(昭和20年)の空襲により工場は焼失。
終戦後、斉藤武司氏は横浜から単身浜名郡(現在の浜松市)に進出し、斉藤ピアノ株式会社を設立し、
ピアノ製造を再開。この年に完成させたルビンシュタインピアノで高い評価を得たほか、ピアノ関連で
実用新案特許や専売特許を取得するなど、常に新たな開発につとめ技術の向上を図っていた。
その頃製造したSAITOH & SONS(サイトー&サンズ)は父の栄一氏と次男の武司氏親子を意味している。
1950年(昭和25年)、「斉藤ピアノ株式会社」から「斉藤楽器株式会社」に社名変更。
経営は順調に伸び、従業員も大幅に増えていった。
後にアトラスピアノ製造の常務取締役になる雨宮辰雄氏もこの時期に参画していた。
1955年(昭和30年)あたりから日本国内ではヤマハやカワイの台頭とピアノメーカー過多による
競争の激化により、斉藤楽器株式会社も他メーカー同様に倒産に追い込まれました。昭和31年解散。
しかし、会社解散後も一部社員が製造を継続したことで、後のルビンシュタインピアノ株式会社へと
繋がることになっていきます。
<斉藤ピアノが製造したピアノ>
HORUGEL(ホルーゲル)、PRIMATONE(プリマトーン)、RICHTONE(リッチトーン)、
RUBINSTEIN(ルビンシュタイン)、SAITOH & SONS(サイトーアンドサンズ)
<社史>
1906年(明治39年) 斉藤栄一氏により創業
1943年(昭和18年) 太平洋戦争により創業休止
1948年(昭和23年) 6月10日 斉藤栄一氏の次男、斉藤武司氏により、斉藤ピアノ株式会社設立
1950年(昭和25年)12月12日 社名変更→斉藤楽器株式会社に
1956年(昭和31年) 3月30日 解散
→会社解散後、一部社員で「ルビンシュタインピアノ株式会社」へと継承し製造を続ける
トレードマーク画像の2番目はD1g様からご寄稿頂きました。ありがとうございます! |
|
RUBITZ & SONS


画像クリックでHPへ戻る
|
ルービッツ・アンド・サンズ
発売元:協立楽器 (株式会社 協立インターナショナル)
発売元:アトラスピアノ広島販売株式会社
詳細不明。韓国製だと思われます。
RUBITZ & SONS 正確な読み方も不明。
ルービッツ&サンズのまくり(蓋)のブランドマーク →★ ルービッツアンドサンズの保証書
→★
ルービッツアンドサンズのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★ |
RUCH
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
フランス(パリ) 詳細不明 |
| RUD. IBACH SOHN |
→IBACH(イバッハ)の項目参照 |
RUDOLF
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
Rudolf ルドルフ
1959年にウインター(WINTER & CO.)は、エオリアン・アメリカン社と合併し、
社名をエオリアン・コーポレーションに変更していた間、RUDOLFは
ウィンター&カンパニーが製造していたブランド名の一つです
→詳しくはWINTERの項目へ
※日本のRUDOLPHとは違うピアノです |
RUDOLPH
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ルドルフ RUDOLPH 日本 詳細不明
※アメリカのWINTER社が作っていたRUDOLFとは違うピアノです |
| RUSSELL AND RUSSELL |
詳細不明 |
| RUSSELL, GEORGE |
詳細不明 |
RUTASS

画像クリックでHPへ戻る |
RUTASS ルータス?
詳細不明、生産国も不明
左記の画像は匿名希望様からご寄稿頂きました。
そのご寄稿者様によりますと、戦中戦後か時代は定かではありませんが購入されたのがその時期で
90歳近い叔母様が若い時に購入したピアノとのこと。
2ペダルのアップライトピアノで、写真のようにピアノの内側に葡萄の彫刻があります。
その他、詳細不明 |
| RUYTER |
詳細不明 |
上記Rから始まるブランドの中で、追記出来そうな事項や新情報を発見した場合、修正受付フォーム よりお気軽にお知らせ下さい。
どんな些細な情報でも構いませんので、広く皆様からのフィードバックをお待ちしております。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
 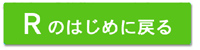 



ピアノ銘柄ブランド
トレードマーク 紹介
& 知名度ランキング

|

メーカー/ブランド説明・会社沿革・歴史・製作者・特徴・音色・他
|
S. RODESTEIN
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
RODESTEIN (S.RODESTEIN) ローデスタイン (S・ローデスタイン)
松本ピアノ 詳細不明
|
S. CHEW

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
S.CHEW エス・シュー/S・シュー
周ピアノ製作所(周興華洋琴専製所)横浜天神橋近く ※周興華洋琴製作所という表記もあり
大正時代中期、上海出身の中国人、周筱正(しょうせい)氏は横浜に工場を建て、
ピアノを製造していた。だが筱正氏は関東大震災で命を落とし、工場も閉鎖。
長男の譲傑(じょうけつ)氏が昭和初期に復興したが、譲傑氏も終戦直後の1946年に死去。
親子二代の「周ピアノ」は約30年でその歴史を閉じ、日本には3台しか現存していない。
19世紀末、横浜の天神橋近くにあった。上海から来た周譲傑氏の製作による。
昭和のはじめモートリーピアノ工場の技師であった周譲傑氏は中国人の工員数人とともに来日、
横浜に工場を持った。当時のレベルでは高級品であり価額も高かった。
外国ピアノ商会(東京ピアノ商会)の沢山清次郎氏とも交流があり、委託生産も行っていた。
人格者で日本人の技術者も多く育てたが、不幸にも戦争中にスパイ扱いされて獄中死した。
※周ピアノについてはこちらに詳しい記事があります →★
|
S. CHEW & SON

このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
エス・シュー・アンド・サン
周ピアノ製作所(周興華洋琴専製所)
音叉が3本交差した印象的なデザインのトレードマークです。 |
S. EDELL
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
エス・エデル 日本 詳細不明 |
S. G. LEE

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
S.G.LEE エス・ジー・リー/S・G・リー
李元氏 スペルは”LEA”ではない
李ピアノ(横浜天神橋)
19世紀末、周ピアノとともに横浜天神橋近くに工場があった。
李佐衡氏が経営指導に当たった。
T.A.リーの項目も参照 |
S. GRIEBEL
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
S.GRIEBEL エス・グリーベル (有)興和楽器製作所(浜松)
S・クリーベル というのも同じ会社で出している?詳細不明
|
| S. KOHLMAN |
エス・コールマン |
S. KRIEBEL

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
S.KRIEBEL S・クリーベル
有限会社 興和楽器製作所(浜松)
ホフマンと同じく工場は天龍川西岸の工場で作られていた。
東京ピアノで同名のピアノが売られている。
S・グリーベル というのも同じ会社で出している?
|
| S. LEDECZY |
→LEDECZYの項目へ |
S. LOADE
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
S.LOADE エス・ローデ/S・ローデ
足立三郎氏:東京都目黒区中目黒
東京の調律師、足立三郎氏の理論を生かして浜松のピアノメーカーに依頼して作られたピアノです。
足立三郎氏は、福島琢郎氏らによって設立された東京楽器研究所(創業1918年/大正7年)において
製造技術を学んだ後に一人で独立。独自の理論を元にピアノを設計したエス・ローデピアノを、
浜松のピアノメーカーに製造を依頼したとの記録が残っています。 |
S. MATSUMOTO

このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
S.MATSUMOTO S・マツモト (S・松本)
松本ピアノ八重原工場 (松本新吉:松本ピアノ創始者) 千葉県君津市八重原
松本ピアノが故あって2つに別れたとき、長男広氏のH・マツモトに対して、
父親の新吉氏のSを頭文字として、千葉県君津で製作されていた。
伝統の製法はマツモト&サンズとなって引き継がれた。
※ 松本ピアノの詳しい歴史については、MATSUMOTO & SONSの欄をご参照下さい
|
S. MIKI
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
S.MIKI エス・ミキ/S・ミキ
製造元:株式会社 河合楽器製作所
発売元:三木楽器店/三木楽器株式会社
河合楽器が製作にあたった三木楽器店ブランドの一つで三木佐助氏の名前をとった特製品。
→ミキの項目も参照 |
S. RODESTEIN
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
エス・ローデスタイン 松本ピアノ工場(君津市八重原) |
S. SCHIMMEL

画像クリックでHPへ戻る |
S.SCHIMMEL S・シンメル 日本ピアノ株式会社 ※ドイツのシンメルとは関係がない。
※トレードマークは下記シュミットと同じマークのようです |
|
S. SCHMIDT



画像クリックでHPへ戻る
|
シュミット S.SCHMIDT
製造:日本ピアノ製造株式会社
当時の本社:東京都中央区日本橋本町4-1(本町ビル内)だが、
シュミット製作時の本社:東京都中央区日本橋小舟町
工場は同じ住所:静岡県磐田郡袋井町袋井駅前 (現:袋井市)
鉄骨部分のロゴにはN.P.Cとありますね。
トレードマークには珍しく、逆三角形の形をしています。
1台しか調律したことはありませんが、まさに昭和を感じるピアノですね♪
シュミットの蓋(まくり部分)にあるブランド名称メインマーク
→★
シュミットのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★ |
SABEL

画像クリックでHPへ戻る |
SABEL サボー スイス 詳細不明
トレードマーク画像は匿名希望様からご寄稿頂きました。ありがとうございます! |
| SAGENHAFT |
詳細不明 |
SAITOH & SONS
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
SAITOH & SONS
サイトー&サンズ/サイトー・アンド・サンズ/サイトウ&サンズ/サイトウアンドサンズ
斉藤楽器株式会社(斉藤ピアノ株式会社) ※漢字は齋藤が正しいようです
ブランド名は「斉藤栄一氏」と次男の「斉藤武司氏」を表している
齋藤ピアノ株式会社 当時の住所:横浜市南区通町4丁目100番地
→詳しくはRUBINSTEINの項目を参照 |
SAKURA

画像クリックでHPへ戻る |
サクラ 東洋ピアノ製造株式会社 |
| SAMANIEGO |
詳細不明 |
SAMES
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
読み方:セイムズ? 詳細不明 |
| SAMES, WILLIAM |
詳細不明 |
SAMICK



画像クリックでHPへ戻る |
サミック 韓国(仁川/インチョン) Samick Piano Company/サミック・ピアノ・カンパニー
韓国にある4社のピアノメーカーのひとつであるサミック社は短い歴史しか持たないが(1958年設立)、
朝鮮戦争休戦直後の世の中の見通しの立たない時代に創業し、短い期間に急成長しました。
サミックはこのような短い歴史にもかかわらず、世界で最も多くのグランドピアノ製作台数を誇る
世界最大クラスのピアノ製作会社になりました。
サミック社のワールド・シリーズ・ピアノは、コリアン・スタンダード・オブ・エクセレンスの認証を受ける。
サミック社のグランドピアノのスケールデザインは、1983年に技術支援を依頼された著名なドイツの設計家、
クラウス・フェナーによって設計された。
<歴史>
1958年に会長のイ・ヒョイクによって設立されたサミック社は、Horugel(ホルーゲル)のブランド名で
アップライトピアノの生産を本格的に開始しました。
このブランド名は1970年代まで使用され、以降はサミックのブランド名が確立。
国内の市場を先導するサミック社は、1964年に韓国で初めてピアノを国外へ輸出した会社で、
はじめて海外輸出したピアノは、10台のアップライトピアノを香港へ送り出しました。
アップライ卜ピアノの生産高は着実に増大し続け、また1970年に韓国産業通商資源部のピアノ開発賞を
受賞したことが弾みになり、サミック社は韓国で最初のグランドピアノの製作会社となりました。
それに続く時代は世界市場における地位を確保することに費やされ、資産は輸出拡大のために
集中して使われました。サミック社は1980年に西ドイツ支店をオープンし、その後、アメリカン・
ボールドウィン・ピアノ・アンド・オルガン・力ンパニーと共同事業を開始しました。
サミック社は設立当初から生産施設を拡大する為に精力的に努力し続け、何度か工場を再編したのち、
1990年代までには、アップライトピアノ、グランドピアノ、デジタルピアノの工場を分離させて、
それぞれに最新の機械設備を導入しました。1996年にサミック社はインドネシアに木材加工場を
持つ工場を建設し、そこでは現在もアップライトとグランドの両方が生産されています。
サミック社のグランドピアノのサイズは、全長140cmから275cmまで、9種類もの幅広い選択肢がある。
サミックのまくり(蓋)部分の銘柄マーク →★ サミックに貼られたプレート →★
<サミック社が取り扱うブランド>
Samick、Hyundai、Kohler & Campbell、D.H.Baldwin、Bernhard Steiner、Otto、
(以下は取り扱い終了ブランド)Horugel、Stegler、Schumann
※参考
下記に列挙するブランドはすべて同じ雰囲気のトレードマークとなっており、どれも韓国製造と思われます。
REID-SOHN、KAFMANN、SAMICK、SCHNABEL、WEINBURG、U. WENDELL、UHLMAN SUPER
サミックのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★
|
SAMPAGUITA
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
SAMPAGUITA サンパギタ フィリピン 詳細不明
|
| SANDBERGEN |
詳細不明 |
| SÄNGLER & SOHNE |
詳細不明 |
| SASSMANN |
詳細不明 |
| SATURN |
詳細不明 |
SAUJIN

画像クリックでHPへ戻る |
ソージン(ソジン) 韓国(ソウル) 詳細不明
「SOJIN」というピアノもあり、同じメーカーが作っているようですが、
日本国内で見るのは「SOJIN」の表記のピアノが多いように感じます。
「SAUJIN」と「SOJIN」の2種類の表記が混在する理由は不明
※「SOJIN」と「SAUJIN」のピアノまくり(蓋部分)にある文字表記違いの参考写真 →★
韓国のSOJIN工場(Daewoo Group/大宇財閥)で作られたピアノ、との情報あり。
別情報として、1999年に破綻した韓国の企業グループである大宇財閥は、
破綻前は、韓国の10大財閥の1つで現代に次ぎ韓国で2位の企業グループだった。
その中に、大宇精密工業(Daewoo Precision Industries)はSojin
ブランドとその他のブランドのピアノを1980年から1991年にかけて米国に輸出。
大宇精密工業はドイツのピアノメーカー「イ・バッハ」に30%出資し、
イ・バッハのピアノ製作機械のコピーをつくり、Sojinとして販売していたようです。
大宇精密工業は韓国で作ったイ・バッハブランド(UPとGP)はカナダに輸出され、
現在は米国には輸出されていないようです。
破綻した大宇精密工業の社名は現在は「S&T Motiv」となっています。
アップライトに加え、グランドも製造
画像は「匿名希望様」からご寄稿頂きました。ありがとうございます!
ご寄稿者様によりますと、ピアノのまくり(蓋部分)には「Clement/Clēment」と書いてあるそうです。
ピアノまくり部分の写真はこちら →★ ※ちなみに「Clément」はクレマンと読み、フランス語圏の姓
※SOJINの項目も参照 |
|
SAUTER


画像クリックでHPへ戻る
|
ザウター Sauter 創業1819年 ドイツ(シュパイヒンゲン)
1813年、家具職人であるヨハン・グリムは、優秀な成績で見習い職人を終了した。
地元の教会において鍵盤楽器に感銘を受けた彼は、次なる修行への冒険を決心。
彼はピアノ製作者の道を志したのである。
そして彼は、当時音楽の都であった、ウィーンに引越し、1819年ピアノ工房の設立。
6年間に及んだヨハン・アンドレアス・シュトライヒャーの下での修行の後、シュパイヒンゲンに戻り、
1819年にスクエアーピアノの製作を開始した。この1819年がトレードマークに記されていますね。
当時この若いピアノ製造技術者の作った楽器は、その品質の為一躍有名になり、
技術を求めて短期間で多くの弟子が集まった。
工房から工場へ
グリム夫妻には子供が授からなかった為、当時16歳の甥カール・ザウターを見習い職人として採用。
カールは音楽的にも職人としても天分に恵まれ、叩き上げのピアノ製造技術者にのし上った。
後継者となり、そしてグリムの死により工房を引継ぎ、1846年にピアノ工場へ拡張させ、
とりわけピアノ製造技術の改良を次々と実現していった。
1863年、早すぎたカール・ザウターの死後、母親と共に17歳のヨハン・ザウターが工場を引き継いだ。
彼は数多くの旅行、とりわけアメリカ旅行より、多くのピアノ製造技術に関する新たなヒントを持ち返った。
最も重要な成果として上げられることは、それ以後のスクエアーピアノの製造ウエイトが、
近代的な形に、すなわちアップライトピアノフォルテに移行したことである。
カールザウター2世苦難の時代での工場拡張。
カールザウターは生産合理化と工場拡張に力を注いだ。
優秀な品質と改良されたピアノモデルは、ザウターの名前をドイツ中に響きわたらせた。
ハンス・ザウター、ザウター社史の新世紀の始まり。
音楽家・ピアノ製造技術者・設計者そして発明家であったハンス・ザウターは、
新しい時代に、彼は新しい経済知識と、時流にあった新しい技術と材料を取り入れた。
その音と美しいデザインのモデルはメッセに展示し評判になり、
間もなく世界中に輸出されて行ったことにより、大繁盛となった。
1968年~ カール・ザウター3世、ダブルレペティションアクションの開発
ハンス・ザウターの死後、弟のピアノ製造マイスターであるカール・ザウターが会社の経営を引き継いだ。
ザウターを最高級ブランドの一つに数えられる数多くの革新をもたらした。
最も重要な部分は、R2アクションのシリーズ化、基本モデルをもとにサウンドボードを大型化し、
豊かな音量の達成を図り、そして高価なMシリーズの導入である。
それに付け加え、160cm 185cm 220cm グランドピアノの改良と新たな導入により、
多くのピアニストに認められついには、同じウィーンに発祥するベーゼンドルファーはもとより
スタインウェイ以上の評価を得るに至った。
1974年そして1984年にシュパイヒンゲンの近代的な工場と管理部門社屋の設計図がひかれ、
これにより、ザウターの生産性と品質レベルの向上の為の本質的な必要条件が充たされた。
1982年から経営陣にハンス・ザウターの息子でマーケティングを学んだウーリッヒ・ザウターが加わり
日本・シンガポール・ホンコン・アメリカ・カナダ等の新たな輸出市場の確立に成功した。
1994年 ザウター社創立175周年。
世界中のピアノ市場の激変は、ザウターに於いても抜本的な構造変化を強いられた。
高級品市場への強化と言う、生産コンセプトの実現が企業方針の中心となった。
ザウターは音色・タッチ・デザインにおいて、そしてピアニストの高い要求に十分応えるべき
最高級ピアノを作ることに全力を傾け続けている。
今ではザウターの歴史は、世界で最も古い伝統をもつ、ピアノ製造会社の1つとなったのである。
世界の3大ピアノと言われる、スタインウエイ・ベヒシュタイン・ベーゼンドルファーよりも更に古い。
ザウター社はアップライトのための”R2ダブルエスケープメント・アクション”を開発しました。
これはアップライトとグランドピアノのタッチの差をなくすためのもので、このアクションには、
レペティションを補助する追加のジャックスプリングが取り付けられています。
■機種/モデル バリエーション
アップライト
モデル110(アトゥディオ・クラシック・アルトドイチュ・バロック)
モデル112(カールス)
モデル120R(クラシック・アルトドイチュ・アルトイングリッシュ・エムパイア・
バロックチッペンデール・ルイスサイズ)・モデル130R(クラシック)
モデル122(ドミノ)
グランドピアノ
モデル160(クラシック・チッペンデール・ノブレッセ)
モデル185(クラシック・チッペンデール・ノブレッセ)、(デルタ)
※ザウターピアノはBVK認証を受けています(詳しくはこちら
→★)
<附録>
ザウターピアノ 製造番号/製造年代 対照表(1840年~2000年) →★
<以下、ウィキペディアより引用抜粋>
カール・ザウター・ピアノフォルテマヌファクトゥーア(独: Carl Sauter Pianofortemanufaktur、
カール・ザウターピアノフォルテ工房)GmbH & Co. KGは、シュパイヒンゲンにある1819年創業の
アップライトピアノおよびグランドピアノ製造業者である。
自身を「ドイツ最古の現存するピアノ工房」と形容している。
ヴュルテンベルクシュパイヒンゲンで生まれ育ったヨハン・グリムはピアノ製造を学ぶため
同じシュヴァーベン人のアンドレアス・シュトライヒャーと共に1813年にウィーンへ移った。
ウィーンに6年間滞在した後、グリムは故郷へ戻り、スクエア・ピアノの製造を始めた。
グリムの甥カール・ザウターが1846年に作業場を引き継ぎ、マニュファクチュア(工場制手工業)への
移行を始めた。それ以後、会社はザウターの名を冠するようになった。
今日、ザウターは国際的に名高いピアノ製造業者である。
1952年以後はグランドピアノ、2000年以後はコンサートグランドピアノも製造している。
1993年、当時の多くのピアノメーカーと同様に、会社は倒産寸前であった。
生産技術者のOtto Hottが経営を引き継ぎ、会社を再建した。
それまでの中価格帯に注力する代わりに、ザウターは富裕層向けの高品質な高価格帯商品の生産に専念した。
これは特に海外で成功を収めた。ザウターのピアノはオスロ歌劇場やパリ国立高等音楽院で使用されている。
アメリカのジャズピアニストBob RavenscroftはザウターのピアノデザイナーMichael Spreemanによって
設計された楽器を所有している。
ザウターは1980年代には年間約2000台のピアノを生産していたのに対して、
今日でも年間約500台を生産しており、約5百万ユーロの年間売上高を挙げている。
会社は約50名を雇用している(2015年現在) |
| SCHAAF & CO. |
詳細不明 |
| SCHAAF, HERMANN |
詳細不明 |
| SCHADHAUSER, JOHANN |
詳細不明 |
SCHAEFFER
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
シェーファー Schaeffer Pianos アメリカ(ニューヨーク) 創業1873年
シェーファー・ピアノ・マニュファクチャリング・カンパニーは、1873年にウィリアム・シェーファーによって
ニューヨークで設立されました。
1888年には、アメリカのピアノ製造拠点であるイリノイ州シカゴに移転しました。
シェーファーは、1920年代後半にW.F.フレデリクス・ミュージックハウスに買収されるまで、
ピアノの卸売りを専門に行っていました。
数年後、ピアノ大手のプライス・アンド・テンプル社がW.F.フレデリックス・ミュージックハウス社を買収、
シェーファーの名前も引き継ぐことになりました。
1931年、世界恐慌の影響でシェーファーピアノの生産は終了した。
シェーファーピアノは、美しい音色を持つ高品質な楽器でした。
パリ万国博覧会で受賞したり、アメリカの大手ピアノディーラーが販売するなど、
音楽界で高い評価を得ていた。
※現在、韓国や中国で製造のシェーファーピアノとはまった別のピアノです。 |
SCHAFER & SONS

画像クリックでHPへ戻る |
SCHAFER & SONS シェファー・アンド・サンズ/シェーファー・アンド・サンズ
韓国製 その他詳細不明
音色は一昔の「THE韓国製」といった感じです。
1931年に廃業した本家アメリカの「シェーファー」とはスペルが違います。
こちらは「E」と「F」が1個づつ足りません。まったく別のピアノですのでご注意下さい。
機種バリエーション:112Rなど
整音にてある程度良い音にも出来ますので、調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★ |
SCHAER & SONS
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
シェファー・アンド・サンズ/シェーファー・アンド・サンズ Schaer&Sons
元々はアメリカ製のブランドで現在は中国製造。
最終調整をアサヒピアノで行い販売していたという情報。
朝日ピアノ(アサヒピアノ)とはウエンドルラング(中国製)などを販売している浜松にある会社。
上記のSCHFER & SONSとは違うのか?不明
1931年に廃業した本場アメリカのシェーファーとはスペルが違います。ご注意下さい。 |
| SCHAFF |
Schaff Bros Co. 詳細不明 |
| SCHANZ |
詳細不明 |
| SCHARF & HAUK |
詳細不明 |
| SCHEEL, CARL |
詳細不明 |
| SCHELL, LOTHAR |
詳細不明 |
| SCHELLENKENS, G. |
詳細不明 |
SCHEMA
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
SCHEMA PIANO CO. スキーマ 詳細不明 |
|
SCHIEDMAYER SOHNE



 
画像クリックでHPへ戻る
|
SCHIEDMAYER & SÖHNE
シードマイヤー・ウント・ゼーネ/(シードマイヤー・アンド・ゼーネ)/(シードマイヤー・ゾーネ)
ドイツ(旧西ドイツ) STUTTGART/シュツットガルト
※現在は日本のカワイが取り扱っています
有名なクラヴィコード製作者のバルタザール・シードマイヤーは、1735年にドイツのエアランゲンで
最初のクラヴィコードを製作したと言われている。
バルタザールのその後の仕事についてはあまり知られていないが、かなりの業績を上げたものと思われる。
1781年にバルタザールが亡くなると、息子のヨハンが父の仕事を継いでブランデンブルク選帝候御用達の
楽器職人になったことからしても、バルタザール・シードマイヤーの店は繁盛していたとうかがえる。
ヨハンはニュルンベルクへ戻り、そこでかなりの成功を収める。
そしてその息子のヨハンがシュトゥットガルトへ移り、ドイツのもっとも有名な会社のひとつの礎を築いた。
進歩的なシードマイヤー社は1842年に早くもアップライトピアノを製作した。
そしてヨハンの上の息子のアドルフとヘルマンを経営に加えてシードマイヤー・ウント・ゼーネと社名を改め、
1851年のロンドン万博では金メダルを獲得した。一方、ヨハンの下の息子のユリウスとパウルは、
J.& P. シードマイヤーのブランドの名前で優れた品質のハルモニウムを製作していたが、ハルモニウムの
先細りに伴い、1860年にピアノ製作への転向を余儀なくされる。ユリウスとパウルは、シードマイヤー・
ピアノフォルテファブリーク(Schiedmayer Pianofortefabrik)のブランド名でピアノを作り始めた。
19世紀の終わりまで、ふたつのシードマイヤー社は先祖の伝統を受け継いで成功を積み重ね、それぞれが
作る質の高い楽器で高い評価を得ていった。
その後、1969年にふたつの会社は合併し、小型のアップライトとグランドピアノを生産するようになった。
※尚、韓国製にもシーマイヤーという同じ名称のピアノがありますがまったく関係ありません。
→韓国製のシードマイヤーの方はわざとスペルを少し変えています
韓国製シードマイヤーのスペルは、「SHCHIED MAYERR」 ※Hを多く入れ、Rを2個にしている所に注目
<附録>
シードマイヤーピアノ 製造番号/製造年代 対照表(1880年~1980年) →★
<以下、ウィキペディアより引用抜粋>
シードマイヤー(Schiedmayer、シートマイヤー)はドイツの楽器製造一家の名前である。
1735年に鍵盤楽器製造業者として設立され、今日も同族経営事業として続いている。
■始まり
シードマイヤー家の最初の楽器製作者はエアランゲンのオルガンおよびピアノ製作者
バルタザール・シードマイヤー(1711-1781年)であり、1735年に最初の楽器を製造した。
彼の三人の息子も楽器製作の術を学んだ。
ヨハン・ゲオルク・クリストフ・シードマイヤー(1740-1820年)は
ノイシュタット・アン・デア・アイシュに定住した。彼が製造した数多くの楽器が現存している。
息子のヨハン・エアハルト・シードマイヤーも同様に楽器製作者であった。
アダム・アハティウス・シードマイヤー(1753-1805年)はエアランゲンのピアノ製作者であった。
彼のグランドピアノが1台現存している。
ヨハン・ダーヴィト・シードマイヤー(1753-1805年)はエアランゲンと1797年の後は
ニュルンベルクで活動した。彼は当時最も有名なピアノ製作者の一人であった。
彼の工房からは、クラヴィコード1台、フォルテピアノ5台、スクエア・ピアノ1台が現存している。
■シードマイヤー&サンズ
1809年、ヨハン・ダーヴィットの息子ヨハン・ロレンツ・シードマイヤーは、
カール・デュドネ(Carl Dieudonné)と共に、シュトゥットガルトで「Dieudonné & Schiedmayer」の
会社を設立した。会社はすぐにこの地域でよく知られるようになった。
作曲家のフリードリヒ・ジルヒャーがシュトゥットガルトに移ってきた時、ジルヒャーは2年間
シードマイヤーの自宅で生活した。
ジュドネの死後、工房は「シードマイヤーのピアノ工房(Pianofortefabrik von Schiedmayer)」に改名し、
ヨハン・ロレンツ・シードマイヤーの年上の2人の息子アドルフとヘルマン・シードマイヤーが会社に加わった
1845年の後、社名は
「シードマイヤー&ゾーネ、ピアノ工房(Schiedmayer & Söhne, Pianofortefabrik)」となった。
1821年から1969年まで、工場はネッカー通り(現在のコンラート・アデナウアー通り)14-16にあった。
この区画には今日、シュトゥットガルト音楽演劇大学とバーデン=ヴュルテンベルク州歴史博物館がある。
1909年、会社の100周年を祝うための大規模な展示会がシュトゥットガルトの王立工商業センター
(現在のシュトゥットガルト商工会議所)で開催された。
来訪者の中にはヴュルテンベルク王ヴィルヘルム2世と妻のシャルロッテがいた。
■J & Pシードマイヤー
ヨハン・ロレンツ・シードマイヤーは若い2人の息子ユリウスとパウルをパリへ送った。
パリで彼らはハーモニウム製造を学び、またその数年後にチェレスタ(の原型)を発明する
ヴィクトル・ミュステルに出会った。シュトゥットガルトに戻った後、彼らは1853年に
「J & Pシードマイヤー」社を設立し、すぐにピアノと後にはチェレスタの製造を開始した。
彼らはSchiedmayer-Scheola(オルガンとハーモニウムとチェレスタが混った楽器)や
いくつかの機械式自動演奏楽器のような珍しい楽器も製造した。
この会社は「シードマイヤー&ゾーネ」社の近くに位置していた。
会社は後に名前を「シードマイヤー・ピアノ工房(Schiedmayer, Pianofortefabrik)」に改名した。
1969年、「シードマイヤー&ゾーネ」社の所有者ゲオルク・シードマイヤーがを
「シードマイヤー・ピアノ工房」(元の「J & Pシードマイヤー」)を当時の所有者のマックスおよび
ハンス・シードマイヤーから買収した。
ピアノ生産は1980年に停止し、会社はチェレスタとグロッケンシュピールの製造のみに特化した。
1992年、ゲオルク・シードマイヤーの死に際して、妻のエリアンヌ・シードマイヤーが
「シードマイヤー&ゾーネGmbH & Co. KG」と「シードマイヤー・ピアノ工房」の2つの会社を相続した。
2008年、シードマイヤー・ピアノフォルテ工房は商業登記簿上で公式に清算された。
■シードマイヤー・チェレスタGmbH
1995年、エリアンヌ・シードマイヤーは「シードマイヤー・チェレスタ
GmbH(Schiedmayer Celestabau GmbH)」を設立した。
(2000年以降はシュトゥットガルト近くのヴェンドリンゲン・アム・ネッカーに本社を置く)
世界的にシードマイヤーのチェレスタと鍵盤付きグロッケンシュピールは
オペラやコンサートホールで使われている。
■ミュラー=シードマイヤー
「ミュラー=シードマイヤー」の工場はヨハン・ロレンツ・シードマイヤーの娘の息子によって
1874年にヴュルツブルクで設立された。
創業者は親族の「J & Pシードマイヤー」および「シードマイヤー&ゾーネ」や、
ニューヨークのスタインウェイ・アンド・サンズで商売を学んだ。事業は1968年に清算された。
最後の所有者はエルヴィン・ミュラー=シードマイヤーであった。 |
| SCHIEDMAYER, J.& P. |
詳細不明 |
| SCHEMELLI & CO. |
詳細不明 |
SCHILLER
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
SCHILLER シラー アメリカ(イリノイ州オレゴン) 創業1892年
ケーブルピアノ社 ケーブル・ネルソン アメリカ(オレゴン州)
シラーピアノ社は、1892年にF.G.ジョーンズによってイリノイ州オレゴンに設立されました。
シラーピアノは、非常によくできた高価なピアノを製造していました。
20世紀初頭、シラーはイリノイ州の多くの学術機関で愛用されていたピアノブランドでした。
1920年代初頭、シラーはケーブル・ピアノ・カンパニーからコノバー・ケーブルに買収された。
ケーブル・ピアノ・カンパニーのコノヴァー・ケーブル社が、1920年代初頭にシラーを買収し、
シラーの名を冠した最高級のピアノを販売したのである。
その後、20世紀半ばから後半にかけて、ウィンター・ピアノ・カンパニーが
シラーのブランドを付けたピアノを製造していた。
シラーのピアノは、その個性と音色が高く評価されています。
同社のスーパーグランドは耐久性に優れており、当時の他のグランドピアノとは異なり、
シラーの響板の振動部はケースから独立している。
シラーブランドは、ケーブルピアノ社の傘下で、有名なジュリアス・バウアーの特許を利用した
グランドピアノの生産ラインの一部となっていた。
シュート&バトラーピアノを製造していた彼らは、以下のブランド名を管理していた。
Cable, Bachmann, Carola, Inner Player, Conover,
Euphona, Schiller, Kingsbury and Wellington. |
SCHILLER. J
J. SCHILLER

画像クリックでHPへ戻る |
SCHILLER.J シラー?シーラー?(読み方不明) ドイツ(ベルリン) 詳細不明
ピアノまくり(蓋部分)のブランド表記部分 →★
画像はすべて「匿名希望様」からご寄稿頂きました。ありがとうございます!
匿名希望様からの情報によりますと、このピアノは今から50年以上前、
「アメリカ屋楽器店」で購入されたとのことです。 |
| SCHILLING, FR. |
シュトゥットガルト(ドイツ) Stuttgart
その他詳細不明 |
|
SCHIMMEL



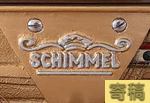
画像クリックでHPへ戻る
|
シンメル 旧東ドイツ(ライプツィヒ) 創業1885年
ウィルヘルム・シンメル/ヴィルヘルム・シンメル (Wilhelm Schimmel)によって1885年に創業。
アップライトの小型化を成し遂げたメーカーで知られています。
日本のヤマハがかつて代理店になったこともあります。
現在の主要株主は中国のパールリバー・ピアノグループである。
<歴史>
西ヨーロッパで最大規模のピアノ製作会社になったシンメル社は、1885年5月2日にライプツィヒの
ヴィルヘルム・シンメルによる小さな工房からスタートしました。
シンメルは家具職人の見習いだったが空いた時間にヴァイオリンを作っていた。
その後、ライプツィヒの有名なピアノ製作会社シュティッヒェル社でピアノ製作の技術を学ぶ。
独立後、シンメルは身につけた技術を大いに発揮していったという。
シンメル社は1891年からライプツィヒ・ロイトニッツ工場で生産していたが、会社が大きくなっていき、
1897年にはそこも手狭になったため、さらに広いライプツィヒ・シュテッテリッツの工場へ移転した。
シンメルピアノはザクセン=ヴァイマル大公の宮廷御用達楽器にも選ばれ、1909年にはルーマニア国王にも
ピアノを納めるようになった。
1914年には1万台を超えるピアノを製作したが、第一次世界大戦と、1920年代にドイツを襲った経済危機で
拒まれることとなった。その後、1927年に会社の経営はヴィルヘルム・アルノー・シンメルに引き継がれた。
ヴィルヘルムは生産拠点をブラウンシュヴァイクへ移したが、市場の崩壊に伴ってドイツのピアノメーカーである
株式会社ドイッチュ・ピアノ・ヴェルケと提携するも、この提携はうまくいかず1931年にシンメル社は
ドイッチュ・ピアノ・ヴェルケ社と決別し、社名を有限会社ヴィルヘルム・ピアノフォルテファブリークへ変更。
シンメル社の工場は第二次世界大戦中も生産を続行することが出来た。
それは超小型のアップライトピアノを作るなど、アルノー・シンメルが多くのアイディアを意欲的に
実現していったからである。
1944年に工場は火事で焼けてしまい、その再建には4年を費やしたが、1948年にシンメル社は再び
見本市に製品を出品するようになる。ドイツのピアノ業界が困難な時代にあったにもかかわらず、
シンメル社は1950年代に、プレキシグラス・グランドピアノのような衝撃的なデザインのピアノを製作し、
成功した。(※プレキシグラス/Plexiglas とはアクリル樹脂のことで、ドイツでの商標名)
1961年にニコラウス・ヴィルヘルム・シンメルが会社を引き継ぎ、ドイツのこの上質な伝統は第三世代へ。
1966年に新工場が建設され、さらにコンサートホールと展示場を併設した大きな工場の建設が決定した。
そしてこの一大プロジェクトは1980年についに完結し、同年、シンメル社は新工場で1万台のピアノを生産し、
その中の1000台はエラール(Erard)、ガヴォー(Gaveau)、プレイエル(Pleyel)等のブランド名だった。
(※シンメル社は、1970年~1993年までこれらのブランドのピアノも生産していたためです)
1961年、フランスのガボー・エラール・プレイエルを買収、
約20数年間にわたりプレイエルのピアノも生産しました。
アメリカ向け生産が激減したことにより、2009年に破産手続申請。
現在は再建がすすめられているとのこと。
※シンメルピアノははBVK認証を受けています(詳しくはこちら
→★)
一番下のトレードマーク画像は「匿名希望様」からご寄稿頂きました。ありがとうございます!
<附録>
シンメルピアノ 製造番号/製造年代 対照表(1894年~2000年) →★
シンメル公式サイト:http://www.schimmel-pianos.de/welcome.html
<以下、ウィキペディアより引用抜粋>
ヴィルヘルム・シンメル・ピアノフォルテファブリック(Wilhelm Schimmel Pianofortefabrik)GmbH、
通称シンメルはドイツのピアノ製造会社である。
生産数が多く、ドイツ最大のピアノメーカー。クリスタル・ピアノの開発などでも知られる。
数世代にわたってシンメル家による同族経営を続けている。
現在の主要株主は中国のパールリバー・ピアノグループである。
1885年、ヴィルヘルム・シンメル (Wilhelm Schimmel) によってライプツィヒで創業され、
1939年にブラウンシュヴァイクに移転した。アップライトピアノの小型化を成し遂げたメーカーであり、
大量生産の利を生かし普及価格帯からのラインナップを持つ。
クリスタル・ピアノやルイジ・コラーニのデザインした "Pegasus" ピアノ等も製造する。
かつてヤマハが日本代理店であった。
1961年にフランスのガヴォー・エラール・プレイエルを買収、25年間、プレイエルのピアノを生産した。
2009年8月に経済危機を受けて破産手続きを申請した。特に米国向けの受注が激減したことが要因となっている。
2010年4月、会社が財政的に再建された後、再び支払能力があり健全となり、ドイツ当局による保護状態が解かれた。
2010年5月、ブラウンシュヴァイクのブラウンシュヴァイク大聖堂で125周年の特別式典が開催され、
いくつかの新モデルが発表された。
2016年1月、中国のパールリバー・ピアノグループがシンメルの株式の90%以上を取得した。 |
| SCHINDHELM |
詳細不明 |
| SCHINDLER |
詳細不明 |
| SCHIRMER & SON |
詳細不明 |
SCHLOGL
SCHLÖGL


画像クリックでHPへ戻る |
シュレーゲル SCHLOGL(SCHLÖGL)
チェコスロバキア製 (イフラヴァ:都市名)1871~
詳しくは、リガー・クロスの項目を参照
|
|
S. SCHMIDT
SCHMIDT



画像クリックでHPへ戻る
|
シュミット S.SCHMIDT
製造:日本ピアノ製造株式会社(磐田郡袋井市)
鉄骨部分のロゴにはN.P.Cとありますね。
トレードマークには珍しく、逆三角形の形をしています。
1台しか調律したことはありませんが、まさに昭和を感じるピアノですね♪
シュミットの蓋(まくり部分)にあるブランド名称メインマーク
→★
シュミットのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★ |
SCHMIDT CART
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
SCHMIDT CART シュミット・カルト ドイツ 詳細不明
|
SCHMIDT FLOHR
SCHMIDT-FLOHR
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
SCHMIDT FLOHR シュミッド・フェアー スイス 詳細不明
|
SCHMITT
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
シュミット アトラスピアノ製造株式会社 |
SCHMITT
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
SCHMITT シュミット フランス 詳細不明
|
| SCHMITZ |
詳細不明 |
SCHNABEL




画像クリックでHPへ戻る |
SCHNABEL シュナーベル/(シュナベル)
※ブランドスペルは”SCHUNARBEL”という表記の資料もありますが、SCHNABELが正しいです。
製造:三益楽器株式会社(韓国)
販売:レスターピアノ製造株式会社(浜松)、トニカ楽器製造株式会社
機種バリエーション:SU-300、SU-200等
シュナーベルの保証書 →★
左記下3枚と、保証書の画像はこのたび「匿名希望様」からご寄稿頂きました。
たくさんの画像をご寄稿頂きまして誠にありがとうございました!
※参考
下記に列挙するブランドはすべて同じ雰囲気のトレードマークとなっており、どれも韓国製造と思われます。
REID-SOHN、KAFMANN、SAMICK、SCHNABEL、WEINBURG、U. WENDELL、UHLMAN SUPER |
SCHNAEIDER
※下記画像は参考

画像クリックでHPへ戻る |
SCHNAEIDER シュナイダー
大和楽器製造株式会社
新レスターピアノ製造株式会社(当時の住所:浜松市竜禅寺町809/現在地名:浜松市中区龍禅寺町)
<左記トレードマーク画像は参考>
シュナイダーのトレードマークは左記レスターのマークとほぼ同じですが、
”LESTER”の部分が”SCHNAEIDER”になっております。 |
| SCHNELL, R.A. |
詳細不明 |
SCHOENBERG


画像クリックでHPへ戻る |
SCHOENBERG
シェーンベルグ(シェンベルグ) ※ショエンベルグと発音表記する情報もあり
富士楽器製造(浜松)、ベルトーンピアノ製造株式会社
※現在は中国か韓国製造
当初、富士楽器のブランドはこのシェーンベルグであった。
ベルトーンになってから良くなったと言われている。
初代社長野田秀治氏によって戦後もしばらく作られていたが、必ずしも秀作とは言えなかったが、
ベルトーンになって面目を一新した。
ご寄稿頂いた左記画像のシェーンベルグの推定購入時期は昭和18~25年ぐらいとのことです。
ピアノ本体は漆塗り、鍵盤は象牙で、鍵盤数は一般的なピアノの88鍵より少し少ない85鍵だそうです。
画像は匿名希望様からご寄稿頂きました。ありがとうございます!
近年製造の「SCHOENBERG」は日本製造ではなく、中国か韓国製造のようです。
機種としてはSC-213などの機種です。
調律師ならすぐ分かりますが、マフラーバーの形状や記録カードが日本製とは違います。
中国は近年、過去にあった日本や世界のピアノブランドの商標権を買いまくっています。 |
SCHOENHUT


画像クリックでHPへ戻る |
SCHOENHUT シェーンハット
シェーンハットカンパニー 創業1872 年(ピアノメーカーではなくトイピアノメーカーです)
創業者:アルバート・フレデリック・シェーンハット(1849年生-1912年没)ドイツ系の移民起業家です
リアルストリングス(本物のピアノ線)を使った機種も過去に販売していたことがあったので掲載しました。
当時販売していたこのリアルストリングスを使ったトイピアノは44鍵盤(3.5オクターヴ)という
ピアノとしては超小型で、なんとアップライトピアノとグランドピアノの両方ありました。
そしてもちろん調律が必要なトイピアノでした。詳しくはリアルストリングスのカタログを参照 →★
トレードマーク画像とカタログ画像は匿名希望様からご寄稿頂きました。ありがとうございます!
<歴史>
ドイツ系移民のアルバート・フレデリック・シェーンハットはおもちゃ工房の家に生まれました。
シェーンハットは小さい頃にトイピアノを製作したのをきっかけに、トイピアノを作る会社を
アメリカのペンシルベニア州フィラデルフィアで設立し、アメリカのトイピアノ最大手となりました。
シェーンハットカンパニーはトイ・ピアノ以外にもさまざまな子ども向け楽器を製造しています。
ちなみに現在、このリアルストリングスを使ったトイピアノは販売しておりません。 |
SCHOLZE
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
SCHOLZE ショルツ
チェコスロバキア製 (現在:チェコ共和国) 現在はペトロフ社グループのブランド
SCHOLEの歴史は、19世紀後半に始まります。
シュルクノフスコ地方で最初のピアノ工場を設立したフランク・ショルツは、1853年に生まれた。
彼は技術的に優れているだけでなく、音楽的にも才能があり、彼はすぐに楽器を作り始めた。
彼がピアノを作るようになったのは、ウィーンのグランドピアノを小型化することに成功したことがきっかけだった。
ドイツで経験を積んだ彼は、1876年にシュルクノフスコ地方に自分のピアノ工場を設立した。
その後、ヴァルンスドルフに移り、アップライトとグランドのための新しい工場を建設した。
ショルツの高品質なピアノは、南アフリカ、アルゼンチン、メキシコ、ウラガイ、トルコ、
そしてヨーロッパ全土と、国内外でよく売れた。
ショルツは、4人の息子たちにピアノ職人としての技術を学ばせ、
海外の企業(イギリスのスタインウェイ、ベルリンのベヒシュタイン)で経験を積ませ、
近代的な製造方法を学ばせた。
1914年に帰国した息子たちは、イリコバのピアノ工場を経営するために入社した。
第二次世界大戦中には、従業員が50人にまで減少しました。
戦後、会社は接収されたが、任命された国家管理者の下で事業を継続した。
1948年、会社の資産はTovárna na piana a varhany v Hradec Královéという国有化された企業に譲渡された。
PETROF社は、現在もショルツピアノを製造しています。
ショルツピアノは、フラデツ・クラーロヴェにあるPETROFの開発工房で設計され、
PETROFの従業員の技術的な監督のもと、中国でライセンス生産されています。 |
| SCHOLZE-GEORGSWALDE |
チェコのプラハ駅にあるストリートピアノがこれ
詳細不明 |
SCHOMACKER
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ショマッカー アメリカ(ペンシルバニア州フィラデルフィア) 創業1838年
1838年、ウィリアム・ボサートとヨハン・ハインリッヒ・ショマッカーは、
ペンシルバニア州フィラデルフィアで「ボサート&ショマッカー」というピアノ製造会社を始めた。
数年後の1842年、ボサートとショマッカーはそれぞれの道を歩み、
ヨハン・ハインリッヒ(ウィーンからアメリカに移住した際にジョン・ヘンリーと改名)が
ショマッカー・ピアノ社を設立した。
1855年、会社が成功して成長していたので、ジョン・ヘンリーはビジネスをより大きな建物に移し、
この1年以内に会社を法人化したのである。
1864年には、H.W.グレイ大佐がショマッカー・ピアノ・カンパニーの社長になり、
ジョン・ヘンリーの息子のヘンリーが会社の秘書になった。
堅実な経営を続けていたJ.H.ショマッカーは、1875年に亡くなる3年前の1872年に引退した。
ヘンリー・ショマッカーは、会社がフィラデルフィアのワナメーカー・ストアーズに売却された後も、
秘書として活躍した。ワナメイカー社が買収したとき、ヘンリーは60歳前後だったが、
彼は数年後に引退するまで勤め上げたのである。
ワナメーカー・ストアーズは、1940年代初頭までショマッカー・ラインのピアノを生産し続けた。
そして、約100年の歴史を経て、ショマッカー社の製品は製造中止となりました。
ショマッカーのピアノで最も興味深いのは、1876年に当時の社長である
H.W.グレイ大佐が取得した特許であろう。
グレイ大佐は、電気メッキと呼ばれる方法でピアノの弦に金メッキを施す技術を開発しました。
ショマッカーのピアノは「金の弦」と呼ばれていたことで有名である。
1853年にニューヨークで開催された万国博覧会や、1876年にフィラデルフィアで開催された
百年記念博覧会では、ショマッカーの楽器は数々の賞を受賞し、メダルを獲得している。
当時、多くの著名なピアニスト、作曲家、政治家(ユリシーズ・S・グラント大統領を含む)が愛用した
ピアノとして、ショマッカーは豊かさと技術を連想させる非常に上質で評判の良いブランドだった。
およそ100年にわたって製造されたショマッカーピアノには、様々なデザインやスタイルがあり、
ケースワークは世紀を超えてデザイントレンドの変化に合わせて進化してきた。 |
SCHONBRUNN
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
SCHÖNBRUNN (SCHONBRUNN) シェーンブルン/(シューンブルン)
宜昌金宝楽器製造(中国湖北省宜昌市)/Yichang Jinbao Musical Instrument Manufacturing Company
シンガポールに販売店があるようですが詳細不明 |
| SCHOTT MAXIMILIAN |
MAX. SCHOTT
詳細不明 |
| SCHRAMM&SONS |
詳細不明 |
SCHREIBER
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
SCHREIBER シュライバー フィリピン 詳細不明 |
| SCHRÖDER, C.M. |
詳細不明 |
SCHROEDER
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
シュローダー アメリカ(ニューヨーク、ペンシルベニア) 創業1905年頃
Schroeder Brothersは、ニューヨークとペンシルバニアの両方に工場を持つピアノメーカーである。
シュローダーは、1905年頃にピアノの製造を開始し、1915年頃に閉鎖したと思われる。
残念ながら、このメーカーについてはあまり知られておらず、製造台数は少なかったようです。
シュローダーブラザーズのピアノは現在ではほとんど残っておらず、あまり知られていない。
アップライトピアノやプレーヤーピアノを製造していたが、製造はわずかと推測されます。
アンティーク・ショー(日本で言う骨董市)では、シュローダー・ブラザーズのピアノを見かけますが、
製造期間が短かったこともあり、滅多に見ることはないピアノのようです。 |
SCHROTHER
SCHRÖTHER
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
SCHROTHER シュロッサー ドイツ 詳細不明 |
| SCHRUDER |
詳細不明 |
SCHUBERT

画像クリックでHPへ戻る |
シューベルト アメリカ(ニューヨーク) 創業1880年
シューベルト・ピアノは1880年にニューヨークで設立された。
1885年には法人化し、ピーター・ダフィーが社長に就任した。
シューベルト・ピアノ社は、ニューヨークの5番街という歴史的な場所を誇っていた。
シューベルトピアノとプレーヤーピアノ「メロディスタイル」の販売と製造で知られていた。
1932年、レスター・ピアノ・カンパニーがシューベルト社を買収し、1937年に社名が廃止された。
最も人気のあるモデルのひとつであるマンドリン・ピアノの成功により、
シューベルト・ピアノ社は初期のピアノメーカーの中でも最も市場性の高いメーカーのひとつになり、
すぐに知名度が上がったとされる。
シューベルトは、アップライトピアノとグランドピアノの両方を製造していたが、
それらのピアノはたいてい、細部に至るまで複雑な彫刻が施されていた。
これらのピアノは当時としては高価なものであり、最高の職人技と材料だけで作られていた。
シューベルトのピアノは、よくできていて贅沢な作りだったと考えられています。
ニューヨークの中心地にあったことから、シューベルトは当時のエリートや著名な音楽家、
音楽愛好家を対象としていた。
シューベルトピアノは、パリ万国博覧会、ロッテルダイン万国博覧会、シカゴ万国博覧会で賞を受賞した。
シューベルトピアノは、真ん中のペダルを踏むとピアノのハンマーと弦の間に
金属製のタブが落ちる仕組みのアップライトピアノ「マンドリン・ピアノ」でよく知られていた。
この新しい機器の技術のおかげで、その音は他の多くの現代のピアノのモデルとは異なる
大変ユニークなものとなった。
このマンドールピアノとその音は、「リンキートンク」又は「ホンキートンク」と呼ばれるものは、
ピアノの音として広く知られるようになり、何十年にも渡って各地のサロンやバーで使用された。
画像は匿名希望様からご寄稿頂きました。ありがとうございます! |
SCHUERMAN
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
キンボール社(KIMBALL)が取り扱ったブランド
→詳しくはKimballの項目へ |
| SCHUETZE & LUDOLFF |
詳細不明 |
SCHUG & SÖHNE
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
詳細不明 |
SCHUHITTEN
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
シュエヒテン (有)及川ピアノ製作所 |
| SCHULTZ & SONS |
詳細不明 |
SCHULZE & SOHN
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
シュルツ・ゾーン
ドイツ(ZWICKAU/ツヴィッカウ)
※ドイツ語の「SOHN」は、英語で言う「SON」です
ツヴィッカウ(Zwickau)は、ドイツ連邦共和国のザクセン州(旧ケムニッツ行政管区)にある都市です。
その他詳細不明 |
SCHULZE POLLMANN

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
SCHULZE POLLMANN
シュルツ・ポールマン(シュルツェ&ポールマン)
現在東洋ピアノで販売?ピアノの発祥はイタリアの"フィレンツェ"にて誕生。
当時のヨーロッパは王侯貴族に職人が宝石・家具・絵画・革製品などを作成していました。
シュルツ(ドイツ人)とポールマン(イタリア人)は伝統の家具職人の経験を活かして、
良質のヨーロッパ木材だけを使用した「家具との調和」を提唱し製作、
木目が表現する妙技は絶賛の一言に尽きます。
寄せ木手法の"ピーコックウォルナット"は木工技術の集大成。
饗版にはバイオリンのストラディバリウスで有名なイタリア産
フィーメ地方の「フィーメとうひ材」を使用しています。
|
SCHUMANN

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
SCHUMANN シューマン
アメリカ エスティピアノ (ESTEY PIANO CORPORATION)
珍しく大音楽家の名前がその名称として付けられているピアノで、エスティピアノに属する。
なんと100年以上このブランド名で作り続けているといいます。
すべてのピアノにダイレクトブローアクションが付けられ、レスポンスと共に音色の点でも
優れていると伝えられるピアノです。
Estey Piano Corporation
→詳しくは「Estey」の項目へ
<別解説>
1847年、イリノイ州にシューマン・ピアノ・カンパニーが設立された。
1885年にはW.N.バンマートルが株主となり、1895年には彼自身も独自のデザインや
ピアノ工学のアイデアを生かしたピアノ作りに興味を持つようになった。
1900年には、会社の支配権を購入し、会社の将来を決定する権限を持つようになった。
彼が社長に就任すると、シューマンピアノは急成長を遂げ、1903年にはイリノイ州ロックフォードに
大きな工場を移転せざるを得なくなった。
世界大恐慌の後、シューマンはエスティ・ピアノ社に売却され、その後キンボール社にも売却された。
現在、シューマンの名前は、南京シューマンピアノ製造有限公司のアジア輸入ピアノのラインで
生産されたピアノに使われている。
シューマンは、アップライトピアノ、プレーヤーピアノ、ベビーグランドなどのフルラインを製造し、
1900年代初頭に人気を博した。
シューマンピアノは、ヴァンマットルの指導のもと、バーンズ&サンズやプリムスのピアノも製造していた。
シューマンピアノは(2006年の時点で)再び復活し、中国の南京市にある真新しい
Moutrie社の工場で作られている。ハンマーはレンナー、弦はドイツ製を使用しているとのこと。 |
SCHUMANN
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
SCHUMANN/シューマン
宜昌金宝楽器製造(中国湖北省宜昌市)/Yichang Jinbao Musical Instrument Manufacturing Company
シンガポールに販売店があるようですが詳細不明 |
SCHUNARBEL
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
SCHUNARBEL シュナーベル トニカ楽器(浜松) 詳細不明
株式会社トニカ楽器の当時の住所:浜松市浅田町1666番地 |
| SCHUPPE & NEUMANN |
詳細不明 |
| SCHÜTZ & CO. |
詳細不明 |
| SCHÜTZE |
詳細不明
※この下の「SCHUTZE, GEBR」と同じかブランドか?不明 |
SCHUTZE, GEBR
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
SCHUTZE,GEBR 読み方不明 ドイツ 詳細不明 |
SCHWALMEN
SCHWÄLMEN |
この下のSCHWARMENとは違うピアノなのか??詳細不明 |
SCHWARMEN & SONS
SCHWÄRMEN & SONS

画像クリックでHPへ戻る |
シュベルマン&サンズ
アイケー・ピアノ社(浜松市中田町)
アポロ販売株式会社(発売元)
スペルは「SCHWALMEN」ではなく「SCHWARMEN」です ※「L」ではなく「R」
このシュベルマンピアノは「アポロ販売株式会社」からの依頼で製造されました。
尚、グロトリアン(GROTORIAN & SONS)やローゼンクランツ(ROSENKRANZ)と
同じトレードマークのようです。
この2羽の鳥が入ったトレードマークが「アイケー・ピアノ社」のものかと推測。
アイケー・ピアノ社は1970年代~80年代に事業展開していました。
画像は匿名希望様からご寄稿頂きました。ありがとうございます!
機種バリエーション:SK-80等 |
SCHWANDER
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
シュワンダー イギリス? 詳細不明 |
SCHWARMEN&SONS
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
Schwarmen&Sons シュベルマン&サンズ
IKピアノ?浜松? IKピアノはもともと鍵盤を製造していた会社?ネットからの情報(詳細不明)
ローゼンクランツ(ROSENKRANZ)と同じメーカーとの情報を見つけたが詳細不明
そもそもローゼンクランツ(ROSENKRANZ)はウイスタリアピアノ製造ではないのか?情報求む |
SCHWECHTEN
G. SCHWECHTEN
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
GEORG SCHWECHTEN ゲオルク・シュヴェヒテン(シュベヒテン)
1853年創業 ドイツ(ベルリン)
鍵盤蓋のブランド銘柄部分「G. SCHWECHTEN」下には、
「Hof-Piano-Forte-Fabrikant, Berlin.」と入っております。
<以下、ウィキペディアより引用抜粋>
ゲオルク・シュヴェヒテン(Georg Schwechten、1827年2月4日シュトルツェナウ生、
1902年8月19日ベルリン没)は、19世紀後半のベルリンの卓越したピアノ製作者の一人である。
オリジナルの保存状態のよい、または修復されたシュヴェヒテンのアップライトピアノおよび
グランドピアノは今でも称賛に値すると見なされており、珍しい。
ゲオルク・シュヴェヒテンは1853年に兄のハインリッヒ・シュヴェヒテン(1812年-1871年)によって
1841年にベルリンKoch通り11番地で開業されたスクエア・ピアノの工房を引き継ぎ、
弟のヴィルヘルム(1833年-1900年)と共に1853年にG. シュヴェヒテン社を創業した。
1861年、ゲオルクはKoch通り60番地に工場を建設し、その後隣の不動産も取得した。
G. シュヴェヒテン社のピアノはすぐに大きな名声を得た。
ゲオルクの死後、娘のAnna Maria Clara Fiebelkornが会社を引き継いだ。
彼女はSchwechtenhausを建設した。
ヴィルヘルムの息子フリードリッヒとヴィルヘルム(1880年-1954年)は1910年に
Pianofabrik Schwechten & Boesを設立した。
(1911年からGebr, Schwechten、1912年からFriedrich Schwechten、ヴィルヘルム通り118番地)
1918年、2人とも親会社に戻った。ピアノ生産は1854年に始まり、1925年まで続いた。
シュヴェヒテンピアノは1839年にゲオルク・シュヴェヒテンの兄ハインリッヒの店で始まった。
ゲオルク・シュヴェヒテンは1853年にベルリンで店を構え、優美な手作りピアノを専門とした。
この素晴らしいピアノはゲオルクが死去した1902年に終わった。
「Schwechten」のブランド名は中国の上海鋼琴有限公司(Shanghai Piano Co. Ltd.、1895年創業)
によっても使用されていたが、ドイツのSchwechtenとの関係は不明である。 |
SCHWEIGHOFER
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
SCHWEIGHOFER 読み方不明 イギリス? 詳細不明
|
|
SCHWEIZER STEIN
SCHWEIZERSTEIN



画像クリックでHPへ戻る
|
SCHWEIZER STEIN (SCHWEIZERSTEIN)
シュバイツァスタイン/(シュバイッツァスタイン)/(シュバイツァースタイン)
製造元:ワールドピアノ製作所(ワールド楽器製作所)(磐田市)
製造元:日本シュバイツアピアノ製作所/(株)シュバイツァ技研(磐田市)
製造元:株式会社 ビオン楽器製作所
発売元(当時):原ピアノ(東京原宿)
昭和30年、磐田市にワールドピアノ製作所を設立して作ったピアノ。
昭和48年に日本シュバイツアピアノと社名を変更した。
東京では原宿の原ピアノが販売に当たった。
シュバイツァー博士が命名したと伝えられ、世界9カ国に特許を持つ特殊な考案の刻み目の入った響棒を使い、
また、その他、スパイラル響板なども使った特殊な楽器である。
※特殊な響板 山本DS響板
手彫りでダイヤモンドカットされた響棒を配列し、その効果は普通響棒の3~4倍の音波記録を持ち、
同じ響板面積のグランドピアノ以上のダイナミックな音色と音量を発揮する。
全音域が平均化される特色を持つとのこと(シュバイツァスタインのHPより引用)
シュバイツァースタインのまくり(蓋部分)にある美しいオールドイングリッシュの書体 →★
トレードマーク画像(上の旧タイプ)と、まくり(ピアノ蓋部分)にある銘柄ブランド部分の画像は
このたび「匿名希望様」からご寄稿頂きました。ご寄稿頂きまして誠にありがとうございます!
機種バリエーション:HU-200等
ワールドピースの項も参照。
<附録>
シュバイツァスタインピアノ 製造番号/製造年代 対照表(1974年~1999年) →★ |
SCHWESTER



画像クリックでHPへ戻る |
SCHWESTER シュベスター
製造:協信社ピアノ製作所(東京蒲田)、シュベスターピアノ製造KK(東京蒲田)
1978年(昭和53年)に移転→(有)エスピー楽器製作所(静岡県磐田市豊田862-2)
※現在の正規販売代理店は有限会社エスプレシーボ(横浜市)
※「SCHWESTER」とはドイツ語で「姉妹」の意で、「手作り」にこだわり、
日本国内唯一の手作りピアノで、2016年まで完全受注生産で作られていました。
松崎妙【読み:まつざき かのお】氏は、木工技術者の松川賢一氏、塗装の小原太作氏の3人の技術者によって、
昭和4年(1929年)に、東京蒲田に協信社ピアノ製作所(北糀谷工場)が設立され、
シュベスターのブランドでピアノが作られた。松崎氏はアクション製作、張弦を担当した。
シュベスターは手作りの楽器として美しい音を誇ってきた。
この協信社ピアノ製作所がシュベスターピアノ製作所の前身である。
創始者である松崎妙氏は、1899年愛知県生まれ。
1912年頃に東京大井町にあった東京楽器研究所に入っている。
その後関東大震災で職を失うが、東京蒲田楽器製作所(蒲田ピアノ)と松本ピアノで製造技術を磨いている。
当時ピアノの価格は法外に高かった。
その頃ヤマハのアップライトは500円、800円、1000円、1200円の4種類であったと
伝えられているが、協信社では、1000円のピアノ1種類だけを、月1台から1.5台作り続けたという。
当時は物品税もない時代である。試みに協信社の1ヶ月の損益計算を分析すれば、
次のように明快に黒字を生むものであった。
1台のピアノの材料費は、木材が10円、ワイヤーが10円、アクションが国産で35円、
外国製で70円、その他を含めても100円ぐらい。
製品は卸値で相手が買いに来た時は定価の半額、逆に売り込んだ時は5割5分引きの450円で売れた。
つまり1台売れれば一人が80円づつの給料を受け取っても、なお110円から160円の利益が残ったのです。
協信社はこのようにして次第に大きくなっていったのである。
シュベスターは調律師を通じての受注生産がほとんどで、過剰在庫を抱えることもなかった。
シュベスターの響板は北海道のエゾ松を専用に使い、輸入品のスプルースは全く用いない。
その理由はスプルースは材質が硬く、音のダイナミックレンジが狭いためであるという。
なお、響板の加工は一切手加工で行われ、これによりピアノに魂を吹き込む。
エゾ松以外の材料を使わないのはこの会社だけであると聞く。その他レンナーハンマーを使用している。
シュベスターピアノはベーゼンドルファーと同様に生産台数が伸びない珍しいメーカーであった。
創業以来の生産台数は50年でわずか2万台である。
シュベスターピアノの製造番号付けには少し工夫が凝らしてあり、
アップライトの場合、上から2桁の数字が昭和○○年とすぐ分かるようになっています。
※平成に入っても数字を加算すれば解読可 (ちなみにグランピアノドの場合は1984年までならこの方式で解読可)
<附録> シュベスターピアノ 製造番号/製造年代 対照表(1981年~2012年) →★
<簡易社史年表>
1929年(昭和4年):東京蒲田で松崎氏、松川氏、小原氏の3人の技術者によって協信社ピアノ製作所を設立。
1958年(昭和33年):シュベスターピアノ製造(株)へ名称変更
1978年(昭和53年):静岡県磐田市に移転
1981年(昭和56年):(有)エスピー楽器製作所設立
<シュベスターピアノの歴史とシュベスターピアノ詳細>
初期の頃のシュベスターピアノは松本ピアノを真似て作られていました。
ちなみに松本ピアノは旧東ドイツのツィンマーマンピアノを真似ての製作だったようです。
シュベスターピアノ第1号機は東京田園調布の病院(佐治家)へ納入されました。
その後昭和50年代に修復された後、ピアノは武蔵野音楽大学(練馬区江古田)へ寄贈されました。
そのピアノのブランド名は「GARTEN」、現在同大学構内にある楽器ミュージアムに展示保存されています。
※GARTEN(ガルテン)に関する詳細は→GARTENの項目へ
その後、シュベスターピアノは1952年、芝白金の調律師斉藤義孝氏の指導により、
ウィーンの名器ベーゼンドルファーのアップライトをコピーしたものに変更されました。
ベーゼンドルファーをモデルに設計されているので、弦の張力が低く、
ピアノ全体にかかる緊張力も軽減されているので、支柱や響板などに経年変化が少ないそうです。
尚、グランドピアノはスタインウェイの”D型”をコピーしたものと言われています。
第二次世界大戦中はピアノの製造を不可能に追いやりました。
戦時中、他社大手のピアノメーカーは飛行機の部品などを作っていましたが、
シュベスターピアノでは魚雷の弾頭と内部の火薬筒を製作していました。
材料不足のため、木材で作り、漆で塗り固めたと伝えられています。
敗戦後はさらにピアノ製作という本来の志から離されてしまいましたが、鍋のふたや、下駄、机、
タバコを巻く機械、椅子、洋服ダンスなど、あらゆるものに手を出し食いつなぎました。
戦後最初のピアノを作ったのは1950年で、ビリヤードの台に使うラシャ
(ビリヤード台の表面に使う縫い合わせのない大きな布)などの代用品を集めて作り、
これが出荷されたときは喜びのあまり、全員で万歳を叫んだと伝えられています。
ちなみに シュベスターは現在も活動しているピアノメーカーとしては、ヤマハ、カワイに次ぐ
日本で3番目に古いメーカーとされております。
2016年、ピアノのフレーム(鉄骨)の在庫がなくなったため新規のピアノ製造は休止したとのことです。
機種バリエーション
■アップライトピアノ:No.50、No.51、No.52、No.53、No.54、301、303等
■グランドピアノ:G60等
<参考>
PRIMATONE(プリマトン)というピアノがありますが、これは横浜元町にあった大塚ピアノ商会のブランドで、
このピアノもシュベスター(旧:協信社ピアノ製作所の蒲田の北糀谷工場で製造された兄弟ブランドです。
その他「HASHIMOTO(ハシモト)」も協信社ピアノ製作所の製造です。→詳しくはHASHIMOTOの項目へ
シュベスターピアノ第1号機(1929年/昭和4年製造)「GARTEN」については→GARTENの項目へ
シュベスターのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★ |
SCOTSMAN
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
SCOTSMAN スコットマン 中国
※ニエアール/ニエアル NIEERの項目参照
|
SEBASTIAN SOMMER
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
セバスチャン・ゾンマー/セバスチャン・ソンマー/セバスチャン・ソマー
アメリカ(ニューヨーク) 創業1897年頃
セバスチャン・ゾンマー・ピアノ・カンパニーは、1897年頃にニューヨークで設立されました。
セバスチャン・ゾンマーの楽器については、生産数が少なかったこともあって、ほとんど情報がありません。
セバスチャン・ゾンマー・ピアノ社が製造したアップライトピアノは、学校や教会などで多く使用されました。
ゾンマーの楽器は、均一な音を出すことができ、非常に丈夫でよくできていました。
公共の場でほぼ独占的に使用される場合には必須の品質です。 |
SECILIA
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
SECILIA セシリア
アトラスピアノ製造株式会社 詳細不明 |
SEEBURG
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
1907年にシカゴで設立されたJ.P.ゼーバーグ・ピアノ・カンパニーは、コイン式ピアノ、オーケストラ、
シアター・オルガンを専門とする会社である。
ゼーバーグは、自動演奏楽器の製造にいち早く着目し、成功を収めた企業である。
ゼーバーグは自社の楽器のほかに、ハドルフ、ゼーボルド、エドモンド・グラムのピアノを使って自動演奏を行った。
しかし、世界大恐慌が始まると、ピアノの需要が減り、自動演奏ピアノの生産を中止するという
苦渋の決断をした。ピアノの生産が減る中、J.P.シーバーグはジュークボックスの生産を開始し、
何十年も人気を維持した。
自動演奏ピアノの先駆者として知られるJ.P.ゼーバーグは、高品質な楽器だけを
自動演奏することを重視し、製品にJ.P.ゼーバーグの名を冠することを約束したのである。
ゼーバーグが自動化のために搭載した機構は、高品質で耐久性に優れたものであった。 |
| SEEGER |
詳細不明 |
SEIBU
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
セイブ
製造元:アトラスピアノ製造株式会社 発売元:西武 |
| SEIDEL, ROB |
詳細不明 |
| SEIDEL & SOHN |
詳細不明 |
SEIKŌ
SEIKO
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
SEIKŌ/SEIKO セイコー 精宏社ピアノ研究所/(精宏社ピアノ製作所?)
(”研究所”か”製作所”のどちらが正しいかは不明)
トレードマークは日本地図をモチーフにした珍しいデザインです。
※ブランドスペルは”SEICO”ではなく”SEIKO”です |
|
SEILER
SEILER, ED.

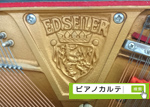

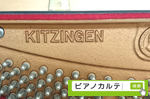
画像クリックでHPへ戻る
|
SEILER ザイラー ドイツ(旧西ドイツ) →現在は韓国の三益楽器(サミック)に買収され存続
家具職人で音楽家でもあったエドゥアルト・ザイラーは、自身の名を付けたピアノ会社を設立した。
ザイラーの目的は、プロの音楽家の要求に応えるピアノを作ることだけではなく、それらのピアノを通じて
「文化に造詣の深い中産階級の人々が容易に音楽に触れられるようにすること」でもあった。
<歴史>
創業1849年 ドイツのリーグニッツ(現在のポーランドのレグニツァ)で小さな会社としてピアノ製造を開始。
コンサートピアノのような高級品だけではなく大衆的で高品質なピアノを目指しました。
1870年までに1000台のピアノを製造し、2年後にはその2倍にもなった。
ピアノ作りの職人技を各方面から称えられ、1872年にモスクワの品評会で金メダルを獲得したことにより、
ザイラーの名声は一気に高まった。
1875年に創立者のエドゥアルトが亡くなると、1879年に息子のヨハネス・ザイラーが会社を引き継いだ。
ザイラーは120人のピアノ職人を雇い、世界中の見本市で賞を取る品質の優れたピアノを作り続け、
1898には25000台を超えるピアノを世に送り出した。
ザイラーピアノはウィーン、アムステルダム、メルボルン、シカゴ、ベルリン、ミラノなどの
コンペティションで次々に受賞し「ザイラー」というブランドを世界的な存在にしました。
1923年、ヨハネスの娘婿アントン・ドゥーツはヨハネスの跡を継ぎ、経営責任者として就任。
アントンはザイラーの成功を維持させ、435名の社員を抱えるピアノメーカーへと成長させ、
年間3000台のピアノを製造するまでになり、ドイツ東部で最大のピアノ工場となりました。
第二次世界大戦後、ザイラーはリーグニッツ(現ポーランドのレグニツァ)にある本社と工場を
手放すことになり、一家はデンマークへと逃れた。
1945年の混乱の中、アントンの息子ステファン・ザイラーはザイラーピアノのフレームと
設計図を修復するために人生をかけて取り組んでいました。
彼の努力によりザイラーのレグニツァモデルピアノの生産がデンマークのコペンハーゲンにて再開、
更には1962年ドイツ・バイエルン州のキッツィンゲン(KITZINGEN)に工場を再建することに成功。
1977年には工場を拡大してコンサートホールと研修施設を併設するようになった。
現在もザイラーピアノはキッツィンゲン工場にて生産されており、ザイラー一族のウルズラとマヌエラが所有。
この2人はメーカー独自の音を守ることに専念しています。
ザイラーのアップライトピアノには、特許を取得したスーパー・マグネット・レペティション・アクションが
採用されている。これは従来のアクションに用いられるスプリングに代わり、二つの磁石を使ったもので、
この磁石によって鍵盤が3分の1しか戻らないうちに次の打鍵が可能になるというものだ。
フレーム右上にはザイラー社縁の人たちの肖像画がデザインされているのが印象的です(写真中央)
ピアノ天板の裏側にはロゴマークと共に ”DER ECHTH SEILER” とあります
→★
ザイラーアクション →★ バーズアイメープル(バーザイメープル材)を使った美しいピアノ外装
→★
<附録>
ザイラーピアノ 製造番号/製造年代 対照表(1870年~2000年) →★
<以下、ウィキペディアより引用抜粋>
ザイラー・ピアノフォルテファブリック(Seiler Pianofortefabrik)GmbHは、
ドイツ・バイエルン州ウンターフランケン行政管区キッツィンゲンに本部を持つ
グランドピアノおよびアップライトピアノ製造業者である。
最初の工場は1849年にエドゥアルト・ザイラーによってシュレージエン州リーグニッツ
(当時はプロイセン王国の一部)に開かれた。
2008年以降、ザイラー社は三益楽器(サミック)によって買収され存続している。
ザイラー社は1849年にエドゥアルト・ザイラーによってニーダーシュレージエン州
リーグニッツ(現在のポーランド・レグニツァ)で創業された。
1873年、エドゥアルト・ザイラーは蒸気駆動の工場を建設し、1874年には100名を越える労働者を雇用した。
しばらくして、エドゥアルト・ザイラーは死去した。
1879年、兄弟のヨハネス・ザイラーがピアノ職人として修行し、1879年末に工場の技術管理を引き継いだ。
会社はドイツ東部で最大のピアノ製造業者になった。
第二次世界大戦の終わりに、ザイラー家と残っていた従業員は避難しなければならなかった。
当面の間は、コペンハーゲン(デンマーク)で生産が再開された。
1961年、ウンターフランケン行政管区キッツィンゲンに工場が再建された。
会社は数多くの技術革新を行い、特許を取得した。
自身の表現によれば、ザイラーは最も大きな製造の垂直的範囲(内製と外注の比率)を持つ
ドイツのピアノメーカーである。
1945年以降、ポーランドに位置していたザイラーの元の工場は1988年まで「Legnica」および
「Th. Betting」ブランドのピアノを製造していた。
1963年、ブラウンシュヴァイクのピアノ製造業者ツァイッター&ヴィンケルマンが
ザイラーグループに加わった。
高品質ピアノの全世界における売上の不振により、ザイラー社は2008年7月に破産を
申し立てざるをえなかった。2008年11月、会社と残った従業員のほとんどが韓国の楽器メーカー
三益楽器(サミック)によって買収された。
ザイラーのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★ |
SEILER & HELMAN


画像クリックでHPへ戻る |
SEILER & HELMAN
セイラー&ヘルマン(読み:ザイラー&ヘルマン?)
製造元:東洋ピアノ製造株式会社 その他詳細不明
トレードマーク画像は「匿名希望様」からご寄稿頂きました。ありがとうございます!
※上記、ドイツのザイラー(SEILER)とは関係はないです |
| SEILER. ED |
SELLER.ED 旧西ドイツ 同上
|
| SEILER, MAX |
詳細不明 |
| SEJUNG PIANO CO. |
詳細不明 |
SELENE

画像クリックでHPへ戻る |
SELENE セレネ?セレーネ?韓国製?
詳細不明 |
SERESARCH
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
SERESARCH セレザーク 製造:フローラピアノ製造(株)(浜松)
森健氏の指導があった。 |
SETTERGREN
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
SETTERGREN セッターグレン アメリカ SETTERGREN PIANO CO.
エスティ(ESTEY PIANO CORPORATION)のブランド
Estey Piano Corporation
→詳しくは「Estey」の項目へ |
| SEUFFERT |
詳細不明 |
SHANGHAI
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
SHANGHAI シャンハイ 中国
※ニエアール/ニエアル NIEERの項目参照
|
| SHATTUCK |
詳細不明 |
SHAW
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
Shaw Pianoは、1890年から1901年までペンシルバニア州エリーを拠点に活動していました。
下院議員のMatthew GriswoldがShaw Pianoの創業者兼社長で、2人の息子である
M. Griswold Jr.とMarvin Griswoldがそれぞれ副社長と財務担当を務めていた。
また、Matthew Griswold Sr.は連邦議会議員に2回当選し、
鋳鉄製の家庭用品やキッチン用品を製造するGriswold Manufacturing社を設立している。
Shaw Pianoは、1124 Peach Streetでスタートし、2年も経たないうちに
West 12th and Raspberry Streetにある4階建てのレンガ造りの工場ビルに移転した。
当初のShaw Piano社は、1901年に債権者から破産を迫られ、Chas .M. Stieffに売却された。
その後まもなく、ショー・ピアノの生産はメリーランド州ボルチモアにある
スティーフ社の工場に移された。
ショー・ピアノ社は、生産の質が良いとされる手頃な価格のピアノを販売していた。
ショー・ピアノのシリアルナンバーは1895年から1915年まで、スティーフのシリアルナンバーは
1930年頃までとなっています。
ショー・ピアノは他のピアノブランドに比べて生産台数が非常に少ない。 |
|
SHCHIED MAYERR



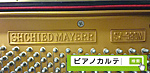
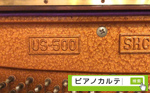


画像クリックでHPへ戻る
|
SHCHIED MAYERR & SONS/SHCHIED MAYERR
シードマイヤー
元々は浜松ピアノ製造株式会社で製造していたブランドで、
後に協立楽器の持ちブランドとして韓国で製造。
ドイツ製シードマイヤー(SCHIEDMAYER)とスペルが違うところに注目 (HとRが余計に入っています)
■ SCHIEDMAYER (本家ドイツ製のスペル)
■ SHCHIEDMAYERR (韓国製造のスペル) 何ともわざとらしいスペル変えです
同社が販売していたローレックスピアノと同系のピアノです。
名称は胡散臭いですが音色はさほど悪くはないです。ただし、ピアノ個体差の善し悪しはかなりあります。
その他詳細不明。
下から2枚の写真はグランドです。
シードマイヤーの保証書 →★ シードマイヤーで使用のアベル(ABEL)のハンマーヘッド
→★
シードマイヤー独特のアグラフ →★ シードマイヤーのまくり(蓋)部分の銘柄マーク
→★
シードマイヤーグランドのデカール →★
■機種バリエーション
KS-122M、KS127M、KS-133M、US-500など
SX-380、SG-157、SK3、SK2、嵯峨野など(協立楽器販売での機種)
シードマイヤーのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★ |
SHERLOCK-MANNING
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
SHERLOCK-MANNING PIANO CO.,LTD シャーロック・マニング
カナダ オンタリオ州クリントンで作られているピアノで、創業以来アップライト専門。
戦後は全製品をカナダ国内で販売・消化していたがその後輸出も展開したとの情報。
|
| SHERMAN, CLAY |
詳細不明 |
| SHERWOOD & SON |
アメリカ(ニューヨーク) 詳細不明 |
| SHIMA-JEHLE |
詳細不明 |
| SHIMLER |
詳細不明 |
SHIGERU KAWAI


画像クリックでHPへ戻る |
シゲル・カワイ/Shigeru Kawai
製造:株式会社 河合楽器製作所
グランドピアノのみの特別ブランド。
匠の技が凝縮されたグランドピアノとのことです。
一般向けグランドピアノとフルコンサートグランドの中間的ピアノという位置づけとなりますが、
SHIGERU KAWAI(SK-EX)は、2021年の第18回ショパン国際ピアノコンクールにおいて、
あの名だたるスタインウェイ&サンズ(476と300の2台)、ヤマハのCFX、ファツィオリのF278と
肩を並べる形でコンペティション演奏に使われ、三次予選まで使用されました。※ヤマハは二次予選まで。
SHIGERU KAWAIの響板にあるデカール →★
SHIGERU KAWAIのピアノ側面とまくり部分にあるブランドマーク →★
以前、浜松駅の新幹線コンコース(改札内)にあった誰でも自由に弾けるストリートピアノがあり、
私自身、実際に弾いてみたことがありますが、とても良い音色でした。
■機種ラインナップ:SK-2、SK-3、SK-5、SK-6、SK-7、SK-EX
シゲルカワイの公式サイトはこちら →★
シゲルカワイのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★ |
| SHINGHAI |
星海 →XINGHAI の項目へ |
SHINKO
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
SHINKO シンコー 新興楽器製造KK(長野県辰野町)
本社工場(当時):長野県辰野町2075番地
東京営業所(当時):東京都千代田区外神田2-18-21
大阪連絡所(当時):大阪府守口市西郷通3-18
ブランドスペルはSHINCOではない |
| SHINHAKKEN |
正しいスペルは、SINHAKKENです。
→SINHAKKEN「新白鍵」の項目へ |
SHONINGER
B. SHONINGER

画像クリックでHPへ戻る |
ショニンガー アメリカ(コネチカット州ニューヘブン) 創業1850年
1850年、バーナード・ショニンガーという人物がコネチカット州ニューヘブンに
ショニンガー・ピアノ・カンパニーを設立しました。
当初は「B.ショニンガー・カンパニー」と呼ばれていたが、1922年にバーナードから会社を譲り受け、
「ショニンガー・ピアノ・カンパニー」と改称した。
バーナードが経営していた初期の頃は、オルガンも製造していたが、
時代の流れや所有者の変更に伴い、ピアノの製造に特化するようになった。
1920年代初頭、事業は成功を収め、ピアノの中心地であるニューヨーク市に拠点を置くまでになった。
ショニンガー・ピアノ・カンパニーは、ニューヨークとニューヘブンの両方にオフィスと工場を持ち、
自社製品だけでなく、ヴォスラー、マロリー、フェルプスなどのピアノ製品も製造することができた。
時系列ははっきりしないが、大恐慌の最中、
Shoninger PianoはNational Piano Manufacturing Companyに買収され、
数年間生産を続けた後、生産を中止した。
しかし、ショニンガーの製造番号は1929年で途絶えていることに注意してほしい。
ナショナル・ピアノ・マニュファクチャリング・カンパニーが製造したショニンガー・ピアノは、
ハレット&デイヴィス社のピアノと同じシリアルナンバーを持っている。
ショニンガーのオルガンやピアノは、もともと音楽界で高い評価を得ていた。
実際、パリ万国博覧会やシカゴ万国博覧会などで受賞している。
古くからあるブランドだけに、経験が何よりの師であり、試行錯誤の結果、
耳の肥えた人たちに好まれる楽器を作ることができたのでしょう。 |
| SHOREWOOD |
詳細不明 |
SHU

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
SHU シュー
周ピアノ工場(周興華洋琴製作所/周興華洋琴専製所)横浜天神橋近く
横浜のS.CHEWと同じく、周譲傑氏の手によるもの。
大正時代中期、上海出身の中国人、周筱正(しょうせい)氏は横浜に工場を建て、
ピアノを製造していた。だが筱正氏は関東大震災で命を落とし、工場も閉鎖。
長男の譲傑(じょうけつ)氏が昭和初期に復興したが、譲傑氏も終戦直後の1946年に死去。
親子二代の「周ピアノ」は約30年でその歴史を閉じ、日本には3台しか現存していない。
詳細はS.CHEWの項目参照。
|
SHUTEINVICH
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
SHUTEINVICH?スペル不明 シュタインヴェッヒ ドイツ 詳細不明
|
SICHER

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
SICHER シッヘル、ジッヘル
有限会社 松本ピアノ工場
茂呂ピアノ修理所
松本ピアノの木工の名人と云われた茂呂芳蔵氏が、
かなりの早わざでこしらえたピアノ。
アクションのアレンジに、少々の冒険があったと伝えられている。
|
| SIEGEL, RUDOLF |
詳細不明 |
| SIEWERT |
詳細不明 |
| SILBERMANN |
詳細不明 |
SILBER STEIN

 画像クリックでHPへ戻る 画像クリックでHPへ戻る |
シルバースタイン 製造:トーカイ楽器 (東海楽器製造株式会社)
TOKAI(トーカイ)同様、ドイツのシンメル社のモデルをもとに設計されています。
→東海楽器に関する詳細な解説は、TOKAI(トーカイ)の項目参照
<東海楽器が製造したブランドを列挙いたします>
■ TOKAI(トーカイ)
■ BOLERO(ボレロ)
■ SILBER STEIN(シルバースタイン)
■ HUTTNER(ヒュッツナー)
■ GOLD STAR(ゴールドスター)
シルバースタインのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★ |
| SILVIA |
詳細不明 |
SIMON
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
中国広州 詳細不明 |
SINGER
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
SINGER PIANO CO. シンガー
アメリカ(イリノイ州シカゴ)
シンガー・ピアノ・カンパニーは、1884年にイリノイ州シカゴで設立されました。
1900年代初頭、ステガー・アンド・サンズ・ピアノ・マニュファクチャリング・カンパニーが同社を買収し、
シンガー・ラインの生産はイリノイ州ステガーに移った。
シンガー・ピアノは1920年代後半に製造中止となった。[1]
残念ながら、シンガーのピアノに関する情報はほとんどない。
僅かに残るシンガーピアノは、美しいタッチで魅力的とのことです。 |
SINHAKKEN
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
SINHAKKEN 「新白鍵」 ※「SHINHAKKEN」ではなく、「SINHAKKEN」が正しいスペル
マイクロネット株式会社(Micronet Inc.)製作
黒鍵が一つもなく白鍵だけの不思議なピアノです。初めて見たときはびっくりしました。
マイクロネット株式会社の製作(改造)したピアノで、2014年の楽器フェアで初めてお披露目されました。
一般的なピアノの鍵盤数は、白鍵52鍵+黒鍵36鍵の合計88鍵ですが、このSINHAKKENも
通常のピアノと同じで白鍵が52鍵あり、残りの黒鍵36鍵がないということになります。
黒鍵用の弦もすでに張ってあるのに、弦はハンマーで叩いていないこということでしょうか。
ハ長調に移調することによりほとんどの楽曲が弾けるようになるとホームページで説明しています。
尚、これは技術者目線ですが、切り欠きのない唯一の白い鍵盤C8(KeyNo.88)の白鍵アクリを
なんと52枚も使っています。※ちなみにKey88番(C8)の白鍵アクリとはこの部分です →★
「新白鍵」の名称は「新発見」というニュアンスが込められて名付けられたものと想像します。
ピアノ自体はスタインウェイを改造して作っているようなので、決してピアノメーカーとは言えませんが、
新しいピアノブランド名として一応ここに掲載しておきます。
<参考>
「新白鍵」は商標登録済み (登録番号:第4711493号 登録日:平成15年9月19日) j-platpat公開情報
「新白鍵」は意匠登録済み
「新白鍵」は特許出願済み
※2013年12月の時点で「特許出願済み」と自社HP公開、2020年3月時点でまだ「特許出願済み」のステータス
もし「新白鍵」の特許が取得されたら、お手数ですがどなたかお知らせ下さい。当ページを即日更新します。
※新白鍵の紹介ページ https://www.microscope-net.com/special-contents/piano/新白鍵/
→その他、詳しくはYouTubeで 「新白鍵 ピアノ」 と検索すると演奏中の動画も出てきます
白鍵だけでドビュッシー/子供の領分、グラドゥス・アド・パルナッスム博士を弾く動画も出てきます。 |
| SKOP |
詳細不明 |
SLEZAK
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
スレザック
フローラピアノ製作所/フローラピアノ製造株式会社
当時の住所:浜松市(現:浜松市東区)北島町558番地 |
| SMART, CHARLES |
詳細不明 |
| SMIDT & WEGENER |
詳細不明 |
SMITH AND BARNES
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
スミス・アンド・バーンズ アメリカ(イリノイ州シカゴ) 創業1891年
スミス・アンド・バーンズ・ピアノ・カンパニーは、1891年に米国イリノイ州シカゴで設立され、
当初はC.A.スミス・アンド・カンパニーと呼ばれていました。
1906年にストローバー・ピアノ・カンパニーと合併し、スミス・バーンズ・アンド・ストローバーとなった。
この社名の下、同社はミルウォーキー、シカゴ、ボストンでピアノを生産する
全米最大のピアノメーカーの1つとなった。
プレーヤーピアノで有名なSmith and Barnesは非常に人気があり、
アメリカの多くのピアノ所有者の家庭で見かけることができた。
しかし、世界大恐慌の影響を受け、スミス・アンド・バーンズのピアノは正式に製造中止となった。
スミス・アンド・バーンズのピアノは、シカゴで最初に卸売りされたことから
「西部のパイオニアピアノ」と呼ばれ、丁寧に作られた最高級品とされている。
スミス・アンド・バーンズのピアノの音階は丁寧に描かれており、非常に正確で、優れた音色を持つ。
大量に販売するために製造されたにもかかわらず、スミス・アンド・バーンズの名は、
現代の技術をもってしても達成することが難しい品質の代名詞となっている。 |
| SNEL |
詳細不明 |
SOHMER

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
SOHMER & CO. N.Y.
SOHMER & CO.INC. ゾーマー 創業1872年 アメリカ
工場:ニューヨーク(ロングアイランド)
アメリカで作られているピアノのうちで、古い歴史と伝統を持ち、高品質を誇り、
更に輝かしい名声を持っているピアノメーカーの一つである。
初代のゾーマーは1884年にベビーグランドを発明し、同年に5本足による
グランドピアノのパテントを取っている。この五本脚のベビーグランドを85年間も
専一に研究開発し続け、現在50型とよばれる優れた小型のピアノを作り出しました。
この楽器の特徴は、ケースが真円を半分に切ったような(半月)のような形で、
左右対称となっており、音質が抜群に優れていることにあるといわれる。
もちろんアップライトピアノも作っていて、極めて耐久性が高く、販売の際には
20年の保証もつけているといいます。
一般には、ピアノは有名な演奏家の推薦や保証によって売れ行きがよくなるものであるが、
このゾーマーピアノは、それら販売手法を誤りとして拒み続けてきました。
ゾーマーピアノの政策上の信念は、『人間の叡智と技術と職人気質、そして家系の伝統とが
重なり合って、初めて最高品質のピアノが出来上がる』ということが基礎になっている。
※MASON & HAMLINや、FALCONEの項目も参照
<別解説>
1872年、ヒューゴ・ソーマーとジョセフ・クルーダーが、ニューヨークのロングアイランドにあった
Marshall and Mittauer社のピアノ工場を買収し、ソーマー社が設立された。
高品質で耐久性のあるピアノを製造することで知られるソーマーは、
カルビン・クーリッジ大統領や、著名な作曲家であるヴィクター・ハーバートや
アーヴィング・バーリンに愛用されていた。
ソーマー社は、世界大恐慌を生き延びた数少ないアメリカのピアノメーカーのひとつであり、
20世紀のほとんどの期間、家族経営を貫いた。
ヒューゴ・ソーマーの息子、ハリーが会社を引き継ぎ、やがて息子のハリー・ジュニアと
ロバート・ソーマーに引き継がれました。
1982年、ハリーとロバートのソーマー夫妻は、家族で経営していた会社をプラット・リード社に売却。
当時、プラット・リード社はアメリカ最大のピアノメーカーであり、ソーマー社のオフィスと工場は
コネチカット州アイボルトンに移転した。
1986年、プラット・リード社はソーマー社をロバート・マクニール社に売却し、
工場はペンシルベニア州イーリスバーグに移転した。
後にメイソン・アンド・ハムリン社に吸収されたファルコーネ・ピアノ・カンパニーは、
1989年にロバート・マクニールからソーマーを購入した。
その後、メイソン・アンド・ハムリン社が破産を宣言した際に、
ミュージック・システムズ・リサーチ社がソーマー社の資産を購入した。
2003年には、韓国のサミック・ミュージック・カンパニーが、
現在韓国で製造されているソーマーのピアノ・ラインを発売した。
ソーマー社は数十年の間に何度も所有者が変わりましたが、
現在ソーマーの名前で作られているピアノは、かつてのソーマーピアノを彷彿とさせる
高品質なものであると多くの人が考えています。
品質の継続性は、これらの高級ピアノが昔も今も人気のある理由のひとつです。
5フィートのベビーグランドを最初に販売し、アグラフ・バーとアクション、
4連残響音階のアグラフ、ブリッジ・アグラフなどのデザインで多くの特許を取得した
有名なピアノメーカーです。
ソーマーは、「丸くて、中が空洞で、木のような、暗い」独特の音で知られる
アップライトピアノやグランドピアノのほか、スクエアピアノやプレーヤーピアノも製造していた。
ゾーマーピアノ製造年対照表(1900年~1982年) →★ |
SOJIN

画像クリックでHPへ戻る |
ソジン(ソージン) 韓国(ソウル) 詳細不明
※機種:DW-1、DW-3、DW-6、DW-9、RS21D等
韓国のSOJIN工場(Daewoo Group/大宇財閥)で作られたピアノ、との情報あり
別情報として、1999年に破綻した韓国の企業グループである大宇財閥は、
破綻前は、韓国の10大財閥の1つで現代に次ぎ韓国で2位の企業グループだった。
その中に、大宇精密工業(Daewoo Precision Industries)はSojin
ブランドとその他のブランドのピアノを1980年から1991年にかけて米国に輸出。
大宇精密工業はドイツのピアノメーカー「イ・バッハ」に30%出資し、
イ・バッハのピアノ製作機械のコピーをつくり、Sojinとして販売していたようです。
大宇精密工業は韓国で作ったイ・バッハブランド(UPとGP)はカナダに輸出され、
現在は米国には輸出されていないようです。
破綻した大宇精密工業の社名は現在は「S&T Motiv」となっています。
アップライトに加え、グランドも製造
「SAUJIN」というピアノもあり、同じメーカーが作っているようですが、
日本国内で見るのは「SOJIN」の表記のピアノが多いように感じます。
SAUJINとSOJINの2種類の表記が混在する理由は不明。
※「SOJIN」と「SAUJIN」のピアノまくり(蓋部分)にある文字表記違いの参考写真 →★
画像は「匿名希望様」からご寄稿頂きました。ありがとうございます!
ご寄稿者様によりますと、ピアノのまくり(蓋部分)には「Clement/Clēment」と書いてあるそうです。
ピアノまくり部分の写真はこちら →★ ※ちなみに「Clément」はクレマンと読み、フランス語圏の姓
トレードマークが「ROYALE & SONS」と同じです |
SOLFA
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ソルファ 株式会社 プルツナーピアノ |
SOLOMON


画像クリックでHPへ戻る |
ソロモン 韓国 SOLOMON MUSICAL INSTRUMENT MF CO.,LTD.
その他詳細不明
画像は「匿名希望様」からご寄稿頂きました。ありがとうございます! |
| SOLTON |
詳細不明 |
| SOMMERFELD |
詳細不明 |
SONARE

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
SONARE ソナーレ
※正しいスペルは「SONARE」で、「SONALE」ではないので注意
製造:日本楽器製造株式会社(横浜工場)、発売元:十字屋楽器店
十字屋楽器店が日本楽器横浜工場で作らせていたブランド。
※1969年の梅宮辰夫主演の映画『不良番長 送り狼』に出ていたピアノとの情報あり |
SONATA
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ソナタ ロシア製? 詳細不明 |
| SONOR |
詳細不明 |
| SONORE |
詳細不明 |
| SOPH, JOSEPH |
詳細不明 |
| SOPNNAGEL |
詳細不明 |
SOUTER
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
アトラスピアノ製造株式会社
機種:NS7B等
ちなみに創業200年を超えるドイツの有名な「SAUTER」とはまったく関係ないです。
スペルが違いますのでご注意。 |
| SOWARD |
Estey Piano Corporation
→詳しくは「Estey」の項目へ |
SPAETHE
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
SPAETHE スペーテ ドイツ 詳細不明
|
SPENCER
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
Spencer スペンサー イギリス(ロンドン) 詳細不明 |
| SPENCER & MURDOCH |
詳細不明 |
SPILMAN

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
SPILMAN スピルマン
(有)小野ピアノ製作所(浜松市)
昭和32年頃、浜松の有限会社小野ピアノ製作所で作られていたという記録がある。 |
SPINET
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
スピネット 日本楽器製造株式会社 |
| SQUIRE |
詳細不明 |
SQUIRE & LONGSON
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
SQUIRE AND LONGSON スクワイアー&ロングソン イギリス(ロンドン)
下のスクワイヤーと一緒? 詳細不明 |
SQUIRE & SONS
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
スクワィアー イギリス 詳細不明 B.SQUIRE & SONS
|
| STANDAART |
詳細不明 |
STANDARD

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
STANDARD スタンダード
有限会社 日米楽器工業所(アトラスピアノ社の前身)浜松
フローラピアノ製造株式会社
アトラスピアノ社の前身、日米楽器工業所で作られたブランド。
85鍵で14万円で売り出されたものもある。
|
| STAPEL |
詳細不明 |
STARCK
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
スタルク アメリカ(シカゴ) 創業1891年
1891年、P.A.スタルクによってシカゴに設立されたスタルク社は、
20世紀半ばまで続いたアメリカの初期の高品質ピアノブランドのひとつである。
1920年には、サークの息子が経営するようになった。
同社はさまざまなピアノを製造し、以下のようなブランド名で販売していた。
スタルク、P.A.スタルク、スタルク&スタルク、スタルケット、コンビネーター、ケンモア、ブレント。
世界大恐慌の発生により多くの企業が倒産を余儀なくされたが、
スタルク・ピアノ・カンパニーは生き残り、株式非公開の家族経営を貫いた。
1956年までに、スタークはジェシー・フレンチ・ピアノ・カンパニーでピアノの製造を始めた。
この会社は1965年に廃業した。
スタルクピアノは、アップライト、ベビーグランド、プレーヤーピアノなどを総合的に製造していた。
実際、スタルクの再現ピアノはその品質と構造で賞を受賞した。
多くのピアニストが支持し、特にスタルクのグランドの音を好んでいた。
しかし、スタルク社はアップライトやプレーヤーなど、グランド以外のすべてのスタイルのピアノも
1939年まで製造していたが、需要が増えたため生産を開始した。 |
| STARCKETTE & KENMORE |
詳細不明 |
| STARNLEY |
ロンドン?詳細不明
STERNLEYというピアノもあり→シンガポールメーカー(中国製造?)詳細不明 |
| STARR PIANO CO. |
詳細不明 |
STATTLICH
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
スタットリッヒ 東洋ピアノ製造株式会社 |
| STAUB, J. |
詳細不明 |
| STAUB & CO. |
詳細不明 |
STECK
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
STECK ステック ドイツ 詳細不明
|
STECK
STECK, GEORGE





画像クリックでHPへ戻る |
STECK & CO.INC.GEORGE ステック アメリカ 工場:ニューヨーク
エオリアン・アメリカン・コーポレーションの子会社で作られていたアメリカの伝統的なピアノ。
工場はニューヨークにあって創業は1857年。以来、各地の展覧会で賞を取っており、
有名なリヒャルト・ワーグナーもこのピアノで楽劇(オペラ)「パルジファル」を作曲したと伝えられています。
ワーグナーが使ったジョージ・ステックのピアノは、彼の友人が寄贈したもので、現在でも
ベイルートのワーグナーの別荘に保存されているとのことです。
ステックはアップライトとグランド双方が作られており、耐久性と高品質の点で定評があり、
多くの一般学校や音楽学校などで使われています。
左記トレードマーク画像はお2人の「匿名希望様」からご寄稿頂きました。
上の2枚(アップライトピアノ)と、下の2枚(グランドピアノ)のトレードマークは、
それぞれ別々の匿名希望様からお写真をご寄稿頂きました。
グランドピアノの方は、自動演奏機能付き(ピアノラ)だそうです。ご寄稿ありがとうございます!
STECK(ピアノラ)の方の追加画像も頂きましたのでここに掲載致します →★ →★ →★ →★ |
STEGER & SONS
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
Steger and Sons ステガー&サンズ アメリカ(イリノイ州ステガー) 創業1879年
1879年に設立されたステガー・アンド・サンズ・ピアノ・マニュファクチャリング・カンパニーは、
イリノイ州のステガーという小さな町にあった。
創業者のJohn Stegerは、シカゴから30マイルほど離れたStegerの町となる
1,500エーカーの土地を購入し、会社を設立した。
ジョン・ステガーは、巨大なステガー・ピアノ工場を中心に、ピアノ職人が集う親密な町を思い描いていた。
公平で思いやりのある雇用主であるジョンは、学校を設立し、
工場で働く人たちが自分たちの住む家を持てるような道筋をつけた。
そのお返しに、Steger and Sons社に雇われた人々は会社に忠誠を誓い、仕事に注力していた。
アルテミス(Artemis)、リード・アンド・サンズ(Reed and Sons)、シンガー(Singer)、
トンプソン(Thompson)などの名機や、自社ブランドのピアノを生産していた。
Steger and Sons社は、世界大恐慌を生き延びた数少ないピアノメーカーの一つであり、
その理由は、製品の品質の高さと、多種多様なピアノを大量に製造していたことにある。
しかし、1959年に80年の歴史に幕を閉じた。
ステガー&サンズ社は、グランド&アップライト、プレーヤーピアノ、プレーヤーグランドピアノ、
リプロダクショングランド&アップライト、蓄音機など様々な種類のピアノを製造していた。
ステガーのピアノを見分けるには、2つの特徴がある。
1つは美しく精巧なケースデザイン、もう1つは美しい音色である。
ステガーピアノは、コストを惜しまずに作られた非常に優れた楽器です。
本格的なピアニストや作曲家に愛され、ピアノの世界に大きな足跡を残しました。 |
| STEGLER |
ステグラー アトラスピアノ製造株式会社 |
| STEIGERMAN |
詳細不明 |
| STEIN |
詳細不明 |
STEINBACH
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
STEIN BACH スタイン・バッハ イタリア 詳細不明 |
STEINBACH


画像クリックでHPへ戻る |
STEINBACH/STEINBACH & SONS
スタインバッハ/スタインバッハ・アンド・サンズ
平和楽器製作所 浜松市 1939年(昭和14年)創業
平和ピアノ研究所 1946年(昭和21年)
平和楽器製造株式会社 1951年(昭和26年)
発売元:株式会社 永栄楽器(名古屋市中村区名駅5丁目24-2)
読みは、永栄(えいさか)です
昭和14年から作られていたアップライトピアノ。
同社は戦時中、航空機生産の下請けをしていたが、昭和21年平和ピアノ研究所として製造を再開し始め、
昭和26年に現社名となった。台湾、東南アジアに輸出していた。
平和楽器製作所(創業1939年)
※永栄楽器の保証書にはSINCE1946年となっています(昭和21年)
エンブレム画像は「PIANO YOSHIKAWA様」よりご寄稿頂きました。ありがとうございます!
機種バリエーション:SX-3、UP-350等
<附録>
スタインバッハピアノ 製造番号/製造年代 対照表(1975年~1990年) →★ |
| STEINBACH |
近年のスタインバッハは上記平和楽器製作所のピアノではありません。
OEM製造の中国製です。
ハイルン社 代理店:アサヒピアノ |
| STEINBACH, ALEX |
詳細不明 |
| STEINBACH & SONS |
STEINBACHと同じブランドか? |
STEIN BELLS

画像クリックでHPへ戻る |
スタインベルズ/(スタイン・ベルス)
東洋ピアノ製造株式会社
機種バリエーション:130等 |
STEINBERG



画像クリックでHPへ戻る |
STEINBERG スタインバーグ、スタインベルグ
日産楽器/日産工業株式会社(浜松市)、浜名ピアノ製作所(浜松市)
日産楽器はこの他に、ウェルバー、スタインメル、K・ヘルマン、タカラヤマトなども製作した。
STEINBERGはドイツ製やイギリス製にも同じ名前があるが異なる。
トレードマークの下には「HAMAMATUPIANO SEISAKUSHO」と入っております。 拡大画像 →★
このSTEINBERGの画像はすべて「匿名希望様」からご寄稿頂きました。
この度は画像のご寄稿を頂きまして誠にありがとうございます! |
STEINBERG
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
STEINBERG スタインベルク イギリス 詳細不明 |
STEINBERG
STEINBERG, WILH

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
WILH.STEINBERG ヴィルヘルム・スタインベルグ/(ウイルヘルム・スタインブルグ)
ドイツ 創業1877年
発売元:東洋ピアノ(現在取り扱い中止)→現在は島村楽器の持ちブランド
製造:スタインベルグ社(アイゼンベルグ) 元はヨーロッパのブランドですが、現在は中国OEM製造
<以下、ウィキペディアより引用抜粋>
Wilh. シュタインベルク(ヴィルヘルム・シュタインベルク、Wilh. Steinberg)は、
ドイツ・テューリンゲン州・アイゼンベルクのテューリンガー・ピアノフォルテ
GmbH(Thüringer Pianoforte GmbH)が販売するアップライトピアノおよび
グランドピアノのブランドである。
日本ではウィルヘルム・スタインベルグとも読まれる。
2008年から香港を拠点とする柏斯琴行(Parsons Music Group)が経営に参加し、
2013年にテューリンガー・ピアノフォルテ社はParsons Music Groupの完全子会社となった。
2018年現在、WILH. STEINBERGブランドのピアノは、Signatureシリーズが
テューリンガー・ピアノフォルテ社の管理の下で、中国本土・香港地域向けのピアノは中国湖北省宜昌市に
所在する宜昌金宝楽器製造(Yichang Jinbao Musical Instrument Manufacturing)で製造されている。
1877年、アドルフ・ハインリッヒ・ガイヤー(Adolph Heinrich Geyer)がアイゼンベルクで
最初のピアノ工場を設立した。
1896年から1902年まで一時的に社名を「Tuch & Geyer(トゥーフ・ウント・ガイヤー)」としたが、
1903年に元のA. Geyerに戻した[5]。1900年代始めに会社は成長し、
「A. GEYER」、「Fuchs & Mohr」、「Wilh. Steinberg」、「Weisbrod」、「Sassmann」などの
ブランドのピアノを製造した。
第二次世界大戦中にアイゼンベルクのほぼ全てのピアノ工場は接収・破壊されたが、
ガイヤー家のピアノ工場は長い歴史のため徴発を免れた。
ドイツ民主共和国(東ドイツ)時代(1949年-1990年)、ガイヤーの工場(WILH. STEINBERG AG)は
VEB Pianofortefabrik Eisenbergとして国有化された。
東ドイツの転換(ドイツ再統一)後、Eisenberger Pianofortefabrik GmbH
(WILH. STEINBERG AG) が再設立された。
1999年に社名をテューリンガー・ピアノフォルテGmbHとした。
テューリンガー・ピアノフォルテはOEM契約の下でその他いくつかのヨーロッパの
ピアノブランドを製造・仕上げを行っている。
スタインベルグの公式メーカーホームページ →★
<下記は東洋ピアノHPより抜粋>
1877年、ピアノメーカーとして最古のピアノシティであるアイゼンベルグにて創業。
それ以前より同所にてピアノの部品メーカーとして一流ピアノメーカ-に部品を供給してた。
ドイツピアノの特有な固めの音"ブリリアントサウンド"は敷物カーペットとの融合を配慮し、
マイスター職人の伝統と感性、経験だけが持つ音質の継承は芸術の一品といえます。
「白ぶな」「赤ぶな」「かえで」「菩提樹」「イチイ」「はんの木」などの
ヨーロッパだけに成育するピアノに適した優良木材を使用。
「無垢材」としての美しさ、木材の「年齢」で決定する音質の美しさを実感ください。
すべてのスタインベルグピアノは、ピアノ作りのパフォーマンス的要素と音楽的優秀性との間に
完璧なバランスを実現させ、トレードマークの"IQマーク(Intelligent Qualitiy-聡明な品質)"
がつけられています(HPより抜粋)
<下記は島村楽器のHPより抜粋>
1877年、ドイツ東部のテューリンゲン州・アイゼンベルグ市にて創業。
ドイツでも厳しい基準を持ったピアノメーカーに部品を提供することで、高度な技術力を持つ
ピアノ製造工場へと成長していきました。
創業以来、ドイツの伝統的な設計を活かしながらピアノを製造し続けるアイゼンベルグの工場と、
世界的に有名なピアノを数多く生産する設備の充実した中国工場で、
2007年よりWILH.STEINBERG社の技術指導のもと製造しています。
そのうち、日本国内で販売されるピアノは、40年以上ピアノ製造と修理に携わる日本人技術者によって、
国内入荷後に浜松の工房で音の最終調整を行い、丁寧に仕上げられています。
何世紀にもわたり培われてきた職人の感性・熟練の技術と、最新のピアノ製造技術から
産み出された芸術の逸品をお届けします。(HPより抜粋)
まだ調律したことはないですが、一昔前の中国製造のピアノよりははるかに良くなっていると思います。
実際に調律する機会があればここに率直な感想を書こうと思いますので今しばらくお待ち下さい^^ |
| STEINBERG, GERH. |
詳細不明
※イギリスのスタインベルグと同じか?不明 |
STEINBURG

画像クリックでHPへ戻る |
スタインブルグ 中国 詳細不明
画像は匿名希望様からご寄稿頂きました。ありがとうございます! |
|
STEINER


画像クリックでHPへ戻る
|
スタイナー ※読み方は、「スタイネル」か「スタイナー」かは不明
日本の「戎ピアノ製作所」が出していたE. STEINERの読みが「スタイネル」ですが、
こちらの読み方は不明。
U-1、U-2E、U-2M、U-3M、U-5などの機種があります。
当時の販売元は協立楽器株式会社です。別名:全日本ピアノ卸センター
その他、詳細不明。 |
| STEINER, B. |
B. STEINER 詳細不明 |
| STEINER, BERNHARD |
詳細不明 |
STEINGRAEBER & SOHNE
STEINGRAEBER & SÖHNE


画像クリックでHPへ戻る |
STEINGRAEBER & SÖHNE (SOHNE) Steingræber & Söhne
創業1852年 ドイツ、バイロイト
シュタイングレ-バ-&ゼ-ネ (シュタイングレーバー・ウント・ゼーネ)
1820年アルンシャウクで創業し、1852年バイロイトへ工場を移転し、創業家が今も事業を受け継ぎ
200年以上の歴史のあるピアノメーカーです。
フランツ・リストやリヒャルト・ワーグナーも愛用したピアノメーカーです。
シュタイングレーバーウントゼーネ社は1852年に29歳のエドゥアルト・シュタイングレーバーによって設立。
もともとシュタイングレーバー家はチェンバロ製作を行っていたが、若きエドゥアルトは旅行中に、
ウィーンのシュトライヒャーに出会ったことが運命となり、ピアノ製作の道へと進んだ。
品質の優れたメーカーとして、シュタイングレーバーはすぐさま評判となり、
1874年にはリヒャルト・ワーグナーに特別なピアノの製作を依頼された。
このピアノは、オペラ「パルジファル」の聖堂の場面で用いられ、鐘の音がするピアノだったという。
1892年に、エドゥアルトの息子のヨハンとブルクハルトが経営に加わりった。
その後、1910年にヨハンはベルリンに移って優れたチェンバロ制作者になった。
1920年に、ブルクハルトの義理の息子ハインリッヒ・ヘルマンが社長に就任し、1951年にはその甥の
ハインリッヒ・シュミットが引き継いだ。
現在も、シュミット=シュタイングレーバー一族がこの会社を経営している。
シュタイングレーバー・ウント・ゼーネ社は地球環境にも優しい楽器など、オーダーメイドのピアノも製作する。
この会社は外装に天然の塗料や接着剤を用いたり、鍵盤表皮に牛骨を使用したりするなど、有機材料のみで
ピアノを製作することを得意としている。
また、古くなって内部の修理が不可能となった場合には、そのピアノの外装を再利用して新しいピアノを
組み立てるということもしている。
尚、シュタイングレーバー・ウント・ゼーネ社は、足の不自由な演奏者のためのピアノも製作している。
このピアノは、演奏者がもっとも操作しやすい場所にレバー式のサスティン(ダンパー)と弱音装置がついている。
このようなことから、シュタイングレーバーウントゼーネ社は、おそらく世界で最も特異なピアノ会社であろう。
シュタイングレイバーはBVK認証を受けています(詳しくはこちら →★)
<附録>
シュタイングレーバーピアノ 製造番号/製造年代 対照表(1860年~2001年) →★
<以下、ウィキペディアより引用抜粋>
シュタイングレーバー&ゼーネ(Steingraeber & Söhne、シュタイングレーバーと
息子達〔シュタイングレーバー家〕、の意)は、ドイツのアップライトピアノおよび
グランドピアノ製造会社である。
この同族会社はバイロイトの歴史的なロココ様式の大邸宅シュタイングレーバー・ハウスに本社がある。
ウド・シュミット=シュタイングレーバーが家業を率いるシュタイングレーバー家の6世代目である。
会社の起源はチェンバロを製造していたテューリンゲン州ルドルシュタットの家族にある。
一家はノイシュタット・アン・デア・オルラに拠点を置き、楽器製造を再開した。
エドゥアルト・シュタイングレーバーは1823年に生まれた。
エドゥアルトは初め叔父のゴットリーブ・シュタイングレーバーに弟子入りし、その後、
有名なアウクスブルクのピアノ職人アンドレアス・シュタインの娘でウィーンのピアノ職人
ナネッテ・シュトライヒャーの工房など様々な場所で働いた。
そこに滞在している間に、エドゥアルトはフランツ・リストのコンサートツアーへの同行を許され、
リストが彼の演奏で「破壊した」ピアノとグランドピアノの世話をした。
1852年、エドゥアルト・シュタイングレーバーはピアノフォルテファブリーク・シュタイングレーバー
(シュタイングレーバーピアノ工房)をバイロイトで創業した。
シュタイングレーバーは1871年にフリードリヒ通りにあるリーブハルト邸を購入し、本社とした。
以後はシュタイングレーバー・ハウスの名を冠している。
会社はすぐにバイエルン王国で最大のピアノ工場となった。
シュタイングレーバーはワーグナー家やバイロイト音楽祭(始まった1876年以降)にもピアノを供給してきた。
1881年、リヒャルト・ワーグナーは自身の歌劇パルジファルの寺院の場面で使われる
パルジファル・ベルとして知られる楽器を発注した。
大量生産期の間は、シュタイングレーバーの(20人のピアノ職人を含む)30人を超える従業員は
今でも大部分手作りされている高品質ピアノの製造を専門にしていた。
ケースは頑丈な木で作られ、パーティクルボードが使用されたことはない。
シュタイングレーバー&ゼーネはポリエステルや合成樹脂ワニスではなくシェラックや蝋で
ケースの表面を処理している。会社は車椅子使用者のピアノ演奏を単純化するため、
とりわけ足を使わない実用的なペダルの操作方法を提供するためのの技術的解決策を模索している。
シュタイングレーバーは現在のところ年間40台のアップライトピアノと17台のグランドピアノを生産している。
しかし、会社が創業されてからは、シュタイングレーバー&ゼーネは4万台を超えるグランドピアノと
アップライトピアノを製造している。
2008年のムジークメッセ・フランクフルト(国際見本市)において、シュタイングレーバー&ゼーネは
全長が232 cmある新型グランドピアノとカーボンファイバー響板を持つグランドピアノを発表した。
この種の構造は極度の気候変動にさらされる楽器を調律する際の安定性を高める。
例えば、グランドピアノが熱帯の屋内に置かれるか野外コンサートで演奏されるならば、
カーボンファイバー響板は道理にかなっている。
左ペダル機構は強化されてきている。ピアニストが左ダルを押し下げると、通常の通りに機構がシフトする。
もしピアニストがペダルを押し下げ続けると、ハンマーは弦にさらに近付く
(アップライトの弱音ペダルと同様の動き)。
これによりピアニッシモの音量での極めて柔らかい演奏が容易になる。
シュタイングレーバーはブリッジ(上駒)を横切って弦を導く別の手法を開発してきた。
これは試験的に実装された古い着想に基づいている。
通常、弦はジグザグ様式の2つのブリッジピンにつながれる。
シュタイングレーバーの代替手法の場合は、ブリッジのアグラフが金属製ローラーを通じて弦を導き、
上からブリッジへと弦を押し付ける。加えて、高さが調節可能なヒッチピンによって弦の張力の調節が可能となる。
この設計特性の背景にある考えは2要素からなる。
ブリッジを横切る均一な弦の張力はエネルギー伝達を改善し、ブリッジピンにおける著しい弦の摩擦が
もはや存在しなければ調律とそれを保持する能力が最適化される。
現在のところ、これらはグランドピアノ生産における標準装備ではない。
しかし、顧客は追加費用を払うことでこれらを注文することができる。
シュタイングレーバーでは、標準的な革張りのナックル(ハンマー)ローラー機構の代わりとして
ボールベアリング機構が利用可能である。
これによるジャックのより低摩擦での開放がレペティション(反復打鍵)の改善を可能とする。
アップライトピアノでは、シュタイングレーバーはジャックの先端とハンマーバットにバネではなく
磁石を組み込んでいる。この磁石はジャックが開放された後、動作位置に戻す。
このシステムは手入れが要らず、より速く、より正確な反復打鍵をもたらす。
シュタイングレーバーは高さが122、130、138 cmのアップライトピアノを製造している。
グランドピアノは全長170、192、212、232、272 cmが販売される。
シュタイングレーバーはまたカーボンファイバー響板とブリッジアグラフを備えた未仕上げの
グランドピアノをイングランドへ出荷している。
このピアノはイングランドのHurstwood Farmのピアノ職人によって改良、仕上げがなされ、
Hurstwoodブランド名で販売されている。
トレードマーク画像はシュタイングレーバー日本輸入代理店「白川ピアノ調律所様」からご寄稿頂きました。
この度はご寄稿いただき誠にありがとうございます! |
STEINHOVEN
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
STEINHÖVEN 詳細不明 |
| STEINMANN, WILH. |
詳細不明 |
STEINMAYER
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
STEINMAYER スタインマイヤー/スタインメイヤー? ドイツ 詳細不明 |
STEINMAYER
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
スタインメイヤー 東洋ピアノ製造株式会社
※下記、STEINMEYERと1文字違いで名称が似ているので注意 |
STEINMEL
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
STEINMEL スタインメル 日産楽器/日産工業株式会社(浜松市) 詳細不明
※ブランドスペルは”STEINMER”という表記の資料もあり |
|
STEINMEYER





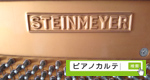
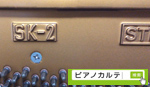
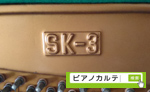
画像クリックでHPへ戻る
|
スタインマイヤー STEINMEYER
製造:遠州ピアノ製造KK(浜松市)、後にアトラスピアノ製造株式会社
発売元:協立楽器株式会社(神戸市)、高島屋(一時期)
当初は、遠州ピアノ製造(株)の主力ブランドで、その後に協立楽器の持ちブランドになりました(高島屋販売)
2枚目の画像参照(短期間高島屋ブランドでしたので、トレードマークも高島屋のバラのシンボルフラワーです)
ピアノ妻土台部分にアトラスピアノ製造のシールが貼ってあるもの
→★ は、
後にアトラスピアノで製造されたピアノです。 一番上のトレードマークが遠州ピアノ時代のものです。
スタインマイヤーまくり部分の銘柄マーク →★ スタインマイヤーの調整検査カード
→★
スタインマイヤーの文部省教育用品審査合格のシール →★
アトラスピアノ製造になってからのアクションレールに貼られたシール →★
スタインマイヤーのフレームのトレードマークはかっこいいデザインですね。
スタインマイヤーという名前のピアノは、イギリスやドイツにもありますがまったく違うピアノです。
一番上のエンブレム画像は「PIANO YOSHIKAWA様」よりご寄稿頂きました。ありがとうございます!
音量・音質、ピアノ自体の作りはとても良く出来ていると感じます。
※上記、ドイツのSTEINMAYERと1文字違いで名称が似ているので注意。
■ 機種バリエーション SK-1、SK-2、SK-3など ※スタインマイヤーの独特な巻線
→★
<ピアノ調律技術者向け附録>
張弦作業に役立つ当該機種ミュージックワイヤー配線仕様 →★
スタインマイヤーのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★ |
STEINMEYER
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
STEINMEYER スタインマイヤー イギリス 詳細不明
|
|
STEINRICH



画像クリックでHPへ戻る
|
スタインリッヒ STEINRICH
製造元:三葉楽器製作所(浜松市)→(有)スタインリッヒ・ピアノ製作所(浜松市)、
発売元:株式会社 玉田ピアノ商会
発売元になったことあり:国際楽器(神戸市生田区)
浜松にあった(有)スタインリッヒピアノ製作所のブランドです。
戦前は三葉楽器でつくっていました。
(国際楽器のブランドになったこともあるようです)
※スタインリッヒ製作所は他に「エルンスト・ホーマイヤー(ERNST HOMEYER)」という
ブランド名のピアノも製造していたというネット上での情報がありますが、詳細不明
機種バリエーション:S17等
画像は「Atelier Pianopia」様からご寄稿頂きました。ありがとうございます!
スタインリッヒのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★ |
STEINRICH & SONS
※下記は参考画像です
 画像クリックでHPへ戻る 画像クリックでHPへ戻る |
スタインリッヒ&サンズ 東洋ピアノ製造株式会社
トレードマークはスタインリッヒとほぼ同じです |
| STEINTHAL, L. |
詳細不明 |
|
STEINWAY



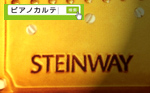
画像クリックでHPへ戻る
|
STEINWAY & SONS スタインウェイ・アンド・サンズ
そう、言わずと知れた世界一のピアノの名器です。スタンウェイと言う人もいます。
名だたるピアニストが皆こぞって愛するピアノです。
又、コンサートホールに納入されたフルコンピアノの台数としては世界一です。
スタインウェイには製造工場の違いからハンブルグスタインウェイと
ニューヨークスタインウェイの2種類に分かれ音色や特徴に違いがあります。
スタインウェイ社が1886年に特許を取得したサウンドベルはあまりにも有名。
→★
<創業>
ニューヨークスタインウェイ(アメリカ)→1853年創業
ハンブルクスタインウェイ(旧西ドイツ)→1880年創業
<歴史>
スタインウェイの創業者、ハインリヒ・エンゲルハルト・シュタインヴェークは、「木炭のマイスター」の家系に
産まれた。若い頃、火事で家族を失い、ワーテルローの戦いの集で軍隊に入隊する。
そこの兵舎では余暇の時間を使って、マンドリンやダルシマー、チターを作り、愛国歌を奏でたという。
除隊後、戦争から戻るとハインリヒは教会用オルガン職人の店の見習いとして働き楽器製作の技術を学び、
見よう見まねで1825年に最初のピアノを台所で作り上げる。
そして1835年、ゼーゼンでピアノ作りを本格的に始動し、その4年後の1839年には2台のスクエアピアノと
1台のグランドピアノをブラウンシュヴァイクの見本市(博覧会)に出展し、金メダル(一等賞)を獲得した。
増加する注文に応えるため、ハインリヒは3人の息子、テオドールとカールとハインリヒを店の経営に加えた。
1848年から1849年にかけてドイツでは革命が起き、家族は分散してしまう。
カールは1849年にニューヨークに渡り、新世界の驚異的な可能性について手紙で報告し、
家族の渡米を強く促した。テオドールはドイツの店を切り盛りするためにひとり国に残り、
あとの家族はニューヨークへ向けて旅立った。アメリカに到着すると、一家は名前をシュタインヴェークから
スタインウェイに改め、さまざまなピアノ工場で働いた。
1853年3月に、一家は家族会社を設立。これがスタインウェイの始まりだ。
彼らが製作した見事なピアノはすぐさま支持者を獲得していき、1855年、スタインウェイ社は
アメリカン・インスティテュートの大博覧会に総鉄フレームのスクエアピアノを出展し、ピアノ業界を驚かせた。
それから会社は大きく繁盛し、ニューヨーク4番街53丁目に巨大な工場が建てられた。
その同じ年、ドイツのテオドールはゼーゼンからブラウンシュヴァイクへ移り、
ゲオルク・グロトリアンと協力して会社を設立し、成功する。
弟たちが亡くなると、テオドールはグロトリアン・シュタインヴェーク社の持ち株を売ってニューヨークへ渡り、
父親の会社に加わった。
テオドールの夢は、誰も試みたことのない張力で弦を張ったグランドピアノを作ることだった。
テオドールは適切な合金を見つけ出すために冶金学を学び、接着剤やニス、その他原材料など
化学作用を研究した。またドイツへ戻って物理学者のヘルムホルツに会い、振動する弦と音楽の
物理現象について意見をきいたと伝えられている。
テオドールの最大の功績は1876年の「センテニアル」コンサートグランドである。
このピアノはデュープレックス・スケールやベントリム・ケースを備えたもので、それ以前までは
とても考えられなかったほどの弦張力(テンション)を支えるキューポラ鉄フレームが採用され、
また大きくなったハンマーヘッドを持ち上げられるようにアクションも強化された。
1889年、テオドールは45もの特許と、ほぼ改良の余地もないほどの完成度の高いグランドの設計を遺し、
この世を去った。創立者の末息子ウィリアムは、1871年にニューヨークにスタインウェイホールを設立し、
1876年にはロンドンにもホールを建てた。
1880年には、拡大するヨーロッパ市場向けのピアノを生産するためのハンブルク工場がオープンする。
またこの同年に、ウィリアムはロングアイランドに400エーカーの土地を購入しており、ウィリアムの死後、
60年の年月が経った1910年にアメリカのスタインウェイ工場は完成した。
1927年~1931年にかけて大恐慌によってスタインウェイ社は大打撃を受け、ピアノの生産高は激減。
第二次世界大戦中、スタインウェイ社は飛行機の部品を製作するように依頼され、また軍隊のための
持ち運び可能な小型アップライトピアノを3000台注文された。(これをG.I.ピアノと呼びます)
一方ドイツでは、ハンブルク工場が政府に没収され、そこではダミーの飛行機が製作された。
スタインウェイ一族は1972年に会社をC.B.S.に売却。
その後会社は1985年、スタインウェイ・ミュージカル・プロパティーズ・インコーポレーテッドに売却された。
そして現代の工学と伝統的な手作りの手法との適正なバランスをとりつつ、ピアノ製造業界以外からも
技術者が雇われ、ピアノの設計に変更が加われることなく生産工程の合理化が図られた。
<その他の特徴>
スタインウェイは、ピアノメーカー御三家の中の1つに数えられるメーカーです。
ピアノ御三家とは→スタインウェイ、ベーゼンドルファー、ベヒシュタインのことを指します。
セオドア(テオドール)・スタインウェイは現在では当たり前の交差弦のピアノを設計しました。
交差弦は、より力強い音量を得るためにグランドピアノのリム(側板)や、フレーム(鉄骨)、
ハンマーの設計を発展させたと言われています。
1872年に特許を取得した「デュープレックス・スケール」は、倍音を発生させることでピアノの音に対し、
豊かな色彩をもたらす仕組みである。これは、現にスピーキングレングス(弦が発音する部分)以外の
2箇所の追加区分を設ける設計で、追加部分はスピーキングレングスの発する基本周波数音に共振する。
1箇所目はフロント・デュープレックスバーとカポ・ダストロ・バーの間の部分で、2箇所目は響板上の
駒とフレーム上のデュープレックスバーの間の部分である。
1936年には円形膜状挙動響板の設計の特許取得。これは響板全体を反応させ、より自由な振動を促す。
円形膜状挙動響板は中央部が厚く、グランドピアノのリム内側に取り付けられている周縁部方向へ
向かうにつれてだんだん薄くなっているのが特徴です。
その他、スタインウェイについてはWikipediaに詳しく書かれていますのでご参照下さい。
■機種/モデルバリエーション (ハンブルグ工場製)
<グランドピアノ>
S:(奥行155cm)、M:(奥行170cm)、O:(奥行180cm)、A:(奥行188cm)、B:(奥行211cm)
<アップライトピアノ>
Z:(高さ114cm)、V:(高さ125cm)、K:(高さ132cm)
<附録>
スタインウェイ 製造年 対照表(1853年~1966年) →★ 製造番号 (483~395,000)
スタインウェイ 製造年 対照表(1966年~2015年) →★ 製造番号 (395,000~602,800)
<参考>
知人に聞いた話ですがスタインウェイの製造番号はその年の初めに予め区切りの良い番号から
番号を付け始めるようなので、製造番号と製造台数は一致しません。
スタインウェイはご存知の通りニューヨークスタインウェイと、ハンブルグスタインウェイという
2つの製造拠点があるため、あらかじめこの位の販売台数になるだろう、という台数を予測して、
「***000~」という区切りを付けて製造番号を割り振っているとのことです。
<以下、ウィキペディアより引用抜粋>
スタインウェイ・アンド・サンズ(英: Steinway & Sons、通称: スタインウェイ)は、
1853年にアメリカ合衆国ニューヨークでドイツ人ピアノ製作者ハインリッヒ・エンゲルハルト・シュタインヴェーク
(後のヘンリー・E・スタインウェイ)によって設立されたピアノ製造会社である。
総合楽器製造複合体スタインウェイ・ミュージカル・インスツルメンツの一角をなす。
スタインウェイ社の成長はニューヨーク工場とドイツ・ハンブルク工場の開業につながった。
ニューヨーク・クイーンズ工場はアメリカ州に、ハンブルク工場は世界のその他の地域に製品を供給する。
スタインウェイは卓越したピアノ会社と評されてきており、高品質のピアノを作ることとピアノの発展における
多くの発明で知られてきた。スタインウェイは1857年から126のピアノ製作における特許を与えられてきた。
最高級グランドピアノ市場のスタインウェイ社の市場占有率は一貫して80パーセントを超える。
この支配的な地位は、ピアノの革新を妨げ、ピアニストが好む音の均質化の原因となると主張する
一部の音楽家および書き手によって批判されてきた。
スタインウェイピアノは非常に多くの賞を受賞してきた。最初に得た賞の一つは1855年にニューヨーク水晶宮で
開催されたアメリカン・インスティチュート・フェアでの金メダルである。1855年から1862年まで、
スタインウェイピアノは35の金メダルを受賞した。さらに多くの賞および表彰がこれに続き、
1867年のパリ万国博覧会では3つのメダルを受け取った。欧州スタインウェイは
イギリス女王エリザベス2世御用達称号を持つ。
主力のスタインウェイブランドに加えて、スタインウェイはその他2つのより低価格の
第二・第三ブランドを「ボストン」および「エセックス」というブランド名の下で市場に出している。
ボストンブランドは中間レベル市場向け、エセックスブランドはエントリーレベル市場向けである。
ボストンおよびエセックスピアノはスタインウェイのエンジニアによって設計され、アジアのピアノメーカー
(ボストンは日本のカワイ、エセックスは韓国のヨンチャンと中国のパールリバー)の工場において
スタインウェイ社員の監督の下で生産されている。
1820年代に、ドイツ・ニーダーザクセン州のゼーゼンで家具製作を営んでいた
ハインリヒ・エンゲルハルト・シュタインヴェーク(後のヘンリー・スタインウェイ)が第一号となる
ピアノを製作した。ハインリヒは1850年に妻と9人の子供のうち8人と共にドイツから
アメリカ合衆国へ移住するまで「シュタインヴェーク」ブランドの名でピアノを作った。
長男のC・F・テオドール・シュタインヴェークはドイツに残り、ピアノ販売業者のフリードリヒ・グロトリアンと
組んで、1856年から1865年までシュタインヴェークブランドのピアノの製造を続けた。
ハインリヒ・シュタインヴェークは米国へ移住の際に、英語風のヘンリー・スタインウェイに改名し、
1853年にスタインウェイ・アンド・サンズをニューヨーク市に設立する。
最初の作業場はマンハッタン区ヴァリック・ストリート85号の小さなロフトであった。
1860年代にはマンハッタンのパーク・アベニュー(現在のシーグラム・ビルディングの立つ場所)に
新しい工場を構えていた。これにより年間生産台数が500台から1800台規模に増加した。
1865年、スタインウェイ家は、ドイツのシュタインヴェーク工場(現在の所在地はブラウンシュヴァイク)
を離れて、兄弟のヘンリーとチャールズが病気のため死去した会社の指揮を取ってもらうため
ニューヨークへ来るよう求める手紙をC・F・シュタインヴェークに送った。
C・F・テオドール・シュタインヴェークはこれに従い、ドイツの会社の株式を共同経営者の
ヴィルヘルム・グロトリアン(フリードリヒ・グロトリアンの息子)と2人の職人Adolph Helfferich、
H. G. W. Schulzに売却した。ドイツ工場は名称を
「C. F. Theodor Steinweg」から「Grotrian, Helfferich, Schulz, Th. Steinweg Nachf.」
(テオドール・シュタインヴェークの後継者、Grotrian、Helfferich、Schulz、の意)に変えた。
この名称は後に「グロトリアン=シュタインヴェーク」に短縮された。
ニューヨークでC・F・テオドール・シュタインヴェークは英語風にC・F・セオドア・スタインウェイと名乗った。
会社の指揮を取った15年の間、セオドアはブラウンシュヴァイクの自宅を残し、ドイツと米国を頻繁に行き来した。
1870年代には、ヘンリー・スタインウェイの息子ウィリアム・スタインウェイによって、クイーンズ区アストリアに
企業城下町Steinway Villageが築かれた。現在も米国本社はこの地区に置かれている。
ヘンリー・スタインウェイの死後、1880年にハンブルクにも生産拠点が置かれた。
ベーゼンドルファーなどのヨーロッパの名門メーカーは、ピアノをチェンバロの発展形として、
音響的に残響豊かな宮廷で使用する前提でピアノを造っていた。
これに対しスタインウェイは、産業革命により豊かになったアメリカ市民が利用していた、
数千人を収用できる音響的に貧弱な多目的ホールでの使用を念頭においていた。
そのために、今では常識となっている音響工学を設計に初めて取り入れた。
結果、スタインウェイは構造にいくつか特色がある。
ピアノの設計思想にはいくつかの流派がある。主に響板の響きを重視したベヒシュタイン。
胴の部分にも響板と同じスプルース材を用い、響きやすくしたベーゼンドルファー。
スタインウェイはそれらに対して、厚く強固な胴でしっかりと響板からの圧を支える構造を持つ。
また胴からの反射音も多彩な響きに貢献していると言われている。
それ以外にも交差弦やデュープレックス・スケールなど、スタインウェイの革新の数々は、
世界的に広く他のピアノ製造者への手本となった。
しかしながら、20世紀後半以降は多くの木材のストックを要し、製造に長い期間をかけるために
生産数が少ないスタインウェイの経営は順風満帆とは行かず、1972年のCBSによる買収、
その後の複数の個人投資家への売却を経て、1995年にセルマー・インダストリーズの傘下に入った。
今日では、セルマーおよびその傘下に収まった旧ユナイテッド・ミュージカル・インスツルメンツ、
ルブラングループらと共に楽器製造企業複合体スタインウェイ・ミュージカル・インスツルメンツ
(旧セルマー・インダストリーズ)を形成するに至っている。
この企業複合体は、1990年代後半にかけてアメリカ経済のバブルの恩恵を受けて、売上高を急激に増やし、
楽器業としては最も高い売上を確保するようになり、財務体質が改善された。
その結果、多くのピアノ製造メーカーが経営難に直面し、良い素材の確保が困難になる中で、スタインウェイは
ピアノ造りに欠かせない良質な素材を確保する点で優位性を保持することとなった。
またこれ以外に、戦後の世界的な高級ピアノ市場をスタインウェイが独占できたのは、
ヨーロッパ、特に敗戦国であるドイツの名門メーカーが第二次大戦の戦災により
壊滅的なダメージを受け、主要な工房や多くの技術者を失ったせいでもある。
しかし、その後、楽器業界は売上高を継続的に伸ばすのが難しい状況となり、
2013年8月、親会社である総合楽器製造会社、米スタインウェイ・ミュージカル・インスツルメンツ(SMI)は
米著名投資家ジョン・ポールソンのファンドへの身売りを発表した。
構造上は以下のような特徴を持つ。
基本的に強力な筺体を作りこみ、ピアノ全体で豊かな音量を実現する点が特長である
カエデなどの硬く緻密な木材を使用し、曲げ練り製法により一体として製造されたアウターリムとインナーリム
放射状支柱を後框および金属フレームと結合することで弦の張力を保ち響きを支柱とリムに拡散する構造
剛性の高い筺体を完成したのちに響板を貼り込みブリッジを削り弦圧を調整する製造法
力学および音響的に優れかつ軽量な金属フレーム
クラウン(むくり)を長く持続させ音質的に優れた響板の周辺の厚みを薄くした製造法
他社に比べ張力が低いスケールデザイン
弦の倍音を有効に活用し音量を増大するデュプレックススケール
フレームとリムを連結し弦圧を最適化するとともに高音域の響きをリムに伝えるサウンドベル
金属チューブに木材を充填したアクションレールおよびハンマー固定方法
レスポンスに優れたエルツ式のウィペン
上記の要素はほぼ19世紀末までに確立された。弦の振動をピアノ全体に分散し響かせる設計によって、
楽器全体から豊かな音を出せ、特に大ホールにおいても充分な量のきらびやかな音を響かせるのである。
また整調、整音により幅広い音色を持たせられるため、クラシックやジャズに限らず、幅広いジャンルに対応でき、
多くのホールや録音スタジオでのファーストチョイスとなっている。
また筐体の強度が高いことから調律が安定し寿命も長く、古くなった楽器でもリビルドすることによって
演奏可能な状態に再生することができるのも、その特色の1つである。
このため現在に至るまで、ほとんどのピアノメーカーはスタインウェイの特徴を取り入れようと努めている。
スタインウェイピアノは世界中の約200の認証スタインウェイディーラーの約300の販売店で販売されている。
スタインウェイは以下のグランドピアノおよびアップライトピアノのモデルを作っている。
ドイツ・ハンブルクにあるスタインウェイの工場は、7種類のグランドピアノと
2種類のアップライトピアノを作っている
(モデルの記号表示の数字部分はグランドピアノでは長さ、
アップライトピアノでは高さをセンチメートル単位で表わす)
グランドピアノ: S-155、M-170、O-180、A-188、B-211、C-227、D-274
アップライトピアノ: V-125、K-132
アメリカ合衆国ニューヨーク州クイーンズにあるスタインウェイの工場は、6種類のグランドピアノと
3類のアップライトピアノを作っている。
グランドピアノ: S (5' 1")、M (5' 7")、O (5' 10 3⁄4")、A (6' 2")、B (6' 10 1⁄2")、D (8' 11 3⁄4")
アップライトピアノ: 4510 (45")、1098 (46 1/2")、K-52 (52")
スタインウェイピアノの生産工場はアメリカのニューヨーク(1853年より)と
ドイツのハンブルク(1880年より)の2箇所にあり、それぞれで材料・形状・アクション・鍵盤・
足の固定方法などが若干異なる。
ニューヨーク・スタインウェイは現在でも伝統的な製造方法で作られていて個体差が大きいといわれる。
比較的柔らかいハンマーフェルトを使い、硬化剤などの使用により幅広い音色を生み出すことも可能であり、
明るい音色とあいまってニューヨーク・スタインウェイを好むユーザーも多い。
鍵盤両端の腕木と呼ばれる部分の角が直角であることとペダルボックスに金属装飾を持つ点が特徴である。
ハンブルク・スタインウェイは、より近代化された工場で製造されており精度が高いと言われる。
他のドイツ製ピアノと同様に比較的堅めのハンマーフェルトを使い、主に針を刺すことで整音を行う。
鍵盤両端の腕木と呼ばれる部分の角が丸いことが特徴である。
日本に入ってくるスタインウェイのほとんどはこのハンブルク製である。
ハンブルク・スタインウェイは日本をはじめとするアジア地域とヨーロッパに輸出され、
ニューヨーク・スタインウェイは北米、南米への出荷が取り決められている。
<別解説>
スタインウェイ&サンズ社の歴史は、ドイツでハインリッヒ・シュタインウェグが
セーゼンで楽器店を経営していたことに始まります。
渡米後、一家は社名をスタインウェイと改め、1853年にニューヨークのヴァリック・ストリート85番地の
元の場所でスタインウェイ&サンズ社を設立しました。
1854年には急成長を遂げ、当時世界最大のピアノ工場としてトップに立つまでに成長した。
南北戦争の頃、会社は低迷したが、1866年にスタインウェイ・ホールがオープンしたことで一気に復活し、
カーネギーホールがオープンするまでの約30年間、ニューヨークの芸術の中心地となった。
1880年、ドイツのハンブルグに工場を開設したスタインウェイ&サンズ社は、ドイツとニューヨークの
2つの拠点で活動しました。1880年にドイツのハンブルグに工場を開設したスタインウェイ&サンズ社は、
ドイツとニューヨークの2カ所で事業を展開していた。
その後、一連の買収により、スタインウェイ・ミュージカル・カンパニーに社名変更し、
現在はニューヨークに本社を置くプライベート・エクイティ・ファームが所有しています。
現在もスタインウェイ&サンズ社、ボストン社、エセックス社のピアノが製造されています。
<スタインウェイ&サンズピアノの様々な種類について>
スタインウェイ&サンズ社のピアノには、さまざまなモデルがあります。
大きさや特徴が異なるスタインウェイは、コンサートステージ用に設計されたものもあれば、
家庭やスタジオに最適なものもあります。
スタインウェイは、グランドピアノとベビーグランドピアノでよく知られていますが、
彼らはこれらを "スタジオ・グランド "と呼んでいます。
モデル "O "は現在 "L "に置き換わり、モデル "A "は1940年代に製造中止となり、
近年になって再生産されました。
<スタインウェイ&サンズ社のピアノ技術開発>
1800年代初頭からピアノ製造をリードしてきたスタインウェイ&サンズ社は、
多くのピアノ技術の進化に貢献してきました。
これらの技術開発の中には、以下のようなイノベーションがあります。
1859年 - オーバーストラングのグランドピアノ
1872年 - フルアイアンのキューポラプレート
1931年 - アクセラレート・アクション
1936年 - 隔膜式響板
1963年 - スタインウェイのヘキサグリップ・ピン・ブロック
H2: 修復されたスタインウェイピアノの価値
スタインウェイ&サンズ社のピアノは、1800年代初頭にさかのぼるアメリカの豊かな歴史と
ブランドの知名度から、高い価値を維持しています。
特に、ニューヨークやドイツの初期の工場で生産された初期モデルは、
修復されていない状態で25,000ドルの価値があると言われています。
スタインウェイのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★ |
| STEINWAY & SONS Fabbrini |
STEINWAY & SONS FABBRINI スタインウェイ・アンド・サンズ・ファブリーニ
スタインウェイ・ファブリーニ/ファブリーニ・スタインウェイ
天才調律師とされるアンジェロ・ファブリーニ氏が改造・監修した特製スタインウェイ(ハンブルグ)とのこと。
側面のSTEINWAY & SONSの文字の下には、Fabbriniの筆記体が本家よりも大きな文字で自己主張しています。
これも自信の表れからなのでしょうか。。正直初めて見たときは何じゃこりゃ?!と思いました(笑)
スタインウェイ社の公認でこのFabbriniの文字がピアノ本体に描かれている訳ですから大したものです。 |
| STEINWAY HAUS |
詳細不明 |
STELZHAMMER
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
STELZHAMMER ステルツハンメル オーストリア?ドイツ? 詳細不明
|
| STENGER |
詳細不明 |
STERNLEY
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
STERNLEY スタンリー
シンガポール販売、中国製造?詳細不明
「STARNLEY」というピアノもあり(ロンドン) |
STERLING

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
STERLING PIANO CO.INC. スターリング スターリング・ピアノ・コーポレーション
アメリカ、テネシー州の新しいメーカーで、一般向きのピアノを作っています。
この会社の製品にはスターリングのブランドのほか、ハンティングトン(HUNTINGTON)、および
メンデルスゾーン(MENDELSSOHN)のブランドもあります。
スターリング・ピアノは、1871年、バーミンガム・オルガン社を買収したチャールズ・スターリングによって、
コネチカット州ダービーに設立された。
当初はオルガンのみを製造していたが、1885年に法人化し、ピアノの製造を開始した。
メンデルスゾーン、ハンティントン、ゲッツ&カンパニー、ローマン、リチャードソンなどのピアノを製造。
また、ハンティントン・ピアノを管理しており、その楽器は後にウィンター社でも作られるようになった。
後にピアノの巨大企業エオリアンの傘下に入り、スターリングの名は1960年代まで生産されていた。
この時代のピアノは高品質で、当時の他の多くの著名なビルダーに匹敵すると考えられていた。
グランドも製造していましたが、主にキャビネット・グランド・ピアノと呼ばれる高級アップライトが有名でした。
スターリング社のピアノの中には、64音ピアノにメロディグランドのシリアルナンバーが付いているものがある。
会社の資料には、このピアノの構造について次のように書かれている。
スターリング・ピアノの構造は次のように説明されている
「完全な鉄製のフレームで作られており、完璧な堅牢性と堅固さを与えている。
響板は厳選されたスプルースを使用しており、楽器の重要な部分であるこの部分には、
柔らかい松や他の材料は一切使われていない。背板は非常に強固に作られており、
楽器は耐久性を考慮して作られている。使われている音階は最も完璧で、
徹底的にテストされており、全体的に均一で、スターリングで作られる音色は長く持続するか、
または歌うような品質であることが特徴である」
1959年にウインター(WINTER & CO.)は、エオリアン・アメリカン社と合併し、
社名をエオリアン・コーポレーションに変更していた間、STERLINGは
ウィンター&カンパニーが製造していたブランド名の一つです
→詳しくはWINTERの項目へ |
| STICHEL, F. |
詳細不明 |
STING
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
Sting スティング
1959年にウインター(WINTER & CO.)は、エオリアン・アメリカン社と合併し、
社名をエオリアン・コーポレーションに変更していた間、STINGは
ウィンター&カンパニーが製造していたブランド名の一つです
→詳しくはWINTERの項目へ |
| STINGL, GEBR. |
詳細不明 |
| STINGL, IGNAZ |
詳細不明 |
| STÖCKER, THEODOR |
詳細不明 |
|
STOCKHAUSEN


画像クリックでHPへ戻る
|
STOCKHAUSEN ストックハウゼン(シュトックハウゼン))
朝日ピアノ扱い(ウエンドル・アンド・ラングなどを扱い、浜松にある中国人社長の会社)
浜松を前面に出していますが、本社が浜松というだけでピアノ製造を浜松でしている訳ではありません。
中国での製造だと思われます。
ピアノ内部に据え付けの調律点検記録カードが「ウエンドル&ラング」というピアノと同じです。
※過去に北朝鮮製造?韓国?→浜松で最終調整? (PACO) この件については詳細不明
■機種バリエーション:SPU-121等 |
| STOCKHOLM |
詳細不明 |
| STODDART |
詳細不明 |
STONE
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
STONE ストーン アメリカ 詳細不明
|
STORY & CLARK

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
STORY & CLARK PIANO COMPANY ストーリー・アンド・クラーク
アメリカ(シカゴ) 工場:ミシガン州グランドヘブン
1857年にハンプトン・ストーリーによって創業されたピアノメーカーで、莫大な数量の
アップライトピアノを市場に販売し続けてきたことによって名が知られ、アメリカで有数の
古い歴史を持ち、もちろんスピネットピアノもグランドピアノも製造しています。
初代のハンプトン・ストーリーは、生まれ持っての音楽的才能を持ちあわせた人物で、
10歳のとき、すでにピアニストとしての演奏技能を習得し、20歳でピアノ教師となり、
なんと22歳でピアノの製造を開始したという。
彼の最初のピアノは、チャンプレイン湖(ニューヨークとベルモントの間にある美しい湖)
を臨む小さい仕事場で作られたが、熱心にピアノ製造に打ち込んだため数年のうちに高品質な
ピアノを次々と完成させ、名声は遠くニューヨーク、バッファローおよびクリーブランドにも
および、バイヤーが次々と訪れるようになった。
その後、1867年に工場はシカゴに移され、ピアノとリードオルガンの製造で急激な発展を
続け、さらに1901年にミシガン州のグランドヘブンに移されている。
現在に至るまでに4代の間、ストーリー一家はピアノ製造の伝統と秘技を受け継ぎ、近代的な
小型のアップライト、すなわち、アメリカでコンソールあるいはスピネットとよばれる機種の
発達のパイオニア的な役割を果たし、さらに、スケールのデザインやキャビネットのスタイルの
先達の役目を果たしたとのことです。
1948年に、この会社は画期的なピアノ響板を作り出している。これはストーリートーン
(STORY-TONE)と名付けられたマホガニー製の響板である。弦楽器の響板は昔から
松あるいは杉などの木目の通ったやや柔らかい木で作るものと相場が決まっていた。
その理由は、音の伝導性が良いという点にあります。ところが、ストーリー・アンド・クラークは、
この伝統を破って合板のマホガニーで響板を作り出したのである。この硬木の響板は温度や湿度の
変化に関係なく、50年の間、絶対にひび割れすることがないことの保証が付けられていた。
さらにマホガニーはスプルースと比較した場合、温度および湿度による収縮・膨張その他の変化が
少ないために、チューニングが狂う率が大幅に減少し、その上、音質を向上させるという。
現在、ストーリー・アンド・クラークのアップライト全機種に、このマホガニーの響板が採用されている。
この会社では、教会用のピアノという特別な楽器も作っている。ケースには特殊なゴシック式の
飾りを付け、やはり合板のマホガニーを響板に使用している。この響板により、オルガンとチューニングを
合わす必要のある教会では調律が極めて容易になったといわれている。
また、学校専用のアップライトも作られている。このピアノの特徴としては、ひとつの鍵(カギ)で
屋根板、前蓋(まくり)、前板を同時にロックできる装置、二重になったゴム製の指し込みの
キャスター、調律を容易にする屋根板とフロントパネルが一体になった構造などがある。
<別解説>
ストーリー&クラーク社は、1859年にハンプトン・L・ストーリーがVT州のバーリントンに
店を開いたのが始まりである。1862年には、StoryはStory & Powers Co.を設立して
パートナーシップを結び、現代のピアノブランドの販売を開始した。
1862年にはStory & Powers社となり、現代的なピアノブランドの販売を開始した。
シカゴで販売していたピアノの広告には、この短い期間の社名が使われている。
1884年、ストーリーはメルビル・クラークと提携して「ストーリー&クラーク」社を設立し、
リードオルガン事業に参入した。
1884年、ストーリー&クラーク社はメルビル・クラークと提携し、
ロンドンとベルリンに工場を設立してオルガンの製造を開始した。
1890年代後半には、アーヴィントン、ストーリーグランド、テニソン、ストーリートーンなどの
ピアノが製造された。1993年にQRS Music Rolls, Inc.がStory & Clark社を買収したことで、
一連の企業売却は終了した。
ストーリー&クラークのピアノは、現在では中堅のアップライトピアノとして知られているが、
プレーヤーピアノとして購入されることも多い。
光センサーとUSB/MIDI技術を内蔵し、すべてのピアノにプレーヤーピアノ機能が標準装備されています。
プレーヤーピアノの技術を可能にしたのは、メルビル・クラークがライブコンサートの
ピアノロールを録音する方法を発明したことです。
1912年に「マーキング・ピアノ」として発売され、有名な演奏の保存と再生を可能にしました。
デジタルピアノで知られるStory & Clark社は、すべてのピアノを、アコースティックな外観と
感触を維持しつつ、デジタルピアノの技術を用いて販売している。
これは、クラシックな外観のピアノを部屋に置きながら、個人の機器やコンピュータを
ピアノに接続したいという多くのお客様にとって魅力的です。 |
STRAUBE
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
STRAUBE シュトラウベ ドイツ(旧西ドイツ) 詳細不明
|
STRAUBE
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ストラウベ Straube Piano Company (1895–1937)
アメリカ(シカゴ) 詳細不明 |
STRAUSS
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
STRAUSS シュトラウス
ドイツ? 詳細不明 |
STRAUSS


画像クリックでHPへ戻る |
STRAUSS シュトラウス/ストラウス
東亜ピアノ、[有限会社小野ピアノ製作所]
戦前にもあったピアノ。
昭和32年ごろ有限会社小野ピアノ製作所で作られていた記録もある。
左記トレードマーク画像は「匿名希望様」からご寄稿頂きました。貴重な画像をありがとうございます!
ご寄稿者様によりますと、このピアノはお母様の形見で1950年代のピアノのようです。 |
STREICHER
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
J.B.Streicher シュトライヒャー/(ストライヒャー)
シュトライヒャー工房 オーストリア(ウィーン) 創業1794年~1896年迄 |
| STRICH & ZEIDLER |
NEW YORK(ニューヨーク) 詳細不明 |
| STRINDBERG |
詳細不明 |
| STROHBER |
CHICAGO U.S.A アメリカ(シカゴ) 詳細不明 |
| STROHMENGER & SONS |
詳細不明 |
| STROTHIER |
詳細不明 |
STROUD
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ストラウド アメリカ(ニューヨーク)
ストロー・ピアノ社はニューヨークで設立され、後にエオリアン社の傘下に入った
数多くのアーリーアメリカン企業の一つとして知られています。
ストロウドピアノは、主にアップライトのプレーヤーピアノで、
エオリアン・ラインの「ストロウド・ピアノラ」と表示されていました。
エオリアンのブランド名は比較的価格の高いピアノだったので、
力のあるエオリアン社は手ごろな価格の代替ピアノとしてストラウドブランドを活用したのです。
全体的に品質と音が似ていたのです。
エオリアン社のStroudと他のブランド名は、一時期、
ウェーバー・ピアノ・アンド・ピアノラ社によって製造されていた。
第2次世界大戦が始まると、ストラウドのブランドは製造されなくなった。
ストロー・ピアノやプレーヤー・ピアノは、しっかりとした作りで耐久性のある楽器だった。
エオリアン・ピアノ社は、比較的平均的なピアノを手頃な価格で製造していた。
当時のアメリカの経済状況にぴったりで、Stroudピアノの価格帯は、
ほとんどのアメリカ人が買える範囲のものでした。
1929年の世界大恐慌の後、エオリアンはStroudブランドで小型のアップライトピアノや
ベビーグランドピアノの製造を開始した。 |
STUART & SONS
STUART AND SONS


画像クリックでHPへ戻る |
スチュアート・アンド・サンズ オーストラリア(シドニー)
スチュアート・アンド・サンズ社は、290cmのコンサートグランドと、220cmのグランド、
130cmのアップライトピアノを製作。
スチュアート・アンド・サンズのピアノは完全8オクターブ97鍵を採用しています。
ベーゼンドルファー290モデルの97鍵とは違い、最低音と最高音の両側に音域を広げた鍵盤を採用しており、
F(21.8268Hz)~F(5587.6517Hz)という音域である。
さらに102鍵の8.5オクターヴのピアノもあり、この音域はなんとC-1(マイナス1)~F7である。
これは通常のピアノの音域(音域A0~C8)からさらに低音部に9鍵多く、高音部に5鍵も多い。
<歴史>
ウェイン・スチュアートはヨーロッパと日本でピアノ製作の技術を学び、1995年に自身の会社を設立。
以来、スチュアートはオーストラリアのピアノ製作における新たなコンセプトを切り開いてきた。
ピアノケースはオーストラリア産のさまざまな木材で出来ており、伝統的で一般的とされるピアノ外装とは
著しく異なっているのがスチュアート&サンズピアノの特徴と言える。
そして、スチュアートピアノはすべて、ウナコルダ、サスティン、ソステヌート、ハーフブローの4本ペダルを
備えているのが特徴である。しかし、スチュアートの真の先見性は発音設計にあるとされる。
従来のピアノは長い木の駒に斜めに駒ピンを打って横からも弦を押さえつけているが、スチュアート製は、
弦と駒を接続する方法として、駒ピンの代わりにアグラフを用いている。そうすることにより、音の減衰速度が
遅くなり、調律の安定性も向上するとスチュアートは信じているとされています。
尚、スチュアート社のピアノはすべてオーダーメイドで、販売とサービスも行うピアノ・オーストラリア社により
生産されている。手作りのピアノはどれも完成まで1年かかるため、このメーカーの生産高は非常に少ない。 |
| STULTZ |
詳細不明 |
| STURN |
詳細不明 |
STUTTGART

画像クリックでHPへ戻る |
STUTTGART シュトゥットガルト/(ストゥットガルト)/(スチットガルト)
※シュトゥットガルト(STUTTGART)とは、ドイツの都市名ですが、ピアノは日本製です。
製造元:株式会社 西川楽器製作所
戦前、浜松で作られていたピアノです。
トレードマーク画像は「匿名希望様」からご寄稿頂きました。ありがとうございます!
2つのト音記号が描かれた印象的なデザインですね。 |
| STUYVESANT |
詳細不明 |
SUNSHINE
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
SUNSHINE サンシャイン
有限会社 アサヒ工芸社(前身:朝日楽器製作所) 大石寛一氏の創業
創業1966年(昭和41年)→廃業1970年(昭和45年)
当時の住所:浜松市中野町798、浜松市天龍川町677
このサンシャインは低価格、小型・軽量なピアノで、鍵盤数が73鍵だった。
アサヒ工芸社は他にWAGNER(ワグナー)、BUXHARD(バックスハルト)も製造 |
| SUPERBA |
詳細不明
※Wertheimの商標? |
| SUZUKI |
詳細不明 |
| SVAHNQUIST |
詳細不明 |
| SVENSKA |
詳細不明 |
SWEETLAND
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
スウィートランド
Cable Nelso(ケーブル・ネルソン)n社が製作していたブランド
→詳しくはCable Nelsonの項目へ |
SYDNEY ZENDER
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
SYDNEY ZENDER &CO ゼンダー イギリス 詳細不明
|
SYSME
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
シスメ 東洋ピアノ製造株式会社
機種バリエーション:SR580等 |
上記Sから始まるブランドの中で、追記出来そうな事項や新情報を発見した場合、修正受付フォーム よりお気軽にお知らせ下さい。
どんな些細な情報でも構いませんので、広く皆様からのフィードバックをお待ちしております。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
 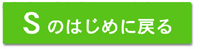 



上記Tから始まるブランドの中で、追記出来そうな事項や新情報を発見した場合、修正受付フォーム よりお気軽にお知らせ下さい。
どんな些細な情報でも構いませんので、広く皆様からのフィードバックをお待ちしております。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
 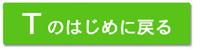 



上記Uから始まるブランドの中で、追記出来そうな事項や新情報を発見した場合、修正受付フォーム よりお気軽にお知らせ下さい。
どんな些細な情報でも構いませんので、広く皆様からのフィードバックをお待ちしております。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
 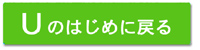 



上記Vから始まるブランドの中で、追記出来そうな事項や新情報を発見した場合、修正受付フォーム よりお気軽にお知らせ下さい。
どんな些細な情報でも構いませんので、広く皆様からのフィードバックをお待ちしております。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
 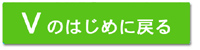 



ピアノ銘柄ブランド
トレードマーク 紹介
& 知名度ランキング

|

メーカー/ブランド説明・会社沿革・歴史・製作者・特徴・音色・他
|
| W. DANEMANN |
W.DANEMANN & CO. ダネマン イギリス 詳細不明
|
W. G. EAVESTAFF
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
W.G.EAVESTAFF & SONS イーベスタッフ イギリス 詳細不明
|
W. M. KNABE


画像クリックでHPへ戻る
|
W.M. Knabe & Company Pianos
WM. KNABE & CO. ウィリアム・クナーベ(ウイリアム・クナービ)
アメリカ メリーランド州(都市:ボルチモア) 1837年創業
創業者:ウィリアム・クナーベ/ヴァレンティン・クナーベ(ドイツ生まれ)
エオリアン・アメリカン・コーポレーション傘下の系列会社の製品。
アメリカン・ピアノ・カンパニー、エオリアン・アメリカン・コーポレーション傘下の系列会社の製品の後、
現所有:ピアノディスク社→現在の製造はサミック社(韓国)とのこと
※MASON & HAMLINの項目や、AEOLIANの項目も参照
1839年にアメリカのボルティモアに設立されたクナーベ社は、アメリカでもっとも有名な
ピアノメーカーのひとつとなった。
当初は「裕福な上流の人々に相応しい品質のピアノ」というスローガンで宣伝されたクナーベのピアノの音質は、
ダルベールやサンサーンスなどの一流のヴィルトゥオーゾに絶賛された。
またクナーベのピアノは見本市に出展されると、高い職人技と優れた構造を称えられて必ず賞を獲得した。
プロイセンの家具、ピアノ職人の見習いだったヴァレンティン・クナーベは、1833年にアメリカに移住し、
ピアノ製作者のヘンリー・ハーティーのもとで働き始めた。
クナーベは英語と商売の技術を学んだ後、1839年にヘンリー・ゲーレと組んで会社を設立し、
クナーベ・アンド・ゲーレのブランド名でピアノを作り始めた。
1854年にクナーベはゲーレから会社を買い取り、息子のウィリアムとアーネストとともにピアノの生産を開始。
ヴァレンティンが1864年に亡くなるまで会社は上質のピアノメーカーの地位を確立し、息子たちの指揮の下、
会社は繁栄し続けた。
1870年には毎年約500台のピアノが生産されるようになり、工場の再開発を経て1890年に生産高は、
年間2000台まで跳ね上がった。19世紀の終わりの四半世紀にクナーベは絶大な評価を得るようになり、
ニューヨークとワシントンにショールームが設立された。
ルービンシュタインをはじめ、多くの音楽家がクナーベ社の支援を受け、クナーベピアノでコンサートを行った。
1891年のカーネギーホールの「こけら落とし」ではクナーベ社がスポンサーとなり、チャイコフスキーを
ゲスト指揮者として招いた。
1889年と1894年にクナーベ兄弟が相次いで突然亡くなってからは、ヴァレンティンの孫が後を継ぎ、
1908年にアメリカン・ピアノ・カンパニーに吸収合併されるまで会社を経営した。
合併の1年後、ウィリアム・ジュニアとアーネスト・ジュニアはこの複合会社を去り、オハイオ州にクナーベ・
ブラザーズ・カンパニーを設立する。
クナーベ・ブラザーズ・カンパニーは短命に終わったが、1914年までクナーベ家伝統の音を
保持したピアノを生産。
会社の買収と、新たなクナーベ・ブラザーズ・カンパニーの設立があったにもかかわらず、元々のクナーベ社は
ピアノを販売し続け、1916年には生産高が年間3000台に達した。
1932年にアメリカン・ピアノ・カンパニーはエオリアン・コーポレーションの一部になり、アップライトと、
グランドピアノを生産し続けたが、1985年にエオリアン社が倒産し、クナーベのブランド名や設備、
型、未完成のピアノはすべて、ゾーマー・アンド・カンパニーへ売却された。
現在は、韓国のサミック社がWm.クナーベ(Wn.Knabe)のブランド名でクナーベピアノを生産している。
<附録>
クナーベピアノ 製造番号/製造年代 対照表(1850年~1980年) →★
<以下、ウィキペディアより引用抜粋>
Wm. クナーベ& Co.(Wm. Knabe & Co.、クナービとも)は、19世紀中頃から20世紀の初めまで
アメリカ合衆国メリーランド州ボルチモアに存在したピアノ製造業者である。
1982年まではニューヨーク州イースト・ロチェスターのエオリアン・カンパニーの一事業として存続した。
現在は三益楽器(韓国)によって製造されるピアノの一ブランドである。
ヴィルヘルム・クナーベは1803年6月3日にザクセン=ヴァイマル公国クロイツブルクで生まれた。
1813年のドイツにおけるフランスの軍事行動によって父親のようにアポセカリーとなるために
学ぶことができなくなり、代わりにキャビネット職人に弟子入りし、その後2年間見習いとして働き、
次に3年間ゴータでピアノ職人のために働いた。その後ドイツのいくつかの都市でピアノ職人見習いとして働いた。
1831年、クナーベはザクセン=マイニンゲン公国からアメリカ合衆国へ移住する婚約者の家族に同行したが、
家長が航海中に死去したため、クナーベと花嫁は兄弟が数年早く定住していたミズーリ州ハーマンへの
旅の途中のボルチモアにとどまった。
クナーベは有名なピアノ職人Henry Hartgeの下で働き、結局は農業従事者になる計画を断念した。
4年後、クナーベはLexington通りのLiberty通りの角にある自宅で中古ピアノの販売と修理を始めた。
1839年、クナーベはピアノを製造する目的のためにHenry Gaehleと共同経営を始め、
1841年までに彼らはSouth Liberty通り13にあるより大きな作業場へと移った。
1843年、彼らはEutaw通りとCowpenアレーの角に商品陳列室を開き、その4年後にはEutaw通り9に
商品陳列室を移転し、ここで180米ドルから400米ドルの価格でピアノを販売した。
1852年までに、店はEutaw通り4、6、8、9、11へと拡大した。
Knabe & Gaehleは1848年、1849年、1850年にスクエア・ピアノで、1849年にはグランドピアノでも
メリーランド機械振興会から一等賞を取った。
1852年、会社はEdward Bettsを共同経営者に加えてKnabe, Gaehle & Co.として再編され、
1853年までに宣伝された彼らの会社は南部で最大で、100人を超える工員を雇用した。
彼らは「チッカリングのようなダブルアクション」を持つ6から7オクターブの音域のピアノを製造し、
200米ドルから500米ドルで販売した。
1853年11月、Eutaw House近くのCowpenアレーにあった工場が火事になり、推定損失額は19万米ドルであった。
共同経営会社を解消するために1855年初頭に訴訟が始まった。
Henry Gaehleは死去し、クナーベは残りの在庫と資材を全て購入したこと、Eutaw Houseの向いにある
North Eutaw通り1、3、5、7にある古くからの売り場でWm. Knabe & Co. として商売を続けると宣伝した。
代表社員となったWilliam GaehleはWm. Gaehle & Co. として営業を続けると宣伝し、Pratt通りとGreen通りの
角の工房でグランドピアノとスクエア・ピアノを製造し、Eutaw通りとFayette通りの角に展示場を構えた。
クナーベはWest通りとChina通りの角にあった元製紙工場を新工場のために購入し、1859年までに
ボルティモア通り207に商品展示場を開設した。
クナーベは1855年、1856年、1857年、1858年にメリーランド機械振興会からスクエア・ピアノで
金メダルを獲得し、1857年にワシントンDCのメトロポリタン協会から銀メダル、1856年に
フィラデルフィアのフランクリン協会からメダル、1855年と1856年にバージニア州リッチモンドの機械工協会から
一等賞を獲得した。
1860年、クナーベはEutaw通りとWest通りに新たに5つの工場の建設を開始したが、南北戦争の勃発のため
その中の一つしか完成できなかった。南北戦争によって、クナーベは南部の主要市場を失なうこととなり、
その損失を埋め合わせるために西部で新たな取引を開拓せざるをえなくなった。
ウィリアム(ヴィルヘルム)・クナーベは1864年5月21日に死去し、
息子のウィリアムとアーネスト・J・クナーベ兄弟と義理の息子のチャールズ・ケイデルが後を継いだ。
1866年、Wm Knabe & Co. は鋳鉄製フレームに直接螺入される代わりに
より重い真鍮の部品へと螺入されたアグラフを持つ「agraffe treble」を発表した。
1866年までに、彼らは約230人の工員を雇用し、
年間約千台のピアノ(アップライト、スクエア、グランド)を製造。
工場は30馬力(22 kW)の蒸気機関や蒸気駆動のエレベータ、乾燥室を備え、グランドピアノのケース、響板、
アクションの製造、ケースのワニス仕上げ、鋳鉄フレームの金めっきを行う12メートル幅の第二建物が増設された。
さらなる補強とキューポラ(円頂塔)によって1869年に工場が完成した。
米国でのKnabe & Co. の売上はニューヨークのスタインウェイ・アンド・サンズとボストンの
チッカリング・アンド・サンズに次いで第3位につけ、1870年までの生産代数は週に約40台
(600米ドルから2千米ドルの間の価格)と見積られた。
1873年、Wm. Knabe & Co. はニューヨーク5番街に自社経営の商品展示場を開設した。
1876年のフィラデルフィア万国博覧会にはグランドピアノ、スクエアピアノ、アップライトピアノ、
Tschudi & Broadwood製ハープシコードを出展し、改訂された表彰システムによりその他多くの共同出展者と共に
最高の栄誉を手にした。1882年にはチェスター・A・アーサーのためにホワイトハウスへローズウッド製
コンサートグランドを届けた。
ウィリアム・クナーベ Jr. は1889年に死去した。
会社は同年、アーネスト・J・クナーベを社長として百万米ドルの資本金で法人格を取得した。
アーネスト・J・クナーベは1894年に死去し、工場で修行していた息子達が後を継いだ。
アーネスト・J・クナーベ Jr. は社長に選出され、ウィリアム・クナーベが副社長兼会計係となった。
Wm. Knabe & Co. は1903年までにカナダとイングランドに代理店を設立し、事業をさらに拡張する目的のために
工場を抵当に入れた。1906年までに、工場は大規模に拡張された元の建物と7つの建物を占有し、
念入りに設計された総床面積は約300,000平方フィート (28,000 m²)、従業員は765人を数えた。
工場設備は個別に動力が供給された機械やボイラーと連結された集塵システムといった現代的な
電気器具を含んでいたものの、Knabeはピアノは丁寧に手作りする必要があるという基準と、
そのために完成までにアップライトで6か月、グランドピアノで2年を要するということを宣伝した。
<別解説>
クナベピアノの歴史は、1803年にドイツで生まれたウィリアム・クナーベから始まった。
彼は伝統的なドイツ人で、教育者になるために学校に通っていたが、
ピアノ職人になるために進路を変更した。
彼はドイツで見習いをした後、1833年にボルチモアに移った。
その後、当時著名な発明家であったヘンリー・ハルチェの下で6年間働き、
英米のビジネスセンスを磨いた後、1839年に友人のヘンリー・ゲーレと共にベンチャー企業を立ち上げた。
クナーベ&ゲールは、1860年に南北戦争が勃発して経営が行き詰まるまでは、
優れたピアノと堅実なビジネス手法で南部全域の市場を掌握していた。
1864年にクナーベが亡くなり、ゲーレも事業から撤退したため、
クナーベの2人の息子であるアーネストとウィリアムが事業を引き継ぐことになった。
彼らには、戦争による市場の低迷からビジネスを回復させるという使命があった。
ボルチモアに工場があったので、ウィリアムが工場を運営し、アーネストは戦争の影響を受けていない
北部や西部の州の市場を開拓するために旅に出た。
ボルチモアの銀行からお金を借りたという逸話もあるほど、アーネストは売り上げを伸ばして
事業を回復させ、ニューヨークに2つの工場を新設したのである。
1894年にウィリアムとアーネストが相次いで亡くなると、会社はアメリカン・ピアノ・カンパニーに買収された。
1932年には、エオリアン・アメリカン・コーポレーションが設立され、Knabe社を買収し、
Sohmer、Falcone、George Steckなど、買収したばかりの多くのブランドと一緒に生産した。
その後、メイソン&ハムリン社の傘下に入り、1996年にYoung Chang氏が製造を引き継ぐまで、
Knabeのピアノは製造されていた。その後の一連の買収により、韓国のSamick Music Corporationが
Knabeの名前で新しいデザインのピアノの生産を続けている。
フランシス・スコット・キー(星条旗の作曲者)が所有していたKnabe & Gaehle社製の
スクエアグランドピアノは、1842年に製造された豪華な螺鈿鍵盤を備えたものだった。
クナーベピアノは、その芸術的な外装で知られており、現在でもインテリアデザイナーや
装飾品を求める住宅所有者に愛されている。
外観の美しさだけでなく、Knabeピアノは信じられないほどの音色の良さと健全性を持っています。
戦時中の不況や事業の回復にもかかわらず、1876年までにKnabeのピアノはその音色、職人技、
品質が評価され、多くの高額な賞を受賞しました。
D'AlbertやSaint Saensなどの有名なピアニストが、コンサートでクナベのグランドピアノを好んで使用した。
アーネストは、アップライトピアノやグランドピアノのために多くの新しい音階を発明し、
クナーベピアノは多くのコンサートホールや音楽家の羨望の的となり、その名声を高めていったのである。
また、ウィリアム・スタインウェイやアルベルト・ウェーバーとも親交があり、業界とのつながりも強かった。 |
W .NAESSENS
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
W .NAESSENS & CO.
ピアノ内部には「BERNE」の文字と「1914」の文字
詳細不明
<オランダの某HPの解説>※日本語に訳しました
J.W.Th.Naessens氏は1862年にオランダのザルトボメルで生まれました(1915年没)
彼はピアニストとしてキャリアをスタートさせました。
1887年に彼はオランダ領東インドでインドネシアの女優(のちに画家)の
ミア・アーウェン(マリア・フレデリカ・ヴァルデナー)と結婚。
インドネシアでのコンサートツアー中に、彼はインドネシアに滞在することを決め、
インドネシアのスラバヤに定住しました。
彼はビジネスの才能もあり、インドで良いピアノが必要とされていることを知っていたので、
1891年にピアノなどの楽器の輸入販売を中心としたW.Naessens & Co.社を設立しました。
やがて、熱帯広葉樹の家具を使ったピアノの製造も始めた。
その後、スマラン、メダン、ジョグジャカルタ(ジョグジャ)に支店が開設されました。
1897年にはバタビアに支店ができ、その後(1911年)にはスマランとメダンにも支店ができました。
1913年にはジョクジャにも支店ができました。
コルミット家のHPによると、スラバヤにあったジョン・コルミットのピアノ工場を引き継いだのは1903年。
ヨーロッパのメーカーが外装に使用していた木材は、東南アジアの気候や害虫による劣化に特に弱かった。
突き板はすぐに剥がれ、外装はひび割れたり反ったりし、艶もすぐに目立たなくなり、
柔らかい木は「ラジャップ」(シロアリ)や「ボエボエック」(木虫)の格好の餌食になった。
インドではジャティ材として知られるチーク材だけが、これらの害虫に強い。
Naessensは、ヨーロッパの大手メーカーを説得して、外装なしでインドに楽器を供給することに成功した。
特別に訓練されたジャワ人や中国人の大工や建具職人が、その場で彼らを中心としたピアノを製作した。
しかし、Naessensは自動演奏のピアノ(ピアノラ)にも大きな可能性を見出していた。
1903年、彼はオランダに戻り、インドでのビジネスは現地のエージェントに任せた。
Naessens&Coは、仲間のパートナー(および従業員)のFGTimmとMOC Adamiによって、
オランダ領東インドで何年も続けられました。
最後に知られている広告は1941年にさかのぼりますが、その会社はまだスラバヤにあるようです。 |
| W. P. EMERSON PIANO CO. |
詳細不明 |
W.P. HAINES
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
W.P. Haines ウィリアム・P・ヘインズ アメリカ(ニューヨーク) 創業1898年
W.P.ヘインズ社(Haines Brothersとは別会社)は、ニューヨークのウォルトンアベニュー
138丁目にあったピアノ製造会社である。
1898年にWilliam P. Hainesによって設立され、2世代後の1910年にHainesの孫である
社長のT. Linton Floyd-Jonesによって法人化された。
大量生産が可能なため、自社の楽器だけでなく、他社の楽器も作ることができた。
ニューヨーク州バッファローの著名なピアノディーラーであるロバート・ラウドは、
20年間にわたってW.P.ヘインズ社製のピアノを使用していた。
W.P.ヘインズ社はブラッドベリ・ピアノ・カンパニーの生産を管理しており、
1920年から1930年のブラッドベリ・ピアノにW.P.ヘインズ社のシリアルナンバーが付いているのは
そのためである。
ウェブスター・ピアノ・カンパニーもブラッドベリと似たような運命をたどった。
世界大恐慌が起こると、W.P.ヘインズ社は以前のような経営ができなくなり、
より大きなウィンター・ピアノ・カンパニーの傘下に入るという苦渋の決断をし、
1950年までW.P.ヘインズのブランド名を使用していた。
W.P.Haines & Co.のピアノは良質の楽器として知られている。
W.P.Haines & Co.のピアノは良質な楽器として知られており、アップライトピアノ、
ベビーグランドピアノ、プレーヤーピアノのフルラインを揃えていた。
W.P.Haines & Co.のアップライトピアノとプレーヤーピアノのシリアルナンバーは
1899年から1949年まで、グランドピアノのシリアルナンバーは1923年から1929年までです。
1959年にウインター(WINTER & CO.)は、エオリアン・アメリカン社と合併し、
社名をエオリアン・コーポレーションに変更していた間、
ウィンター&カンパニーが製造していたブランド名の一つです
→詳しくはWINTERの項目へ
(※ご注意)名称が似ていますがこのピアノ会社は、「HAINES BROS.」とは別の会社です |
W. W. KIMBALL
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
キンボール社(KIMBALL)が取り扱ったブランド
→詳しくはKimballの項目へ |
| W. RITMÜLLER & SOHN |
→RITMÜLLERの項目へ |
| WADDINGTON |
詳細不明 |
WAGNER
(WAGNER HIROSHIMA)







画像クリックでHPへ戻る |
WAGNER ワグナー (通称:広島ワグナー/WAGNER HIROSHIMA)
実はワグナーピアノの元祖はこちらです
製造元:東洋楽器製造株式会社(広島) ※元祖ワグナー
関東大震災後、広田ピアノを創立した広田栄太郎氏の長男の広田武雄氏が
屋代千里氏と合同して作った東洋楽器製造(株)のブランドです。
工場は、広島県の誘致工場として広島市吉野本町879にありました。
当時、ピアノ製造が静岡県の浜松に集中する中、珍しく広島にありました。通称広島ワグナーとも。
作りはかなりしっかりしており、レンナーハンマーなどの高級部品をふんだんに使い、
当時はヤマハピアノも凌駕する超高級機種でした。
鉄骨部分には「TOYO GAKKI S.K.K.」と入っております。
ちなみに、エンブレムの内の下の部分には「HIROSHIMA」と入っていますね。
左記画像の「寄稿」と入っているものは「匿名希望様」からすべてご寄稿を頂きました。
この度はたくさんの画像のご提供を頂きまして誠にありがとうございます!
■機種バリエーション
No300、YW20、W20、W30、W40等
この広島にあった東洋楽器製造株式会社は昭和39年(又は昭和40年?)に一旦廃業しました。
ちなみにピアノ販売最盛期は昭和55年頃なのですが、この昭和39年というのは日本に於ける
ピアノ製造の趨勢最盛期よりもかなり前になります。
廃業後、別法人として「東洋ピアノ製造株式会社」と、「アトラスピアノ製造株式会社」が
この「WAGNER」ブランドの商標権利を引き継ぎ製造を継続。最盛期には大きく販売を拡大させました。
※最盛期については下記東洋ピアノ製造株式会社になってからのワグナーの項目参照
この度、私自身もこの広島ワグナーに出会う機会がありましたので画像を掲載致します。
左記下の2枚のトレードマーク画像と下記の画像です。(ピアノカルテと入っている画像)
昭和34年製造で60年以上経っていました、本当に良く出来ているピアノという印象を受けました。
<画像集>
アクションレールに付いているTOYOのプレート →★ ピアノ全体画像 →★
当時の領収證 →★(価格は10,2500円だったようで、表記は領収証ではなく領収證になっています)
ピアノ保証票 →★(保証書ではなく保証票という点が歴史を感じますね♪)
当時は八重洲ピアノ社等が販売元だったようです。 |
|
WAGNER




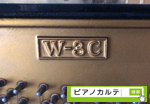
画像クリックでHPへ戻る
|
ワグナー/(ワーグナー)
※あの有名な作曲家は”ワーグナー”と伸ばして呼ぶことが多いですが、
経験上、このピアノの正式な読み方は”ワグナー”が一般的な感じを受けます。
(元祖)製造元:東洋楽器製造株式会社(広島) ※敢えて上記の「広島WAGNER」とは分けています
※詳しくは上記の広島ワグナーの項目を参照
製造元:東洋ピアノ製造株式会社
製造元:アトラスピアノ製造株式会社
製造元:有限会社 アサヒ工芸社(前身:朝日楽器製作所)(浜松市)
<広島ワグナー時代の歴史>
関東大震災後、広田ピアノを創立した広田栄太郎氏の長男の広田武雄氏が
屋代千里氏と合同して作った東洋楽器製造(株)のブランド。
広島県の誘致工場として広島市吉野本町879にありました。
当時、ピアノ製造が浜松に集中する中、珍しく広島にありました。通称広島ワグナーとも。
東洋ピアノ製造の頃、協立楽器のブランドとして販売していました。
私自身もよく納品調律に伺いました。
本当に良く出来ているピアノで、むしろヤマハより良いピアノと感じるほど。
ピアノのつくりは東洋ピアノの全盛期の技術がふんだんに入っており、とても良いピアノです。
特に低音域の音の広がりは好きです。
また、チューニングピンのピン味(いわゆるトルク具合)も、たとえ製造から30年経っている
古いピアノだとしてもピンルーズが出ることもあまりなく長持ちします。
総合的にバランスが取れており、むしろ当時同じ時期発売の廉価版ヤマハよりもはるかに良いです。
当時ヤマハ・カワイとの販売競争が熾烈を極め、それを超えるピアノを作ろうと努力していた賜でしょう。
<追記>
近年販売の新品WAGNERは過去の面影はまったくなく、アサヒピアノ(輸入ピアノの総合総社)が
東洋ピアノ製造から商標権を譲り受けて製造している中国製ピアノのようです。
過去の輝かしいあの東洋ピアノの歴史をすべてパクっているところが中国らしいです。
中国製ワグナーを実際に調律する機会があれば品質についてここにレビューさせて頂きます。
■機種バリエーション (協立楽器販売以降)
W1(W-1CE、W-1CM)
W2(W-2CE、W-2CM)
W3(W-3E、W-3M、W-3CE、W-3CM、W-3CLM)
W5(W-5CE、W-5CM)
W71(W-71E、W-71M、W-71W)など
ワグナーのM.O.T.(下パネ内部の天秤棒部分に書かれた記載)
→★
M.O.T.通称:ガチャガチャ部品本体の写真 →★
ワグナーの調律記録カード(アポロ時代と同じですね)
→★ ワグナーのキーカバー純正品
→★
ワグナーピアノのまくり(フタ部分)にあるブランド銘柄マーク
→★ 口棒にあるTOYOの銘柄 →★
親板内側にある文部省教育用品審査合格シール →★ ルイスレンナー製のハンマーを使用 →★
アポロピアノもワグナーピアノも東洋ピアノ製造なのでTPKと入っています(2つを並べた写真)
→★
<ピアノ調律技術者向け附録>
張弦作業に役立つ当該機種ミュージックワイヤー配線仕様 →★
平成29年2月3日、ワグナーピアノ(W1)をりっこう幼稚園のチャペルへ寄贈させて頂きました
→★
ワグナーのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★ |
|
WAGNER
(HANKYU WAGNER)


画像クリックでHPへ戻る
|
阪急ワグナー/ハンキュウ ワグナー (HANKYU WAGNER)
通称:ハンキューワグナー
製造元:アトラスピアノ製造株式会社
製造元:東洋ピアノ製造株式会社
販売元:阪急百貨店(阪急阪神百貨店)
こちらは阪急(HANKYU)と入っているワグナーピアノです。
阪急百貨店向けで売られていたブランド
非常に珍しいトレードマークです。
詳細はワグナーの項目を参照してください。
ワグナーのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★ |
WAGNER
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ワグナー 日本のワグナーとは違うようだが、詳細不明
→詳しくはYoung Chang(ユンチャン)の項目へ
<追記>
近年販売の新品WAGNERは過去の面影はまったくなく、アサヒピアノ(輸入ピアノの総合総社)が
東洋ピアノ製造から商標権を譲り受けて製造している中国製ピアノのようです。
過去の輝かしいあの東洋ピアノの歴史をすべてパクっているところが中国らしいです。
中国製ワグナーを実際に調律する機会があれば、品質についてここにレビューさせて頂きます。 |
| WAGNER SPECIAL |
ワグナー・スペシャル 東洋ピアノ製造株式会社
※トレードマークはワグナー(WAGNER)と同じ |
| WAGNER CLASSIC |
ワグナー・クラシック 東洋ピアノ製造株式会社
※トレードマークはワグナー(WAGNER)と同じ |
| WAGNER IMPERIAL |
ワグナー・インペリアル 東洋ピアノ製造株式会社
※トレードマークはワグナー(WAGNER)と同じ |
WAINBACH
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ワインバッハ 韓国
機種バリエーション:W-5等
その他詳細不明
※WEINBACHというチェコ製のピアノもありますが、違うピアノです(スペルが違います) |
| WALDHÄUSL, ROBERT |
詳細不明 |
WALDSTEIN


画像クリックでHPへ戻る |
WALDSTEIN バルトシュタイン/ワルドシュタイン/(ワールドシュタイン)
製造元:三高アクション製作所(浜松市薬師町763番地)
製造元:及川ピアノ製作所(浜松)→のちに東洋ピアノ製造(TPK)
製造元:東海楽器製造株式会社
発売元:三浦ピアノ店(文京区東大前)
戦前から、東京文京区東大前の三浦ピアノ店を代理店として売り出された。
”CHOPIN/ショパン” というピアノ機種も同様。 |
| WALLACE ASH |
詳細不明 |
| WALLACE PIANOFORTE CO. |
詳細不明 |
| WALSMANN M. |
詳細不明 |
WALTER


画像クリックでHPへ戻る |
WALTER PIANO CO. ウォルター
アメリカはインディアナ州エルクハートにあり、以前は有名な管楽器メーカーである
コーン社の一部門としてピアノの研究製作がなされていたが、その後ジャンセンピアノ社に
買収された。ブランドはジャンセン(JANSEN)である。
このトレードマーク画像はMelody様からご寄稿いただきました。 |
WALTER
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ウィーンのWALTER(ワルター)は、
→ANTON WALTERの項目へ |
| WALTER, CHARLES R. |
詳細不明 |
| WALTERFORTH |
ワルターフォルス/ウォルターフォルス アカシアピアノ株式会社 |
WALTHAM PIANO CO.
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ウォルサム アメリカ(ウィスコンシン州ミルウォーキー) 創業1885年
ウォルサムピアノは、ウィスコンシン州ミルウォーキーにある
ウォルサム・ピアノ・コーポレーションで製造されていました。
この会社は1885年に設立され、1900年代初頭に買収されるまで事業を続けていた。
1906年には法人化し、様々なスタイルやモデルのピアノを製造することに成功した。
ウォルサム・ピアノ社は、社名の由来となったウォルサム・ピアノのほか、
以下のようなモデルを製造していた。
Warfield、Wilson、Electratone、Kilbourne、Auburn、Lincoln、Sherwood、Oakland
後にウォルサムはネットゾウ・ピアノ・カンパニーの傘下に入り、これらのピアノの生産を継続したが、
数十年の間に特定のブランドを徐々に廃止していった。
ウォルサムはアップライトピアノ、プレーヤーピアノ、グランドピアノ、
リプロダクション・プレーヤーピアノを製造していた。
プレーヤーピアノのモデルの一つは、プレーヤーピアノのシステムをデジタル化する初期の動きの中で、
プレーヤーの電源を入れるスイッチを電動化したものだった。
ウォルサムは、当時の他の多くの企業と同様に、高品質の素材、ケースデザイン、
音質を誇るピアノを宣伝していた。 |
WALWORTH
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
アメリカ(シカゴ) 読み:ウォルワース?
ピアノ鉄骨部に「SCHULZ CO MAKERS」と書いてあります。
→M. SCHULZ & CO.の項目も参照
その他詳細不明 |
WANAMAKER
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
Estey Piano Corporation
→詳しくは「Estey」の項目へ |
| WARFIELD |
詳細不明 |
WARTBURG
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ヴァルトブルグ/ワルトブルグ 東洋ピアノ製造株式会社 |
| WASNICZEK |
詳細不明 |
| WATERS, HORACE |
詳細不明 |
| WATLEN, JOHN |
詳細不明 |
| WEAVER |
詳細不明 |
|
WEBER


画像クリックでHPへ戻る
|
WEBER ウェーバー
製造:ユンチャン社(韓国)
→詳しくはYoung Chang(ユンチャン)の項目へ
(注)ウェーバーというピアノですが、ニューヨークのエオリアン・アメリカン・コーポレーション傘下の
系列会社製品の「ウェーバー」という本家本元のピアノがありますが、このエンブレムのピアノは
明らかに韓国製のウェーバーですのでご注意下さい。※長年の経験から分かります。
その他、中国でもウェーバーというブランドがあるらしいですが詳細は不明。
韓国製ウェーバーのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★ |
WEBER
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
WEBER ウェーバー 中国 ドンペイ 詳細不明
|
WEBER

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
WEBER PIANO CO. ウェーバー 創業1852年
※エオリアン・アメリカン・コーポレーション(ニューヨーク)
1852年にアルバート・ウェーバーによってニューヨークで創業されたピアノメーカー。
極めて歴史の古い楽器で、ローマ法王庁に納入されたものであるというが、日本では
このことはほとんど知られていません。
ピアノのまくり(蓋部分)のWEBERの下には「NEW YORK LONDON」と書いてあります
1852年にアルバート・ウェーバーによって設立されたウェーバー・ニューヨーク・ピアノ社は、
当時の有名なピアノメーカーでした。
ピアノをはじめとするさまざまな楽器を扱うことで知られていた。
世界大恐慌の影響を受けたにもかかわらず、ウェーバー社は事業を継続し、
20世紀に入っても繁栄を続けた。
ウェーバーピアノは、当時、最も高価で最高の素材を使って作られていた。
ウェーバーのピアノは、当時入手可能な最も高価で最高の材料を使って作られており、
アメリカの富裕層やプロのピアニスト向けに販売されていました。
19世紀後半には、ウェーバーは業界でも最も高価で精巧なピアノを製造していた。
1903年、ウェーバーはエオリアン・ピアノ・カンパニーの傘下に入り、
1930年代にはエオリアン・アメリカン・コーポレーションとなった。
1980年代にエオリアン社が倒産した後、ウェーバーのブランド名は
韓国のYoung-Chang社に買収され、現在もウェーバーの名前でアジアの輸入ピアノを製造している。
19世紀、ウェーバーは最高級のスクエアピアノとグランドピアノを専門に製造していたが、
世紀末を迎えてピアノの様式が変化すると、一般の需要に合わせてアップライトピアノと
グランドピアノに力を入れるようになっていった。
ウェーバーの需要の多くは、エリート層の家庭内ピアノ演奏の増加に伴い、アップライトが占めていた。
アルフォンソ13世やピウス10世はウェーバーを御用達とし、ローマ教皇は使徒座の宮殿にピアノを注文した。
1876年のフィラデルフィア百年祭、1887年のロンドン万国博覧会、1889年のパリ万国博覧会でも、
ウェーバーのピアノは栄誉ある賞を受賞している。 |
WEBERN
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
WEBERN ウェーベルン (有)及川ピアノ製作所(浜松) 詳細不明 |
| WEBSTER |
詳細不明 |
WEGMAN
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ウェグマン(ウェッグマン) アメリカ(ニューヨークのオーバーン) 創業1882年
ウェグマン・ピアノ・カンパニーは、1882年にニューヨークのオーバーンで設立されました。
創業者であるヘンリー・ウェグマンは、スイスで生まれ、ニューヨークに渡り、スタインウェイ社に就職。
1882年、彼は独立してイサカに「ウェグマン&ハニング・ピアノ・カンパニー」を設立した。
その後、パートナーのハニングとともに、5年後にはオーバーンに会社を移転することを決めた。
ビジネスパートナーのクリスチャン・ハニングもスイスからの移民である。
新しい工場では、週に6台のピアノを生産していた。
少ないとはいえ、アメリカでピアノが普及する前の1880年代後半にしては、驚異的な生産量であった。
20世紀に入ってからはオルガンの製造を中止していたが、
製造初期の頃はピアノと並行して製造していたことで知られている。
また、Chase & BakerやVoughのブランド名でピアノを製造していた。
後に、エスティ・ピアノ・カンパニーの傘下に入り、ウェグマンのブランドは1956年頃に廃止された。
ウェグマンは、当時としてはモダンで質の高いピアノを作ることで知られていた。
そのデザインは非常に美しく、音色も優れていた。
オーバーン社製のピアノには、特許を取得したチューニングピン・ファスナーが採用され、
ウェグマンは、他のピアノに比べて調律が長持ちすると評判だった。
また、価格も手ごろだったので、西部での人気も高かった。
1895年の広告では、ウェグマン・ピアノ社が万国博覧会の審査員に認められたことを伝えており、
審査員は次のように述べている。
"まず、第一に音色が非常に良い。
第二に、持続時間と歌唱力が優れていること。
第三に、音階のバランスがよいこと。
第四に、動作が軽く、反応が迅速であること。
第五に、芸術的なデザインのケースです。
第六に、新しい特徴として、
チューニングピンをロックするために、鉄製のフレームに偏心した穴があり、
そこにチューニングピンがうまく収まっていること。
第七に、職人の技と材料の両方が優れていること。"と述べられている。
→「Estey」の項目も参照 |
| WEIDENSLAUFER |
詳細不明 |
| WEIDIG, C. |
詳細不明 |
| WEIHENMEYER & CO. |
詳細不明 |
WEINBACH

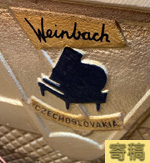
画像クリックでHPへ戻る |
WEINBACH ワインバッハ
チェコスロバキア製 (現在:チェコ共和国) ペトロフ社のセカンドブランドです
WEINBACHの外観写真 →★ WEINBACHの内部写真 →★
まくり(蓋部分)にあるWEINBACHの文字部分 →★
まさにペトロフそのものという雰囲気ですね!
左記トレードマーク画像をはじめ、その他の画像は「高永ピアノ調律事務所様」からご寄稿頂きました。
この度は画像のご寄稿を頂きまして誠にありがとうございます! |
|
WEINBERGER






画像クリックでHPへ戻る
|
ワインバーガー WEINBERGER
韓国製。ローゼンストックやエッシェンバッハと同系のピアノです。
ワインバーガーは小さなタイプのピアノのみ。初期タイプはWB109、全盛WB110、後継はWB117。
協立楽器/キョーリツ インターナショナル販売 (KYORITSU INTERNATIONAL INC.)
値段は新品で30万円を切る安価で、電子ピアノを購入しようと思っていた方が、
アコースティックピアノとさほど値段が変わらないならばと選ぶことが多い機種でした。
同系のローゼンストック(RS101やRS108)と並んで、このワインバーガーもかなりの台数が売れたようです。
小型のわりにはそこそこの音量は出ますが、音色・音質はTHE韓国製といった感じです。
JIS規格(日本工業規格)8507・8508 表示承認
ワシのトレードマークですが、過去に国内で販売されていた(有)共立工芸社のアストリア(ASTORIA)や
井ヅツ楽器株式会社の(KUHLMANN)というピアノブランドのトレードマークに非常にそっくりです。
尚、ドイツの国章にもそっくりです →★ トレードマークを並べて比べた画像 →★
■機種バリエーション
黒塗→ WB109E、WB110E、WB117E マホガニー塗→ WB109M、WB110M、WB117M
極限までコンパクトにしたアクション(キータッチのレスポンスが悪いのはこのためです)
→★
ワインバーガー外装の銘柄マーク →★
<ピアノ調律技術者向け附録>
張弦作業に役立つ当該機種ミュージックワイヤー配線仕様 →★
ワインバーガーのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★ |
WEINBURG
 画像クリックでHPへ戻る 画像クリックでHPへ戻る |
WEINBURG ワインバーグ 韓国(三益) 詳細不明
機種:SU-42F、SU-118F、WE-118、WE-121等
レスターピアノ製造株式会社という情報もあり
※参考
下記に列挙するブランドはすべて同じ雰囲気のトレードマークとなっており、どれも韓国製造と思われます。
REID-SOHN、KAFMANN、SAMICK、SCHNABEL、WEINBURG、U. WENDELL、UHLMAN SUPER |
| WEINSTEIN & SONS |
WEINSTEIN AND SONS
詳細不明 |
| WEINSTEIN CURVEX ACOUSTICON |
詳細不明 |
WEISS
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
WEISS ウェイス ドイツ(旧西ドイツ) 詳細不明
|
| WEISSBROD |
詳細不明 |
WEIZENBACH
WEIßENBACH


画像クリックでHPへ戻る |
WEIßENBACH WEZENBACH Weißenbach ヴァイゼンバッハ
ドイツ クリマ社? バイエルン州ヴァイゼンプルーン
ヴァイゼンバッハピアノは、バイエルン州北部の小さな町、ヴァイゼンプルーンで造られています。
製作者であるドイツピアノマイスター、フランク・デッケルマン氏は1990年に責任者として勤めていた
ピアノ会社を辞め、自分と数少ない職人と共にヴァイゼンプルーンに移り、ピアノ造りを始めました。
彼のピアノ造りに対するこだわりはコストダウンの為、オートメーション化され、安価な材料を使った
ピアノ造りを否定し、職人自身の手によるピアノ造りにあります。
そして彼自身の手によって一台一台作られるピアノはゆっくり時間をかけ、最高の材料を吟味し、
納得のいく音色を奏でるまでに丹念に作りあげられています(HPより抜粋)
トレードマーク画像は「白川ピアノ調律所様」からご寄稿頂きました。ありがとうございます! |
WELBER

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
WELBER ウェルバー
日英ピアノ製作所(浜松市浅田町)
浜松市浅田町にあった日英ピアノ製作所で作られたピアノ。
昭和30年代のピアノ。
|
WELBER
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
WELBER ウェルバー
日産工業株式会社/日産楽器(浜松)、内山楽器KK(浜松) 昭和20~30年代のピアノ。 |
| WELCE |
ウェルス →P. WELCEの項目へ |
WELLINGTON

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
WELLINGTON ウェリントン/ウエリントン
ケーブル・ネルソン(ケーブルピアノ社)で作られているピアノブランドで工場はオレゴン州にある。
大衆向きに大量生産される普及品の楽器とのこと。
ウェリントンは、ニューヨークのケーブル・ピアノ・カンパニーが製造していたピアノのシリーズです。
ウェリントンは、1885年頃から1953年頃まで、何十年にもわたって生産された。
ケーブル社は、高級ブランドに手が届かない人々のために、
より低価格な選択肢としてウェリントンを製造していたが、
ウェリントンは高品質でよくできた楽器であった。
美しいケースと魅力的な音色、そして手頃な価格でありながら耐久性にも優れているという
稀有な品質を持っていた。その品質と価値から、ウェリントンピアノは国内外を問わず、
長年にわたって高い需要があった。 |
WELMAR
WELMAR U.K.


画像クリックでHPへ戻る |
WELMAR ウェルマー イギリス(ロンドン、ストラウド)
ブリュートナーのイギリス代理店であったウェルプデール、マックスウェルは第一次世界大戦後
なんとか生き延びたブリュートナー工場で生産を開始するが、ドイツ製品に対する反感がイギリス中に強まり、
独自のピアノを製造するようになった。
<歴史>
ロンドンのスクワイアー・アンド・ロングソン社は、ロンドンのキャンバーウェルの工場で
ウェルマーのブランド名でピアノ製造をする契約を持ちかけられた。
しかし、そのロンドンの工場は1929年に火災で焼けてしまい、再建後も経営不振が続いた。
高い評判を得ていたにもかかわらずスクワイアー・アンド・ロングソン社は廃業を余儀なくされ、ブランド名は
ケンブル社に買われた。
ウェルプデール、マックスウェル・アンド・コッドが所有するウェルマー・カンパニーはクラパムの新工場へ移り、
その際、スクワイアー・アンド・ロングソン社から有用な人物が参加した。
ウェルマー・カンパニーは137cmと183cmの2種類のグランドピアノを製作した。
ライプツィヒのブリュートナー社の工場で修行を積んだジャック・コッドの経験を生かし、
ウェルマー・カンパニーはブリュートナーの音色を持つピアノの製作に力を注いだとされる。
1939年に第二次世界大戦が始まると、イギリス政府はピアノ製造会社の合併を強いた。
そしてマーシャル・アンド・ローズや、ロジャーズ、ブロードウッドなどのイギリスのピアノブランドは、
ロンドン(クラパム)にあるウェルマーの工場へ移った。
ウェルマーのアップライトピアノは2000年までこのロンドンの工場で生産されたが、この年にウェルマーや、
ナイト、ベントレー、ブロードウッド、マーシャル・アンド・ローズのブランド名でピアノを製造する、
ウェルプデール、マックスウェル・アンド・コッド・グループは、ウッドチャスター・ピアノ・カンパニーと合併し、
ブリティッシュ・ピアノ・マニファクチャリング・カンパニーとなった。
現在、これらのすべてのブランドのピアノは、イギリスで最も有名なピアノ工場である、ストラウド近郊の
ウッドチェスター・ミルズ工場で生産されている。
<附録>
ウェルマーピアノ 製造番号/製造年代 対照表(1925年~2000年) →★ |
WELLTONE

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
WELLTONE ウェルトン
製造元:三高アクション製作所/三高アクション製造株式会社(浜松市薬師町763番地)
製造元:有限会社 松本ピアノ工場
昭和31年頃に作られた。浜松市薬師町にあった三高アクション製作所で、
85鍵、73鍵などの小型ピアノも作った。
二重交差弦を採用していることを広告していた。
|
WELT & KREUTZER

画像クリックでHPへ戻る |
ウェルト&クロイツェル
株式会社 クロイツェルピアノ
機種名にPU-が付くと当時技術提携していたPACO(北朝鮮製)です。
詳しくは→KREUTZERの項目へ |
| WELTE-MIGNON |
WELTE-MIGNON アメリカ(ニューヨーク)
詳細不明 |
| WELTE & SOHNE |
→M. WELTE & SOHNEの項目へ |
| WELZEL P.F. |
詳細不明 |
|
WENDL & LUNG




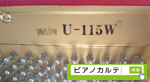

画像クリックでHPへ戻る
|
ウエンドルラング(ウエンドルアンドラング)
WENDL & LUNG (ウエンドル・アンド・ラング)
朝日ピアノ販売(浜松(に拠点を置く会社))、製造は中国製のピアノです。
ピアノ線(ミュージックワイヤー)はレスロー弦を使用しているのが特徴 (3枚目画像の青いシール)
中国製の割にはとても丁寧に作っている感じですが、ピン味に粘りがあってとても音を合わせづらい印象。
音色はシャリシャリした感じで繊細さに欠けますが、粘り強く調律と整音を重ねればかなり良くなります。
一番下の画像はウエンドルラングのグランドピアノです。
ピアノ内部に貼ってあるレスローワイヤーのシールの拡大写真
→★ 朝日ピアノの保証書
→★
ウェンドル&ラングのグランドピアノまくり(蓋)部分の銘柄マーク →★
<ピアノ調律技術者向け附録>
張弦作業に役立つ当該機種ミュージックワイヤー配線仕様 →★
<以下、ウィキペディアより引用抜粋>
ヴェンドル・ウント・ルング(Wendl & Lung)またはウェンドル・アンド・ラングは、
オーストリアのウィーンに本拠を置くピアノメーカーである。ピアノの製造は中国の協力工場で行われている。
ウェンドル・アンド・ラングのブランドは、1910年に、2人のオーストリア人、
シュテファン・ルング(Stefan Lung)とヨハン・ヴェンドル(Johann Wendl)の協力で、
オーストリアのウィーンで始まった。1926年には、生産台数が累計1000台に達した。
ウェンドル・ラングのピアノは、中欧および東欧を中心に供給された。
3代目のアレクサンダー・ヴェレツキ(Alexander Veletzky)は、1956年に会社を継ぎ、
楽器生産者共同組合の会長もつとめた。各地の博物館にある歴史的に貴重なピアノの修復など、
生涯をかけたその業績が認められ、ウィーン市から「ゴールデンメリット勲章」を授与された。
ピアノ製造については1930年ごろから減り始め1956年に中断した。
1980年に一旦再開したものの4年後にはウィーン工場での製造を終了していた。
シュテファン・ルングから4代目にあたるペーター・ヴェレツキ(Peter Veletzky)は、
22歳のときにオーストリアの史上最年少のピアノマイスターになり、1994年に家業を継いだ。
彼は中国の様々なピアノメーカーの技術アドバイザーとして活動した。
この関係は、2000年に彼の事業パートナーとなったErnest Bitterの中国系の妻Bai Linを通してもたらされた。
上海から近い寧波にある寧波海倫楽器 (Ningbo Hailun Musical Instruments Co.Ltd.) は、
はじめ楽器部品の製造をしていたが、2000年ごろからピアノの製造を開始していた。
社長の陳海倫は、ペーター・ヴェレツキと出会い、特別な友人となった。
ヴェレツキとBitter、そして陳夫妻のパートナーシップによって、2003年に、
ウェンドルアンドラングのブランドをもったピアノの製造が、中国寧波で新たに開始された。
アップライトピアノの生産からスタートし、後にグランドピアノモデルも生産されるようになった。
2010年時点での年間製作台数は約2400台で、オーストリア本社に20名、海倫鋼琴(ハイルンピアノ)には
800名の従業員がいるとのことである。ハイルンピアノは、中国のピアノメーカーの中でも
よく近代化された設備を持つピアノ製造工場である。
2010年には、ドイツ・ライプツィヒで1851年に創業された歴史あるピアノメーカーの
フォイリッヒ (FEURICH) を買収した。同時にウェンドル・アンド・ラングのブランド名は、
その製造専門技能・知識と共にハイルンピアノに移行し作り続けられている。
中国メーカーと、欧米ブランドの組合わせは、今日のピアノ業界では一般的なことである。
なじみある欧米のブランド名のピアノを、低価格で供給することができるのがその理由である。
しかし、それらのブランドは、しばしば中国の製造会社によって買い取られ使われているものである。
ウェンドル・アンド・ラングの場合は、現存する歴史ある欧州企業と新しい中国企業(工場)との
確かな協業であるという点で、珍しい例と言える。
アップライトピアノのラインナップとして122 cm、115 cm、110 cmの合計3モデル、
グランドピアノのラインナップとしてStephen Paulelloの設計による218 cmモデルの他、
178 cm、161 cmの合計3モデルがある。
基本はオーソドックスな現代ピアノの設計だが、新しい技術の導入にも積極的である。
外部のピアノ技術者との共同開発による新技術として、グランドピアノの第4のペダル(The harmonic pedal)、
アップライトピアノの高速連打アクション (Real double Repetition Action for upright pianos)、
磁石を利用したアクション(W&L-Dotzek High Speed Piano Action)などが、公式サイトで紹介されている。
これらのうちHarmonic Pedalが2009年に商品化された。
ウェンドル・アンド・ラングは、ディーラー網を通して、主として欧州、そしてアジアにピアノを供給している。
寧波海倫楽器は、いくつかの異なるブランド名のピアノを製造している。
Hailun(ハイルン)の他、Steigerman Premium、そしてWendl & Lungである。
このことが、市場でのHailunピアノにある種の混乱を生じている。ブランド間の差異は、技術的なもの、
そして材料や部品の供給元の違いであるとするが、Hailunブランドで"Vienna Series"と呼ぶ
新しいアップライトとグランドのシリーズを出すなど、曖昧になってきている。
日本には、2001年創立のアサヒピアノ(本社・浜松市)が総代理店となって、2004年から輸入している。
アサヒピアノでは、基礎組み立てを終えた状態のピアノを輸入し、先ず日本の環境に慣らすための
シーズニングを行ったあと、15名の技術者が最終調整して出荷しているという。
アサヒピアノの公式サイトに掲載されているラインナップは、アップライトで5サイズ、グランドで6サイズと、
前述のウェンドル・ラングの公式サイト掲載のラインナップより多くなっている。
ウエンドルラングのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★ |
| WERCH, LOTHAR |
詳細不明 |
WERLEIN
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ウェーレイン/(ワーレイン)/(ウェーレン)/(ウェーリン)/(ワレイン)
アメリカ(ニューオーリンズ) 創業1843年
1843年にフィリップ・ウェーレインがニューオリンズで始めたウェーレリンブランドのピアノ。
ウェーレインブランドのピアノの歴史についてはあまり知られていないが、興味深いことが分かっている。
1861年に南北戦争が勃発すると、北軍はニューオーリンズを占領した。
しかし、北軍が在庫をすべて押収する前に、フィリップ・ウェーレインは近くの納屋に数台のピアノを隠していた。
戦争が終わると、フィリップはピアノを隠し場所から取り出し、再建で引き裂かれた南部でビジネスを再開した。
再開したフィリップ・ウェーリン社は、ピアノをはじめとする様々な楽器を販売。
ウェーレインは全国各地に店舗を展開し、ビジネスマンとして大成功を収めた。
1900年代初頭には、ピアノの製造を中止し、「Werlein's for Music」という店名に変更しました。
Werlein社はあまりピアノを製造しておらず、Werlein社がいくつかの店舗を持っていた
アメリカ南部や西海岸以外ではほとんど見られません。
グランドスクエアとアップライトはどちらもWerleinが製造しており、
Werleinブランドの愛用者は非常に多い。
中にはスタインウェイのモデルよりもウェアリンのブランドを好むプレイヤーもいたほどです。
残念ながら、Werlein社のピアノに関する情報はあまりありません。 |
WERNER
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ワーナー アメリカ(イリノイ州シカゴ) 創業1920年
1900年代初頭に数多く存在したピアノ会社のひとつであるワーナーは、
1920年にイリノイ州シカゴのモーガン・アンド・スーペリア・ストリートに設立された。
ワーナー・ピアノ・カンパニーは、メイナード、ワード、ロングなどのピアノも製造していた。
その後、M.シュルツ社との提携により、シカゴのミルウォーキー通り711番地にある工場に
生産拠点を移した。
20世紀初頭のピアノ産業の多くがそうであったように、この会社も世界恐慌の頃に操業を停止した。
M.シュルツ社のプレーヤーユニットを搭載したワーナー・プレーヤー・ピアノは、
その操作性とコントロールのしやすさで定評があった。
シュルツ社のプレーヤーピアノは、当時の他の多くのピアノ会社とは異なり、
メーカー自身が製作したものであるため、他のプレーヤーユニットとは異なり、かなり珍しいものであった。 |
| WERNER, F.W. |
詳細不明 |
| WERNER, HANS |
詳細不明 |
| WERTHEIM |
オーストラリア(メルボルン)
THE WERTHEIM PIANO FACTORY
MELBOURNE AUSTRALIA |
WESER BROTHERS
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ウェーザーブラザーズは、1879年にジョン・ウェーザーによって設立されました。
ジョン・ウェーザーの5人の兄弟全員が、ニューヨークの大企業で働いていたという、
まさに家族経営の会社であった。
1920年代には、ウェーザーブランドのピアノだけでなく、Coloniet(コロニエット)、
Marveola(マルヴェオラ)、Re-Rendo(リ・レンド)、Orpheola(オルフェオラ)、
Winfield(ウィンフィールド)などのピアノも製造していた。
ウェザー社の工場は、3エーカー以上の広さがあり、複数のラインに対応できるようになっており、
ピアノの製造には最も熟練した職人しか雇わないという評判だった。
30年代半ば、ウィンター、ストーリー&クラーク、コーラー&キャンベルという2つの
大手ピアノメーカーがヴェーザーの名前を取得し、ヴェーザーブランドのピアノを生産するようになった。
ウェーザーの工場では、当時12万5千台以上のピアノを生産し、世界中に出荷していた。
しかし、第二次世界大戦が勃発すると、ヴェーザーピアノの生産は停止し、
戦後のアメリカでは完全に復活することはできませんでした。
ヴェーザーはグランドピアノ、アップライトピアノ、そしてプレーヤーピアノを製造していた。
緻密なケースデザインや上質な音色、コロニアルやピリオドモデルなどの特徴があり、
多くの人に親しまれている。
豊かな音色と耐久性が評価され、1800年代後半から1900年代前半にかけて、
音楽家の間で高い人気を誇った。
また、多くのモデルに搭載されているダイレクトドライブ・コンソールは、
ウェザーが世界に先駆けて開発したもので、同時代のピアノとは一線を画している。 |
| WESSELL. NICKEL & GROSS |
アメリカ(ニューヨーク) 1874年創業(※アクションメーカー)
1874年、Wessell, Nickel & Gross社は、Otto Wessell、Adam Nickel、Rudolph Grossの
3人の友人からで事業を開始しました。通称WNG。
彼らはそれぞれ、スタインウェイ社で働く優秀なピアノアクションを作る技術者でしたが、
友人の一人であるオットー・ウェッセルは、スタインウェイ社の組立ラインに縛られることに
満足していませんでした。彼や仲間たちは、ピアノアクションを改良するためのアイデアや
工夫をたくさん持っていましたが、スタインウェイ社で働いているために、
それを実験したり生かしたりすることができなかったのです。
このことを知っていたオットーは、自分と仲間の能力を確信し、アダムとルドルフにスタインウェイを辞め
自分たちのピアノアクション会社ウェッセル・ニッケル&グロスを設立するよう持ちかけました。
ウェッセル、ニッケル&グロス社は、設立当初から品質にこだわり、
さまざまな工夫や改善をアクションに反映させていました。
やがてWessell, Nickel, & Grossは優れたピアノアクションを作るという評判を確立していったのである。
評判が広まったことで注文が殺到し、ウェッセル・ニッケル・アンド・グロス社は工場を拡張し、
多くの従業員を雇い、より効率的にアクションを製作するための専用の機械や技術を開発した。
Wessell,Nickel & Grossは、革新的で高品質な伝統を維持しながら事業を拡大し、
"Wessell,Nickel & Gross "の名前はアメリカだけでなく世界的に知られるようになり、
最高品質のピアノアクションの代名詞となりました。
この時代、WNGは多くの著名なピアノメーカーにアクションを供給した。
Mason & Hamlin、Knabe、Ivers & Pond、J & C Fischer、Mehlin、Julius
Bauer、Everett、
Hallet & Davis、Star、Strohbert、Stieff、Packard、Mayland、Bush & Lane、Gabler、Heintzman、
Bush & Gertz、Hardman、Conover、Wheelock、Phragmatone、Behning and Son、Steinertなどの
著名なピアノメーカーにアクションを供給した。
しかし、Wessell, Nickel & Gross社の成功は永遠に続くものではなく、大恐慌の際には、
他の多くのピアノやピアノ関連企業とともに廃業に追い込まれました。
その後、WNGはエオリアン・ピアノ・コーポレーションに吸収され、独立した会社ではなくなった。
エオリアン社の傘下に入ったことで、Wessell, Nickel & Gross社は、エオリアン社以外のピアノメーカーにアクションを
供給することをやめなければならなくなり、悲しいことに品質が低下してしまったのだ。
その後、1953年から2005年までの間、Wessell, Nickel & Grossの名前は眠っていましたが、
2人の兄弟、Kirk BurgettとGary Burgettがこれを取得しました。
複合材やエポキシ・カーボンファイバーなどの現代の素材でアクションを製作。 |
| WESTBROOK |
詳細不明 |
WESTEN
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
WESTEN ウェステン 東洋楽器製造株式会社(広島) 詳細不明 |
| WESTERLUND |
詳細不明 |
WESTERN

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
WESTERN ウェスターン
製造元:株式会社 西川楽器製作所(西川ピアノ) 横浜
※(西川ピアノ時代のピアノ製造期間は1916年~1921年までとの記録がある)
発売元:株式会社 山野楽器店
西川ピアノの後期に上級品として特別に製作されたもの。
|
WESTMINISTER

画像クリックでHPへ戻る |
WESTMINISTER ウェストミンスター
スワン楽器製造株式会社
東日本ピアノ製造株式会社(浜松)
トレードマーク画像は「匿名希望様」からご寄稿頂きました。ありがとうございます!
<参考資料>
東日本ピアノ製造株式会社を含む会社遍歴は下記の通り
昭和28年 大岡楽器製作所が発足
昭和31年 白鳥楽器製作所
昭和33年 スワン楽器製造株式会社
昭和38年 ガーシュインピアノ株式会社
昭和42年 東日本ピアノ製造株式会社
昭和62年 株式会社バロック |
WESTON
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ウェストン 西村ピアノ商会 |
| WETZEL |
詳細不明 |
WHEELOCK
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ウィーロック 1873年創業 第二次世界大戦まで製造
ウィーロックのピアノは約150年の歴史がありますが、何度もメーカーが変わっています。
1873年にビリングス・アンド・ウィーロック社が設立されたが、すぐに解散し、
ウィリアム・ウィーロックがピアノの製造を始めた。
1880年、ウィリアムはウィリアム・E・ウィーロック・アンド・カンパニーを立ち上げ、
ニューヨークに大きな工場を購入した。
そして、1886年にウィーロックはスチュイベセント・ピアノ・カンパニーを立ち上げた。
1892年、いくつかの買収・合併を経て、ウィリアム・ウィーロックは、チャールズ・ローソン、
ジョン・メイソンとともに、ウェーバー・ピアノ・カンパニーを設立した。
1903年、ウェーバー・ピアノ・カンパニーは巨大なエオリアン・ウェーバー・ピアノ&ピアニラ社の
傘下に入った。20世紀後半、ウィーロックのブランドはウェイメイ(Wei Mei,)という
中国のピアノメーカーに買収されたが、現在もアメリカで製造されている。
ウィーロックのピアノはとても人気のある楽器で、甘い音と表現力のある音色が特徴です。
アラスカスプルース、ジュニパー、ブナ、メイプルなどの木材を使用し、今でも丁寧に手作りされています。
ウィーラー(Wheeler)ピアノは最初から最後まで約1年かけて製作され、
そのこだわりは正確な音にも表れています。ウィーロックは、アップライト型とグランド型の両方を製作し、
現在では世界中で見られるようになった。
古い物はアンティークピアノとして珍重されています。 |
| WHELPDALE |
詳細不明 |
| WHITE |
ホワイト 詳細不明 |
WHITMORE
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
キンボール社(KIMBALL)が取り扱ったブランド
→詳しくはKimballの項目へ |
|
WHITNEY



画像クリックでHPへ戻る
|
ホイットニー/(ウィットニー)/(ウイットニー)
アメリカ(シカゴ) WHITNEYピアノの製造期間1890年~1955年
ホイットニーはキンボール社(Kimball)の子会社が出していたブランドです
キンボール社(KIMBALL)が取り扱ったブランド →詳しくはKimballの項目へ
KIMBALL PIANOS キンボール ジャスパーコーポレーション(アメリカ/シカゴ)
キンボールの創業は1857年 下記はキンボールの解説
キンボール社は小さな小売店から始まり、世界最大クラスのピアノ製造会社へ発展。
一時はベーゼンドルファーの傘下にもなったことがあるようです。
1959年、オフィス家具メーカーのジャスパーコーポレーションによって買収。
1995年にグランドピアノの製造中止、翌年1996年にはアップライトピアノも製造中止に。
ピアノの雰囲気や音色はTHEアメリカ製ピアノといった感じです。
<ホイットニーピアノの解説>
ホイットニーピアノは、イリノイ州シカゴに本拠を置くキンボール社の子会社として、
1890年から1955年まで製造されていた。
ホイットニーピアノは、高価なキンボールピアノよりも手頃な価格のピアノとして販売されていました。
→キンボールの詳しい歴史はKIMBALLの項目をご参照ください。
キンボール社が製造したホイットニーピアノは、主にアップライトピアノと
スピネットスタイルのピアノでした。
ホイットニーピアノの多くは、平均的な音色と品質で知られ、
現在でも比較的良好な状態で使用されている。
家庭や学校での使用に最適なホイットニーピアノは、
キンボール・ピアノにとって非常に成功したピアノでした。
ホイットニーの天板のシリアルNoプレート →★
ホイットニーのアクションレールに貼られたシール →★
ホイットニーピアノの蓋にあるブランド名称マーク →★
|
WHITTAKER
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
キンボール社(KIMBALL)が取り扱ったブランド
→詳しくはKimballの項目へ |
| WHITTINGTON |
THE WHITTINGTON LONDON
詳細不明 |
WICKHAM AND WINTER & CO.
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
Wickham and Winter & Co.
1959年にウインター(WINTER & CO.)は、エオリアン・アメリカン社と合併し、
社名をエオリアン・コーポレーションに変更していた間、WICKHAM AND WINTER & CO.は
ウィンター&カンパニーが製造していたブランド名の一つです
→詳しくはWINTERの項目へ |
| WIECK |
詳細不明 |
| WIELER |
詳細不明 |
WILBER
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ウィルバー/ウイルバー 音調社楽器店(神戸市) |
WILCOX AND WHITE
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ウィルコックス・アンド・ホワイト
アメリカ(工場:コネチカット州メリデン、事務所:ニューヨーク) 創業1877年
<ウィルコックス&ホワイト社のオルガンの歴史>
ウィルコックス&ホワイト社は、1877年にホレス・ウィルコックスとヘンリー・ホワイトによって設立された。
工場はコネチカット州メリデンにあり、事務所はニューヨークにあった。
ウィルコックス&ホワイト社は家族経営で、ヘンリー・ホワイトの息子や孫が会社の成功と発展に
重要な役割を果たしていた。
この会社は、アンジェラスグランドとオーケストラピアノの再生機構である
Artrio-Angelusで知られており、オーケストラピアノの再生機とオルガンの両方を幅広く製造していた。
興味深いことに、ウィルコックス&ホワイト社が「アンジェラス」という名前をつけたのは、
同名の人気絵画が高額であることが話題になったためである。
この「アンジェラス」という名の絵画から連想される豪華さを、同名の楽器に応用するという
独創的なマーケティングを展開した。さらに、この絵をトレードマークのロゴにしてしまった。
ウィルコックス&ホワイト社は、1920年代前半まで楽器を製造していたが、その後、製造中止に。
ウィルコックス&ホワイト社の自鳴式オーケストラ・ピアノやオルガンは、
当時としては人気の高い高品質な楽器であった。
音楽家が最新かつ最高のものに魅了されていた時代に、時代を先取りした
複雑な楽器を製造していたのである。
美しい筐体と、柔らかくも力強い音色は、アメリカの音楽家たちに高く評価された。 |
WILDSTEIN
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ワイルドスタイン (有)及川ピアノ製作所
★★★
「WORLDSTEIN」とスペル間違いの可能性もあります。
詳しくは→WORLDSTEINの項目へ(トレードマーク画像があります) |
WILH. STEINBERG

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
WILH.STEINBERG ヴィルヘルム・スタインベルグ/(ウイルヘルム・スタインブルグ)
ドイツ 創業1877年
発売元:東洋ピアノ(現在取り扱い中止)→現在は島村楽器の持ちブランド
製造:スタインベルグ社(アイゼンベルグ) 元はヨーロッパのブランドですが、現在は中国OEM製造
<以下、ウィキペディアより引用抜粋>
Wilh. シュタインベルク(ヴィルヘルム・シュタインベルク、Wilh. Steinberg)は、
ドイツ・テューリンゲン州・アイゼンベルクのテューリンガー・ピアノフォルテ
GmbH(Thüringer Pianoforte GmbH)が販売するアップライトピアノおよび
グランドピアノのブランドである。
日本ではウィルヘルム・スタインベルグとも読まれる。
2008年から香港を拠点とする柏斯琴行(Parsons Music Group)が経営に参加し、
2013年にテューリンガー・ピアノフォルテ社はParsons Music Groupの完全子会社となった。
2018年現在、WILH. STEINBERGブランドのピアノは、Signatureシリーズが
テューリンガー・ピアノフォルテ社の管理の下で、中国本土・香港地域向けのピアノは中国湖北省宜昌市に
所在する宜昌金宝楽器製造(Yichang Jinbao Musical Instrument Manufacturing)で製造されている。
1877年、アドルフ・ハインリッヒ・ガイヤー(Adolph Heinrich Geyer)がアイゼンベルクで
最初のピアノ工場を設立した。
1896年から1902年まで一時的に社名を「Tuch & Geyer(トゥーフ・ウント・ガイヤー)」としたが、
1903年に元のA. Geyerに戻した[5]。1900年代始めに会社は成長し、
「A. GEYER」、「Fuchs & Mohr」、「Wilh. Steinberg」、「Weisbrod」、「Sassmann」などの
ブランドのピアノを製造した。
第二次世界大戦中にアイゼンベルクのほぼ全てのピアノ工場は接収・破壊されたが、
ガイヤー家のピアノ工場は長い歴史のため徴発を免れた。
ドイツ民主共和国(東ドイツ)時代(1949年-1990年)、ガイヤーの工場(WILH. STEINBERG AG)は
VEB Pianofortefabrik Eisenbergとして国有化された。
東ドイツの転換(ドイツ再統一)後、Eisenberger Pianofortefabrik GmbH
(WILH. STEINBERG AG) が再設立された。
1999年に社名をテューリンガー・ピアノフォルテGmbHとした。
テューリンガー・ピアノフォルテはOEM契約の下でその他いくつかのヨーロッパの
ピアノブランドを製造・仕上げを行っている。
スタインベルグの公式メーカーホームページ →★
<下記は東洋ピアノHPより抜粋>
1877年、ピアノメーカーとして最古のピアノシティであるアイゼンベルグにて創業。
それ以前より同所にてピアノの部品メーカーとして一流ピアノメーカ-に部品を供給してた。
ドイツピアノの特有な固めの音"ブリリアントサウンド"は敷物カーペットとの融合を配慮し、
マイスター職人の伝統と感性、経験だけが持つ音質の継承は芸術の一品といえます。
「白ぶな」「赤ぶな」「かえで」「菩提樹」「イチイ」「はんの木」などの
ヨーロッパだけに成育するピアノに適した優良木材を使用。
「無垢材」としての美しさ、木材の「年齢」で決定する音質の美しさを実感ください。
すべてのスタインベルグピアノは、ピアノ作りのパフォーマンス的要素と音楽的優秀性との間に
完璧なバランスを実現させ、トレードマークの"IQマーク(Intelligent Qualitiy-聡明な品質)"
がつけられています(HPより抜粋)
<下記は島村楽器のHPより抜粋>
1877年、ドイツ東部のテューリンゲン州・アイゼンベルグ市にて創業。
ドイツでも厳しい基準を持ったピアノメーカーに部品を提供することで、高度な技術力を持つ
ピアノ製造工場へと成長していきました。
創業以来、ドイツの伝統的な設計を活かしながらピアノを製造し続けるアイゼンベルグの工場と、
世界的に有名なピアノを数多く生産する設備の充実した中国工場で、
2007年よりWILH.STEINBERG社の技術指導のもと製造しています。
そのうち、日本国内で販売されるピアノは、40年以上ピアノ製造と修理に携わる日本人技術者によって、
国内入荷後に浜松の工房で音の最終調整を行い、丁寧に仕上げられています。
何世紀にもわたり培われてきた職人の感性・熟練の技術と、最新のピアノ製造技術から
産み出された芸術の逸品をお届けします。(HPより抜粋)
まだ調律したことはないですが、一昔前の中国製造のピアノよりははるかに良くなっていると思います。
実際に調律する機会があればここに率直な感想を書こうと思いますので今しばらくお待ち下さい^^ |
WILHELM







画像クリックでHPへ戻る |
ウィルヘルム WILHELM / K. WILHELM
製造元:ドレスデンピアノ製造株式会社(浜松)
製造元:東邦楽器製造株式会社
製造元:東洋ピアノ製造株式会社
一時製造:大成ピアノ製造KK(浜松和田町)
発売元:株式会社 福山ピアノ社(東京)
福山ピアノの主力銘柄の一つでした。
ドレスデンピアノ(株)製造。さまざまの形式が製造されました。
一時、大成ピアノが製造を引き受けたことがあるらしいです。
ウィルヘルムの特徴としては、ミュージックワイヤーの番手が一般的な位置(駒)にではなく
張弦しやすいようにチューニングピンのすぐ横に記載してあります。
上から4枚の画像は、D1g様からご寄稿頂きました。ありがとうございます!
一番下の画像は福山ピアノが作っていた時のエンブレムです。フクヤマピアノと同じです。
ウィルヘルムの蓋部分の銘柄マーク →★ (D1g様からご寄稿頂きました)
ウィルヘルムの蓋部分(FUKUYAMA & SONSバージョン) →★ (匿名希望様からご寄稿頂きました)
ウィルヘルムのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★ |
WILHELM BIESE
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
WILH.BIESE
<以下、ウィキペディアより引用抜粋>
ヴィルヘルム・ビーゼ(Wilhelm Biese、1822年4月20日ラーテノウ生、
1902年11月14日ベルリン没)は、ドイツの国際的に輸出されたアップライトピアノの製作者、製造業者であった。
ヴィルヘルム・ビーゼは工業化の始まりの時期にプロイセン王国で生まれた。
ビーゼは1851年から「高く評価されたピアノ製作者」としてベルリンで働き始め、
1853年にプロイセンの首都で設立した工場でアップライトピアノの生産を専門とし、
すぐに国際的な評価を獲得した。ビーゼはグランドピアノも製造し、王室御用達称号を得た。
「W. Biese Flügel- und Pianinofabrik」(W. ビーゼ・グランドピアノおよびアップライトピアノ工場)は
ノイケルンヴァイガンドウーファー18番地に位置し、販売店はヴィルヘルム通り56番地にあった。
現在のブランドの使用は、中国で生産されたW.Bieseという名称の新品のピアノが販売されている。
HP:http://www.biese.de/ |
| WILHELM SCHIMMEL |
→SCHIMMELの項目へ |
| WILHELM SPAETHE |
詳細不明 |
| WILKINSON, GEORGE |
詳細不明 |
| WILKINSON & WORNUM |
詳細不明 |
WILLIAM ROLFE & SONS
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ウィリアム ロルフ・アンド・サンズ イギリス 創業1790年
スクエアピアノ(横に長い机のような形のピアノ)
1823年7月6日、ドイツ人医師シーボルトが、長崎において親交のあった
4代五右衛門義比(ごえもんよしかず)にに贈られたというピアノ。
イギリス製のもので、日本に残る最古のピアノとしても有名です。
現在は山口県萩市の熊谷美術館に所蔵(一般公開)されております。
江戸時代に長崎出島に持ち込まれたピアノはこの1台の他にも数台存在したといわれていますが、
現存するのはこのシーボルトのピアノだけのようです。
このピアノは1955年、熊谷家の土蔵より発見され、その後、調査と鑑定が行われ、
1957年に中国地方の某ピアノメーカーで修理されました。製造年は1819年、鍵盤数68鍵。
ピアノにはオランダ語下記のように書かれているようです
「我が友クマヤ留別のために ドクトル・フォン・シーボルト 1828」
<さらに詳しい解説はこちら>
■ 山口県魅力発信サイト「きらりんく」
https://www.hagishi.com/search/detail.php?d=100060
■ 山口県が発行するメールマガジン「山口きらメール」
http://kirara.pref.yamaguchi.lg.jp/vol311/yamaguchigaku/index.php |
| WILLIAM WALLACE KIMBALL |
詳細不明 |
| WILLIAMS & SON, R.S. |
→R.S. WILLIAMSの項目へ |
WILLIAMS PIANO CO.
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
Williams Piano & Organ Co.
<ウィリアムズ・ピアノ・アンド・オルガン社の歴史>
ウィリアムズ・ピアノ&オルガン社は、初期のアメリカのピアノ会社が
オルガンも生産していたのに対し、ピアノだけを生産するようになってからも、
最初の主力製品の生産を継続していた。
ウィリアムズ・ピアノ&オルガン社は、1855年にJWウィリアムス社という社名でスタートした。
1899年にウィリアムズ・ピアノとして法人化し、シカゴに工場を建設した。
歴史的なシカゴ大火の後、同社は1875年に6階建ての防火施設を印象的に新築した。
1932年には世界大恐慌の影響を受けて廃業した。
ウィリアムズ・ピアノ社は、通信販売のみで楽器を販売しており、
工場は最新鋭のものを使用していた。
エプワース、ウィリアムス&サン、ペニントンなどのピアノとリードオルガンを製造していた。
ウィリアムズ氏は、「音楽家のさまざまな気分に自発的に反応するピアノを製作した。
このような特徴や品質は、商業的な観点ではなく芸術的な観点から製作されたピアノにしか見られない」
と言われていた。
このような理由から、ウィリアムズ社のピアノとオルガンは、会社が閉鎖された後も、
その品質と耐久性で長年にわたって知られていた。 |
| WILLIAMSON |
詳細不明 |
| WILLERMANN |
詳細不明 |
WILLIS
WILLIS & CO.
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
WILLIS ウィリス ドイツ(旧西ドイツ) 詳細不明
|
WILLMOTT
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
Ducat Willmott & Co. ダケット・ウィルモット
LONDON/ロンドン その他詳細不明 |
WILSON
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ウィルソン WILSON PIANO CO.
アメリカ(ウィスコンシン州ミルウォーキー)
→詳しくは「WALTHAM PIANO CO.」の項目へ |
|
WILSON


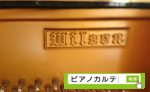
画像クリックでHPへ戻る
|
ウィルソン/(ウイルソン) WILSON
製造元:浜松楽器製造株式会社、(→ウィルソンピアノ?)
発売元:永栄楽器
製造元:浜松楽器製造有限会社(浜松市中野町670番地)
1970年(昭和45年)設立→1989年(平成元年)廃業
創業者の新井正男氏は1970年に資本金200万円で浜松楽器製造有限会社を設立し、
翌年の1971年(昭和46年)には従業員が13名の規模になった。
ANGEL(エンジェル)というピアノも製造→詳しくはANGELの項目参照
ウィルソンピアノの特徴は20tの張力にも耐えうる6本支柱と、北海道産の蝦夷松を響板に採用している。
尚、すべてのピアノに10年間の完全責任保証を付けていたとのことです。
余談ですが、浜松楽器製造株式会社のピアノ内部の調律記録カードには赤いフェルトリボンが付いています。
ウィルソンのトレードマークは、人魚姫をモチーフにしており、
数あるピアノのトレードマークの中では最も凝ったデザインだと感じます。
ウィルソンのまくり(フタ部分)にあるメーカー銘柄マーク →★
上記画像では”王冠マーク”が、Wil(王冠)son、となっていますが、(王冠)Wilsonもあります。
<ピアノ調律技術者向け附録>
張弦作業に役立つ当該機種ミュージックワイヤー配線仕様 →★
ウィルソンのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★ |
WIMMBERT
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
中国 詳細不明 |
| WINCHESTER |
詳細不明 |
| WINDHAM |
ピアノのまくり(蓋部分)の右側には下記のような表記
REBUILT BY
B. MAX STARKE & SON
PHILADELPHIA 11, PA.
詳細不明 |
| WINDHOFER, RUDOLF |
詳細不明 |
| WINDOVER |
詳細不明 |
| WINDSOR |
詳細不明 |
WINFIELD
このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
Winfield(ウィンフィールド)
WESER BROTHERSが製造していたブランド
→詳しくはWESER BROTHERSの項目へ |
WINKELMANN
WINKELMANN & CO.
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
WINKELMANN
ツァイッター&ヴィンケルマン(ウィンケルマン) ドイツ(旧西ドイツ)
<以下、ウィキペディアより引用抜粋>
ツァイッター&ヴィンケルマン(Zeitter & Winkelmann)は、ブラウンシュヴァイクで
最古のピアノ製造会社であった。
1837年にクリスティアン・ルードヴィヒ・テオドール・ヴィンケルマン
(Christian Ludewig Theodor Winkelmann)によって創業された。
ヴィンケルマンはWollmarkt 3番地の家で最初のスクエア・ピアノを製作し、すぐにグランドピアノも製作。
フリードリヒ・ツァイッター(Friedrich Zeitter)が1851年に共同事業者として会社に加わった後、
ツァイッターはとりわけ交差弦と鋳鉄フレームを導入した。年間生産数は60から80台に増加した。
1888年、Hildesheimer通りに新たな建物が建築され、この建物は1924年に拡張された。
同年には3万台のピアノが生産された。
1920年代、ツァイッター&ヴィンケルマンとブラウンシュヴァイクを拠点とするシンメル社、
その他いくつかのピアノ製造会社が協力し、
「Deutsche Pianowerke AG」(ドイツピアノ工場株式会社)を設立した。
1930年代にこの連合は再び分裂し、ツァイッター&ヴィンケルマンとシンメルは独立を確保し続けた。
1944年10月15日のブラウンシュヴァイク空襲によって生産施設が破壊された。
しかしながら、後継者のルドルフ・ヴィンケルマン jun. がライプツィヒ通りに会社を再建した。
1963年以降、ツァイッター&ヴィンケルマンはザイラーグループに加わった。 |
WINKELMANN
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ウィンケルマン/ウインケルマン アトラスピアノ製造株式会社
上記ドイツの”WINKELMANN”とは違うピアノです |
| WINKLER, PAU |
詳細不明 |
WINSTEIN
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ウィンスタイン/ウインスタイン 東洋ピアノ製造株式会社 |
WINTER
WINTER & CO.

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ウインター
WINTER PIANO COMPAY, INC. アメリカ(テネシー州)
テネシー州に近代的な工場を持つ、大規模なピアノメーカーです。
単一工場としてはアメリカで最も生産量が多く、その反面、歴史的な背景はほとんどない。
一途に、大量生産工程の近代化と能率化を計って発展してきたメーカーで、この点が
日本と似ているといえよう。
アップライトからグランドピアノ、自動ピアノに至るまで総合的な多種類のピアノを生産。
<別解説>
1899年にゴットリーブ・ヘラーとヘンリー・ヘラーによってヘラー社としてスタートしたが、
1901年にウィンター社がヘラー社を買収し、社名を変更した。
1903年にはニューヨークに新工場を設立し、1940年代半ばから50年代にかけての大量生産を支えた。
年間25,000台近くのピアノを生産していたと推定されるウィンター社は、当時の世界最大の
ピアノメーカーの1つとして、瞬く間に注目を浴びるようになった。
1900年代に入ると、ウィンター社は会社を成長させるために、買収や合併を繰り返した。
特に1959年には、エオリアン・アメリカン社と合併し、社名をエオリアン・コーポレーションに変更している。
その間、ウィンター&カンパニーは次のようなピアノ名を生産した。
Andrus & Co.、Bradbury、George P. Bent、Elbridge、W.P. Haines、
Hallet & Davis、Heller & Co. Huntington、Mehlin、Mendelssohn Musette、
Pease、Pianette、Pianola、Resotonic、Rudolf、Sterling、Ivers & Pond、
Kranich & Bach、Melodigrand、Henry F. Miller、Hardman、Poole、Sting、
Thomas、Wickham、Winter & Company
ウィンター社のピアノは、現在でも品質や価格の面で中間的なピアノとして知られているが、
その裾野は広い。1900年代のアメリカでは、彼らのピアノの多くが家庭やスタジオ、
教室などで使われていた。
1904年に "Master Player "を設計したことで有名だが、このピアノは現在でも
良好な状態で発見されれば貴重な音楽的財産となる。
また、1935年には初のスピネットピアノやコンソールピアノを設計したが、
ウィンター&カンパニーは幅広いタイプのピアノを製造した。
ミュゼットピアノは、コンソールを現代風にアレンジした新しいピアノスタイルのムーブメントに貢献した。
また、ウィンター社は、アルマトーン・プレート、静かにピアノを練習するための装置である
プラクティアーノ、レゾトニック・スケールなど、いくつかの革新的な技術をピアノのラインに
導入したことでも知られている。
WINTERピアノの天板を開けたところに貼ってあるエオリアンのシール →★
「Another Product Of AEOLIAN Corporation」と書いてありますね。別会社としての製造という意味でしょうか。
こちらの画像は「いろいろライオン様」よりご寄稿頂きました。ご寄稿を頂きありがとうございます! |
| WIRTH, JOHANN |
詳細不明 |
|
WISTARIA



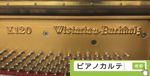
画像クリックでHPへ戻る
|
WISTARIA ウイスタリア
WISTARIA U-BUCHHOLZ/Wistaria u-Buchholz ウィスタリア・ウント・ブッフホルツ
ウィスタリア・ピアノ製作所(製造) 神奈川県大和市、[横浜市戸塚区]
現在の会社所在地:神奈川県大和市上草柳5-8-4
(有限会社 ツルミ楽器との情報もあるが詳細不明)
蒲田ピアノの創立者、斉藤喜一郎氏の長男、斉藤成一郎氏によって作られていたピアノ。
神奈川県大和市だったが、横浜市戸塚区にあたこともある。
[下記、ウイスタリアピアノのHPより一部抜粋]
1924年、創立者斉藤喜一郎、1920年から1923年までピアノ製作技術研究のためドイツに留学、
帰国後「東京蒲田楽器製作所」を設立し、ブッフホルツおよびホルーゲルピアノを製作する。
戦後、横浜に(有)クレールピアノ製作所を設立。
西ドイツピアノ製作業界視察のため再渡欧、特にグロトリアン、
スタインウェッヒピアノ会社の親交を得てピアノ製作技術の指導を受ける。
1956年、ウィスタリア・ピアノ製作所と改称。
1971年、大和市に新工場を建設、移転。
1973年、喜一郎氏の没後、成一郎氏が社長となる。
ウィスタリアのまくり(蓋部分)の銘柄マーク →★ ウイスタリアのアクション部分の内部写真 →★
ペダルスプリング強弱調整装置(拡大写真) →★ ウイスタリアピアノの下パネ内部 →★
ウィスタリアピアノのオリジナルキーカバー →★
画像を見ますと、ペダルは沢山清次郎氏の発明によるペダルスプリング強弱調整装置(特許No453845)
が採用されているようですね。このペダルスプリング強弱調整装置は他にも「クリーベル(KRIEBEL)」や
「ベルトーン(BELTON)」にも採用されていますが、個人的見解ではさほど強弱が出来る感じではありません。
ウィスタリアのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★ |
WITTON & WITTON
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
WITTON AND WITTON
ウィットンアンドウィットン イギリス(ロンドン) 詳細不明 |
| WITTMAYER |
詳細不明 |
|
WM. KNABE
|
→W. M. KNABEの項目へ |
| WOHLFAHRT |
詳細不明 |
| WOLFFRAMM |
詳細不明 |
| WOODCHESTER |
詳細不明 |
| WOODWARD & BROWN |
創業1843年 アメリカ(ボストン/BOSTON)
その他詳細不明 |
WORLD PEACE

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
WORLDPEACE ワールドピース
製造元:ワールドピアノ製作所/ワールド楽器製作所(磐田市)
発売元:株式会社 原ピアノ店(東京原宿)
原宿のピアノ店、原信義氏が世界平和を念願して名付けたピアノ。
|
WORLD STEIN
(WORLDSTEIN)



画像クリックでHPへ戻る |
WORLDSTEIN/WORLD STEIN
ワールド・スタイン/ワールドスタイン/(ワールドシュタイン)
詳細不明 (有)及川ピアノ製作所?
当初「WILDSTEIN」及川ピアノ製作所、との解説をしておりましたが、
「WORLDSTEIN」だった可能性もあります。今のところ不明です。
ワールドスタインのまくり(蓋部分)にあるブランド銘柄部分 →★
全体画像 →★ 調律記録カード →★ 下パネを開けた写真 →★ 飾りペダル部分 →★
左記トレードマーク画像、その他の画像はすべて広島県の「匿名希望様」からご寄稿頂きました。
このピアノは約50年ほど前、スガナミ楽器から購入したとの情報を頂きました。
この度は画像のご寄稿を頂きまして誠にありがとうございます!
<参考>
ちなみに、この「WORLDSTEIN」と似た名称のピアノで「WALDSTEIN」というピアノもあります。
→詳しくはWALDSTEINの項目へ |
| WORNUM, ROBERT |
詳細不明 |
| WORNUM, ROBT. & SONS |
詳細不明 |
|
WURLITZER



画像クリックでHPへ戻る
|
ウーリッツァー/マイテー・ウーリッツァー WURLITZER
アメリカ 創業1856年(ピアノ製造開始は1880年、オハイオ州シンシナティにて)
※各ホームページや資料により、さまざまな発音の仕方が散見されます。
例えば、ウェルリッツァー、ワーリッツァー、ウルウイツァー、ウルリッツァー、ウルウィッツァー等。
当方独自の見解では「ウーリッツァー」が日本国内では最も一般的な表記ではないかと考えます。
このウーリッツァーピアノはハンマーベッドに硬化剤がたっぷり入っているため、
音色はかなり硬めで苦労します。
ハンマー針刺し(ニードリング/ボイシング)で音色を柔らかく整音することも出来ます。
その他の特徴としましては、3本ペダルのうち、真ん中のペダルが低音域のみ利きます。
これを「バスサステインペダル」と呼びます。
アメリカ製のピアノにこの方式が多く、ボールドウィンの3本ペダル機種もこの方式を採用しています。
(一般的な3本ペダルの真ん中は弱音ペダル、別名マフラーペダルです)
左記トレードマーク画像ですが、上がアップライトで下がグランドピアノのものになります。
<詳細解説>
ウーリッツァーのブランドは、日本ではピアノの名称としてではなく、むしろ電子オルガンや電子ピアノ、
又はジュークボックスの名前として良く知られています。
また、この会社は元来有名なパイプオルガンのメーカーで、日本橋の三越本店にあるパイプオルガン
(これは1920年代の製品で、通常シアターオルガンとよばれ、当時のアメリカでは無声映画の
伴奏その他に使用されたもの)も、このウェルリッツァー製です。
しかし、現在はパイプオルガンは作られていません。
参考:日本橋三越のパイプオルガン写真 →★ 参考:日本橋三越の歴史再発見の公式ページ
→★
ウーリッツァーは現在、アコースティックピアノ、電子ピアノ、電子オルガンなどの製造部門と、
各種管楽器および弦楽器などの販売部門を持つ巨大な会社です。
ピアノの製造については、かつては全米随一の生産量を誇っていた名門で、アメリカにおいては
最も親しまれているピアノブランドといわれています。
アメリカ国内の販売においては10年の保障をつけ、その種類もスピネットからグランドピアノ、
自動ピアノに至るまで40種類におよびます。
尚、この会社は1955年に電子ピアノを作り出している。この楽器は言うまでもなく、
弦や響板などはなく、電気的にピアノの音を作り出す楽器です。
この電子ピアノの出現によって、ピアノの集合教育が可能になったと伝えられています。
ピアノ製造の歴史系譜
1880年、本格的ピアノ工場を建設し、ウーリッツァーブランドを付ける
1908年、デクライスト社のニューヨーク州工場を買収し、ピアノ工場として使用開始
1919年、メルビィーユ・クラーク・ピアノ社を買収
1935年、スピネットピアノの製造を開始
1961年、ミシシッピー州のホーリースプリングに新ピアノ工場を建設、鍵盤とアクションの製造開始。
1969年、ピアノ工場を拡大
1970年、ユタ州のローガンにピアノ工場を新設
この工場は驚くほど巨大なもので、ミュージックワイヤー(ピアノ線)やアクションに至るまで、
すべて自社工場の製品であるといいます。
1980年代後半、ボールドウィン社によって買収される
※2001年、ボールドウィン社は経営に行き詰まり破産申し立て
※2001年11月1日(破産申立の1ヶ月後)、ボールドウィン・ピアノ・アンド・オルガン・カンパニーは、
ギブソン・ギター・コーポレーションによって買収
現在は韓国のユンチャン社が製造? →詳しくはYoung Chang(ユンチャン)の項目へ
ウーリッツァーグランド、まくり部分(蓋部分)にあるブランドマーク →★
ウーリッツァーグランド、響板部分にあるデカール(シールです) →★
ウーリッァーはエレクトリックピアノでも有名です
<下記、Wikipediaから引用>
リード(振動板)を叩く構造。ローズと比べてピアノに近いアクションを持ち、
スピーカーを内蔵しているが、ローズより軽量。
1960年代後半から1970年代中盤にかけて広く使われた。
カーペンターズ、スモール・フェイセス、スーパートランプ、ダニー・ハサウェイなどで有名な他、
クイーンの「マイ・ベスト・フレンド」でも演奏されている。
<別解説>
Wurlitzer のピアノ製造は、1880年にオハイオ州シンシナティのWurlitzer工場で始まりました。
Wurlitzer Company は、1856 年に Franz Rudolph Wurlitzer によって設立されましたが、
彼は長い家族の楽器製造の基礎からビジネスを始めました。
17世紀にさかのぼり、Wurlitzerファミリーの歴史は、有名なバイオリンメーカーである
Hans Andreas Wurlitzerから始まりました。
1900 年代、Wurlitzer Companyは、ピアノ、オルガン、ジュークボックス、メロディオンなどの
様々な楽器を販売していたことで知られていました。
多くの楽器はヨーロッパから輸入され、Wurlitzerの会社名で販売されていました。
ルドルフ・ウーリッツァーが亡くなった1914年までに、会社のフットプリントはアメリカ全土に拡大し、
ニューヨーク州のノース・トナワンダに縦型ピアノを、イリノイ州のデ・カルブにグランドピアノを製造する
工場を持っていました。
1990 年代を通して、次のピアノブランドがWurlitzerの名前で生産、所有されていました
Apollo、Julius Bauer、Melville Clark、De Kalb、Farney、
Kingston、Student Butterfly Clavichord、Kurtzmann、Merriam、
Schaff Bros.、Spinette Strad、Underwood
1990年代初頭、チッカリングピアノを買収したばかりで、会社の所有権が流動的になり、
1995年にボールドウィンに買収されました。
<Wurlitzerピアノの特徴>
Wurlitzer ピアノのブランドは、様々なピアノに見られます。
Florentine(フィレンツェ)、Spanish(スペイン)、French(フランス)のような様々なスタイルの影響から、
スピネット、アップライト、グランド/ベビーグランド、エレクトロニックのような全く異なるモデルまで、
Wurlitzerは様々な美学で知られる多様なブランドです。
初期のアメリカのブランドとして最も人気のあるWurlitzerは、よく作られた、
よい音のするピアノとして 象徴されています。
特に、アップライトのスピネットモデルピアノを市場に出したとき、
Wurlitzerは日常的なアメリカ人をターゲットにしていました。
そのため、1900年代には多くのカフェ、家庭、スタジオで使用されていました。
ウーリッツァーのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★ |
WYMAN

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ワイマン 創業1949年 WYMAN Pianoforte アメリカ
クラシックはもとより、ポップス、ジャズなどに於いても適した楽器とのこと。
元ボールドウィン幹部が集まって創業、製造はアジア。年間50000台製造。
作り・デザインはボールドウィンそっくりです。
鉄骨部分のエンブレムにはQUALITY & VALUEと入っています。
ワイマン公式HP →★(英語サイトです)
|
上記Wから始まるブランドの中で、追記出来そうな事項や新情報を発見した場合、修正受付フォーム よりお気軽にお知らせ下さい。
どんな些細な情報でも構いませんので、広く皆様からのフィードバックをお待ちしております。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
 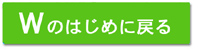 



上記Xから始まるブランドの中で、追記出来そうな事項や新情報を発見した場合、修正受付フォーム よりお気軽にお知らせ下さい。
どんな些細な情報でも構いませんので、広く皆様からのフィードバックをお待ちしております。どうそ宜しくお願い申し上げます。
 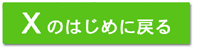 



上記Yから始まるブランドの中で、追記出来そうな事項や新情報を発見した場合、修正受付フォーム よりお気軽にお知らせ下さい。
どんな些細な情報でも構いませんので、広く皆様からのフィードバックをお待ちしております。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
 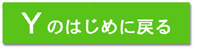 



ピアノ銘柄ブランド
トレードマーク 紹介
& 知名度ランキング

|

メーカー/ブランド説明・会社沿革・歴史・製作者・特徴・音色・他
|
| ZAHL, GEORG |
詳細不明 |
| ZAPKA |
詳細不明 |
ZAUBER


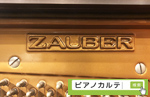
画像クリックでHPへ戻る |
ZAUBER ツァーベル/(ツアーベル) アサガピアノ調律所、浅賀ピアノ商会 創業1941年
※正しいつづりは「ZAUBER」です ×誤「ZAUBEL」(最後の文字は「L」ではなく「R」なので注意)
製造元:スワン楽器製造株式会社(浜松)
発売元:浅賀ピアノ商会(当時の住所:東京都文京区駒込動坂町221)/アサガピアノ調律所 創業1941年
※駒込動坂町は現在の千駄木四・五丁目、本駒込三・四丁目付近です
浅賀ピアノ商会(当時:東京都文京区動坂町221)がスワン楽器株式会社に作らせたもの。
トレードマークにはASAGA(浅賀)という文字が入っています。
ちなみに”ASAGA”というピアノブランドもありますのでそちらも参照。
※ASAGA(アサガ)とまったく同じトレードマークです。
<参考>
多摩六都科学館にはピアノ弦の張力解説用にツァーベルのフレーム部分が展示されています →★
創業者である浅賀伝次郎氏は1925年4月に16歳でピオバ楽器に入社、ピオバ楽器の野口喜象氏から
ピアノ製造技術を学び、1941年に32歳で
独立してアサガピアノ調律所を開業。
ここで自社ブランドである「ASAGA」アサガピアノを完成させました →詳しくはASAGAの項目へ
1955年には「アサガ音楽教室」を開設もしました。
このZAUBER(ツァーベル)はスワン楽器株式会社に作らせたものです。
<ZAUBERの画像集>
まくり(蓋部分)にあるZAUBERのブランド文字部分(Zの文字が特徴的です) →★
ZAUBERのリーフレット1 →★ リーフレット2 →★ ZAUBERの親板内部に描かれた文字 →★
上記の写真はすべて「匿名希望様」からご寄稿頂きました。この度はたくさんの画像をありがとうございました! |
ZEITTER & WINKELMANN

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
ZEITTER & WINKELMANN
ツァイッター&ヴィンケルマン(ウィンケルマン) ドイツ(旧西ドイツ)
<以下、ウィキペディアより引用抜粋>
ツァイッター&ヴィンケルマン(Zeitter & Winkelmann)は、ブラウンシュヴァイクで
最古のピアノ製造会社であった。
1837年にクリスティアン・ルードヴィヒ・テオドール・ヴィンケルマン
(Christian Ludewig Theodor Winkelmann)によって創業された。
ヴィンケルマンはWollmarkt 3番地の家で最初のスクエア・ピアノを製作し、すぐにグランドピアノも製作した。
フリードリヒ・ツァイッター(Friedrich Zeitter)が1851年に共同事業者として会社に加わった後、
ツァイッターはとりわけ交差弦と鋳鉄フレームを導入した。年間生産数は60から80台に増加した。
1888年、Hildesheimer通りに新たな建物が建築され、この建物は1924年に拡張された。
同年には3万台のピアノが生産された。
1920年代、ツァイッター&ヴィンケルマンとブラウンシュヴァイクを拠点とするシンメル社、
その他いくつかのピアノ製造会社が協力し、「Deutsche Pianowerke AG」
(ドイツピアノ工場株式会社)を設立した。
1930年代にこの連合は再び分裂し、ツァイッター&ヴィンケルマンとシンメルは独立を確保し続けた。
1944年10月15日のブラウンシュヴァイク空襲によって生産施設が破壊された。
しかしながら、後継者のルドルフ・ヴィンケルマン jun. がライプツィヒ通りに会社を再建した。
1963年以降、ツァイッター&ヴィンケルマンはザイラーグループに加わった。 |
ZENDER
ZENDER, SYDNEY
このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |
SYDNEY ZENDER &CO ゼンダー イギリス 詳細不明
|
|
ZENON
ZEN-ON


画像クリックでHPへ戻る
|
ZENON/ZEN-ON ゼンオン
※ブランド名にハイフン(-)が入るのが正式な表記です
製造元(元来):タイガー楽器製造株式会社(磐田市)
製造元:全音楽器製造株式会社(浜松)
製造元:東洋ピアノ製造株式会社
発売元:株式会社 全音楽譜出版社
発売元:ビクター全音
全音楽譜出版社の事業部と山葉良雄氏のタイガー楽器との間で、
”ゼンオン”のブランドでピアノを作ることが協議され、
事実上タイガー楽器を引き継いだ形で生産が行われ、
磐田市に最新式のベルトコンベアーによる工場を作ったが、
ビクターの参加も不調に終わり、ビクター・ゼンオンのブランドは一時期だけであった。
<参考>
ビクターゼンオンの項目もご参照ください
ゼンオンのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい→★ |
|
ZIMMERMANN



画像クリックでHPへ戻る
|
ZIMMERMANN チンメルマン(ツィンマーマン) ドイツ(旧東ドイツ)
現在の設計:ベヒシュタイングループ 現在の製造:中国の海倫鋼琴(ハイルンピアノ)
新しい楽器はよい出来で、数十年もすると世界的に知られるようになりました。
1904年には製造拠点が一気に拡大され、ツィンマーマンはベルリン、ハンブルク、ドレスデン、
アムステルダム、デン・ハーグ、ブエノスアイレスに営業拠点を築いて、ヨーロッパでも屈指のピアノメーカーへ。
40万台を越える楽器が売れたことが、ツィンマーマンの価値を物語っています。
ツィンマーマンは、ベヒシュタイングループ・ベルリンのノウハウによって作られており、
その製造工程では世界的に有名なピアノメーカーの設計基準が採用されています。
例えば、木材の買い付けは厳しい環境的選択基準にしたがって行われます。
丁寧なシーズニング、妥協を許さない乾燥の過程を経て、木材は、無理なく自然に望ましい湿度に達し、
厚板として乾燥されるトウヒ、マツ、ブナといった木材は、高い安定性を獲得します。
ツィンマーマンは同時に、細かく製材加工された部分にも気をつけています。
コンピュータ制御された機器を使った精密な作業は素晴らしく高い安定性をもたらすので、
気候の変化にも動じなくなります。
ツィンマーマンは響板を楽器の魂としています。このしなやかな振動板と、フライス盤で加工され、
ほぞに組み込まれて張力を支える響棒は、年輪が細かく最高の音響伝導能力をもつトウヒでできています。
鍵盤アクションを載せている棚板は安定していなければなりません。
金属がその持ちをよくし、特殊な木のパネルがやはり響きを支えます。
最高品質の羊毛フェルト、柔らかな天然皮革、頑丈なナラは、いずれも自然素材からなり、
ツィンマーマンのアクションを構成しています。
■機種/モデル バリエーション
アップライト:111CH(高さ110cm)、111M(高さ110cm)
グランドピアノ:M-145(奥行き145cm)など
画像は「Atelier Pianopia」様からご寄稿頂きました。ありがとうございます!
<以下、ウィキペディアより引用抜粋>
ツィンマーマン(Zimmermann)はドイツのピアノメーカー、ブランド名であり、
1992年からはC・ベヒシュタイングループに属している。
Gebr. Zimmermann(ツィンマーマン兄弟)としてマックス・ツィンマーマンと
リヒャルト・ツィンマーマンによって創業された。
(後に社名はLeipziger Pianoforte-Fabrik Gebr. Zimmermann Aktiengesellschaftに改名)
その一方で、ベヒシュタインの全てのアップライトピアノおよびグランドピアノはザイフヘナースドルフにある
かつてのツィンマーマンの工場で製造されている。ツィンマーマンの歴史的な生産拠点は
メルカウ、アイレンベルク、およびコッタ(ドレスデン)である。
現在、ツィンマーマンブランドのピアノはベヒシュタインが設計し、
中国の海倫鋼琴(ハイルンピアノ)が製造している。
マックスとリヒャルト・ツィンマーマン兄弟はライプツィヒにある父親の工房で木工を学んだ。
マックス・ツィンマーマンはその後ピアノ製作者のアウグスト・ヘルマン・フランケ(ライプツィヒ)、
Robert Seitz(ライプツィヒ)、Philippi Frères(フランクフルト・アム・マイン)、
そしてスタインウェイ・アンド・サンズ(ハンブルク)で働いた。
テオドール・シュタインヴェークはハンブルクからこの才能豊かな若者をニューヨークへ送り、
マックスは整音師としてスタインウェイ・ホールで働いた。
1884年、マックスとリヒャルト・ツィンマーマンはライプツィヒ・アレクサンダー通りに自身の
ピアノ工房「Gebr. Zimmermann」(ツィンマーマン兄弟)を設立した。
1890年、ライプツィヒ・ツァイツァー通りに販売店を開いた。
1892年には、ライプツィヒ近郊のメルカウに新たな生産施設を開いた。
1895年、法人形態を株式会社(Aktiengesellschaft)に変更し、
社名を「Leipziger Pianoforte-Fabrik Gebr. Zimmermann Aktiengesellschaft」とした。
1904年、ツィンマーマン兄弟はピアノ工場を建設するためにアイレンベルクに居を定めた。
兄弟はピアノの生産のために、アイレンベルクの北部(Jacobsplatz)にあった破産したコットン印刷業者
「Ehrenberg und Richter」の元工場を高い設備投資額を使ってピアノ工場にした。
この工場は年間1万台のピアノを生産する能力があった。
1911年から1914年の期間の広告には、社名に当時事実上の本拠地であった
アイレンベルクの地名が加えられていた。
1911年、ザイフヘナースドルフに工場が開業した。
年間生産数は1万2千台、従業員は1400人となったツィンマーマン社は
ヨーロッパ最大のピアノメーカーとなる成功を収めた。
1914年にはアイレンベルクで700人を雇用し、ドイツセルロイド工場(DCF)に次いで都市で
2番目の多い従業員を雇用する企業であった。
第一次世界大戦中は、主に女性の人員が弾薬箱を生産した。戦後、少数のピアノ生産が再開した。
徐々に、ピアノの生産数は再び上昇し、1926年には4500台となった。しかし、会社は家具も製造した。
同年、Gebrüder Zimmermannの生産はライプツィヒ近くのベーリッツ=エーレンベルクにある
ルートヴィヒ・フップフェルトAGと合併した。これによってヨーロッパで最大かつ現在は
最古のピアノ工場ができあがった。それ以降、社名は
「Leipziger Pianoforte- und Phonola-Fabriken Hupfeld-Gebr. Zimmermann AG
Eilenburg」
に改名された。1929年1月、アイレンベルク工場で大火があり、
ライプツィヒ消防署の助けによってようやく鎮火した。
同年の10月の頭に世界恐慌が起こった。
1931年初頭、アイレンベルク工場は閉鎖され、生産はザイフヘナースドルへと移転した。
メルカウにある工場は少なくとも1925年まで存在した。
1932年から1937年までアイレンベルク工場には国家社会主義ドイツ労働者党(NSDAP)の
労働奉仕キャンプが置かれた。
これが移転した1937年、フップフェルド=ツィンマーマンAGが戻ってきた。
現在の工場4では木材と金属の加工が行われている。
第二次世界大戦中も軍需生産が行われた。
1945年4月13日、アイレンベルクにおけるフップフェルド=ツィンマーマン社の残る
全ての従業員は解雇された。
1945年の後、会社は国有化され、「VEB Deutsche Piano-Union Leipzig」の下部組織となった。
ツィンマーマンのブランドは存続した。
東西ドイツ統一後の1992年、C・ベヒシュタイン・ピアノフォルテファブリークがツィンマーマン社を買収し、
ドイツにおける生産拠点をザイフヘナースドルフへ移転した。 |
| ZWANG |
詳細不明 |
| ZWICKI |
詳細不明 |
|
参考文献 : 世界の楽器図鑑、楽器事典ピアノ(東京音楽社)、ピアノ図鑑(ヤマハミュージックメディア社)、
国産ピアノ総合カタログ(ミュージックトレード社)、ピアノの技術と歴史、ピアノの誕生(講談社)、
日本のピアノメーカーとブランド およそ200メーカーとブランドを検証する(按可社)、
ピアノの歴史(河出書房新社・音楽の友社)、高度経済成長期のピアノ文化史等
内容の一部にはWikipediaからの引用文もあります(Wikiから引用させて頂いた場合は必ず引用したことを入れてあります)
※本文中に登場する創業者や技術者などのお名前には敬称を付けていない場合もありますことをご了承下さい。
ページ内の情報は「過去にこうだった」という情報の場合も多く、現在進行形で今も同じ状況かどうかは分かりません。
当ページ内に記載のピアノメーカー/製造会社・販売会社の多くが現在既に廃業、又は統廃合しておりますのでご注意下さい。
|
上記Zから始まるブランドの中で、追記出来そうな事項や新情報を発見した場合、修正受付フォーム よりお気軽にお知らせ下さい。
どんな些細な情報でも構いませんので、広く皆様からのフィードバックをお待ちしております。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
 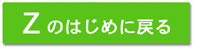 

個別ページへ A B C D E F G H I J K
L M N O P Q R S T U V W X Y Z


下記にフォームが表示されない場合は、何度かリロード(ページの更新)をしてみてください
それでも下記にフォームが表示されない場合は→こちらをクリック

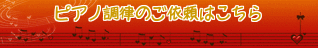
 

当方、調律した経験台数的には決して多い方ではないと思いますが、
協立インターナショナルの専属調律師として約20年間、関東1都7県をはじめ
東北地方までのかなりの広範囲を調律師として全力で走り続けてきました。
ヤマハやカワイと言った「メーカー系ピアノ調律師」とはだいぶ違うスタイルでしたが、
珍しいピアノブランドを多数調律してきた「種類」としての経験台数はかなり多いと思います。
現在、今まで培った経験を生かしフリーのピアノ調律師として仕事をさせて頂いております。
調律のご依頼は経験の豊富さと、ピアノカルテ を発行する調律師 私杉本豊へどうぞ
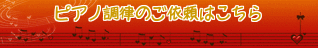
■杉本ピアノ調律事務所 出張範囲:能登半島全域(奥能登・中能登)
東京で30年間ピアノ調律師を経験後、現在は能登半島唯一の調律師として活動しております
輪島市、七尾市、珠洲市、羽咋市、かほく市、志賀町、宝達志水町、中能登町、穴水町、能登町等
あなたのお宅に来てくれる調律師さんは『ピアノカルテ』を発行してくれますか?
ピアノカルテを発行する日本全国の調律師さんのご紹介も出来ます→こちらへどうぞ
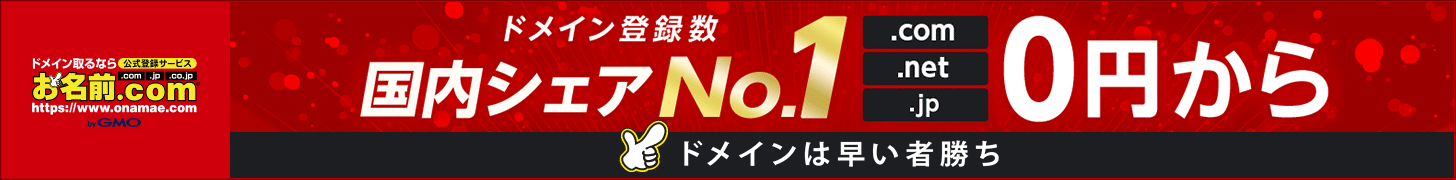

令和5年3月をもちましてピアノ寄贈マッチングサービスを終了させていただきました。
長きにわたり皆様からご利用頂きましたことを深くお礼申し上げます。
 
「ピアノカルテ」と「ピアノメーカー」の公式Facebookページがあります♪
「ピアノメーカー.com」 という日本語URLでも検索が可能です(※別ページです)
http://www.ピアノメーカー.com
最終更新日:2023/11/25
Last Updated : November 25, 2023

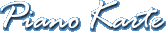
|





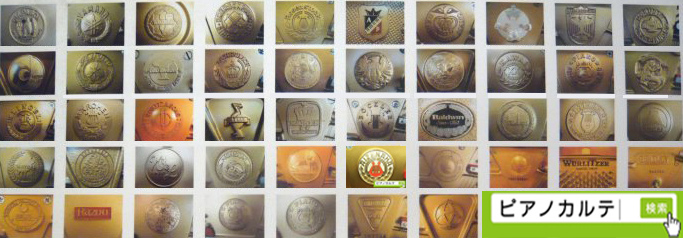

 日本国内ピアノ知名度ランキング
日本国内ピアノ知名度ランキング